
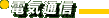
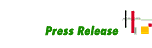


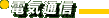
発表日 : 5月16日(金)
タイトル : 5/16付:「平成8年度 電気通信の番号に関する研究会」の報告
郵政省では、国内中継事業と国際通信事業の相互参入、移動体通信事業の新た なサービスの展開等といった最近の電気通信分野の動向を踏まえ、今後の電気通 信の番号の在り方について検討を行うため、平成8年(1996年)11月から 「平成8年度電気通信の番号に関する研究会」(座長:齊藤 忠夫東京大学工学 部教授)を開催し検討を進めてきましたが、このたび、その報告書がとりまとめ られました。 報告書では、国内中継・国際通信相互参入の番号計画、0AB0系番号の使用 方法の具体化、移動体通信事業の直収サービスの番号計画及び番号ポータビリテ ィ実施時の番号管理について提言が行われています。 報告書の概要は別紙1、研究会構成員は別紙2のとおりです。 郵政省では本報告書を受け、関連規定の整備を行なう等の所要の措置を講じて いくこととします。 連絡先:電気通信局電気通信事業部 電気通信技術システム課 (担当:杉野専門職、鈴木企画係長) 電 話:03−3504−4923 別 紙1 「平成8年度 電気通信の番号に関する研究会」報告書概要 1 国内中継・国際通信相互参入の番号計画 現在、国内中継事業者は00XY番号空間において007〜008列の事業 者識別番号を、国際通信事業者は001〜006列の事業者識別番号をそれぞ れ使用してサービスを行っているが、最近では国内中継事業者の国際通信事業 参入、国際通信事業者の国内中継事業参入による競争の促進及びそれを通じた 利用者の利益の増進が期待されているところであり、相互参入に適した番号計 画が必要とされている。 円滑な相互参入を可能とするためには、番号計画は、利用者にとって番号に よる事業者認識が容易で既存の番号形態・ダイヤル手順を維持できることなど の利便性が確保され、かつ、番号の有効利用を図りつつ、既存の国内中継・国 際通信事業者双方ともできるだけ早期に対応しうるものとすることが適当であ る。 したがって、第一種電気通信事業者における当面の国内中継・国際通信事業 相互参入の番号体系としては、00XY番号空間の001〜008列において、 現行の番号形態・ダイヤル手順を維持しつつ、既存00XY番号の使用状況を 踏まえて同一番号又は同一列隣接番号を使用することが望ましい。 さらに、今後の相互参入、新規参入による00XY番号空間の逼迫に備えて 番号容量の拡大を図る必要があるが、既存利用者の番号使用に影響を及ぼさず 早期に迅速な対応を可能とすることが重要であることから、既存番号の移行に 伴って平成11年4月以降新規使用が可能となる002列を5桁番号002Y Zとして使用することが望ましい。 2 0AB0系番号の使用方法の具体化 これまでフリーフォン(着信課金)サービスの番号として、0120が第一 種電気通信事業者間で共通化されているが、今後、各事業者が利用者の要望に 応じて多様な高度サービスを適時かつ円滑に提供していくためには、0AB0 系番号全般について共用化方法の一般化を図る必要がある。 0AB0系番号の共用に当たっては、サービスを行いうる全ての第一種事業 者において番号が使用できること、サービス毎に加入者需要に応じた番号容量 を確保すること等が重要であることから、今後、新規に開始するサービスにつ いて、次の番号体系とすることが望ましい。 [1] 百万加入までの需要が見込まれるサービス: 0AB0−DEF−×××(B≠0、10桁) [2] 百万以上一千万加入までの需要が見込まれるサービス: 0A00−DEF−××××(11桁) (注 DEFは必要に応じて事業者ごとに割当て) また、既に行われているサービスについても、共用化の要望を踏まえ、「大 量呼受付サービス」(0180)、「統一番号サービス」(0570)、「情 報料代理徴収サービス」(0990)の番号の共用化を行うことが適当である。 3 移動体通信事業の直収サービスの番号計画 携帯・自動車電話事業者において、NTTや地域系NCCが提供する専用線 を介して、自らの交換機に利用者の固定端末を直接収容し、移動体端末との間 で通信を行うサービスの提供が計画されているが、他の網と接続してこのサー ビスを提供するためには、直収固定端末を識別する番号が必要である。 この携帯・自動車電話事業者による直収サービスの番号体系としては、利用者 が直収固定端末を識別するためにわかりやすく、これまで広く利用者に定着し てきた一般の固定電話と同じ「市外局番−市内局番−加入者番号」の番号体系 を採用することが望ましい。 4 番号ポータビリティ実施時の番号管理 地域系事業者間の競争促進及び利用者利便の増進の観点から、一般加入電話 ・ISDN番号等について、利用者が加入を変更する場合にこれまでと同じ番 号を引き続き使用できるようにする「番号ポータビリティ」の実現が期待され ており、早期に実現方式を検討することが重要となっているが、その具体的検 討に先立って番号ポータビリティ実施時における番号管理方式について検討す る必要がある。 一般加入電話・ISDNの番号ポータビリティ実施時の番号管理方法につい ては、番号ポータビリティによらない番号の管理も含めて番号割当て等の効率 的実施及びルーチング処理の軽減を可能とすることが重要であることから、各 地域系事業者毎に市内局番を割り当てる方式とすることが望ましい。 さらに、市内局番の割当てを受けた事業者は、番号ポータビリティにより他 事業者に移転した利用者の番号について、移転先情報を管理すること、移転先 において使用されなくなった場合には再利用すること等が適当である。 (参考資料)我が国の00XY使用状況 国内中継・国際通信相互参入の番号計画
国内中継・国際通信相互参入の番号計画 00XY番号空間の逼迫対策(一部桁増)
00XY番号空間の逼迫対策(一部桁増)
○KDDの00XY番号の整理により平成11年4月から空き番号として使用
可能となる002列を、5桁化して使用
→ 百個程度の空き番号空間を創出し、新規需要に対応
空き列 002 → 002YZ(5桁化):新規に百個程度の番号容
量を追加
(その他の列については、引き続き4桁で使用
−既存00XY番号の桁増等の変更なし)
 0AB0系番号共用化の番号計画 1 今後、新規に行われるサービスについての番号計画 +−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |百万加入までの需要が| 0AB0−DEF−×××(B≠0,10桁番号)| |見込まれるサービス | | +−−−−−−−−−−+−−↑−−−−↑−−−−−−−−−−−−−−−−+ サービスを 事業者ごと に表す番号 割り当てる番号 +−−−−−−−−−−+−−↓−−−−↓−−−−−−−−−−−−−−+ |百万以上一千万加入ま| 0A00−DEF−××××(11桁番号) | |での需要が見込まれる| | |サービス | | +−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ (注)注平成11年1月1日の携帯・自動車電話、PHSの0A0番号の一斉桁 増(10桁→11桁)後に使用可能
0AB0系番号共用化の番号計画 1 今後、新規に行われるサービスについての番号計画 +−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |百万加入までの需要が| 0AB0−DEF−×××(B≠0,10桁番号)| |見込まれるサービス | | +−−−−−−−−−−+−−↑−−−−↑−−−−−−−−−−−−−−−−+ サービスを 事業者ごと に表す番号 割り当てる番号 +−−−−−−−−−−+−−↓−−−−↓−−−−−−−−−−−−−−+ |百万以上一千万加入ま| 0A00−DEF−××××(11桁番号) | |での需要が見込まれる| | |サービス | | +−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ (注)注平成11年1月1日の携帯・自動車電話、PHSの0A0番号の一斉桁 増(10桁→11桁)後に使用可能2 既に行われているサービスについての番号共用化
大量呼受付
サービス
0180−DEF
−XXX
D=0,1,9:使用中
D=2〜8 :今後、必要に応じて各事業者で使用
統一番号サ
ービス
0570−DEF
−XXX
D=0 :使用中
D=1〜9 :今後、必要に応じて各事業者で使用
情報料代理
徴収サービ
ス
0990−DEF
−XXX
D=3 :使用中(大人向け番組)
D=5,6 :使用中(大人向け番組以外)
D=2 :今後、必要に応じて各事業者で使用
(大人向け番組)
D=4,7〜9:今後、必要に応じて各事業者で使用
(大人向け番組以外)
 別 紙2 平成8年度 電気通信の番号に関する研究会 名簿 〔研究会〕(21名) (敬称略、五十音順) さいとう ただお 座長 齊 藤 忠 夫 東京大学 工学部教授 あいだ ひとし 相 田 仁 東京大学 工学部助教授 いしかわ ひろし 石 川 宏 日本電信電話(株) 取締役 いちりき け ん 一力 健 (社)テレコムサービス協会 会長 いわさき きんじ 岩 崎 欣 二 国際電信電話(株) 常務取締役 おおた はじめ 太 田 元 (社)経済団体連合会 産業本部長 おのでら ただし 小野寺 正 第二電電(株) 常務取締役 かとう まさよ 加 藤 真 代 主婦連合会 常任委員 ぱとりっく きゃろる P. キャロル 欧州ビジネス協会 通信・情報処理 アドバイザー くぼた しまお 久保田 司馬男 東京通信ネットワーク(株) 常務取締役 こすげ としお 小 菅 敏 夫 電気通信大学 電気通信学部教授 しのはら しげこ 篠 原 滋 子 (株)現代情報研究所 代表取締役所長 しまやま ひろあき 島 山 博 明 日本電気(株) 常務取締役 しみず えいいち 清 水 英 一 日本ルーセント・ 代表取締役副社長 テクノロジー(株) つ だ しろう 津 田 志 郎 NTT移動通信網(株) 取締役経営企画部長 ふるかわ ひろし 古 川 弘 志 (社)電波産業会 専務理事 ほりぐち しげのり 堀 口 榮 則 国際デジタル通信(株) 専務取締役 ますざわ たかよし 増 澤 孝 吉 通信機械工業会 常務理事 みやはら ひであき 宮 原 英 明 (社)電気通信事業者協会 専務理事 むらかみ てるやす 村 上 輝 康 (株)野村総合研究所 取締役・新社会シ ステム事業本部長 とーます ぱとりっく ろーがん トーマス P.ローガン 米国電子協会 日本担当本部長・ 所長 〔専門委員会〕(21名) (敬称略、五十音順) こすげ としお 主査 小 菅 敏 夫 電気通信大学 電気通信学部教授 あいだ ひとし 副主査 相 田 仁 東京大学 工学部助教授 いがらし よしお 五十嵐 善 夫 (株)アステル東京 技術部長 (平成8年12月まで) かまた てるもち 鎌 田 光 帯 (株)アステル東京 技術部長 (平成9年1月から) いしだ よしひで 石 田 良 英 (社)電波産業会 研究開発本部移動通信 グループ主任研究員 いとう かずひさ 伊 藤 和 久 日本生活協同組合連合会 組合員活動部長 (平成9年3月まで) かがみ よしみ 鏡 良 美 日本生活協同組合連合会 組合員活動部長 (平成9年4月から) おかもと はるゆき 岡 本 晴 行 日本国際通信(株) 交換部付部長 かのう さだひこ 加 納 貞 彦 日本電信電話(株) 常務理事 ネットワーク部次長 かわぐち けんいち 川 口 憲 一 国際電信電話(株) ネットワーク計画部長 きさいち とみお 私 市 富 男 東京テレメッセージ(株) 技術部長 く ま あきら 久 間 晃 (社)日本ケーブル 業務課長 テレビ連盟 く め ゆうすけ 久 米 祐 介 日本ルーセント・ 技師長 テクノロジー(株) こばやし たかお 小 林 隆 男 国際デジタル通信(株) 交換技術部長 さとう ひろし 佐 藤 浩 日本電気(株) システム統括部長 たきざわ こうじゅ 滝 沢 光 樹 (株)インテック 企画室長 たちばな かおる 橘 薫 第二電電(株) 取締役 ネット ワーク技術部長 なかむら ゆきお 中 村 行 男 日本高速通信(株) マルチメディア 推進部長 ふじわら しおかず 藤 原 塩 和 NTT移動通信網(株) 経営企画担当部長 みやた よしあき 宮 田 良 明 日本移動通信(株) 常務取締役 やまぞえ てつろう 山 添 哲 郎 通信機械工業会 第一技術部長 ゆ げ てつや 弓 削 哲 也 日本テレコム(株) 技術部長 わたなべ あきまさ 渡 辺 明 正 東京通信ネット 理事 技術部部長 ワーク(株)
別 紙2 平成8年度 電気通信の番号に関する研究会 名簿 〔研究会〕(21名) (敬称略、五十音順) さいとう ただお 座長 齊 藤 忠 夫 東京大学 工学部教授 あいだ ひとし 相 田 仁 東京大学 工学部助教授 いしかわ ひろし 石 川 宏 日本電信電話(株) 取締役 いちりき け ん 一力 健 (社)テレコムサービス協会 会長 いわさき きんじ 岩 崎 欣 二 国際電信電話(株) 常務取締役 おおた はじめ 太 田 元 (社)経済団体連合会 産業本部長 おのでら ただし 小野寺 正 第二電電(株) 常務取締役 かとう まさよ 加 藤 真 代 主婦連合会 常任委員 ぱとりっく きゃろる P. キャロル 欧州ビジネス協会 通信・情報処理 アドバイザー くぼた しまお 久保田 司馬男 東京通信ネットワーク(株) 常務取締役 こすげ としお 小 菅 敏 夫 電気通信大学 電気通信学部教授 しのはら しげこ 篠 原 滋 子 (株)現代情報研究所 代表取締役所長 しまやま ひろあき 島 山 博 明 日本電気(株) 常務取締役 しみず えいいち 清 水 英 一 日本ルーセント・ 代表取締役副社長 テクノロジー(株) つ だ しろう 津 田 志 郎 NTT移動通信網(株) 取締役経営企画部長 ふるかわ ひろし 古 川 弘 志 (社)電波産業会 専務理事 ほりぐち しげのり 堀 口 榮 則 国際デジタル通信(株) 専務取締役 ますざわ たかよし 増 澤 孝 吉 通信機械工業会 常務理事 みやはら ひであき 宮 原 英 明 (社)電気通信事業者協会 専務理事 むらかみ てるやす 村 上 輝 康 (株)野村総合研究所 取締役・新社会シ ステム事業本部長 とーます ぱとりっく ろーがん トーマス P.ローガン 米国電子協会 日本担当本部長・ 所長 〔専門委員会〕(21名) (敬称略、五十音順) こすげ としお 主査 小 菅 敏 夫 電気通信大学 電気通信学部教授 あいだ ひとし 副主査 相 田 仁 東京大学 工学部助教授 いがらし よしお 五十嵐 善 夫 (株)アステル東京 技術部長 (平成8年12月まで) かまた てるもち 鎌 田 光 帯 (株)アステル東京 技術部長 (平成9年1月から) いしだ よしひで 石 田 良 英 (社)電波産業会 研究開発本部移動通信 グループ主任研究員 いとう かずひさ 伊 藤 和 久 日本生活協同組合連合会 組合員活動部長 (平成9年3月まで) かがみ よしみ 鏡 良 美 日本生活協同組合連合会 組合員活動部長 (平成9年4月から) おかもと はるゆき 岡 本 晴 行 日本国際通信(株) 交換部付部長 かのう さだひこ 加 納 貞 彦 日本電信電話(株) 常務理事 ネットワーク部次長 かわぐち けんいち 川 口 憲 一 国際電信電話(株) ネットワーク計画部長 きさいち とみお 私 市 富 男 東京テレメッセージ(株) 技術部長 く ま あきら 久 間 晃 (社)日本ケーブル 業務課長 テレビ連盟 く め ゆうすけ 久 米 祐 介 日本ルーセント・ 技師長 テクノロジー(株) こばやし たかお 小 林 隆 男 国際デジタル通信(株) 交換技術部長 さとう ひろし 佐 藤 浩 日本電気(株) システム統括部長 たきざわ こうじゅ 滝 沢 光 樹 (株)インテック 企画室長 たちばな かおる 橘 薫 第二電電(株) 取締役 ネット ワーク技術部長 なかむら ゆきお 中 村 行 男 日本高速通信(株) マルチメディア 推進部長 ふじわら しおかず 藤 原 塩 和 NTT移動通信網(株) 経営企画担当部長 みやた よしあき 宮 田 良 明 日本移動通信(株) 常務取締役 やまぞえ てつろう 山 添 哲 郎 通信機械工業会 第一技術部長 ゆ げ てつや 弓 削 哲 也 日本テレコム(株) 技術部長 わたなべ あきまさ 渡 辺 明 正 東京通信ネット 理事 技術部部長 ワーク(株)