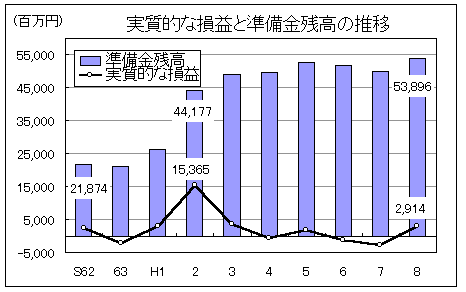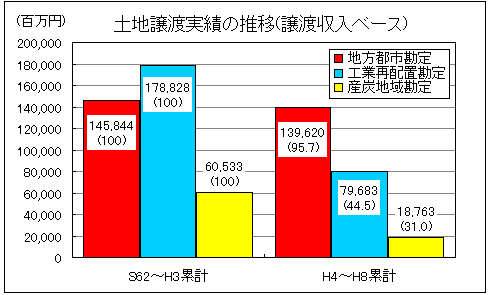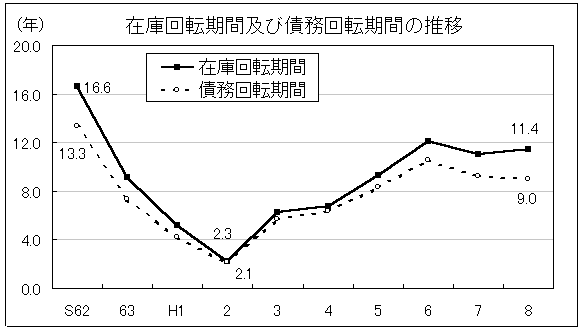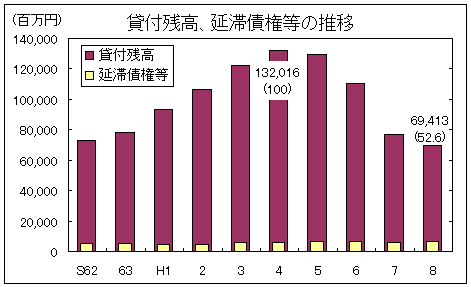|
1
|
土地造成事業
|
| |
| ○ |
昭和62年度以降10年間で分譲された土地については、おおむね実質的な利益が計上されている状況 |
| ○ |
バブル期後、土地譲渡実績が大きく低下 |
| ○ |
一方、投資は増加しており、保有する土地資産及び債務残高は増加 |
| ○ |
この結果、バブル期後在庫回転期間と債務回転期間が長期化しており、これらは土地資産の収益力低下と債務償還の長期化を通じ、将来的に財務内容に悪影響を及ぼす要因 |
|
|
| |
| (1) |
土地の譲渡差益を収益と、譲渡差損を費用とみなした実質的な損益は、昭和62年度以降10年間では全体的に利益が計上されている状況 |
| |
| ※ |
土地の安定的な供給を行うため、土地の譲渡差益に相当する額を費用計上して準備金に繰り入れ、譲渡差損に相当する額は準備金を取り崩して収益計上 |
| → |
準備金の残高は10年間に大幅に増加
(S62:219億円 → H8:539億円) |
|
|
| |
| (2) |
バブル期後、特に工業団地、事業用団地で大きく譲渡実績が低下 |
| |
| |
S62〜H3 |
|
H4〜H8 |
| 地方都市勘定(宅地造成等) |
100
|
→ |
95.7
|
| 工業再配置勘定(工業団地等造成) |
100
|
→ |
44.5
|
| 産炭地域勘定(事業用団地造成) |
100
|
→ |
31.0
|
|
| (3) |
バブル期後も依然として土地取得・造成に係る費用、土地取得面積が増加 |
| |
→保有する土地資産の増加、事業費の原資である債務性資金(債券、長期借入金)残高の増加
(土地資産 H2:100→ H8:143 債務性資金残高 H2:100→ H8:116) |
| |
|
| (4) |
譲渡実績の低下の一方で投資が増加したため、バブル期後は、
| ・ |
在庫回転期間が長期化=投下資金の回転効率が悪化 |
| ・ |
債務回転期間が長期化=債務の負担が相対的に加重 |
|
| |
| 在庫回転期間、債務回転期間: |
土地資産額、債務性資金残高がそれぞれ土地譲渡収入の何年分あるかをみたもの |
|
| |
↓
|
| |
これらの経営指標の悪化は、土地資産の収益力低下と債務償還の長期化を通じ、将来的に財務内容に悪影響を及ぼす要因 |
| (5) |
産炭地域の事業用団地については、国の産炭地域振興対策の円滑な完了に向け、平成13年度までに造成中の団地を完成させる予定(平11.8.5産炭審答申) |
| ○ |
地方都市勘定及び工業再配置勘定については、各事業の需要動向を的確に把握して事業を展開する必要 |
| ○ |
産炭地域勘定については、企業ニーズに合わせた事業用団地の供給方法を検討するなど企業誘致に工夫を凝らし、造成が完了した土地の分譲促進に努めていく必要 |
|
|
| |
|
| 2 |
貸付事業 |
| |
| ○ |
貸付残高は減少しているが、延滞債権額は横ばいの状況 |
| ○ |
貸倒引当金の額は延滞債権額には及ばないものの、利益剰余金相当額までは欠損を出さずに損失処理が可能 |
|
|
| |
| (1) |
貸付残高及び延滞債権(元本の返済が6か月以上延滞している債権)等の状況(平成8年度末現在)
| ・ |
貸付残高 |
694億円
|
|
| ・ |
延滞債権(うち2年以上) |
66億円
|
(49億円) |
| ・ |
元本及び利息の支払を猶予している債権
(延滞に結び付く可能性あり) |
19億円
|
|
|
| (2) |
貸倒引当金計上額:16.5億円(H8末)
ただし、利益剰余金が105億円(H8末)存在 |
| |
|
| (3) |
貸付事業は日本政策投資銀行の設立とともに同銀行へ移管(平11.10)。地域公団は既貸付分の債権管理のみ継続して実施 |
|
| |
| ○ |
回収可能性に注意しつつ債権管理を進めることが必要 |
|
|