


平成13年8月2日
総務省
| ○ | 総務省行政評価局は、次の行政相談を受け、行政苦情救済推進会議(座長:味村治)に諮り、その意見(別添要旨参照)を踏まえて、平成13年8月3日、厚生労働省に対し、改善を図るようあっせん。 |
|
| ○ | 行政相談の申出要旨は、「児童扶養手当を受給しながら2人の孫と生活していた娘が失踪してしまい、私が孫を養育することとなったが、老齢年金を受給していることから、同手当は支給されないとのこと。通常、年収が 325万円以下であれば同手当が全額支給されるのに、年額 170万円の老齢年金(私の所得はこの年金のみ)が支給されていることを理由に同手当が支給されないのは納得できない」というもの。 |
|
| ○ | 当省のあっせん内容は、以下の理由から、老齢基礎年金、老齢厚生年金等(以下「老齢年金等」という。)を受給していることのみをもって、児童扶養手当を支給しないとしていることについて見直すことを含め、児童が養育される家庭の生活の安定と自立の促進、児童の心身の健やかな成長という観点から、このような場合の施策の在り方について検討を求めるもの。 | |
 |
児童扶養手当は児童を養育する世帯の所得能力の低下又は喪失に対して支給されるものであるのに対し、老齢年金等は年金加入者の老齢による所得能力の低下又は喪失に対して支給されるものであり、その趣旨・目的が異なること。 | |
 |
老齢年金等では想定されていない児童を養育することになったことに伴う生活費の増大には着目することなく、祖父母が老齢年金等の支給を受けていることをもって二重の所得保障になるとして児童扶養手当は支給しないとしておくことは、児童の健全な育成を図るという同手当の趣旨から、妥当なものといえるかどうか疑問であること。 | |
 |
児童を養育することとなった年金生活者である祖父母が、手当の支給がなく生活に困窮した場合、例えば、養護施設への入所や里親制度の活用といった方法が考えられるが、児童の養育における家庭の役割の重要性を踏まえた場合、直ちにこれらの措置に移行させることが、より妥当なものといえるかどうか疑問であること。 | |
苦情救済推進会議における意見要旨
別 添
○ 二重給付になるから児童扶養手当を一切支給しないということは、あまりにも冷たい行政ということにならないか。母親が失踪しなければ、祖父の老齢年金は支給されるし、児童扶養手当も支給される。祖父の老齢年金では、孫を扶養することまでは想定されていない。想定されていないのに、二重給付になるから手当を支給しないという理屈は、一般国民には理解が困難ではないか。祖父と母親が同居していれば手当が支給されるので、母親がいなくなって養育者となった祖父に対して手当を支給しても新たに税金からの負担が増えるわけではないと考える。 ○ 所得保障の併給を調整するという基本理論は、間違っていないと考える。しかし、老齢年金の趣旨は、老齢に達して稼得能力がなくなった場合に加入者の生活レベルをある程度維持するために年金を給付するところにあると考えられる。一方、児童扶養手当は、本人の生活ではなく子供を扶養しなければならなくなり、そのためにお金がかかるという別の目的のための費用を賄えないからこれを補完する趣旨の手当であると理解され、本来、支給する目的、その想定しているレベルが違うと考えられる。それを併給禁止にするということは、どちらか禁止される方の趣旨をいかしていないのではないかと考える。 ○ 本件のテーマである併給調整については、所得保障の二重給付を避けるための調整として最高裁の判決等過去の判決において維持されてきているのではないか。したがって、併給調整そのものを見直すことには困難な面があるかも知れない。しかし、次世代を担う児童の健全育成という観点も重要であり、児童扶養手当を所管している担当課だけでなく厚生労働省(雇用均等・児童家庭局)全体で考えてもらうことが必要ではないか。 ○ 理想的なことをいえば、児童扶養手当制度が子供の健全育成、子供の福祉のためのものであるなら、子供を扶養している人の所得の程度によって給付するかどうかを決めるというすっきりした制度をめざすべきではないか。
《行政苦情救済推進会議》
総務省に申し出られた行政相談事案の処理に民間有識者の意見を反映させるための総務大臣の懇談会(昭和62年12月発足)。会議の現在のメンバーは、次のとおり。
座長 味村 治 元内閣法制局長官、元最高裁判所判事 大森 彌 千葉大学法経学部教授 加賀美幸子 千葉市女性センター館長 加藤 陸美 財健康・体力づくり事業財団理事長 塩野 宏 東亜大学大学院総合学術研究科教授 田村 新次 中日新聞社論説顧問 堀田 力 さわやか福祉財団理事長、弁護士
資 料
1 児童扶養手当制度の沿革2 支給要件
昭和34年の国民年金制度の創設により死別母子世帯については、母子福祉年金(無拠出制)が支給されることとなったが、死別母子世帯と経済的困窮の度合いが変わらない離婚等による生別母子世帯に対しても同様の社会保障制度を設けるべきであるとの議論があった。このようなことを背景に生別母子世帯に対して一定の手当を支給することとした児童扶養手当制度が創設されることとなり、昭和36年にその根拠法たる児童扶養手当法(以下「法」という。)が制定された。
児童扶養手当制度は、発足当初、母子福祉年金の補完的制度と位置付けられていたため、他の公的年金との併給は認められていなかったが、昭和48年10月から障害又は老齢の状態にありながら児童を養育している者の生活実態を考慮して、それらの者の負担の軽減を図るため、障害福祉年金(無拠出)及び老齢福祉年金(無拠出)との併給が認められた。
その後、「離婚の増加、女性の職場進出の進展等の変化を踏まえ、児童扶養手当の社会保障政策上の位置付けを明確にし、手当支給に要する費用の一部についての都道府県負担導入問題について、早急に結論を得る」とした第二次臨時行政調査会最終答申(昭和58年3月)を踏まえ、昭和60年3月に法が改正され、児童扶養手当制度は、母子家庭の生活安定と自立促進を通じて父と生計を同じくしていない児童の健全育成を図るという福祉制度として明確に位置付けられている。
なお、このときの法律改正と同時期に国民年金法(昭和34年法律第 141号)の一部が改正され、児童扶養手当との併給が認められていた障害福祉年金は、子についての加算が認められる障害基礎年金に裁定替えになったことから、現在、同手当との併給が認められる公的年金は老齢福祉年金のみとなっている。
(注) 障害福祉年金・・・ 施行時点である昭和34年11月1日に20歳を超える者(昭和14年11月1日以前に生れ た者)で一定程度の傷病等に状態にある者に支給される年金(全額国庫負担) 老齢福祉年金・・・・ 国民年金制度が導入された昭和36年4月1日時点で既に高年齢に達し最低加入期間(10年間)を満たせない者が70歳に達したときに支給される年金(全額国庫負担)
受給者の例:明治44年4月1日以前に生れた者(当時50歳以上)3 支給額(月額)
ア 児童扶養手当は、次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)の母がその児童を監護するとき、又は当該児童の母以外の者がその児童を養育(その児童と同居して、監護し、かつ、その生計を維持することをいう。)するときに、その母又はその養育者に対して支給(法第4条第1項)。 父母が婚姻を解消した児童
父が死亡した児童
父が一定程度の障害の状態にある児童
父の生死が明らかでない児童
父が引き続き一年以上遺棄している児童
父が法令により引き続き一年以上拘禁されている児童
母が婚姻によらないで懐胎した児童
いわゆる遺棄等
イ 児童扶養手当は、母又は養育者が、次のいずれかに該当するするときは支給されない(法第4条第3項)。 日本国内に住所を有しないとき
改正前の国民年金法に基づく老齢福祉年金以外の公的年金を受けることができるとき。ただし、その全額が支給停止されているときを除く
4 支給制限
ア 児童1人の場合 全部支給 42,370円 一部支給 28,350円 イ 児童2人以上の加算額 2人目 5,000円 3人目以降1人につき 3,000円
ア 受給資格者(母又は養育者)の前年の所得が、扶養親族等の有無及び数に応じて児童扶養手当法施行令(以下「政令」という。)で定める額以上であるときは、手当の全部又は一部は支給されない(法第9条及び第9条の2)。 イ 受給資格者の配偶者の前年の所得又はその受給資格者の民法第 877条第1項に定める扶養義務者で受給資格者と生計を同じくするものの前年所得が、扶養親族等の有無及び数に応じて政令で定める額以上であるときは、手当は支給されない(法第10条及び第11条)。
扶養親族等の数が3人の場合の政令で定める額 (単位:円)
受給資格者(法第9条、第9条の2) 受給資格者と同居の配偶者又は扶養義務者
(法第10条、第11条)全部支給の場合 一部支給の場合 収入額 所得額 収入額 所得額 収入額 所得額 3,254,000 1,748,000 4,025,000 2,680,000 5,050,000 3,500,000
(注) 1 政令では、手当の支給が制限される所得の最低限度額は給与所得控除等後の課税対象となる所得額で規定されている。本表の収入額は、厚生労働省が給与所得者を例として給与所得控除額等を加えて算定した額である。 2 所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族又は特定扶養親 族がある者についての限度額は、所得額に所要の額が加算される。
5 受給者数等
児童扶養手当受給者数及び予算額の推移 (単位:世帯、千円) 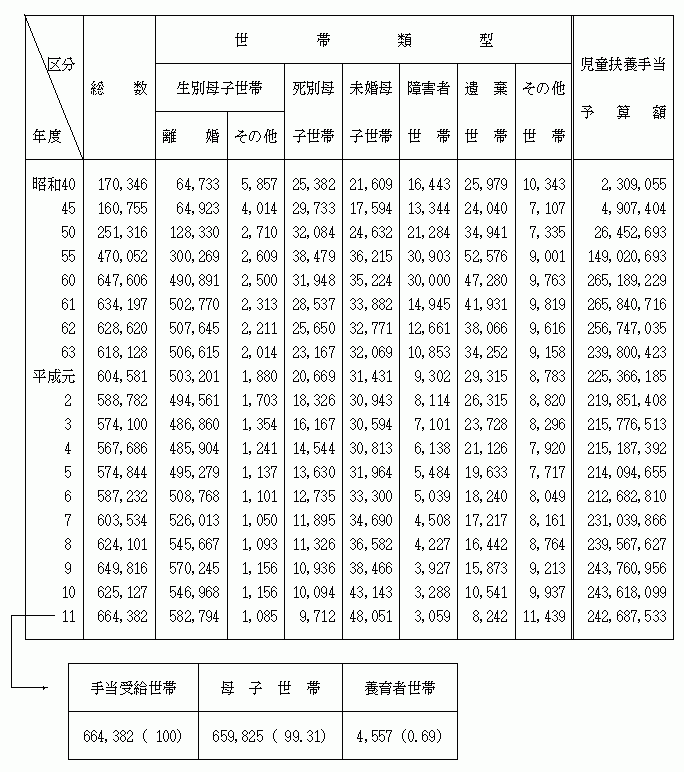
(注) 1 厚生省「社会福祉行政業務報告」(平成11年)等による。 2 世帯数は、各年度末現在である。 3 予算額は、当初予算額である。 4 ( )内は、構成比である。