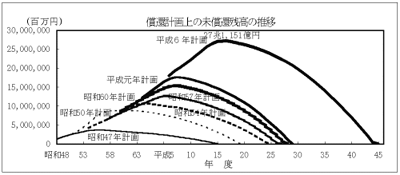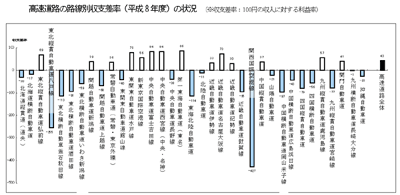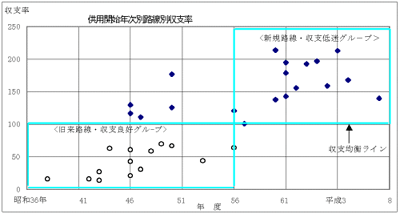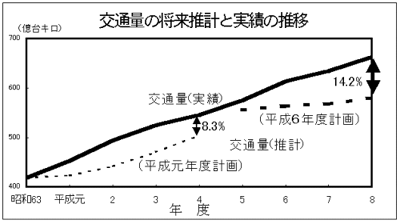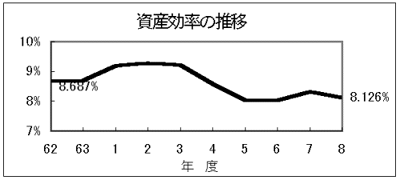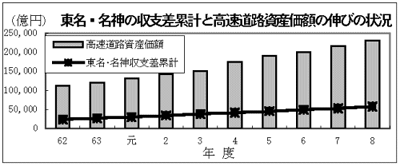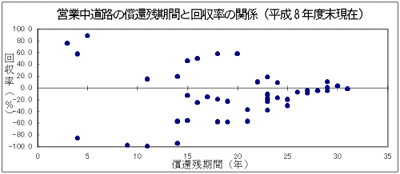|
| (1) 無料開放道路の償還の実態 |
| ○ |
個別採算制の下、償還期間が満了し無料開放された道路の5割強は、自力での償還ができず |
|
無料開放済み76道路のうち40道路は、自力での償還ができず「損失補てん引当金」を充当
|
補てんなし |
自力償還はしたが、
決算処理上、精算的
費用を補てんしたもの
|
自力での償還ができなかったもの(40)
|
| 元本の一部が不足したもの |
元本全額が不足したもの |
| 道路数 |
32
|
4
|
15
|
25
|
※「損失補てん引当金」は、各道路の料金収入の一部を積み立て、 開放する道路の未償還額に充当する制度であり、各道路の収支のリスク管理等が適正に行われるならば有効な仕組み |
| (2) 償還の現状と見通し |
| ○ |
営業中の道路には、償還計画の達成が困難と考えられるものが少なくない |
|
- 営業中の46道路中30道路が回収率マイナス(投下資金の償還が進まず、累積欠損が発生)
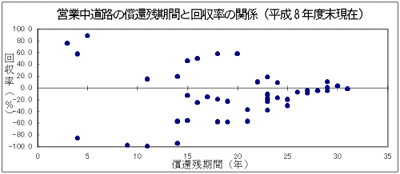
- 30道路分の償還対象総額は2兆2,655億円 ←→ 「損失補てん引当金」の残高は 2,314億円
- 公団でも、一定条件下で、平成33年度に34道路につき引当金が6,000億円不足すると試算
(ポイント)
| ○ |
損失補てん引当金制度を将来にわたり、いかに的確に機能させていくかが大きな課題 |
|
|
| (3) 東京湾横断道路事業 |
| ○ |
東京湾横断道路の開通により、一般有料道路事業のリスクの構造が大きく変化 |
|
- 平成9年から、東京湾横断道路の管理運営を、一般有料道路事業の一環として公団が担当
- 東京湾横断道路の償還対象総額(1兆4,058億円)は、一般有料道路のそれの約4割と大規模
- 利用実績は、償還計画で見込んでいる交通量の5割程度 → 収支見通しは楽観を許さず
(ポイント)
| ○ |
「一般有料道路事業」の経営の健全性確保のため、東京湾横断道路の的確な収支管理が不可欠 |
|
|
|