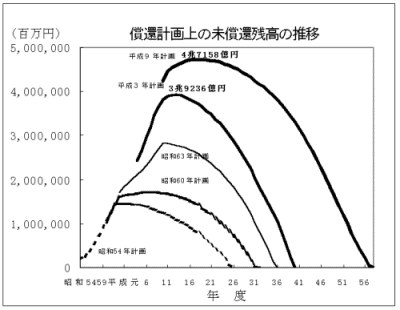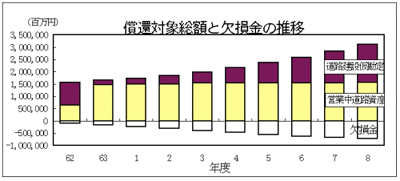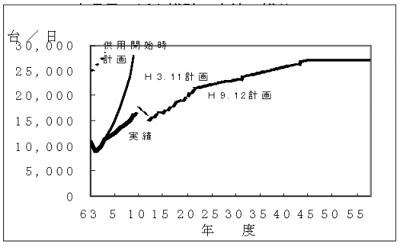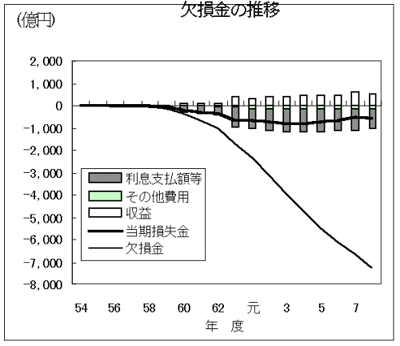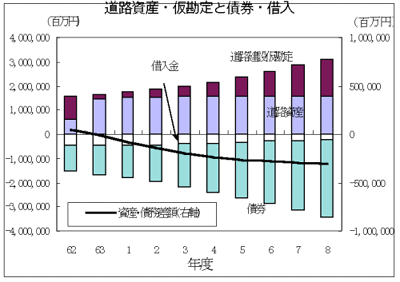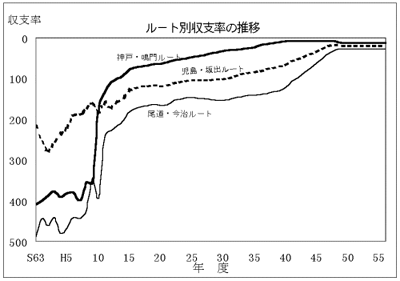| 1 |
事業の概要 |
|
- 公団は、本州四国連絡橋に係る有料道路及び鉄道を建設・管理する法人として、昭和45年に設立
- 国がルートを決定。国が公団に対して事業の指示(道路は平成11年度全ル−ト概成予定)
- 建設費の回収の仕組みは「3ルートプール制」(3ルート全体で償還/50年償還)
- 有料道路建設のための財源は主として「公団債券」により調達
|
| 2 |
財務の概要 |
|
| (1) |
道路事業 |
| |
- 債務超過の状態(資産総額< 債務総額 )/累積欠損金は7,242億円
- 業務収入では、管理費と金利の一部しか賄えない状況→キャッシュフローは健全とはいえない
|
| (2) |
鉄道事業 |
| |
資産総額/5,496億円、損益はゼロ(貸付料等により確実に費用を回収するスキーム) |
|
| 3 |
道路建設費等の償還状況 |
|
| (1) |
償還計画とその改定状況 |
|
- 償還計画(建設費等の償還見通し)は、新たな区間(橋)が供用開始される都度見直し
- 計画は「交通量推計」を基礎とした収入見通しと費用見通しによって策定
|
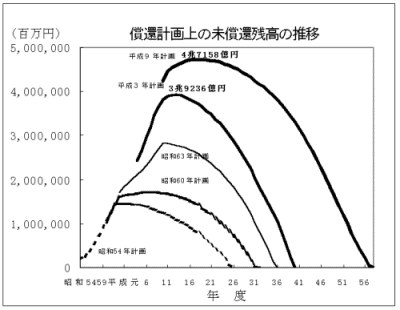
|
|
| (2) |
償還状況 |
| ○ |
償還準備金(償還の達成状況を示すもの)の積み立てはゼロ/毎年度多額の欠損金が発生 |
|
- 収支差は一貫してマイナス (いわゆる「創業赤字」) →
7,242億円の欠損金が累積
|
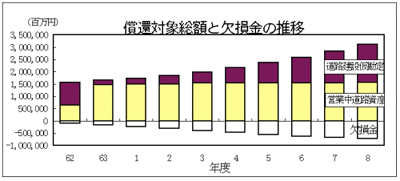
|
- 収支率は211→ 100円の収入をあげるのに、211円の費用を要する状況
収支率の推移
| 年度 |
S.63' |
H.元' |
2' |
3' |
4' |
5' |
6' |
7' |
8' |
| 収支率 |
275 |
313 |
324 |
300 |
294 |
276 |
259 |
183 |
211 |
|
|
|