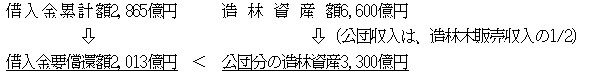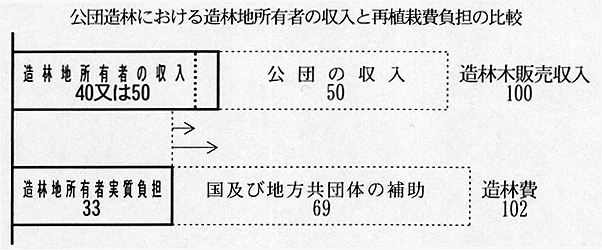| 1. |
約40万haの水源かん養保安林(H8末造成実績)=年間28億トンの貯水能力(H8末現在公団試算)
=東京都上水道使用量(H8=15億m3)の約2年分に相当 |
| 2. |
主伐後は造林地所有者に再植栽の義務(保安林に対する森林法上の義務) |
| 3. |
林業の現状は、造林費が造林木販売収入を上回っている状況 |
| |
→造林木販売収入:造林費=100:102(H8) |
| |
| ・ |
国産材の需要が減少し、価格は低下傾向(H2=100→H8=87) |
| ・ |
造林費の主要な構成要素である労務費は経年的に上昇傾向(S62=8,010円/人→H8=14,383円/人) |
|
| 4. |
公団造林における造林地所有者の造林木販売収入は、収入総額の50%又は40%
造林費については、別に国及び地方公共団体の助成制度(70%程度までの負担軽減) |
| |
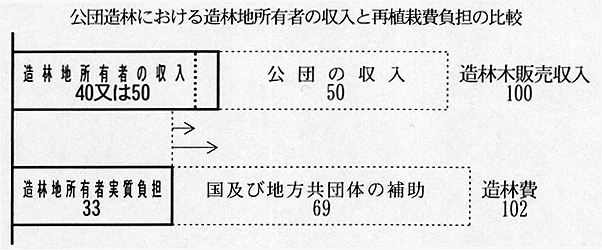 |
| |
|
| → |
造林費助成制度を前提にしても、造林木販売収入に対する造林費の割合が現状程度で維持されなけば、資金的には、収入でもって新たな植栽を行うことが難しくなるおそれ |
(ポイント)
| ○ |
水源林造成についての一定の事業効果は認められる。 |
| ○ |
水源林の造成という政策目的に沿って本事業を安定的に展開していくためには、費用対収入のバランスが適切に維持されていくことが課題 |
|
|