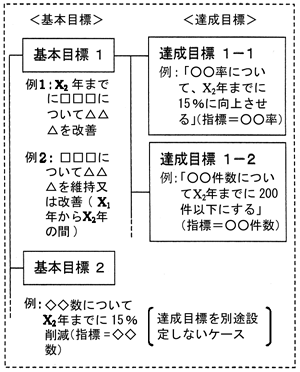| |
| 第1 政策評価の目的及び基本的枠組み |
| 1 目的 |
| |
| (1) |
国民に対する行政の説明責任(アカウンタビリティ)を徹底すること |
| (2) |
国民本位の効率的で質の高い行政を実現すること |
| (3) |
国民的視点に立った成果重視の行政への転換を図ること |
|
| 2 政策評価の基本的枠組み |
| |
| (1) |
「政策評価」の概念 |
| |
| 今般導入される「政策評価」とは、「国の行政機関が主体となり、政策の効果等に関し、測定又は分析し、一定の尺度に照らして客観的な判断を行うことにより、政策の企画立案やそれに基づく実施を的確に行うことに資する情報を提供すること」。 |
|
| (2) |
評価の対象 |
| |
政策評価の対象としての「政策」は、多くの場合、「政策(狭義)」、「施策」及び「事務事業」という区分において捉えられ、相互に目的と手段の関係を保ちながら、全体として一つの体系を形成。
|
| (3) |
評価の実施主体 |
| |
| 各府省は、政策を企画立案し遂行する立場からその政策について自ら評価を実施。総務省は、評価専担組織の立場から各府省の政策について評価を実施。 |
|
| (4) |
第三者等の活用の在り方 |
|
各府省が評価を行うに当たって、高度の専門性や実践的な知見が必要な場合等にあっては、必要に応じ学識経験者、民間等の第三者等を活用。
総務省に置かれる政策評価・独立行政法人評価委員会は、総務省の政策評価の中立性及び公正性を確保するため、総務大臣の諮問に応じ、総務省が行う政策評価の計画、実施状況、主要な勧告等を調査審議するとともに、これに関し、総務大臣に意見を述べる。
|
|
| |
| 第2 政策評価の実施に当たっての基本的な考え方 |
| 1 評価の時点 |
| |
評価を行う時点については、基本的には事前、事後の評価、場合によっては途中(中間)の評価があり、評価の目的、評価対象の性質等に応じて具体的に実施。 |
| 2 評価の観点、一般基準等 |
| |
| (1) |
各府省及び総務省は、次のような観点及び一般基準を基本としつつ、評価の目的、評価対象の性質等に応じて適切な観点等を選択し、総合的に評価。 |
|
| 「必要性」: |
目的の妥当性や行政が担う必然性があるかなど |
| 「効率性」: |
投入された資源量に見合った結果が得られるかなど |
| 「有効性」: |
期待される結果が得られるかなど |
| 「公平性」: |
政策の効果の受益や費用の負担が公平に配分されるかなど |
| 「優先性」: |
上記観点からの評価を踏まえ、他の政策よりも優先的に実施すべきかなど |
|
| (2) |
各府省及び総務省は、評価の目的、評価対象の性質等に応じた適用可能で合理的な評価手法により政策評価を実施。 |
|
|
| 3 評価の方式及び実施の考え方 |
| |
| 各府省は、以下の標準的な三つの評価の方式を踏まえつつ、所掌する政策の特性や各々の分野における政策評価に対する要請などに応じて、適切な評価の方式を採用・実施。(下記:標準的な政策評価の方式参照) |
| (1) |
「事業評価」: |
事務事業を中心に事前の時点で評価を行い、途中や事後の時点で検証。 |
| (2) |
「実績評価」: |
行政の幅広い分野において、あらかじめ達成すべき目標を設定し、それに対する実績を測定しその達成度を評価。 |
| (3) |
「総合評価」: |
特定のテーマを設定し、様々な角度から掘り下げて総合的に評価。 |
|
|
|
| 4 評価結果の政策への反映 |
| |
| (1) |
各府省は、評価結果が企画立案作業に適時的確に反映される仕組みを構築。 |
| (2) |
総務省は、評価結果を関係する府省に通知し、必要があると認められる場合には勧告。勧告の後、政策への反映状況について適期に報告を求め、勧告事項のうち特に必要があると認められる場合には、内閣総理大臣に対し、意見を具申。 |
| (3) |
予算への反映について、各府省は、評価結果を予算要求の段階等で適切に反映。財政当局は、予算編成の過程で政策評価の結果の適切な活用。 |
|
|
| 5 評価結果等の公表 |
| |
| (1) |
各府省及び総務省は、評価の結論だけでなく、評価の際に使用した仮定等の前提条件、評価手法・指標、データ、学識経験者の意見等評価の過程を含めて可能な限り具体的に公表。また、国民にとって容易に入手できる方法で、かつ、速やかに分かりやすい形で公表(インターネットのホームページへの掲載等)。 |
|
|
| |
| (2) |
総務省は、政府全体の政策評価及び政策への反映状況等を毎年度取りまとめ公表。 |
| (3) |
各府省及び総務省は、政策評価に関する外部からの意見・要望を受け付ける仕組みを整備。 |
|
| |
|
| 第3 各府省の政策評価 |
| |
| 1 実施体制・組織 |
| |
各府省の政策評価担当組織は、所管行政の政策評価に関する基本的事項の企画立案、府省における評価状況の取りまとめや公表などの役割を担うことにより、府省の評価の厳正かつ客観的な実施を確保。
|
| 2 政策評価の実施要領の作成等 |
| |
(1) |
各府省は、体系的かつ継続的な政策評価の実施を確保するため、本ガイドラインに沿って政策評価の基本的な手続、手順等を規定した実施要領を策定。実施要領には、(ア)評価の目的等、(イ)評価の実施体制、(ウ)評価の観点、一般基準等、(エ)評価の方式、(オ)評価結果の政策への反映、(カ)評価結果等の公表、(キ)政策評価に関する外部からの意見・要望等を受け付ける窓口などについて規定。 |
| |
(2) |
実施要領を踏まえ、各年度の政策評価の計画的な実施に係る具体的な運営の方針を策定。 |
|
| |
| 第4 総務省の政策評価 |
| |
| 1 総務省の役割 |
| |
各府省の政策について、統一的若しくは総合的な評価や政策評価の客観的かつ厳格な実施を担保するための評価を行うほか、政府全体の評価結果及び政策への反映状況等の取りまとめ・公表、「政策評価各府省連絡会議」の開催等の事務を実施。
|
| 2 政策評価の実施要領の作成等 |
| |
体系的かつ継続的な政策評価の実施を確保するため、各府省に準じ、本ガイドラインに沿って、実施要領及び運営の方針を策定。 |
| 3 行政評価・監視との関係 |
| |
政策評価と政策評価を除く行政評価・監視とは明確に区分されるものとし、その運営に当たっては、作業の重複を避けるなど効率的な運営に配慮。
|
|
| |
| 第5 その他 |
| |
|
(1)
|
各府省の政策評価担当組織の長等により構成される「政策評価各府省連絡会議」を開催。 |
| (2) |
政策評価を担当する人材を養成・確保するため、評価の分野における官民交流、政策評価担当職員の人事交流、行政内外からの有能な人材を養成・確保する仕組み等の方策を推進。 |
| (3) |
評価に関する情報の所在情報を国民が一元的、かつ、容易に検索できるクリアリング・ハウス機能を充実。 |
| (4) |
評価実施の必要に応じた評価手法の調査研究を推進。 |
| (5) |
政策評価の実施状況、評価手法の研究開発の動向等を踏まえ、必要に応じ標準的ガイドラインや実施要領を見直し、改定。 |
|
| |
|
|
| |
事業評価
|
実績評価
|
総合評価
|
|
基本的
性 格
|
事前の時点で評価を行い、途中や事後の時点での検証を行うことにより、行政活動の採否、選択等に資する情報を提供することを主眼。 |
行政の幅広い分野において、あらかじめ達成すべき目標を設定し、それに対する実績を測定しその達成度を評価することにより、政策の達成度合いについての情報を提供することを主眼。 |
| 特定のテーマを設定し、様々な角度から掘り下げて総合的に評価を行い、政策の効果を明らかにするとともに、問題点の解決に資する多様な情報を提供することを主眼。 |
 |
|
 |
<実施例>
実績評価の際に、掘り下げた総合的な評価が必要と判断された場合に実施。 |
| |
|
|
対 象
|
事務事業が中心。必要に応じ、おおむね施策として捉えられる行政活動のまとまりについても対象(以下「事業等」。)。 |
共通の目的を有する行政活動の一定のまとまり(おおむね施策程度のまとまりに相当。以下「施策等」。)を対象。
各府省の主要な施策等に関し幅広く対象。
|
特定の行政課題に関連する行政活動のまとまり(おおむね政策(狭義)や施策ととらえられる行政活動のまとまりに相当。以下「政策・施策」。)を対象 |
|
評価の
時 点
|
事前の時点で評価し、途中や事後の時点で検証。 |
あらかじめ目標を設定し、定期的・継続的にその実績を測定。
目標期間終了時に当該期間全体における達成度を評価。
|
政策・施策の導入から一定期間を経過した時点を中心。 |
|
評価の
内 容
|
| ● |
事前の時点で、あらかじめ期待される効果やそれらに要する費用などを分析・検討。 |
| |
・ |
事業等の目的が妥当か、行政関与の在り方からみて行政が担う必要があるかを検討。 |
| |
・ |
事業等の実施により予測される効果や必要な費用を可能な限り推計・測定し、比較。 |
| |
・ |
事業等の目的の実現のために必要な結果が得られるか、より効率的で質の高い代替案がないかを検討。 |
| ● |
途中・事後の時点で、事前の時点で行った評価内容を踏まえ検証。 |
| ● |
公共事業、研究開発及びODA事業については評価の取組の一層の改善・充実。規制については実施可能なものから順次評価。補助事業や新規に開始しようとする事業等についても評価の実施等を検討。 |
|
| ● |
主要な施策等に関し、成果(アウトカム)に着目した「基本目標」を設定。その達成状況を測定するため、「達成目標」を設定。 |
| ● |
目標について、定期的・継続的に実績を測定。 |
| ● |
目標期間が終了した時点で、目標期間全体を総括し、基本目標の達成度を評価。 |
| ● |
目標の設定、実績の測定、目標期間終了時の評価について、各段階で結果等を公表。 |
|
| ● |
政策・施策の効果の発現状況を様々な角度から具体的に明らかにする。政策・施策の直接的効果や因果関係等について分析。 |
| ● |
政策・施策に係る問題点を把握し、その原因を分析。 |
| ● |
政策・施策の目的妥当性を検討。 |
| ● |
時々の課題に対応して、評価の実施体制、業務量、緊急性等を勘案しつつ、次のようなテーマを選択し、重点的に実施。 |
| |
・ |
社会経済情勢の変化により改善・見直しが必要とされるもの。 |
| |
・ |
国民からの評価に対するニーズが高く、緊急に採り上げて実施することが要請されるもの。 |
| |
・ |
従来の政策・施策を見直して、新たな政策展開を図ろうとするもの。 |
|
|