小型船舶操縦士海技免状の更新申請手続の簡素化(概要)
《行政苦情救済推進会議の検討結果を踏まえたあっせん》
| あっせん日 | : 平成12年9月25日 |
| あっせん先 | : 運輸省 |
| ○ | 総務庁行政監察局は、下記の行政相談を受け、行政苦情救済推進会議(座長:茂串 俊)に諮り、その意見(別添要旨参照)を踏まえて、平成12年9月25日、運輸省に対し、改善を図るようあっせん。 | ||
| ○ | 行政相談の申出要旨は、「私は小型船舶操縦士海技免状の交付を受けており、5年ごとの更新に当たっては、指定講習機関の実施する更新講習を修了した上で、更新申請のため、最寄りの管海官庁に出向かなければならない。私の住んでいる県では、更新講習は交通の便利な県庁所在地でも行われているものの、申請先である最寄りの管海官庁は遠隔地にあることから、更新申請をする場合、そのために仕事を1日休まなければならない上、交通費もかかる。管海官庁に出向かせることなく、郵送等により更新申請を受け付けてほしい。」というもの。 | ||
| ○ | 当庁のあっせん内容は、以下の理由から、郵送による更新申請を認める方向で検討を求めるもの。 | ||
| 1. | 免許申請では、郵送による申請が認められているが、更新申請書と免許申請書は、 記載事項に大きな違いがなく、また、添付書類もほぼ同様なものとなっており、更新申請についてのみ、出頭を求め、記載漏れ・記載誤り、添付書類の不備の補正等を対面指導する必要はないと考えられる。 | ||
| 2. | 更新申請を海事代理士に委託する際には、海事代理士が出頭することとされている が、海事代理士は、受託業務を誠実かつ敏速に処理すること等は義務付けられているものの、業務を受託する際に、面会して本人確認を行うことまでは求められておらず、
本人が自ら更新申請を行う場合にのみ出頭による本人確認を行う必要はないと考えら れる。 仮に、更に入念な本人確認が必要であるとしても、旧海技免状と新免状貼付用の写真とを照合した結果、必要があると認められる場合にのみ出頭を求めること、あるいは更新講習修了証明書に写真を貼付させるなど出頭に代わる本人確認のための措置を講ずることを検討する余地があると考えられる。 |
||
| 3 | 更新講習を行う6機関のうち財団法人日本海洋レジャー安全・振興協会の平成11年4月から6月における更新講習の開催状況をみると、管海官庁が所在する79市町村では56市町村で延べ294回開催、管海官庁が所在しない市町村では193市町村で延べ400回開催されている。このように、更新講習は、需要に応じ受講者の多い地域で開催されているが、管海官庁が必ずしも更新申請者が多い地域に設置されているわけではないことから、本人が申請しようとする場合、管海官庁への出頭は負担が大きいものと考えられる。 | ||
| (参考) | 管海官庁:地方運輸局(神戸海運監理部及び沖縄総合事務局を含む。計11)及びその海運支局(沖縄にあっては海運事務所。計69) | ||
|
資 料
|
| 1 | 小型船舶の乗組み基準 |
| 船舶所有者は、船舶職員法(昭和26年法律第149号)に基づき、その船舶に、船舶の用途、航行する区域、大きさ、推進機関の出力その他の船舶の安全に関する事項を考慮 して定められた乗組み基準に従い、海技免状を受有する海技従事者(海技士又は小型船舶操縦士)を乗り組ませることとされており、この基準において、総トン数20トン未満の小型船舶については、小型船舶操縦士の有資格者を乗り組ませることとされている。この小型船舶操縦士の資格は、表1のとおり、航行する区域等によって1級から5級までの小型船舶操縦士に区分されている。これらの規定は湖、河川や海岸付近で使用される船舶や水上オートバイ、数人乗りの船外機付きボートにも適用される。このため、個人がレジャーを目的として自ら小型船舶を操縦する場合であっても、小型船舶操縦士海技免状を受有する必要がある。 |
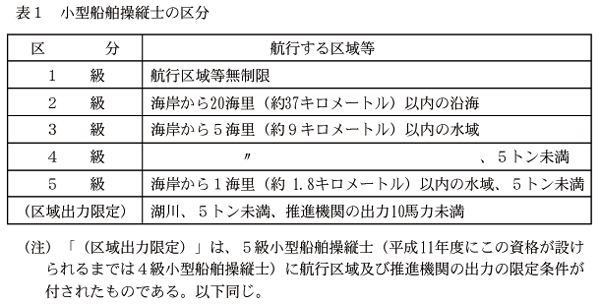 |
| 2 | 小型船舶操縦士の新規免許 | |
| (1) | 新規免許 | |
| 小型船舶操縦士の新規免許は、指定試験機関(財団法人日本海洋レジャー安全・振興協会)の実施する海技従事者国家試験の合格者の申請に基づき、運輸大臣が与えている。このとき、表2において1から5までに掲げる事項が海技従事者免許原簿に登録され、有効期間5年の小型船舶操縦士海技免状が交付される。 海技従事者免許原簿は、運輸省の電算機により管理されており、同省は、地方運輸局、神戸海運監理部、沖縄総合事務局及び一部の海運支局にその端末を設置して免許申請の受付・審査、原簿への登録及び海技免状の作成・交付を行っている。 なお、本人の住所は登録事項とされていない。 |
||
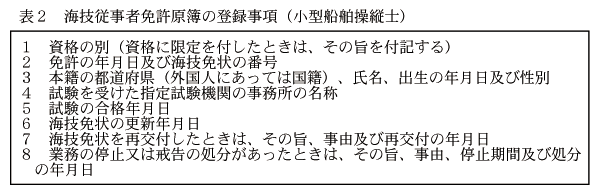 |
| (2) | 国家試験合格者 | |
| 級別資格が設けられた昭和49年度から平成11年度までの小型船舶操縦士の国家試験合格者数は、表3のとおり、約 200万人となっており、このうち、海岸から5海里以内の水域で5トン未満の小型船舶を操縦できる4級小型船舶操縦士が約170万人 (84.5 パーセント)を占めている。 |
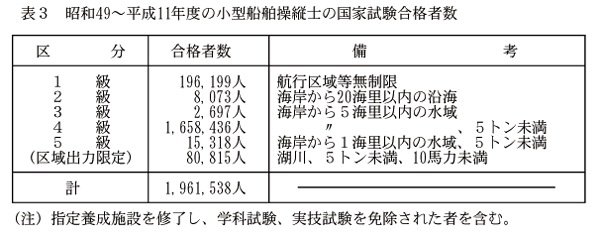 |
| また、小型船舶操縦士の国家試験合格者の推移をみると、表4のとおり、毎年度8万人から10万人で推移しており、5海里以内の水域や湖、河川で5トン未満の小型船舶を操縦できる4級、5級及び区域出力限定の小型船舶操縦士が増加傾向にある。 |
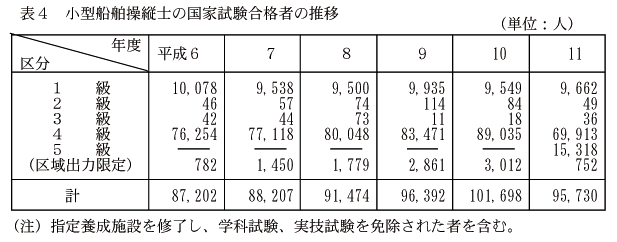 |
| (3) | 免許を受けている者 | |
| 小型船舶操縦士の免許を受けている者の数は、表5のとおり、昭和60年度の約 170万人から、平成11年度の約 290万人に増大している。 |
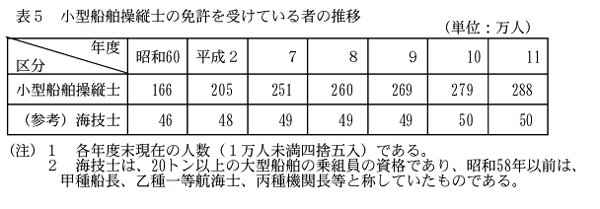 |
| (参考)検査実績からみた小型船舶の隻数の推移 | ||
| 小型船舶(12海里以内の水域で操業する漁船、旅客定員7人未満のろかい船等を除く。)は、船舶安全法(昭和8年法律第11号)により、日本小型船舶検査機構の検査を受けることとされている。その検査実績からみた小型船舶の隻数の推移は、表6のとおりである。 | ||
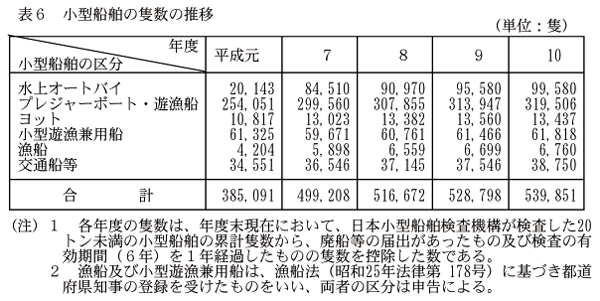 |
| 3 | 小型船舶操縦士海技免状の更新 | ||
| (1) | 更新の要件 | ||
| 小型船舶操縦士海技免状の有効期間(5年)は、海技士海技免状とともに昭和58年の船舶職員法の改正により定められ、その更新手続は、昭和62年4月から実施されている。海技免状の更新を受けるには、身体適性に関する基準を満たすとともに、次のいずれかの要件に該当しなければならないとされている。 | |||
| 1. | 1か月以上の乗船履歴を有する者(通例、船員手帳によって確認) | ||
| 2. | 運輸大臣が、その者の業務に関する経験を考慮して、上記1.と同等以上の知識及び経験を有する者と認定した者(海難審判官、海技試験官、船舶職員養成施設の教員等を認定) | ||
| 3. | 運輸大臣が指定する更新講習を修了した者 | ||
| 船員手帳は、船舶に乗り組む船長や海員などの船員が受有することとされているが、総トン数5トン未満の船舶、湖、川又は港のみを航行する船舶、政令で定める総トン数30トン未満の漁船は除外されている。このため、小型船舶操縦士の有資格者のうち船員手帳を受有しないなど乗船履歴を証する書類を提出できない者は、更新講習を修了し、更新申請を行うこととなる。 更新の要件別の申請状況を申出人の居住する県についてみると、約9割が更新講習を修了し、海技免状の更新申請を行っている。 |
|||
| (2) | 更新申請書等 | ||
| OCR方式の更新申請書には、海技免状の種類、免状番号、氏名、現住所、出生年月日、性別、本籍の都道府県(又は国籍)、申請日を記載することとされており、この記載事項は新規免許の申請書の記載事項と大きな違いがない。 | |||
| また、更新申請書には、更新講習修了証明書(又は上記(1)−1.、2.を証する書類)、海技免状用写真票(新免状貼付用の写真及び署名シールを帖付)、身体検査証明書、旧海技免状及び手数料納付書(更新手数料相当額の収入印紙を貼付)を添付することとされており、これらの添付書類は、新規免許の申請書の添付書類(海技従事者国家試験合格証明書(学科・実技試験及び身体検査)、海技免状用写真票及び手数料納付書)とほぼ同様なものとなっている。 | |||
| (3) | 更新申請の受付等 | ||
| 更新申請は、申請者が希望する管海官庁に提出することとされている。端末が設置されている管海官庁が受け付けた場合は、当該管海官庁において審査、海技従事者免許原簿への登録及び海技免状の作成・交付を行うが、その他の管海官庁が受け付けた場合は、これらの事務のうち登録及び免状作成を当該管海官庁を管轄する地方運輸局、神戸海運監理部又は沖縄総合事務局に依頼することになる。 | |||
| (4) | 更新申請件数 | ||
| 小型船舶操縦士海技免状の更新申請件数は、表7のとおりとなっている。 | |||
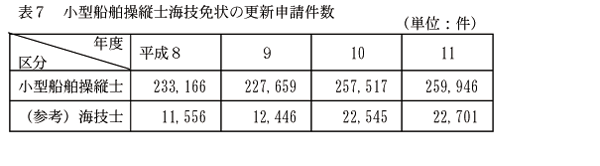 |
| 4 | 小型船舶操縦士海技免状に係る更新講習 | |
| (1) | 指定講習機関 | |
| 更新講習は、運輸大臣の指定を受けて、表8に掲げた6指定講習機関が実施している。 | ||
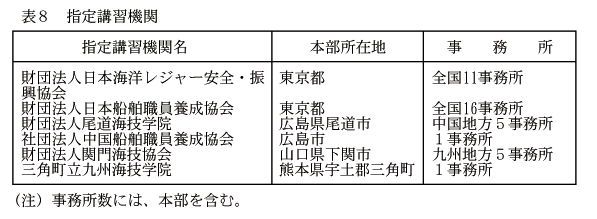 |
| (2) | 更新講習の開催状況 | |
| 財団法人日本海洋レジャー安全・振興協会の平成11年4月から6月における更新講習の開催状況をみると、管海官庁が所在する79市町村では56市町村で延べ
294回開催さている。この外、5指定講習機関が更新講習を開催していることを踏まえると、管海官庁所在地ではおおむね更新講習が開催されていると考えられる。一方、管海官庁の所在しない市町村においても、
193市町村で延べ 400回開催されており、これらの地域における更新講習の需要も多いとみられる。 また、同協会では、更新講習の実施に当たっては、海技免状などと照合することにより受講者が本人に相違ないかを確認した上で受講させ、更新講習修了証明書を交付しているとしている。 |
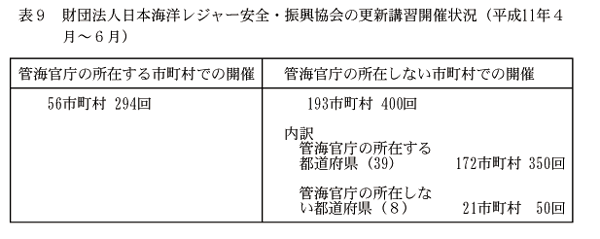 |
| 5 | 新規免許申請と更新申請の手続の比較(出頭の要否等) | |
| (1) | 出頭の要否 | |
| 新規免許申請では、国家試験の合格日から1年以内に免許申請を行う必要があるが、その申請は、「船舶職員法事務取扱要領」(昭和58年5月2日付け員職第
219号)において、郵送による申請が認められている。 更新申請では、海技免状の有効期間満了日までの1年間に更新申請を行う必要があるが、その申請は「海技免状の有効期間の更新及び失効再交付に関する事務取扱要領」(昭和62年4月8日付け海職第 188号)において、本人又は海事代理士が窓口に出頭して行うと定められており、郵送による申請が認められていない。このため、最寄りの講習会場で更新講習を受講した後、本人自身が更新申請を行おうとする場合、管海官庁が地理的に離れているときには、通例、日を改めて管海官庁に出向いて更新申請を行う必要がある。 なお、海技免状の有効期間満了日を経過した場合は、更新講習とは別の失効再交付講習を受講し、失効再交付申請を行わなければならない。 |
||
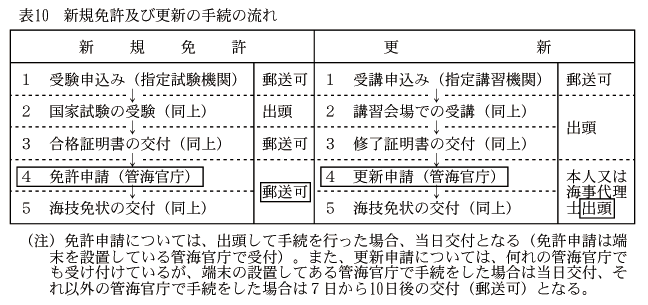 |
| (2) | 合格証明書等の写真貼付の有無 | |
| 新規免許の申請書に添付する指定試験機関作成の国家試験合格証明書には、写真が貼付されており、指定試験機関が本人確認を行った上で割り印を押しているが、更新申請書に添付する指定講習機関作成の更新講習修了証明書には写真が貼付されていない。 |
| 6 | 海事代理士による更新申請の代行 |
| 海事代理士の資格は、海事代理士試験合格者又は行政官庁で海事事務に10年以上従事し、海事代理士の業務に必要な知識があると認定された者とされている。その業務は、船舶職員法等の海事関係法令に基づく申請等の代行や必要な書類を作製することであり、小型船舶操縦士海技免状の更新申請についても受託することができる(平成11年7月現在
784人)。 小型船舶操縦士海技免状の更新申請について海事代理士による代行状況を申出人の居住する県についてみると、更新申請を行った 852人中 841人(98.7パーセント)が海事代理士に更新申請を委託しており、11人( 1.3パーセント)が自ら管海官庁に出頭して更新申請を行っている。 運輸省では、海事代理士は、受託業務を誠実かつ敏速に処理することやその概要等を記録しておくことなどが義務付けられており、業務を受託する際、少なくとも書類により本人確認が行われていると説明しているが、その方法については特段の規定がなく、本人に面会して確認を行うことまでは求められていない。 |
|
参 考
|
行政苦情救済推進会議における意見要旨
|