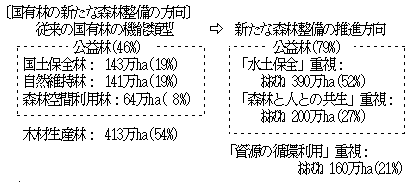|
主な勧告事項等
|
関係省庁が講じた改善措置
|
| |
| → |
国有林野事業の改善については、第 143回臨時国会において可決・成立し、平成10年10月19日に公布・施行(農林水産省設置法の改正に係る部分については、11年3月1日施行)された国有林野事業の改革のための特別措置法(平成10年法律第
134号。以下「改革特別措置法」という。)及び国有林野事業の改革のための関係法律の整備に関する法律(平成10年法律第 135号。以下「関係法律整備法」という。また、これらをまとめて「改革関連法」という。)により、以下のとおり措置した。
〔改革特別措置法の概要〕
国有林野事業の抜本的な改革についての国民の理解を深めるため、改革の趣旨や全体像を明らかにするとともに、改革に必要な特別措置を規定
|
| 1. |
法律の施行日から平成15年度までの期間を「集中改革期間」として、改革に係る特別措置、経過措置等を集中的に実施
|
| 2. |
管理経営の基本方針を公益的機能重視に転換するとともに、民間事業者を活用しつつ効率的な業務運営を推進 |
| 3. |
組織・要員の合理化を推進することとし、定員外職員の定年前退職者に特別給付金を支給する措置を制度化 |
| 4. |
財務の健全化を図るため、約3兆 8,000億円(平成10年10月)の累積債務のうち、約2兆 8,000億円を一般会計が承継(同年10月19日)するとともに、残り約1兆円の債務処理のため、借入金(借換え等)の利子を一般会計から繰り入れる等の処理方針を法定化
|
| 〔関係法律整備法の概要〕 |
| 1. |
国有林野法の一部改正
国有林野法を「国有林野の管理経営に関する法律」に改正し、国有林野の管理経営の目的等を明示するとともに、国民の意見を踏まえた管理経営基本計画の策定・公表等を制度化
|
| 2. |
国有林野事業特別会計法の一部改正
国有林野事業の事業目的に森林の公益的機能の維持増進を基本としつつ運営する旨を追加するとともに、公益林の管理費、事業施設費等に対する一般会計からの繰入れを恒久化
|
|
3.
|
農林水産省設置法の一部改正
営林局及び営林支局を「森林管理局」に、営林署を「森林管理署」に改組 |
| 4. |
国有林野の活用に関する法律の一部改正
国有林野について、新たに保健利用のための活用を積極的に行うものとして位置付け |
|
|
|
| 1 |
国有林野事業の改善に関する計画の抜本的見直し等 |
| (勧 告) |
| 1. |
国有林野の管理・整備、事業経営の目的・方針等国有林野事業の役割及び基本的在り方並びに費用負担の在り方等について、法的措置を含め明確化すること。 |
|
| (説 明) |
| ○ |
国有林野事業の役割と費用負担の状況 |
| |
現在の国有林野事業は、独立採算による事業経営と国土保全・森林管理という2つの性格。しかし,事業経営の採算性と公益性との調整、費用負担の在り方等に関する考え方は、関係法律上必ずしも明確にされないまま、次のような措置が採られてきたところ
| ・ |
国有林野事業改善特別措置法に基づく一般会計からの繰入額:平成8年度 569億円 |
| ・ |
林木育種センター(旧林木育種場)・森林技術総合研修所(旧林業講習所)の一般会計への移替、職員の一般会計への移替(3〜9年度
138人) |
|
|
| → |
○ |
国有林野の管理経営の目標は、第一義的にはその有する公益的機能の維持増進を図ることにある旨、また、管理経営の基本方針を林産物の供給に重点を置いたものから公益的機能の重視へと転換する旨を改革関連法に明記。
また、改革関連法に基づき、独立採算制を前提とした企業特別会計制度から、公益林の適切な管理等のための一般会計繰入れを前提とした特別会計制度への移行、借入金の利子に係る一般会計からの繰入れ措置等を制度化
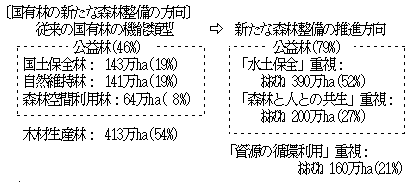 |
|
|
|
| 2. |
国有林野事業に関する抜本的改善方策を早急に策定・公表すること。 |
| 3. |
2.の新たな改善方策の実効性を担保するため、国有林野事業に係る長期収支見通しを策定・公表するとともに、この見通しに基づく国有林野の管理・経営の現状と財政状況、事業全体の改善目標に対する達成状況等を、毎年度作成し公表すること。
|
|
| (説 明) |
| ○ |
国有林野事業の改善に関する計画の達成状況
| 1. |
現行改善計画の基本的枠組み(経常事業部門は平成12年度までに財政の健全化。22年度までに収支の均衡を回復)は達成不可能
| ・ |
平成8年度の財務状況: 1,067億円の損失、累積債務残高は3兆5,228 億円 |
|
| 2. |
個別改善事項についても、
| ・ |
事業全体の財政状況が悪化していることから、収入の確保が求められており、国土保全林、木材生産林等4つの森林の機能類型を踏まえた施業は行い難い状況、 |
| ・ |
林野・土地等の資産処分も、今後、高額な売払いは見込めない状況 |
| 等、推進取組が不徹底で目標の達成は困難 |
|
|
| ○ |
毎年度公表される「国有林野事業の改善の推進状況」においても、現行改善計画にいう、経常事業部門と累積債務処理部門を区分した財政状況は、明らかにされていない。 |
|
| → |
○ |
改革関連法に基づき、平成10年12月25日、農林水産大臣が、1.国有林野の管理経営に関する基本方針、
2.伐採、造林等の事業の実施行為の民間事業者への委託、 3.組織・機構の簡素・合理化、4.職員数の適正化による事業実施体制の効率化、5.長期的な収支の見通し等を内容とする「管理経営基本計画」(5年ごとに策定する10年を1期とする計画。計画期間は平成11年1月1日〜21年3月31日)を、国民の意見を聴いて策定・公表。今後、同計画に即して抜本的改革を推進
|
|
|
|
|
| → |
○ |
累積債務の本格的な処理に当たり、今後50年間を5年ごとに区分した国有林野の管理経営に係る収支の見通しについて試算し、その内容を平成9年度の林業白書の参考付表として公表。
また、改革関連法に基づき、平成11年度以降毎年度、国有林野事業の実施状況に関し、 1管理経営基本計画の前年度の実施状況を公表、
2債務の処理に関する施策の実施状況の国会への報告を制度化。なお、森林の機能類型ごとの収支の把握(森林管理局単位)については、平成10年度にプログラムを開発、11年度から試行的に実施予定
|
|
| 2 |
組織・要員の徹底した合理化 |
|
|
| (1) |
要員規模の見直し |
| (勧 告) |
| 1. |
事業の全面民間実行を早期に行うこととし、要員については、徹底した縮減を図り、要員規模の目標及びその達成時期並びにこれに向けての要員調整の方策等を項目1でいう抜本的改善方策の中で明らかにすること。 |
| 2. |
上記の具体化に向けて、事業の全面民間実行の円滑な移行のための受け皿等の条件整備について検討スケジュール等を明らかにすること。
|
| 3. |
直ようによる製品生産事業は、事業の全面民間実行への移行時期にかかわらず早期に中止すること。 |
|
| (説明) |
| ○ |
要員の合理化状況
要員の縮減は図られつつある(平成3年度期首31,098人→9年度期首 15,444 人)が、7年12月に公表された12年度末1万人規模(定員内約
7,000人、定員外約 3,000人) を達成するためには、自然減のみでは困難 |
| |
(参考)
林野庁は、平成10年度予算概算要求において、「将来目標として現在の約15,000人を15年度末に約3分の1程度とする」要員の合理化策を公表 |
|
| ○ |
直ようの生産コスト等
直ようによる製品(丸太)生産は、請負と比較して約2倍の高コスト、低い労働生産性 |
| ○ |
林政審は、事業の全面民間実行を指摘 |
|
| → |
1. |
国有林野事業の職員数については、国会における法案審議の経過等を踏まえ、改革関連法に基づき、平成10年11月13日に「国有林野事業に係る職員数の適正化について」を閣議決定。
これを踏まえ、管理経営基本計画において、要員調整方策を次のとおり明記
| i |
平成15年度までの集中改革期間終了後できるだけ早い時期に、職員数を今後の業務に応じた必要かつ最小限のものとすること。
|
| ii |
このため、同期間内において、本人の意思に反して退職させないとの考え方の下で、職員数の適正化を緊急に推進すること。 |
| iii |
省庁間配置転換に加え、改革関連法に基づく定員外職員を対象とした特別給付金支給制度等を活用して定年前退職を促進すること。 |
| 〔参考〕 |
| ・ |
職員数:平成11年4月1日現在12,187人(対前年度 ▲ 1,479人)
[うち定員内 7,587人、定員外 4,600人] |
| ・ |
定員内職員の新規採用者数:平成10年度80名、11年度75名 |
|
|
|
|
|
| → |
2. |
今後の事業の実施については、国会における法案審議の経過等を踏まえ、管理経営基本計画において、次のとおり明記
| i |
民間事業者の能力を活用しつつ、国の業務は、保全管理、森林計画、治山等に限定し、伐採、造林等の事業の実施行為は、集中改革期間終了後できるだけ早い時期にそのすべてを民間事業者に委託して行うこと。また、これまで国が実施してきた収穫調査等の業務については、改革関連法で新たに設けられた指定調査機関への委託を推進すること。
|
| ii |
地域の実情等を踏まえつつ民間委託になじまないものについては、国で実施するなど適切に対処すること。 |
| なお、収穫調査等については、平成11年度から委託を開始する予定
|
|
| → |
3. |
上記 2の民間事業者への委託を推進するに当たり、製品生産事業に従事している基幹作業職員等については、その就労の確保に関し、早急に条件整備を図りつつ森林調査、境界の保全等の保全管理業務に係る作業への移行に努めていくとともに、当面、このような業務では年間雇用の確保が困難な場合には、造林、林道等の業務による就労の確保に努める予定 |
|
| (2) |
営林局、営林支局及び営林署等の在り方の見直し |
| (勧 告) |
| 1. |
現在の営林局、営林支局及び営林署は、抜本的に縮小・再編成するものとし、廃止される組織の代替組織は設けないこと。例外的に経過措置として代替組織を設ける場合においては、廃止期限を明確にすること。
また、新たに設ける組織体の内部組織は、主たる業務の性格に沿った簡素なものとするととも に、経理処理については、条件整備を早期に行い、事業経営、管理・財産保全及び治山の各部門に明確に区分すること。 |
| 2. |
現在の営林局、営林支局及び営林署の下部組織(木材サービスセンター、営林事務所など)については、速やかに廃止するなど、抜本的に縮小・再編成すること。
|
|
| (説 明) |
| ○ |
営林局、営林支局 |
| |
・ |
組織区分別の推移
| |
営林局
|
(支局)
|
営林署
|
森林事務所
|
事業所
|
|
昭和53年度首
|
14
|
(0)
|
351
|
2,333
|
1,214
|
|
平成3年度首
|
9
|
(5)
|
316
|
1,844
|
522
|
|
〃9年度首
|
9
|
(5)
|
264※
|
1,256
|
71
|
|
※ 平成9年度末に35の営林署を廃止済み
|
|
| ・ |
営林局を廃止して設置した営林支局は再編前とほぼ同様のブロック組織体 |
| ○ |
営林署 |
| |
・ |
営林署本署は、現在まで87署廃止したとしているが、代替組織を76設置
| (局に設置) |
森林技術センター(14)、森林センター(7)、木材サービスセンター(1)
需要開発センター(1)、木材販売所(1) |
| (署に設置) |
森林経営センター(17)、森林管理センター(10)、営林事務所(22)
森林環境保全センター(1) 、分室(2)
|
|
| |
・ |
また、営林署では、借入金及び一般会計からの繰入金並びに自己収入による事業等に区分した経理処理は全く行われておらず、経営分析・評価も未実施
|
| |
・ |
森林事務所については、統廃合可能なものや署内に集約設置が可能なもの |
| |
・ |
組織規程等上は廃止されたこととなっている種苗事業所、製品事業所等についても、引き続き旧事業所等の現場で直よう事業を行っている例が多数
|
|
| → |
1. |
国有林野事業の組織については、改革関連法等により、現行の14営林(支)局を7ブロックの「森林管理局」に、また、
229営林署を、森林整備の単位である流域を基本とした98の「森林管理署」、14の「森林管理署支署」及び8の「森林管理事務所」(森林管理局直轄組織)に再編。
なお、新組織への移行を円滑に進めるため、暫定組織として、被統合営林(支)局に森林管理局の分局7(15年度末に廃止)を、また、被統合営林署に森林管理署の事務所
109(15年度末までに逐次廃止)をそれぞれ設置。
新たに設ける組織体の内部組織については、局の森林管理部と事業部を計画部と森林整備部に再編するなど、森林管理等を主体とする業務運営への変化に対応したものに改編。引き続き、業務運営を効率的に行い得る簡素なものにしていく予定。
国有林野事業の経理処理については、事務機械システム等の改善を行い、事業経営(造林、林道整備等)、管理・財産保全(森林保全管理、
資産処理等)及び治山の各部門の経費について把握する方向で検討中 |
|
|
|
|
| → |
2. |
これまでの営林局、営林支局及び営林署の下部組織については、その在り方について、廃止を含め徹底した見直しを行い、集中改革期間終了までに、逐次結論を得、廃止するとしたものについては逐次廃止する予定 |
|
| 1. |
国有林野における林道整備については、補修・修繕、森林保全の維持に係るものを除き、当分の間、必要最小限なものに抑制すること。
|
| 2. |
林道整備費等を営林局、営林支局及び営林署の一般管理費的な経費に支出する場合の額あるいは割合について、基準を明確にすること。 |
|
| (説 明) |
| ○ |
経常事業部門の歳出額に占める造林、林道の事業投資(事業施設費)は、ほぼ同じ割合で推移。これら事業投資額の大半は一般会計繰入れ及び借入金。自己資金は、8年度では林道事業費0.6%
、造林事業費1.0%にすぎない。
|
| ○ |
林道開設の投資効果(当該林道を使用した伐採・これに伴う林産物販売収入)が乏しい例。また、今後、既設林道の活用を図ることが一層重要
|
| ○ |
林道整備費の一般管理費的な経費への支出 |
| ・ |
営林局及び営林署では、林道整備との関連性が必ずしも明確でない一般管理費的な経費に林道整備費から多額の支出
営林局の中には、8年度に管内全組織の一般管理費的な経費の約5割を林道整備費から支出している例。この額は当該営林局の林道整備費総額(6億
3,400万円)の10.9%
なお、民有林補助事業では、消耗品購入・光熱水料等の工事雑費等はおおむね事業費の額に応じて3%(3億円超)から8%( 3,000万円まで)を限度
|
|
| → |
1. |
林道整備については、林野庁業務部業務第一課長通達(「林道開設路線の選定等について」(平成9年12月19日付け9−16号))により、投資の適正化を指導。
平成10年1月及び11年1月の営林(支)局担当課長会議で通達の趣旨を徹底。
これを受けて、営林(支)局では、平成10年度の開設路線の選定に当たり、直近のデータによる林業効果指数等を用いるなど、投資の必要性について精査し、投資のより一層の適正化を図ったところ。
なお、平成10年度の林道開設費及びその延長は、それぞれ 165億円(対前年度比89%)、 347キロメートル(同86%)(いずれも当初予算)
|
|
|
|
|
| → |
2. |
林道整備費等を森林管理局及び森林管理署の一般管理費的な経費に支出する場合の額あるいは割合については、組織再編後における事業の運営状況等を勘案しつつ検討してきたところ。
一般管理費的な経費については、組織・体制と密接な関係があり、引 き続き、局・署の下部組織の見直しを検討し、また職員数の適正化を進めていくこととしていることから、これらの状況の推移を踏まえつつ、今後も引き続き検討を進め、早期に結論を得る予定 |
|
| 3. |
国有林野における治山事業費による植付け・保育等については、国土保全上治山事業として真に必要なものに限定すること。 |
|
| (説 明) |
| ○ |
造林事業費は近年総額が抑制されていることから、必要な事業量を確保できず、治山事業費による植付・保育等を実行。8年度の更新総面積(4,233
ha) のうち治山事業費による実行面積は 1,428haと33.7%に及ぶ。 |
| |
(参考) 造林事業費:3年度 221 億円 → 8年度 144 億円
治山事業費のうち保安林整備名目による造林関係費:3年度 8億円 → 8年度 73 億円 |
|
| → |
○ |
治山事業における保安林改良事業等については、林野庁業務部業務第一課長通達(「保安林改良事業等の対象地の選定について」(平成10年1月28日付け10−1号))により、事業の適正な実施を指導。
また、平成10年7月及び11年1月の営林(支)局担当課長会議で通達の趣旨を徹底。
林野庁において、3森林管理局等(平成10年度の治山事業費約51億円のうちその4分の1の約13億円を執行予定)を抽出して治山事業費による植付け等の実施状況を把握した結果、いずれの森林管理局等においても、すべて非皆伐林を対象に植付け、保育等を行っているなど、事業の適切な実施が図られていることを確認
|
|
|
|
|
|
| 1. |
多方面にわたる需要開拓が必要な物件などについて、広域的にかつ迅速な売払いを行うための一元的な仕組みを早急に確立すること。 |
| 2. |
非事業用資産及び非効率な使用あるいは管理実態となっている事業用資産についての実態把握(洗い出し)を徹底して行い、これら資産のうち売却可能なものについては、公用・公共用優先の原則を踏まえつつ売却を推進すること。また、貸付地のうち、道路敷あるいはダム敷等で公的機関が借受人となっているものについては、売却あるいは有償所管換えの推進を図ること。 |
| 3. |
公的機関側の資金事情等から売却処分を長期にわたり留保しているもののうち、買受け意向が明確なものについては具体的な売却スケジュールを確定すること。 |
|
| (説 明) |
| ○ |
林野、土地等の売払実績は、8年度は計画額約 920億円に対して 600億円。3〜8年度の資産処分累計額は、 3,381億円(計画達成率:65.5%)。今後、高額な売払いは見込めない状況 |
| ○ |
処分可能性の見込みがあり処分計画に計上したものの、市町村の財政事情等から長期間売払いを留保しているものや、大規模資産であることから売払いに工夫が必要なものなど、結果的に売却できないものが多数。しかし、その原因・処分促進方策について組織的な検討・取組が不十分 |
| ○ |
事業所等を廃止しても、当該土地等を処分計画に計上していないものが多数ある等処分可能資産の徹底的な洗い出しが必要(苗畑、営林署、森林事務所、貯木場等)。
非効率な事業用地(庁舎敷、宿舎敷等)、非効率な管理実態となっている小規模林地など多数 |
| ○ |
道路敷あるいはダム敷等の公的機関への貸付地について、有償所管換えあるいは有償貸付が相手側の財政事情等により進んでいない。 |
|
| → |
1. |
林野・土地売り払いについては、局・署管内のみでは需要開拓等が困難とされる物件(金額が大きいものなど)については、必要な情報収集、需要開拓等に関し、林野庁と局・署が一体となった全庁的な体制で取り組むこととしており、平成10年度には、不動産業界等への働きかけを重点化するとともに、
| i |
「一般情報公開物件一覧表」(年間に予定する公売物件の全国情報)の配布先の拡大(建設業界等) |
| ii |
公売情報等をファクシミリで提供するファクシミリサービスの開始 |
| iii |
月刊誌等への広告掲載の再開 |
等を実施 |
|
|
|
|
| → |
2. |
資産の売却、有償所管換え等については、次のとおり推進
| ・ |
平成10年2月の営林(支)局事業担当部長会議等により、非事業用資産等の実態把握の徹底を指導。
勧告で指摘した「廃止事業所等の跡地で資産処分計画に計上されていないもの」については、平成9年度には、13件(77ヘクタール)を資産処分計画に計上し、うち4件(44ヘクタール、約
3,900万円)について売払いを実施 |
| ・ |
無償貸付地(全国約2万件、約2万 4,000ヘクタール)については、平成9年度には、
225件、70ヘクタール、約 1,300万円の有償化を実現するとともに、 199件、 262ヘクタール、約31億
900万円を売却。
このうち、無償で使用させている財産価格が 3,000万円以上の一般国道敷(平成9年9月1日現在:全国で36路線、
733ヘクタール)については、平成9年4月に建設省と調整後、順次所管換えを実施(9年度:11路線、31ヘクタール、5億
5,800万円)。
また、平成10年3月には、新規のダム敷地について、有償所管換えとすることで建設省と調整を終えたところ。今後、引き続き、財産価格が
3,000万円未満の一般国道敷についても有償所管換えが図られるよう建設省等と協議を進める予定 |
|
| → |
3. |
公的機関から活用要望があっても活用計画等が具体的なものとなっていない物件については、国有林野事業と公的機関との密接な関係に配慮しつつ、再度活用の意向の確認を行い、スケジュールの早期確定に努めることとし、平成10年2月の営林(支)局事業担当部長会議等により局を指導したほか、林野庁自らも他省庁等に対する働きかけを実施。
これらにより、売払いが実現した例(平成10年度)は次のとおり。
| i |
建設省の公園用地(福岡県内)
毎年度の働きかけ、補正予算等の機会をとらえた働きかけにより平成11年3月に有償所管換え |
| ii |
宿舎跡地(長野県内)
取得の要否の検討が長期にわたっていたが、早期の結論付けを要請し、取得要望のないことを確認の上、平成11年3月に公売
|
| iii |
返地された旧貸付地(高知県内)
地元から取得要望があったが、具体化が遅れていたため、再度確認したところ、取得要望を撤回したことから、平成10年9月に公売 |
|
|