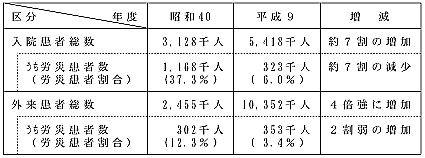| |
(2) |
保険給付の支給制限等に係る運用の統一化 |
| |
|
労働者が、故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、負傷、疾病、障害等を生じさせ、又はその原因となった事故を生じさせたときは、労災保険法第12条の2の2第2項に基づき、保険給付の全部又は一部を行わないことができるとされている。この支給制限の取扱いについて、労働省は、通達により、「事故発生の直接の原因となった行為が、法令(労働基準法、鉱山保安法、道路交通法等)上の危害防止に関する規定で罰則の附されているものに違反するものと認められる場合」に、療養補償給付及び療養給付を除く保険給付について、給付の都度、所定給付額の30パーセント相当額の支給を制限することとしている。
また、事業主の故意又は重大な過失により生じた業務災害については、労災保険法第25条第1項に基づき、当該事業主から保険給付に要した費用の全部又は一部を徴収することができるとされている。この費用徴収の取扱いについて、労働省は、通達により、事業主が法令の危害防止のための規定に明白に違反したため、又は監督行政庁から危害防止のための具体的措置について指示を受けたが、その措置を講ずることを怠ったため、事故を発生させたと認められる場合に、療養補償給付及び療養給付を除く保険給付に要した費用の30パーセント相当額を徴収することとしている。
|
| |
|
|
|
| |
|
今回、13労基局における労働者への支給制限及び事業主からの費用徴収の実施状況について調査した結果、以下のような状況がみられた。 |
| |
|
1.
|
平成7年度から9年度までの間における労働者への支給制限及び事業主からの費用徴収の実績をみると、支給制限は7労基局で74件、費用徴収は10労基局で
125件となっている。 |
| |
|
2.
|
労働者への支給制限の取扱方針をみると、労基局の中には、前述の通達に基づく支給制限の要件に付加して、i)交通事故の場合、人身事故を伴った場合のみに適用を限定する(1労基局)、ii)有罪が確定したもののみに適用を限定する(1労基局)との独自の取扱方針をとっているものがある。
また、個別事案への適用状況をみると、労働者の一方的な過失のみに限定して適用している例(1労基局)、労働者の一方的な過失でも適用していない例(2労基局)等と、労基局により、その適用が区々となっている。
|
| |
|
3.
|
事業主からの費用徴収の取扱方針をみると、労基局の中には、前述の通達に基づく費用徴収の要件に付加して、i
)有罪が確定したもののみに適用を限定する(4労基局)、ii )書類送検したもののうち死亡事故のみに適用を限定する(1労基局)との独自の取扱方針をとっているものがある。
また、個別事案への適用状況をみると、i )罰金刑を受けたものでも適用していない例(2労基局)、ii )書類送検したものについて適用している例(1労基局)、書類送検したものでも適用していない例(1労基局)等と、労基局により、その適用が区々となっている。
|
| |
|
|
|
| |
|
このように、労働者への支給制限及び事業主からの費用徴収に係る各労基局の取扱いに差異が生じている理由は、本省の示している支給制限又は費用徴収に係る通達のみでは具体性に欠けるため、各労基局が個別事案に適用する場合に的確な判断が行い難くなっていることによると認められる。 |
| |
|
|
|
| |
|
したがって、労働省は、労働者への支給制限及び事業主からの費用徴収の適切な運用を図る観点から、行政実例を分類・体系化するなどの方法により支給制限及び費用徴収の取扱いに係る判断基準の一層の具体化を図る必要がある。 |
| |
|
|
|
| |
(3) |
労災保険担当職員の配置の見直し |
| |
|
労災保険に係る適用、徴収、認定及び保険給付の業務は、労基局及び監督署が分担して実施しており、労基局は、主に、i)労災保険の適用業務、ii)過年度保険料の徴収業務、iii)複雑・困難な事案の労災認定支援業務等を、監督署は、主に、i)現年度保険料の徴収業務、ii)労災認定業務、iii)保険給付業務等を実施している。
労基局及び監督署の労災保険担当職員の定員は、労基局では、「過労死」等の複雑・困難な事案の迅速な処理を図るためとして、平成7年度の 1,793人から9年度には
1,857人と徐々に増員され、監督署では、7年度の 1,663人から9年度には 1,587人と減員されてきている。 |
| |
|
|
|
| |
|
今回、18労基局及び19監督署における労災保険担当職員の配置状況について調査した結果、以下のような状況がみられた。 |
| |
|
1.
|
労基局における労災保険関係の業務を量的に把握する際の基礎的な指標と認められる事業所・企業統計調査の事業所数・労働者数、適用事業数、適用労働者数、労働災害発生件数及び新規受給者数に基づき、平成9年度の労災保険担当職員1人当たりの指数を最大の労基局と最少の労基局とで比較すると、事業所・企業統計調査の事業所数で
2.1倍、同労働者数で 3.7倍、適用事業数で2.5倍、適用労働者数で 3.4倍、労働災害発生件数で 3.4倍、新規受給者数で 3.8倍の格差が生じている。 |
| |
|
2.
|
監督署における労災保険関係の業務を量的に把握する際の基礎的な指標と認められる適用事業数、適用労働者数、労働災害発生件数及び保険給付支払件数に基づき、平成9年度の労災保険担当職員1人当たりの指数を最大の監督署と最少の監督署とで比較すると、適用事業数で
2.8倍、適用労働者数で 3.1倍、労働災害発生件数で 4.5倍、保険給付支払件数で 4.4倍の格差が生じている。 |
| |
|
|
|
| |
|
このような格差が生じている原因は、労働省において、従前からの経緯等により配分した各労基局管内の定員について、労働災害を取り巻く環境の変化や前述の指数などに対応した十分な見直しを行ってきていないことによるものと認められる。 |
| |
|
|
|
| |
|
したがって、労働省は、労災保険業務に係る適正な職員配置を図る観点から、地域特性等質的な面をも配慮しつつ、労基局及び監督署の業務の実態に即して職員配置の見直しを行う必要がある。 |
| |
労働省は、労災保険法第2条の2及び第23条に基づき、業務災害及び通勤災害を被った労働者(以下「被災労働者」という。)の療養に関する施設の設置・運営等の社会復帰促進事業、被災労働者及びその遺族の援護を図るための援護事業、業務災害の防止に関する活動に対する援助、労働者の安全及び衛生の確保のための安全衛生確保事業等の労働福祉事業を行っており、これらの事業は労働省、労働福祉事業団(以下「労福事業団」という。)及び各種関係団体により実施されている。 |
| |
(1) |
労災病院の在り方の見直し等 |
| |
|
ア |
労災病院の在り方の見直し |
| |
|
|
労災病院は、被災労働者に対する診療、医療リハビリテーションを行う施設であり、昭和20年代後半から30年代に31病院が集中的に設置され、平成10年3月末現在、39病院(運営の収支差が赤字の場合に、それを交付金で補てんする総合せき損センター及び吉備高原医療リハビリテーションセンター(以下「交付金病院」という。)の2病院を含む。)が労福事業団によって設置・運営されている。
労災病院は、昭和30年代までは、多発する外傷性疾患についての外科的ないし整形外科的医療、リハビリテーション医療、じん肺症等を中心とする労災医療に取り組んできた。その後、墜落、崩壊等の外傷的な事故が減少した反面、様々な就業形態の変化により複雑多様な障害が発生してきたため、多診療化による総合性を強め、50年代以降は、健康診断機能の拡充など、労働災害の予防面にも取り組んできている。
最近では、労災病院は、職場でのメンタルヘルスや過労死、深夜業・VDT作業等による健康障害等、労働環境の変化に伴う新たな健康問題についても取り組んできており、労災病院の機能の見直しや地域医療機関との連携の在り方などが検討課題となっている。
今日、労災病院をめぐる環境は、その設置当初とは大きく変化しており、政府は、平成9年12月、労災病院の今後の在り方について、「1)勤労者医療の中核的機能を高めるため、労災指定医療機関や産業医等との連携システムを含め、その機能の再構築を図る。2)労災病院の実態(労災患者入院比率8パーセント)にも照らし、その運営の在り方につき、統合及び民営化を含め検討する。3)毎年度損失が生じている経営状況を改善し、労災保険からの出資金の縮減を図る。」ことを閣議決定している。
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
今回、労災患者に対する医療供給体制の整備状況、労災病院の果たしている機能、労災患者への寄与状況、損益状況等について調査した結果、以下のような状況がみられた。 |
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
1.
|
(労災患者に対する医療供給体制の整備状況) |
| |
|
|
|
国は、労災患者に対する診療機関を確保するため、労災保険制度の発足当初から、労災病院以外に、都道府県労働基準局長が指定する医療機関(以下「労災指定医療機関」という。)においても、労災保険による療養の給付ができるよう措置してきている。これら労災指定医療機関は、昭和40年当時1万
3,805機関であったものが、平成9年12月末には2万 7,538機関と約2倍に増加している。また、調査した20労災病院(交付金病院を除く。)と病床数が同等規模の15労災指定医療機関とを比較すると、医療従事者数、診療科目、診療設備等はほぼ同様となっており、労災患者の診療上、両者の間に大きな相違はなく、労災患者に対する医療供給体制は、労災病院の設置当初と比較し、格段に整備充実されている。 |
| |
|
|
|
(被災労働者の減少と労災病院の利用状況) |
| |
|
|
|
被災労働者の推移についてみると、昭和43年度の 172万人をピークに、官民の労働災害防止努力の成果、労働環境の変化等を反映して、平成9年度には65万人(ピーク時の約3分の1)にまで減少してきている。
また、労災病院の利用状況をみると、下表のとおり、入院、外来とも患者数が増加しているものの、被災労働者の著しい減少傾向を背景に、労災患者数の占める割合は、入院、外来とも著しく減少し、昭和40年度当時と平成9年度とを比較すると、入院は37.3パーセントから
6.0パーセント、外来は12.3パーセントから 3.4パーセントにまで、それぞれ低下している。 |
| |
|
|
|
|
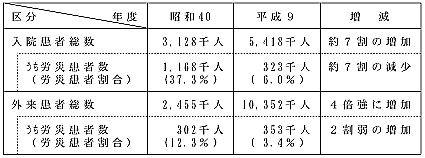 |
| |
|
|
|
なお、調査した労災指定医療機関の中には、同一の医療圏に設置されている労災病院を上回る労災患者を診療しているものもみられる。
このように、労災病院の労働災害の「専門病院」としての役割は低下してきており、新たな健康問題等への対応を含め、その再編整備が必要となっている。
|
| |
|
|
2.
|
(労災病院全体の経営状況) |
| |
|
|
|
次に、労災病院全体の経営状況についてみると、交付金病院を除く37労災病院の経営は、労災保険からの出資金に係る収支を除いた医業収支で行われており、平成4年度以降は毎年度収入が支出を上回っている。その結果、収支差から生じる剰余金を内部留保として積み立てており、平成9年度末現在の累計額は
507億 6,300万円となっている。
一方、37労災病院の昭和63年度から平成9年度までの10年間における施設や機器等の整備に要した経費は、約 3,640億円となっており、このうち、その大半に当たる約
3,302億円(90.7パーセント)は出資金で賄われ、労災病院の自前収入からは約338億円(9.3パーセント)の支出となっている。この結果、37労災病院の昭和63年度から平成9年度までの出資金に見合う減価償却費を含めた損益をみると、毎年度損失を計上しており、この10年間の損失金の累計は約
1,370億円に達している。 |
| |
|
|
3.
|
(個別労災病院の配置と経営状況) |
| |
|
|
|
個別の労災病院の配置状況をみると、同一の二次医療圏に複数設置されているものが3地区(北海道、愛知及び北九州地区)に6病院、都県は異にするものの、病院間の距離で約10キロメートルと近距離に設置されているものが1地区(首都圏)に3病院みられる。これらの病院の経営状況をみると、いずれも、平成7年度から9年度まで連続して、減価償却を行った損益ベースで損失を計上している。
労働省では、施設・設備に投入する出資金の抑制や人件費率の引下げ等経営の合理化を図る観点から、これら既存施設の配置の見直しの検討を行っているものの、いまだ統廃合等の措置は講じられていない。
なお、37労災病院の中には、医業収支で3年連続で黒字となっている病院が21病院あり、損益ベースにおいても利益を計上しているものが平成7年度に2病院、8年度に2病院、9年度に1病院みられる。
|
| |
|
|
|
| |
|
|
したがって、労働省は、労働福祉事業の効果的かつ効率的な実施の推進を図る観点から、以下の措置を講ずる必要がある。 |
| |
|
|
1.
|
労災病院をめぐる環境の変化に的確に対応するため、労災病院の機能の再構築を進めるとともに、同一の二次医療圏等に複数設置されているなど労災病院の配置状況、損益ベースにおける経営状況、労災患者の利用実態等を総合的に勘案し、労災病院として存置する必要性の乏しい施設については、その統合又は民営化を進めることとし、そのため、早急に再編整備計画を策定し、速やかに当該計画の実現を図ること。 |
| |
|
|
2.
|
上記の再編整備計画の実現までの間においても、単年度損益を改善し、出資金の更なる抑制を行い、その縮減を図ること。 |
| |
|
|
|
|
|
| |
|
イ |
労災病院の経営の改善 |
| |
|
|
労災病院に対する出資金の縮減を図るためには、労災病院について、損益ベースによる経営管理を行うとともに、業務運営全般にわたって、経営改善の視点からの見直しを行っていくことが必要となっている。 |
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
今回、労福事業団本部及び労災病院における経営管理及び業務運営の実施状況について調査した結果、以下のような状況がみられた。 |
| |
|
|
1.
|
労福事業団本部及び22労災病院(交付金病院を含む。)の経営改善に向けた取組状況をみると、以下のような状況にある。 |
| |
|
|
|
i
|
労福事業団本部では、人件費率等22項目の経営分析指標を設定し、毎年度、各労災病院ごとに分析を行った上、その結果を一覧表にして各労災病院に送付しているが、分析結果に基づく経営指導は十分なものとなっていない。
なお、労福事業団本部が行っている経営分析は、労災病院相互間の比較が中心であり、民間病院の経営状況と比較するなどの分析は行われていない。 |
| |
|
|
|
ii
|
いずれの労災病院においても、詳細な経営分析を行っておらず、経営改善に向けた個別具体的な目標を盛り込んだ中長期的な経営改善計画等を策定していない。
また、調査した労災病院のうち20病院は、経営改善を推進するための委員会等を設置していない。 |
| |
|
|
2.
|
全労災病院の職員数は、正職員については、平成4年度末現在の定員1万 2,938人から9年度末には1万
3,325人と 387人の増員となっており、嘱託職員についても、4年度末現在の2,214人から9年度末には 2,556人と 342人の増員となっている。
20労災病院(交付金病院を除く。)における医師、薬剤師、検査技師の配置状況をみると、以下のような状況にある。 |
| |
|
|
|
i
|
平成9年度における医師(勤務形態は正職員の医師とほぼ同様である嘱託医師を含む。)1人当たりの延べ患者数をみると、平均で
6,865人となっているものの、病院により相当の開き(9,000人以上が3病院、 6,000人以下が3病院) があり、延べ患者数の割に医師の配置数が多い病院の中には、医師1人当たりの延べ患者数が
5,625人と平均延べ患者数の約8割となっている病院(1病院)がある。
また、診療科別の医師1人当たりの延べ患者数を内科についてみると、平均で 7,117人となっているものの、病院により相当の開き(1万人以上が4病院、
6,000人以下が3病院)がある。 |
| |
|
|
|
ii
|
平成9年度における薬剤師(嘱託薬剤師を含む。嘱託薬剤師については、勤務時間が正職員より短いことから 0.5人で換算)1人当たりの調剤件数をみると、平均で3万
4,483件となっているものの、病院により相当の開き(4万件以上が4病院、2万件以下が2病院)があり、調剤件数の割に薬剤師の配置数が多い病院の中には、薬剤師1人当たりの調剤件数が
8,815件と平均調剤件数の約4分の1となっている病院(1病院)がある。
なお、この病院では、平成8年度から院外調剤の拡大を行ったことから院内調剤が大幅に減少したにもかかわらず、薬剤師の配置数の見直しを行っていない。
|
| |
|
|
|
iii
|
平成9年度における検査技師(嘱託検査技師を含む。嘱託検査技師については、勤務時間が正職員より短いことから0.5人で換算)1人当たりの検査件数をみると、平均で5万8,906件となっているものの、病院により相当の開き(7万件以上が6病院、5万件以下が4病院)があり、検査件数の割に検査技師の配置数が多い病院の中には、検査技師1人当たりの検査件数が2万
5,114件と平均検査件数の約4割となっている病院(1病院)がある。
なお、この病院では、病理検査及び生体検査以外の検査を外部委託しているにもかかわらず、検査技師の配置数の見直しを行っていない。 |
| |
|
|
3.
|
物品の購入等の契約手続については、「労働福祉事業団会計規程」(昭和32年11月1日付け規程第12号)に基づき、予定価格の額等に応じ指名競争契約又は随意契約をする場合を除き、すべて公告して競争に付すこととされている。
22労災病院(交付金病院を含む。)における契約事務等の実施状況をみると、以下のような状況にある。 |
| |
|
|
|
i
|
平成8年度及び9年度に行った物品購入等の契約 1,249件のうち、随意契約によっているものが 525件(42.0パーセント)となっている。これらの中には、i)ほかにも契約が可能な業者がいるにもかかわらず、その確認を十分行わないまま随意契約とした例(4病院)、ii)一括して競争契約とする余地があったにもかかわらず、個々に随意契約とした例(5病院)、iii)競争契約にすると事務手続に時間を要するとして随意契約とした例(2病院)があり、競争入札を推進すべき必要性のあるもの等がある。 |
| |
|
|
|
ii
|
医薬品の調達状況をみると、大半の労災病院は、他の労災病院における価格情報を収集していないため、同一の医薬品の同一の包装薬価(一定の量を販売の単位とする価格)に対する調達価格が、i)病院間で包装薬価の98.0パーセントから88.0パーセントと10ポイントもの格差がみられる例(注射薬フェロン)、ii)同一の医療圏に所在する病院間で包装薬価の97.6パーセントと89.1パーセントと
8.5ポイントもの格差がみられる例(内用薬メバロチン錠)等があり、病院間での情報交換を密にする必要性がある。 |
| |
|
|
|
iii
|
高額医療機器の導入状況等をみると、i)平成7年度に脳血管障害等の検査を行うとしてMRI(磁気共鳴断層撮影装置)を導入しているが、当初の利用見込みに対する利用率が9年度で59.6パーセントと低調な例(1病院)、ii)4年度及び5年度に血管連続撮影装置をそれぞれ1機導入しているが、利用見込みが過大であったため、当初の利用見込みに対する利用率が9年度で57.7パーセント及び54.9パーセントといずれも低調な例(1病院)等がみられ、高額医療機器の導入に当たっての利用見込みの検討が不十分となっているものがある。 |
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
したがって、労働省は、労災病院の経営改善を図る観点から、以下の措置を講ずる必要がある。 |
| |
|
|
1.
|
労福事業団本部による経営分析をより的確なものとするとともに、その分析結果をも踏まえた経営改善計画の策定及びその適切な実施を推進すること。 |
| |
|
|
2.
|
医師、薬剤師及び検査技師の配置の適正化を図り、要員の合理化を推進すること。 |
| |
|
|
3.
|
物品購入における一般競争入札の拡大、医薬品の調達における病院相互の情報交換の充実、適切な利用計画に基づく高額医療機器の導入を推進すること。 |
| |
|
|
|
|
|
| |
(2) |
その他の労働福祉事業の見直し |
| |
|
ア |
休養所の廃止 |
| |
|
|
休養所は、主として被災労働者であって休養を必要とする者のための宿泊施設であり、昭和39年度から55年度にかけて11か所設置された。その後、平成10年3月に廃止されたもの1か所を含め、3か所が廃止され、平成10年度末現在では、8か所が設置・運営されている。休養所の運営は、昭和57年10月から財団法人労働福祉共済会(以下「共済会」という。)に委託して行われており、施設及び備品等の整備については、労災保険から出資金が支出されているが、施設の運営に要する経費は、労災保険から支出されておらず、共済会が運営による収入で賄うこととしている。 |
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
今回、休養所の運営状況について調査した結果、以下のような状況がみられた。 |
| |
|
|
1.
|
休養所の利用状況についてみると、平成9年度における9休養所の延べ宿泊者数は8万 2,028人で、このうち被災労働者の延べ宿泊者数は
1,846人と 2.3パーセントを占めている。また、この 1,846人は、障害等級8級以上の被災労働者9万 5,139人の 1.9パーセントとなっている。
被災労働者の延べ宿泊者数のうち、温泉保養制度(原則として、障害等級8級以上の障害補償給付又は障害給付の支給決定を受けた者又は受けると見込まれる者が、休養所又は都道府県労働基準局長が温泉保養を委託した民間等の宿泊施設において温泉保養を行った場合に、その宿泊費(最長6泊)及び交通費を労災保険が負担する制度)を利用した平成9年度の9休養所の延べ利用者数は
304人である。これは、全国における温泉保養制度の延べ利用者数(保養日数から換算)1,058人の28.7パーセントに相当し、残りの71.3パーセントは民間等の宿泊施設を利用していると推計できる。
|
| |
|
|
2.
|
9休養所の経営状況をみると、宿泊定員に占める宿泊者数の割合は、年々減少してきており、平成9年度では31.7パーセントとなっている。また、9休養所全体の平成9年度の運営収支は、約
2,800万円の赤字となっており、共済会の休養所の運営に係る欠損金の累計は、9年度末現在で約 7,000万円に達している。 |
| |
|
|
3.
|
また、休養所の老朽化に伴う建て替えや大規模補修等のために、平成5年度から9年度までの間に約32億円が労災保険の出資金から支出されている。 |
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
したがって、労働省は、民間等の宿泊施設の普及状況、被災労働者の利用状況及び休養所の経営実態等を踏まえ、労働福祉事業の効果的かつ効率的な実施の推進を図る観点から、休養所については、民間への売却等により、順次、廃止する必要がある。
なお、廃止までの間、新たな建て替え、大規模補修等は行わないこととする必要がある。 |
| |
|
|
|
|
|
| |
|
イ |
リハビリテーション学院の廃止 |
| |
|
|
リハビリテーション学院(以下「リハビリ学院」という。)は、労災病院に勤務する理学療法士及び作業療法士(以下「理学療法士等」という。)を養成するため、昭和41年4月に九州労災病院(北九州市)に設置され、毎年度40人程度の卒業生を送り出している。 |
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
今回、リハビリ学院の運営状況について調査した結果、以下のような状況がみられた。 |
| |
|
|
1.
|
平成4年度から9年度の間にリハビリ学院を卒業した 253人のうち、労災病院に就職した者は
109人(43.1パーセント)であり、残りの 144人(56.9パーセント)は、民間の病院等に就職している。
また、学院生は、九州出身者が約8割を占めていることから、九州地域等近隣の労災病院への就職は多いが、遠隔地の労災病院への就職はほとんどみられない。
|
| |
|
|
2.
|
リハビリ学院については、職員給与のほか、運営の収支が赤字の場合、その収支差を労災保険からの交付金で賄っており、平成9年度の交付金総額は、約2億円となっている。 |
| |
|
|
3.
|
平成10年度における理学療法士等の養成施設は、全国に 197施設(入学定員 6,510人)と、リハビリ学院設置当時の6施設(入学定員
140人)と比較して、著しく増加してきており、厚生省においても、11年末時点で需給バランスがほぼ均衡するものと予測している。これらのことから、労災病院においては、リハビリ学院によらずとも理学療法士等の補充が可能なものとなっている。 |
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
したがって、労働省は、リハビリ学院を自ら設置・運営して理学療法士等を養成する必要性が乏しくなっている状況にかんがみ、リハビリ学院を廃止する必要がある。 |
| |
|
|
|
|
|
| |
|
ウ |
労災保険会館の民営化の検討 |
| |
|
|
労災保険会館は、被災労働者及びその遺族であって、宿泊、教養文化又は健康の増進等を必要とする者に利用させることにより、当該被災労働者等の福祉の増進を図ることを目的とした施設であり、昭和57年7月に東京都に設置され、その運営は、平成8年7月から共済会に委託されている。 |
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
今回、労災保険会館の運営状況について調査した結果、以下のような状況がみられた。 |
| |
|
|
1.
|
労災保険会館の主要な施設である宿泊施設の利用状況についてみると、平成9年度の延べ宿泊者数は1万
9,721人で、このうち被災労働者及びその遺族等の延べ宿泊者数は 965人と 4.9パーセントを占めている。
また、労災保険会館は、その他の施設として、会議室(大、中、小)及びアスレチック施設を有しているが、ほとんどが一般の利用となっている。
労災保険会館は、全国に1か所だけ設置された施設であり、その活動実態も、民間等の会議室を備えた宿泊施設と差異はなく、労働福祉事業としての役割を果たしているとは認められない状況にある。
|
| |
|
|
2.
|
また、被災労働者等の利用が低調となっているにもかかわらず、労災保険会館の施設及び備品の整備のため、労災保険から出資金が平成8年度及び9年度に計約
5,500万円支出されている。
一方、共済会の労災保険会館の運営に係る収支は、平成8年度及び9年度にそれぞれ約 1,200万円の黒字を計上している。 |
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
したがって、労働省は、労働福祉事業の効果的かつ効率的な実施の推進を図る観点から、労災保険会館の施設等の整備のための出資金の支出を抑制し、民営化について検討する必要がある。 |
| |
|
|
|
|
|
| |
|
エ |
特殊健康診断業務に対する交付金の廃止の検討 |
| |
|
|
粉じん作業等特定の有害な業務に従事する労働者については、じん肺法(昭和35年法律第30号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)等に基づき、特別の項目による健康診断(以下「特殊健康診断」という。)が必要とされている。
労福事業団は、昭和48年度から全国8か所の労災病院に健康診断センターを付置するとともに、健康診断センターを付置しない労災病院のうち大牟田労災病院及び交付金病院を除く28病院については、54年度から順次、特殊健康診断部を設置し、特殊健康診断と併せて一般健康診断も実施している。
これらの業務の実施に当たっては、8健康診断センターについては、職員の人件費のほか、運営の収支が赤字の場合、その収支差を、28労災病院の特殊健康診断業務については、職員の人件費を、それぞれ交付金で賄っており、平成9年度の交付金総額は約15億円となっている。
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
今回、労福事業団及び民間等の健康診断機関における特殊健康診断の実施状況について調査した結果、以下のような状況がみられた。 |
| |
|
|
1.
|
労福事業団と民間等の健康診断機関との間で特殊健康診断の料金に差異がないにもかかわらず、労福事業団の実施している特殊健康診断については、前述のとおり、交付金が交付されているが、民間等の健康診断機関に対しては、健康診断用機器の購入等に要する資金を労福事業団が融資する制度が設けられているのみであり、人件費等の助成措置は講じられていない。
なお、労福事業団では、健康診断センターにおいて、特殊健康診断に係る新しい検査方法の開発や職業性疾病に関する調査研究など、民間等の健康診断機関では十分に実施し得ない研究開発業務を実施しており、また、民間等の健康診断機関では整備が困難な分野の高度医療機器の整備を図っている。
|
| |
|
|
2.
|
健康診断センター及び特殊健康診断部における特殊健康診断件数は、平成9年度で6万 2,604件となっており、特殊健康診断総件数が
179万 9,882件であることから、特殊健康診断における労福事業団の寄与割合は 3.5パーセントとなっている。 |
| |
|
|
|
| |
|
|
したがって、労働省は、特殊健康診断に係る助成措置の公平化を図る観点から、民間等の健康診断機関では実施し得ない研究開発業務等に係る経費分を除き、健康診断センター及び労災病院における特殊健康診断業務に対する交付金の廃止について検討する必要がある。 |
| 適用事業 |
| |
労災保険の適用対象となる事業であり、国家公務員、地方公務員(現業の非常勤職員を除く。)及び船員保険の被保険者並びに農林水産の事業のうち5人未満の労働者を使用する個人経営の事業を除き、労働者を1人以上使用するすべての事業が対象となる。
また、事業所・企業統計調査による事業所は、「物の生産又はサービスの提供が事業として行われている一定の場所」をいい、1事業所で内容の異なる複数の事業を実施している場合も、1事業所としてカウントされる。これに対し、労災保険における事業は、「一定の場所において一定の組織の下に有機的に相関連して行われる一体の作業を指し、通常事業として考えられる企業体を指称するものではなく、場所的かつ組織的に独立した最少単位の作業体」をいう。
|
| |
|
| 二次医療圏 |
| |
医療法(昭和23年法律第 205号)第30条の3第2項第1号に基づく主として病院の病床の整備を図るべき地域的単位として区分する区域をいい、都道府県が策定する医療計画において、地理的条件等の自然的条件及び日常生活の需要の充足状況、交通事情等の社会的条件を考慮して、一体の区域として病院における入院に係る医療を提供する体制の確保を図ることが相当であると認められるものを単位として設定するものであり、通常、一体となった郡市を一つの「二次医療圏」とする。これに対し、法律等で定義されてはいないが、市区町村の個々の行政単位を一つの圏域とする医療圏を「一次医療圏」又は「初期医療圏」ということもある。また、先進的な技術を必要とするもの、特殊な医療機器の使用を必要とするもの、発生頻度が低い疾病に関するもの、救急医療であって特に専門性の高いものといった特殊な診断又は治療を必要とする保健医療サービス体制の整備を図るべき地域的単位としての区域を「三次医療圏」(医療法第30条の3第2項第2号)といい、通常、都道府県の区域を一つの単位として設定されている。 |
| |
|
| 病理検査 |
| |
手術等で得られた臓器や組織材料について、脱水、薄切り、染色等を施し、光学顕微鏡で鑑別する検査であり、臨床的に確定が困難な疾患を最終的に診断するために利用されるが、中でも腫瘍の良性、悪性を鑑別するのに有用である。 |
| |
|
| 生体検査 |
| |
循環器、神経、筋、呼吸など各機能別の検査であり、直接、人体に検査機器を用いて行う心電図検査、超音波検査、脳波検査、筋電図検査などをいう。 |
| |
|
| 注射薬フェロン |
| |
「慢性活動性肝炎(B型及びC型)」の治療のために使用される静脈注射薬である。 |
| |
|
| 内用薬メバロチン錠 |
| |
血液中の脂質(脂肪)が異常に多い疾病である「高脂血症」の治療のために使用される錠剤である。 |
| |
|
| 高額医療機器 |
| |
労災保険の出資金により労災病院に整備されるおおむね 1,000万円以上の医療機器をいう。労働福祉事業団では、「昭和62年度以降の労災病院における機器等の整備方針について」(昭和61年12月9日付け労働福祉発第1167号労働福祉事業団理事長通知)により、病院運営上の骨格となる主要機器のうち、おおむね
1,000万円以上の「高額機器等」については、原則として、「出資金予算」により整備するものとし、おおむね1,000万円未満の「一般機器」については、当面、「病院予算」によるものとしている。 |
| |
|
| 磁気共鳴断層撮影装置(MRI) |
| |
人体のあらゆる部位の断層像を任意の裁断面で撮影し、骨格筋を始め心筋、脳、腎臓、肝臓、前立腺、腫瘍など、ほぼ全臓器の診断が可能である。通常、MRIと略称する。同様の機能を持つCTスキャンと異なり、X線撮影装置を使用しないため、繰り返し検査が可能である。 |
| |
|
| 血管連続撮影装置 |
| |
血管が複雑に走行している頭部や心臓、腹部、四肢の血管造影撮影に使用する。血管の位置、状態等を詳細に把握するとともに、カテーテルを用いた治療にも使用する。 |
| |
|
| 理学療法士 |
| |
「理学療法」とは、身体に障害のある者に対し、主としてその基本的動作能力の回復を図るため、治療体操その他の運動を行わせ、電気刺激、マッサージ、温熱その他の物理的手段を加えることをいい、「理学療法士」は、厚生大臣の免許を受けて、医師の指示の下に理学療法を行うことを業とする者をいう。 |
| |
|
| 作業療法士 |
| |
「作業療法」とは、身体又は精神に障害のある者に対し、主としてその応用的動作能力又は社会的適応能力の回復を図るため、手芸、工作その他の作業を行わせることをいい、「作業療法士」は、厚生大臣の免許を受けて、医師の指示の下に作業療法を行うことを業とする者をいう。 |
| |
|
| 特殊健康診断 |
| |
ガス、蒸気、粉じん、有害放射線、振動、騒音、異常気圧その他の有害要因にさらされる一定の業務に従事する労働者については、一般健康診断以外にも特別の項目による健康診断を行うことが事業主に義務付けられている。この特別の項目による健康診断を特殊健康診断という。特殊健康診断に係る具体的な検査項目等は、じん肺法(昭和35年法律第30号)、有機溶剤中毒予防規則(昭和47年労働省令第36号)、鉛中毒予防規則(昭和47年労働省令第37号)等において定められている。 |