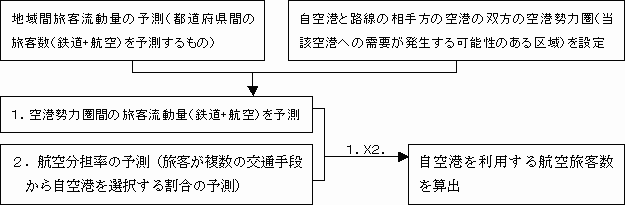
・需要予測の客観性・透明性の確保のため、需要予測の方法の公開が必要
| 勧告日 | : | 平成13年5月24日 |
| 勧告先 | : | 内閣府、国土交通省 |
| 実施時期 | : | 平成11年8月〜13年5月 |
| ○ | 厳しい財政事情の下、空港整備を含む公共事業について、重点的かつ効果的実施が求められており、事業の採択時等において、その必要性等の観点からの的確な評価が必要。このため、空港整備事業の採択時の評価の基となる需要予測の精度の一層の向上、費用対効果分析の的確な実施が必要 また、評価の透明性等の確保のため需要予測の方法の公開等が必要 |
||
| ○ | 本行政評価・監視は、空港の整備等に関する行政運営の実態について調査し、関係行政の改善に資するため実施 | ||
| ○ | 調査対象機関 | : | 内閣府、国土交通省、空港設置・管理者(特殊法人、地方公共団体等)、航空運送事業者等 |
| ○ | 担当部局 | : | 行政評価局、管区行政評価局(7)、四国行政評価支局、沖縄行政評価事務所、行政評価事務所(14) |
・需要予測の方法について基準は特に定められていないが、一般的には以下の手順で実施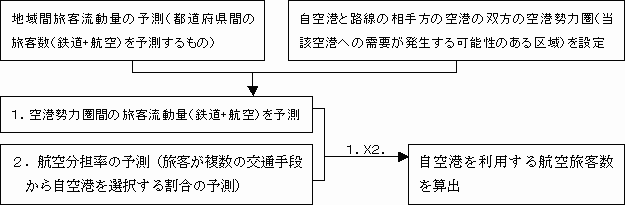 ・需要予測の客観性・透明性の確保のため、需要予測の方法の公開が必要 |
| ○ | 地域間旅客流動量の予測 同一時期に予測したにもかかわらず、同一の都道府県間の旅客流動量の予測値が、予測を実施した空港によって大きく異なっている例あり (例)A県〜B県間の平成22年度の旅客流動量予測値(平成5年度に予測) a空港(A県所在)の整備に当たって予測したA県〜B県間の旅客流動量: 66.0千人 b空港(B県所在)の整備に当たって予測したA県〜B県間の旅客流動量:116.5千人 これは、予測を実施する空港により、予測の方法(予測のために採用したデータの対象期間、旅客流動量と経済指標との相関に関する前提の置き方等)が異なることに起因 |
||||||
| ○ | 航空分担率の予測 ・ 航空分担率(競合するとみられる交通手段と運賃、所要時間等を比較・分析して予測)は、一般に空港に近接する地区ほど高く、空港から遠距離にあり鉄道等の利便がよい地区では低くなる。このため、同一の空港勢力圏内でも地区により交通手段の利用の利便性が異なる場合には、航空分担率は、空港勢力圏を細分した地区別に予測することが必要。しかし、このような細分を行わず空港勢力圏内の中心都市のみで予測し、当該中心都市が空港近接地であるために、結果的に、空港勢力圏を細分した地区別に予測した場合に比較して高い航空分担率が適用されているとみられる例あり ・ 既存の他空港の航空分担率実績値(=航空旅客数/(航空旅客数+鉄道旅客数))を基礎に自空港の航空分担率を予測する手法を用いる場合、航空分担率実績値を算出する際の前提となる航空旅客数と鉄道旅客数の把握範囲の整合を図ることが必要。しかし、航空旅客数の把握範囲に対し鉄道旅客数の把握範囲が狭いため、算出された航空分担率実績値は実際より高い値となっているとみられる例あり (例)C県(C空港)と東京(東京国際空港)間の航空分担率実績値算出例
|
||||||
| ○ | 他の空港と空港勢力圏が相当程度重複すると考えられる空港が整備される場合、空港整備の必要性の評価においては、当該空港の需要のみならず、地域内の他空港及び地域全体の需要の見込みが明らかである必要あり。しかし、地域内の他空港及び地域全体の需要の見込みが明らかにされている例なし |
| 国土交通省 | : | 記録は保存されているが、予測方法の検証に足る内容となっておらず |
| 地方公共団体 | : | 記録は保存されているが、予測方法の十分な検証を行うには記述内容が不十分な例あり |
|
||||||||||
|
・国土交通省は、平成11年度に空港整備事業の採択時等の評価の一要素である費用対効果分析のマニュアルを策定 ・費用対効果分析は、供給者便益、利用者便益と費用(建設費、維持改良費等)を比較考量する方法 |
| ○ | 費用対効果分析マニュアルでは、供給者便益(空港整備により空港管理者等が受ける増収の便益)の計測において、空港の運営上必要不可欠な管制等業務及び気象等業務に係る収入及び費用の増加額を算入するものとされておらず、不十分 |
供給者便益の計測において、管制等業務及び気象等業務に係る収入及び費用の増加額を算入するよう、費用対効果分析マニュアルを見直すこと。 併せて、空港管理業務、管制等業務及び気象等業務について、費用対効果分析の対象空港ごとに供給者便益の計測に必要な費用を整理・集計し、把握すること。 |
||
|
・ 昭和42年度以降空港整備五箇年計画を策定するとともに、45年度に空港整備特別会計を創設し、着陸料等を原資に、空港整備事業を推進 ・ 空港整備特別会計については、近年、一般会計からの受入れの額が増加しており、一層事業の重点化・効率化が求められる状況 |
| ○ | 空港の新設事業の採択に当たり、当該事業の検討当時、需要に影響を与えたとみられる要素を取り込んだ需要予測の方法が確立されていなかったこと等から、これを勘案できなかった例あり。しかし、近年、当該要素を予測に取り込むことが可能となりつつあり、今後の空港の新設等において、このような要素に十分配意することが必要 ・ 空港新設時の検討では東京国際空港等との間の路線で多くの需要を予測していたが、東京国際空港等への便数を当初想定したとおりに確保できず、さらに近隣空港の方が運航便数が多く、このようなことが要因の一つとなって、実績が予測を下回ることとなったと考えられる地方公共団体管理空港の例あり。近年、国管理空港では運航便数の要素を予測に取り込む等の状況あり |
今後、計画又は検討されている空港整備事業の採択に当たり、空港の新設等については、首都圏の空港の発着枠の拡大見込み及び近隣空港の運航便数に十分配意して行うこと。 |
||
|
・NDB(無指向性無線標識施設)とVOR(超短波全方向式無線標識施設)は同様の用途(空港への着陸方式、航空路の設定等)に利用。NDBはVORに比べ測定精度が低く、VORが無線標識施設の中心的役割 ・着陸機数が多く悪天候時においても航空機の円滑な運航の確保が必要な空港の中には、滑走路の双方向にILS(計器着陸装置)が設置されているものあり(4空港) |
| ○ | 調査した31空港中、20空港においてVORとNDB(24施設)が併設。これらNDBの多く(15施設)は、VORと同様の用途のものであることなどから存置の必要性が乏しい |
| ○ | 現在ILSが設置されていない滑走路方向へのILSの増設を行うことにより、気象に起因して多数発生している欠航あるいは離発着の遅れの解消が可能な空港の例あり |
|
||||||
|
・航空保安無線施設等の運用・保守、工事の設計・施工を行う業務(管制技術業務)あり ・全国94空港のうち53空港の空港事務所等に航空管制技術官を配置(平成11年度末現在 1,180人) ・保守対象施設が一定数を超えた場合などは航空管制技術官を一律に増員する基準 |
| ○ | 各時間帯とも同数の要員が配置される24時間運用空港の中には、昼夜間帯に集中実施している点検業務を深夜帯にも実施することにより、保守対象施設数が一定数を超えたとしても必ずしも基準どおりに増員を行わなくとも業務の遂行が可能な例などあり |
管制技術業務については、保守対象施設数が一定数を超えた場合あるいは特定の保守対象施設が整備された場合には一律に増員することとしている施設規模要員の配置基準の考え方を業務実施方法及び業務量を勘案したものとなるよう見直し、適正な要員配置を図ること。 |
||