| 2 |
食中毒の発生防止対策 |
| |
(1) |
集団給食施設に対する監視指導の充実 |
| |
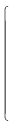 |
・ |
厚生省は、平成9年3月に衛生管理マニュアルを作成し、これに基づき学校給食施設及び社会福祉施設に対し一斉点検を実施するよう、都道府県等を指導。また、同マニュアルに基づき社会福祉施設及び医療機関自らも自主点検を推進するよう都道府県等を指導 |
|
| |
・ |
文部省は、平成9年4月に学校給食衛生管理基準を示し、これに基づき学校給食施設における定期衛生点検及び日常点検(自主点検)の実施に努めるよう都道府県教育委員会を指導 |
| |
|
○ |
調査した37学校給食施設及び23社会福祉施設では、当庁の調査結果において、495事項の衛生管理が不適切。このうち、保健所の一斉点検において指摘していないものが152事項(30.7%)。この原因は、一斉点検が限定された期間内(学校給食施設は2か月、社会福祉施設は4か月)で多数の施設に対して行われていることが一因 |
| |
|
○ |
一斉点検結果による改善指導が口頭により行われており不徹底であること等から改善が不十分な例多数 |
| |
|
○ |
調査した23社会福祉施設及び19病院での自主点検は適切に行われているとは言いがたい状況 |
| |
|
○ |
厚生省の衛生管理マニュアルに盛り込まれている事項(例:「調理機械の分解・洗浄・消毒」)が、学校給食衛生管理基準に盛り込まれておらず。調理機械の分解・洗浄が不十分なことにより、学校給食施設で食中毒事件が発生している例あり |
| |
[ 勧告要旨 ]
| 1. |
学校給食施設及び社会福祉施設に対する保健所の一斉点検について、点検期間を延長する等の方途を講じることにより、これを適切に励行するよう都道府県等に対し助言・指導すること。(厚生省) |
| 2. |
一斉点検結果に基づく指摘事項については、改善勧告の文書による実施及び改善計画の徴収を徹底するとともに、未改善施設の積極的な公表を励行するよう都道府県等に対し助言・指導すること。また、自主点検の励行を指導することについて、都道府県等に対し助言・指導すること。(厚生省) |
| 3. |
文部省は、厚生省と協議の上、学校給食衛生管理基準について、衛生管理マニュアルとの整合を図ること。(文部省) |
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
(2) |
総合衛生管理製造過程承認制度の運用の適切化 |
| |
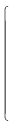 |
・ |
平成7年5月に創設された、総合衛生管理製造過程承認制度( 以下「承認制度」という。) は、食品の製造又は加工及びその衛生管理の方法につき、食品衛生上の危害の発生を防止するための措置が総合的に講じられた製造又は加工の過程を厚生大臣が承認するもの。これにより食品衛生がより一層確保される一方、規制緩和の効果 |
|
| |
・ |
承認制度が適用される食品は、6食品(乳、乳製品、清涼飲料水、食肉製品、魚肉ねり製品、容器包装詰加圧加熱殺菌食品)。承認制度の承認を受けた施設は、平成12年4月7日現在、409施設(923品目) |
| |
|
○ |
平成12年6月に、承認制度を導入している乳・乳製品製造工場を原因施設とする食中毒事件が発生。有症者数は、1万4,000人(15府県内)超(平成12年8月10日現在) |
| |
|
○ |
上記の食中毒事件についてみると、 |
| |
|
|
1. |
食中毒原因施設の承認制度の承認申請書類に、乳・乳製品製造設備の一部の工程が未記載。管轄都道府県等の立入検査においても、当該未記載工程の存在は認知されず |
| |
|
|
2. |
同施設は、省令で認められていない加工乳再利用による加工乳の製造を実施。原料に毒素が混入しているかどうか、バルブ洗浄が不十分である実態が、管轄都道府県等の立入検査(平成11年度に6回)において、確認できておらず |
| |
|
|
3. |
承認施設に対する立入検査の検査事項等を厚生省が示したチェックリストでは、上記2.の実態が明確にチェックできず |
| |
[ 勧告要旨 ]
| 1. |
承認審査に際しては、製造工程等に係る実地調査を綿密に実施する等申請内容の確認を徹底すること。 |
| 2. |
承認施設について、今回の食中毒事件の経緯をも踏まえ、立入検査のチェックリストを見直した上で、これに基づき、都道府県等と連携しつつ、立入検査を厳正に行うこと。 |
|
|
| 3 |
食品残留化学物質に対する安全確保対策及び新開発食品に対する表示対策 |
| |
(1) |
食品のダイオキシン汚染対策の推進 |
| |
 |
政府は、「ダイオキシン対策推進基本指針」(ダイオキシン対策関係閣僚会議決定。平成11年3月)を策定し、健康への影響を含め、各省庁が推進すべき対策を掲示。平成11年7月に、ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)が制定 |
 |
| |
|
○ |
厚生省は、ダイオキシン汚染事故が発生した場合に、汚染食品であることを判定するための基準を含め、その流通被害の防止に的確に対応するための方針未策定。このため、ベルギー産豚肉等のダイオキシン汚染事故発生時に速やかに対応できず |
| |
[ 勧告要旨 ]
健康への影響に関する幅広い調査研究を行い、その結果を踏まえて、食品のダイオキシン汚染事故に的確に対応するための方針の策定を含め、ダイオキシン事故に関する対策を検討すること。
|
|
| |
|
|
|
|
| |
(2) |
内分泌かく乱化学物質の健康影響評価の推進 |
| |
 |
厚生省は、内分泌かく乱化学物質(いわゆる環境ホルモン)について、主として人の健康への影響の観点から、作用メカニズムの解明、健康影響評価、毒性評価方法等の確立に関する調査研究を分担 |
 |
| |
|
○ |
厚生省は、OECDにおいて開発中の内分泌かく乱化学物質をスクリーニングするための統一試験法の確立を待って、健康影響に関する評価を順次行うとの方針 |
| |
|
○ |
調査した消費者団体(26団体)の半数は、人の健康への影響の調査研究、ホルモン作用のメカニズムの解明を急ぐべき等の意見 |
| |
[ 勧告要旨 ]
内分泌かく乱化学物質の安全対策を推進する観点から、人の健康への影響が懸念される化学物質について、関係省庁と連携を図り、早急にその評価を行うこと。
|
|
| |
|
|
|
|
| |
(3) |
遺伝子組換え食品の表示の適正化 |
| |
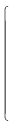 |
・ |
農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和25年法律第175号。JAS法)の改正(平成11年7月22日)により、遺伝子組換え食品の表示の義務付けを規定(13年4月1日から適用) |
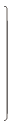 |
| |
・ |
表示は、「遺伝子組換え」、「遺伝子組換え不分別」、「遺伝子組換えでない」の3種類。「遺伝子組換えでない」と表示するためには、「分別生産流通管理」された非遺伝子組換え農作物を原材料とする必要あり(農林水産省告示) |
| |
|
○ |
農林水産省によれば、分別生産流通管理により、遺伝子組換え作物(大豆)の混入率が5%以下。しかし、現状では、遺伝子組換え作物の食品への混入率を定量する分析法は世界的にみても確立しておらず、消費者にとっては不安が絶えず。
なお、同省は、平成12年度から、食品原料や加工食品から組換え遺伝子やそれに由来するタンパク質を検知・定量する技術の開発に着手 |
| |
[ 勧告要旨 ]
遺伝子組換え作物の食品への混入率を定量する分析方法の確立を急ぐこと。(農林水産省) |
|
| |
|
|
|
|
| |
|
○ |
その他の勧告事項 |
| |
|
|
・ 食中毒の原因究明の迅速化・的確化 |
| |
|
|
・ 輸入食品に係る監視指導の適切化 |