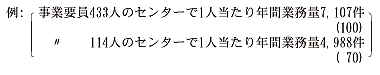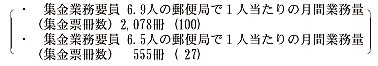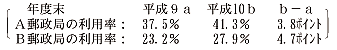|
|
|
| 1 |
経営の効率化 ・ 合理化等 |
| |
(1) |
簡易保険事務センター |
| |
|
ア |
簡易保険事務センターの要員合理化 |
| |
(勧告)
1. 業務量に対応した要員配置の見直しを行うこと。 |
|
| |
(説明) |
| |
〇 |
事業要員1人当たり業務量に簡易保険事務センター(以下「簡保事務センター」という。)間で最大30%の格差 |
| |
|
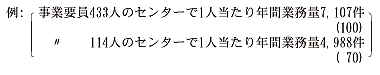 |
|
| |
|
| |
簡易保険事務センター(以下「簡保事務センター」という。)の業務運営体制の簡素効率化を図る観点から、次の措置を講じ、要員の合理化を図った。 |
| |
|
→○
|
貸付金・還付金の即時払受領証の確認業務の効率化等により、平成10年度は50人、11年度は40人の純減を実施した。 |
| |
|
| |
|
|
| |
(勧告)
| 2. |
電子計算機のオペレーション業務について、民間委託を積極的に推進すること。 |
|
|
| |
(説明) |
| |
〇 |
電子計算機のオペレーション業務について、依然、直営で実施しているものあり |
|
| →○ |
電子計算機のオペレーション業務について、平成13年1月に更改・拡充予定の簡易保険業務総合機械化システムにおいて、業務の一部自動化を行うのに併せ、個人情報保護及びセキュリティ確保の対策を講じ、磁気テープのハンドリング等の業務を部外委託の予定 |
| |
|
|
| |
|
イ |
簡易保険事務センターの再編整理 |
| |
(勧告)
組織の簡素化を図る観点から、小規模な簡保事務センターを廃止するなど、簡保事務センターの組織の再編整理を行うこと。 |
|
| |
(説明) |
| |
〇 |
簡保事務センター業務は、後方支援業務であり、特段の現地性を有するものではなく、オンラインシステムの充実等の情報・通信手段の発達により広域的処理が可能 |
| |
〇 |
全業務量の30%を処理するセンター(事業要員 571)がある反面、全業務量の4%しか処理していないセンター(事業要員100)があるなど、大規模センターと小規模センターが併存 |
| |
〇 |
小規模センターは、事業要員1人当たりの業務量が少なく、全要員に占める共通管理要員の割合も高いなど非効率 |
| |
|
|
|
|
| →○ |
簡保事務センターについては、加入者サービスの維持及び郵便局への指導機能の維持に配意しつつ、小規模な簡保事務センターの事務を他の簡保事務センターに集約することにより、現在の7簡保事務センター体制を平成17年度に5簡保事務センター体制に再編整理することとしており、現在準備中
|
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
| |
(勧告)
業務量に対応した要員配置の見直しを行い、要員の合理化を図ること。 |
|
| |
(説明) |
| |
〇 |
内務員1人当たりの業務量に郵便局間で最大32%の格差 |
| |
|
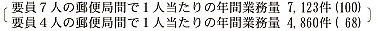 |
|
| |
|
|
| |
|
| |
内務業務の運営体制の簡素効率化を図る観点から、次の措置を講じ、要員の合理化を図った。
|
| →○ |
自動振替払込みの推進による業務の効率化等により、平成10年度は50人、11年度は41人の純減を実施した。 |
| |
|
| |
|
|
| |
|
イ 外務員の要員合理化 |
| |
(勧告)
| 1. |
集金業務の業務量に対応した要員配置の見直しを行うこと。 |
|
|
| |
(説明) |
| |
〇 |
集金業務要員について、要員1人当たりの集金業務量に郵便局間で最大70%の格差 |
| |
|
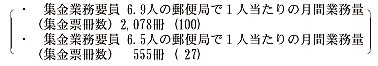 |
|
| |
外務業務の運営体制の簡素効率化を図る観点から、次の措置を講じ、要員の合理化を図った。 |
| →○ |
自動振替払込みの推進による業務の効率化等により、平成10年度は52人、11年度は85人の純減を実施した。 |
| |
|
| |
|
|
| |
(勧告)
| 2. |
目標値の設定等により自動振替払込みの利用の一層の推進を図ること。また、その推進状況を踏まえ、集金業務について非常勤職員の積極的活用を図ること。 |
|
|
| |
(説明) |
| |
〇
|
集金業務が不要となる自動振替払込みの利用の推進に郵政局間で格差(平成8年度末) |
| |
|
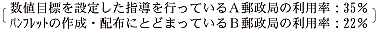 |
|
| |
|
| →○ |
平成10年度に目標値(過去の実績を上回る 200万件)の設定等を新たに行い、自動振替払込みの利用の一層の推進を図った結果、9年度末の
1,830万件が10年度末には 2,015万件に増加。
なお、集金業務の非常勤職員の積極的活用については、保険料の自動振替払込みの推進状況を踏まえ、検討していくこととする。 |
| |
【個別事例の改善状況】 |
| |
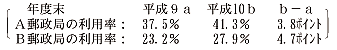 |
|
| 2 |
事業運営の適正化等 |
| |
(勧告)
| 1. |
窓口で成立した保険契約について、契約成立に至るまでの勧奨形態の実態を把握し、職員の積極的な勧奨によって成立したと認められるもののみに奨励手当を支給する仕組みの導入を検討すること。 |
|
|
| |
(説明) |
| |
〇 |
窓口成立の契約について、年金保険は、手当支給に当たり認定の仕組みが設けられ、商品説明のみで積極的な勧奨と認められないものは手当を不支給。一方、保険は、勧奨行為の有無にかかわらず、基本的に手当を支給 |
|
| |
|
|
→○
|
平成10年9月から実施した勧奨形態の実態調査の結果、職員の積極的な勧奨によって成立したと認め難い契約もみられたが、加入意思を有して窓口を訪れる顧客の状況等を踏まえつつ、平成15年の郵政公社の設立に併せて検討したい。 |
| |
|
|
| |
(勧告)
| 2. |
同一郵便局職員を契約者とする保険及び年金保険契約については、従事業務のいかんにかかわらず、奨励手当の支給対象外とすること。 |
|
|
| |
(説明) |
| |
〇 |
同一局内の簡保事業職員を契約者とする契約は手当の支給対象外。しかし、他事業職員の契約については、保険知識を有しているものの、積極的な勧奨を必要とするとして支給対象
|
|
| |
|
| →○ |
平成11年3月、郵政事業職員特殊勤務手当支給規程(昭和49年公達第1号)を改正し、同一郵便局職員を契約者とする保険及び年金保険契約を奨励手当の支給対象外とした。
|
| |
|
|
| |
(勧告)
| 3. |
乗換契約に該当する年金保険に係る奨励手当の支給率を見直すこと。 |
|
|
| |
(説明) |
| |
〇
|
乗換契約は、通常の勧奨ほどの労力を要しないため保険では手当の支給率が2分の1であるのに対し、年金保険は支給率を下げる制度なし
|
|
| →○ |
上記規程の改正において、乗換契約に該当する年金保険に係る奨励手当の支給率を2分の1に引下げ。 |
| |
|
|
| 3 |
加入者福祉施設の設置・運営の見直し |
| |
(勧告)
| 1. |
簡保事業団に対して、加入者福祉施設は収支相償を基本とした運営を行うこととし、 |
| |
i) |
加入者福祉施設について、利用料金の見直し、要員合理化等の収支改善方策を織り込んだ加入者福祉施設ごとの中期収支改善計画を立て、これに基づき収支改善を図ること、 |
| |
ii) |
中期収支改善計画の計画期間中又はその最終年度において計画目標の達成が困難と認められる施設で、収支改善効果に乏しく、施設全体の収支改善に寄与しないものについては、廃止すること。また、診療所は速やかに整理すること。 |
| |
iii) |
簡保事業団本部についても一層の経費・要員の縮減を図ることを指導すること。 |
| |
|
|
|
| (説明) |
| |
〇・ |
施設運営に係る経常収支は、平成8年度約31億円の黒字。しかし、収入の3割は交付金で、これを除いた実質的な収支は217億円の赤字(赤字施設
105施設) |
| |
・ |
経営合理化の観点から施設に係る現行費用負担の仕組みをみると、用地費・建設費が出資されるとともに、固定資産に関する費用(減価償却費、修繕費等)等も交付されていることから、簡保事業団の負担は一般に比べ軽減。施設については、施設収入で人件費等の経費を賄う収支相償を基本とした運営を行うことが適当。 |
| |
・ |
簡保事業団の収支改善・交付金縮減への取組は不十分。このため、施設単位の収支改善に全力で取り組む等経営合理化のための抜本的な対策が必要。 |
| |
|
i) |
周辺類似施設より低料金設定の施設、不採算のレストラン部門を維持している施設、 |
| |
|
ii) |
観光客数が減少傾向にあり1億円程度の赤字(平成8年度)となっている施設、 |
| |
|
iii) |
整理予定の診療所で、いまだ整理されていないものあり。また、施設部門の要員合理化に対応した本部職員の合理化は不十分
|
|
| |
簡保事業団の抜本的な経営の合理化等を図る観点から、次の措置を講じた。 |
| →○ |
平成10年6月、郵政省は、加入者福祉施設は収支相償を基本とした運営を行うことを含め、勧告の趣旨を踏まえて適切な措置を講じるよう、「郵政事業に関する行政監察結果に基づく勧告−簡
易生命保険事業を中心にして−について」により簡保事業団を指導。
これを受け、簡保事業団は、次の措置を講じている。 |
| |
|
|
| |
i) |
平成11年度からの5年間で施設ごとの中期収支改善計画を順次策定し、これに基づき収支改善を図る旨の基本方針を定め、11年度は11施設(保養センター)の収支改善に着手しており、また、12年度は20施設(加入者ホーム1施設、保養センター17施設及び総合レクセンター2施設)の収支改善に着手する。 |
| |
|
|
| |
ii) |
中期収支改善計画期間の中間年度又は最終年度において、計画目標の達成が困難と認められる施設で、利用状況が悪く、施設の存在意義が希薄であり、かつ、施設の収支改善効果に乏しく、施設全体の収支改善に寄与しない施設は廃止する方針。
また、平成11年3月に3診療所(出雲、小松島、高松)、同年4月に4診療所(燕、福岡、大分、宮崎)を廃止
なお、このほか、3施設(伊豆大島保養センター、峰山高原総合レクセンター及び筑後小郡レクセンター)について、「特殊法人の整理合理化について」(平成7年2月24日閣議決定)に基づき12年3月31日をもって廃止。 |
| |
|
|
| |
iii) |
簡保事業団本部について、平成11年度から5年間で約20人の要員削減と約5%の経費削減を目標とする効率化施策を実施 |
| |
|
|
|
| |
(勧告)
| 2. |
加入者福祉施設については、原則、費用のうち人件費及び賃金は自らの収入で賄うこととし、上記の収支改善措置等を通じ、人件費等の交付率の段階的な引下げにより、交付金を一層縮減すること。 |
|
|
| |
(説明) |
| |
〇 |
施設の収支にかかわりなく、人件費等の一定割合が交付金として交付されることから、施設の収支改善努力相当額まで交付金が縮減する仕組みとなっていない。交付金は、施設運営に係る赤字を上回って交付され、利益を生む働き(平成8年度利益剰余金:77億円)。
収支改善の実を挙げ交付金縮減を図るには、人件費等に係る現行の費用負担の見直しも必要 |
|
| →○ |
加入者福祉施設については、効率的な運営を図る観点から、平成12年度予算において人件費等に係る交付率の引下げ(加入者ホーム、保養センター及びレクセンターについて50%から48%に
引下げ)により交付金を一層縮減。
今後においても、交付金の縮減が図られるよう、人件費等に係る交付率の引下げについて検討する。 |
| |
|
|
|
| |
(勧告)
| 3. |
加入者福祉施設の設置については、保養センター及び会館は既定の方針を厳守するとともに、それ以外の施設は、民間宿泊施設に十分配意し、収支見込みのない施設の新設は行わないこと。
総設置施設数については現有施設数を上限とすること。
加入者福祉施設の増改築及び併設施設の設置は、当分の間、原則として行わないこと。 |
|
|
| |
(説明) |
| |
〇 |
公的部門のスリム化が求められており、施設の新設や拡大についても厳しい対応が必要。民間競合の回避等の観点から、施設の新設抑制の対象となっていない施設についても、閣議決定の趣旨に沿った配意が必要。特に、採算性の見込まれない施設の新設は問題。また、既存施設の統廃合を含む配置の見直し等経営合理化を行う中で、総施設数の増加は問題。多額の経費をかけて併設施設の設置や増改築を行ったものの、収支悪化の要因となっている併設施設、当初見込みを上回る赤字の増改築施設あり |
|
| →○ |
保養センター及び会館の新設については、臨調最終答申(昭和58年3月)等を厳守しており、今後とも原則として行わない。
また、総合レクセンター、総合健診センター等の施設で、現在既に用地を取得し計画中のものの新設に当たっては、地元との調整を行うとともに、収支見通しを十分勘案する。その他の施設は、民間宿泊施設に十分配意し、収支見込みのない施設の新設は行わない。
加入者福祉施設の数は、現有施設数( 123所)を上限としており、今後とも当該施設数を超える増置は行わない。
加入者福祉施設の増改築及び併設施設の設置については、今後においても、当分の間、原則として行わない。 |
| |
|
|
|