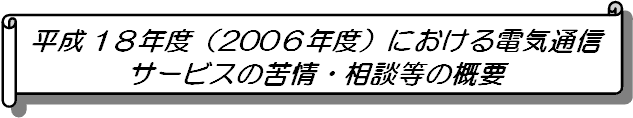
1 苦情・相談等の総受付件数
平成18年度(2006年度)に総務省電気通信消費者相談センターに寄せられた苦情・相談等の総受付件数は、4,883件でした。前年度(平成17年度(2005年度))の総受付件数と比べて1,475件(23.2%)の減少となっています。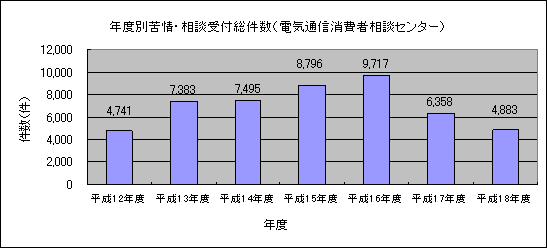
(参考)
総務省では、電気通信消費者相談センター(本省)のほか、総合通信局等(各総合通信局及び沖縄総合通信事務所)においても、電気通信サービスに関する利用者からの苦情・相談等を受け付けています。平成18年度(2006年度)に、総合通信局等に寄せられた苦情・相談等の総件数は、合計で5,108件となっています。
この結果、平成18年度(2006年度)に、総務省の電気通信消費者相談センター及び地方総合通信局等に寄せられた電気通信サービスに関する利用者からの苦情・相談等の総件数は、合計で9,991件となっており、これは、前年度の合計件数と比べて1,927件(16.2%)の減少となっています。
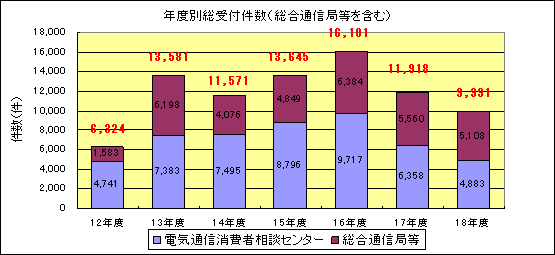
2 月別の苦情・相談等の受付件数
電気通信消費者相談センターに寄せられた苦情・相談等の受付件数は次のとおりです。各月の平均は407件です。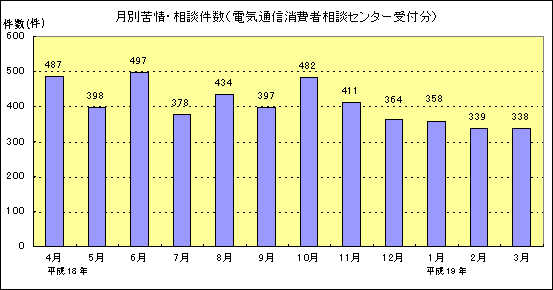
(参考)
前年度(平成17年度(2005年度))における月別の苦情・相談等の受付件数は、次のとおりです。
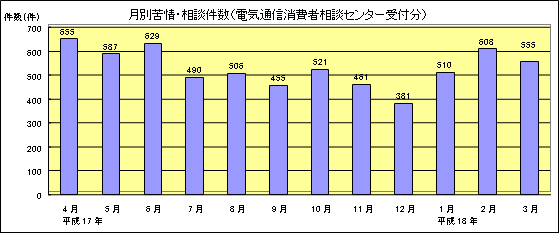
3 主な苦情・相談内容
平成18年度の主な苦情・相談内容としては以下のものが挙げられます。| 苦情・相談件数 上位5位 | ||
| 1 | 有料アダルトサイト等の情報料をかたった不当請求関係 | 677件 |
| 2 | 事業者との料金トラブル関係 | 379件 |
| 3 | インターネット上の誹謗中傷等 | 167件 |
| 4 | 129件 | |
| 5 | 携帯電話不正利用防止法関係 | 125件 |
■ 有料アダルトサイト等の情報料をかたった不当請求に関する苦情・相談等
- 苦情・相談等の概要
- 総務省で講じた措置等
「アダルトサイトの『入り口』をクリックしただけで、登録完了の画面とともに、料金請求の画面が表示されるようになった。これは、支払わなければならないのか。」「ネットサーフィン中にいきなり登録完了の画面が表示され、料金請求等の情報が書かれている。支払わなければならないか。」といった有料アダルトサイト等の情報料をかたった不当請求に関する苦情・相談等が寄せられています。
その受付件数は、677件で平成18年度(2006年度)の電気通信消費者相談センター総受付件数の約13.9%を占める一方で、前年度に比べて956件の減少(58.5%減)となっています。
月別の苦情・相談件数は、平成17年2月以降、減少傾向にあります。これは、官民挙げての周知啓発活動や法整備・取締り等の対策の成果とも考えられますが、手口の巧妙化・悪質化も見られることから、引き続き対策の検討・実施が不可欠と考えられます。
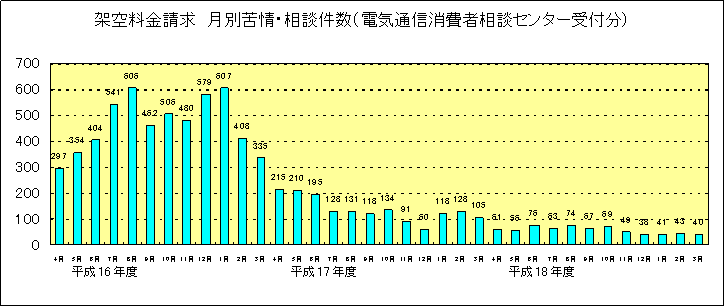
なお、以前から多く見られるケースとして、アダルトサイトや音声番組を利用したと偽って電話・メール・郵便等で架空の料金請求をするもの、バナー広告や送りつけた広告メール等から番組にアクセスさせ、意に反する契約と不利な利用規約により登録されたと思わせた上で、不当な料金請求をするものがあるほか、サイトにアクセスしたところ、本人の気付かないままプログラムがパソコンにインストールされ、デスクトップに表示された請求画面等を消すことができないがどうしたらよいかといった相談事例がみられます。
平成17年4月に、振り込め詐欺等への対策として「携帯電話不正利用防止法」が成立しました。この法律は、携帯電話・
総務省では、この法律に違反して譲渡時本人確認を行っていなかった携帯電話ショップの運営事業者に対し違反の是正を命じるなど、携帯電話が振り込め詐欺等の犯罪に不正に利用されることを防止するための措置を執っています。
今後とも同法の厳正な執行に努めるとともに、ホームページ等を通じた周知啓発に取り組んでまいります。
【関連報道資料等】
- 「総務省の振り込め詐欺対策(総合サイト)」
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/furikomesagi.html
(注:関係省庁における対策も掲載しています。)
- 「携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律について」(平成17年法律第31号)
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/050526_1.html
- 携帯電話不正利用防止法に基づく契約者確認の実施状況
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/2005/050729_5.html
■ 事業者との料金トラブルに関する苦情・相談等
- 苦情・相談等の概要
- 使用した覚えのない高額なパケット通信料の請求を受けた。支払わなければならないか。
- 携帯電話をパソコンに接続してパケット通信を利用した。その場合パケット定額料金の対象外であるとは知らなかった。
- 契約期間内に解約を申し出たら違約金の請求を受けた。納得できない。
- 自分ではかけた覚えのない通話料金の請求を受けている。支払わなければならないか。
- 総務省で講じた措置等
平成18年度(2006年度)に総務省電気通信消費者相談センターに寄せられた事業者との料金トラブルに関する苦情・相談は379件でした。
具体的な内容としては、
総務省電気通信消費者相談センターでは、電気通信事業者との料金トラブルに関する苦情・相談を受け、事業者に対して、苦情等があった旨を伝え、更なる対応や解決の促進を図っています。
また、携帯電話のパケット通信料金が思いがけず高額になってしまったという苦情・相談が依然として多数寄せられていることから、パンフレットの配布などにより携帯電話のパケット通信料金の高額利用の防止策について周知を行いました。
■ インターネット上の誹謗中傷等に関する苦情・相談等
- 苦情・相談等の概要
- サイト上に自己に対する誹謗中傷が書かれていた。削除するにはどうしたらよいか。
- 誹謗中傷等の書込みを放置している掲示板等のサイトは取り締まるべきだ。
- 総務省で講じた措置等
平成18年度(2006年度)に総務省電気通信消費者相談センターに寄せられたインターネット上の誹謗中傷等に関する苦情・相談は167件でした。
具体的な内容としては、
インターネット上における児童ポルノの公然陳列、出会い系サイトへの違法な書込み、規制薬物の濫用を唆す情報等の違法な情報や、自殺サイト、爆発物の不正な製造方法等の公序良俗に反する情報が社会問題となっています。
総務省では、平成
本報告書を踏まえ、電気通信事業者団体にあっては、インターネット上に掲載された情報の違法性の判断基準及び送信防止措置等の手続を定めた「インターネット上の違法情報への対応に関するガイドライン」並びにプロバイダ等が違法・有害情報に対して契約約款に基づく自主的な対応を行うための「違法・有害情報への対応等に関する契約約款モデル条項」を定めたところです。
総務省としては、これらの取組を通じて、プロバイダ等によるインターネット上の違法・有害情報への適切かつ迅速な対応が促進されることを期待しています。
また、未成年者がいわゆる出会い系サイトなどインターネット上の有害な情報にアクセスし、事件に巻き込まれるケースが多発し、中でも、保護者の目が届きにくい携帯電話からのアクセスについては、未成年者を保護する観点から早急な対策が必要となっています。
これには、受信者側で情報の取捨選択を行うフィルタリングサービスを利用することが有効であると考えられますが、フィルタリングサービスの認知率は、未だに低水準にとどまっている状況にあります。
総務省では、携帯電話事業者等に対し、フィルタリングサービスの普及促進に向けた自主的取組を強化するよう要請しました。
引き続き、業界や関係省庁等と連携し、未成年者が携帯電話端末から安心してインターネットに接続できる環境の整備に取り組んでまいります。
さらに、「インターネット上の違法・有害情報への対応に関する研究会最終報告書」を受け、権利者団体、学識経験者、電気通信事業者団体等を構成員とする「プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会」は、権利侵害情報の発信者情報を開示できる場合の判断基準を可能な範囲で明確化するとともに、発信者情報開示請求に関する手続を分かりやすく説明した「プロバイダ責任制限法 発信者情報開示関係ガイドライン」を策定しました。
これらの取組により、発信者情報開示制度の円滑かつ適切な運用が促進されることが期待されます。
(参考1)サービス形態別の苦情・相談等の概要
苦情・相談等をサービス形態別に分類すると、「インターネット・パソコン通信」が1,795件と総受付件数の37%を占めています。次いで、「携帯電話・前年度との比較でみると、「インターネット・パソコン通信」が前年度の2,170件から約17%減の1,795件、「携帯電話・
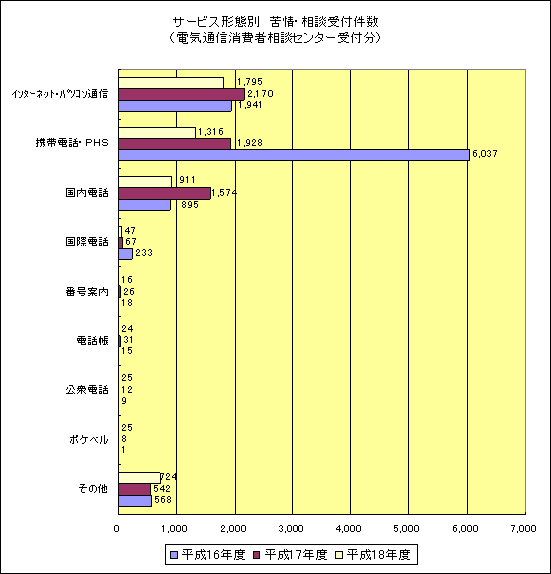
(参考2)内容分類別の苦情・相談等の概要
苦情・相談等を内容分類別に見ると、「情報提供サービス」が780件と最も多く、総受付件数の16%となっています。次いで「営業活動」が451件、「料金徴収」が446件、「制度」が385件となっています。平成18年度においても有料アダルトサイトに登録になってしまった等により情報料等を請求されるトラブルに関する問合せが多く寄せられたことにより「情報提供サービス」の件数が多くなっています。しかし、平成17年度の「情報提供サービス」の件数に比べて約56.2%の減少となっています。
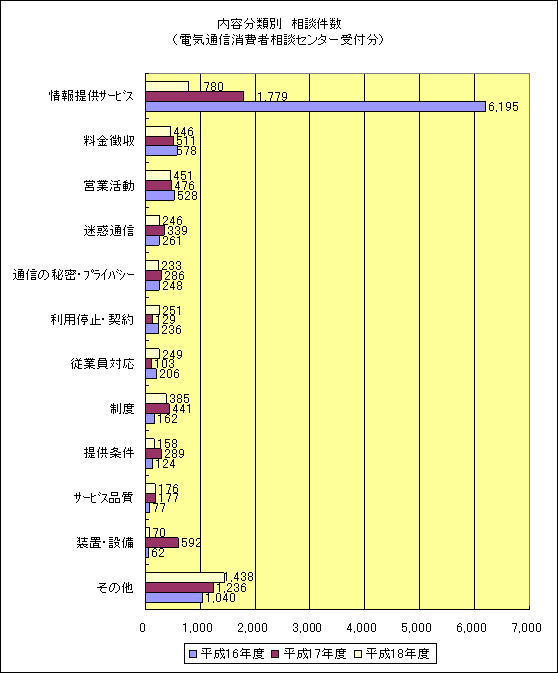
| 参考 |
電気通信サービス別分類、内容別分類の各項目
| 項目 | 対象サービス |
| 国内電話 | 国内対象の電話サービス(加入、長距離、地域、インターネット電話(国内)、 |
| 国際電話 | 国際電話サービス(インターネット電話(国際)など)及びこれに関するサービス等(国際電話のみなし契約、国際情報提供サービスなど) |
| 携帯電話・ |
携帯電話・ |
| ポケベル | 無線呼出(ポケットベル)サービス |
| インターネット・パソコン通信 | インターネット、パソコン通信サービス |
| 電話帳 | 電話帳業務(タウンページの広告を含む。) |
| 番号案内 | 番号案内サービス |
| 公衆電話 | 公衆電話業務 |
| その他 | 上記の項目に属さないもの(電報、テレホンカード、通信政策に関する意見・要望など) |
| 注:端末や故障等、問合せの内容で具体的に事業者が分かっている場合は、その事業者の区分による。 |
| 項目 | 対象内容 |
| 制度 | 制度の在り方や法解釈全般(他の項目に関するものは除く。) |
| 提供条件 | 料金やサービス提供における提供条件など |
| 営業活動 | 電気通信事業者(代理店を含む。)の営業活動(「従業員対応」に関することは除く。広報活動、広告内容等を含む。) |
| 従業員対応 | 電気通信事業者(代理店を含む。)の従業員の窓口対応等 |
| 料金徴収 | 料金の徴収・料金額(下記の「情報提供サービス」に関する料金徴収は除く。) |
| 利用停止・契約 | 利用停止やサービス契約(契約解除等に伴う違約金、未成年者契約を含む。) |
| サービス品質 | 提供するサービスの質、通信品質など |
| 装置・設備 | 鉄塔、電柱、アダプタ、端末機など |
| 通信の秘密・プライバシー | 通信の秘密やプライバシー、個人情報など |
| 迷惑通信 | 迷惑電話やインターネットのホームページ上の誹謗中傷など |
| 情報提供サービス | ダイヤル |
| その他 | 上記の項目に属さないもの(利用マナー、携帯電話・ |
電気通信サービスの利用者の相談窓口の所在地・電話番号
| 名称 | 住所 | 電話番号・担当窓口 | 管轄都道府県 |
| 北海道総合通信局 | 〒060-8795 札幌市北区北8条西2-1-1 札幌第1合同庁舎 |
011-709-3956 【電気通信事業課】 |
北海道 |
| 東北総合通信局 | 〒980-8795 仙台市青葉区本町3-2-23 仙台第2合同庁舎 |
022-221-0632 【電気通信事業課】 |
青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島 |
| 関東総合通信局 | 〒102-8795 千代田区九段南1-2-1 九段第3合同庁舎 |
03-6238-1935 【電気通信事業課】 |
茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨 |
| 信越総合通信局 | 〒380-8795 長野市旭町1108 長野第1合同庁舎 |
026-234-9952 【電気通信事業課】 |
新潟、長野 |
| 北陸総合通信局 | 〒920-8795 金沢市広坂2-2-60 金沢広坂合同庁舎 |
076-233-4429 【電気通信事業課】 |
富山、石川、福井 |
| 東海総合通信局 | 〒461-8795 名古屋市東区白壁1-15-1 名古屋合同庁舎第3号館 |
052-971-9133 【電気通信事業課】 |
岐阜、静岡、愛知、三重 |
| 近畿総合通信局 | 〒540-8795 大阪市中央区大手前1-5-44 大阪合同庁舎第1号館 |
06-6942-8519 【電気通信事業課】 |
滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山 |
| 中国総合通信局 | 〒730-8795 広島市中区東白島町19-36 |
082-222-3376 【電気通信事業課】 |
鳥取、島根、岡山、広島、山口 |
| 四国総合通信局 | 〒790-8795 松山市宮田町8-5 |
089-936-5042 【電気通信事業課】 |
徳島、香川、愛媛、高知 |
| 九州総合通信局 | 〒860-8795 熊本市二の丸1-4 |
096-326-7862 【電気通信事業課】 |
福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島 |
| 沖縄総合通信事務所 | 〒900-8795 那覇市東町26-29-4階 |
098-865-2302 【情報通信課】 |
沖縄 |
| 【受付時間 平日 9時〜12時、13時〜17時】 |
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
| 電気通信消費者相談センター | 〒100-8926 千代田区霞が関2-1-2 中央合同庁舎第2号館 |
03-5253-5900 |
| 【受付時間 平日 9時半〜12時、13時〜17時】 |