発表日 : 1998年 9月29日(火)
タイトル : 携帯電話の短期ばく露では脳(血液ー脳関門)に障害を与えず
−生体電磁環境研究推進委員会の研究結果− 郵政省では、昨年10月より「生体電磁環境研究推進委員会(委員長:上野照剛 東京大学教授)」を開催し、電波の生体安全性評価に関する研究・検討を行って いるところです。 同委員会では、このたびラットを用いた短期電波ばく露実験の結果、携帯電話に 対する電波防護指針の電波強度レベルにおいて、血液−脳関門に障害を及ぼすよう な影響が引き起こされないことを確認しました。 1 概 要 携帯電話から発射される電波の脳に対する影響を確認するため、脳血管と脳細 胞の間に存在し、高分子や水溶性分子の通過を制限することにより脳内への毒性 物質の侵入を防御している「血液−脳関門(BBB)」に対して電波ばく露の影響を調 べました。その概要は次のとおりです。 (1)実験環境 ア 実験動物 ラット48匹[(ばく露群8匹、偽ばく露群8匹、対照群8匹)×2セッ ト] イ ばく露期間及びばく露量 2週間及び4週間(1時間/日のばく露を5日/週実施) 脳部SAR(注) 2W/kg(電波防護指針における一般環境指針値) (注)SAR(Specific Absorption Rate:比吸収率) 生体が電磁界にさらされることによって単位質量の組織に単位 時間に吸収されるエネルギー量をいう。 ウ 周波数、変調方式 1,439MHz PDC方式(我が国におけるデジタル携帯電話の変調 方式) (2)実験の結果 ア 血液−脳関門の透過性に対する影響 複数の方法を用いた検討を行った結果、2週間及び4週間実験とも電波ば く露による影響は認められない。 イ 神経細胞の形態学的影響 形態学的変化は認められない。 ウ 体重変化 各群間に差が認められず、電波ばく露が体重の増減に影響を及ぼすほどの ストレス刺激にはなっていない。 (3) 評価 同委員会では、実験方法及び影響の確認方法が適当であると判断し、携帯 電話に対する電波防護指針の電波強度レベルでの短期ばく露では、血液ー脳 関門に障害を及ぼすような影響は引き起こされないことを確認しました。 2 今後のスケジュール 同委員会では、今後、電波の長期ばく露が脳に及ぼす影響等について、引き続 き研究を行うこととしています。 連絡先:電気通信局電波部電波環境課 担 当:堀内課長補佐、伊藤生体電磁環境係長 電 話:03−3504−4900 (参考) 1 血液-脳関門(Blood - Brain Barrier:BBB)について 血液−脳関門とは、脳毛細血管と脳細胞の間に存在し、高分子や水溶性分子の 通過を制限することにより脳内への毒性物質の侵入を防御し、また脳細胞周囲の 細胞環境(浸透圧、pH、電解質濃度(特にカリウム濃度))を維持する働きをし ている構造の総称である。BBBは、熱刺激、外傷、急性高血圧、脳虚血、けいれん 発作等の際、その透過性がこう進していることが確認されている。 もし、電波ばく露によりBBBの透過性がこう進するならば、発がん物質が脳内に 侵入することによる脳しゅようの発生や、てんかん発作、けいれんなどが電波ば く露により引き起こされる可能性が生じる。 2 電波ばく露によるBBBへの影響についてのこれまでの研究 これまで次のような実験が報告されているが、このうち影響が認められたとい う報告については、電波の強さにかかわらず影響が出るなど実験方法に問題があ る可能性や、ばく露電力が大きく電波の熱作用により体温が上昇した結果である 可能性が指摘されており、熱作用の影響のない電波強度においてもBBBの透過性に 影響を及ぼしうるかについて追試が必要と考えられている。 このため、本研究では、電波防護指針の一般環境指針値である2W/kgを用い、非 熱作用のみによる影響を検討した。
時期 | 研究者 | 周波数 | 出 力 | 影響の有無 |
1979年 1982年 1982年 1994年 1997年 | Preston (カナダ) Gruenau (アメリカ合衆国) Ward (アメリカ合衆国) Salford (スウェーデン) Fritze (ドイツ) | 2,450 MHz 2,800 MHz 2,450 MHz 915 MHz 900 MHz | 0.1〜30mW/cm2 1〜40mW/cm2 2〜6W/kg 0.016〜5W/kg 7.5W/kg | 無 無 無 有 有 |
注: 以前は、動物を入れない状況での電波の強さの単位(mW/cm2)を使用して いたが、現在は、動物にどの位のエネルギーが局所的に吸収されるかの単 位(W/kg)を使用。 3 電波ばく露装置について ラットの大きさに合わせてばく露装置を開発した。最大直径を80mmとし、頭部 を先細りにし、長さは体長に合わせ調節可能な仕様とした。90×90×70cmの小型 電波暗室の中に、開発したばく露装置を放射状に8個、中央の電波発生アンテナ にラットが頭をつき合わせるように設置した。 使用した電波は、周波数が1,439MHzで脳内での最大の比吸収率(SAR)が2W/kg となるように強度を調節した。ラットの代謝熱や電波による温度上昇を防止する ために、アンテナ上部より各アクリル容器に向かい、送風器による送風冷却を行 った。 以上の装置を、ばく露実験用及び偽ばく露実験用に計2個準備した。 4 ラットの群分けについて 頭部への局所に集中したばく露実験を行うため、通常のラット(Wisterラット) よりも身体のより大きなラット(SD(Sprague-Dawley)ラット)を用い、2週間 ばく露実験及び4週間ばく露実験でそれぞれ24匹を8匹ずつ以下の3群に分けた。 1)ばく露群 :ばく露装置にて1日1時間電波ばく露を行った。これを5日間連 続して行い、2日休んだ後、再び1日1時間、5日間のばく露を行 った(4週間ばく露の実験では、さらに2週間ばく露を行った)。 2)偽ばく露群:ばく露装置に、ばく露群と同一期間入れたラット群。実際の電波 ばく露は行っていない。 3)対照群 :実験期間中、通常の飼育ケージ内で飼育し続けたラット群。 5 血液-脳関門(BBB)への影響を検討するための方法について BBBに及ぼす影響については、エバンスブルー(Evans blue:EB)法、アルブミ ン免疫染色法、HRP(horseradish peroxidase)法の3種類の方法で検討を行った。 1) エバンスブルー法 エバンスブルーは静脈内に投与されると速やかに血清アルブミンと結合する。 血清アルブミンは正常なBBBを通過しない。血管外の脳内にEBが存在している場 合、異常と判定される。 2) アルブミン免疫染色法 ラットのアルブミンにのみ結合する抗体を血液中に注入し、その後その抗体 を発色させることにより脳内のアルブミンを確認する方法。血管外の脳内で発 色が見られた場合、異常と判定される。 3) HRP法 HRPは分子量44,000の糖蛋白質で、静脈内投与されても正常なBBBを通過しな い。また、HRPは電子顕微鏡で観察することができるので、微細形態としての蛋 白質の動きを確認するのに適している。血管外の脳内にHRPが存在している場合、 異常と判定される。 6 病理組織学的検討について 脳組織をヘマトキシリン-エオジン(HE)法により染色し、神経細胞の形態学的 変化の有無を光学顕微鏡により検討した。 7 体重変化について 表 ばく露実験前後の体重変化(4週間ばく露実験)
8 実験者 (1)動物実験 名川弘一(東京大学大学院医学系研究科助教授) 連絡先:03-5800-8653 釣田義一郎(東京大学大学院医学系研究科大学院生) 上野照剛(東京大学大学院医学系研究科教授) (2)ばく露装置開発 多氣昌生(東京都立大学大学院工学系研究科教授) 連絡先:0426-77-2763 渡辺聡一(郵政省通信総合研究所)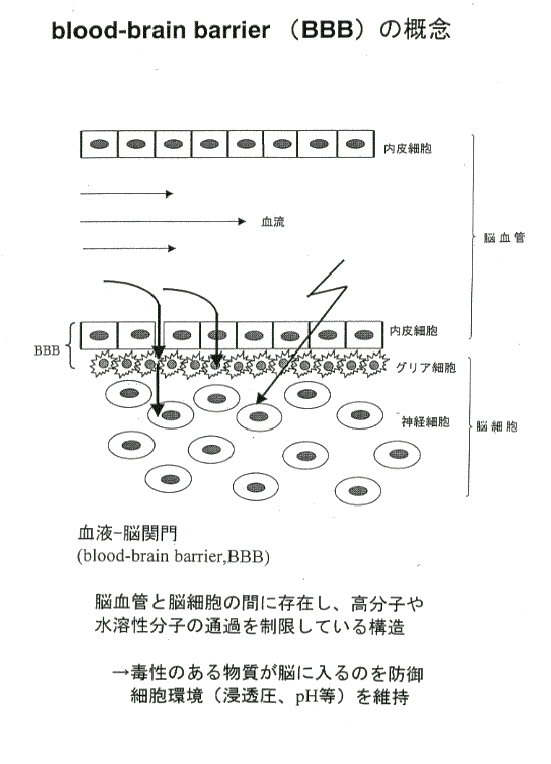
生体電磁環境研究計画 平成10年9月現在
(※)ドシメトリ:電磁界にばく露した人又は動物における体内電界強度又はエネ ルギー吸収量等を測定又は計算によって求めること。 注:本計画は、研究結果等を踏まえ、その都度見直すこととしている。 「生体電磁環境研究推進委員会」構成員 (敬称略 あいうえお順) あいはら しげのぶ 相 原 重 信 通信機械工業会第2技術部長 あさの たかひさ 浅 野 隆 久 (社)電気通信事業者協会業務部長 あべ としあき 阿 部 俊 昭 東京慈恵会医科大学教授 うえの しょうごう 委員長 上 野 照 剛 東京大学大学院医学系研究科教授 うちだ くにあき 内 田 國 昭 (社)電波産業会研究開発本部次長 おおくぼ ちよじ 大久保 千代次 厚生省国立公衆衛生院生理衛生学部長 おの てつや 小 野 哲 也 東北大学医学部教授 きくい つとむ 菊 井 勉 (財)テレコムエンジニアリングセンター理事 (平成10年7月〜) ((財)無線設備検査検定協会理事企画調整部長) しらい ともゆき 白 井 智 之 名古屋市立大学医学部教授 すぎうら あきら 杉 浦 行 郵政省通信総合研究所総合研究官 たき まさお 多 氣 昌 生 東京都立大学大学院工学研究科教授 つるた ひろし 鶴 田 寛 労働省産業医学総合研究所健康障害予防研究部長 ながた たかし 永 田 孝 志 日本モトローラ(株)戦略統括本部本部長 ながわ ひろかず 名 川 弘 一 東京大学医学部助教授 ふじわら おさむ 藤 原 修 名古屋工業大学工学部教授 みやこし じゅんじ 宮 越 順 二 京都大学医学部助教授 やまぐち なおと 山 口 直 人 厚生省国立がんセンター研究所がん情報研究部長