第一章 一般加入電話・ISDNの番号ポータビリティの実現方式 第一章 一般加入電話・ISDNの番号ポータビリティの実現方式 1 実現方式を特徴付ける要素 一般加入電話・ISDNの番号ポータビリティの実現方式については、「電気 通信の高度化のための番号の在り方に関する研究会報告書」(平成7年5月)に おいて、次のように3種類に分類されている。(図1−1) ○ 着信転送方式 移転元事業者(番号ポータビリティにより事業者を移転する前に加入者が 契約してい た事業者)の加入者交換機まで回線を設定し、着信者が移転している場合 に移転先事業者(番号ポータビリティにより事業者を移転した後に加入者が 契約する事業者)へ呼の転送を行うこととして、回線を延長して設定する方 式 ○ リルーチング(クランクバック)方式 移転元事業者の加入者交換機まで回線を設定し、着信者が移転している場 合に設定された回線を途中まで遡って開放し、途中から移転先事業者まで回 線を設定する方式 ○ IN(Intelligent Network)方式 発信者が収容されている加入者交換機又は中継交換機でINのデータベー スにアクセスし、着信者が移転している場合に移転先事業者まで回線設定を 行う方式 図1−1 「電気通信の高度化のための番号の在り方に関する研究会報告書」 (平成7年5月)における一般加入電話・ISDNの番号ポータビリ ティの実現方式の分類 また、ITU−T SG2(国際電気通信連合電気通信標準化部門第2研究委 員会)において番号ポータビリティに関する勧告化作業が行われており、199 8年3月現在の勧告草案では、次の4種類が示されている。(図1−2) ○ オンワード・ルーチング(Onward Routing)方式 移転元事業者のネットワークまで回線を設定し、移転元事業者のネットワ ークにおいて着信者が移転していることを識別する。移転元事業者が移転先 の情報をデータベース(移転元事業者が保有)に問い合わせて、移転先事業 者のネットワークまで呼の転送を行うこととして、移転元事業者のネットワ ークから回線を延長して設定する。 ○ ドロップバック(Dropback)方式 移転元事業者のネットワークまで回線を設定し、移転元事業者のネットワ ークにおいて着信者が移転していることを識別する。移転元事業者が移転先 の情報をデータベース(移転元事業者が保有)に問い合わせて、この呼の信 号メッセージに基づき設定された回線を途中まで遡って開放し、途中から移 転先事業者まで回線を設定する。 ○ キュエリー・オン・リリース(Query on Release)方式 移転元事業者のネットワークまで回線を設定し、移転元事業者のネットワ ークにおいて着信者が移転していることを識別する。移転元事業者の前段に 位置する中継事業者のネットワークまで遡って回線を開放し、中継事業者が 移転先の情報をデータベースに問い合わせて、移転先事業者まで回線を設定 する。 ○ オール・コール・キュエリー・ワンステップ(All Call Query One Step) 方式 発信事業者(発信者が収容されている事業者)のネットワークにおいて、 (少なくとも番号ポータビリティにより移転している呼について)着信先 の情報をデータベースに問い合わせて、移転先事業者まで回線を設定する。 これらの方式から、実現方式を特徴付ける要素として次の3点が考えられる。 ア)移転先を示す情報を取得する事業者 イ)取得された情報に基づいて移転先事業者への回線設定を起動する事業者 ウ)移転先事業者への回線設定の起動点まで回線を戻す方法 図1−2 ITU−T SG2における番号ポータビリティの実現方式の分類 2 移転先を示す情報の取得及び回線設定の方法 2.1 検討対象となる方式案 一般加入電話・ISDNの番号ポータビリティの実現方式を特徴付ける3つの 要素について、次のように考えられる。 ア)移転先を示す情報を取得する事業者 移転先を示す情報を取得する事業者としては、 ・発信事業者 ・移転元事業者 ・中継事業者 が考えられる。 イ)取得された情報に基づいて移転先事業者への回線設定を起動する事業者 取得された情報に基づいて移転先事業者への回線設定を起動する事業者とし ては、 ・発信事業者 ・中継事業者 ・移転元事業者 が考えられる。 ウ)移転先事業者への回線設定の起動点まで回線を戻す場合の方法 移転先事業者への回線設定の起動点まで回線を戻す場合の方法としては、 ・折返し回線を設定する方法(折返しの部分は二重に回線を使用) ・回線を遡って開放する方法 が考えられる。 これら3つの要素の組み合わせから、一般加入電話・ISDNの番号ポータビ リティの実現方式として検討対象とすべき方式案としては、図1−3に示すもの が考えられる。 図1−3 一般加入電話・ISDNの番号ポータビリティの実現方式として検討 対象とすべき方式案 各方式案の概要は次のとおりである。 【案1−1】 [1]発信者によりダイヤルされた番号により移転元事業者まで回線設定を行 う。 [2]移転元事業者において、ダイヤルされた番号の加入者が番号ポータビリ ティにより移転していることを確認し、移転先を示す情報を取得する。 [3]取得した情報に基づき、回線を折り返して移転先事業者への回線設定を 起動する。 図1−4 【案1−1】の概要
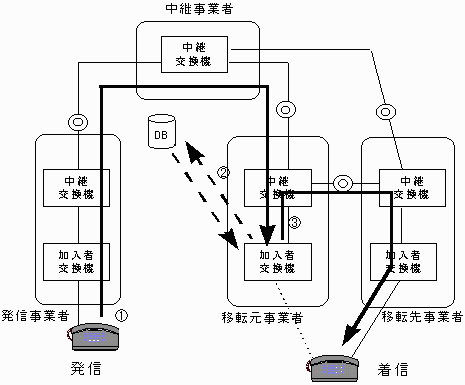
【案1−2】 [1]発信者によりダイヤルされた番号により移転元事業者まで回線設定を行 う。 [2]移転元事業者において、ダイヤルされた番号の加入者が番号ポータビリ ティにより移転していることを確認し、移転先を示す情報を取得する。 [3]取得した情報に基づき、必要に応じて、移転元事業者内で回線を開放し て、移転先事業者への回線設定を起動する。 図1−5 【案1−2】の概要
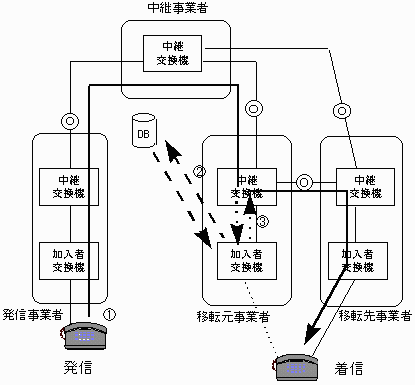
【案1−3】 [1]発信者によりダイヤルされた番号により移転元事業者まで回線設定を行 う。 [2]移転元事業者において、ダイヤルされた番号の加入者が番号ポータビリ ティにより移転していることを確認し、移転先を示す情報を取得する。 [3]取得した情報に基づき、前位事業者(中継事業者又は発信事業者)まで 回線を開放して、移転先事業者への回線設定を起動する。 図1−6 【案1−3】の概要
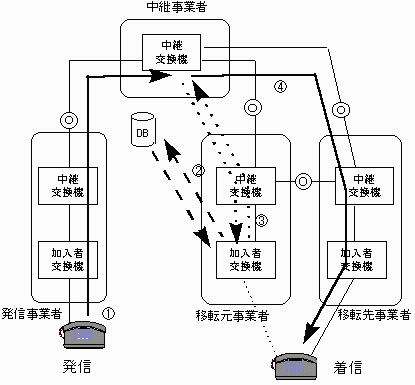
【案1−4】 [1]発信者によりダイヤルされた番号により移転元事業者まで回線設定を行 う。 [2]移転元事業者において、ダイヤルされた番号の加入者が番号ポータビリ ティにより移転していることを確認し、前位事業者まで回線を開放する。 [3]前位事業者において移転先を示す情報を取得する。 [4]取得した情報に基づき、移転先事業者への回線設定を起動する。 図1−7 【案1−4】の概要
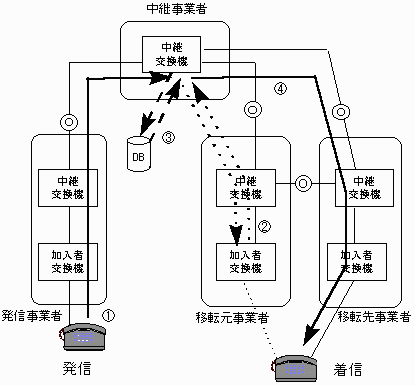
【案1−5】 [1]発信者によりダイヤルされた番号により中継事業者まで回線設定を行う。 [2]中継事業者において、ダイヤルされた番号の加入者が番号ポータビリテ ィにより移転していることを確認し、移転先を示す情報を取得する。 [3]取得した情報に基づき、移転先事業者への回線設定を起動する。 図1−8 【案1−5】の概要
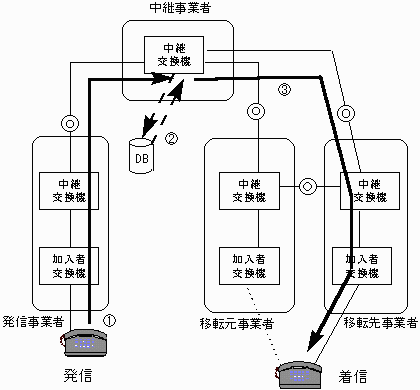
【案1−6】 [1]発信事業者において、ダイヤルされた番号の加入者が番号ポータビリテ ィにより移転していることを確認し、移転先を示す情報を取得する。 [2]取得した情報に基づき、移転先事業者への回線設定を起動する。 図1−9 【案1−6】の概要
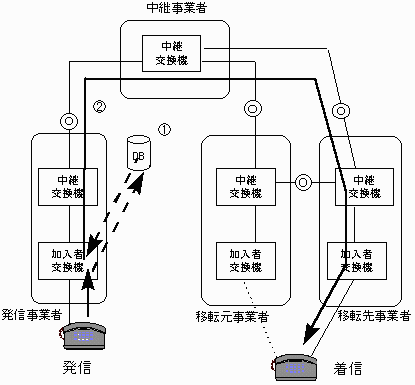
2.2 望ましい方式の選定 (1)回線の効率的利用及びネットワークの改修規模から見た各案の評価 2.1項で挙げた6つの方式案について、評価を行った結果は次のとおりであ る。 [1]【案1−5】及び【案1−6】は、回線の効率的利用の観点からは最適 であると考えられるが、全ての発呼についてデータベースにアクセスする ことを前提とした方式であり、ネットワークの改修が比較的大規模になる こと、また、中継事業者又は発信事業者となり得る全ての事業者において この方式を導入するためのネットワーク改修が必要になることから、導入 可能とすべき時期を考慮すると現実的な方式ではないと考えられる。 [2]【案1−3】、【案1−4】、【案1−5】及び【案1−6】は、中継 事業者又は発信事業者において相当規模のネットワーク改修を実施するこ とを前提とする方式である。 番号ポータビリティは、関連する事業者の協力により実現されるもので あるが、番号ポータビリティの導入のためのインセンティブを有する事業 者以外の事業者に相当規模の負担をかけることは望ましくないことから、 これらの方式は望ましい方式とは考えられない。 なお、前位事業者が希望する場合には、関係事業者間で合意の上、当該 事業者のネットワークを改修することを前提とする方式を採用することを 許容すべきと考えられる。 [3]【案1−1】は、折返し回線を設定する方式であるが、折返しの部分は 呼が保留される間回線が二重に使用されることになり、回線利用が非効率 となることから、可能な限り避けるべきである。 [4]【案1−2】は、移転先を示す情報の取得及び回線設定のための処理が 移転元事業者のネットワーク内で行われる方式であり、ネットワークの改 修については特段の問題が認められない。また、回線の効率的利用につい ても、折り返し回線の設定を避ける方式となっている。 以上の評価から、6つの方式案の中で【案1−2】(移転元事業者が移転先を 示す情報を取得し、移転元事業者内で必要に応じて回線を遡って開放し、移転先 事業者への回線設定を起動する方式)が最適と考えられる。 (2)発信事業者が移転元事業者又は移転先事業者となる場合についての検討 (1)項での検討は、発信事業者が移転元事業者や移転先事業者とならない場 合を想定しており、中継事業者を経由しない呼についても同様の結果となる。発 信事業者が移転元事業者又は移転先事業者となる場合は次のように考えられる。 発信事業者が移転元事業者又は移転先事業者となる場合、移転先を示す情報を 取得し、移転先事業者への回線設定を起動することができるのは、中継事業者を 経由する呼については発信事業者、中継事業者又は移転元事業者、中継事業者を 経由しない呼については移転元事業者となる。この場合も、最適な方式を選定す るためにネットワークの改修規模及び回線の効率的利用を重視することとすれば、 【案1−2】において移転元事業者又は移転先事業者を発信事業者とみなしたも のが最適と考えられる。 なお、発信事業者が移転先事業者となる場合、この事業者が番号ポータビリテ ィにより自己に移転した着信者への呼であることを認識し、この事業者のネット ワーク内で回線設定を完結することは許容されるべきと考えられる。 (3)前位事業者がネットワークの改修を行う場合についての検討 【案1−2】は、発信事業者、中継事業者、移転元事業者及び移転先事業者に またがる回線設定を行う方式となっている。このため、料金精算等の観点から、 前位事業者が、自身のネットワークの改修を許容して、【案1−3】(移転元事 業者が移転先を示す情報を取得し、前位事業者まで回線を遡って開放し、前位事 業者が移転先事業者への回線設定を起動する方式)による番号ポータビリティの 実現を希望する場合が考えられる。 【案1−3】と【案1−2】の相違点は、移転先事業者への回線設定の起動点 まで回線を遡って開放する際に前位事業者まで遡るか否かである。 交換機において前位事業者へ回線を遡って開放する機能については、既にIT U勧告に準拠した形でTTC標準が作成されており、【案1−3】と【案1−2】 のいずれを採用する場合にも、このTTC標準に基づく交換機を使用することが 一般的と考えられる。(例えば、【案1−2】を採用する場合は、当該TTC標 準における前位事業者へ回線を遡って開放するための機能を停止させればよいこ ととなる。) このため、【案1−2】を実現することとしている事業者が、これに加えて 【案1−3】を実現する機能を追加するとしても大きな負担にはならないものと 考えられる。
4 社団法人電信電話技術委員会(TTC)によるTTC標準JT−Q.730 (ISDN付加サービスの信号手順、1996年11月27日制定)におい てリダイレクション手順が規定されている。このTTC標準は、ITU−T 勧告1993年版Q.730に準拠したものであり、1996年10月のI TU−T SG11ラポータ会合でのQ.730勧告草案に基づきリダイレ クション手順を追加している。なお、ITU−T勧告Q.730については、 リダイレクション機能の高度化等のため、現在、ITU−T SG11にお いて改訂作業が行われている。
したがって、前位事業者が希望する場合には関係事業者間で合意の上で【案1 −3】を採用することを許容することが適当であると考えられる。(なお、【案 1−4】は、【案1−3】と比較して、移転先を示す情報の取得のために前位事 業者のネットワークの改修が必要となることから、前位事業者が希望する方式と は考えられない。) (4)まとめ 以上の検討をまとめると、移転先を示す情報の取得及び回線設定の方法につい ては、【案1−2】(移転元事業者が移転先を示す情報を取得し、移転元事業者 内で必要に応じて回線を遡って開放し、移転先事業者への回線設定を起動する方 式)を採用することとし、関係事業者間で合意が得られる場合には、この方式を 一部変更した【案1−3】(移転元事業者が移転先を示す情報を取得し、前位事 業者まで回線を遡って開放し、前位事業者が移転先事業者への回線設定を起動す る方式)を採用することとすることが適当である。(移転元事業者においては、 【案1−2】、【案1−3】のいずれにも対応する必要がある。)
5 【案1−2】を最適回線再設定方式と呼ぶこととする。また、【案1−3】 を最適回線再設定方式のオプションと呼ぶこととする。 6 なお、【案1−2】において移転元事業者と移転先事業者の間にPOIを設 けることができない場合及び【案1−3】において中継事業者と移転先事業 者の間にPOIを設けることができない場合は、両者に接続する事業者を経 由して回線設定を行うことを許容するものとする。
3 移転先を示す情報の形式及び内容 番号ポータビリティが導入されると、ダイヤルされた番号の市内局番の指定を 受けた事業者(移転元事業者)と実際に加入者が契約している事業者(移転先事 業者)が異なるため、一旦ダイヤルされた番号に基づき処理を行い、番号ポータ ビリティより移転している場合にはデータベースにアクセスして移転先を示す情 報を取得することが必要になる。番号ポータビリティにより移転した利用者への 回線設定を事業者間で確保するためには、移転先を示す情報の形式及び内容を事 業者間で共通化しておくことが必要である。 3.1 検討対象となる案 番号ポータビリティにより移転した着信者へ回線を設定するために必要な移転 先を示す情報の形式及び内容の検討に当たっては、次の3つの要素が考えられる。 ・ 移転した着信者の加入者回線を示す電話番号を利用するか否か ・ 各事業者のネットワーク内の既存の回線設定機能が利用可能となる形式の 情報とするか否か ・ 情報が示す内容を何にするか(着信者の加入者回線か、着信者の加入者回 線が収容される加入者交換機か、移転先事業者か) これら3つの要素から、検討対象となる案としては図1−10に示すものが考 えられる。 図1−10 一般加入電話・ISDNの番号ポータビリティの移転先を示す情報 の形式及び内容に関して検討対象となる案 3.2 望ましい案の選定 図1−10に示す5つの案について、評価を行った結果は次のとおりである。 [1]【案2−1】は、着信者の加入者回線を示す電話番号を移転先を示す情 報として利用するもので、番号ポータビリティにより移転した加入者に対 して、当初より加入者が使用している番号に加えて回線設定を行うための 番号を使用することとなる。このため、番号の利用が非効率的となり、望 ましい案とは言えない。 [2]【案2−5】は、ネットワーク内の既存の回線設定機能を利用しない方 式であるが、この場合、移転先を示す情報により回線の設定を行う機能を 新たに各事業者において具備するために大規模なネットワーク改修が必要 となる。 したがって、現実的な案とは言えない。 [3]【案2−2】、【案2−3】及び【案2−4】は、既存の回線設定機能 を利用可能とするために、「市外局番+市内局番」又は「市外局番+市内 局番+加入者番号」という形式の情報(ただし、利用者がダイヤルする電 話番号そのものではない。)を用いるものである。この情報により移転し た着信先へ回線設定を行う場合とダイヤルされた番号により回線設定を行 う場合とを区別して着信先までの回線設定を完結させるために、また、 【案2−2】及び【案2−3】では移転先事業者のネットワーク内で着信 先を特定できるように、ネットワークの改修が必要となるが、【案2−5】 に比べて改修の規模を小さくすることが可能である。 【案2−2】、【案2−3】及び【案2−4】の3つの案の特徴は表1−1の とおりである。 表1−1 移転先を示す情報の形式及び内容
|
|
情報の形式 |
情報が示す内容 |
|
【案2-2】 |
「市外局番+市内局番」の形式(移転先事業 者が使用する代表的な市内局番を使用) |
移転先事業者 |
|
【案2-3】 |
「市外局番+市内局番」の形式 |
移転先の加入者交換機 |
|
【案2-4】 |
「市外局番+市内局番+加入者番号」の形式 |
加入者回線 |
【案2−2】は、「市外局番+市内局番」の形式を持ち、市内局番部分に移転 先事業者の代表的な市内局番を使用する案である。この場合、まず回線が移転元 事業者又は前位事業者と接続される移転先事業者の交換機まで設定され、この交 換機から加入者回線まではダイヤルされた着信者の番号により回線設定が行われ ることになる。 【案2−3】は、「市外局番+市内局番」の形式を持ち、市内局番部分に移転 した着信者が収容されている加入者交換機の市内局番を使用するものである。こ の場合、この情報により移転先事業者の加入者交換機まで回線が設定され、加入 者交換機においてダイヤルされた着信者の番号により加入者回線が設定されるこ とになる。 【案2−4】は、「市外局番+市内局番+加入者番号」の形式を持ち、市内局 番部分に移転した着信者が収容されている加入者交換機の市内局番を、加入者番 号部分に移転した着信者が収容されている加入者回線を示す情報を使用するもの である。この場合、この情報により加入者回線まで回線設定ができることになる。 これら3つの案では、移転先事業者以外の事業者においてはいずれであっても 移転先を示す情報を移転先事業者へ転送する機能を具備すればよい。 一方、移転先事業者にとっては案によって回線設定の方法が異なるが、移転先 事業者によっては移転元事業者に通知しておくべき情報を必要最小限にしたいと の考え方があり得ることから、移転先事業者が望ましい案を選択し、これによっ て移転先を示す情報を移転元事業者に通知することが適当と考えられる。 以上をまとめると、移転先を示す情報については、【案2−2】(「市外局番 +市内局番」の形式を持ち、市内局番部分に移転先事業者の代表的な市内局番を 使用する案)、【案2−3】(「市外局番+市内局番」の形式を持ち、市内局番 部分に移転した着信者が収容されている加入者交換機の市内局番を使用する案) 及び【案2−4】(「市外局番+市内局番+加入者番号」の形式を持ち、市内局 番部分に移転した着信者が収容されている加入者交換機の市内局番を、加入者番 号部分に移転した着信者が収容されている加入者回線を示す情報を使用する案) から移転先事業者が選択する方法とすることが適当と考えられる。 なお、【案2−4】については、移転先事業者において番号ポータビリティに より移転してくる加入者が多くなった場合にも対応し得るようにすることが適当 であり、加入者番号部分を電話番号の加入者番号の4桁より最低1桁多くするこ とができるような措置を予め採っておくことが望ましい。 4 実現方式がサービス品質等に及ぼす影響 番号ポータビリティを導入した場合に、既存の網サービス、機能、能力への悪 影響、並びに、サービス品質及びネットワークの信頼性への悪影響が現れないこ とが必要である。 一般加入電話・ISDNの番号ポータビリティの実現方式として【案1−2】 又は【案1−3】を採用する場合に、これらについて検討した結果は次のとおり である。 (1)既存の網サービス、機能、能力への影響 番号ポータビリティを導入する際に新たに必要となる処理としては、次が考え られる。 [1]移転先を示す情報を取得し、これにより回線を設定 ダイヤルされた番号による回線設定に替えて、交換機においてデータベー スへ問い合わせて取得した移転先を示す情報により回線設定を行うこととな るが、この情報はダイヤルされた番号と同様の形式を持つ。 [2]回線を遡って開放 移転先を示す情報を取得する交換機及び移転先事業者への回線設定を起動 する交換機への機能追加により回線が開放されるが、開放後に移転先事業者 へ転送される情報に影響を及ぼさない。 これらの処理を行うことにより、着信先の加入者回線の特定のための信号情報 が付加されることを除いて、基本的に移転先事業者の加入者交換機へ転送される 信号情報に変更はなく、既存の網サービス、機能、能力に大きな影響を与えるこ とはないものと考えられる。 なお、番号ポータビリティにより移転した加入者からの発信に際しては、その 加入者が契約している番号を加入者交換機から転送できるよう機能追加が必要と なる。 (2)サービス品質及びネットワークの信頼性への影響 新たに必要となる処理は上記の通りであるが、これらの処理はいずれも既に実 現されているサービスにおいて行われているものである。番号ポータビリティに おいては、これらを組み合わせて処理を行うこととなるが、このことによってサ ービス品質及びネットワークの信頼性を大きな影響を及ぼすことはないものと考 えられる。 なお、番号ポータビリティの提供を受けている利用者への呼は、それ以外の利 用者への呼に比べて接続のための処理が余分に必要となるが、例えば、接続型P HS端末から接続型PHS網へローミング中の活用型PHS端末への発呼の接続 のためにより複雑な処理が許容されていることを考えれば、不合理な遅延を生じ る接続とはならないものと考えられる。 5 ネットワークにおいて具備すべき機能 望ましい方式として【案1−2】又は【案1−3】、その際の移転先を示す情 報に関する案として【案2−2】、【案2−3】又は【案2−4】を採用する場 合に、前位事業者、移転元事業者及び移転先事業者のネットワークに具備すべき 主な機能は次のとおりである。 【案1−2】の実現に必要な機能 移転元事業者において、移転先を示す情報を取得した後、必要に応じて回線を 遡って開放する機能が必要となる。また、移転先を示す情報に基づき移転先事業 者への回線設定を起動する機能及びダイヤルされた着信者の番号(移転した着信 者が契約している番号)を移転先事業者へ転送する機能が必要となる。 移転先事業者においては、移転先を示す情報及び移転した着信者が契約してい る番号(【案2−4】による場合は移転先を示す情報)により加入者回線まで回 線を設定する機能を具備する必要がある。 【案1−3】を採用する場合に必要な機能 前位事業者は、移転元事業者へ回線を設定する過程において、移転元事業者に 対して回線を遡って開放することを要求する旨の通知を行う機能が必要となる。 移転元事業者においては、移転先を示す情報を取得した後、前位事業者からの 通知に基づき前位事業者まで回線を遡って開放する機能及び移転先を示す情報を 転送する機能が必要となる。 前位事業者では、移転元事業者までの回線を開放する機能、移転元事業者が取 得した移転先を示す情報に基づき移転先事業者への回線設定を起動する機能及び 移転した着信者が契約している番号を移転先事業者へ転送する機能が必要となる。 移転先事業者では、【案1−2】の実現に必要な機能として示した機能と同じ ものが必要となる。 なお、以上の機能の他に、事業者間精算等のために必要な情報を転送する機能 が必要になるものと考えられる。 また、【案1−2】、【案1−3】では移転元事業者自身が移転先を示す情報 を取得する事業者となることから、移転元事業者が個別にデータベースを構築す ることとしても問題はない。
7 なお、移転元事業者と移転先事業者の間にPOIを設けることができない 場合に両者の間で回線を設定する事業者について、移転先を示す情報に基づ き移転先事業者への回線設定を行う機能が必要となる。 8 なお、中継事業者と移転先事業者の間にPOIを設けることができない場 合に両者の間で回線を設定する事業者について、移転先を示す情報に基づき 移転先事業者への回線設定を行う機能が必要となる。
(参考) 【案1−2】又は【案1−3】と【案1−5】又は【案1−6】との混在について 【案1−5】及び【案1−6】は、2.2(1)において述べたように、ネット ワークの改修が比較的大規模となることから、導入可能とすべき時期を考慮する と現実的な方式ではない。 しかしながら、回線の効率的利用の観点において優れていることから、【案1 −2】又は【案1−3】が実現されている状態において、特定の事業者が【案1 −5】又は【案1−6】の実現を希望する場合が考えられる。 【案1−5】又は【案1−6】では、移転元事業者まで回線設定が行われる前に 前位事業者において移転先を示す情報が取得され、移転先事業者への回線設定が 起動されることになる。このため、【案1−2】又は【案1−3】が採用されて いる状態において、特定の事業者により【案1−5】又は【案1−6】が実現さ れたとしても、いずれかの事業者において必ず必要な情報が取得され、回線設定 が起動されることになるので、問題は生じない。 なお、移転先を示す情報の取得は、前位事業者が全ての呼に対して行う必要が あるが、この場合にアクセスされるデータベースについては、前位事業者毎に構 築する方法と前位事業者が共同で構築する方法が考えられる。いずれの場合も、 情報を更新するために移転元となる事業者の協力が必要であり、これらの方式を 採用する場合は事前に事業者間で協議を行うことが必要である。
9 この場合、前位事業者と移転先事業者の間で回線を設定する事業者につい て、移転先を示す情報に基づき移転先事業者への回線設定を行う機能が必要 となる。