接続ルールの見直しに関する意見書
平成13年2月9日
総務大臣殿
|
郵便番号 |
104-8508 |
|
住 所 |
とうきょうとちゅうおうくはっちょうぼり 東京都中央区八丁堀四丁目7番1号 |
|
氏 名 |
にっぽんてれこむかぶしきがいしゃ 日本テレコム株式会社 |
|
|
むらかみ はるお 代表取締役社長 村上 春雄 |
|
担 当 |
経営企画部 担当部長 白石 規哲 経営企画部 吉野 充信 |
|
(電話番号) |
(03)4288−8013 |
|
(メールアドレス) |
myoshino@japan-telecom.co.jp |
別紙のとおり意見を提出します。
| 別紙 |
<はじめに>
昨年10月の「接続ルール見直しに関する意見募集」から昨年12月の「接続ルール見直しについての第一次答申」公表まで、短期間に「接続ルール」に関する一定の方向性を示された事については、評価に値するものであると考えます。その上で、第一次答申で結論を得られなかったものを継続検討事項としてこのような形で意見を提出する機会を与えていただいたことを厚くお礼申し上げます。継続検討事項に関する弊社意見につきましては、下記の通り各論にて述べさせていただいておりますので、宜しくお取り計らいの程お願い致します。
<各論>
- 光ファイバ設備について地域毎に異なる接続料を設定することの是非
- 光ファイバ設備との接続に関する接続料について、別会社である東西NTTに関しては、別々に設定するべきであると考えます。その上で、各地域会社のエリア内については、業務エリア内一律料金に設定することが望ましいと考えます。ただし、特定のエリア(各地域会社のエリア内)において、競争が生じた場合は、地域毎のコストに見合った接続料を設定することは問題ないと考えます。
- また、「全国一律料金とする義務が発生する場合にはコストの回収もれが生じる」という意見がありますが、一般的に、低コスト地域の方が高コスト地域よりも需要が高いため、低コスト地域で発生した利益を高コスト地域の不採算分に補填することになり、総費用を総回線数で除して業務エリア内一律の接続料を算出している過去原価方式を採る限り、回収もれが生じることはないと認識しております。
- なお、「電話等の利用者料金が地域毎の料金となるといった議論や懸念」については、現在は利用者料金については届出制であるのにも関わらず、総括原価方式的な考え方で議論そのものに矛盾があると考えます。
- 仮に地域毎に異なる接続料を設定するとした場合、過去の投資の非効率性を排除するという観点から、将来的には長期増分費用方式による算定方法が望ましいと考えます。具体的な算定については、現在「長期増分費用モデル研究会」において見直しを行っている事項に準拠するものと考えます。
- 接続料の算定根拠及びルールの在り方が明確になっていれば、「不当な差別的取扱い」にあたらないと考えます。
- 別会社として存在しているNTT東とNTT西については、異なる接続料を設定することが妥当であると考えます。さらに、仮に細分化が必要な場合は、「県単位」で算定することが適当であると考えます。
- 現在モデルの見直しを行っている長期増分費用方式により、具体的な料金を算定するべきと考えます。ただし、モデルの見直しが行われるまでは、過去原価方式とすることはやむを得ないと考えます。
- 実際の接続料算定の考え方に則して、個別具体的な接続料を設定し接続約款に規定することが重要であると考えます。上限値や平均値で規定することは、接続料設定における恣意性を許すこととなり、結果的に、根拠が不明確な料金が設定されることになると考えます。
- 地域毎に異なる接続料を設定するとした場合、固定資産明細及び費用明細等についても「地域単位」(県単位等)に分ける必要があると考えます。
- 仮に、光ファイバ設備について地域毎の接続料を設定する場合は、メタル回線についても同様に設定する必要があると考えます。接続料の設定の方式については、設備毎に区別する理由が無いことから、全て統一するべきであると考えます。
- なお、「電話等の利用者料金が地域毎の料金となるといった議論や懸念」については、1.(1)で述べたとおりです。
- 定額の接続料の具体的な算定方法
- 定額の接続料の設定については、不要であると考えます。
- GC,ZC等の機能についてはTSコストであるため、従量制として接続料を算定するべきであると考えます。
- 利用者料金と接続料金の関係については、両者が適当な水準になるよう、英国のスタックテストのようなチェック機能により是正するべきであり、個別のサービスに対応した形の接続料を設定することは不適当であると考えます。
- 公衆網における事業者向け割引料金の具体的な考え方
- 専用線におけるキャリアズレート導入が実現に向けて動いている現状を鑑み、公衆網におけるキャリアズレートについても、その考え方は同様であると考えるため、導入については問題ないと考えております。
- キャリアズレートの料金設定にあたっては、ネットワークコスト(設備料相当のコスト)を下限とするべきであると考えます。
- なお、キャリアズレートを導入した場合、公平性確保の観点から、利用者料金との関係を明確に規定し、キャリアに適用される料金は一律とすべきであると考えます。
- キャリアズレートの導入については、サービス毎に設定するのではなく、公平性確保の観点から全サービスに設定するべきであると考えます。
- キャリアズレートを設定するにあたり、通話料と基本料と区別する必要性がないことから、基本料についても対象とするべきであると考えます。
- 接続,非接続といった接続形態に関わらず、「事業者向け料金と一般向け料金との間の費用範囲の違いを反映させる」という点については、控除するべき営業費用等が同等であると考えるため、両者については、適用及び割引の考え方を同様とすることで問題ないと考えます。
- 基本的には専用線における事業者向け割引料金と同様、ユーザー料金から営業費等を控除したものを事業者向け割引料金として適用する事が適当であると考えます。
- なお、事業者向け割引料金については、前述の通り、ネットワークコストを下限とするべきであると考えます。
- 営業費等を控除した事業者向け割引料金の適用を受け、そのネットワークを利用して事業を行う第二種電気通信事業者についても、コスト負担の公平性の確保の観点から、第一種電気通信事業者同様、ユニバーサルサービスの費用を負担するべきであると考えます。
- 接続関連費用の負担の考え方
- 多くの事業者が利用できる又は利用している機能については、網使用料として広く薄く負担する事が適当であると考えます。具体的には以下の4点を新たに網使用料とすべきであると考えます。
- 網機能提供計画
- 指定電気通信設備を有するNTT地域会社が、一定のルールの下、網改造着手前に情報開示を行うことについては、他事業者との公正競争確保の観点から大変重要であるとともに、情報開示をしていることにより、接続開始が遅れるといったトラブルを防いでいると認識しております。よって、引き続き、網機能提供計画の届出公表義務は必要不可欠であると考えます。
- 公表を行う範囲については、現行の通りで問題ないと考えます。
- 公表期間については、原則現行のルールの通りで問題ないと考えております。
- ただし、例えば、網機能提供計画公表後一定期間を設け、その間に他事業者から協議開始要望がなかった場合、「網機能提供計画の届出」から「ソフトウェア開発着手」までの期間(200日以上)等を繰り上げて網改造着手することができる等、より運用の柔軟性をもたせる措置をとることについては問題ないと考えます。
- 仮に、このような運用の柔軟措置を講じた場合は、一定期間の経過をみた上で、運用方法に問題が生じる事実があった場合は、再度見直しを検討するような措置を講じるべきであると考えます。
| (1)光ファイバ設備との接続に関する接続料について、昨年10月の意見招請時に、全国一律料金とする義務が発生する場合にはコストの回収もれが生じる等の意見が出されたが、これに関して、地域毎に異なる接続料を設定することの是非をどう考えるか?(その場合、電話等の利用者料金が地域毎の料金となるといった議論や懸念についてどう考えるか。) |
【弊社意見】
| (2)仮に地域毎に異なる接続料を設定するとした場合の接続料算定の考え方、その他ルールの在り方をどのように考えるか? |
【弊社意見】
|
【弊社意見】
|
【弊社意見】
|
【弊社意見】
|
【弊社意見】
|
【弊社意見】
(3)その他
|
【弊社意見】
【弊社意見】
【弊社意見】
|
【弊社意見】
|
【弊社意見】
|
【弊社意見】
|
【弊社意見】
|
【弊社意見】
|
【弊社意見】
| 区分 | |
| (1)事業者間精算機能 | |
| (2)網同期クロック供給機能 | 電気通信事業者の設置する電気通信設備の同期をとるために、当社のクロック発振装置から発振したクロックを提供する機能 |
| (3)加入者交換機接続におけるあふれ呼の中継交換機迂回接続機能 | 当社の電気通信設備と加入者交換機及び中継交換機で接続する場合において、加入者交換機接続のあふれ呼を自動的に中継交換機に迂回する機能 |
| (4)加入者交換機機能メニュー利用機能 | 加入者交換機において加入者交換機メニューを利用し通信の交換を行う機能 |
|
【弊社意見】
|
【弊社意見】
|
【弊社意見】
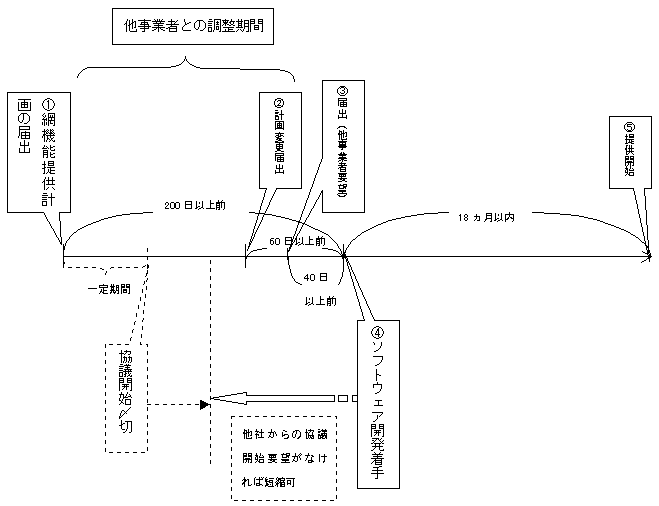
以上






