
伊達市庁舎屋上から(H12.3.31)
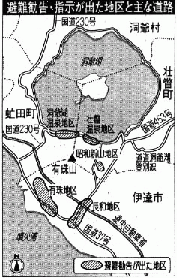
12.3.30 北海道新聞朝刊記事より
昨夜から不気味な揺れが続いていたが、昭和新山火祭りは行われていた。
ベットの中、早朝から遠雷に似た音が連続して聞こえてくるが揺れはそれほど伝わって来ない。
戸外に出て驚いた。巨大な黒い幕が青空に覆い被さろうとしていた。海岸線を見ると真夏の太陽が燦々と降りそそぎ眩しいばかりで奇妙なコントラストである。
いったい何が起こったのだろう?
昭和52年8月7日(日曜日)午前9時12分、有珠山が突然火を噴いた。明治新山生成(明治43年)から67年、昭和新山誕生(昭和20年)から32年ぶりの大噴火の始まりである。
黒い噴煙はまるで原子雲のような姿で我々の目の前に現れ、長い間蓄積されたエネルギーによって澄み切った青空を塗りつぶすかのように12,000メートルの巨大な柱になった。
これは当時市役所の独身寮にいた頃、私が書いた感想文の一部です。貴重な誌面にこのような拙い文章を掲載したことをお許し願いたいと思います。あれから23年、私が50歳をむかえる年に今度は防災担当者としてまた有珠山噴火に出会いましたが、噴火の周期は30年から50年と言われていましたので、公務員生活の中で再び噴火を迎えようとは思いも寄りませんでした。
また、有珠山を囲む伊達市、虻田町、壮瞥町の3市町でつくる有珠火山防災会議協議会では、噴火災害時における情報伝達や災害弱者対策の重要性を認識して、平成11年度、12年度で有珠火山防災計画について見直す予定で作業を進めておりましたが、その矢先での噴火となってしまいました。
既にご承知のことと思いますが、今回の噴火では、3月27日から火山性地震が急激に増え始め、28日午前0時頃胆振支庁から有珠山の異変についての第1報を受け、情報収集体制を整えておりました。2時50分には室蘭地方気象台から臨時火山情報第1号が発表され、その頃洞爺湖温泉街では有感地震が起き始めていたようです。
午前9時30分に有珠山火山活動伊達市災害対策本部を設置し、噴火の可能性が高いとのことから、ハザードマップにおいて危険区域としている有珠地区などで災害弱者への自主避難や一般住民への噴火に対する注意喚起の呼びかけを行いました。
その方法は、関係自治会長への電話連絡、市及び消防車両による広報、自主避難のチラシの配布、自治会役員、市及び消防職員の連携による災害弱者宅への巡回等であります。
翌29日には有感地震が頻発するようになったため、北大有珠火山観測所岡田教授の見解などからも噴火が切迫していることが強く実感できるようになり、有珠・長和地区への避難勧告、指示が出されました。
これらの周知には、消防用遠隔吹鳴装置からのサイレンの吹鳴並びに音声による屋外広報、市及び消防車両による広報、警察、消防による各戸別のローラー巡回等により情報の伝達を行ったところであります。また、この間当然テレビ等のマスコミを利用し情報の周知を図りました。
さらに避難拒否者等の現地説得に努め、全ての住民の避難が完了したのは、30日午後2時40分頃であり、有珠・長和地区住民4,924人のうち、避難所入所者総数は、同日午後4時現在で1,560人を数えました。
以上が避難地区住民が避難指示により避難所等へ避難するまでの状況ですが、情報の正確な伝達は、災害下においては非常に難しいものであり、この方法であれば万全と言うものはありません。従って複数の手段を用いることにより、多くの地域住民に、より正確な情報の伝達が可能になると考えております。
当市では、企業の協力により同報系防災行政用無線を借り受けることができ、有珠・長和地区全世帯に戸別受信機を設置し、毎日13時、17時の2回火山情報などを放送しております。これは、北海道電気通信監理局のご尽力を頂き郵政省の許可を得て設置したものですが、日頃から有珠山の情報を市民と共有することにより、緊急時の冷静な行動を期待してのことであります。
 伊達市庁舎屋上から(H12.3.31) |
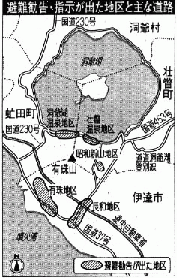 12.3.30 北海道新聞朝刊記事より |