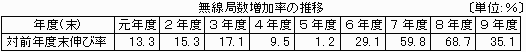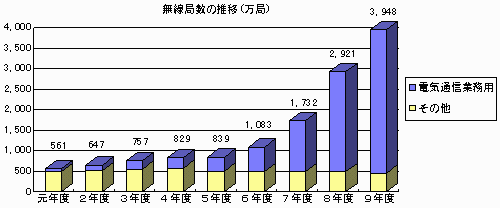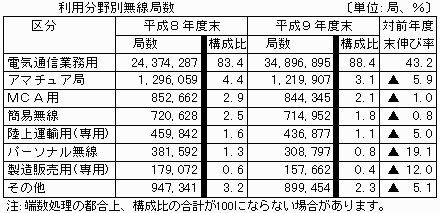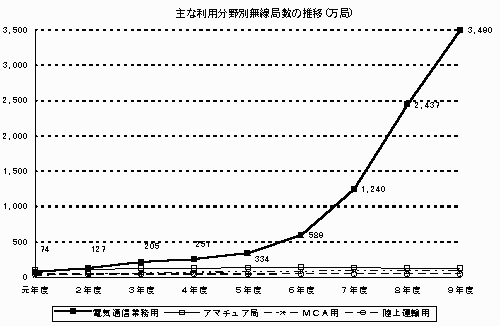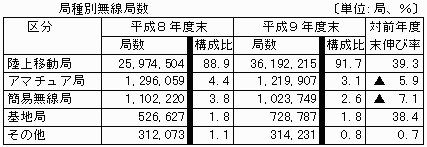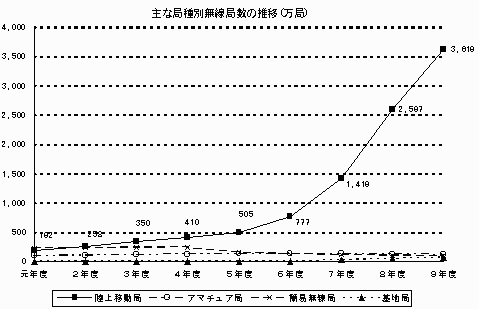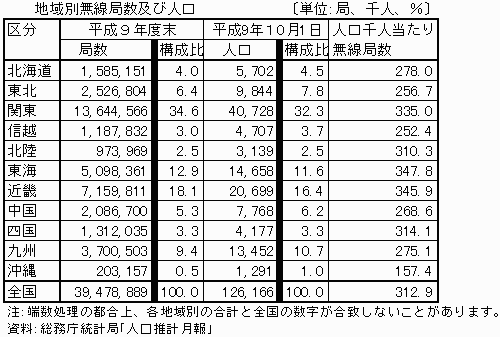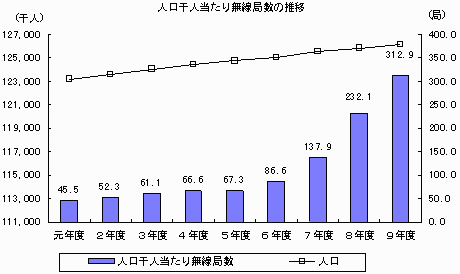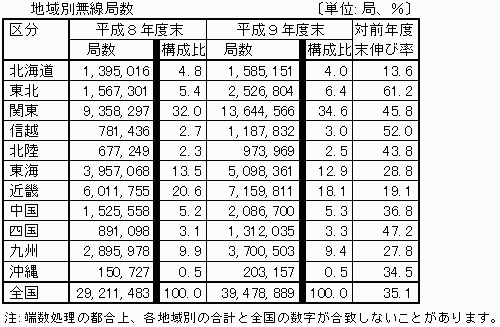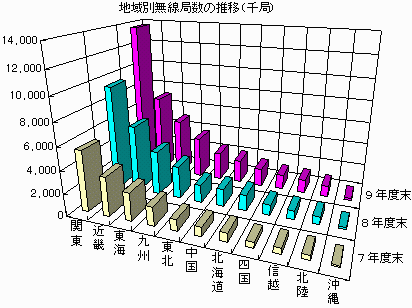発表日 : 5月28日(木)
タイトル : 5/28付:無線局数の状況(平成9年度末現在)
★★ 無線局数の状況(平成9年度末現在)
無線局数、約4千万局。この1年間で1千万局の増加。
〜携帯電話による電波利用が増加を続ける〜
|
郵政省は、この度、平成9年度(1997年度)末現在の無線局数(免許を要
する無線局に限る)について取りまとめました。
平成9年度(1997年度)末現在の無線局数は、39,478,889局
であり、前年度末に引き続き携帯電話の利用増加による陸上移動局(電気通信業
務用)の増加により、8年度末から10,267,406局増(35.1%
増)となっています。
また、平成7年度以降の3年間で約4倍に増加しました。
なお、PHS端末は免許を要しない無線局ですので計上されていません。
平成9年度末現在での無線局数の特徴としては、次のことが挙げられます。
1 携帯電話の利用急増により、電気通信業務用が43%の増加。
全体の約9割を占める
利用分野別では、携帯電話の利用急増により、電気通信業務用無線局が34,
896,895局と前年度末から43.2%増加し、他の利用分野での無線局
数が減少傾向(平均5.3%減少)にある中で、全体の約9割を占めるまでに
なりました。
2 人口千人当たりの無線局数は、全国平均で313局。地域別では、東
海、近畿、関東が上位。
人口千人当たりの無線局数は、平成8年度より22局増の約313局となっ
ています。地域別では、東海、近畿、関東の順で三大都市圏をかかえる地域が
上位を占めています。
3 対前年度末伸び率は、東北、信越が高い伸び。
対前年度末の地域別の無線局数伸び率は、他地域に比べて人口千人当たりの
無線局数の少ない東北、信越が、それぞれ61.2%増、52.0%増と、全
国平均35.1%に比べ高い伸びとなっています。
連絡先:通信政策局情報企画課
(担当:増沢専門職、松本統計企画係長)
電話 03−3504−4955
平成9年度末現在の無線局数は、3,948万局。前年度末比35.1%の増
加。
前年度に引き続き、1千万局を超える増加
|
平成9年度(1997年度)末現在の無線局数は、39,478,889局で
あり、前年度末に引き続き携帯電話の利用増加による陸上移動局(電気通信業務
用)の増加により、8年度末から10,267,406局増(35.1%増)と
なっています。
また、平成7年度以降の3年間で約4倍に増加しました。
なお、PHS端末は免許を要しない無線局となりますので計上されていません。
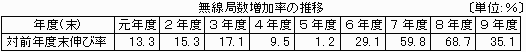
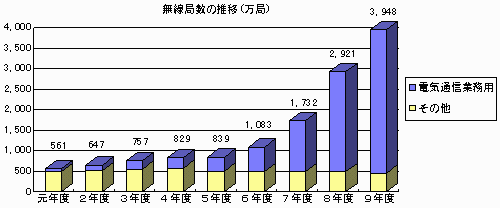
参考:無線局数が100万局を超えたのは昭和48年度(1971年度)、
500万局を超えたのは平成元年度(1989年度)、1,000万
局を超えたのは平成6年度(1994年度)です。
携帯電話の利用急増により、電気通信業務用が43%の増加。全体の約9割を
占める。
|
利用分野別の内訳は、局数の多い順に[1]電気通信業務用34,896,8
95局、[2]アマチュア局1,219,907局及び[3]MCA用844,
345局が上位を占め、次いで[4]簡易無線714,952局、[5]陸上運
輸用(専用)436,877局、[6]パーソナル無線308,797局となっ
ています。
特に、電気通信業務用は前年度末に比べ、10,522,608局増(43.
2%増)と携帯電話の利用急増により大きく増加しています。
逆に、電気通信業務用以外の利用分野では、全体で255,202局減(5.
3%減)となっています。
(参考):携帯電話の加入者数の伸び(平成9年3月末〜10年3月末)
1,065万加入の増加(平成10年3月末現在の加入数:
3,153万加入)
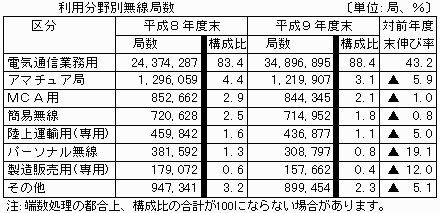
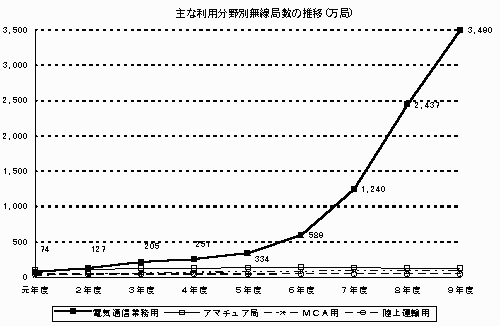
前年度に引き続き携帯電話の利用急増により陸上移動局が39.2%の増加。
また、携帯電話及びPHSのサービスエリア拡大等により基地局が38.4%
の増加。
|
局種別の内訳は、[1]陸上移動局36,192,215局と総無線局数の90
%を占め、次いで、[2]アマチュア局1,219,907局、[3]簡易無線局
1,023,749局となっています。
また、前年度末からの伸びでは、携帯電話の利用急増に伴い陸上移動局が10,
217,711局増(39.3%増)であり、基地局については、携帯電話及びP
HSのサービスエリア拡大等により、202,160局増(38.4%増)となっ
ています。
注1:携帯電話端末は、陸上移動局に含まれます。なお、PHS端末は免許を
要しない無線局となりますので計上されていません。
注2:携帯電話端末及びPHS端末と通信をするための無線局は基地局に含ま
れます。
注3:簡易無線局には、簡易無線とパーソナル無線が含まれています。
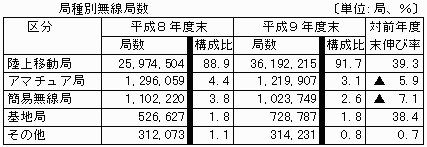
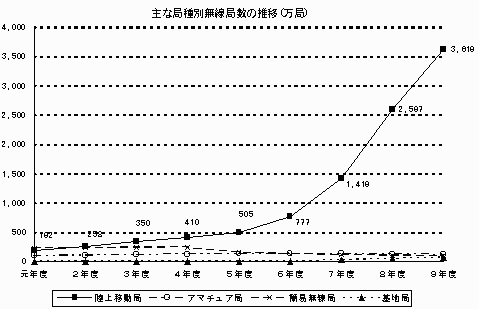
人口千人当たりの無線局数は、全国で313局、地域別では東海が約348局、
近畿が約346局であり、つづいて関東、四国の順で全国平均を上回る。
|
人口千人当たりの無線局数は、平成8年度より22局増の約313局となって
います。
地域別では、東海約348局、近畿約346局、関東約335局、四国約31
4局の順で全国平均を上回っており、三大都市圏をかかえる地域が上位を占めて
います。
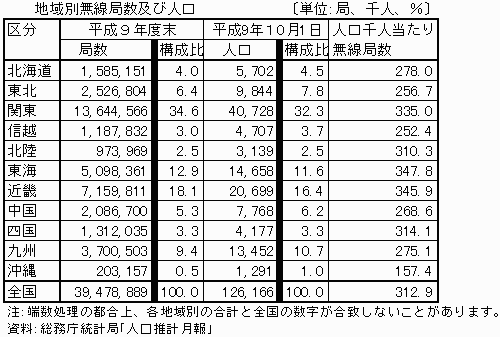
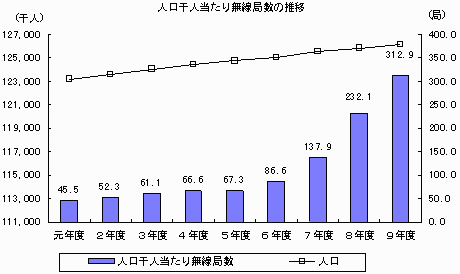
対前年度末の地域別無線局数の伸び率は、東北、信越が高くなっている。
|
対前年度末の地域別では、局数の多い順に[1]関東13,644,566局、
[2]近畿7,159,811局[3]東海5,098,361局であり、総無
線局数の65.6%となっています。
また、前年度末からの伸び率は、他地域に比べて人口千人当たりの無線局数の
少ない東北、信越がそれぞれ61.2%増、52.0%増と高く、次いで、四国、
関東、北陸、中国の順に全国平均を上回る伸び率となっています。
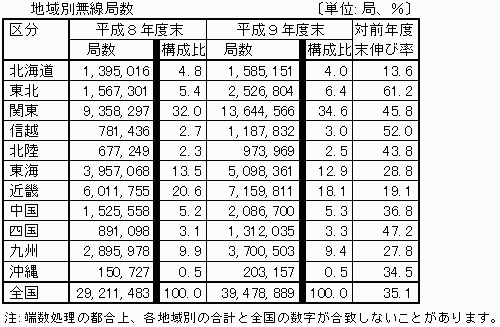
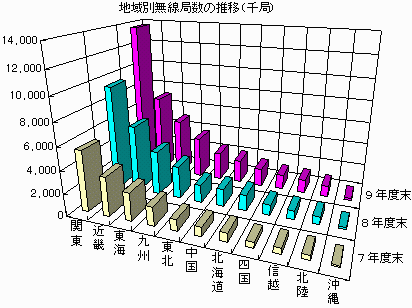
〜無線局数の取りまとめ方法について〜
1 免許を要しない無線局は、計上されていません。
現在、免許を要しない無線局には、以下のような無線局がありますが、これ
らの無線局は計上されていません。
○発射する電波が著しく微弱な無線局
○市民ラジオの無線局(CB無線)
○コードレス電話の無線局
○特定小電力無線局
○小電力セキュリティシステムの無線局
○小電力データ通信システムの無線局
○デジタルコードレス電話の無線局
○簡易型携帯電話の陸上移動局(PHS端末)
○有料道路自動料金収受システムの陸上移動局
2 包括免許制度により免許された無線局(特定無線局)については、現に開設
されている無線局数が計上されています。
平成9年10月1日より改正電波法の施行により、包括免許制度が始まりま
した。
この制度は、携帯電話端末等(携帯・自動車電話、MCA、N−STAR、
オムニトラックス、インマルサット等)の無線局について個別の無線局ごとに
免許を受けることなく、一つの免許により同一タイプの複数の無線局の開設を
可能とするものです。
このため、集計に当たっては、免許時に許可された指定無線局数(最大運用
局数)ではなく、毎月末現在の開設無線局数について免許人から届出のあった
無線局数により行っています。なお、別添集計表には参考として開設無線局数
(再掲)を提示しています。
無線局施設状況表(監理局別、局種別)はこちら
無線局施設状況表(用途別、局種別)はこちら