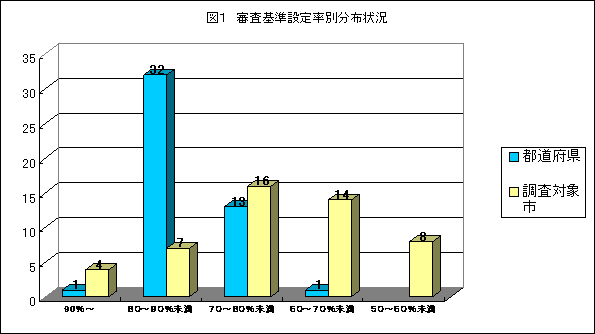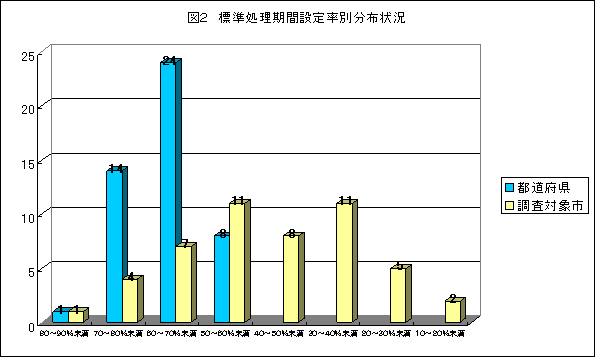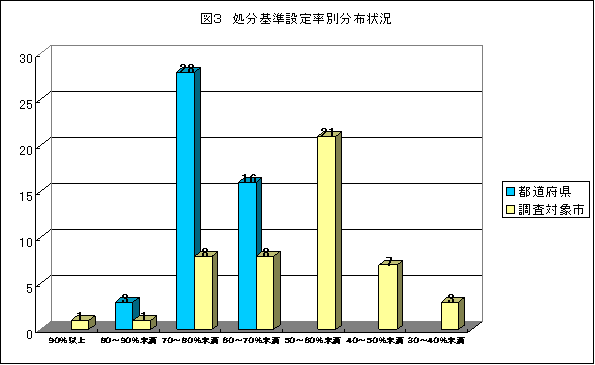| (2) |
処分基準が設定されていない処分
今回、処分基準が設定されていない処分(1団体当たりの平均値)は、都道府県で338種類、調査対象市で135種類みられ、その未設定理由の内訳を調査した結果は、表8のとおりであった。
未設定の理由として多く挙げられているものは、都道府県、調査対象市のいずれにおいても、1)「将来的に処分の対象が見込まれるものの、過去に処分実績がなく又は稀であって、あらかじめ処分基準を設定することが困難」又は2)「事案ごとの裁量部分が大きく、処分基準を設定することが困難」であり、この2つで全体の約9割以上を占めていた。
表8 処分基準未設定処分の未設定理由別内訳(1団体当たりの平均値)
| 未設定処分数(合計) |
都道府県 |
調査対象市 |
| 338(100) |
135(100) |
| 未設定理由 |
| 1) |
将来的に処分が見込まれるものの、過去に処分実績がなく又は稀であって、あらかじめ処分基準を設定することが困難 |
|
192(56.8) |
89(65.9) |
| 2) |
事案ごとの裁量が大きく、処分基準を設定することが困難 |
|
131(38.8) |
42(31.1) |
| 3) |
過去に処分実績があるものの、将来的に処分が見込めず、処分基準を設定する実益がない |
|
10(3.0) |
2(1.5) |
| 4) その他 |
5(1.5) |
2(1.5) |
| (注) |
( )内は、未設定処分種類数(合計)を100 とした場合の各理由の占める割合を示す指数である。 |
|
| (3) |
新たな処分基準の設定状況
前回調査時(平成12年3月31日)において、「将来的に処分の対象が見込まれるものの、過去に処分実績がなく又は稀であって、あらかじめ処分基準を設定することが困難」、「事案ごとの裁量部分が大きく、処分基準を設定することが困難」などの理由から処分基準が未設定となっていた処分(都道府県及び調査対象市1団体当たりの平均値)について、今回新たにを設定したものを調査したところ、都道府県では前回未設定だった326種類のうち、7種類(2.1パーセント)、調査対象市においては、未設定だった124種類のうち、4種類(3.2パーセント)について新たに設定している状況がみられた。
|
| (4) |
聴聞及び弁明の手続の実施状況
「行政庁は、不利益処分をしようとする場合には、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、意見陳述のための手続を執らなければならない。」(法第13条第1項)こととされている。
具体的には、許認可等の取消し、資格又は地位のはく奪など名あて人となるべき者に及ぼす不利益の程度が大きい不利益処分をしようとするときには、聴聞手続を執ることとし、それ以外の不利益処分をしようとするときには、弁明書、証拠書類等の提出による弁明の機会の付与の手続を執ることとしている。
今回、聴聞又は弁明の手続が執られた処分について、聴聞又は弁明手続のための実施通知が行われた件数を調査した結果は、表9のとおりであり、行政手続法の規定にのっとり、聴聞手続が都道府県において25,703件及び調査対象市において37
件、弁明手続が都道府県において126,132 件及び調査対象市において37,498 件実施されていた。このうち、当事者の聴聞期日への不出頭又は弁明書の未提出のまま終結されたものの割合は、聴聞で都道府県が23.3パーセント及び調査対象市が40.5パーセント、弁明で都道府県が63.2パーセント及び調査対象市が81.0パーセントを占めていた。
表9 聴聞手続又は弁明手続の実施状況(平成13年度)
| 区分 |
| 不利益処分の名あて人に対する手続の実施通知の件数 |
| (a) |
|
| 名あて人の聴聞不出頭又は弁明書未提出により手続を終結したものの件数 |
| (b) |
|
| 不出頭または未提出による終結の割合(%) |
| (b/a) |
|
| 聴聞相当処分 |
都道府県 |
25,703 |
5,987 |
23.3 |
| 調査対象市 |
37 |
15 |
40.5 |
| 弁明相当処分 |
都道府県 |
126,132 |
79,653 |
63.2 |
| 調査対象市 |
37,498 |
30,382 |
81.0 |
| (注) |
1 |
行政庁は、1)当事者が正当な理由なく聴聞の期日に出頭せず、かつ、陳述書又は証拠書類等を提出しない場合には、聴聞を終結することができることとされており(法第23条第1項)、また、2)弁明の機会の付与についても、弁明書の提出期限までに当事者から何ら応答がない場合には、弁明の機会を与え終えたことになると解される。 |
| |
2 |
実施通知件数、終結件数は、都道府県及び調査対象市とも合計数である。 |
|
| (5) |
聴聞・弁明手続が執られていない処分の種類数
行政庁が不利益処分をしようとする場合には、聴聞又は弁明の手続を執ることが原則であるが、例外的に当該処分の行われる個別具体の状況ないし処分の内容の特殊性により、聴聞又は弁明の手続を執ることを要しない場合がある。
今回、聴聞又は弁明の手続を執ることなく不利益処分を行ったものについて、理由別の処分の種類数を調査した結果は表10のとおりである。
聴聞又は弁明手続を省略した理由として最も多かったのは、「最終的に金額の多寡によって解決されるものであり、行政効率の観点から、事前に意見を述べる機会を与えることなく処分を行い、争いがある場合には事後的な処理に委ねることが適当である」とされる4)の理由に該当するものであった。
表10 聴聞・弁明手続が執られていない処分の理由別内訳(平成13年度)
| 理由別 |
処分の種類数 |
| 都道府県 |
調査対象市 |
| 1) 公益上、緊急に不利益処分をする必要があるため、聴聞又は弁明の手続を執ることができないとき |
81 |
16 |
| 2) 法令上必要とされる資格がなかったこと又は失われるに至ったことが判明した場合に必ずすることとされている不利益処分であって、その資格の不存在又は喪失の事実が裁判所の判決書又は決定書、一定の職に就いたことを証する当該任命権者の書類その他の客観的な資料により直接証明されたものをしようとするとき |
51 |
14 |
| 3) 施設若しくは設備の設置、維持若しくは管理又は物の製造、販売その他の取扱いについて遵守すべき事項が法令において技術的な基準をもって明確にされている場合において、専ら当該基準が充足されていないことを理由として当該基準に従うべきことを命ずる不利益処分であって、その不充足の事実が計測、実験その他客観的な認定方法によって確認されたものをしようとするとき |
48 |
11 |
| 4) 納付すべき金銭の額を確定し、一定の額の金銭の納付を命じ、又は金銭の給付決定の取消しその他の金銭の給付を制限する不利益処分をしようとするとき |
114 |
135 |
| 5) 当該不利益処分の性質上、それによって課される義務の内容が著しく軽微なものであるため名あて人となるべき者の意見をあらかじめ聴くことを要しないものとして政令で定める処分をするとき |
5 |
0 |
|
| (6) |
聴聞主宰者の指名方針
「聴聞は、行政庁が指名する職員その他政令で定める者が主宰する」(法第19条第1項)こととされている。また、「主宰者は、聴聞の審理において、関係人に参加許可を与え、審理を進行させて必要に応じ当事者等に陳述等を促し質問を発し、また、審理を終結させ、更には審理の記録を作成するといった聴聞の運営について必要な一切を司るもの」である。
今回、都道府県、調査対象市における聴聞主宰者の指名方針について調査した結果は、表11のとおりであった。
表11 都道府県、調査対象市における聴聞主宰者の指名方針の内訳(平成14年3月31日現在)
| 指名方針の内訳 |
都道府県 |
調査対象市 |
| 1) |
当該不利益処分を所管する担当部課の職員を主宰者として指名 |
|
20 |
9 |
| 2) |
当該不利益処分を所管する部局の担当部課が所属する部局の筆頭課等の職員を主宰者として指名 |
|
5 |
8 |
| 3) |
行政手続法担当課等の職員を全庁一律に主宰者として指名 |
|
1 |
2 |
| 4) |
統一的な方針を特に定めず、聴聞を必要とする事由が生じた段階でその都度適任者を指名 |
|
19 |
27 |
| 5) その他 |
3 |
4 |
| 計 |
48 |
50 |
| (注) |
1 |
各部局により指名方針が異なるため重複回答を行った団体が含まれている。 |
| |
2 |
実際に聴聞を必要とする事由が生じた際にこれらの内容と異なる形で指名が行われる場合があり得る。 |
|