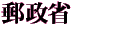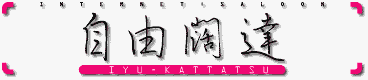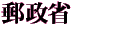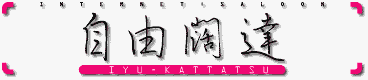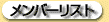サロンの中で寄せられたご要望なり、議論された主な論点、ご意見、及びそれに対する行政側の対応状況は次のとおりです。
(1)XDSL技術の早期実用化
インターネット・ユーザの中から、近年特に、既存のメタル回線上でメガビット級の高速アクセスを実現するためのXDSL技術の早期導入に対する要望が強いことが判明。これを受けて、本年3月に外部の専門家を集めた「ネットワークの高度化・多様化に関する懇談会」に「高速デジタル加入者線部会」を設置して検討を進め、6月に最終報告をとりまとめました。
そのポイントは、光ファイバーの全国整備までの「橋渡し」的な役割を果たすXDSL技術の導入は望ましいとした上で、来年春までに一定の技術評価を行うこととするものです。郵政省では、この提言を受けて、近く利用者や学識経験者等から成る実証実験評価委員会(仮称)を設置し、実証実験の実施状況をフォローしていく予定です。
(2)次世代インターネットの研究開発の推進
委員の皆様から、米国で昨年夏にクリントン大統領から発表された次世代インターネット開発計画のご紹介があり、安全・信頼性が高く、超高速で大容量伝送が可能な新しいインフラの研究開発に我が国としても積極的に貢献できる道があるのではないかとのご指摘がありました。
それらを踏まえ、郵政省として平成9年度予算として、インターネット上の電子マネーの通信実験など各種関連した要求内容を予算の編成過程で「次世代インターネットの研究開発」として一本化、その結果、初年度総額8.9億円の予算が認められました。このため、サイバービジネス協議会の協力を得て推進している既存の電子商取引に関する実証実験とあわせて、今後3年計画でサイバービジネスの一層の振興を図っていくこととしております。
(3)商用IXの事業化
最近になって、地域IXの設立や事業者による商用IX設立などNSPIXP以外の相互接続点の実用化の動きが表面化してきました。IXは、インターネットの効率的かつ安定的な相互接続に欠かせない、いわば「へそ」の役割を果たすものであり、今後各種IX相互の関係や役割分担、連携の確保が重要な課題になるとの認識が高まってきました。
こうした動きを受けて、郵政省では本年5月に「IX研究会」(座長:慶応大学村井先生)を設置して、検討を進めており、7月には報告書をとりまとめる予定でいます。
(4)インターネット上のハッカー・ウィルス対策の強化
他人のコンピュータ・ネットワークに侵入して、データの不正コピーや破壊を行う、いわゆるハッカーやウィルスに対する被害が増大している現状のご説明がありました。こうした状況を受けて、郵政省では昨年11月に、「情報通信ネットワークの安全性・信頼性に関する研究会」を設置して、対応策を検討してきましたが、本年6月に報告書をとりまとめました。
この中で、セキュリティに関する相談・窓口体制の強化やネットワークの安全対策の推奨基準である「情報通信ネットワーク安全・信頼性基準」(郵政大臣告示)をインターネットの普及・発展に見合う内容となるよう改正すべきことなどが提言されました。
(5)インターネット上の違法又は有害情報への対応や個人情報保護について
インターネット上の有害情報の発信・流通については、最近になって米国通信品位法に関する最高裁の違憲判決が出されるなど国際的にも大きな社会問題となりつつあり、特に青少年に悪影響を及ぼすことが懸念されています。サロンでも、こうした問題意識や懸念が何度か話題となりました。
第二種電気通信事業者の団体である社団法人テレコムサービス協会においては、こうした状況を受けて、「電気通信事業における公然性を有する通信サービスに関するガイドライン」の案を策定・公開し、インターネット上で意見を募集しています。
また、有害情報の取扱いに関する技術的な解決策として、郵政省ではコンテンツの格付け/選別を支援するフィルタリング技術の研究開発を横浜市、文部省と連携しつつ推進していく予定でいます。
さらに、サイバービジネス協議会では、「サイバービジネスに係る個人情報の保護に関するガイドライン」をとりまとめ、インターネット上で公開、意見募集中であり、郵政省としては、これら一連の民間レベルの自主的な活動を支援していきたいと考えております。
以 上
|