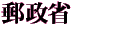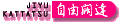| Q | 日米間のインターネット回線容量が600Mbpsとのことだが、その中でKDDが使用している容量は。 |
| A | 100Mbps程度。その他にIIJが100Mbps。しかし600Mbpsの容量一杯にデータが流れているわけでなく、若干余裕がある。
|
| Q | 光海底ケーブルの大容量化が進むと、容量あたりのコストが下がるのか。 |
| A | そう。容量が4倍になっても、コストは1.5倍に過ぎないなど、かなり下がってきている。
|
| Q | 国際インターネット接続におけるコスト負担の原則は。 |
| A | 米国への接続は、全額接続する国側の負担だが、米国以外の国の間では半々に負担する。先述のアジアバックボーンでは、アジア内でのトラフィックの中継を当初低速の間は精算なしで行う考え。
|
| Q | 国際的な通信量を見ると、インターネットが国際電話を上回っているのか。 |
| A | 日米間の場合は、昨年12月にインターネット用の容量と電話用の容量が双方400Mbpsで並んだ。実トラフィック量としては本年中には前者の方が上回る見込み。
|
| Q | 国際電話のトラフィックは、電子メールへの需要移行等により減少しているのではないか。 |
| A | 減少はしていないものの確かに伸びていない。これはコールバックの影響もあると思われる。ファックスは電子メールにとって替わられると言われているが、ファックスに対する一定の需要は残るものと考えている。
|
| ○ | IXP(インターネット・エクスチェンジ・ポイント)は、ISPが相互に接続する接続ポイント。 |
| ○ | ISPが、NSP(ネットワーク・サービス・プロバイダ)経由でIXPに接続するケースは、日本には余りみられない。 |
| ○ | IXPの技術的構成では、ノンATMベースとATMベースとがあるが、その比率は、米国では半々、その他の国では前者の方が多い(日本のNSP/IXP IIの構成は前者)。 |
| ○ | 米国のメジャーなIXとしては、バージニア州レストンにあるMAE(Metropolitan Area Exchange)−EAST(750Mbpsのトラフィックを交換)やPB−NAP等がある。NAP(ネットワーク・アクセス・ポイント)は、パックベル等の通信事業者によって運営されていることが多いが、ATMベースが多いNAPは最近までパフォーマンスが悪く、余りうまく動いていなかった。 |
| ○ | 現在IXで用いられているのはスイッチベースの技術だが、これの問題は、一カ所でつまると全体のパフォーマンスが落ちる点。このため、一カ所に集中して接続するのを避ける傾向がある。 |
| ○ | ここに、NSPの必要性がある。NSPは、ATMサービス等の高速の公衆網によって、IX機能を面的に提供するサービスプロバイダである。 |
| ○ | 97年1月現在で5700万人と推定されるインターネット利用者のうち、75%が専用線アクセスのビジネスユースと見られるが、こうしたビジネスユーザが望むインターネットは現在のインターネットとは異なるものであるとの見解もある。 |
| ○ | 現在25%を占めるダイヤルアップユーザが、ADSLのような比較的高速のアクセスに移行した場合に、バックボーンはどうなるかとの懸念もあるが、こうしたユーザは全体のわずか25%にしか過ぎない(のであまり問題ではない)。 |
| Q | IXPは元々接続ポイントとして認識されていたが、面的展開の必要性もあるということか。米国ではそうでも、日本では難しい議論と思われるが。 |
| A | 日本の場合、根本的に東京に一極集中しているので、面的広がりの議論をしても意味をなさないかも知れない。
|
| Q | インターネットが多層化して、イントラネット専用等のプレミアムなネットワークができるということか。 |
| A | 用途にあった丁度いい品質のネットワークが必要。今まで通信事業者(キャリア)が提供してきた専用線のネットワークはオーバースペック。IPを通すのであれば、それほど高品質でなくても問題ない。キャリアが責任分界点にDSUを置いて、きちっと監視するというのでは、安いサービスにならない。
|
| Q | ATMネットワークができてくれば、面的なIXPが主流となり、点としてのIXPの役目は終わるのか。 |
| A | 面的なものと点的なものが、両方併存していくものと思われる。
|
| Q | 米国において、どのような事業者がNSPサービスを提供しているのか。 |
| A | 主に、日本でいう2種事業者がフレームリレーベースで提供しているが、1種事業者に相当する設備ベースキャリアも若干ある。
|
| Q | 米国の場合、IXは面的に広がっていくのか、それともIXをさらに集中化していく方向にあるのか。 |
| A | 米国では、UUNet/MCI/スプリントという3大バックボーンネットワークに集約されてしまっている。キャリアがISPをどんどん買収して、大型化していくというのが今の流れではないか。また、大手のコンテント・プロバイダは上記の3大バックボーンに接続している。日本では、それほど系列化は進んでいない。
|
| Q | 日本のような小さな国で、NSPビジネスが成立するのかは疑問。米国ではビジネスとして成り立っているのか。 |
| A | 米国でもIXPは余り儲かっていない様子。IXPだけでのビジネスというのはありえないのではないか。付加価値を付けていく必要がある。
|
| ○ | インターネットのドメインネームの中では、".jp"の数が非常に伸びてきており、注目度も高く責任も重くなってきている。 |
| ○ | 日本の提案により、現在インターネットでファックスを送るためのプロトコルの標準化を行っているが、これは、ファックスを電子メールとして運ぶようなものである。全世界のファックスの総量を試算すると192Mbps程度であり、インターネット上で十分伝送できるものと思われ、インターネット電話も可能であろう。 |
| ○ | ビジネスモデルはインターネットの一番の課題であり、現在インターネット(に関わるビジネス)で儲けている人はほとんどいない。 |
| ○ | 現在のインターネットの主な課題として、まずJPNICの社団法人化等の識別子の問題がある。これは社会とインターネットの関係がより密接になってきたためクローズアップされてきている。 |
| ○ | 次にインターネット上の実効スループットが落ちてきているという問題がある。これは、現在のインターネットが採用している混雑回避システムの前提が変わってきている(分散ネットワークにおける集中化)ためである。 |
| ○ | xDSL、PHSデータ通信、衛星通信、ATMといった従来型の通信で一般的なのはトップダウンのアプローチだが、インターネットの使命は「デジタル情報がどこにでも流れる」ことであり、ボトムアップ・アプローチが採られている。 |
| ○ | インターネットがこれだけ普及した理由は、インターネットに用いられているプロトコルであるTCPが、輻輳制御とフロー制御のアルゴリズムを備えているからである。これにより、ネットワークが混んできたと判断すれば様子を見ながらデータを少しずつ送出するという自然の抑制効果が生まれる。これを「スロースタート」のアルゴリズムという。 |
| ○ | ただ、インターネットは均一なネットワークを前提としているため、衛星通信や携帯電話を用いた場合には伝送遅延や回線の瞬断によって上記のアルゴリズムが働いてしまい、回線の利用効率が低下するという問題が起こる。 |
| ○ | 衛星通信は同報型通信に適しているが、片方向の通信であって双方向を前提とするインターネットとの齟齬が生じるため、これを吸収するためのメカニズムが必要。また、光ファイバー、銅線、衛星通信、携帯電話等の媒体が混在するネットワークがスムースに稼働するシステムが重要。 |
| ○ | インターネットソサエティ(IS)の今後の課題としては、現在ワシントンD.C.にある活動の中心を、他の国際機関が本拠としているジュネーブに移すことや、2000年にアジアで開催するコンファレンス(INet2000)を東京に誘致することなどがある。 |
| ○ | 次世代のIPであるIPv6は、全人類が同時に使用できるようなアドレス空間を持ち、さらに上述したリアルタイム性、セキュリティ、モビリティ等の問題を解決する可能性を持っている。我が国でもIPv6の開発に国の予算等の支援を行うべきではないか。 |
| ○ | 従来どおりの、コンセンサスを得た後にルール作りをし、実施する、というプロセスでは遅すぎる。インターネットの世界では、まず実施ありきで、これに対してコントリビューションを行い、必要であればルールを作るという手法である。 |
| ・ | インターネットはやはり米国から来た文化で、日本独自のものとしてはインターネットファックス位と思われるが。 |
| ・ | 確かにインターネット利用者の60%は米国にいると言われるとおり、米国は大きなマーケットではあるが、日本発の技術かそれとも米国発かというのは大した問題ではないが、日本発が少ないのは、日本企業には新たな製品・技術を作る力はあるものの、戦略上の問題で製品開発のゴーサインが出ていないためではないか。また、開発の出足が遅く、大胆さも足りないように思われる。
|
| ・ | 最近マイクロソフトがウェブTVの会社を買収したが、そのインパクトは。 |
| ・ | そもそもテレビとパソコンとを区別する必要はないのでは。 |
| ・ | やはり、テレビとパソコンの間には谷があって、技術的な谷は越えているがマーケティング等の谷は以前存在する。ビジネス向けの大型機と一般消費者向けの製品との両方を手がけて成功した例はない。 |
| ・ | いまやパソコンは家電店でも販売しており、その意味では一般消費者向け製品といえるだろう。
|
| ・ | マイクロソフトの凄いところは、OSから始めてアプリケーションに行き、今やメディア/コンテントを押さえにかかっているところ。 |
| ・ | コンテントとの関係では、米国の映画産業等も押さえているソニーの方が凄いと言えるだろう。 |