
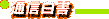


 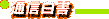 |
1 国内情報通信の動向(第1図参照)
(1) 電気通信サービス
(電話サービス)
NTTの加入電話契約数は、8年9月末現在6,156万契約(対前年同期比1.4%増)となっている。長距離系新第一種電気通信事業者3社(第二電電(株)、日本テレコム(株)及び日本高速通信(株))の市外電話サービス契約数(ID登録数の3社単純集計)は、8年9月末現在、3,400万契約(対前年同期比10.9%増)となっている。
(移動通信サービス)
携帯・自動車電話サービスの総契約数(NTTDoCoMo等地域別9社と新第一種電気通信事業者17社の合計)は、8年9月末現在1,531万契約(9年3月末現在の速報値2,088万契約)であり、対前年同期比129.5%増と加入電話と比べて大幅に伸びている(第2図参照)。
このような携帯・自動車電話サービスの著しい成長の背景としては、NTTからの移動体通信部門の分離・分割による公正有効な競争環境の整備や、活発な新規参入による1地域3社又は4社体制という世界的に見て最も競争の進んだ市場の実現、端末売り切り制の導入、デジタル方式のサービス開始や端末の小型化、軽量化等の技術革新といった要因により、結果として急速な料金の低廉化、多様化が進んだことが挙げられる。
PHSサービスは、7年7月の首都圏、札幌市(北海道)でのサービス開始以来、エヌ・ティ・ティパーソナル通信網グループ9社、ディーディーアイポケット電話グループ9社、アステルグループ10社が順次サービスを開始し、1地域3社体制の競争市場となっている。
PHSサービスの総契約数は、8年9月末現在396万契約(9年3月末現在の速報値603万契約)であり、対前年同期比2,889%増と、サービス開始後の1年間で爆発的に増加している。
無線呼出しサービスの総契約数(NTTDoCoMo等地域別9社と新第一種電気通信事業者31社の合計)は、8年9月末現在1,063万契約であり、伸び率は前年度に比べ鈍化(14.1ポイント減)しており、対前年同期比2.9%増にとどまっている。
(ISDNサービス)
インターネットやパソコン通信の利用の拡大に伴い、一般家庭においても、ISDNサービスが導入されてきている。ISDNサービスの回線数は、8年9月末現在、基本インターフェースが74万4,055回線(対前年同期比82.4%増)、一次群速度インターフェースが1万3,800回線(同76.6%増)である。
(専用サービス)
高速デジタル伝送サービスの総回線数(NTTと長距離系及び地域系新第一種電気通信事業者の合計15社の総数)は、8年9月末現在、9万7,465回線(対前年同期比87.8%増)と高い伸びを示している。このうち新事業者の回線数は1万7,467回線(同62.6%増)で、総回線数に占めるシェアは17.9%(同2.8ポイント減)である。
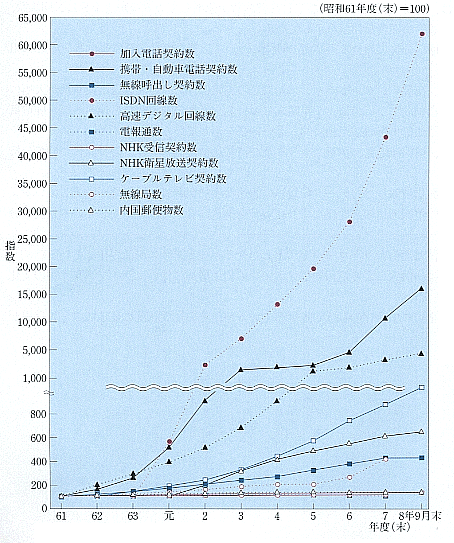
|
・加入電話契約数 46,771,699契約(61年度末) →61,342,737契約(8年9月末) ・携帯・自動車電話契約数 95,131契約(61年度末) →15,306,191契約(8年9月末) ・無線呼出し契約数 2,487,946契約(61年度末) →10,631,301契約(8年9月末) ・ISDN回線数 1,198回線(63年度末) →744,055回線(8年9月末) ・高速デジタル回線数 2,225回線(61年度末) →97,465回線(8年9月末) ・電報通数 40,050千通(61年度) →41,385千通(7年度) ・NHK受信契約数 31,954,635契約(61年度末) →35,377,295契約(7年度末) ・NHK衛星放送契約数 1,207千契約(元年度末) →7,813千契約(8年9月末) ・ケーブルテレビ契約数 437,344契約(61年度末) →4,034,104契約(8年9月末) ・無線局数 4,155,554局(61年度末) →17,315,536局(7年度末) ・内国郵便物数 18,033,930千通(61年度) →25,357,701千通(8年度) |
| 郵政省資料により作成 | ||
| (注) | 1 | ISDN回線数は昭和63年度末、NHK衛生放送契約数は元年度末を100とした。 |
| 2 | ISDN回線は基本インターフェースの回線数である。 | |
| 3 | ケーブルテレビは、自主放送を行うものを対象とする。 | |
| (単位:指数) |
| 年度(末) | 61 | 62 | 63 | 元 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8.9 |
| 加入電話契約数 | 100.0 | 103.5 | 107.6 | 112.1 | 116.6 | 120.3 | 123.3 | 125.8 | 128.1 | 130.0 | 131.2 |
| 携帯・自動車電話契約数 | 100.0 | 158.5 | 255.3 | 514.6 | 912.5 | 1448.6 | 1800.2 | 2240.5 | 4553.1 | 10726.3 | 16089.6 |
| 無線呼出し契約数 | 100.0 | 118.7 | 141.5 | 170.7 | 204.3 | 237.6 | 268.8 | 324.1 | 375.9 | 426.5 | 427.3 |
| ISDN回線数 | − | − | 100.0 | 563.8 | 2279.9 | 7023.3 | 13089.4 | 19598.2 | 28143.1 | 43392.8 | 62108.1 |
| 高速デジタル回線数 | 100.0 | 198.1 | 290.1 | 387.8 | 511.2 | 683.0 | 905.5 | 1188.2 | 1795.6 | 3196.0 | 4380.4 |
| 電報通数 | 100.0 | 102.5 | 103.5 | 108.3 | 111.1 | 117.3 | 116.7 | 112.4 | 108.1 | 103.3 | − |
| NHK受信契約数 | 100.0 | 101.4 | 102.8 | 103.9 | 105.0 | 106.2 | 107.5 | 108.6 | 109.6 | 110.7 | − |
| NHK衛生放送契約数 | − | − | − | 100.0 | 194.8 | 315.7 | 414.3 | 484.7 | 545.2 | 611.0 | 647.3 |
| ケーブルテレビ契約数 | 100.0 | 100.6 | 140.4 | 184.7 | 233.0 | 317.0 | 427.8 | 553.9 | 718.7 | 831.7 | 922.4 |
| 無線局数 | 100.0 | 107.8 | 119.2 | 135.0 | 155.7 | 182.3 | 199.6 | 201.9 | 260.7 | 416.7 | − |
| 内国郵便物数 | 100.0 | 107.2 | 112.1 | 118.5 | 125.8 | 132.1 | 134.5 | 135.0 | 132.6 | 136.8 | 140.6 |
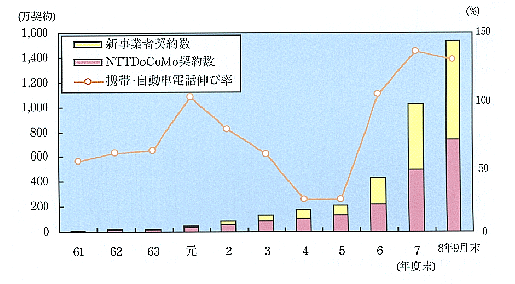
| NTT、NTTDoCoMo、新事業者資料により作成 (注)NTTDoCoMo契約数の3年度以前はNTTの数値 |
| (単位:万契約、%) |
| 年度(末) | 61 | 62 | 63 | 元 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8.9 |
| NTTDoCoMoの契約数 | 9.5 | 15.1 | 23.9 | 37.8 | 54.9 | 84.6 | 102.7 | 132.2 | 220.6 | 493.9 | 739.9 |
| 新事業者の契約数 | − | − | 0.4 | 11.1 | 31.9 | 53.2 | 68.5 | 80.9 | 212.5 | 526.5 | 790.7 |
| 携帯・自動車電話 契約数の伸び率 | 53.2 | 58.9 | 60.9 | 101.2 | 77.5 | 58.8 | 24.2 | 24.5 | 103.2 | 135.6 | 129.5 |
(衛星放送)
BS放送の8年12月末現在の受信契約数は、NHKが約797万1千契約(対前年同期比11.5%増)、JSBが約224万9千契約(同13.8%増)、SDABが約11万3千契約(同11.9%増)となっており、BS放送が社会生活に着実に普及してきていることがうかがえる。
CSアナログ放送の8年12月末現在の受信契約数は、テレビジョン放送では加入者約14万9千世帯の63万1千契約(対前年同期比66.5%増)、PCM音声放送では約4万3千契約(同22.9%増)となっている。
CSデジタル放送は、映像・音声等の情報を、デジタル信号の形態で伝送することを可能としたものである。8年3月に放送普及基本計画等を変更し、8年6月、衛星デジタル多チャンネル放送の試験放送が、通信衛星JCSAT−3を使用して開始され、8年10月には本放送が開始されている。受信契約数を見ると、8年9月に2万件だった受信契約数は、8年12月現在約10万2千件(仮契約件数を含む。)に達している。
(ケーブルテレビ)
ケーブルテレビのうち、自主放送を行うものについてその推移を見ると、8年9月末現在において業務開始施設数は862施設(7年度末比3.9%増)となっている。また、受信契約数については、8年9月現在約404万契約(7年度末比11.0%増)となり、堅調な伸びを示している。
2 国際情報通信の動向(第3図参照)
(1) 電気通信サービス
(国際電話サービス)
7年度における国際電話サービスの発着信合計時間数(KDD、ITJ及びIDCの合計)は、29億5,210万分(対前年度比10.8%増)となっている。
取扱地域別に全体に占める割合を見ると、発着信合計時間数では、6年度に引き続き米国が全体の30.0%(対前年度比1.4ポイント増)と最も大きな割合を占めている。以下、アジアNIEs、ASEAN諸国等が上位を占め、それぞれの割合も6年度とほぼ同様となっているが、特に中国(同0.6ポイント増)及びタイ(同0.1ポイント増)については前年度に比べシェアが伸びている。このうち、国際ダイヤル通話サービスの発信時間数についてその対前年度伸び率を見ると、7年度の対前年度伸び率の上位10位までの地域について、2年度から7年度までの順位の推移では、これまで上位に入ったことのなかったヴィエトナムが1位となっている。
(国際専用回線サービス)
国際専用回線サービスの7年度末総提供回線数(KDD、ITJ及びIDCの合計)は、1,691回線(対前年度末比2.9%増)となっている。これを品目別に見ると、音声級回線は昭和62年をピークに、電信級回線も昭和56年をピークに、引き続き減少傾向となっているのに対し、中・高速符号伝送用回線は1,317回線(同14.8%増)と前年に引き続き増加し、総提供回線数に占める割合は77.9%(対前年度比8.1ポイント増)で増加している。このように、国際専用回線サービスにおいては、近年、大容量回線への需要のシフトが急速に進んでいることが分かる。
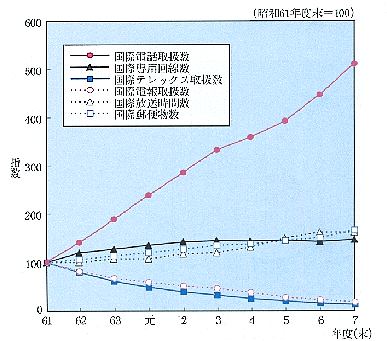
|
・国際電話取扱数 1341.1百万回(61年度) →685.2百万回(7年度) ・国際専用回線数 1,149回線(61年度末) →1,691回線(7年度末) ・国際テレックス取扱数 4,379万回(61年度) →583万回(7年度) ・国際電報取扱数 120.0万通(61年度) →21.7万通(7年度) ・国際放送時間数 40時間(61年度) →65時間(7年度) ・国際郵便物数 242.5百万通(61年度) →404.0百万通(7年度) |
| 郵政省の資料により作成 |
| (単位:指数) |
| 年度(末) | 61 | 62 | 63 | 元 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 国際電話取扱数 | 100.0 | 140.4 | 188.6 | 238.3 | 285.3 | 332.1 | 359.0 | 392.6 | 447.0 | 510.9 |
| 国際専用回線数 | 100.0 | 119.7 | 127.2 | 135.2 | 142.0 | 144.8 | 144.0 | 145.9 | 143.1 | 147.2 |
| 国際テレックス取扱数 | 100.0 | 79.3 | 60.7 | 48.7 | 39.3 | 32.5 | 25.4 | 20.5 | 16.1 | 13.3 |
| 国際電報取扱数 | 100.0 | 80.8 | 66.7 | 58.3 | 50.8 | 45.8 | 37.5 | 27.5 | 22.5 | 18.1 |
| 国際放送時間数 | 100.0 | 100.0 | 107.5 | 107.5 | 117.5 | 120.0 | 131.3 | 150.0 | 162.5 | 162.5 |
| 国際郵便物数 | 100.0 | 106.3 | 113.7 | 120.2 | 127.2 | 135.1 | 138.0 | 145.0 | 150.9 | 166.6 |
(インマルサットミニMサービスの提供の開始)
通信方式及び利用可能なサービスが異なる、インマルサットA、B、C、Mサービスシステムに加え、インマルサットミニMサービスが、8年10月、KDDにより提供が開始された。本サービスでは、五つのサービスシステムの中で最小・最軽量のノートブック型パソコン大に縮小された可搬型地球局を用い、デジタル方式により音声、ファクシミリ、データ通信が提供されている。
(2) 放送サービス
NHKによる短波国際放送の8年度の放送時間を見ると、全世界に向け日本語と英語で放送する一般向け放送は、1日当たり延べ32時間で、特定地域に向けその地域で使用されている言語を用いて放送する地域向け放送は、21言語で、1日当たり放送時間は延べ33時間であった。
3 電波利用の動向
7年度末現在の無線局数は、約1,732万局(前年度比59.8%増)である。7年度の無線局数の増加は、6年度と同様、携帯・自動車電話加入局の大幅な増加(前年度比135.6%増)によるものである。
7年度末現在の利用分野別無線局数は、移動通信用が88.7%であり、以下、アマチュア無線7.8%、パーソナル無線2.7%、固定局、放送局、実験局、レーダー等が0.8%となっている。移動通信用のうち電気通信事業用の利用が最も多く(全体に対して71.5%)、そのうち陸上移動局の携帯・自動車電話加入局が占める割合は、全体の58.9%である。
4 通信料金の動向
(国内電気通信料金)
国内電気通信の価格の推移について、「物価指数月報」(日本銀行)における企業向けサービス価格指数により概観すると、8年10月〜12月平均においては、総平均は101.8であり1.8ポイント上昇しているのに対して、国内電気通信の指数は86.9であり、13.1ポイント低下している。特に、携帯・自動車電話(8年10月〜12月平均の指数57.3)、専用回線(同72.7)の指数が大きく低下している(第4図参照)。
8年度においては、携帯・自動車電話サービスの分野で基本料金・通話料金の大幅な値下げが実施され、加入料については廃止された。また、公−専−公接続の解禁に伴い、公衆網と専用線の接続付加料の大幅な値下げが実施された。
(国際電気通信料金)
国際電気通信の価格の推移について、国内電気通信料金と同様に概観すると、8年10月〜12月平均においては、国際電気通信の指数は82.6であり、17.4ポイント低下している。特に、国際電話(8年10月〜12月平均の指数80.5)の指数が大きく低下している(第4図参照)。
8年度においては、国際電話ダイヤル通話サービスの値下げが行われたほか、国際ISDNサービス、航空衛星通信サービスにおいては値下げとともに料金の簡素化も併せて実施されている。
| (1) 国内電気通信 |
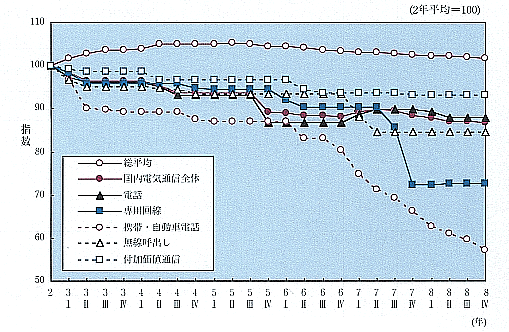
| 「物価指数月報」(日本銀行)により作成 | |
| (注) | 図中のI、II、III、IVは暦年四半期 |
| (2年平均=100) |
| 期 | 2 | 3I | 3II | 3III | 3IV | 4I | 4II | 4III | 4IV | 5I | 5II | 5III | 5IV |
| 総平均 | 100 | 101.6 | 102.9 | 103.6 | 103.7 | 103.9 | 105.0 | 105.0 | 105.0 | 104.9 | 105.4 | 105.1 | 104.6 |
| 国内電気通信全体 | 100 | 98.5 | 96.5 | 96.5 | 96.5 | 96.4 | 95.3 | 93.8 | 93.7 | 93.7 | 93.7 | 93.7 | 89.3 |
| 電話 | 100 | 97.4 | 96.3 | 96.3 | 96.3 | 96.3 | 95.1 | 93.0 | 93.0 | 93.0 | 93.0 | 93.0 | 86.9 |
| 専用回線 | 100 | 98.4 | 96.0 | 96.0 | 96.0 | 96.0 | 96.0 | 96.0 | 94.7 | 94.6 | 94.6 | 94.6 | 94.6 |
| 携帯・自動車電話 | 100 | 96.7 | 90.1 | 89.8 | 89.2 | 89.2 | 89.2 | 89.2 | 89.2 | 87.6 | 87.1 | 87.1 | 87.1 |
| 無線呼出し | 100 | 96.6 | 95.2 | 95.2 | 95.2 | 95.2 | 94.9 | 94.4 | 93.5 | 93.5 | 93.5 | 93.5 | 93.5 |
| 付加価値通信 | 100 | 99.3 | 98.8 | 98.8 | 98.8 | 98.8 | 96.8 | 96.8 | 96.8 | 96.8 | 96.8 | 96.8 | 96.8 |
| 期 | 6I | 6II | 6III | 6IV | 7I | 7II | 7III | 7IV | 8I | 8II | 8III | 8IV |
| 総平均 | 104.6 | 104.3 | 103.7 | 103.3 | 103.1 | 103.0 | 102.8 | 102.4 | 102.2 | 102.2 | 102.2 | 101.8 |
| 国内電気通信全体 | 89.0 | 88.5 | 88.3 | 88.2 | 89.3 | 89.8 | 89.5 | 88.4 | 87.9 | 87.0 | 87.0 | 86.9 |
| 電話 | 86.7 | 86.7 | 86.7 | 86.7 | 88.8 | 89.8 | 89.8 | 89.8 | 89.2 | 88.0 | 88.0 | 88.0 |
| 専用回線 | 92.1 | 90.4 | 90.4 | 90.4 | 90.4 | 90.4 | 85.8 | 72.4 | 72.4 | 72.7 | 72.7 | 72.7 |
| 携帯・自動車電話 | 87.1 | 83.2 | 83.2 | 80.4 | 74.8 | 71.3 | 69.3 | 66.2 | 62.8 | 61.0 | 59.0 | 57.3 |
| 無線呼出し | 93.5 | 93.5 | 93.5 | 93.5 | 88.2 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 |
| 付加価値通信 | 96.7 | 94.6 | 93.7 | 93.7 | 93.7 | 93.7 | 93.7 | 93.2 | 93.2 | 93.2 | 93.2 | 93.2 |
| (2) 国際電気通信 |
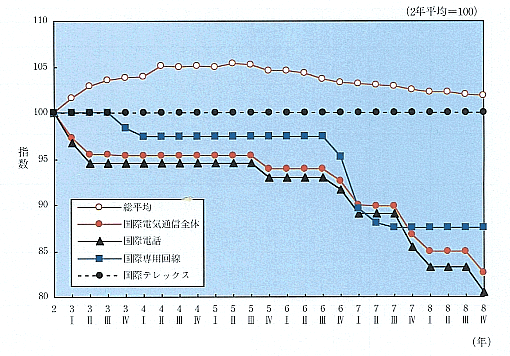
| 「物価指数月報」(日本銀行)により作成 (注) 図中のI、II、III、IVは暦年四半期 |
| (2年平均=100) |
| 期 | 2 | 3I | 3II | 3III | 3IV | 4I | 4II | 4III | 4IV | 5I | 5II | 5III | 5IV |
| 総平均 | 100.0 | 101.6 | 102.9 | 103.6 | 103.7 | 103.9 | 105.0 | 105.0 | 105.0 | 104.9 | 105.4 | 105.1 | 104.6 |
| 国際電気通信 | 100.0 | 97.3 | 95.5 | 95.5 | 95.4 | 95.3 | 95.3 | 95.3 | 95.3 | 95.3 | 95.3 | 95.3 | 93.9 |
| 国際電話 | 100.0 | 96.7 | 94.6 | 94.6 | 94.6 | 94.6 | 94.6 | 94.6 | 94.6 | 94.6 | 94.6 | 94.6 | 93.0 |
| 国際専用回線 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 98.3 | 97.4 | 97.4 | 97.4 | 97.4 | 97.4 | 97.4 | 97.4 | 97.4 |
| 国際テレックス | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 期 | 6I | 6II | 6III | 6IV | 7I | 7II | 7III | 7IV | 8I | 8II | 8III | 8IV |
| 総平均 | 104.6 | 104.3 | 103.7 | 103.3 | 103.1 | 103.0 | 102.8 | 102.4 | 102.2 | 102.2 | 102.2 | 101.8 |
| 国際電気通信 | 93.9 | 93.9 | 93.9 | 92.6 | 90.0 | 89.9 | 89.9 | 86.8 | 84.9 | 84.9 | 84.9 | 82.6 |
| 国際電話 | 93.0 | 93.0 | 93.0 | 91.7 | 89.1 | 89.1 | 89.1 | 85.4 | 83.2 | 83.2 | 83.2 | 80.5 |
| 国際専用回線 | 97.4 | 97.4 | 97.4 | 95.1 | 89.7 | 88.1 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 |
| 国際テレックス | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
5 インターネット、パソコン通信サービスの動向
(1) インターネットの普及状況
インターネットに接続されるホストコンピュータ数は、米Network Wizards社の公表によると、1997年1月現在、全世界で約1,615万台(対前年比70.5%増)であり、我が国は約73万台となっている(第5図参照)。
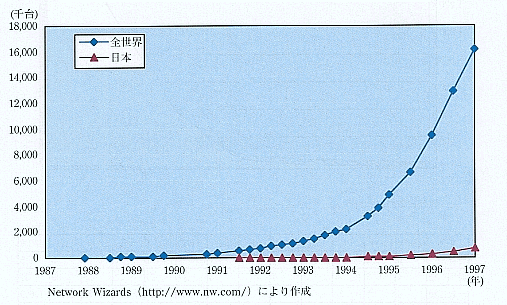
| (単位:千台) |
| 年月 | 1987.12 | 1988.7 | 198.10 | 1989.1 | 1989.7 | 1989.10 | 1990.10 | 1991.1 | 1991.7 |
| ホスト数(全世界) | 28.2 | 33.0 | 56.0 | 80.0 | 130.0 | 159.0 | 313.0 | 376.0 | 535.0 |
| ホスト数(日本) | − | − | − | − | − | − | − | − | 6.7 |
| 年月 | 1991.10 | 1992.1 | 1992.4 | 1992.7 | 1992.10 | 1993.1 | 1993.4 | 1993.7 | 1993.10 |
| ホスト数(全世界) | 617.0 | 727.0 | 890.0 | 992.0 | 1,136.0 | 1,313.0 | 1,486.0 | 1,776.0 | 2,056.0 |
| ホスト数(日本) | 8.2 | 8.6 | 12.4 | 15.8 | 20.4 | 23.2 | 25.9 | 35.6 | 43.7 |
| 年月 | 1994.1 | 1994.7 | 1994.10 | 1995.1 | 1995.7 | 1996.1 | 1996.7 | 1997.1 |
| ホスト数(全世界) | 2,217.0 | 3,212.0 | 3,864.0 | 4,852.0 | 6,642.0 | 9,472.0 | 12,881.0 | 16,146.0 |
| ホスト数(日本) | 42.8 | 72.4 | 82.6 | 96.6 | 159.8 | 269.3 | 496.4 | 734.4 |
| (注) 日本国内のでーたのうち「−」で示すものについては採取できなかったものである。 |
(国内普及状況)
8年2月末現在、インターネット・サービス・プロバイダとしてインターネット接続サービスを行っている第二種電気通信事業者は1,640社であり、これは、第二種電気通信事業者全体の約4割に当たる。第一種電気通信事業者については、NTT、KDD、IDC、ITJ及び武蔵野三鷹ケーブルテレビの5社となっている。
また、8年10月現在で、インターネットにダイヤルアップIP接続するためのアクセスポイントは、全国に282か所(3分間の通話が10円でかけられる単位料金区域)存在し、その数はインターネットの普及に伴い増加している。
(国別普及状況)
インターネットに接続されるホストコンピュータ数を主な国別で見ると、米国が約1,011万台(全体の62.6%)と最も多く、以下、日本(約73万台、全体の4.5%)、ドイツ(約72万台、全体の4.5%)、カナダ(約60万台、全体の3.7%)、英国(約59万台、全体の3.7%)の順となっている。過去3年間の成長を見ると、タイ(33.50倍)、インド(22.74倍)、日本(17.17倍)、ニュー・ジーランド(14.64倍)、シンガポール(10.42倍)の成長が目ざましい。
(2) パソコン通信サービスの普及状況
(財)ニューメディア開発協会が8年6月に行った「全国パソコンネット局実態調査」結果によると、パソコンネット局数は、2,741局(対前年比4.7%増)であり、パソコンネット局数の増加は年々鈍化している。
また、全パソコンネット局の会員数は573.2万人(推計値を含む。対前年同期比55.4%増)である。そのうち、会員数が1万人以上のパソコンネット局19局の会員数合計は466.8万人(同55.8%増)であり、全ネット局会員数の81.4%を占める。
1 事業者数の動向
事業者数については、衛星系放送事業者(8年度、対前年度比294.1%増)に顕著な新規参入が見られた(第6表参照)。
| (単位:社数) |
| 7 年 度 | 8 年 度 | 増 減 | |||||
| 電 気 通 信 事 業 者 | 第一種 | 国内 | NTT | 1 | 1 | 0 | |
| NTTDoCoMo等 | 9 | 9 | 0 | 新事業者 | 長距離系 | 3 | 3 | 0 |
| 地域系 | 16 | 28 | 12 | ||||
| 衛星系 | 2 | 2 | 0 | ||||
| 移動系 | 90 | 90 | 0 | 国際 | KDD | 1 | 1 | 0 |
| 新事業者(うち衛星系) | 4(2) | 4(2) | 0 | ||||
| 計 | 126 | 138 | 12 | ||||
| 第二種 | 特別(うち国際特別) | 50(37) | 78(56) | 28(19) | |||
| 一般 | 3,084 | 4,510 | 1,426 | ||||
| 計 | 3,134 | 4,588 | 1,454 | ||||
| 計 | 3,260 | 4,726 | 1,466 | ||||
| 放送事業者 | 地上系 | NHK | 1 | 1 | 0 | ||
| 放送大学学園 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 民間放送 | 222 | 266 | 44 | ||||
| 計 | 224 | 268 | 44 | ||||
| 衛星系(NHKを除く) | 放送衛星利用 | 2 | 2 | 0 | |||
| 通信衛星利用 | 委託 | テレビジョン | 11 | 56 | 45 | ||
| 音声 | 2 | 7 | 5 | ||||
| 受託 | 2 | 2 | 0 | ||||
| 計 | 17 | 67 | 50 | ||||
| 計 | 241 | 335 | 94 | ||||
| ケーブルテレビ事業者 | 641 | 696 | 55 | ||||
| 郵便事業 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 郵政省資料により作成 |
2 経営動向等
(1) 電気通信事業者
(電気通信事業者の経営動向)
「法人企業統計年報」(大蔵省)によると、7年度の営業収益(売上高)は、全産業については対前年度比3.2%増、製造業については同1.5%増、非製造業については、同3.8%増である中で、郵政省の調査によれば、7年度の第一種電気通信事業者全体の電気通信事業営業収益は8兆8,060億円(対年前年度比12.1%増)であった。その内訳を見ると、国内第一種電気通信事業者は8兆4,612億円(同12.6%増)、国際第一種電気通信事業者は3,448億円(同1.2%増)であった。
(電気通信事業者の設備投資動向)
8年3月及び10月に郵政省が実施した「通信産業設備投資等実態調査」によると、電気通信事業者全体の7年度の設備投資実積額は3兆5,052億円(対前年度比21.8%増)、8年度の設備投資修正計画額は4兆5,641億円(対前年度実績額比30.2%増)となっている。なお、「法人企業動向調査報告」(経済企画庁、8年12月実施)によると、8年度の設備投資修正計画額は、全産業が46兆1,993億円(対前年度実績額比11.2%増)、製造業が14兆9,290億円(同11.9%増)、非製造業が31兆2,704億円(同10.9%増)となっている。
(2) 放送事業者
(放送事業者の経営動向)
7年度のNHKの経営状況(一般勘定)について見ると、事業収入は5,717億円(対前年度比1.2%増)であり、事業収入の大部分を占める受信料は5,541億円(同2.0%増)であった。一方、事業支出は5,687億円(同3.4%増)であり、事業収支差金は30億円となった。
7年度の民間放送事業者全体の経営状況について見ると、地上系民間放送事業者のうち190社と放送衛星及び通信衛星を利用する衛星系民間放送事業者15社の営業収益の合計は2兆3,677億円(対前年度比8.2%増)となっている。
(放送事業者の設備投資動向)
8年3月及び10月に郵政省が実施した「通信産業設備投資等実態調査」によると、放送事業者全体の7年度の設備投資実績額は3,452億円であり、6年度実績額に比べ59.7%増加している。また、8年度の設備投資修正計画額は2,784億円であり、対前年度実績額比19.2%減となっている。
(3) 郵便事業
7年度の郵便事業の経営状況を見ると、郵便業務収入が増加し、収益全体で2兆2,865億円(対前年度比2.3%増)となる一方、費用については、効率化・合理化努力により2兆1,647億円(対前年度比2.1%増)に抑えられた。この結果、郵便事業利益は、1,218億円(対前年度比1.9%増)となった。
1 情報流通の動向
(1) 全国の情報流通の動向
各情報流通量について、7年度までの10年間の推移を見ると、原発信情報量、発信情報量の伸びが大きく、それぞれ昭和60年度の3.82倍、2.79倍となっている。昭和60年度からの10年間の年平均伸び率は、原発信情報量が14.6%、発信情報量が10.9%、選択可能情報量が7.2%、消費可能情報量が5.5%、消費情報量が5.3%であり、全情報量とも、同期間の実質GDPの伸び(年平均3.1%)を上回っている(第7図参照)。
また、この1年間の伸び率を見ると、原発信情報量(対前年度比30.3%増)及び発信情報量(対前年度比23.1%増)が、選択可能情報量(対前年度比7.3%増)、消費情報量(対前年度比11.1%増)より大きく伸びている。これは、原発信情報量の70%以上、発信情報量の50%以上のシェアをもつデータ伝送において、インターネット等の普及に伴うマルチメディア化の進展により、伝送容量の大きい回線が急増し、情報流通量が高い伸び(対前年度比43.5%増)を示したことが要因である。
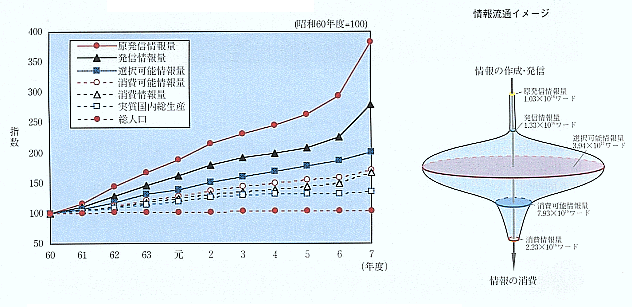
| (指数) |
| 年度 | 60 | 61 | 62 | 63 | 元 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 原発信情報量 | 100.0 | 115.5 | 143.7 | 167.3 | 188.8 | 214.6 | 230.6 | 245.2 | 263.1 | 292.9 | 381.6 |
| 発信情報量 | 100.0 | 110.2 | 128.6 | 146.0 | 162.3 | 180.4 | 191.8 | 198.8 | 208.8 | 226.3 | 278.6 |
| 選択可能情報量 | 100.0 | 107.7 | 117.4 | 130.9 | 139.6 | 150.9 | 161.0 | 168.8 | 178.7 | 187.1 | 200.8 |
| 消費可能情報量 | 100.0 | 103.9 | 112.2 | 121.7 | 128.6 | 136.7 | 144.2 | 150.1 | 155.4 | 158.3 | 170.3 |
| 消費情報量 | 100.0 | 104.7 | 110.6 | 117.2 | 125.0 | 131.2 | 135.5 | 138.5 | 143.9 | 150.1 | 166.8 |
| 実質国内総生産 | 100.0 | 103.2 | 108.3 | 114.8 | 120.2 | 126.6 | 130.3 | 131.3 | 131.7 | 132.5 | 135.8 |
| 総人口 | 100.0 | 100.5 | 101.0 | 101.4 | 101.8 | 102.1 | 102.5 | 102.8 | 103.1 | 103.3 | 103.7 |
(2) 地域の情報流通の動向
7年度における各都道府県別の発信情報量のシェアを見ると、東京都のシェアが20.0%と突出しており、2位の大阪府(シェア7.3%)の2.7倍となっている。東京都のシェアが突出しているのは、新聞、雑誌、書籍等が多く出版されており、輸送系メディアによる情報発信が他の地域と比べて突出して大きい(全国の輸送系メディアの28.4%)ためである。
各都道府県の一人当たりの選択可能情報量を見ると、山梨県(全都道府県平均の1.82倍)、長野県(同1.52倍)、東京都(同1.46倍)、埼玉県(同1.41倍)、三重県(同1.36倍)の順となっている。山梨県、長野県は昭和60年度と比較した一人当たり選択可能情報量の伸びが大きい県でもあり(山梨県3.68倍、長野県3.03倍)、両県の特徴としてケーブルテレビの普及が進んでいることが挙げられる。
2 情報ストックの動向
我が国において、様々な形態で蓄積されている情報ストック量は、7年度において1.23×1015ワード(前年度比0.3%増)であり、昭和60年度と比較して1.45倍となっている。
7年度の情報ストック量と昭和60年度からの増加率(倍数)を各メディアについて見ると、情報ストック量が多い10メディアの中で増加率が高いものは、CD−ROM(63.5倍)、ケーブルテレビ(15.6倍)、ビデオソフト(10.2倍)が挙げられる。そのほかBSテレビ放送(855.6倍)、レンタルビデオ(94.8倍)が非常に高い伸びを示している。
3 情報通信機器ストックの動向
5年末における我が国の情報通信機器ストックは、全体で66兆6,400億円(対前年末比4.7%増)であった。これを部門別に見ると、家計部門は12兆4,800億円(同9.5%増)、企業部門は46兆400億円(同3.2%減)、公共部門は8兆1,200億円(同6.4%増)であった。各部門が情報通信機器ストック全体に占める構成比を見ると、家計部門が18.7%、企業部門が69.1%、公共部門が12.2%であった。
1 情報通信と経済活動
(1) リーディング産業として成長する情報通信産業
情報通信産業の実質国内生産額の推移を見ると、昭和60年が52.8兆円、2年が80.6兆円及び7年が92.6兆円である。年平均成長率は、我が国産業全体の年平均成長率と比較すると、より高い水準で推移している。また、情報通信産業の実質国内生産額が我が国産業全体の実質国内生産額に占める比率は、7年には10.3%と初めて10%を超え、その拡大が続いている(第8図参照)。
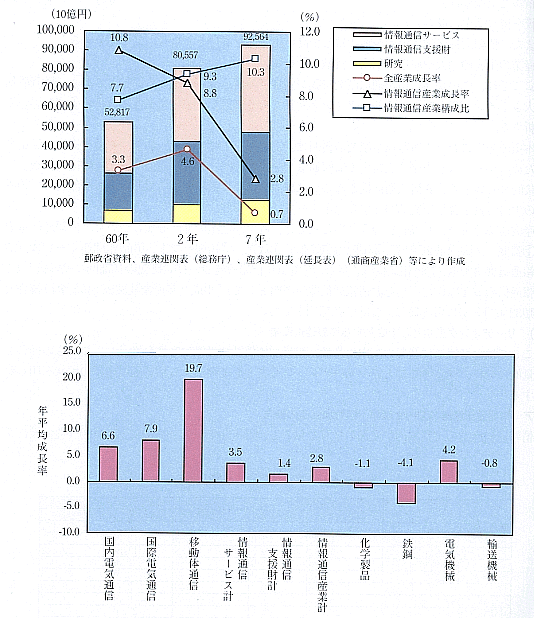
情報通信産業の労働生産性の推移を見ると、昭和60年が雇用者1人当たり1,600万円、2年が2,053万円及び7年が2,348万円であり、我が国産業全体のそれぞれ同期の労働生産性と比較すると、高い水準で推移している。また、2年から7年にかけては我が国産業全体の年平均変化率が0.8%減とマイナスになったのに対し、情報通信産業では同期間に2.7%の上昇を記録しており、情報通信産業においては事業の効率化が順調に進んでいることがうかがえる。
(2) 情報通信産業の生産増加による波及効果
2年から7年の情報通信産業の生産額の増大が、我が国産業全体の生産額をどの程度押し上げたかを計測する。その結果を見ると、情報通信産業の生産額は同期間に12.0兆円の増加を記録しているが、それによる情報通信以外の産業への波及額も4.7兆円あり、その合計は16.7兆円と、全産業における同時期の生産増加額31.1兆円の53.6%を占めている(第9図参照)。
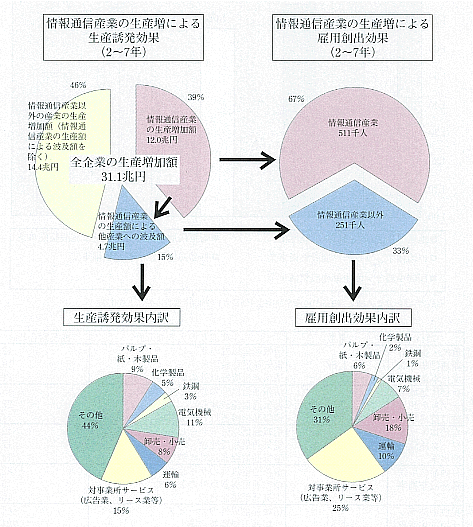
| (単位:10億円、千人) |
| 情報通信による波及 | |||
| 生産額 | 雇用者数 | ||
| 情報通信産業 | 12,007 | 511 | |
| 情報通信産業以外計 | 4,675 | 251 | |
| パルプ・紙・木製品 | 402 | 16 | 化学製品 | 246 | 5 | 鉄鋼 | 117 | 2 | 電気機械 | 505 | 17 | 卸売・小売 | 399 | 44 | 運輸 | 277 | 24 | 対事業所サービス | 718 | 64 | その他 | 2,011 | 79 |
| 全産業計 | 16,682 | 763 | |
| 郵政省資料、産業連関表(総務庁)、産業連関表(延長表) |
(3) 電気通信分野の価格低下による消費増大効果、GDP拡大効果
国内電気通信(移動体通信を含む。)及び国際電気通信の価格低下が、我が国の実質消費をどの程度増大させたかを計測すると、昭和60年から2年までが3,900億円、2年から7年までが8,840億円であった。電気通信分野における価格低下が、同時期の実質国内総支出の成長にどれだけ寄与したかを計測すると、昭和60年から2年にかけての実質国内総支出の成長率4.4%のうち、価格低下によってもたらされた部分は0.02%(寄与率で0.45%)、2年から7年にかけてが1.48%のうち0.05%(同3.38%)であった。また、2年から7年にかけての価格低下が及ぼす波及効果について計測すると、実額、伸び率とも「情報通信以外のサービス」への波及が最も大きくなっている(第10図参照)。
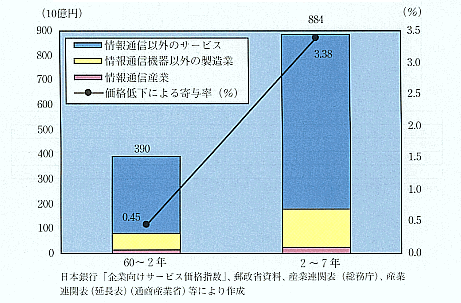
| (単位:10億円) |
| 消費増大効果の波及先 | 60〜2年 | 2〜7年 |
| 増加額 | 増加額 | |
| 情報通信産業 | 13 | 25 |
| 情報通信機器以外の製造業 | 70 | 155 |
| 情報通信以外のサービス(金融、卸・小売等) | 307 | 704 |
| 全産業 | 390 | 884 |
| 価格低下による寄与率 (実質GDP成長率に占める価格低下による寄与率) (%) |
0.45 | 3.38 |
| (価格低下率) | (単位:%) |
| 60〜2年 | 2〜7年 | |
| 国内電気通信 | -4.1 | -10.0 |
| 国際電気通信 | -45.3 | -11.8 |
| 移動体通信 | -18.0 | -24.4 |
(4) 情報化投資に伴う乗数効果の計測
産業連関分析の手法を用いて、郵政省が行う地域・生活情報通信基盤高度化事業について、7年における乗数を計測すると1.68となった。本事業のうち、自治体ネットワーク施設整備事業の乗数は1.67、新世代地域ケーブルテレビ施設整備事業の乗数は1.76であった。また、郵政省が行う移動通信用鉄塔施設整備事業及び民放中波ラジオ中継施設整備事業について、7年における乗数をそれぞれ計測すると、移動通信用鉄塔施設整備事業については1.62、民放中波ラジオ中継施設整備事業については1.51となった(第11図参照)。
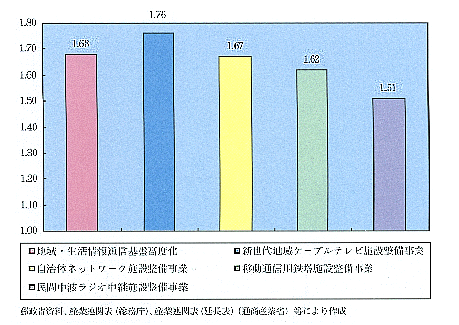
2 産業の情報化
(1) サイバービジネスの展望
ここ数年のインターネットの普及により、サイバースペースを利用した電子商取引に代表されるサイバービジネスが大きく注目されている。サイバービジネスとは、「情報通信ネットワーク内のビジネス空間・社会的空間を提供し、その中で一般消費者、製造業者、サービス業者、各種団体等の取引(商品の受発注、決済等)・相互交流を実現するネットワークビジネス」(電気通信審議会答申、8年2月)である。
(サイバービジネスの市場規模)
日本におけるサイバービジネスの8年度の市場規模は約285億円である。7年度の市場規模は7億円(推定)であり、この一年未満の間で約40倍の急成長を遂げている。これを、全世界の市場規模約3,490億円(予測)と比較すると約8%のシェアを有している。国別に見れば、米国が約77%と他を大きく引き離している(第12図参照)。また、サイバー店舗数の推移を見ると、7年後半から8年にかけて急激な増加が見うけられる。
| (1) サイバービジネスの市場規模 |
| (単位:億円、%) |
| 市場規模 | 7年度 | 8年度 |
| 日本 米国 その他 | 7.0 (1%) 417.6 (80%) 98.6 (19%) |
285.0 (8%) 2686.8 (77%) 517.8 (15%) |
| 世界 | 523.2 (100%) | 3489.6 (100%) |
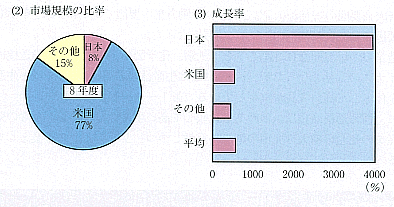
| (注) | 1 | 日本: | 郵政省資料により作成。 7年度の値は、8年3月時点の推計値。 8年度の値は、9年1月調査時点での値。 |
| 2 | 海外: | ActivMedia社調査による。 7年度の値は、7年春及び9月の調査からの推計値。 8年度の値は、8年12月時点の予測値 | |
| 3 | 調査対象は、インターネット上での一般消費者向けのサイバービジネス。企業と企業の間の中間財の取引は除く。 | ||
(サイバービジネスの既存ビジネスとの比較)
サイバー店舗で取り扱う商品の価格を、実在店舗での販売価格と比較して見ると、多くの店舗が「同価格」で販売しているが、サイバー店舗で販売する方が安価に商品を提供している店舗も存在している。
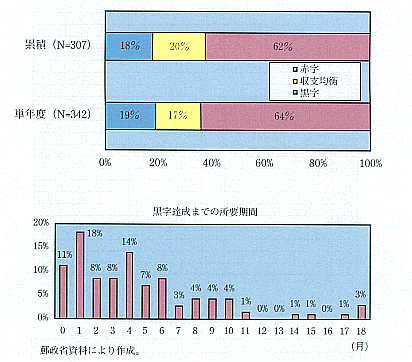
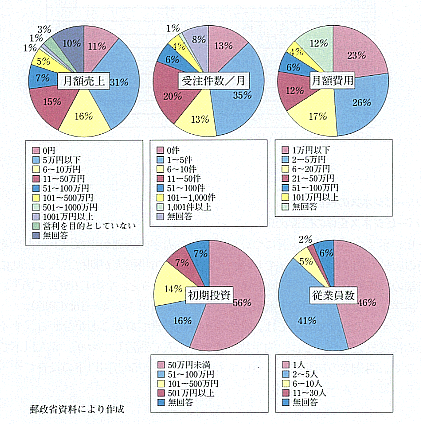
(サイバービジネスの地域別傾向)
サイバービジネスでの地域別の傾向について見ると、サイバービジネスの経営者の本業所在地では、4分の1が海外であり、サーバーの設置場所も、3割弱が海外となっている。
また、国内については、サイバー店舗の経営者の本業の所在地、サーバー設置場所ともに東京都に集中していることが分かる。
3 国民生活の情報化
(1) 家庭の情報化
(収入弾性値から見る家庭の情報化)
家計における収入と情報通信関連支出との関係を見るため、昭和46年から7年までの期間の家計支出各項目について、支出の収入弾性値(収入が1%増加した時の支出の増加率)の比較を行った。情報通信関連財支出及び情報通信関連サービス支出が他の家計支出項目に比べ高くなっている一方、新聞、雑誌、書籍等のいわゆるパッケージ型情報ソフトが含まれる「教養・娯楽」の項目が低くなっている。このことから、今後の所得の増加に対し、情報通信関連財及び情報通信関連サービス支出はその増加以上の伸びを見せる可能性があることが分かる(第15図参照)。
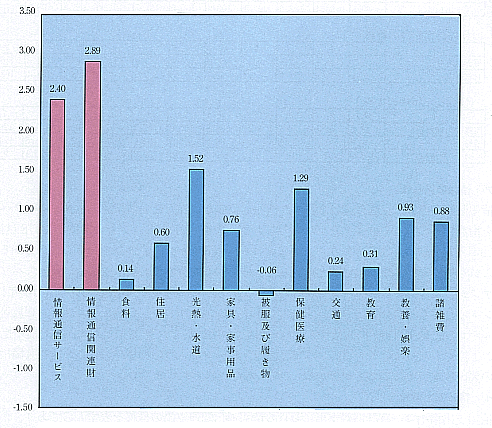
| 「家計調査年報」(総務庁)、「消費者物価指数年報」(総務庁)により作成 | ||
| (注) | 1 | 「情報通信関連サービス」に含まれるものは次のとおりである。 郵便料、電話利用料、放送受信料、映画・演劇入場料、複写機使用料 |
| 2 | 「情報通信関連財」に含まれるものは次のとおりである。 通信機器、ラジオ、テレビ、ステレオセット、テープレコーダ、ビデオテープレコーダ、パソコン・ワープロ、オーディオ・ビデオディスク、オーディオ・ビデオ未使用テープ、オーディオ・ビデオ収録済テープ | |
(2) 個人の情報化
(インターネットの利用動向)
私的時間におけるインターネットの今後の需要予測について、インターネット利用者では69.8%、利用意向のある未利用者では65.6%が「着実に増える」としているのに対し、利用意向のない未利用者では、「専門的な研究や趣味としてある程度利用されるが伸びは横ばい」及び「一時的なブームとして下火になる」というように、需要は伸びないとする回答が75.1%を占めている。このように、インターネット利用者及び利用意向のある未利用者と利用意向のない未利用者では、意識の差が大きくなっていることが分かる(第16図参照)。インターネットの需要が伸びないとする回答者について、その主な理由を見ると、「思ったほど有益な情報がない」が最も多くなっている。また、「ランニングコストが高い」、「操作性が悪い」、「初期投資が高い」等の、コスト意識に根差した項目が多く挙げられている(第17図参照)。
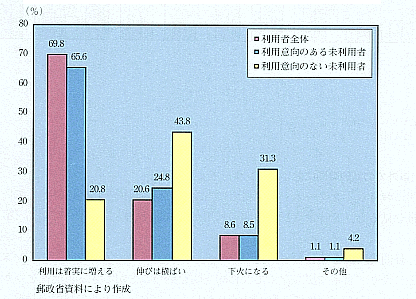
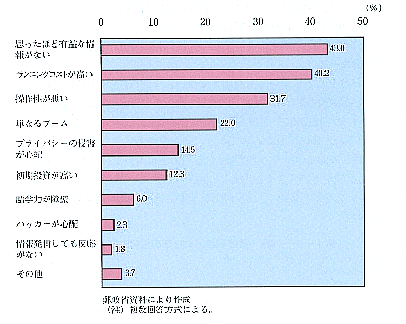
(携帯電話・PHSの利用上の問題点に対する意識)
携帯電話・PHSの普及の拡大に伴い、利用者の利用マナーの欠如、自動車の運転等のその他の行為をしながら利用する「ながら利用」に対する危険性等、様々な問題点の存在が指摘されている。携帯電話・PHSの利用上の問題点について、利用者に対してはそのような問題点の指摘に対してどのように認識しているのか、また、未利用者に対しては、利用者に対しどのような問題点を感じているのか、それぞれの立場における意識について見ると、利用者においては、「自分は気をつけて使っているので大丈夫」が圧倒的に多く、次いで「他人が使っているのは気になる」、「迷惑をかけていると思うが使わざるを得ない」となっている。未利用者においては、「自動車の運転中の利用は事故につながり危険」、「通話に夢中で周囲の人の存在を無視している」、「通話している人の声がうるさい」の順に多くなっている(第18表参照)。
| (利用者の意識) |
| 項目 | 全体 | 男性 | 女性 |
| 自分は気をつけているので大丈夫 | 40.9 | 42.2 | 35.4 |
| 他人が使っているのは気になる | 18.1 | 18.3 | 17.4 |
| 迷惑をかけているとは思うが使わざるを得ない | 13.6 | 13.1 | 15.8 |
| 問題点はあるが便利さは捨てがたい | 6.8 | 6.0 | 10.4 |
| 使ったことがない人ほど問題点を気にする | 6.3 | 6.3 | 6.6 |
| 自動車の運転は危険だが便利さには代えられない | 4.2 | 4.3 | 3.8 |
| 大目に見るべきだ | 3.3 | 3.6 | 2.2 |
| その他 | 6.7 | 6.3 | 8.2 |
| (未利用者の意識) |
| 項目 | 全体 | 男性 | 女性 |
| 自動車の運転中の利用は事故につながり危険 | 26.0 | 23.7 | 31.8 |
| 通話に夢中で周囲の人の存在を無視している | 21.0 | 20.8 | 21.3 |
| 通話している人の声がうるさい | 18.8 | 20.6 | 14.3 |
| 公共の空間に私的空間を持ち込むのはわがまま | 11.8 | 13.5 | 7.6 |
| 精密機器の誤作動を招くおそれがあり危険 | 9.9 | 8.3 | 13.8 |
| 呼び出し音がうるさい | 7.7 | 7.5 | 8.3 |
| その他 | 4.8 | 5.6 | 2.9 |
| 郵政省資料により作成 |
4 地域における情報化の進展
(1) 情報化の現状
全国3,255市町村(東京23区を含む。)の情報化の進展状況を地域情報化指標を用いて分析すると、先進的な一部地域を除き、多くの市町村が全国平均より下位のレベルに集中して位置していることが分かる。また、先進的な地域については、東京都23区、政令指定都市、県庁所在地及びその近郊都市が上位を占めている(第19図参照)。
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 利用環境 指標(A) | 開発整備 指標(B) |
地域情報化 指標(A+B) |
| 1 | 福岡県 | 北九州市 | 36 | 32 | 68 |
| 2 | 兵庫県 | 神戸市 | 39 | 24 | 63 |
| 3 | 大阪府 | 堺市 | 40 | 22 | 62 |
| 4 | 神奈川県 | 藤沢市 | 38 | 22 | 60 |
| 5 | 神奈川県 | 横浜市 | 41 | 18 | 59 |
| 6 | 神奈川県 | 川崎市 | 42 | 16 | 58 |
| 6 | 神奈川県 | 相模原市 | 38 | 20 | 58 |
| 8 | 宮城県 | 仙台市 | 34 | 22 | 56 |
| 8 | 愛知県 | 名古屋市 | 36 | 20 | 56 |
| 8 | 愛知県 | 豊田市 | 36 | 20 | 56 |
| 11 | 北海道 | 札幌市 | 33 | 22 | 55 |
| 12 | 東京都 | 新宿区 | 38 | 16 | 54 |
| 12 | 東京都 | 墨田区 | 38 | 16 | 54 |
| 12 | 神奈川県 | 厚木市 | 34 | 20 | 54 |
| 12 | 大阪府 | 岸和田市 | 38 | 16 | 54 |
| 16 | 東京都 | 江東区 | 41 | 12 | 53 |
| 16 | 東京都 | 世田谷区 | 41 | 12 | 53 |
| 16 | 石川県 | 金沢市 | 31 | 22 | 53 |
| 16 | 京都府 | 京都市 | 39 | 14 | 53 |
| 20 | 東京都 | 文京区 | 38 | 14 | 52 |
| 20 | 東京都 | 板橋区 | 38 | 14 | 52 |
| 20 | 東京都 | 江戸川区 | 42 | 10 | 52 |
| 20 | 神奈川県 | 鎌倉市 | 38 | 14 | 52 |
| 20 | 神奈川県 | 大和市 | 36 | 16 | 52 |
| 20 | 福岡県 | 福岡市 | 36 | 16 | 52 |
| 規定最高点(満点) | 47 | 42 | 89 | ||
| 郵政省資料により作成 |
(2) 情報化の進展
(過去10年間の時系列分析)
利用環境指標の平均点の推移を見れば、過去10年間、着実に情報化が進展しているのが分かる。しかし、過去10年間全く情報化が進展していない地域もある一方で、情報化が急速に進展している地域もあり、両者の差は拡大している(第20図参照)。
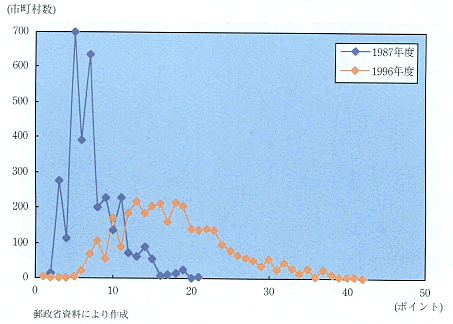
(都道府県別の情報化の進展状況)
地域情報化の進展状況を都道府県別に見ると、情報化の進展度に差異が生じている。例えば、北海道、宮城県、兵庫県及び福岡県のように、政令指定都市があるところほど同一都道府県内における差異が大きい。また、19の府県においては県庁所在地よりも情報化が進展している市があり、必ずしも、各都道府県の県庁所在地において情報化が一番進展しているわけではないことが分かる(第21表参照)。
| 都道府県名 | 市町村名 | 利用環境 指標 | 開発整備 指標 |
地域情報化 指標 | 全国 順位 |
| 北海道 | 札幌市 | 33 | 22 | 55 | 11 |
| 青森県 | 青森市 | 30 | 10 | 40 | 147 |
| 岩手県 | 北上市 | 27 | 8 | 35 | 283 |
| 宮城県 | 仙台市 | 34 | 22 | 56 | 8 |
| 秋田県 | 秋田市 | 26 | 12 | 38 | 195 |
| 山形県 | 米沢市 | 27 | 8 | 35 | 283 |
| 福島県 | 郡山市 | 26 | 14 | 40 | 147 |
| 茨城県 | 日立市 | 28 | 16 | 44 | 78 |
| 土浦市 | 30 | 14 | 44 | 78 | |
| 栃木県 | 宇都宮市 | 29 | 12 | 41 | 127 |
| 群馬県 | 前橋市 | 31 | 12 | 43 | 94 |
| 高崎市 | 31 | 12 | 43 | 94 | |
| 埼玉県 | 大宮市 | 35 | 16 | 51 | 26 |
| 千葉県 | 千葉市 | 36 | 14 | 50 | 28 |
| 東京都 | 新宿区 | 38 | 16 | 54 | 12 |
| 墨田区 | 38 | 16 | 54 | 12 | |
| 神奈川県 | 藤沢市 | 38 | 22 | 60 | 4 |
| 新潟県 | 新潟市 | 29 | 18 | 47 | 50 |
| 富山県 | 富山市 | 32 | 8 | 40 | 147 |
| 高岡市 | 32 | 8 | 40 | 147 | |
| 石川県 | 金沢市 | 31 | 22 | 53 | 16 |
| 福井県 | 福井市 | 28 | 16 | 44 | 78 |
| 山梨県 | 甲府市 | 28 | 22 | 50 | 28 |
| 長野県 | 塩尻市 | 30 | 14 | 44 | 78 |
| 岐阜県 | 大垣市 | 28 | 14 | 42 | 111 |
| 静岡県 | 浜松市 | 33 | 14 | 47 | 50 |
| 愛知県 | 名古屋市 | 36 | 20 | 56 | 8 |
| 豊田市 | 36 | 20 | 56 | 8 | |
| 三重県 | 四日市市 | 32 | 10 | 42 | 111 |
| 滋賀県 | 大津市 | 30 | 8 | 38 | 195 |
| 京都府 | 京都市 | 39 | 14 | 53 | 16 |
| 大阪府 | 堺市 | 40 | 22 | 62 | 3 |
| 兵庫県 | 神戸市 | 39 | 24 | 63 | 2 |
| 奈良県 | 生駒市 | 29 | 14 | 43 | 94 |
| 和歌山県 | 田辺市 | 26 | 10 | 36 | 259 |
| 鳥取県 | 米子市 | 28 | 12 | 40 | 147 |
| 島根県 | 松江市 | 28 | 16 | 44 | 78 |
| 岡山県 | 岡山市 | 27 | 12 | 39 | 171 |
| 倉敷市 | 31 | 8 | 39 | 171 | |
| 広島県 | 広島市 | 33 | 10 | 43 | 94 |
| 山口県 | 徳山市 | 27 | 16 | 43 | 94 |
| 徳島県 | 徳島市 | 30 | 6 | 36 | 259 |
| 鳴門市 | 30 | 6 | 36 | 259 | |
| 香川県 | 高松市 | 34 | 8 | 42 | 111 |
| 愛媛県 | 今治市 | 29 | 10 | 39 | 171 |
| 高知県 | 高知市 | 28 | 6 | 34 | 323 |
| 福岡県 | 北九州市 | 36 | 32 | 68 | 1 |
| 佐賀県 | 佐賀市 | 26 | 16 | 42 | 111 |
| 長崎県 | 長崎市 | 29 | 10 | 39 | 171 |
| 熊本県 | 熊本市 | 31 | 8 | 39 | 171 |
| 大分県 | 大分市 | 29 | 10 | 39 | 171 |
| 宮崎県 | 延岡市 | 27 | 8 | 35 | 283 |
| 鹿児島県 | 鹿屋市 | 25 | 14 | 39 | 171 |
| 沖縄県 | 那覇市 | 30 | 6 | 36 | 259 |
| 郵政省資料により作成 |
(過疎地域の状況)
過疎地域と過疎地域以外の市町村の地域情報化指標の分布について比較すると、過疎地域の市町村は、過疎地域以外の市町村に比較し、指標値がより低い位置に分布している。
(地域情報化と各種指標との相関分析)
情報化の進展と市町村の有する特性(財政力、人口、産業別就業人口比率、高齢者比率)との相関について分析を行う(第22図参照)。
地域情報化指標は、財政力指数との間に正の相関が見られ、財政が豊かな地域ほど地域情報化が進んでいる傾向が現れている。また、人口規模との間に正の相関が見られ、人口が多い市町村ほど情報化が進んでいる傾向が現れている。さらに、地域情報化指標は、各市町村ごとの第一次産業就業人口比率との間に負の相関が見られ、第三次産業就業人口比率との間には正の相関が見られる。高齢者比率(65歳以上の人口比率)との相関では、地域情報化指標は、負の相関が見られ、高齢者比率が高い市町村ほど情報化が遅れている傾向が現れている。
(1) 財政力指数と地域情報化
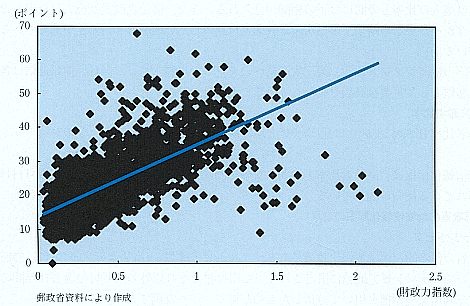
(2) 人口と地域情報化
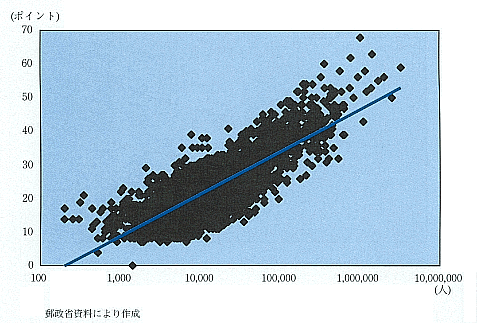
(3) 産業別人口比率と地域情報化
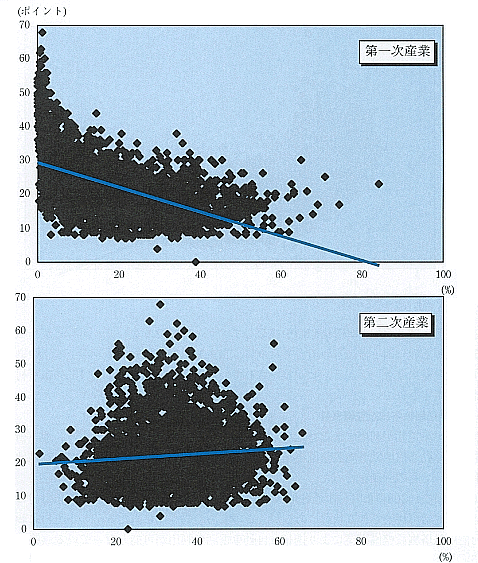
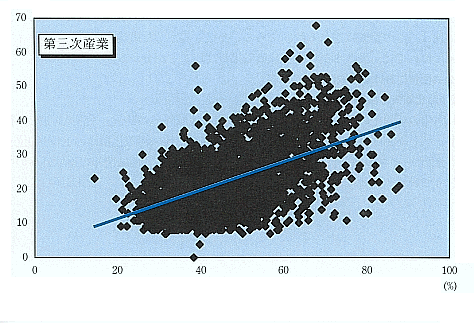
(4) 高齢者比率と地域情報化
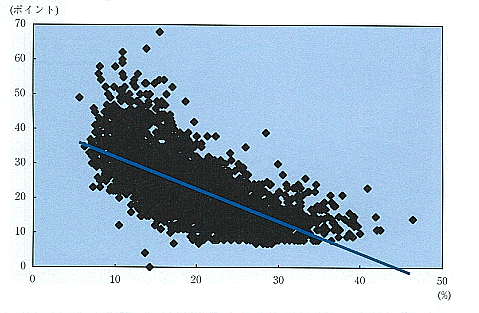
(3) 郵政省の地域情報化施策の効果
郵政省の代表的な地域情報化政策である「テレトピア構想」の効果について、テレトピア地域に指定されている市町村とそれ以外の市町村の過去10年間の情報化の推移を利用環境指標を用いて分析したものが第23図である。テレトピア地域において民間事業者が整備する情報通信インフラやサービスの進展度に関しては、過去一貫してその他地域よりも高い状況にある。また、現在、全国で1,208の市町村が過疎地域に指定されており、そのうち、679の市町村において携帯・自動車電話が利用できる状況にあるが、このうちの約9%に当たる63の市町村においては、移動通信用鉄塔施設整備事業により携帯・自動車電話の利用が可能となっている。
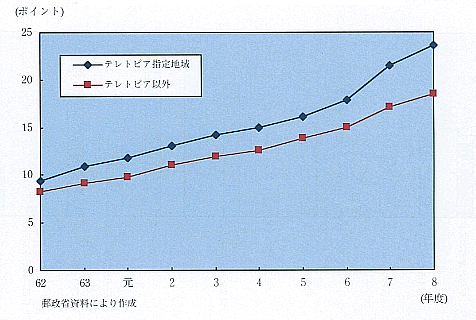
| (単位:ポイント) |
| 年 度 | 62 | 63 | 元 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| テレトピア指定地域 | 9.5 | 10.9 | 11.8 | 13.0 | 14.2 | 15.0 | 16.1 | 17.8 | 21.5 | 23.6 |
| テレトピア以外 | 8.3 | 9.1 | 9.7 | 11.0 | 11.9 | 12.5 | 13.8 | 15.0 | 17.1 | 18.4 |