
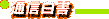


 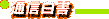 |
1 情報通信におけるデジタル化の動向
情報通信の高度化は、かつての市民革命や産業革命に匹敵する情報通信革命とも称される大きな変革の潮流を生み、経済フロンティアの拡大、国土の均衡ある発展の促進や、真のゆとりと豊かさの実感できる国民生活を可能とするものと期待されている。情報流通量について見ても、デジタル情報の流通量が急速に増加している(第24図参照)。こうした情報通信の高度化の背景には、デジタル技術の発達が大きく影響している。
(1) 発信情報量
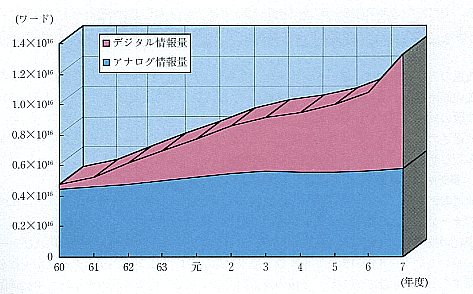
(2) 消費情報量
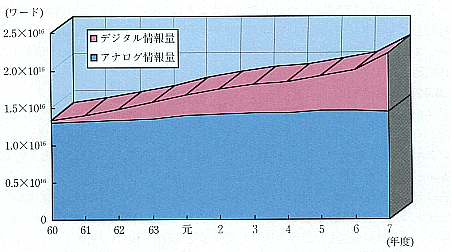
| 「情報流通センサス」(郵政省)により作成 | |
| (注) | 情報流通センサスの計量メディアのうち、伝送形態がデジタル方式のメディア、デジタル化された情報を送受信するメディア及びデジタル記録されたメディアの各情報量を合計したものをデジタル情報量とした。 |
こうした情報通信分野にあって、放送は、現在まで主としてアナログ方式により情報伝送が行われてきたため、電波資源の有限希少性から限られたチャンネル数の中で発達してきた。放送のデジタル化は、このような形で発達を遂げてきた放送が、様々な面において開かれた分野へ変革することを意味する。21世紀に向けた情報通信革命の潮流の中で、デジタル化の進展に伴い、放送の領域にも革命ともいえる大きな変化が起きつつある。
2 デジタル化による放送の高度化
(1) 多チャンネル化
放送のデジタル化により、同一の周波数帯域幅を用いた場合、従来の伝送方式に比べてより多くのチャンネル数を確保することが可能となる。
現在の技術では、デジタル化によって、テレビジョン放送の場合、衛星放送及びケーブルテレビにおいては4〜6倍のチャンネル数、地上放送においては3倍程度のチャンネル数をそれぞれ確保することが可能であるが、今後の技術開発によって、更に多数のチャンネルを確保することが可能と考えられている。
(2) 高品質化・高機能化
デジタル技術には、様々な情報をデジタル信号として統一的に扱うことができるといった特徴がある。デジタル放送は、アナログ放送と比較して、画質の向上(ゴーストキャンセル処理等)、画像処理が容易となるほか、新しいサービスの可能性も広がる。
(3) 通信との融合による放送サービスの高度化
近年、ケーブルテレビ網を利用した電話やインターネット接続サービスといった通信・放送の情報伝送路の共用化や、FM波の多重領域を利用した無線呼出しサービス等に見られるように、通信と放送の融合が進展している。
デジタル技術の発展により、通信ネットワークとの接続による双方向機能を有するサービスが出現するなど、通信と放送の融合が加速化するものと期待される。
3 放送革命の意義と役割
(1) 経済フロンティアの誕生
将来的には数百チャンネルと想定されている放送チャンネル数の増大は、放送ソフトの需要を拡大させるとともに、発信・編集機器及び受信機器等の需要を拡大させるなど、放送事業以外の放送関連産業への波及効果も期待される。
(2) 生活様式の変革
放送のデジタル化に伴う本格的な多チャンネル放送の開始により、選択肢の幅が飛躍的に拡大したことや、好きな時間に視聴を行い得るサービスが登場したことから、自分の嗜好に合った専門的な番組を時間的な制約に合わせて選択する「能動的視聴」が可能となる。
このように、デジタル放送は、教育、娯楽等様々な面で、新しい文化を創り出す最前線としての役割を担うとともに、大きなビジネスチャンスをもたらすことが期待されている。
4 デジタル化に向けた放送メディアの新たな展開
(1) 衛星放送
衛星放送においては、我が国初の本格的な衛星デジタル多チャンネル放送である「パーフェクTV」が8年6月から開始され、同年10月に有料放送を開始した。9年2月末現在で、テレビジョン放送60チャンネル、超短波放送105チャンネル、データ放送14チャンネルが提供されている。9チャンネルあるペイ・パー・ビューチャンネルでは、ニア・ビデオ・オン・デマンド方式で映画、スポーツ等の番組が提供されている。
(2) ケーブルテレビ
8年12月に定められたケーブルテレビのデジタル方式は、衛星デジタル放送と同じ動画像の圧縮符号化技術(MPEG−2)を用いており、衛星デジタル放送の4〜6番組をケーブルテレビの1チャンネルでそのまま伝送することが技術的に可能である。これにより、今後増加する衛星デジタル放送の番組を、ケーブルテレビでの再送信をはじめとした、より一層の多チャンネル放送等が可能となり、早期導入が見込まれている。
(3) 地上放送
我が国における地上デジタル放送の早期実現に向けて、9年1月から郵政省通信総合研究所及びNHKが地上デジタル放送の共同野外実験を行っている。
この実験では、サービスエリアの測定、単一周波数中継実験、移動体向け放送実験等が実施される。その成果は電気通信技術審議会デジタル放送システム委員会に報告され、技術基準の策定に向けて検討が行われることになっている。
5 通信・放送の融合分野の動向
(FM文字多重放送)
FM文字多重放送は、FM放送の電波に重畳し、文字、図形又は信号を送信する放送である。FM文字多重放送の機能を応用し、テレビ放送と連動したゲーム、クイズ番組、個人向けの情報等を提供する視聴者参加型のサービスや、各種情報とCM等のオリジナルメッセージを組み合わせて電光掲示板に表示し、公共メッセージの告知板、販売促進用のツール、看板等としての利用を想定したサービスも開始されている。
(地上データ多重放送)
地上データ多重放送は、テレビジョン放送の電波のすき間にデジタル化された音声その他の音響、文字、図形及び映像の信号を重ねて伝送する放送である。文字・静止画によるニュース等の情報のほか、ソフトウェア等の各種データの提供を可能としている。現在、地上データ多重放送は、地上テレビ放送の垂直帰線消去期間(VBI)を利用する方式で行われている。
(衛星データ多重放送)
衛星データ多重放送は、全国一斉に送信できる衛星放送の電波を用いて、パソコン、テレビ受信機、ファクシミリ等の端末に各種データを高速かつ安価に送信する放送である。衛星放送のデジタル化により、更に高速・大容量のデータ伝送が可能となる。
1 放送産業の市場拡大
(1) 放送産業全体の市場規模の動向
我が国における放送産業全体(放送事業、放送番組制作業、放送機器製造業)の市場規模は、7年度には4兆5,000億円程度となっている(第25図参照)。
その内訳を見ると、放送事業は約3兆円であり、5年度以降漸増傾向にあるほか、放送番組制作業についても、その規模は相対的に小さいが増加傾向にある。一方、放送機器製造業の市場規模については、7年度には1兆3,000億円程度となっており、6年度以降持ち直し気味に推移している。
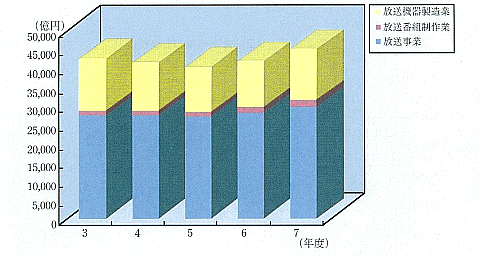
| 郵政省資料,NHK資料、郵政関連業実態調査報告書等により作成(一部推計) (注) 放送番組制作業は郵政関連業実態調査報告書に基づいて作成(3、4年は推計) |
| (単位:億円) |
| 年 度 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 放送事業 | 28,041 | 27,875 | 27,464 | 28,516 | 30,244 |
| 放送番組制作業 | 1,367 | 1,367 | 1,351 | 1,548 | 1,723 |
| 放送機器製造業 | 12,648 | 11,504 | 10,931 | 11,427 | 12,734 |
| 合 計 | 42,056 | 40,746 | 39,746 | 41,491 | 44,701 |
(2) 放送事業の市場規模
放送事業の市場規模の推移を見ると、6年度以降増加に転じており、7年度には3兆円程度(前年度比6.1%増)となっている。「法人企業統計年報」(大蔵省)によると、7年度における営業収益(売上高)の全産業平均は対前年度比3.2%増、非製造業は同3.8%増となっており、放送事業が他産業に比べ相対的に高い成長を遂げている。
放送事業の伸び率が相対的に高くなっている背景としては、地上放送の市場規模が順調に推移していることに加え、衛星放送、ケーブルテレビの市場規模が著しい成長を遂げていることが挙げられる(第26図参照)。
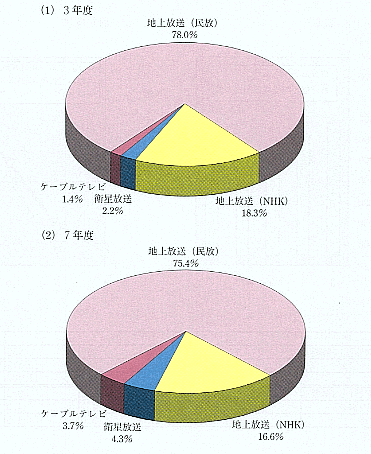
2 放送事業の変化
(1) 事業経営の動向
放送事業者全体の経営状況について経常損益の動きを見ると、5年度にかけて減少したものの、その後増加に転じ、7年度においては全体で前年度比70.6%増と顕著な伸びを示している。その内訳を見ると、地上放送(NHK、民放)については、6年度以降順調に増加している。また、衛星放送(NHK、民放(BS、CS))については、民放のBS放送が7年度において初めて黒字化しているほか、CS放送についても赤字幅が縮小している。
(2) 収入構造の変化
広告料による放送は、視聴者にとっては無料で視聴できるというメリットがある一方、自分の嗜好に合った番組の選択、自分の時間の都合に合った視聴等の選択の幅が限られるという側面も見られる。特に近年、個人の嗜好・ライフスタイルの多様化が進展する中においては、自ら料金を負担しても、自分のニーズに合った視聴を行えるという選択肢が増えていくものと予想される。なお、広告料、受信料、視聴料別の収入比率を見ると、地上民放における広告料収入が大きな比率を占めているが、BS・CS放送及びケーブルテレビの収入増加により、徐々に視聴料による収入の比率が増加してきている。
(3) 設備投資の動向
我が国における放送産業全体(放送事業、放送番組制作業、放送機器製造業)の設備投資の動向を見ると、7年度(実績額)は4,400億円程度(前年度比55.6%増)となっており、放送事業者の設備投資活発化を背景に前年度から大幅増加に転じている(第27図参照)。
放送事業における設備投資の推移を見ると、7年度(実績額)には前年度比70.8%増と大幅に拡大している。これは、一部キー局による本社社屋の移転による一時的な要因によるものも大きい。
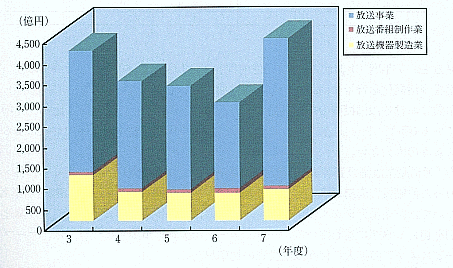
| 郵政省資料,NHK資料、日本民間放送年鑑、通信産業設備投資等実態調査報告書により作成(一部推計) |
| (単位:億円) |
| 年 度 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 放送事業 | 2,950 | 2,621 | 2,548 | 2,103 | 3,591 |
| 放送番組制作業 | 97 | 86 | 84 | 96 | 107 |
| 放送機器製造業 | 696 | 633 | 601 | 628 | 700 |
| 合 計 | 3,743 | 3,340 | 3,233 | 2,827 | 4,398 |
(4) 雇用の動向
我が国における放送産業全体(放送事業、放送番組制作業、放送機器製造業)の雇用者数の動向を見ると、7年度末において10万7,000人程度となっており、前年度から増加に転じている。放送事業の雇用者数について見ると、7年度末には5万人程度となっている(第28図参照)。内訳については、地上民放事業者及びNHKがそのほとんどを占めており、衛星放送、ケーブルテレビの規模は小さい。もっとも、衛星放送においては7年度には前年度比2桁台の高い伸びを示している。
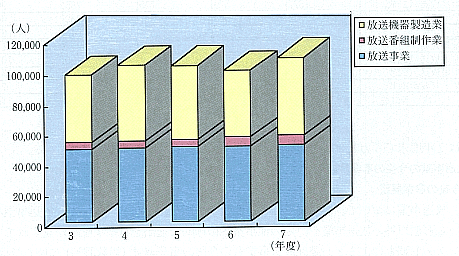
| NHK資料、日本民間放送年鑑、通信産業実態調査報告書、郵政関連業実態調査報告書等により作成(一部推計) |
| (単位:人) |
| 年 度 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 放送事業 | 47,418 | 48,433 | 48,971 | 49,048 | 49,617 |
| 放送番組制作業 | 4,550 | 4,599 | 4,636 | 6,190 | 6,434 |
| 放送機器製造業 | 44,785 | 49,891 | 48,926 | 43,932 | 51,320 |
| 合 計 | 96,753 | 102,923 | 102,533 | 99,170 | 107,371 |
(5) 放送事業の今後の事業展開
今後、放送事業において、多事業者間による競争の激化が予想される中で、放送事業者が現在行っている形態以外の放送事業や、その他事業へ積極的に進出を目指す動きが見られている。郵政省が委託したアンケート調査によると、委託放送事業者の今後の事業運営(複数回答)に関しては、積極的に経営拡大を考えている先が多くなっている。
なお、前述のアンケート調査によると、放送産業全体の将来像としては、新たな事業者の増加やサービスの展開等、大きな変革を見込む事業者が多くなっている。
CSデジタル多チャンネル放送の開始、多様なサービスの出現により、放送産業以外の資本による放送産業への参入が増加している。CS放送の委託放送事業者数の推移を見ると、アナログ事業者についても順次増加してきていたが、特に、衛星デジタル多チャンネル放送の開始に伴い8年以降事業者が急増している。こうした委託放送事業には、他産業からの参入が顕著に見られている。前述の委託放送事業者向けアンケートにより、参入前に営んでいた事業の動向を見ると、放送以外の事業を営んでいた事業者は60%に上り、その事業内容も、新聞、出版、流通、その他(教育、燃料等)と様々である。
チャンネル数の量的な増加に加え、放送サービスの提供形態にも様々な広がりが見られている。コストの低下により従来に比べ相対的に少ない視聴者を対象としても、放送が事業として成立するようになっていることに伴い、限られた一定のニーズに焦点を絞った専門的な放送を行うことも可能である(第29図参照)。現在、衛星デジタル多チャンネル放送においては、教育分野の中でも中学生にのみ対象を絞っているチャンネル、高校生にのみ対象を絞っているチャンネルや、英会話のみを提供しているチャンネル等が存在している。また娯楽分野でも、海外旅行情報のみに限定したチャンネル、囲碁・将棋のみを放送しているチャンネル、カラオケの専門チャンネル等、多種多様なチャンネルが存在している。
さらに、衛星デジタル多チャンネル放送においては、大量のチャンネルを確保することが可能であるため、数チャンネルを用いて、見たい時間に番組を見ることができるニア・ビデオ・オン・デマンドも提供されている。
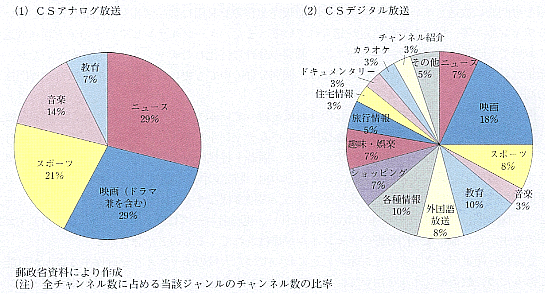
デジタル化に伴う多チャンネル放送の実現により、こうした多数事業者による多様な番組の提供、新しいサービスの提供が可能となり、視聴者の放送利用の選択肢も更に拡大することとなる。
1 ソフト制作構造の変化
(1) ソフト制作環境の動向
多メディア・多チャンネル化の進展により放送ソフトに対するニーズが増加するに伴い、放送ソフトの制作・供給における放送番組制作事業者の重要性が高まることが予想される。良質で多量なソフトの提供には、ソフト制作能力の向上が必要で、そのための環境整備が望まれている。
(2) 放送番組制作事業者の現状
(主要業務)
放送番組制作事業者の主な業務として、テレビ番組、テレビCM、ビデオソフト等の企画・制作がある。最も売上げの大きい業務が、「テレビ番組の企画・制作」である会社は、57.8%で、「テレビCMの企画・制作」を入れると、67.5%となり、テレビ放送に大きく依存していることが分かる。
(経営規模)
資本金について見ると、3,000万円未満の会社が75%程度、8割以上の会社が5,000万円未満の中小規模である。6年度の売上高について見ると、1億円以上、5億円未満の会社が半数近くを占めており、1社当たりの年間売上高は、5億円弱となっている。
(財政基盤(資金調達手段))
放送番組制作事業者の資金調達は、不動産を担保とする融資、放送事業者からの受注契約が固まっている場合の回収日までのつなぎ融資による資金調達が一般的である。
(設備の装備状況)
設備投資額の動向を見ると、5年度から6年度にかけて減少した設備投資額が、7年度の実績額から増加に転じている。
(デジタル設備導入状況と今後の見通し)
設備のデジタル化のための投資額は、7年度実績で、1社当たり平均1,680万円(投資額全体の64%)に対して、8年度見込みで、同3,771万円(同97%)と急増している。
(経営上の課題)
放送番組制作事業者は、実態調査によると、受注量の不安定さをはじめとして、資金調達面、人材面、ソフト制作設備面について、事業運営上の課題が生じている。
(放送産業の変化に向けた期待)
放送のデジタル化の進展による放送産業の今後の変化について、半数以上の放送番組制作事業者が、放送ソフトが不足し、質の低下が起こるという危惧を持ちながら、一方では、放送と通信の融合化が進展し、新しいサービスや事業が誕生するという期待を抱いている。
(今後の事業戦略)
今後の放送番組制作事業者の事業戦略として、最も力を入れたい事業内容は、国内地上放送向け番組制作及び販売が44%と多いが、衛星デジタル多チャンネル放送向け番組の制作及び販売がパッケージ商品(ビデオ等)化とともに、約10%ずつと上位に挙がっている。
2 ソフト流通構造の変化
(1) ソフト流通の現状
放送ソフトの流通構造は、単一メディアによる利用形態から、ワンソース・マルチユースという形態に変化してきている。
(2) 流通市場規模(一次・二次利用)
7年度の放送ソフトの流通市場規模を推計すると、総流通量1,514億時間(対4年度比7.5%増)、金額41,103億円(対4年度比18.1%増)である(第30図参照)。
マルチユースの進展状況を見ると、テレビ番組の二次利用は、4年度と比較して18.8%増となっている。二次利用の内訳を見ると、ビデオ販売、レンタルビデオでの利用が大きく伸びている(第30図参照)。
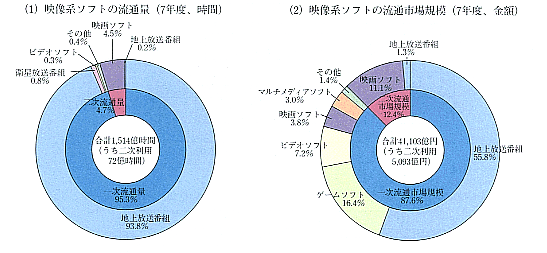
| 映画年鑑、日本民間放送年鑑,NHK年鑑,CATV年鑑、情報メディア白書、月刊トイジャーナルマルチメディア白書、レジャー白書、日本ビデオ協会統計調査報告書、ビデオレンタル店実態調査報告書、各放送局の番組表等から推計により作成。 (3)〜(5)の4年度の数値は、「徹底研究メディアソフト」より作成。 (注)二次利用は、異なるメディアでソフトを使用した場合をさす。同じメディアでの再放送は、一時利用とみなす。 |
| 一次・二次別 (億時間・億円) |
一次流通市場 | 二次流通市場 | ||
| 流通量 | 市場規模 | 流通量 | 市場規模 | |
| 映画ソフト | 1.9 | 1,579 | 69.0 | 4,576 |
| ビデオソフト | 4.3 | 2,967 | 0.0 | 0 |
| 地上放送番組 | 1,420.6 | 22,925 | 2.9 | 517 |
| 衛星放送番組 | 11.4 | 493 | 0.0 | 0 |
| CATV番組 | 1.7 | 75 | 0.0 | 0 |
| ゲームソフト | 2.4 | 6,751 | 0.0 | 0 |
| マルチメディアソフト | 0.2 | 1,220 | 0.0 | 0 |
| 映像ソフト 計 | 1,442.5 | 36,010 | 71.9 | 5,093 |
| メディア別 (億時間・億円) |
地上放送 | 衛星放送 | CATV | ビデオ販売 | レンタルビデオ | 映画 | ||||||
| 流通量 | 市場規模 | 流通量 | 市場規模 | 流通量 | 市場規模 | 流通量 | 市場規模 | 流通量 | 市場規模 | 流通量 | 市場規模 | |
| 映画ソフト | 56.9 | 1,060 | 1.3 | 135 | 2.0 | 94 | 0.2 | 984 | 8.6 | 2,303 | 1.9 | 1,579 |
| ビデオソフト | 0.6 | 1,482 | 3.7 | 1,485 | ||||||||
| 地上放送番組 | 1,420.6 | 22,925 | 2.1 | 69 | 0.0 | 138 | 0.8 | 309 | ||||
| 衛星放送番組 | 11.4 | 493 | ||||||||||
| CATV番組 | 1.7 | 75 | ||||||||||
| ゲームソフト | ||||||||||||
| マルチメディアソフト | ||||||||||||
| 映像ソフト 計 | 1,477.5 | 23,985 | 14.8 | 698 | 3.7 | 169 | 0.8 | 2,604 | 13.1 | 4,098 | 1.9 | 1,579 |
3 ソフト制作、流通環境の整備に向けた課題と行政への要望
今後の放送番組制作業の運営に際し行政に望むこととして、二次利用を促進するための権利処理ルールの確立等の環境整備、資金調達を容易化するような仕組みの整備、人材育成に対する支援、ソフト制作用機材の標準化、二次利用が可能となるようなソフト流通市場環境の整備の順に挙げられている(第31図参照)。
多メディア・多チャンネル時代の到来は制作事業者にとって大きな転換期であるが、創造性あふれる個性豊かなソフトを制作していくには地上放送事業者との間に対等なパートナーシップの確立が必要であり、そのための制作面・流通面での環境整備が望まれている。
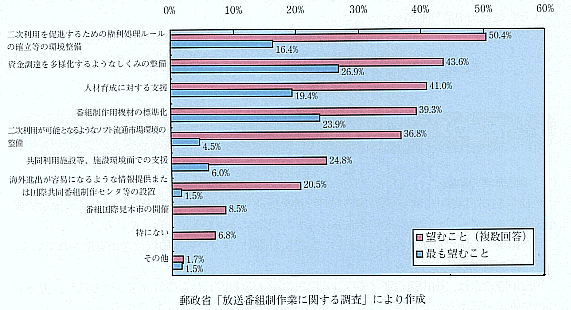
1 放送のグローバル化の動向
激動する国際情勢の中で、諸外国の対日理解を促進するとともに在外邦人に対して必要な情報を提供するため、我が国からの国際放送の果たす役割は極めて重要となっている。8年度末現在、NHKによる短波国際放送及び映像国際放送が実施されている。
在日外国人の増加等に伴う外国語による情報提供ニーズの高まりを背景に、FMによる外国語放送が7年2月に制度化された。8年度末現在、大阪市(大阪府)等及び東京都特別区等を放送区域とする2局で放送を実施している。
2 テレビ番組の輸出入の動向
我が国のテレビ番組の輸出入額を推計すると、7年度のテレビ番組の輸出金額は、53億円(対前年度比16.4%増)であり、増加を続けている。また、輸入金額は、248億円(対前年度比25.3%増)であった(第32図参照)。
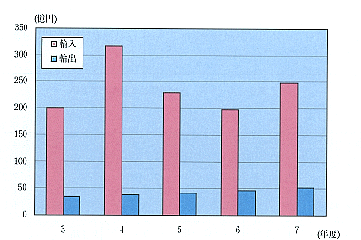
| 「国際収支月報」(日本銀行)、日本銀行資料、郵政省調査等により作成 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 輸 入 | 200 | 318 | 230 | 198 | 248 |
| 輸 出 | 33 | 37 | 41 | 47 | 53 |
7年度のテレビ番組の輸出について民放キー局5局に対して調査を行ったところ、輸出先で最も多い地域はアジアで47.3%、2位が北米で25.7%となっている(第33図参照)。また、テレビ番組の輸入に関して番組時間を調査したところ、地上放送では、外国制作番組の割合は、5.7%であり、制作地域では、圧倒的に米国が多く86.2%となっている。これに対して、衛星放送では、外国制作番組の割合が31.1%と高く、地域別では、米国が72.4%となっている。
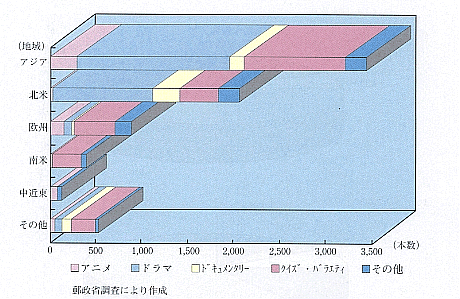
3 グローバルなメディア産業の展開
(1) 本邦企業による海外におけるプロジェクト
3年より、欧州及び北米地域において、日系企業の出資による現地法人が「TVジャパン事業」として、衛星を利用し我が国の番組の放送を行っている。また、JET社は、9年3月から、日本の番組を英語や中国等に翻訳し、衛星によりアジア10か国へ配信している。
(2) 世界的なメディア産業の再編
世界のメディア産業では、国際競争市場で優位を確保するため、グローバルな提携や買収・合併が行われている。コンテント事業者が放送事業者を買収した事例としては、ウォルト・ディズニー社による米国3大ネットワークの一つであるABCの買収が挙げられる。また、通信と放送の融合の事例としては、地域電話会社であるUSウエストによるケーブルテレビMSOのコンチネンタル・コミュニケーションの買収が挙げられる。このほか、ニューズ社やヒューズ社は、米国、欧州、アジア、南米の各地で買収・提携を進めている(第34図参照)。
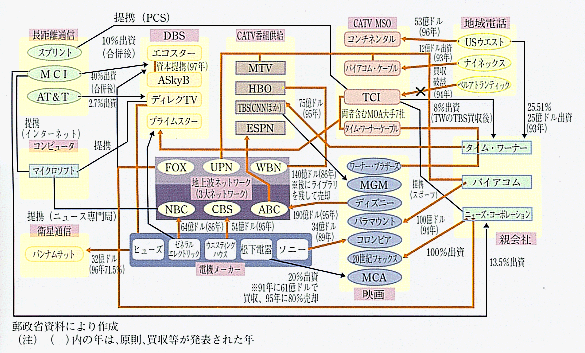
4 欧米における放送デジタル化への対応
米国では、7年11月、放送方式案がFCCに提出され、8年12月に技術基準が制定されている。実用化に向けた取組としては、8年6月実験放送が開始され、10年には、本放送が開始される見込みである。
英国では、8年4月に地上放送のデジタル化の実験が行われ、また、8年7月に成立した1996年放送法において、地上デジタル放送の導入が規定されており、10年初頭の本放送の開始に向けて準備が進められている。
5 欧米における放送関連政策の動向
世界の放送政策の動向を見ると、放送を産業という面から捉え、規制緩和を行うことにより、その振興を図るという政策が広くとられる傾向のある一方で、公序良俗や社会的弱者保護等の観点から規制を強化するという動きがある。
米国では、1996年電気通信法において、産業政策としての規制緩和の観点から、放送局の所有規制が緩和され、ケーブルテレビ事業者と地域電話会社の相互参入が認められた。また、公共の福祉の観点からの規制強化については、13インチ以上のテレビ受像機等に暴力や性的シーンの多い番組をブロックする装置(Vチップ)をつけることを義務づけた。
6 欧米における放送番組制作・流通に対する支援政策の動向
欧米においては、良質で多彩な放送番組の制作と流通を促進するため、放送番組制作者に対する金融的な支援、放送番組制作に従事する人材の育成、放送番組の二次利用の促進等の観点から、各種の政策的支援が積極的に行われている。
1 国民生活の変化の現状
(世帯における各テレビ放送加入率の推移)
郵政省の「通信利用動向調査(世帯調査)」により、家庭におけるケーブルテレビ及び衛星放送(BS放送(NHK、JSB)及びCSアナログ放送)(以後、総称する場合は「多チャンネルテレビ放送」という。)の加入率の推移を、3年から8年までの期間について見る。加入率については、各種放送ともおおむね増加傾向にあり、特にケーブルテレビの8年における加入率は大きく伸びている(対前年比2.8ポイント増)。
(衛星デジタル多チャンネル放送の加入状況)
8年6月から放送が開始された衛星デジタル多チャンネル放送の契約者数は、本放送が開始された10月以降急速に増加していることが分かる。また、8年12月末現在の契約者につき、県別世帯加入率を見ると、宮崎県、福井県、高知県、富山県、島根県の順に高くなっており、衛星デジタル多チャンネル放送の普及は、民放チャンネル数が少ない地域において伸びていることなどが読み取れる(第35図参照)。
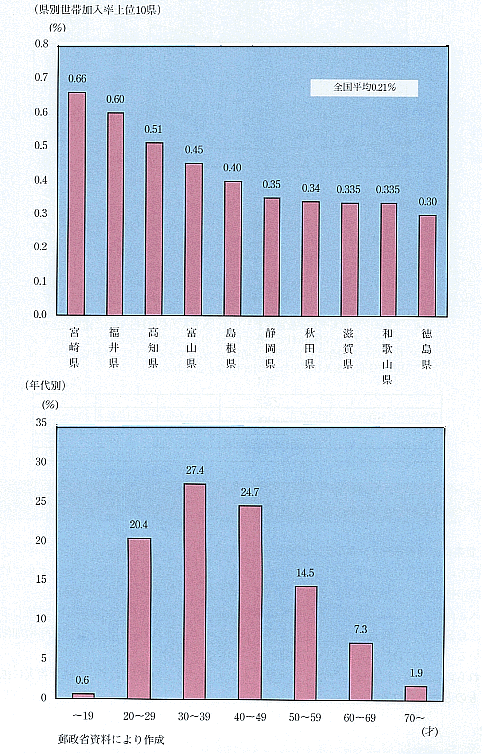
2 将来的な国民生活の変化
(個人の多チャンネルテレビ放送の利用動向)
郵政省の委託調査による「情報通信とライフスタイルに関するアンケート」(8年12月)により、多チャンネルテレビ放送に期待する具体的なメリットについて見ると、多チャンネルテレビ放送加入者も今後利用したいとする未加入者も、「自分の興味に沿った番組がある」、「様々な番組の中から選ぶことができる」を上位に挙げており、多様な番組を視聴することに対して大きな期待を寄せていることが分かる。
(放送を利用した新規サービス)
郵政省の委託調査による「情報通信とライフスタイルに関するアンケート」(8年12月)によると、テレビ放送において視聴する番組及び見てみたい番組の分野として、教育、ショッピング、ゲーム、カラオケといった、従来の番組分野ではあまり見られなかったものが挙げられており、新しい分野の番組に対する需要が高まりつつあることが分かる。
衛星デジタル多チャンネル放送では、9年2月末現在、4チャンネルにより教育専門番組が、9チャンネルにより趣味・教養番組が、30チャンネルによりテレビゲームの紹介、海外のエンタテインメント情報、競艇情報、カラオケ等の娯楽楽番組が放送されている。
インフォマーシャル番組の1週間当たりの放映時間について、各テレビ放送メディア別に見ると、既存メディアの中ではCSアナログ放送における放映時間が一番長く、合計1,345分であるのに対し、CSデジタル放送における放映時間は1万8,480分と約13.7倍となっており、新しい放送メディアの登場が、インフォマーシャル番組の提供手段として大いに活用されていることが分かる。
(利用における今後の課題)
衛星デジタル多チャンネル放送の開始に当たり、各放送事業者においては提供サービスの差別化を図る目的から、受信機についても事業者ごとに独自に機器開発が進められていた。しかしながら、視聴者の利便性の向上の観点から見ると、各受信機間に互換性がない場合、視聴者の事業者選択を制約するおそれがあるため、1台の受信機で複数の放送サービスを受けることができるシステムがあることが期待されている。このような考え方に基づき、8年11月、郵政省は、衛星デジタル多チャンネル放送事業者、受信機製造業者等で組織する(社)電波産業会(ARIB)に対し、サービス横断的に利用可能な受信機のはん用化の可能性について検討するよう要請した。これを受けてARIBでは、検討に着手している。
1 放送高度化ビジョンの策定
放送を取り巻く環境が急激に変化する中で、放送の将来イメージが見えにくくなっており、国民の放送の将来像に対する関心が高まっていることから、郵政省では、2010年の放送の将来像とそこに至るまでの道筋を、可能な限り明らかにすることを目的として、8年2月から「放送高度化ビジョン懇談会」を開催してきたが、8年6月に最終報告として「放送高度化ビジョン」が取りまとめられた。
本報告では、2010年においては、各放送メディアが連携・競合しながらケーブルテレビ・衛星放送が一層進展するとともに、すべての放送メディアのデジタル化が進むことによって、一般家庭においても数百チャンネルの放送番組が視聴できる環境が実現していることを想定し、その実現のために今後取り組むべき課題について提言している。
2 地上放送のデジタル化に向けた取組
国民に最も身近な基幹メディアである地上放送のデジタル化は、マルチメディア社会の実現には必須であるとともに、電波資源の有効利用を図ることを可能とする。また、放送を取り巻く動きが急速に変化していることから、地上デジタル放送が2000年以前に開始できるよう、放送方式、チャンネルプランの策定、制度整備等を行っていくこととしている。
3 BS放送のデジタル化の推進
放送衛星(BS)を利用した放送については、8年7月から「衛星デジタル放送技術検討会」を開催し、BS−4後発機段階での衛星デジタル放送技術の動向につき具体的な検討を行った。また、具体的な利用方法及び放送方式については、8年10月から「BS−4後発機検討会」において検討を行ってきたが、9年2月、 BS−4後発機段階での放送方式としては、多様な方式が可能となるデジタル方式が適当であり、
BS−4後発機段階での放送方式としては、多様な方式が可能となるデジタル方式が適当であり、 その放送についてはデジタルHDTVを中心とすることが適当であるとする報告を取りまとめた。
その放送についてはデジタルHDTVを中心とすることが適当であるとする報告を取りまとめた。
4 衛星デジタル多チャンネル放送の開始
通信放送を利用した放送(CS)については、8年2月にCSデジタル多チャンネル放送のマスメディア集中排除原則の緩和によって制度面の整備が行われ、8年6月から衛星デジタル多チャンネル放送としてサービスが開始された。
1 放送革命の意義と今後の展望
(1) 産業の変化
放送事業においては、デジタル化に伴う多チャンネル化の動きにより、新規参入が活発化している。現在約3兆円である放送事業の市場規模については、こうした、多チャンネル放送事業の開始に伴う多数の新規参入やサービスの増加等により、その拡大が期待される。現状を見ると、市場全体に占める地上放送(NHK、民放)のシェアは7年度において75.4%と大きいが、衛星放送、ケーブルテレビといった有料放送は2桁台の成長を続けており、そのシェアも3年度3.6%から7年度には8.0%へ拡大している。
また、放送事業への新規参入の増加は、こうした市場規模の拡大とともに、複数メディアによる競争の促進につながるものと想定される。今後、放送事業者には、放送関連事業や通信事業等を含め、幅広い視野を持った経営が必要とされてくるものと考えられる。既にケーブルテレビ事業者においては、インターネット接続サービスやホームセキュリティサービス等、そのネットワーク網を生かした通信事業への参入が見られている。
また、デジタル化により放送が通信ネットワークと共通の技術基盤を持つことにより、通信と並び新たなネットワーク基盤として活用されることが期待される。教育、娯楽、ショッピング等のアプリケーションを利用するための新たなインフラとして、放送が果たす役割は拡大していくことが想定される。
一方、こうした放送事業における変化の動きは、他の放送関連産業にも波及する影響力を有している。デジタル化に伴う多チャンネル化や高画質化の動きは、これに対応した放送ソフトに対する需要を増大させることにより、放送番組制作業の市場規模拡大に波及していくものと期待される。
(2) 生活様式の変化
多チャンネル化は、国民生活における放送利用の根本的な変化をもたらすものとなる。
第一に、放送は不特定多数に向けた総合番組中心の一方向の伝達という従来の枠組とともに、多彩な専門性を有した番組の伝達という側面を持つことになる。この結果、視聴者は、番組を無料で視聴する従来型の「受動的視聴」に加え、自分の嗜好に合った専門的な番組を対価を払って視聴する「能動的視聴」を選択することも可能となる。
第二に、多チャンネル放送により自分の生活時間に合わせた放送の視聴も可能となる。視聴者は、自分の嗜好にあった専門分野の番組をいつでも視聴できるほか、多チャンネルを生かしたニア・ビデオ・オンデマンドを利用することにより、映画等をほぼ自分の希望する時間に視聴することも可能となるのである。
第三に、視聴者は放送をインフラとし、多様なニーズに合った新たなサービスを受けることも可能となる。ショッピングの分野では、商品に関する機能や実際に利用している様子を放送することにより購入の申込みを受け付けるインフォマーシャルの放送が活発化している。CSデジタル多チャンネル放送においては、地上放送やBS放送等に比較して大量のショッピング番組が放送されているが、情報の受信のみならず、注文及び代金の決済に至る一連の処理がデジタル受信機の機能により実現される。
第四には、放送がデジタル化されることに伴い、通信ネットワークと共通の基盤を利用したマルチメディアサービスの可能性が広がることとなる。将来的には、受信機を利用して、放送を通じたデータの入手、加工・編集等を行うことも可能となるものと予想される。
(3) グローバル化の進展
放送分野におけるグローバルなメディアの再編が起きている中で、我が国においても、海外資本の我が国の放送事業への流入、我が国資本による海外の放送分野への進出が活発化することが予想される。
現在、我が国においては、衛星デジタル多チャンネル放送において、米国企業との共同出資によりディレクTVジャパンが設立されているほか、JSkyB構想も発表されている。
一方、多チャンネル化に伴う放送ソフトの世界的な不足に対応して、我が国放送ソフトの海外での利用、海外ソフトの我が国における利用が更に活発化し、国際的な番組の交流が進展することが想定される。既に我が国の放送番組は、ドラマやアニメーション等が諸外国においても高い評価を得ており、こうした動きは更に活発化することが予想される。
2 放送革命に向けた課題
放送分野における変革の動きは、将来に向けた多くの可能性とともに、様々な課題も包含しており、こうした課題について、今後、適切かつ早急な対応を図ることが必要とされる。
(1) 放送技術に関する課題
放送革命の進展は急速な技術革新を背景としたものであるが、今後も更なる放送の高度化のために積極的な技術開発を推進することが必要である。8年6月から実現されている衛星デジタル多チャンネル放送に続き、BS放送のデジタル化が2000年ごろ打上げられる予定であるBS−4後発機により実現される予定であり、ケーブルテレビにも導入が計画されているほか、地上放送についてもその導入に向けた実験が実施されている。
また、こうした放送のデジタル化に伴い、様々な方式による放送サービスの提供が予想されるが、視聴者の利便性を十分確保した受信機等の技術開発等を積極的に推進していくことが必要である。さらに、我が国が相対的に優位にあるといわれるディスプレイ技術を生かし、高画質化やコンピュータとの整合性を考慮した取組も進めて行く必要がある。
(2) 放送行政の枠組に関する課題
今後の放送事業を展望する上では、伝送事業(ハード)と放送事業(ソフト)の切り分けが課題として挙げられる。伝送事業と放送事業とを分離することにより伝送施設に係る資金負担が不要となることから、放送事業(番組の制作・調達及び供給)への参入が容易になり放送事業が活性化することが期待される一方で、競争が激化し、質の低い番組の増加等が発生する恐れもある。我が国においては、現在CS放送の委託・受託制度において、ソフトとハードの切り分けを行っているが、今後、地上放送、BS放送、ケーブルテレビにおいてもこうした課題について検討を進めていく必要がある。
また、放送は通信と並ぶインフラとして、今後益々その活発な利用が見込まれるものである。そのためには、情報通信インフラの一環としての放送ネットワークの整備が必要である。郵政省では、現在、世界中で放送衛星の打上げが積極的に行われている中で、既にプラン化されている軌道に関する見直し、新たな周波数帯のプラン化等に関する国際間の調整作業を積極的に進めている。また、ケーブルテレビにおいては大容量の情報伝送を可能とする光ファイバの促進を図るため、7年度からケーブルテレビ事業者に対する特別融資制度(加入者系光ファイバ網整備特別融資制度)を行っている。
(3) 放送ソフトの振興に関する課題
多チャンネル化に伴い見込まれる番組数の不足に対処するためには、放送事業者や放送番組制作事業者が保有している番組を活発に利活用できるような、二次流通市場を整備することが必要である。そのためには、マルチメディア時代に対応した権利処理ルールの確立や集中的な権利処理を行う機関の整備等、権利処理の円滑化に関する対応が早急の課題として求められる。また、放送番組の利活用を図るとともに、増大する番組需要に対応するためには、放送番組の受信装置とパソコンとの技術方式の共通化を図ることが必要である。これにより、放送番組のパソコンでの利用、パソコンソフトの放送受信装置での利用が可能となるものである。さらに、資本・人材面において小規模事業者が大きな割合を占める放送番組制作業においては、資金調達や人材確保等を円滑に行えるような体制を整備することも大きな課題である。郵政省では、8年9月から「放送ソフトの振興に関する調査研究会」を開催し、こうした課題に関する検討を行っている。
(4) 利用格差是正に関する課題
従来、放送のチャンネル数には限りがあったことなどから、視聴覚障害者や在日外国人等は、必ずしも放送の利便を十分に享受できる状況になかったが、放送のデジタル化は、こうした方々が十分に放送の利便を受けられるような形で進められるべきである。そのためには、視聴覚障害者向けや在日外国人向けの専門放送が実現されるとともに、可能な限り多くの番組で日本語字幕放送、解説放送や複数の外国語放送が利用できる環境を整備することが望ましい。郵政省では、こうした課題に対応するため、5年度から通信・放送機構に設けた基金を原資として障害者利用円滑化法に基づく助成を実施してきたが、9年度からは、一般会計からの補助金を原資とする新たな助成制度を創設することとしている。
また、現在、地上放送が1チャンネルも視聴できない南北大東島を始めとして、地上波による放送の視聴が困難な難視聴地域が存在している中で、地域格差のない情報受信の体制を早急に整備することが必要である。衛星を利用した多チャンネル放送の開始はこうした地域格差の是正にも有効なものといえる。
(5) グローバル化に関する課題
デジタル技術の革新や、社会経済のグローバル化を背景として、放送産業においてもグローバル化が進展している。また、今後、我が国において多数事業者間の競争状態が発生することが予想されている状況において、新たなマーケットを開拓する意味で、我が国独自の番組等を生かした更に積極的な海外進出が望まれている。そのためには、国際的な放送ソフトの流通を積極化できるような流通体制の整備、著作権等の権利処理に関する国際的なルール作りを推進していく必要があると考えられる。郵政省では、映像国際放送、放送番組交流促進事業の推進等を積極的に行っている。