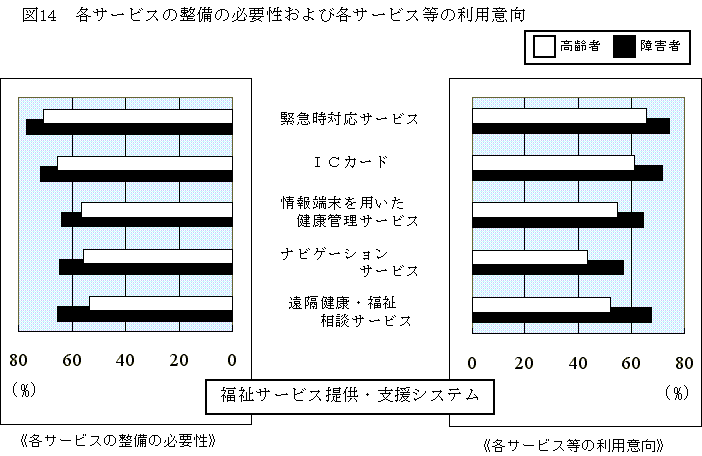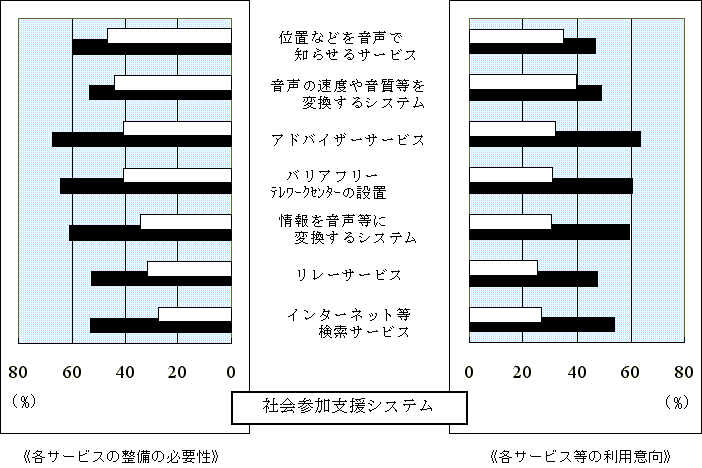第3章 ライフサポート(生活支援)情報通信システムの現状と課題につい
て
1 現状と課題
(1)現状
現在、高齢者・障害者のライフサポート(生活支援)情報通信システム
については、先進的な自治体等において、システムの導入が進められてい
る。
例えば、地方自治体においては、緊急通報システムを中心として、約
1,600のシステムが導入されている(「地方公共団体における地域情報化施
策の概要(平成9年3月自治大臣官房情報管理室)」)。
現在、先進事例として有効に機能しているシステムは、以下のように分
類される。
 福祉サービス提供・支援システム
ア 在宅健康管理システム
イ 緊急時対応システム
ウ 福祉情報等提供システム
福祉サービス提供・支援システム
ア 在宅健康管理システム
イ 緊急時対応システム
ウ 福祉情報等提供システム
 社会参加支援システム
ア 障害者向けパソコン通信ネットワーク
イ オンラインショッピング
ウ その他高齢者・障害者社会参加支援システム
(2)課題
これらのシステムは、サービス提供のための人員・費用の効率化、高齢
者・障害者の社会参加の促進等に一定の成果をあげている。
しかし、現在はモデル事業が中心であり、本格的な普及・定着を図るこ
とが今後の課題である。そのためには、個別システムごとの課題に解決を
図るとともに、全てのシステムについて共通の課題である、個人情報開示
の基準等の制度的課題、インターフェースの向上等の技術的課題の解決が
必要である。
(3)各システムの現状及び課題
社会参加支援システム
ア 障害者向けパソコン通信ネットワーク
イ オンラインショッピング
ウ その他高齢者・障害者社会参加支援システム
(2)課題
これらのシステムは、サービス提供のための人員・費用の効率化、高齢
者・障害者の社会参加の促進等に一定の成果をあげている。
しかし、現在はモデル事業が中心であり、本格的な普及・定着を図るこ
とが今後の課題である。そのためには、個別システムごとの課題に解決を
図るとともに、全てのシステムについて共通の課題である、個人情報開示
の基準等の制度的課題、インターフェースの向上等の技術的課題の解決が
必要である。
(3)各システムの現状及び課題
 在宅健康管理システム
ア サービスの種類と概要
(ア)健康相談システム(映像、音声)
要介護者宅と病院、健康管理センター、健康福祉機関間等を結び、
医者や保健婦と要介護者間の健康相談、介護情報の講習会等を行うも
の。
(付加サービス)
健康情報や介護情報に関するデータベースを構築し、当該システム
を通じた要介護者やその家族からのアクセスを可能とする。
(イ)健康管理システム
在宅の要介護者の健康データ(血圧、脈拍等)を定期的に健康管理
センター等に送信。保健婦がデータを見ながら健康相談、健康指導等
を行うもの。(ア)の発展形態。
(ウ)個人健康データ、ケア記録等の共有システム
(イ)の健康管理システム等で得たデータやケア記録等をデータベー
ス化し、各保健福祉関係機関でデータを共有。例えば訪問看護や在宅
介護サービス等の際にそのデータを参照してきめの細かいサービスの
提供を実現するなど、介護、福祉サービスの高度化を図るもの。介護
記録のデータベースは診療報酬の効率的な処理にも貢献。
(発展形態)
訪問看護婦等がもつ携帯端末と接続可能。要介護者宅で、健康デー
タの読み出し、入力ができる。
イ システムの形態
(ア)健康相談システム
電話、又は市販のテレビ会議システムを利用したシステムが一般的。
(イ)健康管理システム
健康管理用の専用データ端末を用いてデータ収集。
データは、CATV網を利用して伝送。
(ウ)個人健康データ、ケア記録等の共有システム
データベースを、保健福祉センター等に設置。そのデータベースと
健康福祉関連機関をオンラインで結び、各機関での参照・更新を可能
とするシステムが一般的。
ICカードや光カード等のデータカードに個人基本情報、緊急情報、
病歴情報等を一元的に管理する例もあり。
ウ 効果
(ア)健康相談システム
一人暮らしの高齢者等に、孤立していない安心感と健康に対する意
識の高まりが見られた。
(イ)健康管理システム
健康異常の早期発見が可能となった。
訪問が難しい地域の一人暮らしの高齢者の健康状況の把握、安否確
認が可能となった。
医療機関までの距離が遠い集落等において、医療機関に行く回数の
削減を通じた医療関連コストの削減が図られた。
(ウ)個人健康データ、ケア記録等の共有システム
個人情報の蓄積、共有化による個人のニーズに応じた一元的・効果
的ケアが可能になった。
データカードを行政ネットワークと接続することで行政サービスが
向上した例もある。
エ 主な問題点
上記(ア)〜(ウ)のシステム共通の問題点として以下のものがある。
(ア)設備上の問題
端末が大きすぎ、小型化が必要(訪問看護婦持参の携帯端末、高齢
者宅設置端末等)
データカードリーダーなど、バージョンアップごとに交換が必要な
設備がある。
(イ)システムの運用上の問題
高齢者が機械にあがり、血圧の正確な測定等が困難となることがあ
る。
システム運用にかかる要員不足のため、必要な頻度での健康相談等
が困難。
介護者が定期的に健康データを伝送してこないことがある。
(ウ)コスト上の問題
機器が高額である。(現在はモデル事業で行っているものがほとん
ど)
(エ)システムの操作性
高齢者が扱う端末機器の操作性が問題。
オ 今後の展望
(ア)システム構築の順序
健康相談システム導入→健康管理システム機能の付加→保健福祉関
係機関での情報の共有という順序でシステム構築が進展する。
ケア記録のデータベース化が別々に進行し、両者が統一化されると
いう順序でシステムの構築がなされることが予想される。
また、行政の広域化に伴い、将来的にはこれらのシステム同士が接
続される可能性がある。
更に、これらのシステムは、ケアマネジメントシステムの導入に伴
い、その重要性を増すことが考えられる。一方で、現存のシステムに
ついては、介護保険制度対応に更新する必要がある。
(イ)それぞれのシステムごとの展望とそれに伴う課題
A 健康相談システム
低廉化、デジタル回線の普及と共に、テレビ会議システム、テレ
ビ電話の利用が普及が進む。
B 健康管理システム
健康データの収集技術の高度化
→モニタリングを感じさせない技術とモニタリング項目の多様化が
必要となる。
C 個人データ等の保健福祉機関間での共有
データ収集の対象拡大と、共有化されたデータの有効利用の方策
の確立。
→その際、個人情報の管理の方法についての方針を決定する必要が
ある。
在宅健康管理システム
ア サービスの種類と概要
(ア)健康相談システム(映像、音声)
要介護者宅と病院、健康管理センター、健康福祉機関間等を結び、
医者や保健婦と要介護者間の健康相談、介護情報の講習会等を行うも
の。
(付加サービス)
健康情報や介護情報に関するデータベースを構築し、当該システム
を通じた要介護者やその家族からのアクセスを可能とする。
(イ)健康管理システム
在宅の要介護者の健康データ(血圧、脈拍等)を定期的に健康管理
センター等に送信。保健婦がデータを見ながら健康相談、健康指導等
を行うもの。(ア)の発展形態。
(ウ)個人健康データ、ケア記録等の共有システム
(イ)の健康管理システム等で得たデータやケア記録等をデータベー
ス化し、各保健福祉関係機関でデータを共有。例えば訪問看護や在宅
介護サービス等の際にそのデータを参照してきめの細かいサービスの
提供を実現するなど、介護、福祉サービスの高度化を図るもの。介護
記録のデータベースは診療報酬の効率的な処理にも貢献。
(発展形態)
訪問看護婦等がもつ携帯端末と接続可能。要介護者宅で、健康デー
タの読み出し、入力ができる。
イ システムの形態
(ア)健康相談システム
電話、又は市販のテレビ会議システムを利用したシステムが一般的。
(イ)健康管理システム
健康管理用の専用データ端末を用いてデータ収集。
データは、CATV網を利用して伝送。
(ウ)個人健康データ、ケア記録等の共有システム
データベースを、保健福祉センター等に設置。そのデータベースと
健康福祉関連機関をオンラインで結び、各機関での参照・更新を可能
とするシステムが一般的。
ICカードや光カード等のデータカードに個人基本情報、緊急情報、
病歴情報等を一元的に管理する例もあり。
ウ 効果
(ア)健康相談システム
一人暮らしの高齢者等に、孤立していない安心感と健康に対する意
識の高まりが見られた。
(イ)健康管理システム
健康異常の早期発見が可能となった。
訪問が難しい地域の一人暮らしの高齢者の健康状況の把握、安否確
認が可能となった。
医療機関までの距離が遠い集落等において、医療機関に行く回数の
削減を通じた医療関連コストの削減が図られた。
(ウ)個人健康データ、ケア記録等の共有システム
個人情報の蓄積、共有化による個人のニーズに応じた一元的・効果
的ケアが可能になった。
データカードを行政ネットワークと接続することで行政サービスが
向上した例もある。
エ 主な問題点
上記(ア)〜(ウ)のシステム共通の問題点として以下のものがある。
(ア)設備上の問題
端末が大きすぎ、小型化が必要(訪問看護婦持参の携帯端末、高齢
者宅設置端末等)
データカードリーダーなど、バージョンアップごとに交換が必要な
設備がある。
(イ)システムの運用上の問題
高齢者が機械にあがり、血圧の正確な測定等が困難となることがあ
る。
システム運用にかかる要員不足のため、必要な頻度での健康相談等
が困難。
介護者が定期的に健康データを伝送してこないことがある。
(ウ)コスト上の問題
機器が高額である。(現在はモデル事業で行っているものがほとん
ど)
(エ)システムの操作性
高齢者が扱う端末機器の操作性が問題。
オ 今後の展望
(ア)システム構築の順序
健康相談システム導入→健康管理システム機能の付加→保健福祉関
係機関での情報の共有という順序でシステム構築が進展する。
ケア記録のデータベース化が別々に進行し、両者が統一化されると
いう順序でシステムの構築がなされることが予想される。
また、行政の広域化に伴い、将来的にはこれらのシステム同士が接
続される可能性がある。
更に、これらのシステムは、ケアマネジメントシステムの導入に伴
い、その重要性を増すことが考えられる。一方で、現存のシステムに
ついては、介護保険制度対応に更新する必要がある。
(イ)それぞれのシステムごとの展望とそれに伴う課題
A 健康相談システム
低廉化、デジタル回線の普及と共に、テレビ会議システム、テレ
ビ電話の利用が普及が進む。
B 健康管理システム
健康データの収集技術の高度化
→モニタリングを感じさせない技術とモニタリング項目の多様化が
必要となる。
C 個人データ等の保健福祉機関間での共有
データ収集の対象拡大と、共有化されたデータの有効利用の方策
の確立。
→その際、個人情報の管理の方法についての方針を決定する必要が
ある。
 緊急時対応システム
緊急時対応システムとしては、「緊急通報システム」と「行方不明老
人等安全確認システム」の2システムが典型的。
ア 緊急通報システム
(ア)サービスの概要
在宅老人等に緊急状態が発生したとき、通信回線網を介して介護セ
ンター、親戚等に通報し、受けた者は電話により通報者の状況を把握
した後、必要に応じ消防等に連絡する等緊急事態に対応するもの。
(イ)システムの形態
いずれも公衆回線網(アナログ電話回線、ISDN)又はCATV
網を利用。
A 手動方式
緊急時は専用端末に付加する緊急通報ボタンを押下、または端末
から離れている場合は通常身につけているペンダント等遠隔通報器
の緊急通報ボタンを押すもの
B 自動方式
一定時間通常の日常生活と異なる行動パターン(水道を使わない、
湯を沸かさない等)が生じた時に異常が発生したとして緊急通報を
送信
(ウ)システムの効果
一人暮らしの高齢者及び遠隔地の家族等にとって、通信網により常
時連絡体制がとれているという安心感が得られる。
専用端末で緊急通報信号に自動的に個人の識別情報を付加して通報
することにより、早急かつ適切な処置を行うことが可能となる。
(エ)今後克服すべき課題
A 通報器の小型化。
B 誤操作を設備側で防ぐ機能の付加。
C 適切な使用基準の定着。(必要な時に我慢して通報しない、軽微
な事態でもすぐ通報するなどの例が多発)
(オ)今後の展望
緊急通報システムは、現在約2,000システムが稼働しているなど、広
く全国に普及している。一人暮らし老人の増加等に伴い、今後もより
広範な普及が予想される。
→端末の誤操作を防ぐ操作性の向上が望まれる。
手動の場合の誤動作、使用基準の困難性等から、非常時の測定技術
の向上、常時監視装置(赤外線カメラの利用が考えられる。)等の導
入等とともに、全体としては自動方式に移行する方向になると思われ
る。
現在屋内での利用がほとんどであるが、今後は屋外でも機能するシ
ステムの導入、普及が望まれる。
→広域的な展開を前提としたシステムの標準化が必要。
その場合、行方不明老人等安全確認システムとのシステム融合も考
えられる。
また、福祉サービスの高度化の観点から、介護支援システムと接続
され、緊急時の記録が要介護者情報としてデータベース化されること
も考えられる。
イ 行方不明老人等安全確認システム
(ア)サービスの概要
徘徊癖のある老人等が外出し行き先が不明となった場合、老人等が
所持する現在の位置確認が可能な通信端末によりその情報を無線回線
網により家族等の探索者に伝送し、その情報をもとに探索者は迅速に
現場に出向き保護する。
(イ)システムの形態
A PHS利用システム
徘徊老人等が所持するPHSの位置情報を探索者に伝送すること
により徘徊者の位置を確認する方式。
B GPS利用システム
GPS衛星からの位置情報を、徘徊老人等が所持する端末(PH
S改良)を用いて、探索者に伝送することにより徘徊者の位置を確
認する方式。
(ウ)システムの効果
これまでの人手に頼っていた探索・保護方法に比べ、少人数で、か
つ、短時間での探索が可能となる。これにより介護者の経済的、心理
的負担の軽減、徘徊老人の安全の確保が期待されている。
(エ)今後克服すべき課題
A 徘徊老人等に所持させる端末の小型・軽量化。
B 徘徊老人等に所持させる端末は、身に付けたものをすぐ脱ぎ捨て
る習性等を考慮した捨て去られることのない形状、装着感のもの。
C 徘徊者及びその家族のプライバシーの確保。
(オ)今後の展望
当システムは、未だ実験段階であり、本格的な実用には至っていな
い。
しかし、徘徊老人問題の深刻さから当システムに対する期待は大き
く、研究開発等による、上記課題克服が望まれる。
当システムは、システムの導入地域をまたいで徘徊老人が移動して
しまうと役に立たなくなることから、システム同士の接続、広域化が
予想される。
→広域的な展開を前提としたシステムの標準化が必要。
その場合、今後普及が期待されているGISシステムの利用が効果
的であると考えられる。
また、サービス提供の形態として、個人ナビゲーションシステムや
広域対応の緊急通報システムとの融合化も考えられる。
緊急時対応システム
緊急時対応システムとしては、「緊急通報システム」と「行方不明老
人等安全確認システム」の2システムが典型的。
ア 緊急通報システム
(ア)サービスの概要
在宅老人等に緊急状態が発生したとき、通信回線網を介して介護セ
ンター、親戚等に通報し、受けた者は電話により通報者の状況を把握
した後、必要に応じ消防等に連絡する等緊急事態に対応するもの。
(イ)システムの形態
いずれも公衆回線網(アナログ電話回線、ISDN)又はCATV
網を利用。
A 手動方式
緊急時は専用端末に付加する緊急通報ボタンを押下、または端末
から離れている場合は通常身につけているペンダント等遠隔通報器
の緊急通報ボタンを押すもの
B 自動方式
一定時間通常の日常生活と異なる行動パターン(水道を使わない、
湯を沸かさない等)が生じた時に異常が発生したとして緊急通報を
送信
(ウ)システムの効果
一人暮らしの高齢者及び遠隔地の家族等にとって、通信網により常
時連絡体制がとれているという安心感が得られる。
専用端末で緊急通報信号に自動的に個人の識別情報を付加して通報
することにより、早急かつ適切な処置を行うことが可能となる。
(エ)今後克服すべき課題
A 通報器の小型化。
B 誤操作を設備側で防ぐ機能の付加。
C 適切な使用基準の定着。(必要な時に我慢して通報しない、軽微
な事態でもすぐ通報するなどの例が多発)
(オ)今後の展望
緊急通報システムは、現在約2,000システムが稼働しているなど、広
く全国に普及している。一人暮らし老人の増加等に伴い、今後もより
広範な普及が予想される。
→端末の誤操作を防ぐ操作性の向上が望まれる。
手動の場合の誤動作、使用基準の困難性等から、非常時の測定技術
の向上、常時監視装置(赤外線カメラの利用が考えられる。)等の導
入等とともに、全体としては自動方式に移行する方向になると思われ
る。
現在屋内での利用がほとんどであるが、今後は屋外でも機能するシ
ステムの導入、普及が望まれる。
→広域的な展開を前提としたシステムの標準化が必要。
その場合、行方不明老人等安全確認システムとのシステム融合も考
えられる。
また、福祉サービスの高度化の観点から、介護支援システムと接続
され、緊急時の記録が要介護者情報としてデータベース化されること
も考えられる。
イ 行方不明老人等安全確認システム
(ア)サービスの概要
徘徊癖のある老人等が外出し行き先が不明となった場合、老人等が
所持する現在の位置確認が可能な通信端末によりその情報を無線回線
網により家族等の探索者に伝送し、その情報をもとに探索者は迅速に
現場に出向き保護する。
(イ)システムの形態
A PHS利用システム
徘徊老人等が所持するPHSの位置情報を探索者に伝送すること
により徘徊者の位置を確認する方式。
B GPS利用システム
GPS衛星からの位置情報を、徘徊老人等が所持する端末(PH
S改良)を用いて、探索者に伝送することにより徘徊者の位置を確
認する方式。
(ウ)システムの効果
これまでの人手に頼っていた探索・保護方法に比べ、少人数で、か
つ、短時間での探索が可能となる。これにより介護者の経済的、心理
的負担の軽減、徘徊老人の安全の確保が期待されている。
(エ)今後克服すべき課題
A 徘徊老人等に所持させる端末の小型・軽量化。
B 徘徊老人等に所持させる端末は、身に付けたものをすぐ脱ぎ捨て
る習性等を考慮した捨て去られることのない形状、装着感のもの。
C 徘徊者及びその家族のプライバシーの確保。
(オ)今後の展望
当システムは、未だ実験段階であり、本格的な実用には至っていな
い。
しかし、徘徊老人問題の深刻さから当システムに対する期待は大き
く、研究開発等による、上記課題克服が望まれる。
当システムは、システムの導入地域をまたいで徘徊老人が移動して
しまうと役に立たなくなることから、システム同士の接続、広域化が
予想される。
→広域的な展開を前提としたシステムの標準化が必要。
その場合、今後普及が期待されているGISシステムの利用が効果
的であると考えられる。
また、サービス提供の形態として、個人ナビゲーションシステムや
広域対応の緊急通報システムとの融合化も考えられる。
 福祉情報等提供システム
ア サービスの概要
住民の福祉の増進、生活向上等のために役立つ福祉情報、生活情報、
行政情報等を、地方自治体、社会福祉協議会等がオープンなネットワー
クであるインターネット、FM放送等により提供するもの。
(参考:提供される情報)
(ア)デイサービスの空き状況
(イ)各種行政情報
(ウ)求人情報
(エ)ボランティア情報 等
イ システムの概要
(ア)提供者側
インターネットのホームページによる情報提供。
(イ)利用者側
A 住民への端末の貸し出し
B 公共施設等への端末の配置
その他、コミュニティFM放送による情報提供も計画中。
ウ 効果
公共施設等に端末が配備される場合等で、相当のアクセスがあり効果
が見られる例があったが、住民への端末貸出によるものはアクセス数は
伸び悩んでいる。
一方、当システム開始により、各種情報のデータベース化が進展、提
供される情報そのものの質的向上が図られるという効果も見られた。
エ 問題点
当システムの現状での問題点は以下のとおり。
(ア)インターネットの普及率の低さ。
(イ)高齢者・障害者にとって魅力のある情報が少ない。
オ 今後の展望
現状では一般家庭へのインターネット普及率が未だ低いため、既存の
メディアによる情報提供の代替手段とはなっていないが、「インター
ネットは今後の普及・発展が期待されること」、「福祉情報等の情報提
供の必要性」を鑑みれば、インターネットを利用したこのようなシステ
ムは普及していくと考えられる。
その際、以下のような点に配慮することが必要。
(ア)コンテントの内容の充実を図ること
(イ)受け手の情報リテラシーの向上を図ること
(ウ)メディア変換機能の提供等により障害を持つ人も利用できる機能を
備えること。
福祉情報等提供システム
ア サービスの概要
住民の福祉の増進、生活向上等のために役立つ福祉情報、生活情報、
行政情報等を、地方自治体、社会福祉協議会等がオープンなネットワー
クであるインターネット、FM放送等により提供するもの。
(参考:提供される情報)
(ア)デイサービスの空き状況
(イ)各種行政情報
(ウ)求人情報
(エ)ボランティア情報 等
イ システムの概要
(ア)提供者側
インターネットのホームページによる情報提供。
(イ)利用者側
A 住民への端末の貸し出し
B 公共施設等への端末の配置
その他、コミュニティFM放送による情報提供も計画中。
ウ 効果
公共施設等に端末が配備される場合等で、相当のアクセスがあり効果
が見られる例があったが、住民への端末貸出によるものはアクセス数は
伸び悩んでいる。
一方、当システム開始により、各種情報のデータベース化が進展、提
供される情報そのものの質的向上が図られるという効果も見られた。
エ 問題点
当システムの現状での問題点は以下のとおり。
(ア)インターネットの普及率の低さ。
(イ)高齢者・障害者にとって魅力のある情報が少ない。
オ 今後の展望
現状では一般家庭へのインターネット普及率が未だ低いため、既存の
メディアによる情報提供の代替手段とはなっていないが、「インター
ネットは今後の普及・発展が期待されること」、「福祉情報等の情報提
供の必要性」を鑑みれば、インターネットを利用したこのようなシステ
ムは普及していくと考えられる。
その際、以下のような点に配慮することが必要。
(ア)コンテントの内容の充実を図ること
(イ)受け手の情報リテラシーの向上を図ること
(ウ)メディア変換機能の提供等により障害を持つ人も利用できる機能を
備えること。
 障害者向けパソコン通信ネットワーク
ア 概要
パソコン通信を利用した、障害者間または障害者と健常者間での情報
交換を目的として運営されるネットワーク。
イ 活動内容
主な活動は、「パソコン通信を通じての障害者同士、あるいは健常者
との交流」と「障害者に対する情報提供」であるが、現在これら以外に、
「実際に対面しての交流会」、「障害者への機器の貸し出し、サポート
及びこれらを行うボランティアグループの運営」、「障害に対応した機
器の展示やシンポジウム」、「テレワークの仕事の紹介」の活動を行っ
ている団体が多く存在。
ウ 効果
以下のように、障害者の情報収集、社会参加に大きな効果をあげてい
る。
(ア)パソコン通信を通じて、ネット上での気軽な相談等が可能となった
ことから、障害者の情報収集が従来より容易となっている。
(イ)パソコン通信、交流会を通じた社会参加の促進
(ウ)障害者の就労の機会の増大
エ 問題点
(ア)システム面での問題点
A 情報通信端末は、まだ障害者に対応したものが少ない。
B 既存の端末についてもまだ使いづらく特別に教えることが必要で
あるが、相談に応じてくれるような機関が存在しない。
C 通信費用の負担が大きい。
(イ)運営上の問題点
A パソコン等の指導者が不足している。
B 機材が高価であり、運営が困難。
C メディア変換の際に生じる著作権コストが大きい。
オ 今後の展望
(ア)障害者ネットワークは、大きな成果をあげており、今後とも規模、
活動内容共に拡大していくものであると思われる。
具体的には、「障害者のうち情報リテラシーが低い人の参加による
参加人数の拡大」、「福祉関連の情報提供や、就労支援のためのパソ
コン講座等への活動内容の拡大」等が期待できる。
(イ)一方で、障害者ネットワークは、そのシステムをインターネット化
する構想を持っているものが多く、今後はインターネット化が進むも
のと思われる。ただし、そのための資金の確保に苦労している団体も
多いのが現状である。
障害者向けパソコン通信ネットワーク
ア 概要
パソコン通信を利用した、障害者間または障害者と健常者間での情報
交換を目的として運営されるネットワーク。
イ 活動内容
主な活動は、「パソコン通信を通じての障害者同士、あるいは健常者
との交流」と「障害者に対する情報提供」であるが、現在これら以外に、
「実際に対面しての交流会」、「障害者への機器の貸し出し、サポート
及びこれらを行うボランティアグループの運営」、「障害に対応した機
器の展示やシンポジウム」、「テレワークの仕事の紹介」の活動を行っ
ている団体が多く存在。
ウ 効果
以下のように、障害者の情報収集、社会参加に大きな効果をあげてい
る。
(ア)パソコン通信を通じて、ネット上での気軽な相談等が可能となった
ことから、障害者の情報収集が従来より容易となっている。
(イ)パソコン通信、交流会を通じた社会参加の促進
(ウ)障害者の就労の機会の増大
エ 問題点
(ア)システム面での問題点
A 情報通信端末は、まだ障害者に対応したものが少ない。
B 既存の端末についてもまだ使いづらく特別に教えることが必要で
あるが、相談に応じてくれるような機関が存在しない。
C 通信費用の負担が大きい。
(イ)運営上の問題点
A パソコン等の指導者が不足している。
B 機材が高価であり、運営が困難。
C メディア変換の際に生じる著作権コストが大きい。
オ 今後の展望
(ア)障害者ネットワークは、大きな成果をあげており、今後とも規模、
活動内容共に拡大していくものであると思われる。
具体的には、「障害者のうち情報リテラシーが低い人の参加による
参加人数の拡大」、「福祉関連の情報提供や、就労支援のためのパソ
コン講座等への活動内容の拡大」等が期待できる。
(イ)一方で、障害者ネットワークは、そのシステムをインターネット化
する構想を持っているものが多く、今後はインターネット化が進むも
のと思われる。ただし、そのための資金の確保に苦労している団体も
多いのが現状である。
 オンラインショッピング
ア サービスの概要
外出困難な高齢者・障害者が在宅で購買をできるようにするサービス。
イ システムの概要
一般のオンラインショッピングと同じであるが、端末を高齢者・障害
者の利用に配慮したシステムも一部見られる。
ウ 主な効果
今後の市場の拡大が予想されるオンラインショッピングは、高齢者・
障害者の生活支援に有効なものとなりうることが分かった。
エ 主な問題点
高齢者・障害者が使いやすいインターフェースが実現されていない。
オ 今後の展望
オンラインショッピングの普及に伴い、高齢者・障害者の利用も増加
していくことが予想される。
その場合、パソコン操作になれていない高齢者・障害者の操作に配慮
したシステム(タッチパネルの導入など)の開発が求められる。
オンラインショッピング
ア サービスの概要
外出困難な高齢者・障害者が在宅で購買をできるようにするサービス。
イ システムの概要
一般のオンラインショッピングと同じであるが、端末を高齢者・障害
者の利用に配慮したシステムも一部見られる。
ウ 主な効果
今後の市場の拡大が予想されるオンラインショッピングは、高齢者・
障害者の生活支援に有効なものとなりうることが分かった。
エ 主な問題点
高齢者・障害者が使いやすいインターフェースが実現されていない。
オ 今後の展望
オンラインショッピングの普及に伴い、高齢者・障害者の利用も増加
していくことが予想される。
その場合、パソコン操作になれていない高齢者・障害者の操作に配慮
したシステム(タッチパネルの導入など)の開発が求められる。
 その他高齢者・障害者社会参加支援システム
ア 概要
その他、以下のようにインターネット等の情報通信を利用して、高齢
者・障害者の社会参加等を行っているネットワークや活動が見られる。
(ア)インターネットを利用したボランティア活動の仲介
インターネットを用い、ボランティアを募集する団体とボランティ
ア希望者との仲介を行うもの。
(イ)マルチメディア制作等による障害者の就業支援
A 通所授産施設等の障害者に対するインターネット上における就業
支援
B 障害者を対象とし、テレビ会議システムを用いて教材ソフト等を
共有したソフト研修の実施
(ウ)障害児の学校単位での交流、自主的な学習の実施
(エ)富山県山田村における高齢者へのパソコン配布
村の全戸数の7割にパソコンを貸与し、インターネットに接続。自由
に使わせる。
(オ)郵便局における高齢者等を対象としたパソコン教室の開催
郵便局の既存の施設等の有効活用を図るとともに、地方自治体及びボ
ランティア団体等の協力を得つつ、地域の高齢者等を対象としたパソコ
ン教室を開催
イ 効果
これらの取組はインターネットのオープンネットワーク性、場所を克
服するという情報通信の特性を高齢者・障害者の社会参加、自立に生か
そうというものであり、今後、情報通信システムのインターフェース、
機能の向上に伴い、さらに広範な活動に発展していくことが予想される。
特に、障害者の就業支援の取組は、その意義に鑑み、大きく期待される
ものである。
(4)各システムに共通する一般的課題
ライフサポート(生活支援)情報通信システム活用の上での課題につい
ては、システムごとの現状で記載したとおりであるが、これらを一般的な
課題としてまとめれば以下のとおりとなる。
その他高齢者・障害者社会参加支援システム
ア 概要
その他、以下のようにインターネット等の情報通信を利用して、高齢
者・障害者の社会参加等を行っているネットワークや活動が見られる。
(ア)インターネットを利用したボランティア活動の仲介
インターネットを用い、ボランティアを募集する団体とボランティ
ア希望者との仲介を行うもの。
(イ)マルチメディア制作等による障害者の就業支援
A 通所授産施設等の障害者に対するインターネット上における就業
支援
B 障害者を対象とし、テレビ会議システムを用いて教材ソフト等を
共有したソフト研修の実施
(ウ)障害児の学校単位での交流、自主的な学習の実施
(エ)富山県山田村における高齢者へのパソコン配布
村の全戸数の7割にパソコンを貸与し、インターネットに接続。自由
に使わせる。
(オ)郵便局における高齢者等を対象としたパソコン教室の開催
郵便局の既存の施設等の有効活用を図るとともに、地方自治体及びボ
ランティア団体等の協力を得つつ、地域の高齢者等を対象としたパソコ
ン教室を開催
イ 効果
これらの取組はインターネットのオープンネットワーク性、場所を克
服するという情報通信の特性を高齢者・障害者の社会参加、自立に生か
そうというものであり、今後、情報通信システムのインターフェース、
機能の向上に伴い、さらに広範な活動に発展していくことが予想される。
特に、障害者の就業支援の取組は、その意義に鑑み、大きく期待される
ものである。
(4)各システムに共通する一般的課題
ライフサポート(生活支援)情報通信システム活用の上での課題につい
ては、システムごとの現状で記載したとおりであるが、これらを一般的な
課題としてまとめれば以下のとおりとなる。
 技術上の課題
ア インターフェース、使い勝手の向上
様々な障害をもつ高齢者・障害者自らが情報の入出力等を行うケース
が多く発生することから、様々な障害に対応でき、かつ、例えばテレビ
並の使いやすさを実現したインターフェースが必要となる。
イ システムの標準化と相互接続性の確保
介護支援システム、緊急通報システム、行方不明老人等安全確認シス
テム等、広域での運営が予想されるものの、現状では相互接続が困難で
あるシステムについては、その仕様の標準化もしくは相互接続性の確保
を図ることが求められる。
ウ 機能の高度化
行方不明老人等安全確認システムの端末の小型化、健康データの収集
を人に感じさせない自動データ収集システムの実現など、システムをよ
り有用にするために機能の高度化を図る必要がある。その際、たとえば、
中軽度の人たちに対する視点を踏まえたシステムの開発も視野に入れる
必要がある。
エ プライバシー確保のための技術
介護支援システム、行方不明老人等安全確認システムなどでは個人情
報がネットワーク上で受発信されるため、認証技術等セキュリティ技術
の確立が必要。その際、どの程度までセキュリティ機能を求めるかにつ
いても検討が必要。
技術上の課題
ア インターフェース、使い勝手の向上
様々な障害をもつ高齢者・障害者自らが情報の入出力等を行うケース
が多く発生することから、様々な障害に対応でき、かつ、例えばテレビ
並の使いやすさを実現したインターフェースが必要となる。
イ システムの標準化と相互接続性の確保
介護支援システム、緊急通報システム、行方不明老人等安全確認シス
テム等、広域での運営が予想されるものの、現状では相互接続が困難で
あるシステムについては、その仕様の標準化もしくは相互接続性の確保
を図ることが求められる。
ウ 機能の高度化
行方不明老人等安全確認システムの端末の小型化、健康データの収集
を人に感じさせない自動データ収集システムの実現など、システムをよ
り有用にするために機能の高度化を図る必要がある。その際、たとえば、
中軽度の人たちに対する視点を踏まえたシステムの開発も視野に入れる
必要がある。
エ プライバシー確保のための技術
介護支援システム、行方不明老人等安全確認システムなどでは個人情
報がネットワーク上で受発信されるため、認証技術等セキュリティ技術
の確立が必要。その際、どの程度までセキュリティ機能を求めるかにつ
いても検討が必要。
 情報基盤整備に関する課題
ア 情報通信インフラの整備
テレビ電話等を利用した介護支援システム等の実現には、情報通信イ
ンフラの整備が不可欠。CATV、ISDN等の早期整備が高度なライ
フサポート(生活支援)情報通信システムの実現には不可欠。更に高速
大容量の情報通信インフラの整備が必要。
イ 費用の低廉化
通信費用及びシステムの設置費用が、例えばテレビ電話を用いた個人
宅と介護施設とを結んだ健康相談システムの普及が進展しない理由の一
つとなっているなど費用の低廉化を図ることが課題。
また、高齢者、障害者に特に配慮した機器を開発する場合、開発費用
が相対的に高額となり、これが開発の防げとなりうる。
情報基盤整備に関する課題
ア 情報通信インフラの整備
テレビ電話等を利用した介護支援システム等の実現には、情報通信イ
ンフラの整備が不可欠。CATV、ISDN等の早期整備が高度なライ
フサポート(生活支援)情報通信システムの実現には不可欠。更に高速
大容量の情報通信インフラの整備が必要。
イ 費用の低廉化
通信費用及びシステムの設置費用が、例えばテレビ電話を用いた個人
宅と介護施設とを結んだ健康相談システムの普及が進展しない理由の一
つとなっているなど費用の低廉化を図ることが課題。
また、高齢者、障害者に特に配慮した機器を開発する場合、開発費用
が相対的に高額となり、これが開発の防げとなりうる。
 その他の課題
ア 制度面の整備
(ア)個人情報がネットワーク上で受発信されるシステム等において、誰
がどの情報までアクセスすることを可能とするかの個人情報開示の基
準、個人情報の保護をどの様に担保するか等について検討を行う必要
がある。
(イ)予想される介護機関同士の情報の共有化に対応した組織連携の在り
方も検討する必要がある。
(ウ)テレビ電話を用いた健康相談を行う場合、責任の所在についても整
理が必要。
(エ)広域的なケア記録データベース構築の際の用語、コードの統一も必
要。
イ 高齢者・障害者の情報通信の利活用をサポートする体制
ライフサポート(生活支援)情報通信システムの活用にあたっては、
高齢者・障害者が自ら情報通信端末を利用する必要がある。
そこで、「身体上の特性から情報通信を利用する際に特殊な設備等が
必要である」、「情報通信の利用に慣れ親しんでいない」ような高齢
者・障害者をサポートする体制が必要である。
2 高齢者・障害者の情報通信の利用の現状
情報通信を用いた高齢者・障害者のライフサポート(生活支援)を図る上
では、高齢者・障害者が自ら情報通信を円滑に利用することが可能であるこ
とが前提となる。
しかし、高齢者・障害者の情報通信の利用動向を調査したところ、パソコ
ン通信、インターネットの利用状況について、高齢者については約8割、障
害者については約7割の人が、いずれも利用経験がないなど、新たな情報通
信サービスに関しては、高齢者・障害者による利用が進展していない。
その原因としては、パソコン通信、インターネットの内容がわからない、
情報通信端末の費用が高いという理由があげられる。
情報通信端末の利便性については、複数の要因のうち、特に操作方法が複
雑であることや通話料の高さについて、高齢者・障害者が不便を感じている。
このように、高齢者・障害者の情報通信の利用は進展していないが、「情
報バリアフリー」環境の実現の観点から、その利用を促進することが重要で
あり、そのためには
その他の課題
ア 制度面の整備
(ア)個人情報がネットワーク上で受発信されるシステム等において、誰
がどの情報までアクセスすることを可能とするかの個人情報開示の基
準、個人情報の保護をどの様に担保するか等について検討を行う必要
がある。
(イ)予想される介護機関同士の情報の共有化に対応した組織連携の在り
方も検討する必要がある。
(ウ)テレビ電話を用いた健康相談を行う場合、責任の所在についても整
理が必要。
(エ)広域的なケア記録データベース構築の際の用語、コードの統一も必
要。
イ 高齢者・障害者の情報通信の利活用をサポートする体制
ライフサポート(生活支援)情報通信システムの活用にあたっては、
高齢者・障害者が自ら情報通信端末を利用する必要がある。
そこで、「身体上の特性から情報通信を利用する際に特殊な設備等が
必要である」、「情報通信の利用に慣れ親しんでいない」ような高齢
者・障害者をサポートする体制が必要である。
2 高齢者・障害者の情報通信の利用の現状
情報通信を用いた高齢者・障害者のライフサポート(生活支援)を図る上
では、高齢者・障害者が自ら情報通信を円滑に利用することが可能であるこ
とが前提となる。
しかし、高齢者・障害者の情報通信の利用動向を調査したところ、パソコ
ン通信、インターネットの利用状況について、高齢者については約8割、障
害者については約7割の人が、いずれも利用経験がないなど、新たな情報通
信サービスに関しては、高齢者・障害者による利用が進展していない。
その原因としては、パソコン通信、インターネットの内容がわからない、
情報通信端末の費用が高いという理由があげられる。
情報通信端末の利便性については、複数の要因のうち、特に操作方法が複
雑であることや通話料の高さについて、高齢者・障害者が不便を感じている。
このように、高齢者・障害者の情報通信の利用は進展していないが、「情
報バリアフリー」環境の実現の観点から、その利用を促進することが重要で
あり、そのためには
 情報通信を利用することの有益性、利用方法等の周知・啓発活動
情報通信を利用することの有益性、利用方法等の周知・啓発活動
 電気通信設備を使いやすくするための基準の策定
等の施策が必要である。
なお、潜在的には、高齢者・障害者ともに福祉サービス提供・支援情報通
信システム、社会参加支援システムの普及に対する要望は強い。
今回、高齢者・障害者の情報通信の利用の現状について以下の項目につい
て調査を実施した。
電気通信設備を使いやすくするための基準の策定
等の施策が必要である。
なお、潜在的には、高齢者・障害者ともに福祉サービス提供・支援情報通
信システム、社会参加支援システムの普及に対する要望は強い。
今回、高齢者・障害者の情報通信の利用の現状について以下の項目につい
て調査を実施した。
(1)パソコン通信、インターネットの利用状況と問題点について
(2)情報通信端末の利便性について
(3)高齢者・障害者にとって普及が望まれる情報通信サービス
|
その結果は以下の通りである。
(1)パソコン通信、インターネットの利用状況と問題点について
高齢者・障害者自らが自由に外部と情報をやりとりすることで、これら
の人々の自立と社会参加に有効な手段として考えられるパソコン、イン
ターネットの利用状況と問題点について調査を行った。
調査項目は以下の通り。
 パソコン通信、インターネットの利用状況 パソコン通信、インターネットの利用状況
 パソコン通信、インターネットを利用しない人について
ア パソコン通信、インターネットを利用しない理由
イ パソコン通信、インターネットを利用したいと思う条件 パソコン通信、インターネットを利用しない人について
ア パソコン通信、インターネットを利用しない理由
イ パソコン通信、インターネットを利用したいと思う条件
 パソコン通信、インターネットを利用している人について
ア パソコン通信、インターネットの利用方法
イ パソコン通信、インターネットを始めるにあたって苦労した点
ウ パソコン通信、インターネットを利用する際の不便な点、不満な点 パソコン通信、インターネットを利用している人について
ア パソコン通信、インターネットの利用方法
イ パソコン通信、インターネットを始めるにあたって苦労した点
ウ パソコン通信、インターネットを利用する際の不便な点、不満な点
|
 パソコン通信、インターネットの利用状況
パソコン通信、インターネットの利用状況を示したのが図1である。
高齢者については約8割、障害者については約7割の人が、「パソコ
ン通信、インターネットのいずれも利用していない」と回答しているこ
とがわかる。
パソコン通信、インターネットの利用状況
パソコン通信、インターネットの利用状況を示したのが図1である。
高齢者については約8割、障害者については約7割の人が、「パソコ
ン通信、インターネットのいずれも利用していない」と回答しているこ
とがわかる。
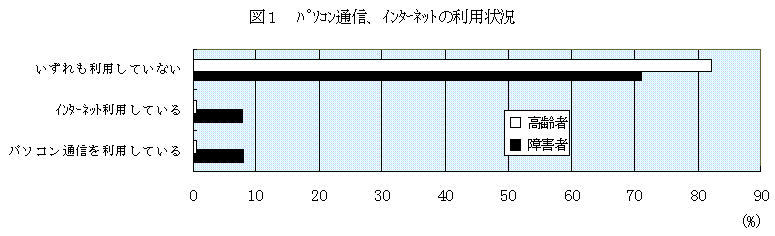
 パソコン通信、インターネットを利用しない人について
ア パソコン通信、インターネットを利用しない理由
パソコン通信、インターネットを利用しない理由について示したのが、
図2である。高齢者、障害者ともに
○ パソコン通信、インターネットの内容がわからない
○ 通信機器の購入費が高い
といった点に不便を感じている人が多い。
また、個別に見ると、高齢者では
○ 利用方法を教えてくれる人がいない(18.5%)
一方障害者では
○ 通信費が高い(28.8%)
といった点に不便を感じている人が多い。
パソコン通信、インターネットを利用しない人について
ア パソコン通信、インターネットを利用しない理由
パソコン通信、インターネットを利用しない理由について示したのが、
図2である。高齢者、障害者ともに
○ パソコン通信、インターネットの内容がわからない
○ 通信機器の購入費が高い
といった点に不便を感じている人が多い。
また、個別に見ると、高齢者では
○ 利用方法を教えてくれる人がいない(18.5%)
一方障害者では
○ 通信費が高い(28.8%)
といった点に不便を感じている人が多い。
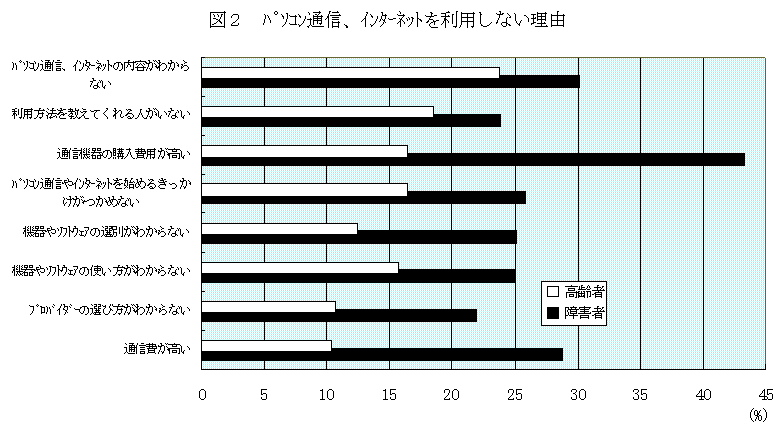 イ パソコン通信、インターネットを利用したいと思う条件
パソコン通信、インターネットを利用したいと思う条件について示し
たのが、図3である。
高齢者は、
○ 自分に適した機器やソフトウェアがあれば利用したい(47.7%)
障害者は、
○ 機器の購入や通信料に対して金銭的補助があれば利用したい
(62.2%)
と回答した人が最も多い。
また、
○ 使い方を学ぶための場所や機会
○ 相談や手助けをしてくれる人や場所
についても、高齢者、障害者ともに、利用したいと思うための条件とす
る人が多い。
イ パソコン通信、インターネットを利用したいと思う条件
パソコン通信、インターネットを利用したいと思う条件について示し
たのが、図3である。
高齢者は、
○ 自分に適した機器やソフトウェアがあれば利用したい(47.7%)
障害者は、
○ 機器の購入や通信料に対して金銭的補助があれば利用したい
(62.2%)
と回答した人が最も多い。
また、
○ 使い方を学ぶための場所や機会
○ 相談や手助けをしてくれる人や場所
についても、高齢者、障害者ともに、利用したいと思うための条件とす
る人が多い。
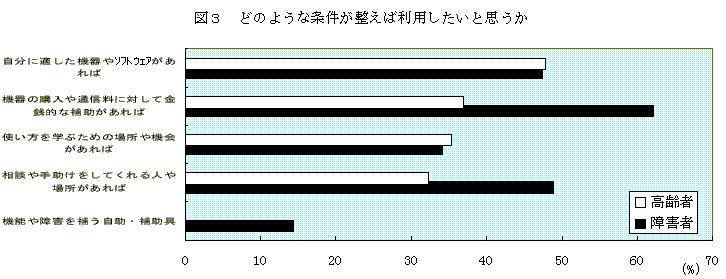
 パソコン通信、インターネットを利用している人について
ア パソコン通信、インターネットの利用方法
パソコン通信、インターネットの利用方法について示したのが、図4
である。高齢者、障害者ともに
○ 個人的な電子メールの交換
○ ホームページの閲覧・ネットサーフィン
といった利用方法が多くなっている。なお、障害者については、この他
に
○ メーリングリストによる交換(78.7%)
で利用する人が多い。
パソコン通信、インターネットを利用している人について
ア パソコン通信、インターネットの利用方法
パソコン通信、インターネットの利用方法について示したのが、図4
である。高齢者、障害者ともに
○ 個人的な電子メールの交換
○ ホームページの閲覧・ネットサーフィン
といった利用方法が多くなっている。なお、障害者については、この他
に
○ メーリングリストによる交換(78.7%)
で利用する人が多い。
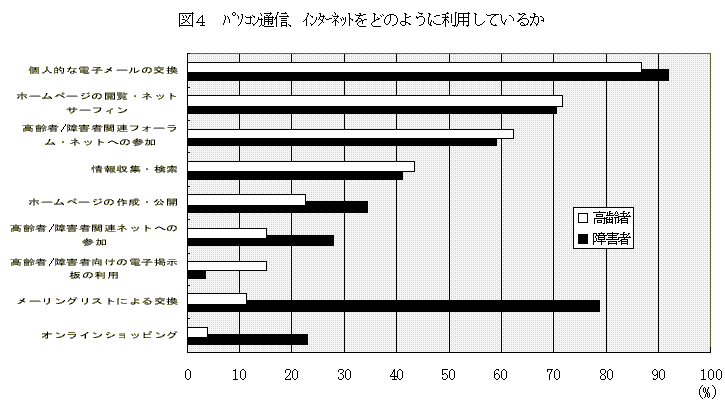 イ パソコン通信、インターネットを始めるにあたって苦労した点
パソコン通信、インターネットを始めるにあたって苦労した点につい
て示したのが図5である。
高齢者は、
○ わからないことがあったときの相談相手がない・わからない
(43.4%)
○ 通信ソフトの選定やインストール方法がわからない(43.4%)
といった点に苦労した人が多いのに対し、障害者では、
○ 機器やソフトウェアの購入費が高い(36.1%)
○ 通信費が高い(29.5%)
といった費用面で困っている人が多い。
イ パソコン通信、インターネットを始めるにあたって苦労した点
パソコン通信、インターネットを始めるにあたって苦労した点につい
て示したのが図5である。
高齢者は、
○ わからないことがあったときの相談相手がない・わからない
(43.4%)
○ 通信ソフトの選定やインストール方法がわからない(43.4%)
といった点に苦労した人が多いのに対し、障害者では、
○ 機器やソフトウェアの購入費が高い(36.1%)
○ 通信費が高い(29.5%)
といった費用面で困っている人が多い。
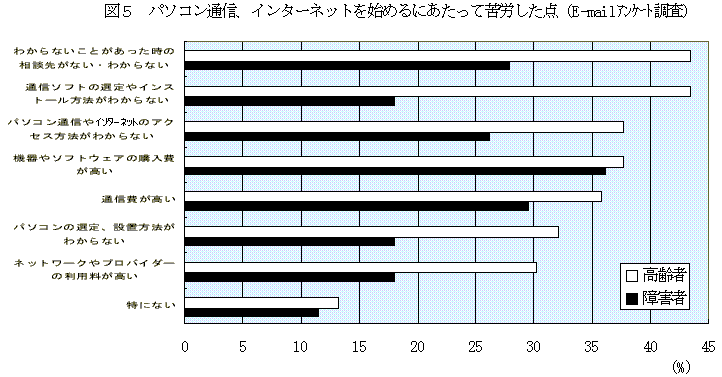 ウ パソコン通信、インターネットを利用する際の不便な点、不満な点
パソコン通信、インターネットを利用する際の不便な点、不満を感じ
ている点の上位の項目を示したのが、図6である。
高齢者、障害者ともに
○ 通信費が高い
○ 機器やソフトウェアの購入費が高い
○ プロバイダーの利用料が高い
といった、費用面についての不満を感じている人が多い。
ウ パソコン通信、インターネットを利用する際の不便な点、不満な点
パソコン通信、インターネットを利用する際の不便な点、不満を感じ
ている点の上位の項目を示したのが、図6である。
高齢者、障害者ともに
○ 通信費が高い
○ 機器やソフトウェアの購入費が高い
○ プロバイダーの利用料が高い
といった、費用面についての不満を感じている人が多い。
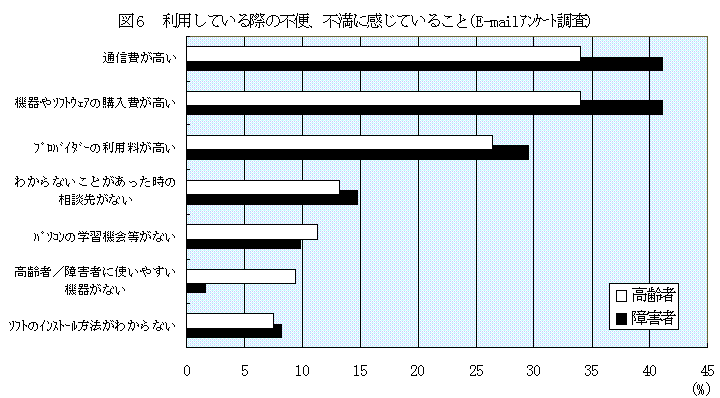 (2)情報通信端末の利便性について
現在情報通信を利用する上で、最初の障害となりやすい情報通信端末の
利便性について調査を行った。
調査対象端末は以下の通り。
(2)情報通信端末の利便性について
現在情報通信を利用する上で、最初の障害となりやすい情報通信端末の
利便性について調査を行った。
調査対象端末は以下の通り。
 ワープロ・パソコン ワープロ・パソコン
 固定電話(加入電話) 固定電話(加入電話)
 ファクシミリ ファクシミリ
 携帯電話・PHS 携帯電話・PHS
 ポケットベル ポケットベル
 携帯情報端末 携帯情報端末
|
 ワープロ・パソコン
ア ワープロ・パソコン利用上の不便な点
ワープロ・パソコン利用上の不便な点の上位の項目を示したのが、図
7である。高齢者・障害者ともに
○ 使用説明書(マニュアル)がわかりにくい
○ 操作方法が複雑でわかりにくい
○ 2つ以上のキーを同時に押すのが難しい
といった点に不便を感じている人が多い。
ワープロ・パソコン
ア ワープロ・パソコン利用上の不便な点
ワープロ・パソコン利用上の不便な点の上位の項目を示したのが、図
7である。高齢者・障害者ともに
○ 使用説明書(マニュアル)がわかりにくい
○ 操作方法が複雑でわかりにくい
○ 2つ以上のキーを同時に押すのが難しい
といった点に不便を感じている人が多い。
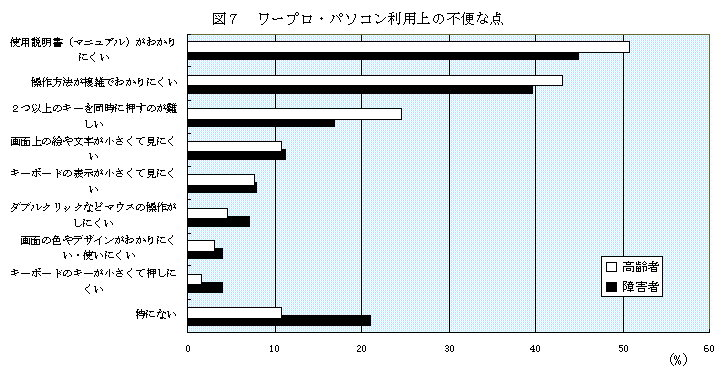 イ パソコンに入出力する際に困った点、苦労した点
パソコンに入出力する際に困った点、苦労した点の上位の項目を示し
たのが図8である。半数は特に苦労を感じていないが、高齢者、障害者
ともに
○ 画面の文字が見にくい
という点で苦労した人が見受けられる。
また、個別に見ると、高齢者では
○ キーボードの文字の配列がわかりにくい、わからない
一方障害者では、
○ マウスが使いにくい
といった点で苦労した人が見受けられる。
イ パソコンに入出力する際に困った点、苦労した点
パソコンに入出力する際に困った点、苦労した点の上位の項目を示し
たのが図8である。半数は特に苦労を感じていないが、高齢者、障害者
ともに
○ 画面の文字が見にくい
という点で苦労した人が見受けられる。
また、個別に見ると、高齢者では
○ キーボードの文字の配列がわかりにくい、わからない
一方障害者では、
○ マウスが使いにくい
といった点で苦労した人が見受けられる。
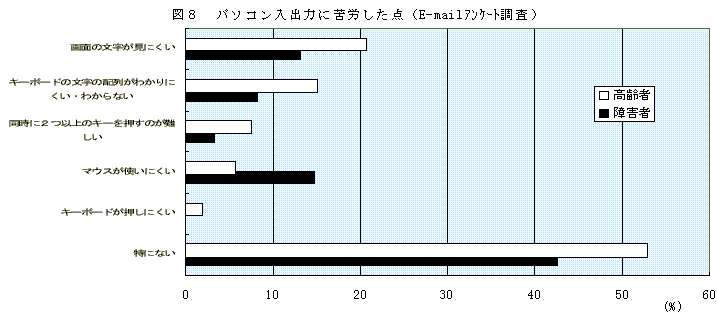
 固定電話(加入電話)
固定電話(加入電話)を利用する際の不便な点の上位の項目を示した
のが、図9である。高齢者、障害者ともに
○ 通話料が高い
○ 機器の購入費が高い
といった点に不便を感じている人が多い。
また、個別にみると、高齢者では、
○ 機能が多すぎる
一方障害者では
○ 身体の機能の衰えや障害に係る機能・装置が不十分
といった点に不便を感じている人が多い。
固定電話(加入電話)
固定電話(加入電話)を利用する際の不便な点の上位の項目を示した
のが、図9である。高齢者、障害者ともに
○ 通話料が高い
○ 機器の購入費が高い
といった点に不便を感じている人が多い。
また、個別にみると、高齢者では、
○ 機能が多すぎる
一方障害者では
○ 身体の機能の衰えや障害に係る機能・装置が不十分
といった点に不便を感じている人が多い。
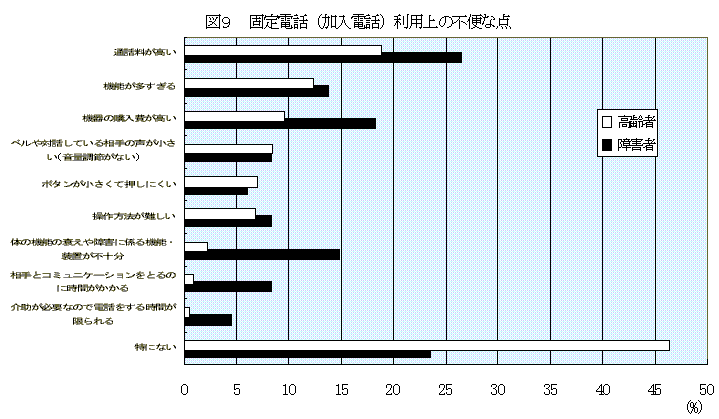
 ファクシミリ
ファクシミリを利用する際の不便な点の上位項目を示したのが、図10
である。高齢者、障害者ともに
○ インクや用紙などの取り替えがめんどう
○ 機器の購入費が高い
といった点に不便を感じている人が多い。
また、個別に見ると、高齢者では
○ 機能が多すぎる
一方障害者では、
○ 相手とのコミュニケーションをとるのに時間がかかる
といった点に不便を感じている人が多い。
ファクシミリ
ファクシミリを利用する際の不便な点の上位項目を示したのが、図10
である。高齢者、障害者ともに
○ インクや用紙などの取り替えがめんどう
○ 機器の購入費が高い
といった点に不便を感じている人が多い。
また、個別に見ると、高齢者では
○ 機能が多すぎる
一方障害者では、
○ 相手とのコミュニケーションをとるのに時間がかかる
といった点に不便を感じている人が多い。
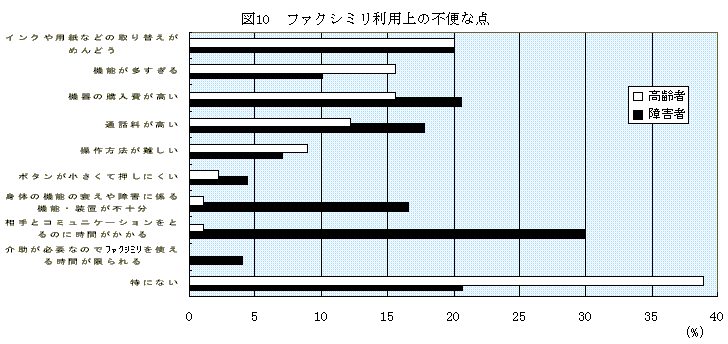
 携帯電話・PHS
携帯電話・PHSを利用する際の不便な点の上位の項目を示したのが、
図11である。高齢者、障害者ともに
○ 通話料が高い
○ ボタンが小さくて押しにくい
といった点に不便を感じている人が多い。
また、個別に見ると、高齢者では
○ 液晶画面の文字が小さい・見にくい
一方障害者では
○ 機能が多すぎる
といった点に不便を感じている人が多い。
携帯電話・PHS
携帯電話・PHSを利用する際の不便な点の上位の項目を示したのが、
図11である。高齢者、障害者ともに
○ 通話料が高い
○ ボタンが小さくて押しにくい
といった点に不便を感じている人が多い。
また、個別に見ると、高齢者では
○ 液晶画面の文字が小さい・見にくい
一方障害者では
○ 機能が多すぎる
といった点に不便を感じている人が多い。
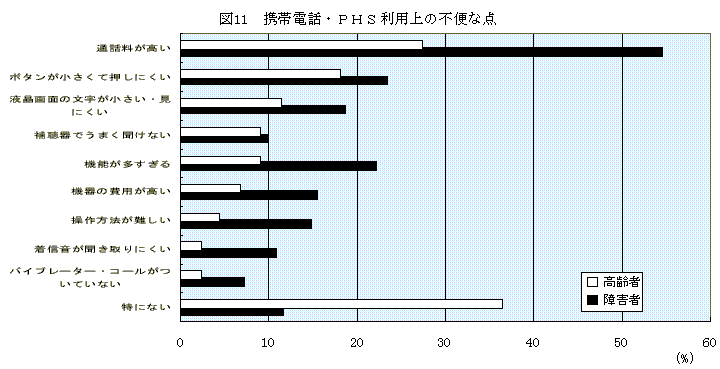
 ポケットベル
ポケットベルを利用する際の不便な点の上位の項目を示したのが、図
12である。高齢者、障害者ともに
○ 操作方法が難しい
○ 利用料が高い
といった点に不便を感じている人が多い。
また、個別に見ると、高齢者では
○ ボタンが小さくて押しにくい
一方障害者では
○ 機器の費用が高い
といった点に不便を感じている人が多い。
ポケットベル
ポケットベルを利用する際の不便な点の上位の項目を示したのが、図
12である。高齢者、障害者ともに
○ 操作方法が難しい
○ 利用料が高い
といった点に不便を感じている人が多い。
また、個別に見ると、高齢者では
○ ボタンが小さくて押しにくい
一方障害者では
○ 機器の費用が高い
といった点に不便を感じている人が多い。
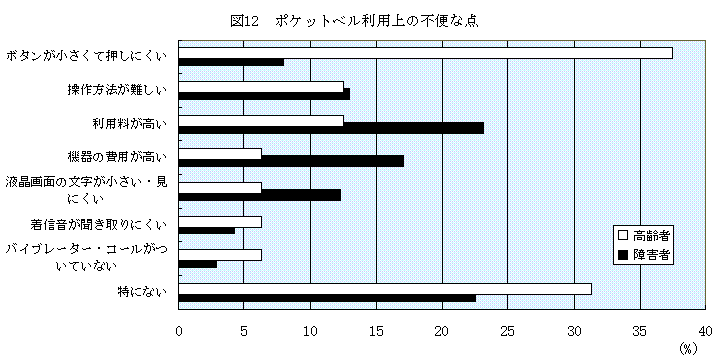
 携帯情報端末
携帯情報端末を利用する際の不便な点の上位の項目を示したのが、図
13である。高齢者、障害者ともに
○ 通信費が高い
といった点に不便を感じている人が多い。
また、個別に見ると、高齢者では
○ ボタンが小さくて押しにくい
○ 操作方法が難しい
一方障害者では
○ 機器の費用が高い
○ 液晶画面の文字が小さい・見にくい
といった点に不便を感じている人が多い。
携帯情報端末
携帯情報端末を利用する際の不便な点の上位の項目を示したのが、図
13である。高齢者、障害者ともに
○ 通信費が高い
といった点に不便を感じている人が多い。
また、個別に見ると、高齢者では
○ ボタンが小さくて押しにくい
○ 操作方法が難しい
一方障害者では
○ 機器の費用が高い
○ 液晶画面の文字が小さい・見にくい
といった点に不便を感じている人が多い。
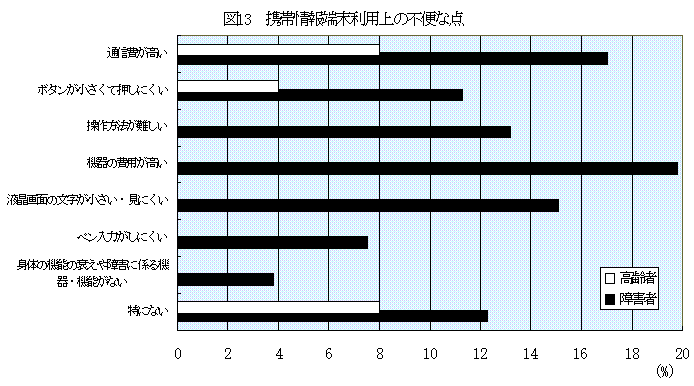 (3)高齢者・障害者にとって普及が望まれる情報通信サービス
高齢者、障害者が、整備の必要があり、また利用意向があると回答した
情報通信サービスについて示したのが、図14である。
高齢者、障害者は、福祉サービス提供・支援システム、社会参加支援シ
ステムともに整備の必要性を感じており、高い利用意向を持っている
(3)高齢者・障害者にとって普及が望まれる情報通信サービス
高齢者、障害者が、整備の必要があり、また利用意向があると回答した
情報通信サービスについて示したのが、図14である。
高齢者、障害者は、福祉サービス提供・支援システム、社会参加支援シ
ステムともに整備の必要性を感じており、高い利用意向を持っている
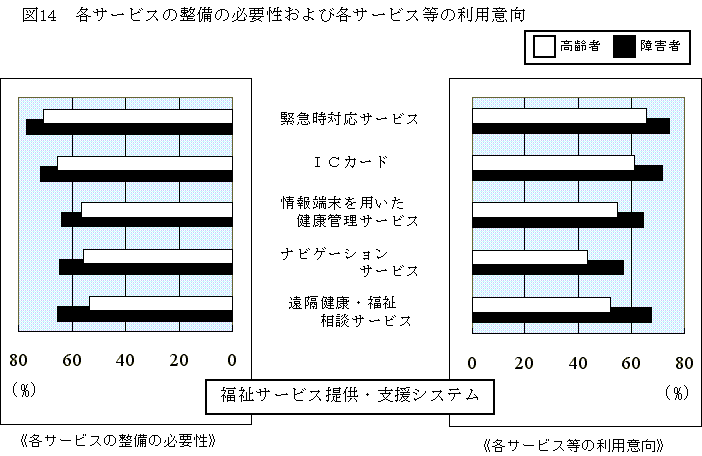
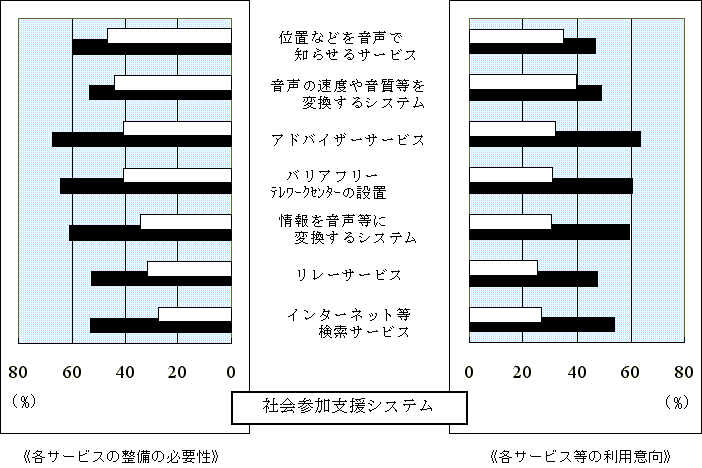
福祉サービス提供・支援システム ア 在宅健康管理システム イ 緊急時対応システム ウ 福祉情報等提供システム
社会参加支援システム ア 障害者向けパソコン通信ネットワーク イ オンラインショッピング ウ その他高齢者・障害者社会参加支援システム (2)課題 これらのシステムは、サービス提供のための人員・費用の効率化、高齢 者・障害者の社会参加の促進等に一定の成果をあげている。 しかし、現在はモデル事業が中心であり、本格的な普及・定着を図るこ とが今後の課題である。そのためには、個別システムごとの課題に解決を 図るとともに、全てのシステムについて共通の課題である、個人情報開示 の基準等の制度的課題、インターフェースの向上等の技術的課題の解決が 必要である。 (3)各システムの現状及び課題
在宅健康管理システム ア サービスの種類と概要 (ア)健康相談システム(映像、音声) 要介護者宅と病院、健康管理センター、健康福祉機関間等を結び、 医者や保健婦と要介護者間の健康相談、介護情報の講習会等を行うも の。 (付加サービス) 健康情報や介護情報に関するデータベースを構築し、当該システム を通じた要介護者やその家族からのアクセスを可能とする。 (イ)健康管理システム 在宅の要介護者の健康データ(血圧、脈拍等)を定期的に健康管理 センター等に送信。保健婦がデータを見ながら健康相談、健康指導等 を行うもの。(ア)の発展形態。 (ウ)個人健康データ、ケア記録等の共有システム (イ)の健康管理システム等で得たデータやケア記録等をデータベー ス化し、各保健福祉関係機関でデータを共有。例えば訪問看護や在宅 介護サービス等の際にそのデータを参照してきめの細かいサービスの 提供を実現するなど、介護、福祉サービスの高度化を図るもの。介護 記録のデータベースは診療報酬の効率的な処理にも貢献。 (発展形態) 訪問看護婦等がもつ携帯端末と接続可能。要介護者宅で、健康デー タの読み出し、入力ができる。 イ システムの形態 (ア)健康相談システム 電話、又は市販のテレビ会議システムを利用したシステムが一般的。 (イ)健康管理システム 健康管理用の専用データ端末を用いてデータ収集。 データは、CATV網を利用して伝送。 (ウ)個人健康データ、ケア記録等の共有システム データベースを、保健福祉センター等に設置。そのデータベースと 健康福祉関連機関をオンラインで結び、各機関での参照・更新を可能 とするシステムが一般的。 ICカードや光カード等のデータカードに個人基本情報、緊急情報、 病歴情報等を一元的に管理する例もあり。 ウ 効果 (ア)健康相談システム 一人暮らしの高齢者等に、孤立していない安心感と健康に対する意 識の高まりが見られた。 (イ)健康管理システム 健康異常の早期発見が可能となった。 訪問が難しい地域の一人暮らしの高齢者の健康状況の把握、安否確 認が可能となった。 医療機関までの距離が遠い集落等において、医療機関に行く回数の 削減を通じた医療関連コストの削減が図られた。 (ウ)個人健康データ、ケア記録等の共有システム 個人情報の蓄積、共有化による個人のニーズに応じた一元的・効果 的ケアが可能になった。 データカードを行政ネットワークと接続することで行政サービスが 向上した例もある。 エ 主な問題点 上記(ア)〜(ウ)のシステム共通の問題点として以下のものがある。 (ア)設備上の問題 端末が大きすぎ、小型化が必要(訪問看護婦持参の携帯端末、高齢 者宅設置端末等) データカードリーダーなど、バージョンアップごとに交換が必要な 設備がある。 (イ)システムの運用上の問題 高齢者が機械にあがり、血圧の正確な測定等が困難となることがあ る。 システム運用にかかる要員不足のため、必要な頻度での健康相談等 が困難。 介護者が定期的に健康データを伝送してこないことがある。 (ウ)コスト上の問題 機器が高額である。(現在はモデル事業で行っているものがほとん ど) (エ)システムの操作性 高齢者が扱う端末機器の操作性が問題。 オ 今後の展望 (ア)システム構築の順序 健康相談システム導入→健康管理システム機能の付加→保健福祉関 係機関での情報の共有という順序でシステム構築が進展する。 ケア記録のデータベース化が別々に進行し、両者が統一化されると いう順序でシステムの構築がなされることが予想される。 また、行政の広域化に伴い、将来的にはこれらのシステム同士が接 続される可能性がある。 更に、これらのシステムは、ケアマネジメントシステムの導入に伴 い、その重要性を増すことが考えられる。一方で、現存のシステムに ついては、介護保険制度対応に更新する必要がある。 (イ)それぞれのシステムごとの展望とそれに伴う課題 A 健康相談システム 低廉化、デジタル回線の普及と共に、テレビ会議システム、テレ ビ電話の利用が普及が進む。 B 健康管理システム 健康データの収集技術の高度化 →モニタリングを感じさせない技術とモニタリング項目の多様化が 必要となる。 C 個人データ等の保健福祉機関間での共有 データ収集の対象拡大と、共有化されたデータの有効利用の方策 の確立。 →その際、個人情報の管理の方法についての方針を決定する必要が ある。
緊急時対応システム 緊急時対応システムとしては、「緊急通報システム」と「行方不明老 人等安全確認システム」の2システムが典型的。 ア 緊急通報システム (ア)サービスの概要 在宅老人等に緊急状態が発生したとき、通信回線網を介して介護セ ンター、親戚等に通報し、受けた者は電話により通報者の状況を把握 した後、必要に応じ消防等に連絡する等緊急事態に対応するもの。 (イ)システムの形態 いずれも公衆回線網(アナログ電話回線、ISDN)又はCATV 網を利用。 A 手動方式 緊急時は専用端末に付加する緊急通報ボタンを押下、または端末 から離れている場合は通常身につけているペンダント等遠隔通報器 の緊急通報ボタンを押すもの B 自動方式 一定時間通常の日常生活と異なる行動パターン(水道を使わない、 湯を沸かさない等)が生じた時に異常が発生したとして緊急通報を 送信 (ウ)システムの効果 一人暮らしの高齢者及び遠隔地の家族等にとって、通信網により常 時連絡体制がとれているという安心感が得られる。 専用端末で緊急通報信号に自動的に個人の識別情報を付加して通報 することにより、早急かつ適切な処置を行うことが可能となる。 (エ)今後克服すべき課題 A 通報器の小型化。 B 誤操作を設備側で防ぐ機能の付加。 C 適切な使用基準の定着。(必要な時に我慢して通報しない、軽微 な事態でもすぐ通報するなどの例が多発) (オ)今後の展望 緊急通報システムは、現在約2,000システムが稼働しているなど、広 く全国に普及している。一人暮らし老人の増加等に伴い、今後もより 広範な普及が予想される。 →端末の誤操作を防ぐ操作性の向上が望まれる。 手動の場合の誤動作、使用基準の困難性等から、非常時の測定技術 の向上、常時監視装置(赤外線カメラの利用が考えられる。)等の導 入等とともに、全体としては自動方式に移行する方向になると思われ る。 現在屋内での利用がほとんどであるが、今後は屋外でも機能するシ ステムの導入、普及が望まれる。 →広域的な展開を前提としたシステムの標準化が必要。 その場合、行方不明老人等安全確認システムとのシステム融合も考 えられる。 また、福祉サービスの高度化の観点から、介護支援システムと接続 され、緊急時の記録が要介護者情報としてデータベース化されること も考えられる。 イ 行方不明老人等安全確認システム (ア)サービスの概要 徘徊癖のある老人等が外出し行き先が不明となった場合、老人等が 所持する現在の位置確認が可能な通信端末によりその情報を無線回線 網により家族等の探索者に伝送し、その情報をもとに探索者は迅速に 現場に出向き保護する。 (イ)システムの形態 A PHS利用システム 徘徊老人等が所持するPHSの位置情報を探索者に伝送すること により徘徊者の位置を確認する方式。 B GPS利用システム GPS衛星からの位置情報を、徘徊老人等が所持する端末(PH S改良)を用いて、探索者に伝送することにより徘徊者の位置を確 認する方式。 (ウ)システムの効果 これまでの人手に頼っていた探索・保護方法に比べ、少人数で、か つ、短時間での探索が可能となる。これにより介護者の経済的、心理 的負担の軽減、徘徊老人の安全の確保が期待されている。 (エ)今後克服すべき課題 A 徘徊老人等に所持させる端末の小型・軽量化。 B 徘徊老人等に所持させる端末は、身に付けたものをすぐ脱ぎ捨て る習性等を考慮した捨て去られることのない形状、装着感のもの。 C 徘徊者及びその家族のプライバシーの確保。 (オ)今後の展望 当システムは、未だ実験段階であり、本格的な実用には至っていな い。 しかし、徘徊老人問題の深刻さから当システムに対する期待は大き く、研究開発等による、上記課題克服が望まれる。 当システムは、システムの導入地域をまたいで徘徊老人が移動して しまうと役に立たなくなることから、システム同士の接続、広域化が 予想される。 →広域的な展開を前提としたシステムの標準化が必要。 その場合、今後普及が期待されているGISシステムの利用が効果 的であると考えられる。 また、サービス提供の形態として、個人ナビゲーションシステムや 広域対応の緊急通報システムとの融合化も考えられる。
福祉情報等提供システム ア サービスの概要 住民の福祉の増進、生活向上等のために役立つ福祉情報、生活情報、 行政情報等を、地方自治体、社会福祉協議会等がオープンなネットワー クであるインターネット、FM放送等により提供するもの。 (参考:提供される情報) (ア)デイサービスの空き状況 (イ)各種行政情報 (ウ)求人情報 (エ)ボランティア情報 等 イ システムの概要 (ア)提供者側 インターネットのホームページによる情報提供。 (イ)利用者側 A 住民への端末の貸し出し B 公共施設等への端末の配置 その他、コミュニティFM放送による情報提供も計画中。 ウ 効果 公共施設等に端末が配備される場合等で、相当のアクセスがあり効果 が見られる例があったが、住民への端末貸出によるものはアクセス数は 伸び悩んでいる。 一方、当システム開始により、各種情報のデータベース化が進展、提 供される情報そのものの質的向上が図られるという効果も見られた。 エ 問題点 当システムの現状での問題点は以下のとおり。 (ア)インターネットの普及率の低さ。 (イ)高齢者・障害者にとって魅力のある情報が少ない。 オ 今後の展望 現状では一般家庭へのインターネット普及率が未だ低いため、既存の メディアによる情報提供の代替手段とはなっていないが、「インター ネットは今後の普及・発展が期待されること」、「福祉情報等の情報提 供の必要性」を鑑みれば、インターネットを利用したこのようなシステ ムは普及していくと考えられる。 その際、以下のような点に配慮することが必要。 (ア)コンテントの内容の充実を図ること (イ)受け手の情報リテラシーの向上を図ること (ウ)メディア変換機能の提供等により障害を持つ人も利用できる機能を 備えること。
障害者向けパソコン通信ネットワーク ア 概要 パソコン通信を利用した、障害者間または障害者と健常者間での情報 交換を目的として運営されるネットワーク。 イ 活動内容 主な活動は、「パソコン通信を通じての障害者同士、あるいは健常者 との交流」と「障害者に対する情報提供」であるが、現在これら以外に、 「実際に対面しての交流会」、「障害者への機器の貸し出し、サポート 及びこれらを行うボランティアグループの運営」、「障害に対応した機 器の展示やシンポジウム」、「テレワークの仕事の紹介」の活動を行っ ている団体が多く存在。 ウ 効果 以下のように、障害者の情報収集、社会参加に大きな効果をあげてい る。 (ア)パソコン通信を通じて、ネット上での気軽な相談等が可能となった ことから、障害者の情報収集が従来より容易となっている。 (イ)パソコン通信、交流会を通じた社会参加の促進 (ウ)障害者の就労の機会の増大 エ 問題点 (ア)システム面での問題点 A 情報通信端末は、まだ障害者に対応したものが少ない。 B 既存の端末についてもまだ使いづらく特別に教えることが必要で あるが、相談に応じてくれるような機関が存在しない。 C 通信費用の負担が大きい。 (イ)運営上の問題点 A パソコン等の指導者が不足している。 B 機材が高価であり、運営が困難。 C メディア変換の際に生じる著作権コストが大きい。 オ 今後の展望 (ア)障害者ネットワークは、大きな成果をあげており、今後とも規模、 活動内容共に拡大していくものであると思われる。 具体的には、「障害者のうち情報リテラシーが低い人の参加による 参加人数の拡大」、「福祉関連の情報提供や、就労支援のためのパソ コン講座等への活動内容の拡大」等が期待できる。 (イ)一方で、障害者ネットワークは、そのシステムをインターネット化 する構想を持っているものが多く、今後はインターネット化が進むも のと思われる。ただし、そのための資金の確保に苦労している団体も 多いのが現状である。
オンラインショッピング ア サービスの概要 外出困難な高齢者・障害者が在宅で購買をできるようにするサービス。 イ システムの概要 一般のオンラインショッピングと同じであるが、端末を高齢者・障害 者の利用に配慮したシステムも一部見られる。 ウ 主な効果 今後の市場の拡大が予想されるオンラインショッピングは、高齢者・ 障害者の生活支援に有効なものとなりうることが分かった。 エ 主な問題点 高齢者・障害者が使いやすいインターフェースが実現されていない。 オ 今後の展望 オンラインショッピングの普及に伴い、高齢者・障害者の利用も増加 していくことが予想される。 その場合、パソコン操作になれていない高齢者・障害者の操作に配慮 したシステム(タッチパネルの導入など)の開発が求められる。
その他高齢者・障害者社会参加支援システム ア 概要 その他、以下のようにインターネット等の情報通信を利用して、高齢 者・障害者の社会参加等を行っているネットワークや活動が見られる。 (ア)インターネットを利用したボランティア活動の仲介 インターネットを用い、ボランティアを募集する団体とボランティ ア希望者との仲介を行うもの。 (イ)マルチメディア制作等による障害者の就業支援 A 通所授産施設等の障害者に対するインターネット上における就業 支援 B 障害者を対象とし、テレビ会議システムを用いて教材ソフト等を 共有したソフト研修の実施 (ウ)障害児の学校単位での交流、自主的な学習の実施 (エ)富山県山田村における高齢者へのパソコン配布 村の全戸数の7割にパソコンを貸与し、インターネットに接続。自由 に使わせる。 (オ)郵便局における高齢者等を対象としたパソコン教室の開催 郵便局の既存の施設等の有効活用を図るとともに、地方自治体及びボ ランティア団体等の協力を得つつ、地域の高齢者等を対象としたパソコ ン教室を開催 イ 効果 これらの取組はインターネットのオープンネットワーク性、場所を克 服するという情報通信の特性を高齢者・障害者の社会参加、自立に生か そうというものであり、今後、情報通信システムのインターフェース、 機能の向上に伴い、さらに広範な活動に発展していくことが予想される。 特に、障害者の就業支援の取組は、その意義に鑑み、大きく期待される ものである。 (4)各システムに共通する一般的課題 ライフサポート(生活支援)情報通信システム活用の上での課題につい ては、システムごとの現状で記載したとおりであるが、これらを一般的な 課題としてまとめれば以下のとおりとなる。
技術上の課題 ア インターフェース、使い勝手の向上 様々な障害をもつ高齢者・障害者自らが情報の入出力等を行うケース が多く発生することから、様々な障害に対応でき、かつ、例えばテレビ 並の使いやすさを実現したインターフェースが必要となる。 イ システムの標準化と相互接続性の確保 介護支援システム、緊急通報システム、行方不明老人等安全確認シス テム等、広域での運営が予想されるものの、現状では相互接続が困難で あるシステムについては、その仕様の標準化もしくは相互接続性の確保 を図ることが求められる。 ウ 機能の高度化 行方不明老人等安全確認システムの端末の小型化、健康データの収集 を人に感じさせない自動データ収集システムの実現など、システムをよ り有用にするために機能の高度化を図る必要がある。その際、たとえば、 中軽度の人たちに対する視点を踏まえたシステムの開発も視野に入れる 必要がある。 エ プライバシー確保のための技術 介護支援システム、行方不明老人等安全確認システムなどでは個人情 報がネットワーク上で受発信されるため、認証技術等セキュリティ技術 の確立が必要。その際、どの程度までセキュリティ機能を求めるかにつ いても検討が必要。
情報基盤整備に関する課題 ア 情報通信インフラの整備 テレビ電話等を利用した介護支援システム等の実現には、情報通信イ ンフラの整備が不可欠。CATV、ISDN等の早期整備が高度なライ フサポート(生活支援)情報通信システムの実現には不可欠。更に高速 大容量の情報通信インフラの整備が必要。 イ 費用の低廉化 通信費用及びシステムの設置費用が、例えばテレビ電話を用いた個人 宅と介護施設とを結んだ健康相談システムの普及が進展しない理由の一 つとなっているなど費用の低廉化を図ることが課題。 また、高齢者、障害者に特に配慮した機器を開発する場合、開発費用 が相対的に高額となり、これが開発の防げとなりうる。
その他の課題 ア 制度面の整備 (ア)個人情報がネットワーク上で受発信されるシステム等において、誰 がどの情報までアクセスすることを可能とするかの個人情報開示の基 準、個人情報の保護をどの様に担保するか等について検討を行う必要 がある。 (イ)予想される介護機関同士の情報の共有化に対応した組織連携の在り 方も検討する必要がある。 (ウ)テレビ電話を用いた健康相談を行う場合、責任の所在についても整 理が必要。 (エ)広域的なケア記録データベース構築の際の用語、コードの統一も必 要。 イ 高齢者・障害者の情報通信の利活用をサポートする体制 ライフサポート(生活支援)情報通信システムの活用にあたっては、 高齢者・障害者が自ら情報通信端末を利用する必要がある。 そこで、「身体上の特性から情報通信を利用する際に特殊な設備等が 必要である」、「情報通信の利用に慣れ親しんでいない」ような高齢 者・障害者をサポートする体制が必要である。 2 高齢者・障害者の情報通信の利用の現状 情報通信を用いた高齢者・障害者のライフサポート(生活支援)を図る上 では、高齢者・障害者が自ら情報通信を円滑に利用することが可能であるこ とが前提となる。 しかし、高齢者・障害者の情報通信の利用動向を調査したところ、パソコ ン通信、インターネットの利用状況について、高齢者については約8割、障 害者については約7割の人が、いずれも利用経験がないなど、新たな情報通 信サービスに関しては、高齢者・障害者による利用が進展していない。 その原因としては、パソコン通信、インターネットの内容がわからない、 情報通信端末の費用が高いという理由があげられる。 情報通信端末の利便性については、複数の要因のうち、特に操作方法が複 雑であることや通話料の高さについて、高齢者・障害者が不便を感じている。 このように、高齢者・障害者の情報通信の利用は進展していないが、「情 報バリアフリー」環境の実現の観点から、その利用を促進することが重要で あり、そのためには
情報通信を利用することの有益性、利用方法等の周知・啓発活動
電気通信設備を使いやすくするための基準の策定 等の施策が必要である。 なお、潜在的には、高齢者・障害者ともに福祉サービス提供・支援情報通 信システム、社会参加支援システムの普及に対する要望は強い。 今回、高齢者・障害者の情報通信の利用の現状について以下の項目につい て調査を実施した。
パソコン通信、インターネットの利用状況 パソコン通信、インターネットの利用状況を示したのが図1である。 高齢者については約8割、障害者については約7割の人が、「パソコ ン通信、インターネットのいずれも利用していない」と回答しているこ とがわかる。
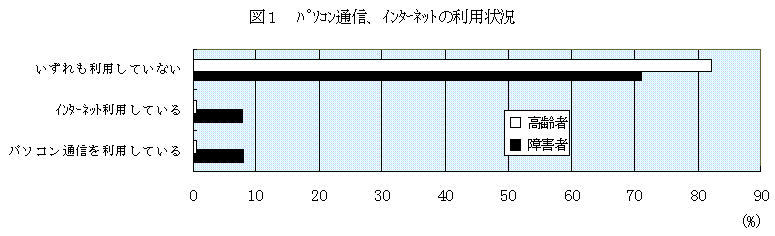
パソコン通信、インターネットを利用しない人について ア パソコン通信、インターネットを利用しない理由 パソコン通信、インターネットを利用しない理由について示したのが、 図2である。高齢者、障害者ともに ○ パソコン通信、インターネットの内容がわからない ○ 通信機器の購入費が高い といった点に不便を感じている人が多い。 また、個別に見ると、高齢者では ○ 利用方法を教えてくれる人がいない(18.5%) 一方障害者では ○ 通信費が高い(28.8%) といった点に不便を感じている人が多い。
イ パソコン通信、インターネットを利用したいと思う条件 パソコン通信、インターネットを利用したいと思う条件について示し たのが、図3である。 高齢者は、 ○ 自分に適した機器やソフトウェアがあれば利用したい(47.7%) 障害者は、 ○ 機器の購入や通信料に対して金銭的補助があれば利用したい (62.2%) と回答した人が最も多い。 また、 ○ 使い方を学ぶための場所や機会 ○ 相談や手助けをしてくれる人や場所 についても、高齢者、障害者ともに、利用したいと思うための条件とす る人が多い。
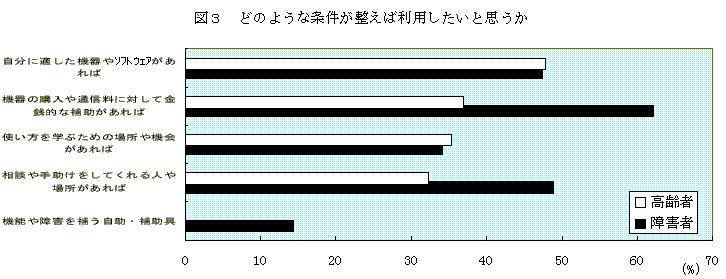
パソコン通信、インターネットを利用している人について ア パソコン通信、インターネットの利用方法 パソコン通信、インターネットの利用方法について示したのが、図4 である。高齢者、障害者ともに ○ 個人的な電子メールの交換 ○ ホームページの閲覧・ネットサーフィン といった利用方法が多くなっている。なお、障害者については、この他 に ○ メーリングリストによる交換(78.7%) で利用する人が多い。
イ パソコン通信、インターネットを始めるにあたって苦労した点 パソコン通信、インターネットを始めるにあたって苦労した点につい て示したのが図5である。 高齢者は、 ○ わからないことがあったときの相談相手がない・わからない (43.4%) ○ 通信ソフトの選定やインストール方法がわからない(43.4%) といった点に苦労した人が多いのに対し、障害者では、 ○ 機器やソフトウェアの購入費が高い(36.1%) ○ 通信費が高い(29.5%) といった費用面で困っている人が多い。
ウ パソコン通信、インターネットを利用する際の不便な点、不満な点 パソコン通信、インターネットを利用する際の不便な点、不満を感じ ている点の上位の項目を示したのが、図6である。 高齢者、障害者ともに ○ 通信費が高い ○ 機器やソフトウェアの購入費が高い ○ プロバイダーの利用料が高い といった、費用面についての不満を感じている人が多い。
(2)情報通信端末の利便性について 現在情報通信を利用する上で、最初の障害となりやすい情報通信端末の 利便性について調査を行った。 調査対象端末は以下の通り。
ワープロ・パソコン ア ワープロ・パソコン利用上の不便な点 ワープロ・パソコン利用上の不便な点の上位の項目を示したのが、図 7である。高齢者・障害者ともに ○ 使用説明書(マニュアル)がわかりにくい ○ 操作方法が複雑でわかりにくい ○ 2つ以上のキーを同時に押すのが難しい といった点に不便を感じている人が多い。
イ パソコンに入出力する際に困った点、苦労した点 パソコンに入出力する際に困った点、苦労した点の上位の項目を示し たのが図8である。半数は特に苦労を感じていないが、高齢者、障害者 ともに ○ 画面の文字が見にくい という点で苦労した人が見受けられる。 また、個別に見ると、高齢者では ○ キーボードの文字の配列がわかりにくい、わからない 一方障害者では、 ○ マウスが使いにくい といった点で苦労した人が見受けられる。
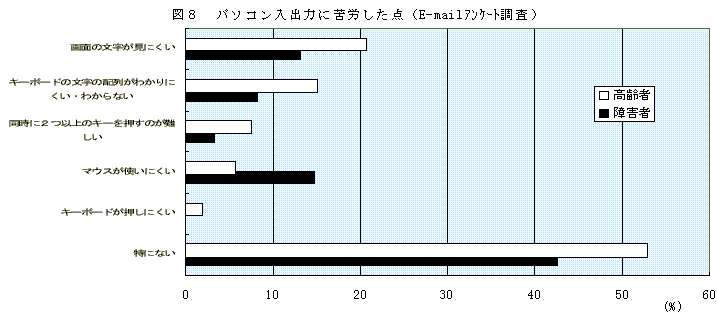
固定電話(加入電話) 固定電話(加入電話)を利用する際の不便な点の上位の項目を示した のが、図9である。高齢者、障害者ともに ○ 通話料が高い ○ 機器の購入費が高い といった点に不便を感じている人が多い。 また、個別にみると、高齢者では、 ○ 機能が多すぎる 一方障害者では ○ 身体の機能の衰えや障害に係る機能・装置が不十分 といった点に不便を感じている人が多い。
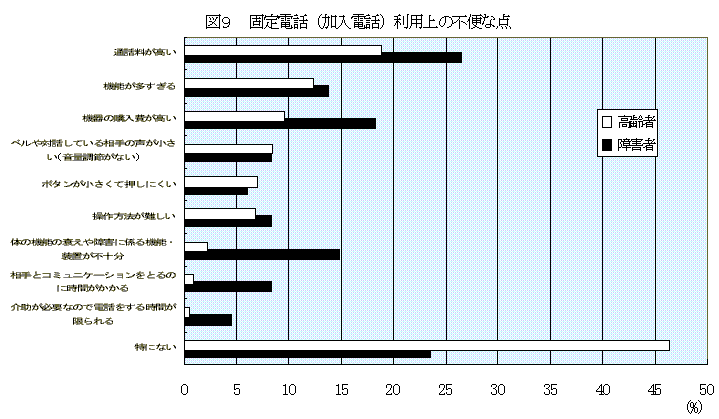
ファクシミリ ファクシミリを利用する際の不便な点の上位項目を示したのが、図10 である。高齢者、障害者ともに ○ インクや用紙などの取り替えがめんどう ○ 機器の購入費が高い といった点に不便を感じている人が多い。 また、個別に見ると、高齢者では ○ 機能が多すぎる 一方障害者では、 ○ 相手とのコミュニケーションをとるのに時間がかかる といった点に不便を感じている人が多い。
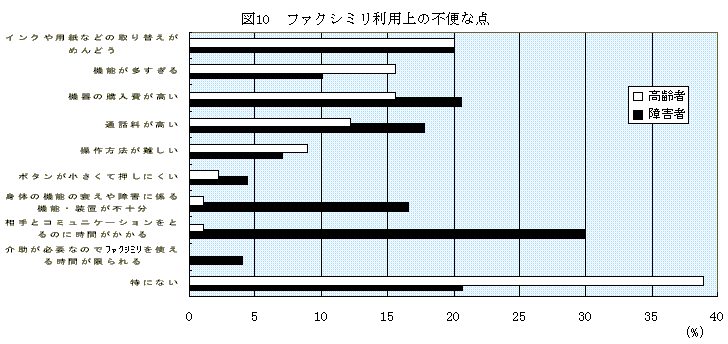
携帯電話・PHS 携帯電話・PHSを利用する際の不便な点の上位の項目を示したのが、 図11である。高齢者、障害者ともに ○ 通話料が高い ○ ボタンが小さくて押しにくい といった点に不便を感じている人が多い。 また、個別に見ると、高齢者では ○ 液晶画面の文字が小さい・見にくい 一方障害者では ○ 機能が多すぎる といった点に不便を感じている人が多い。
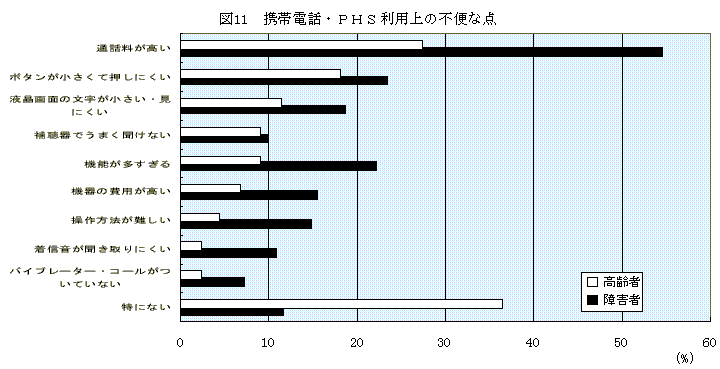
ポケットベル ポケットベルを利用する際の不便な点の上位の項目を示したのが、図 12である。高齢者、障害者ともに ○ 操作方法が難しい ○ 利用料が高い といった点に不便を感じている人が多い。 また、個別に見ると、高齢者では ○ ボタンが小さくて押しにくい 一方障害者では ○ 機器の費用が高い といった点に不便を感じている人が多い。
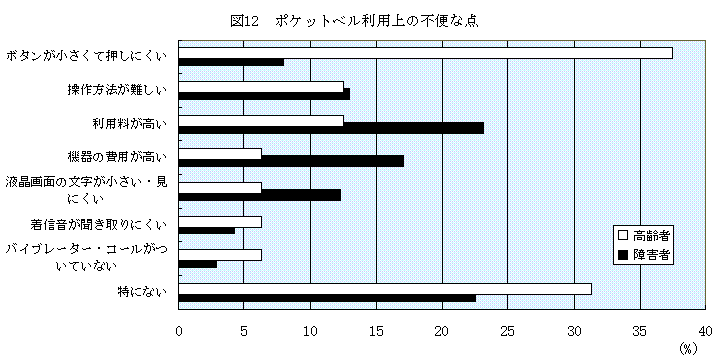
携帯情報端末 携帯情報端末を利用する際の不便な点の上位の項目を示したのが、図 13である。高齢者、障害者ともに ○ 通信費が高い といった点に不便を感じている人が多い。 また、個別に見ると、高齢者では ○ ボタンが小さくて押しにくい ○ 操作方法が難しい 一方障害者では ○ 機器の費用が高い ○ 液晶画面の文字が小さい・見にくい といった点に不便を感じている人が多い。
(3)高齢者・障害者にとって普及が望まれる情報通信サービス 高齢者、障害者が、整備の必要があり、また利用意向があると回答した 情報通信サービスについて示したのが、図14である。 高齢者、障害者は、福祉サービス提供・支援システム、社会参加支援シ ステムともに整備の必要性を感じており、高い利用意向を持っている