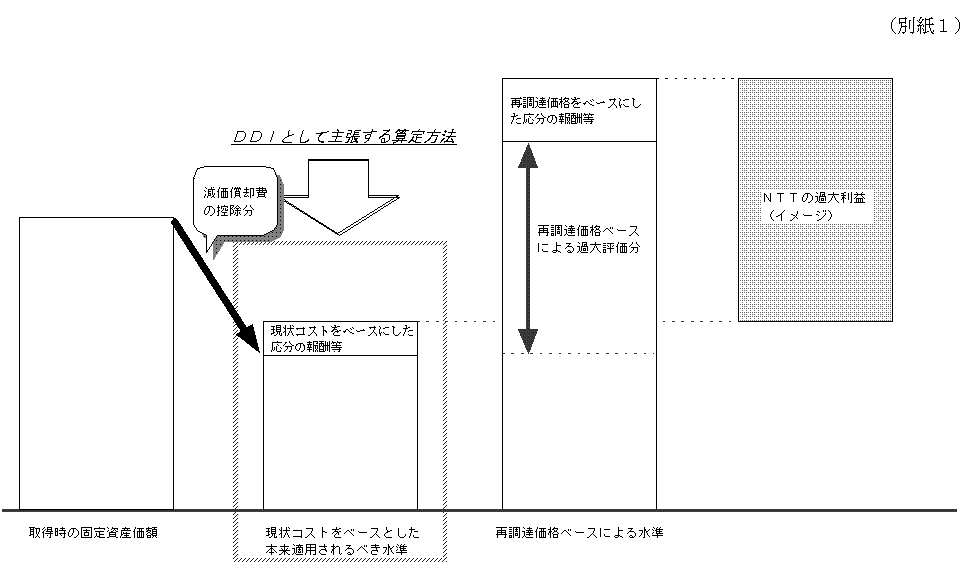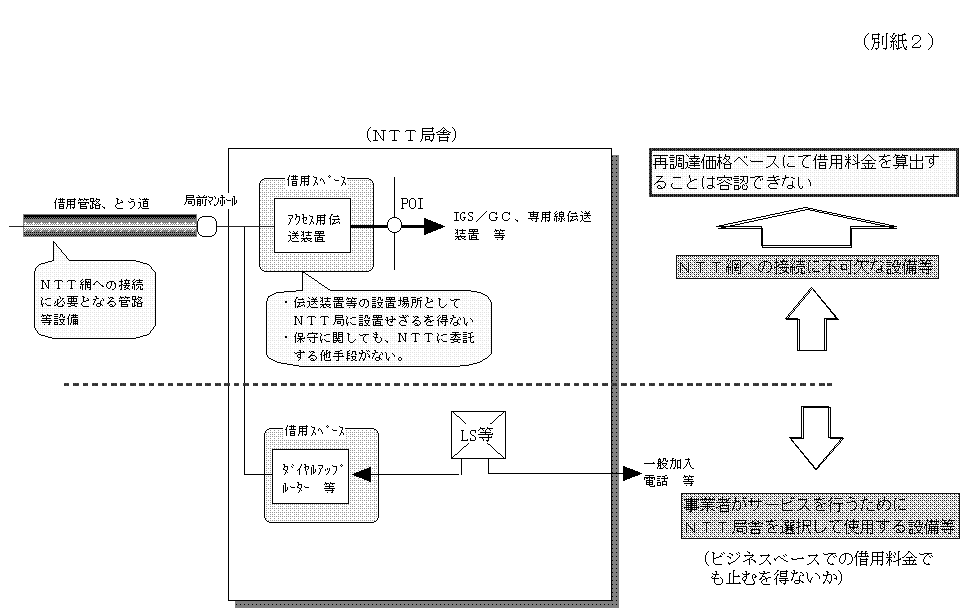|
再 意 見 書
平成9年10月3日
電気通信審議会
電気通信事業部会長 殿
郵便番号 104
住 所 東京都千代田区一番町8番地
氏 名 第二電電株式会社
代表取締役社長 奥山 雄材
電気通信審議会議事規則第5条の2及び接続に関する議事手続細則第2条の規定により、平成9年8月22日付け郵通議第51号で公告された郵政省令案に関し、別紙のとおり再意見を提出します。
(別 紙)
平成9年10月3日
電気通信事業法施行規則の改正案に対する再意見
第二電電株式会社
1 機能のアンバンドルについて
【郵政省令案】
(指定電気通信設備との接続に関する接続約款の認可の基準)
第二十三条の四
2 法第三十八条の二第三項第一号ロの郵政省令で定める機能は、次の表のとおりとする。
(表省略)
【日本テレコム(株)】
〜 (略)。
同項に規定する「中継伝送機能」の費用の額については、その「指定加入者交換機」に接続する「指定中継交換機」の設置位置が、同一の「単位指定区域」であるものとそうでないもの(いわゆる「二重帰属回線」)とに区分して算定されるべきであり、省令に明記すべきと考えます。
【弊社の要望等】
「二重帰属回線」については、費用の厳格化を図る観点から、日本テレコム(株)の主張どおり、可能な限りアンバンドルメニューに明記すべきと考えます。
*各事業者の敬称は省略させていただいております。以下同様。
2 管路等について
【郵政省令案】
(指定電気通信設備との接続に関する接続約款の認可の基準)
第二十三条の四
三〜七 (略)
3 法第三十八条の二第三項第一号二の郵政省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 (略) 二 指定電気通信設備にその電気通信設備を接続する他の電気通信事業者(以下この条において「他事業者」という。)が接続に必要な装置を指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者の建物並びに管路、とう道及び電柱等に設置する場合において負担すべき金額及び取扱い方法
【日本テレコム(株)】
第3項に、電気通信事業法第38条の2第11項の考え方に基づく接続の円滑化に必要な情報(例えば、ネットワーク、局舎、管路、とう道、電柱の情報)を接続約款の記載事項として、号を追加すべきと考えます。
【弊社の要望等】
(1) NTTの所有する建物並びに管路、とう道及び電柱等は公社時代からの資産であり概ね百年近く独占を経て整備された準社会的インフラであります。また、多くは物価の安い時期に調達したものであり、さらに償却期間の終了しているものもあると想定されることから、他のNTTの設備とは異なり、こうした管路等については再調達価格で他事業者に負担を強いるべきではないと考えます。(別紙1参照)
* 例えばIGS等については、償却期間終了後には減価償却費等を負担していないという実例もあります。 * また、土地保有税等、実際に発生する費用についてはその実額を負担する方向で考えております。 (2) そもそも、全国の約1600にのぼるGCへのアクセスが一般化することや、6000万にものぼる加入者回線を踏まえると、NTTの管路等は明らかにボトルネック設備であり、本省令第二十三条の四第2項のアンバンドルメニューの中に明記すべきと考えます。 (3) また、他事業者が借用する管路等については、基本的にNTTが使用していない部分を借用することとなっておりますが、基本的にNTTにて当該区間の利用計画がでた段階で他事業者へ事前通告を行った上で、他事業者が借用している設備をNTTに返却する方向で検討されております。 (4) しかしながら、仮に、他事業者に貸与したために、NTTが新たに管路等を構築もしくは再調達価格で他から管路を借用しなければならないという事態が想定された場合でも、例えば全国平均又はエリアごとの平均した帳簿価格により管路等の費用を算定することによって他事業者とNTTの平等な費用負担が可能となると考えます。(こうすることで、先に管路等を借用した事業者も同等のコスト負担が可能となり、事業者間での平等性も担保できます。)
* 利用する事業者の観点から、管路、とう道については区別することなく同一の条件で扱うべきと考えます。 (5) なお、特に建物については、NTT局舎にアクセス用の伝送装置等を他事業者が設置せざるを得ない状況を勘案すると、当該建物等(当該管路等を含む)はボトルネック設備であると考えられます。(別紙2参照) (6) 以上を踏まえ、建物並びに管路、とう道及び電柱等については、NTT自身が使用するときのコストである帳簿価格をベースに算定すべきであると考えます。 (7) また、建物並びに管路、とう道及び電柱等の空き情報等、接続に必要な情報については、日本テレコム(株)の主張のように、法第三十八条の二第十一項に基づき接続約款の記載事項として本省令に明記すべきと考えます。
* 鉄塔のように空き情報が開示されている実例があります。
3 届出約款の扱いについて
【郵政省令案】
(届出を要する接続料及び接続の条件)
第二十三条の六
法第三十八条の二第四項の郵政省令で定める接続料及び接続の条件は、次のとおりとする。
一 付加的な機能の接続料及び接続の条件 二 法第四十一条第一項の技術基準又は法第四十八条の二第一項の電気通信番号の基準を定める郵政省令その他の法令の規定に基づき変更する接続の技術的条件
【(株)四国情報通信ネットワーク】
付加的な機能の接続料及び接続の条件について、届出制とすることに賛同しますが、〜(略)。
【日本電信電話(株)】
接続約款の認可事項の範囲は限定的なものとし、他の電気通信事業者との接続に与える影響が軽微な事項等については届出で対応できるようにするなど、弾力的な運用を要望します。
【弊社の要望等】
(1) 届出接続約款については、郵政省の審査の対象ではないことから、中でも接続料については対象範囲を限定しないと、接続ルールの主旨である「合理的な接続料金を設定する」ことが困難なことも想定されます。 (2) したがって、当該省令の「付加的な機能」の対象とする範囲は極力限定すべきと考えます。
* 詳細については、前回の弊社の意見を参照 以 上