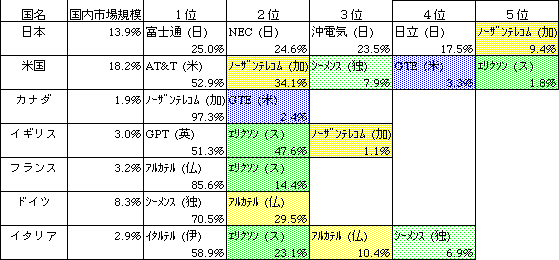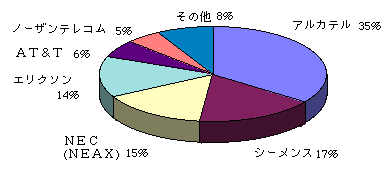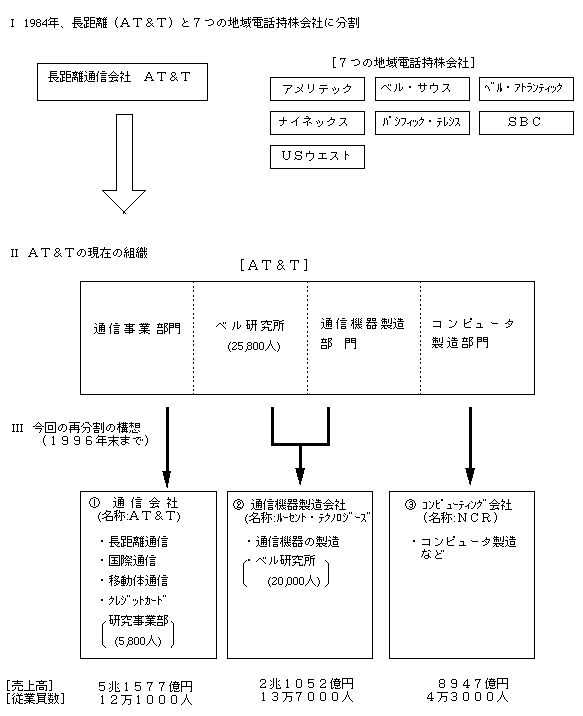第3章 第2次情報通信改革の姿
第2次情報通信改革とは、以下のように情報通信産業のダイナミズムを創
出し、国民利用者にとって望ましい情報通信を実現することを目指すもので
ある。
1 国民利用者にとって望ましい姿
国民利用者のニーズの多様化が進む中で、情報通信についても多種多様
な利用形態を実現することが期待されているが、国民利用者にとって望ま
しい情報通信の姿として、次のような点が挙げられる。
(1) 多様なサービス
利用者が豊富な選択肢を享受することによって、供給者主導ではなく
利用者主導の情報通信の実現が期待される。
基本的な通信サービスは言うまでもなく、質的に全く新しいマルチメ
ディアサービス(例:オープンなネットワーク上での電子商取引、画像
を用いた遠隔教育やコンピュータによる情報提供・情報検索)が多様に
提供されることが望まれる。
その際、利用者が、多種多様なサービスの中から真に必要とするサー
ビスを選択できるためには、正確で分かりやすい情報が供給者側から提
供されていくことが重要となる。
(2) 料金の低廉化
今後、生活及び企業活動のあらゆる局面で、情報通信サービスを利活
用するようになると予想されることから、できるだけ低廉な料金で利用
できることが必要である。
(例)
(ア) 内外価格差の抜本的是正
(イ) 遠距離料金の引下げによる遠近格差の抜本的是正
(ウ) 低廉で多様な定額制の料金メニュー
(エ) 新規加入料の撤廃又は大幅な引下げ
(3) 安心して利用可能
利用者が安心してサービスを利用できることが望まれる。
(ア) 高品質、高信頼のサービス水準
伝送品質の維持・向上や障害の起こりにくいシステムの構築等によ
り、安心して利用できるサービス品質や信頼性を確保する必要がある。
(イ) プライバシーの保護
利用者のプライバシ−の保護を図るため、個人情報の保護、適正な
管理に関して法制度的な対応について検討するとともに、他人が個人
データに簡単にアクセスすることを防止するための暗号・認証技術の
開発・応用等の措置を講ずる必要がある。
(ウ) 公序良俗に反する情報等の排除
公序良俗に反する情報、反社会的な情報等の流通に関し、表現の自
由とプライバシーの保護に配意しつつ、法制度的な対応を含めルール
づくりについて検討する必要がある。
(エ) 情報通信の安全・信頼性の確保
オープンなネットワーク上での電子決済の実現やハッカーによる不
正アクセスの防止等のため、暗号・認証技術の実用化や関連する制度
の整備への取組を強化し、情報通信の安全・信頼性を確保する必要が
ある。
(オ) 契約内容の明確化
利用者に対する契約約款の周知・徹底を図るなど利用者が契約内容
を明確に認識できる環境を整備する必要がある。
(4) 簡便な利用等
あらゆる利用者が、サービスを簡便に利用できる環境の実現が必要で
ある。
(ア) ワンストップショッピング
今後、競争が一層進展するに伴い、複数の事業者が接続し、互いの
ネットワークを効率的に使用することによって、利用者に多彩なサー
ビスが提供されるものと期待される。
この場合、接続する複数の事業者のうち、1社が代表して、利用者
の窓口(申込みの受付、料金の請求、故障時の対応等)を務めること
により、利用者が複数の事業者の介在を意識せずに、いわゆるシーム
レスなサービスを利用できる環境を実現することが望まれる。
なお、その際、事業者間で加入者情報がやりとりされることから、
利用者のプライバシー保護を図るため、個人情報が不当に利用される
ことのないよう慎重な対応が必要である。
(イ) 操作の簡便性
ヒューマンインタフェースの改善等により、利用者が操作しやすい
環境を実現することが望まれる。
(ウ) 利用者志向のサービス提供体制の確立
利用者がいつでも安心して電気通信サービスを享受できるよう、サ
ービスの申込み、問い合わせ、故障時の対応等における窓口サービス
体制の充実等利用者の立場に立ったサービス提供体制を確立すること
が望ましい。
(5) ユニバーサルサービスへのアクセス機会の保障
ユニバーサルサービスに対する平等かつオープンなアクセスの機会を
保障し、情報を「持つ者」と「持たざる者」の二極化を回避することが
必要である。
(6) 個人の情報発信の拡大
(ア) 情報化が進展すると、個人も容易に情報の発信者になり得ることか
ら、通信ネットワークを基軸とした、従来と異なる新しい人間関係・
社会が創造され、個人の生活様式や社会に対し大きな影響を与える可
能性が生じる。
(イ) 例えば、インターネットを使えば、距離等を超越して形成される新
たなコミュニティを通じて従来とは全く異なった人間関係・社会への
参画が可能となるとともに、個人や小グループが世界中に向けて情報
を発信でき、これまでにない社会への影響力を行使できるようになる。
(7) 福祉サービスの確保
(ア) 高度な情報通信システムにより物理的な移動の困難性を克服し、視
聴覚メディアを用いて高齢者・障害者が健常者と同じように社会に参
加できるようにすることが望まれる。
(イ) 高度な福祉情報システムにより、在宅介護・過疎地における医療サ
ービスを質的に高めることが期待される。
2 情報通信産業のダイナミズム創出
国民利用者の利益をより一層増進させるためには、供給主体である情報
通信産業の活性化が不可欠である。
(1) 相互参入の促進
(ア) 現行法制度においては、NTTが国内通信、KDDが国際通信、N
HKが放送に業務を限定されている他は、国内通信/国際通信、地域
通信/長距離通信、固定通信/移動通信、放送/通信といった業務区
分は存在しない。
(イ) しかしながら、現状では、各業務の大半が独立しており、これら
事業分野間の相互参入を促進することが課題である。
また、これに関連して、上記(ア)のように業務区分の規制が行われて
いるものではないことを明確にすべきである旨の指摘がなされている
ところである。
(ウ) こうした指摘を踏まえ、既に業務区分の規制がない旨改めて明確に
されているが、今後、マルチメディア時代に向けて、各事業者の相互
参入を政策的に推進していくことにより、競争の促進及びそれを通じ
た利用者の利益の増進が期待される。
(2) 多様なネットワークの形成
(ア) 情報通信基盤の整備
光ファイバ網の整備については、2010年に全国の家庭まで敷設する
ことが目標となっており、その整備に際しては、第一種電気通信事業
者、CATV事業者等が競争的に光ファイバ網の整備を行っていくこ
とが望ましい。
また、光ファイバ、衛星、移動体なども含めた多層的なネットワー
クが情報通信基盤として整備されることが期待される。
(イ) インターネットワーキングの促進
コンピュータの普及の進展、マルチメディア化の進展に伴って、L
AN間接続などネットワークとネットワークを接続するインターネッ
トワーキングが容易に行われることが望ましい。インターネットに代
表されるようなユーザによるネットワークが多様に形成されていくた
めには、その基盤となる設備ベースのネットワークが誰に対してもオ
ープンで、使いやすく、低廉な料金で提供されることが望ましく、設
備ベースでの競争促進が重要な課題となる。一方、このようなサービ
スを第一種電気通信事業者自らが提供しようとするものとして、NT
Tによりインターネットプロトコルによるオープンコンピュータネッ
トワーク(OCN)が構想されている。
米国においては、長距離系事業者と地域系事業者の接続により同様
のサービスが既に提供されているが、非設備ベースのインターネット
接続事業者は、設備ベースの事業者との公正競争条件の整備を求めて
いる。我が国においても、このようなサービスが提供されるに当たっ
ては、その機能や設備が十分にアンバンドル化(ネットワークの構成
要素や機能ごとの接続費用の細分化)された上、公正な条件で他事業
者に提供されることが必要である。
(ウ) 柔軟なネットワーク構築の促進
さらに、次のような柔軟なネットワーク構築を促進することにより
、意欲ある事業者が様々な形態によって情報通信産業を展開できるこ
とが期待される。
(a) 電力会社や自治体の管路・光ファイバ等を通信事業者が利用して
、ネットワークを構築することを可能とする。
(b) 公専公接続の自由化
(3) 地域の競争の促進
(ア) ボトルネック独占の解消を図るためには、地域通信分野における
競争を創出することが課題となるが、そのための地域通信メディアと
しては、CATVによる通信、地域バイパス、携帯電話・PHSなど
移動通信などが挙げられる。
(イ) これらの地域通信メディアを念頭においた競争促進政策としては、
以下のような例が挙げられる。
(a) 電力鉄塔・管路・電柱等に対するアクセスの確保
(b) 地域通信網への接続の円滑化
(c) イコールアクセス(番号のけた数など利用者がどの事業者に対し
ても同一の条件でアクセスできること)の継続的確保
(d) 番号ポータビリティ
(e) 周波数の確保
(f) その他
(4) 接続の確保
ア 接続の重要性
電気通信サービスは、地域通信、長距離通信、国際通信、移動体通
信等異なる事業者のネットワークが円滑に接続されることによっては
じめて、利用者へサービスを提供できるものであり、接続の確保が重
要な課題である。
とりわけ、NTTの地域通信網のように、他事業者が当該ネットワ
ークと接続することが不可欠な設備とその他の通信網の接続の確保を
図ることが、極めて重要な課題となっている。
NTTなどの一定の市場シェアを有し不可欠な設備を有する事業者
と他事業者との接続に関する基本的ルールを策定するとともに、ルー
ル遵守の実効性を担保する観点から、ルール監視機能の充実を図るこ
とが必要である。
イ 接続確保のための具体的方策
接続の基本的ルールとしては、
一定の市場シェアを有し不可欠な設備を有する事業者との間の迅
速な接続の実現、接続条件の透明性、公平性の確保等の観点から、
(ア)接続の義務づけ、(イ)接続条件の料金表・約款化、(ウ)接続会
計と営業会計の分離(サービス別の収支の状況を明らかにする現在
の営業会計とは別に、他事業者との接続に関する収支の状況を明ら
かにするための会計を設けること)、(エ)アンバンドル化、(オ)番
号ポータビリティの確保等の措置を講じることが必要である。(第
6章において詳述)
〔参考〕諸外国の例
(a) 米国においては、1996年電気通信法により、全電気通信事業者
に対して接続が義務づけられており、また、英国においては、B
Tなどの公衆電気通信事業者に対して免許条件において接続が義
務づけられている。
(b) 米国の地域電話会社については接続条件を料金表及び約款とし
ており、英国のBTについては、接続料金をOFTELが定める
こととなっている。また、BTの免許条件において接続会計と営
業会計を分離することとしている。
(c) 米国においては、1996年電気通信法により、これまで独占的に
サービスを提供してきた地域事業者に対してアンバンドル化が義
務づけられている。英国のBTについては、OFTELが約90
にアンバンドル化した接続料金を設定している。
(d) 米国においては、1996年電気通信法により、全地域事業者に対
して優先接続(事業者番号をダイヤルすることなく、利用者があ
らかじめ登録した事業者に接続すること)によるアクセスの提供
を義務づけている。
(e) 米国においては1996年電気通信法により、全地域事業者に対し
て番号ポータビリティの提供が義務づけられている。英国では、
OFTELがBTに対して番号ポータビリティの提供のための免
許条件の修正を行う手続を進めている。
(5) 国際競争力の向上
ア 国際競争力について
(ア) 国際競争力については、諸外国に対する国益の追求といったとら
え方よりも、基本的には、次のような概念でとらえていくことが適
当である。
(a) 我が国の情報通信産業が活力に満ちた発展を遂げていること
(b) その結果、国民利用者が低廉で良質かつ多様なサービスを享受
できること
(c) 標準化活動、グローバルな情報通信基盤整備等において、世界
的なリーダシップを発揮して、貢献していくこと
(イ) 一方で、国際競争力という言葉が使われる際には、
(a) 我が国の通信事業者等が海外市場へ展開しているかどうか
(b) 世界の通信事業者との連携等国際通信市場での展開が行われて
いるかどうか
といった観点で取り上げられることが多いことから、この点につい
ての検討も必要である。
イ 海外市場への展開
(ア) 通信事業者及びメーカ等の海外市場への展開については、我が国
のシステム、製品、コンテントが国際的に見て良質かつ低廉である
ことが基本的な条件として求められる。
仮にこのような条件が満たされていれば、開発途上国におけるイ
ンフラ整備事業の受注、先進国の通信市場への進出などの積極的な
海外展開により、システム、製品、コンテントの国際的な販路拡大
やデファクト標準(事実上の標準)の実現などに積極的な展開が期
待される。
なお、このような海外展開のためには、国を代表する巨大な通信
事業者、いわゆるナショナルフラッグキャリアの存在が不可欠との
議論がある。しかしながら、欧米の現状を見ると、巨大な通信事業
者が存在しない国に強力なメーカが存在するケースや巨大な通信事
業者が存在するにもかかわらず強力なメーカが存在しないケースも
あり、製品の国際競争力の向上にとってナショナルフラッグキャリ
アの存在は不可欠な条件とは言えない。
(イ) また、NTTを例にとれば、前述したように、海外市場への展
開は十分とは言えない。
海外市場への展開において、経営規模が大きいことが国際競争上
必要であるとの議論がある。
もちろん、海外市場への展開にはリスクを伴うことから一定の経
営規模が求められる面も存在することは否定できない。
しかしながら、現在、世界一の経営規模を誇るNTTが海外市場
への展開をほとんど行っておらず、他方、NTTよりも経営規模の
小さい欧米の通信事業者が積極的に海外進出を行っていることから
すれば、現在の経営規模が、海外市場への展開という意味での国際
競争力の不可欠な条件とは言えない。
ウ 国際通信市場での展開
(ア) 国際通信市場において、諸外国の通信事業者が国境を越えて提携
を行う動きがある。このような提携は、多国籍企業等のグローバル
な国際通信需要を充足させようとするものである。
これらの提携は、国際通信市場をめぐる動きであり、我が国の市
場で言えば、国内・国際通信市場を合わせた市場の5%弱(平成6
年度)にすぎないが、今後の成長性には留意する必要がある。
(イ) また、前述したとおり、LEO衛星通信技術などの移動通信技
術の開発によって、グローバルサービスの実現が可能となってきて
おり、それへの積極的な対応が期待される。
(ウ) なお、情報通信のグローバル化の動きに対応して、我が国が通信
のハブ(情報受発信の拠点)としての役割を担う中で、世界的なグ
ローバル・ネットワークの形成に貢献できるよう努めていくことが
望ましい。
(エ) これらの国際通信市場への展開という観点から見た我が国の国際
競争力を向上させていくことも情報通信のグローバル化の進展の中
で重要な課題である。
エ 国際競争力の向上
(ア) 一般に、国際競争力は、単なる経営規模の巨大さではなく、価格
の低廉さ、サービス・性能面での優位、アイデアの独自性、迅速か
つ機動的な経営行動(スピードの経済性)、研究開発力、信頼性等
の諸要素が総合的に評価されるものと考えられる。
(イ) 価格の低廉さ、サービスの多様性はもちろんのことであるが、マ
ルチメディア時代においては、とりわけ、デファクト標準の台頭に
見られるように、インフラ、機器、コンテントのすべての分野で独
自性を裏打ちできるアイデア、スピードの経済性、高度な研究開発
力などの要素が重要となるであろう。
(ウ) 我が国のシステムが諸外国のシステムに比べて優位性を確保する
ためには、国際競争力の源泉であるこれらの諸要素について不断の
向上を実現していくことが必要となる。
(エ) そのためには、国内に強力な競争相手のない独占的企業の存在す
る体制よりは、国内において強力な競争相手が相互に切磋琢磨する
体制の方が適していると考えられる。
(オ) したがって、活発な事業展開を行う多数の競争主体の形成による
国内におけるダイナミックな競争環境の創出を通じて、国際競争力
の向上を実現していくことが必要である。
(6) 研究開発力の向上
研究開発力は、情報通信産業の発展の源泉である。今後とも、情報通
信分野においては、急速な技術革新の進展の中で、研究開発の果たす役
割が一層大きくなると考えられることから、我が国の研究開発力のより
一層の向上を図ることが重要な課題となっている。
ア 研究開発競争の活性化
情報通信分野におけるニーズの多様化・高度化、技術の高度化、学
際領域的技術分野の拡大、複合化等研究開発力を取り巻く環境の急速
かつ大きな変化を踏まえ、我が国の研究開発力をより一層向上させる
ことが重要である。このためには、市場支配力によるダイナミズムの
低減を生じないよう留意しつつ、自立的に意思決定が可能な多数の組
織により、国内外の組織との間で多元的・機動的な連携を通じダイナ
ミックな競争を促進することが重要である。
イ 通信事業者とメーカーの共同研究開発
NTTは、自社で使用する交換機等の機器をメーカと共同で研究開
発しており、これまで我が国の研究開発力の向上に貢献してきたと考
えられるが、このような、調達を前提としたNTTとメーカの共同研
究開発については、次のような指摘がある。
(ア) 共同研究開発したデジタル交換機は必ずしも市場競争力に結びつ
いていない。
(イ) 我が国の加入者デジタル交換機(固定系)のシェアについて、外
国メーカの参入例はあるものの、従来からNTTと共同研究開発を
行っている4社のシェアにほとんど変化がない。
(ウ) 独占的な事業者であるNTTが、メーカの研究開発に大きな影響
を及ぼす結果、研究開発の多様性が失われているのではないか。
(エ) 技術やニーズの急速かつ大きな変化を踏まえ、多数のメーカがN
TTの調達市場を目指して研究開発を行うことは、研究開発競争の
一層の活性化の観点から望ましい。また、NTTが世界市場から最
も優れた機器を最も低廉な価格で、内外に一層オープンな形で調達
することは、通信料金の低廉化につながることが期待できるもので
ある。
したがって、このような指摘をも踏まえ、通信事業者とメーカの
共同研究開発が、我が国の研究開発の多様化・活性化、市場競争力
の強化及び国民利用者の利益の向上に貢献し、国民や産業界の期待
に応えられるようなものにしていくことが望まれる。
なお、1995年に発表されたAT&Tの再分割では、現在のAT&
Tが通信部門、製造部門、コンピュータ部門の3社に分割される予
定であるが、ベル研究所の大半は、製造部門の会社に移行し、通信
部門の会社は、通信関連の研究開発を行う研究事業部を新たに設置
する予定である。これは、メーカの研究開発力の重要性を示すもの
と考えられる。
交換機【加入者デジタル交換機(固定系)の国際市場シェア】
日米欧の主要国におけるシェア(1993年)
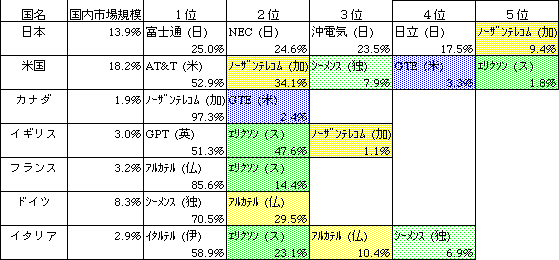
(注1)GPTにはシーメンスが50%出資、イタルテルにはAT&Tが出資
(注2)「国内市場規模」とは世界交換機市場に占める当該国の交換機市場の割合
(注3)シェアはライン数ベース
日米欧以外の市場におけるシェア(1993年)
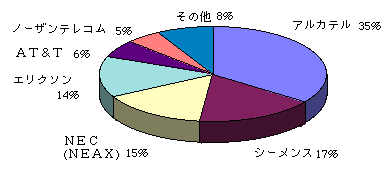
(注) シェアはライン数ベース
(出典)NBIレポート1994
NBI(ノーザン・ビジネス・インフォメーション)社
米国ニューヨークに本社を持つ通信市場を専門とする調査会社
AT&Tの再分割について
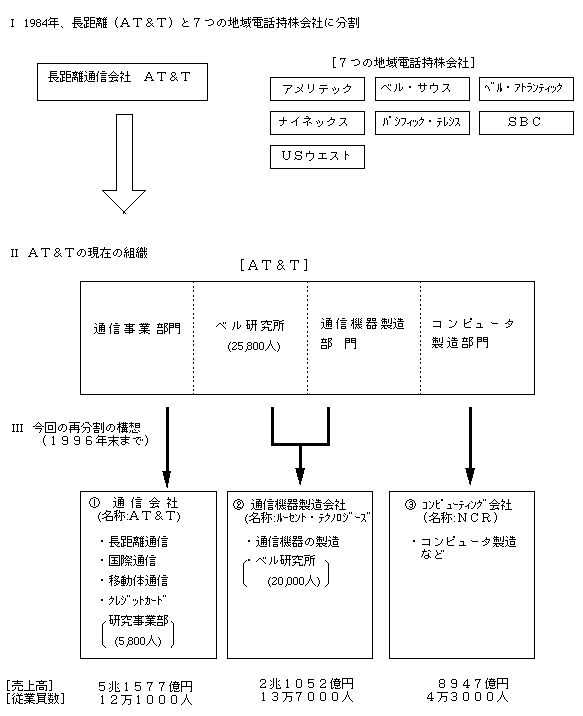
ウ ベンチャー企業の育成
米国においては、研究開発型ベンチャー企業が成長し、これらの企
業を核として連携や競争による研究開発が進展しており、米国の研究
開発力は、応用開発、サービス開発面において一段と向上していると
言われている。
情報通信分野のニーズの多様化・高度化や急速かつ大きな変化に対
応するためには、特定の分野で世界的なレベルのベンチャー企業をで
きるだけ多く育成し、これを核として異なる経験や知識を有する組織
がダイナミックに連携することにより研究開発を活性化することが重
要である。
エ 標準化への対応
情報通信市場のグローバル化に伴い、世界をリードする研究開発を
行うとともに、この成果をタイムリーに世界市場へ普及させていくこ
とが重要であり、ネットワークや端末の相互接続性、相互運用性を確
保するための標準化が一層重要となっている。
(ア) デファクト標準への対応
例えば、パソコンのOSやインターネット用の通信ソフトウェア
に見られるように、特定市場における勝者がデファクト標準となり
、各国の市場においても主導権を握るという状況が生じている。我
が国においても、このような世界的なデファクト標準を形成できる
多元的な主体の確立を強化していくことが必要である。
また、企業間の国際的な連携のほか、関係団体・企業等が国際的
に参加するフォーラム活動によるデファクト標準の策定が活発に行
われており、我が国としても一層機動的な対応が必要となってきて
いる。
(イ) デジュリ標準(公的標準)への対応
デジュリ標準への対応については、市場のグローバル化を十分踏
まえて、技術革新の成果をタイムリーに市場に導入するため、IT
U(国際電気通信連合)等での活動を一層活性化するとともに、デ
ファクト標準の活動との連携を進めるなど、より柔軟な対応を図っ
ていく必要がある。
オ 研究開発リソースの充実
(ア) 研究開発費確保のための方策の検討
電気通信分野における研究開発費を確保するため、売上高の一定
割合を研究開発費とすることをNTTをはじめとする事業者が目標
値として掲げることも検討すべきである。
(イ) 人材の育成等
ネットワーク技術、マルチメディア等に関する多様な知識を有し
、創造性豊かな人材を育成するとともに、そのような人材を確保し
ていくことが、新たな技術やサービスを創出する研究開発を推進す
る上で重要な課題である。
また、分野、組織を越え異なる経験や知識を有する研究者が交流
し、競争を行うことは、個々の研究者に対する大きな刺激となると
ともに、研究機関の活性化を促すことにもなることから、研究交流
を促進し、柔軟で競争的な研究環境を整備することが重要である。
カ 基礎的・先端的研究開発の推進
基礎的・先端的研究開発は、短期的な成功や目に見える成果にとら
われず、長期的な見地に立って取り組む必要があり、国の果たす役割
が重要である。
このため、国においては、基礎的・先端的研究開発に対する研究開
発費及びこれを行う研究機関の充実に努めるとともに、多極型研究開
発による地域ポテンシャルの向上を図りつつ、基礎的・先端的研究開
発を一層推進することが重要である。
キ 産学官の連携強化
産学官がそれぞれの特色を発揮し、連携を強め、相互の研究開発を
補完することにより、基礎、応用、開発研究のバランスがとれた総合
的な研究開発を推進することが必要である。
(7) ネットワークビジネスの推進
コンテント、ネットワークを活用したビジネスの発展を推進していく
必要がある。
(ア) コンテントの発展
コンテント事業の育成を図るためには、人材育成、ベンチャー企業
の育成等の社会環境の整備を進めるとともに、多様な競争を通じた通
信料金の低廉化や情報通信ネットワークの整備を進めることが必要で
ある。
また、通信事業者が各種のコンテント事業者と提携したり、自らコ
ンテント事業に乗り出していく環境を整備することにより、コンテン
ト事業を発展させていくことも望まれる。
(イ) ネットワークビジネスの発展
(a) 既存の製造・サービス業の新事業への変容
既存の製造・サービス業が、情報通信ネットワークを利用して、
従来のサービス、製品の高度化・高付加価値化を図り、あるいはそ
れを超えて新サービス、新製品の開発につなげて、新事業を創出し
ていくと考えられる。その結果、従来とは全く異なる新しい産業へ
と変容を遂げていく可能性もある。
(b) 新しいネットワークビジネスの成長
情報通信ネットワーク内のビジネス空間・社会的空間を提供し、
その中で一般消費者、製造業者、サービス業者、各種団体等の取引
(商品の受発注、決済等)・相互交流を実現するいわゆるサイバー
ビジネスなどの新しいネットワークビジネスが、大きく成長すると
考えられる。
(8) NTTのボトルネック独占への対処
ア ボトルネック独占から生じる問題点
(ア) 情報通信産業の新しい展開のためには、多元的主体による競争の
促進が必要であるが、この意味でNTT地域通信網のボトルネック
独占の解消は、大きな課題となっている。
(イ) 地域通信網のボトルネック独占とは、ほとんどすべての情報通信
サービスが、独占的な地域通信網を経由することによって、はじめ
て供給できる状態を指す。この地域のボトルネック独占から生じる
問題として、次のような点が指摘できる。
(a) 独占力が競争事業者に対して行使され、公正有効競争を損なう
おそれが強い。
(b) コストの削減やサービス向上のインセンティブが働きにくい。
また、コストの削減如何が地域通信網を利用するあらゆる市場の
料金水準を左右する。
(c) 全国一体的なボトルネック独占を保有する経営主体が競争分野
への進出・異業種の融合を進めると、上記(a) の弊害が一層強く
なり、多元的な競争軸を基礎とした産業のダイナミズム創出が困
難になるおそれが強い。
(ウ) したがって、ボトルネックの独占力が様々な分野で行使され、情
報通信産業全体の発展を損なうことを防止し、我が国の通信料金の
低廉化と公正有効競争を促進するために、ボトルネック独占自体の
解消を目指していく必要がある。
イ 地域通信分野における競争
(ア) 現在、我が国の地域通信分野における競争の実態は次のとおりで
ある。
(a) 携帯電話について、NTT地域通信網に依存しない通信は、全
通信の僅か0.4%にすぎない。
(b) PHSの代表的な事業形態(NTT網依存型) は、回線設備を
NTTの地域通信網に全面的に依存している。
(c) CATV電話は、まだ実用化されていない。CATV自体も、
平成6年度末現在、加入数 221万、加入率6%にとどまっている。
(d) 地域系NCCの電話加入者はNTTの6千万加入に対して、約
1万5千加入であり、これは加入電話全体の 0.025%に過ぎない。
(イ) このように、NTTの地域通信網の競争者として期待される携帯
電話、PHS、CATV、地域系NCCのいずれもが、NTTの独
占的な地域通信網と接続することが、サービス提供上不可欠となっ
ている。また、これらの地域通信メディアは、少なくとも当面は、
次に示すような状況にあると考えられる。
(a) 携帯電話やPHSについては、料金面、ネットワーク構築面、
機能面(動画伝送等)での制約がある。
(b) CATVによる通信については、料金面、技術面(流合雑音等
)での制約がある。
(c) また、前述したように、NTTは、平成7年9月に加入者交換
機等への接続を可能とする方針を発表したが、接続にかかる期間
、費用、技術的条件が不明確な状況にある。さらに、このような
接続が円滑に行われるとしても、地域系NCCがNTTの加入者
網に依存する構造や接続料金のコストが独占的なNTTの生産性
を前提とし、これに左右されることに変わりはない。
ウ ボトルネック独占解消の困難性
(ア) 管路等に対するアクセスの確保や地域通信網への接続の円滑化な
どの地域通信分野における競争促進政策を前提としても、次の理由
により、ボトルネック独占の解消には、今後相当の期間と困難性を
伴うと考えられる。
(a) 我が国の現在の地域通信網は、 100年以上の歳月をかけて、法
的独占経営の下で、非課税措置や法律による電信電話債券の加入
者による強制引受制度等の各種の優遇措置の下で構築されてきた
こと。
(b) 地域通信網を建設する工事の高コスト性、困難性
(c) 前述のように、携帯電話、PHS、CATV、地域系NCCな
どの地域通信メディアが、短期間のうちにNTTの地域通信網に
代替する可能性は、極めて低いこと
(イ) 現在の地域通信網が独占を形成しているのは、技術的、経済的要
因に負うところが大きいと考えられるが、ボトルネック独占として
競争阻害要因になることは許されない。
エ NTTの再編成
前述したようにボトルネック独占となっているNTTの地域通信網
を構造的に存置したまま、行政の関与により独占力行使の防止を図る
ことには、競争の促進にとって限界があり、また、それに伴う規制の
コストと時間が多大となるといった限界があると考えられる。
したがって、地域通信市場における競争を促進する抜本的方策をと
り、コスト削減のインセンティブを働かせるため、ボトルネック独占
となっているNTTの地域通信網に構造的な措置を検討するとともに
、それを前提とした非構造的な措置の展開を図る必要がある。
3 情報通信産業の活性化と合わせて確保が必要な課題
(1) ユニバーサルサービスの確保
(ア) 現在、電話については、既に全国あまねく提供する体制が確立され
ており、料金水準の一層の低廉化への要望に応えていくことが求めら
れるものの最低限のユニバーサルサービスはおおむね確保されている
と言える。
(イ) 今後、マルチメディアサービスの発展につれて、ユニバーサルサー
ビスの範囲が、広帯域・双方向の情報通信ネットワーク、さらにそれ
を活用したサービスにまで段階的に拡大していくことが期待される。
(ウ) 多元的主体による競争を通じた情報通信産業の活性化は、基本的に
は次のようにユニバーサルサービスの柔軟な展開を可能とする。
(a) 競争を通じて料金水準全般の引下げを可能とし、利用可能な料金
を実現することに資する。
(b) マルチメディアサービスを提供する主体が情報通信インフラを提
供する事業者だけでなく、情報通信インフラを活用してサービス提
供を行う多数の主体に拡大される。
(エ) 地域通信市場における競争の進展状況を踏まえ、すべての事業者が
離島・過疎地を含む全国あまねく地域におけるユニバーサルサービス
確保のために応分の負担をする仕組み、例えば、ユニバーサルサービ
ス確保のための基金を設置するといった新たな制度について検討を進
める必要がある。
(オ) さらに、福祉サービスの確保を図り、高齢者・障害者・低所得者な
どが、基本的なサービスを同等に享受できる環境を整備することも必
要である。
(2) 災害時その他非常時の通信の確保
(ア) マルチメディア時代には、生活に不可欠な情報や重要な商取引等の
情報通信ネットワークへの依存度が一層高まることから、災害時の影
響を最小限に抑えるため、ケーブルの地中化、衛星通信・地上マイク
ロ通信・光ファイバ、移動体通信の組み合わせ等による強固な情報通
信インフラづくりを進めるなどネットワークシステムの信頼性の向上
を図る必要がある。
(イ) また、マルチメディアサービスの提供主体の多元化が進む場合は、
非常・災害時のふくそう・途絶を最小限のものとし、また、公的機関
の優先利用を確保するため、ネットワークの耐災性の向上、非常時通
信技術の研究開発、通信事業者からなる中央安全・信頼センター(仮
称)の設置等の施策を講ずることによって、安全・信頼性の確保を図
ることを検討すべきである。
(ウ) さらに、地方自治体を中心とする防災無線についても、広域化、双
方向化、映像化が可能となる無線通信技術の研究開発を推進するなど
非常・災害時の安全・信頼性の向上を図るべきである。
(3) 消費者行政の推進
情報化の進展によって、電気通信サービスは、ますます消費者の生活
に密着したものとなり、社会において大きな役割を担うことが予想され
る。電気通信分野における消費者行政の展開に当たっては、消費者の自
主的な判断に基づき、自由かつ適切な選択を行い、真に豊かな消費生活
を営むことができるよう消費者への積極的な情報提供などの環境整備が
なされる必要がある。
(ア) 情報提供の推進
電気通信サービス、料金の多様化に伴い、消費者が適切な選択を行
うためには、正しい情報を容易に入手できる環境を整備することが重
要である。電気通信事業者が積極的な情報提供に努めることはもとよ
り、行政としても消費者の立場に立った情報提供が必要である。
(イ) 苦情処理体制の整備等
市場における消費者の選択は、自らの判断に委ねることが基本であ
るが、事業者と消費者の情報力など力量の格差にかんがみ、苦情処理
・相談体制の充実など被害が生じた場合に消費者を救済できる制度を
確立しておく必要がある。消費者が電気通信サービスに関し、行政に
対し苦情申告等を行える仕組みの法制度化や被害補償の仕組みについ
て検討するとともに、電気通信分野の消費者行政に係わる行政機能の
拡充を検討する必要がある。
〔諸外国の例〕
英国では、電気通信法で、BT等は、苦情処理手続を定め、OF
TELの承認を受けた後に公表しなければならない旨規定されてい
る。
米国では、FCCに消費者から苦情申立てがあった場合、FCC
が消費者と通信事業者間を仲介する仕組みが制度化されている。
(ウ) 情報教育の充実、情報リテラシーのかん養
情報化の進展は、一方で、情報格差を拡大する可能性もあるので、
情報アクセスに関する格差を是正・縮小し、情報を「持つ者」と「持
たざる者」の二極化を回避する必要がある。この観点から、情報教育
の充実、情報リテラシーのかん養を図るべく、学校・社会をはじめあ
らゆる教育分野における積極的な取組が不可欠である。
(エ) 情報倫理の確立
公序良俗に反する情報等の排除をはじめ、利用者がエチケットを遵
守し、真に豊かな情報交流が図られるよう情報教育の充実などを通じ
た情報倫理の確立を図る必要がある。
(オ) 消費者の権利を確保する諸制度の整備
消費者の権利を確保するため、情報化の進展に対応した諸制度の整
備を図る必要がある。
(a) 電気通信の利用の適正化に関する法的整備
電話はその即時性と簡便性のゆえに、現代社会の優れたコミュニ
ケーション・メディアとなっている。しかしながら、電話メディア
の不意打ち性、匿名性、覆面性などの特性を悪用した無言電話、わ
いせつ電話、勧誘電話などの迷惑電話は、市民生活の平穏を妨げる
ため、大きな社会問題となっている。また、最近急速に普及してい
るインターネットにおけるわいせつ通信なども社会問題となってい
る。
このような問題を解決するため、電気通信メディアの特性を踏ま
えた電気通信の利用の適正化に関する法制度化を早期に図ることに
より、健全な高度情報通信社会を構築する必要がある。
〔例〕I 無言電話、わいせつ電話等の禁止
II 深夜早朝の迷惑電話等の防止
III 迷惑電話を防止するため、消費者のプライバシー保護に
十分配慮した発信電話番号通知サービスの導入
IV インターネットやパソコン通信の電子掲示板などいわゆ
る公然性を有する通信における公序良俗に反する通信の規
律
(b) プライバシーの保護
利用者の個人情報・プライバシーの保護を図るため、個人情報の
保護に関する法制度的な対応について検討するとともに、個人情報
の漏えい、改ざん、不正利用を防止するため、暗号・認証技術の開
発・実用化を推進していく必要がある。
(c) 情報通信ネットワーク上の取引に関する制度の整備
〔例〕
電子商取引における本人確認、データの完全性確保、送受信の
事実の証拠記録の確保のための認証に関する制度の整備