





発表日 : 2000年 6月 2日(金)
タイトル : 平成11年度電気通信番号に関する研究会の報告
第2章 IMT−2000で必要な各種番号とダイヤル手順 1 IMT−2000の番号 ITU(国際電気通信連合)で標準化が進められているIMT−2000(Int ernational Mobile Telecommunications -2000)はグローバルサービスやマ ルチメディア通信サービスの提供等を特徴としており、現在普及している第二世 代のデジタル方式携帯・自動車電話に続く第三世代のシステムとなるものであり、 我が国においては2001年からのサービス開始が予定されている(*)。 IMT−2000の番号については、国際標準の規定において、電話網および ISDNと接続されるIMT−2000のユーザ識別子には、ITU−T勧告E. 164番号体系を使用するとなっており、また、E.164番号としては、各国 毎の国内番号体系(グローバル番号でない)で規定することとなっている。 我が国においては、これまで移動体通信サービスの番号として、既存携帯電話 の090番号、PHSの070番号等の0A0系番号が利用されてきており、I MT−2000においても非地理的番号である0A0系番号の利用が想定される。 具体的な0A0を決めるにあたっては、IMT−2000のサービスの特徴を 考慮する必要があるが、次の理由から既存携帯電話と同じ0A0番号の利用が適 当であると考えられる。 ・音声通話においては、既存の携帯電話と同等のサービス仕様であること。 ・IMT−2000端末に対して音声通話の発信をする側の料金も既存携帯電 話と大きな差異がないと想定されること。 ・国際標準の規定において、音声通話と音声通話以外のサービスにおいてユー ザ識別子を異なるようにするという規定はないこと。 ・仮に既存携帯電話とIMT−2000で異なる番号体系とした場合、分割損 が生じ、番号の有効利用の観点から好ましくないと考えられること。 (*)IMT−2000において、ITU勧告の対象となっている技術のうち、 我が国において2001年頃にサービス開始が想定されているものは、DS −CDMA方式、MC−CDMA方式を利用するものである。 DS−CDMA方式:Direct Spread-Code Division Multiple Access (1キャリアを直接広帯域に拡散させて伝送する符号分割多元接続方式) MC−CDMA方式:Multi Carrier-Code Division Multiple Access (拡散された1または複数のキャリアで伝送する符号分割多元接続方式) 2 携帯電話の番号容量拡大 携帯電話の番号は090に続く3桁(CDE)を事業者に指定することとなっ ており、その使用状況は2000年3月末時点で全コード数900(C=0は保 留)のうち、指定済コード数は775となっている(加入者数は5114万)。 2001年からのサービス開始が予定されているIMT−2000も携帯電話と 同じ0A0番号を利用することもあり、これまでと同様の番号需要が今後も続く とした場合には、2001年度末頃には、090番号空間が枯渇すると考えられ、 早期に番号容量拡大方法を決定する必要がある。 番号容量拡大方策としては、利用者への影響等を勘案すると、0A0番号を新 たに一つ追加する方法が適当と考えられる。3 IMT−2000の移動加入者識別番号(IMSI) 既存携帯電話と同様にIMT−2000においては、移動体ネットワークで、 無線区間での移動端末の制御を行うため、電話番号とは異なるITU−T勧告E .212に準拠した移動加入者識別番号(IMSI:International Mobile S ubscriber Identity)を用いる。これにより他の移動体事業者へローミングす る場合や、種々のサービスを提供する際に、電話番号に依存せず、無線区間での 移動端末の制御が可能となる。下図に回線交換接続の例及びITU−T勧告E. 212の番号構成を示す。なお、IMT−2000では、SIMカード(IMS I等の情報を格納するICカード)が移動端末から着脱可能となっている(MC −CDMA方式においてはオプション規定)。
MCC :Mobile Country Code(3桁:日本は440あるいは441) MNC :Mobile Network Code(2〜3桁で事業者を識別) MSIN:Mobile Subscriber Identification Number(最大10桁) NMSI:National Mobile Subscriber Identity(最大12桁) IMSI:International Mobile Subscriber Identity(最大15桁) すでにPDC方式、cdmaOne方式の既存携帯電話において、ITU−T 勧告E.212に準拠した図のようなIMSIを用いているところであるが、I MT−2000においても、ITU−T勧告E.212に準拠したIMSIを利 用することとし、全世界で共通の移動加入者識別番号体系を用いることにより、 海外の事業者との国際ローミングの提供を可能とすることが適当 である。
IMT−2000における事業者を識別するMNCについては、我が国の既存 携帯電話並びに欧米のGSM方式、ANSI−41(我が国のcdmaOneに 相当)方式でも2桁で運用されており、IMT−2000の国際ローミングでの 信号ルーチング時の分析桁数は国際的にも2桁になると考えられること、また、 参入する事業者数が100を超えないと予想されることから、現行と同じく2桁 で使用することが適当であると考えられる(*)。また、IMSIは利用者が直 接使用する番号ではないため、短桁である必要性は大きくなく、既にcdmaO neでは15桁を利用していることから、IMT−2000におけるIMSIの 合計の桁数を15桁とすることが適当である。 なお、IMSIでは、一般の電話番号と異なり、桁数が異なれば、別の番号体 系と扱えることから、IMT−2000におけるMCCはこれまで既存の携帯電 話で利用している440から利用することとする。 (*)IMSIは移動体サービス以外に、UPTでも利用することが可能である。 仮に、今後、MCCが新たに必要になった場合には、ITUへ要請すること が可能である。なお、MCCはパケット交換アドレスとして使用される国番 号のDCC(Data Country Code)に準ずる利用となっている(我が国にお いては、DCCとして、440、441、442、443が割り当てられて いる)。
4 IMT-2000における国際電気通信チャージカード番号の使用 国際電気通信チャージカード番号(International Telecommunication Cha rge Card)は、IMT−2000においては、SIMカードの物理的な個体識 別に利用されることとなっている。ITU−T勧告E.118に規定される国際 電気通信チャージカード番号の番号体系は次の通りである。
「電気通信の番号に関する研究会報告書」(平成5年5月)にて、この国際電 気通信チャージカード番号の我が国での使用について検討され、諸外国で一般的 なことから発行者番号(事業者コード)を2桁とし(日本では、現在、“01”、 “65”を使用)、発行者識別番号を6桁で運用することとしている。 現状の事業者コードは2桁であるが、今後、移動系事業者をはじめ新たな事業 者が国際電気通信チャージカード番号を使用することが考えられ、現状の2桁で は不十分であると考えられる(*)。このことから、収容可能な事業者コード数 を拡大するため、事業者コードは3桁とするのが適当と考えられる。 なお、発行者番号[事業者コード]の桁数は国内において統一する必要がある ことから、3桁化する場合、現在の事業者コード01、65については、その使 用状況を考慮に入れ、今後、010〜019、650〜659を各々に割り当て られたものとする必要がある。 (*)国際電気通信チャージカード番号の国番号は、一般の電話番号(E.16 4番号)と同じ国番号を用いることとしており、我が国では“81”のみで ある。従ってIMSIのMCCやパケット交換アドレスのDCCと異なり、 新たな国番号の取得が不可能である。 5 国際ローミングの本格導入に伴う各種番号の整理 IMT−2000の主要な特徴の一つとして「様々な利用形態で地域を越えた 利用を可能とするグローバルサービスの実現」が目指されており、日本のネット ワークで海外事業者の端末がシームレスに使用できるようにする国際ローミング サービスが計画されている。 国際ローミングの本格導入に伴い、一部海外のダイヤル手順について日本のネ ットワークでの扱いを検討する必要がある。 国際ローミングにより日本のネットワークで海外のダイヤル手順が用いられた 場合の課題として次のものがあげられる。
IMT−2000の付加サービスの制御に「#」「*」で始まる手順が規定さ れており、国内の「#」「*」との整合を検討する必要がある。
海外から日本にローミングした利用者が国際通話をしたい場合、事業者識別番 号と国際プレフィックス(010)をダイヤルする手順の他に、「+」あるい は、事業者識別番号を伴わず、国際プレフィックス(010)からの手順が規 定されており、この手順の扱いについて検討が必要である。 5−1 サービス制御コード「#」「*」の扱い サービス制御コードに関するIMT−2000の国際標準では、DS−CDM A方式、MC−CDMA方式の両方式で規定内容に差異があり、DS−CDMA 方式では*、#を、MC−CDMA方式では*を使用することとしている。なお、 *、#は着番号として用いられるのではなく、DS−CDMA方式の規定では移 動機において、また、MC−CDMA方式の規定では交換機において、その付加 サービス制御に関わる信号に変換されるものである。
DS−CDMA方式の規定では、付加サービス制御のためのダイヤル手順は* または#で始まり、#で終わる手順により実行される。例えば次のように使用さ れる。
SCの番号の例としては次のようなものがある。
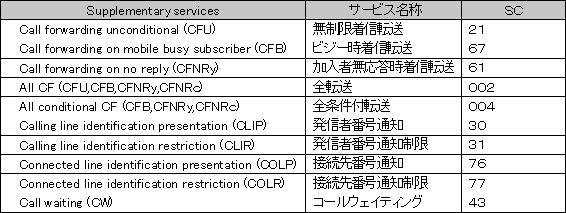
平成10年度電気通信番号に関する研究会報告書において「*」については、 「当面、事業者が独自に加入者の利便性を図るために活用することが適当である。 その際、*ab(c...)の形態で、a、b、c、...を数字として使用すること とする。」とされており、IMT−2000において使用する「*31#」等の 手順はこれと合致しないものである。 また、「#」については、同報告書で、「#から始まる番号は、複数の事業者 が一の契約者に対して同一の短縮番号を設定し、加入者から当該契約者への「呼 接続」を行う場合に利用すること、なお、#ABCDの形態でA=7〜9、B、 C、D=0〜9の数字で使用可能である。」とされている。IMT−2000に おいて使用する「#21#」等の手順はこれと合致しないものである。 しかしながら、日本のネットワークで国際ローミングを可能とする必要があり、 また、これらの番号が、我が国で現に使用されている#ABCDとも番号上齟齬 が生じることはないことから、これらの番号を許容すべきと考えられる。 なお、#ABCDについては、我が国において実際に利用者に割り付けられて おり、このことに注意して今後の国際標準化に取り組む必要があると考えられる。 5−2 国際発信手順「+」の扱い IMT−2000においては、国際発信をする場合には、発信国における国際 プレフィックスを用いたダイヤル手順とともに、国際プレフィックスが各国にお いて異なっていることを考慮して、国によらず、「+」(ファンクションキー等 で選択)のあとに相手先国際番号をダイヤルすることで国際発信が可能となる手 順もサポートしている。
発信国の国際プレフィックス+CC+SN
「+」+CC+SN (CC:国番号、SN:相手国内番号) 一方、日本において携帯電話から発信する場合には、国際系の事業者識別番号 の後に国際プレフィックス(010)、続いて相手先識別番号をダイヤルするこ ととしている(国際プレフィックス(010)の導入は優先接続が導入される平 成13年5月1日以降の予定である)。 事業者識別番号+010+CC+SN このように、我が国においては、国際のダイヤル手順は国際系の事業者を選択 する方式となっているが、海外から来た利用者においては、我が国のIMT−2 000事業者がどの国際系事業者と接続しているか不明であることが多いと考え られることから、海外からの利用者に対しては事業者識別番号を省略した国際プ レフィックス(010)のみによる方法や、「+」を使用する方法も可能とする 必要があると考えられる。 [国際プレフィックスを用いたダイヤル手順] 010+CC+SN [「+」を用いたダイヤル手順] 「+」+CC+SN