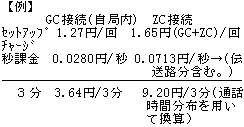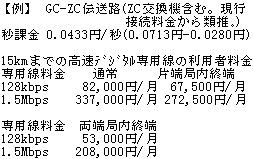条文
|
趣旨
|
指定電気通信設備の接続料に関する
原価算定規則案
目次
第一章 総則(第一条―第三条)
第二章 原価算定
(第四条―第九条)
第三章 料金設定
(第十条―第十二条)
第四章 再計算
(第十三条―第十四条)
附則
|
|
第一章 総則
(目的)
第一条 この省令は、指定電気通信
設備の接続料に関する適正な原価
の算定方法を定め、もって接続料
が能率的な経営の下における原価
に照らし公正妥当なものであるこ
とを確保することを目的とする。
|
○ 法第38条の2第3項第2号の規定
(「接続料が能率的な経営の下における
適正な原価を算定するものとして郵政省
令で定める方法により算定された原価に
照らし公正妥当なものであること。」)
に基づき、本省令を定める旨を規定。
○ 「能率的な経営の下における適正な原
価」とは、事業者の指定電気通信設備運
営の著しい不経済性により生じた費用が
原価に算入されることを排除する趣旨。
|
(用語)
第二条 この省令において使用する
用語は、電気通信事業法(以下
「法」という。)、電気通信事業
会計規則(昭和六十年郵政省令第
二十六号)及び指定電気通信設備
接続会計規則(平成九年郵政省令
第 号。以下「接続会計規則」
という。)において使用する用語
の例による。
|
○ 用語については、事業法、会計規則と
の整合性を確保するとともに、接続料に
関する原価算定の基礎となる接続会計規
則と連携して統一的に扱う旨を規定。
|
(遵守義務)
第三条 指定電気通信設備を設置す
る第一種電気通信事業者(以下「
事業者」という。)は、この省令
の定めるところにより、接続会計
規則に規定する指定設備管理部門
に整理された資産並びに費用及び
収益を基礎とし、接続料の原価を
算定しなければならない。ただし
、特別の理由がある場合には、郵
政大臣の許可を受けて、この省令
の規定によらないことができる。
|
○ 接続料の原価は、原則として、この省
令に定められた方法により接続会計規則
により整理される接続会計の結果に基づ
き算定されなければならないことを規定
。
○ ただし書の「特別な理由がある場合」
としては、指定前の接続協定に基づき既
に行われた網改造や既に設置された設備
について経過的な措置を考慮する必要が
ある場合などを想定。
|
第二章 原価算定
(接続料の原価)
第四条 接続料の原価は、電気通信
事業法施行規則(昭和六十年郵政
省令第二十五号)第二十三条の四
第二項に規定する機能(以下「省
令で定める機能」という。)ごと
に、当該機能に係る指定設備管理
運営費(指定電気通信設備の管理
運営に必要な費用をいう。以下同
じ。)に第七条から第九条の規定
に基づき計算される他人資本費用
、自己資本費用及び利益対応税の
合計額を加えて算定するものとす
る。
2 接続料の原価の算定期間は一年
とする。ただし、指定電気通信設
備にその電気通信設備を接続する
電気通信事業者が省令で定める機
能を利用して提供しようとする電
気通信役務が新規であり、かつ、
今後相当の需要の増加が見込まれ
るものであるときは、省令で定め
る機能に係る接続料の原価の算定
期間を五年までの期間の範囲内で
定めることができる。
|
○ 接続料の原価は、設備の減価償却費及
び施設保全費等からなる設備管理運営費
並びに他人資本費用、自己資本費用及び
利益対応税により構成。
○ これは、利用者料金の総括原価と基本
的に同様の考え方に基づくものであり、
接続に係る機能の提供のために、正当に
投下される資産には報酬を認め、資本調
達コストの回収を可能とするもの。
○ 接続料は、毎年度の会計結果に基づき
毎年見直すこととなっていること(法第
38条の2第10項)から、算定期間は
原則として一年。
○ ただし、当初は当該機能に対する接続
の需要が少ないが将来的に需要が相当増
加すると見込まれる場合には、初期負担
の軽減のために算定期間を5年まで延長
可能。
|
(指定設備管理運営費の算定)
第五条 省令で定める機能に係る指
定設備管理運営費は、次の表の上
欄に掲げる機能の区分ごとに、同
表の下欄に掲げる設備(これの附
属設備及びこれらを設置する土地
及び施設を含む。以下「対象設備
」という。)に係る接続会計規則
別表第二様式第五の設備区分別費
用明細表に記載された費用の額を
基礎として算定するものとする。
ただし、前条第二項ただし書に規
定する電気通信役務を提供するた
めに利用される省令で定める機能
に係る指定設備管理運営費は、接
続会計規則別表第二様式第五の設
備区分別費用明細表に記載された
費用の額及び通信量等の実績値を
基礎として、合理的な将来の予測
に基づき算定するものとする。
|
機能の区分
|
対象設備
|
端末回線伝
送機能
|
指定端末系伝送路設
備(加入者側終端装
置、指定市内交換局
に設置される主配線
盤及び指定端末系交
換等設備との間に設
置される伝送装置等
を含む。)
|
端末系交換
機能
|
指定加入者交換機
(指定端末系伝送路
設備、指定市内伝送
路設備、指定中継系
伝送路設備又は信号
用伝送装置との間に
設置される伝送装置
等を含む。ただし、
手動によるものを除
く。)
|
市内伝送機
能
|
指定加入者交換機間
に設置される指定市
内伝送路設備(指定
市内伝送路設備の両
端に対向して設置さ
れる伝送装置等を含
む。)
|
中継系交換
機能
|
指定中継交換機
(指定市内伝送路設
備、指定中継系伝送
路設備又は信号用伝
送装置との間に設置
される伝送装置等を
含む。ただし、手動
によるものを除く。
)
|
中継伝送機
能
|
指定加入者交換機と
指定中継交換機との
間に設置される指定
中継系伝送路設備(
指定中継系伝送路設
備の両端に対向して
設置される伝送装置
等を含む。)
|
交換伝送機
能
|
指定加入者交換機又
は指定中継交換機以
外の交換等設備(手
動によるものを除く
。)及び当該交換等
設備に係る伝送路設
備
|
信号伝送機
能
|
信号用伝送路設備及
び信号用中継交換機
|
呼関連デー
タベース機
能
|
呼関連データベース
|
番号案内機
能
|
番号案内データベー
ス及び番号案内装置
|
手動交換機
能
|
指定端末系交換等設
備(手動によるもの
に限る。)及び指定
中継系交換等設備(
手動によるものに限
る。)
|
公衆電話機
能
|
公衆電話機
|
|
○ 省令で定める機能ごとの設備管理運営
費は、原則として、それぞれの機能に対
応した対象設備ごとに、接続会計結果に
基づく費用の実績値(実績原価)を基礎
として算定。接続会計においては、接続
に関連する費用のみを細分された設備ご
とに集計することとしており、対象設備
ごとの費用をできるだけ正確に把握可能
。
○ 前条第二項ただし書の規定による場合
には、費用やトラヒックの実績値をベー
スとした合理的な将来予測により費用を
算定。
○ 各機能に密接な関連のある設備を対象
設備とした。
|
(指定設備管理運営費の算定の特
例)
第六条 前条の規定にかかわらず、
対象設備が帰属する設備区分が接
続会計規則別表第二様式第五の設
備区分別費用明細表において独立
した設備区分として整理されてい
ない場合においては、指定設備管
理運営費の額は、次に掲げる式に
より計算することができる。この
場合において、対象設備が法定耐
用年数経過後において更改されて
いないときは、当該対象設備の取
得固定資産価額から残存価額を減
じた差額を法定耐用年数で除して
得た額を控除するものとする。
指定設備管理運営費=第五条の規
定により算定される当該機能と類
似の機能(以下「類似機能」とい
う。)に係る指定設備管理運営費
(減価償却費相当額を除く。)×
対象設備の正味固定資産価額/類
似機能に係る指定設備管理運営費
の算定の対象となる設備の正味固
定資産価額+(対象設備の取得固
定資産価額−対象設備の残存価額
)/法定耐用年数
2 前項の対象設備の正味固定資産
価額は、次に掲げる式により計算
する。
対象設備の正味固定資産価額=対
象設備の取引固定資産価額−(対
象設備の取得固定資産価額−対象
設備の残存価額)/2
3 前項の取得固定資産価額は、合
理的な予測に基づき算定された対
象設備の購入価格又はそれに相当
する額及び設置工事費等とする。
4 第一項の類似機能に係る指定設
備管理運営費の算定の対象となる
設備の正味固定資産価額は、接続
会計規則別表第二様式第四の固定
資産帰属明細表の帳簿価額を基礎
として算定された額とする。
|
○ 交換機の一部のソフトウェアの改造に
より実現される機能の場合など、接続会
計において個別に整理されない対象設備
の管理運営費については、利用者料金の
算定に用いられる料金算定方式Bに準じ
た簡易な方法により料金算定が可能。
○ 料金算定方式Bとは、料金の対象とな
る機器等の平均的な固定資産の額を基に
将来原価を予測して算定する方法で、現
在、接続装置の使用料の算定にも用いら
れている。
○ この場合においても、保守費等の比率
は全社平均ではなく接続会計により算出
された値を用いるとともに法定耐用年数
経過後に設備更改していない場合は減価
償却費相当額を控除。
|
(他人資本費用)
第七条 省令で定める機能に係る他
人資本費用の額は、次に掲げる式
により計算する。
他人資本費用=省令で定める機能
に係るレートベース×他人資本比
率×他人資本利子率
2 省令で定める機能に係るレート
ベースの額は、次に掲げる式によ
り計算する。
省令で定める機能に係るレートベ
ース=(対象設備の正味固定資産
価額×(一+繰延資産比率+投資
等比率+貯蔵品比率)+運転資本
)×原価の算定期間
3 前項の対象設備の正味固定資産
価額は、接続会計規則別表第二様
式第四の固定資産帰属明細表の帳
簿価額を基礎として算定された額
とする。ただし、第四条第二項た
だし書に規定する機能の対象設備
の正味固定資産価額は、接続会計
規則別表第二様式第四の固定資産
帰属明細表の帳簿価額及び通信量
等の実績値を基礎として合理的な
予測に基づき算定された額とし、
前条第二項の規定により対象設備
の正味固定資産価額が算定されて
いるときはその額とする。
4 第二項の繰延資産比率、投資等
比率及び貯蔵品比率は、それぞれ
、接続会計規則別表第二に記載さ
れた指定設備管理部門の電気通信
事業固定資産の額に対する繰延資
産及び投資等(指定電気通信設備
の管理運営に不可欠、かつ、収益
の見込まれないものに限る。)の
額の占める比率並びに電気通信事
業会計規則別表第二に記載された
電気通信事業固定資産の額に対す
る貯蔵品(電気通信事業に関連す
るものに限る。)の額の占める比
率の実績値を基礎として算定する
。
5 第二項の運転資本の額は、次に
掲げる式により計算する。
運転資本=対象設備の指定設備管
理運営費(減価償却費、固定資産
除却損及び租税公課相当額を除く
。)×(省令で定める機能の提供
から当該機能に係る接続料の収納
までの平均的な日数/三百六十五
日)
6 第一項の他人資本比率は、負債
の額が負債資本合計の額に占める
割合の実績値を基礎として算定す
る。
7 第一項の他人資本利子率は、社
債及び借入金(以下「有利子負債
」という。)に対する利子率並び
に有利子負債以外の負債の利子相
当率を、有利子負債及び有利子負
債以外の負債が負債の合計に占め
る比率により加重平均したものと
する。
8 前項の有利子負債に対する利子
率は、有利子負債の額に対する他
人資本費用の額の比率の実績値を
基礎として算定する。
9 第七項の有利子負債以外の負債
に対する利子相当率は、当該負債
の性質及び安全な資産に対する資
金運用を行う場合に合理的に期待
しうる利回りを勘案した値とする
。
|
○ 他人資本費用(金融費用)については
、省令で定める機能ごとにレートベース
を設定し、会計結果から把握される他人
資本比率と他人資本利子率を乗じて算出
。
○ レートベースは、それぞれの機能の提
供に真に必要な範囲での資産であり、対
象設備の正味固定資産価額並びに繰延資
産、投資等(指定電気通信設備の管理運
営に不可欠、かつ、収益性の見込まれな
いもの)、貯蔵品及び運転資本により構
成。
○ 例えば、接続に係る機能の継続的提供
に必要な貯蔵品の適正保有量及び一定の
運転資本についても、レートベースに含
め、資本コストの回収を認めることが適
当。
○ 投資等のうち、「指定電気通信設備の
管理運営に不可欠、かつ、収益性の見込
まれないもの」とは、例えば、国際的な
標準化組織への出資等を想定。
○ 運転資本については、機能の提供から
接続料までの収納期間等を考慮して定め
る一定期間分の営業費により算定。
○ 他人資本の利子率は、有利子負債の利
子率と有利子負債以外の負債(買掛金、
支払手形、退職給与引当金等)の利子相
当率との加重平均とする。
○ 有利子負債以外の負債の利子相当率に
ついては、本来の意味での借入金等では
ないため、事業者が安全な資金運用を行
った場合の利子率をその値とすることと
する。
|
(自己資本費用)
第八条 省令で定める機能に係る自
己資本費用の額は、次に掲げる式
により計算する。
自己資本費用=当該機能に係るレ
ートベース×自己資本比率×自己
資本利益率
2 前項の自己資本比率は、一から
他人資本比率を引いたものとする
。
3 第一項の自己資本利益率は、事
業者の発行する社債券の格付その
他の指標に照らして事業者と類似
していると認められる者の自己資
本利益率及び事業者の電気通信役
務に関する料金の算定に用いられ
た自己資本利益率を勘案した合理
的な値とする。
|
○ 自己資本費用についても、機能ごとの
レートベースに事業者全体の会計結果か
ら把握される自己資本比率と自己資本利
益率を乗じて算定。
○ 自己資本利益率の算定にあたっては、
指定電気通信設備の健全な維持運営を図
るとともに、過大な利益率を防止し、利
用者料金への不当な内部相互補助をチェ
ックする等の観点からほぼ同規模の類似
企業の平均自己資本利益率及び事業者の
利用者料金の算定に用いられた自己資本
利益率を勘案。
|
(利益対応税)
第九条 省令で定める機能に係る利
益対応税の額は、次に掲げる式に
より計算する。
利益対応税=(自己資本費用+(
有利子負債以外の負債の額×利子
相当率))×利益対応税率
2 前項の利益対応税率は、法人税
、事業税及びその他所得に課され
る税の税率の合計を基礎として算
定された値とする。
|
○ 事業者の税引前利益に当たるのは、自
己資本に対する自己資本費用部分と有利
子負債以外の利子相当額にあたる部分と
なるため、利益対応税は、それらに利益
対応税率を乗じて算定。
|
第三章 料金設定
(料金設定の原則)
第十条 接続料は、省令で定める機
能ごとに、当該接続料に係る収入
が、当該接続料の原価に一致する
ように定めなければならない。
2 前項の接続料に係る収入は、当
該接続料に係る機能に対する需要
の実績値に当該接続料を乗じて得
た額とする。ただし、第四条第二
項ただし書又は第六条の規定に基
づき接続料の原価を算定した場合
は、需要の実績値に代えて将来の
合理的な需要の予測値を用いる。
3 接続料の体系は、当該接続料に
係る指定設備管理運営費の発生の
態様を考慮し、回線容量、回線数
、通信回数、通信時間又は距離等
を単位とし、社会的経済的にみて
合理的なものとなるように設定す
るものとする。
|
○ 機能ごとの接続料の原価と機能ごとの
接続料の収入が一致しなければならない
ことを定めたもの。
○ 経済的な効率を高める観点及び費用負
担の公正性を担保する観点から、接続料
の料金体系は、費用の発生の態様を勘案
し、適切な単位を基礎に定めなければな
らないことを定めたもの。
|
(交換機能の料金)
第十一条 交換機能の接続料は、少
なくとも、通信路の設定を行う機
能及び通信路を保持する機能の別
に、それぞれの機能に関連する部
分の価格が対象設備の価格に対し
て占める比率等を勘案して設定す
るものとする。ただし、合理的な
理由がある場合には、この限りで
はない。
2 前項の場合において、通信路の
設定を行う機能の接続料は通信回
数を単位として、通信路を保持す
る機能の接続料は通信時間を単位
として、それぞれ設定するものと
する。この場合において、合理的
な理由があるときは、通信ビット
数その他の単位を組み合わせて定
めることができる。
|
○ 交換機能を提供する交換設備について
は、主に通話回数に比例して使用・損耗
する部分と、主に通話時間に比例して使
用・損耗する部分があると考えられるた
め、それぞれを単位として交換機能の接
続料を定めるべきこととする。
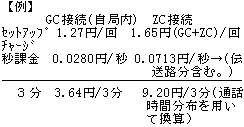
|
(伝送機能の料金)
第十二条 伝送機能の接続料は、少
なくとも、当該伝送機能に関連す
る伝送路設備の通信路が特定の電
気通信事業者との接続にのみ利用
されるもの及びそれ以外のものの
別に定め、それぞれの場合に利用
される通信路の回線容量の比率等
を勘案して設定するものとする。
2 前項の場合において、当該伝送
機能に関連する伝送路設備の通信
路が特定の電気通信事業者との接
続にのみ利用されるものの接続料
は回線容量又は回線数を単位とし
て、それ以外のものの接続料は通
信時間を単位として、それぞれ設
定するものとする。この場合にお
いて、合理的な理由があるときは
、距離その他の単位を組み合わせ
て定めることができる。
|
○ 伝送機能を提供する伝送路設備の利用
形態として、特定の電気通信事業者の通
信のみに専用的に利用する形態(専用線
的利用形態)と、多くの事業者の通信に
共用的に利用する形態(例えば、ZC接
続による中継伝送機能を利用する形態)
とが考えられるが、前者の場合には通信
量(通信時間)に比例して費用が変動す
るとは考えられないので、回線容量又は
回線数等を単位として接続料を設定し、
後者の場合には通信時間等を単位として
接続料を設定することとする。
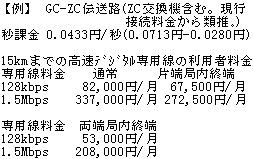
|
第四章 再計算
(接続料の再計算)
第十三条 事業者は、法第三十八条
の二第十項の規定により再計算し
た接続料を、毎事業年度経過後七
月以内にその算出の根拠に関する
説明を記載した書類を添えて郵政
大臣に報告しなければならない。
|
○ 法の規定に従い再計算を行ったときは
、再計算の根拠を明確に説明した書類を
添えて、郵政大臣に報告することとする
。なお、7か月以内としたのは、接続会
計作成後、3か月以内としたため。
|
(精算)
第十四条 事業者は、接続料を再計
算し、その結果に基づき接続料を
変更したときは、省令で定める機
能ごとに、当該機能に係る変更前
の接続料と変更後の接続料との差
額に当該機能に対する需要の実績
値を乗じて得た額の二分の一に相
当する額を、指定電気通信設備に
その電気通信設備を接続する他の
電気通信事業者と精算するものと
する。ただし、第四条第二項ただ
し書及び第六条の規定に基づき当
該機能に係る接続料の原価を算定
した場合は精算することを要しな
い。
|
○ 会計の実績値を基礎として毎事業年度
ごとに接続料を定める場合は、ある年度
の費用を前年度の費用を基礎に算定する
こととなり、現実の費用との乖離(タイ
ムラグ誤差)が生じることとなるので、
これを精算することが必要。
○ なお、タイムラグ誤差が生じる原因と
しては、事業者の合理化努力や他の接続
事業者の営業努力などが考えられるが、
厳密に量的に把握することが困難なため
、現行の接続協定と同様に誤差の二分の
一を精算することとし、事業者に一定の
合理化インセンティブを付与。
○ ただし、算定期間が二年以上の場合及
び簡易な方法により算定する場合につい
ては、一定の予測に基づき算定する方法
を採用し、費用、需要の変動を織り込ん
でいるため、精算を行わないこととする
。
|
附則
この省令は、公布の日から施行す
る。ただし、接続会計規則附則ただ
し書の規定に基づき接続会計規則が
適用されることとなるまでの間は、
第三条中「接続会計規則に規定する
指定設備管理部門に」とあるのは「
電気通信事業会計規則に基づき」と
、第五条及び第六条第一項中「接続
会計規則別表第二様式第五の設備区
分別費用明細表」とあるのは「電気
通信事業会計規則別表第二の損益計
算書及びその他の明細表」と、第六
条第四項及び第七条第三項中「接続
会計規則別表第二様式第四の固定資
産帰属明細表」とあるのは「電気通
信事業会計規則別表第二の貸借対照
表及びその他の明細表」と、第七条
第四項中「接続会計規則別表第二に
記載された指定設備管理部門の」と
あるのは「電気通信事業会計規則別
表第二に記載された」と、「指定電
気通信設備」とあるのは「電気通信
設備」と読み替えるものとする。
|
○ 本省令は、公布の日から施行すること
とする。
○ ただし、接続会計規則が適用されるま
での間は、電気通信事業会計規則に基づ
く会計の整理の結果を基礎とすることと
なる。
|