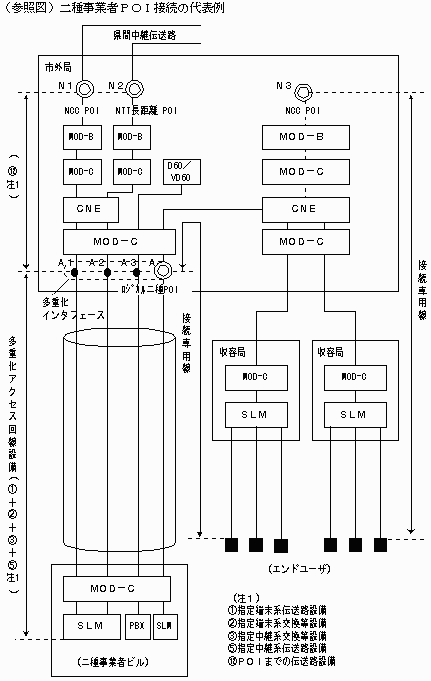指定電気通信設備の拡大・追加に関するもの
|
意見・質問(抜粋)
|
考え方
|
1 添付参照図記載の「二種POIの為の
多重化アクセス回線設備」は、「指定電
気通信設備」として指定される以下の4
設備即ち
[1]指定端末系伝送路設備
[2]指定端末系交換等設備
[3]指定中継系交換等設備
[5]指定中継系伝送路設備
の集合体と見えるが、「指定案」で定義
されている3項の専用役務(一般専用サ
ービス、高速ディジタル伝送サービス、
ATM専用サービスに限る。以下同じ。
)の記述により、前述の[3]/[5]項の設
備は「二種POIの為の多重化アクセス
回線設備」を除外しているようにも解釈
できる。もしそうであれば指定設備に入
るように修正することを要望
2 前項の修正が困難であれば、新たに1
3項をおこし「二種POIの為の多重化
アクセス回線設備」を指定することを要
望
3 参照図のA1点(A2)とN1点(N
2)間の設備は12項の指定に入ること
を確認したい(テレサ協)
|
指定端末系伝送路設備は役務によ
って設備を限定しておらず、二種P
OIのための多重化アクセス回線設
備についても端末系伝送路設備であ
り、指定電気通信設備に該当する。
また、多重化アクセス回線により提
供されるサービスは、高速ディジタ
ル伝送サービスの一種に該当すると
考えられ、その実現に必要な指定中
継系伝送路設備等についても指定電
気通信設備に該当する。
|
・ 本指定案では、当面接続が見込まれな
い設備を指定の対象から除くこととして
おりますが、指定電気通信設備及びそれ
と同様の指定対象外の設備(例えば、各
役務の県内伝送路等)の間に、指定の有
無によるコストの乖離が生じることなく
、全て指定したときと同等のコストとな
るよう、接続会計の主旨に基づき適正に
運用していただきたい(DDI)
・ 総合デジタル通信役務パケット通信モ
ードのIインターフェース加入者系モジ
ュール(ISM)は、通話モードと同様
のものであることから、費用配賦の明確
化を図るため、指定範囲とすべき
伝送路設備等については、本項に規定
された役務以外の役務についても、同一
の設備を共用することから、費用配賦の
明確化を図るため、役務を限定する必要
はない(JT)
・ ISMについては、ISDN役務に係
る指定端末系交換等設備に該当するもの
と理解しておりますが、モードの種類に
係わらず同一の設備を共用していること
から、(1)と同様に、指定するにあたっ
ては、費用配賦の恣意性を排除するとの
観点から、モードを限定すべきではない
端末系交換等設備、中継系交換等設備
、市内伝送路設備、中継系伝送路設備、
信号用伝送路設備、信号用中継交換機に
ついて、役務毎に設備を指定した場合、
指定設備と指定外設備の間で費用配賦の
恣意性が生じる恐れがあるため、当該設
備の指定にあたっては、端末系伝送路設
備と同様に役務を限定すべきではない
仮にこれらの設備を役務毎に指定する
場合には、指定外となった設備は接続会
計上、指定設備利用部門に帰属すると理
解します。その際の費用配賦にあたって
は、恣意性の働かないように充分留意し
て頂きたい
また、同一設備を異役務間で使用する
場合には、稼働当たりのコストは同一で
あることから、役務間で料金格差が生じ
ることはないと考えますので、役務に限
定することなく、設備毎に料金を設定す
ることが適当(TWJ)
|
総合デジタル通信役務(高速通信
モード及びパケット通信モードに限
る。)に用いられる指定端末系交換
等設備等指定の対象とならない設備
については、接続の請求が見込まれ
ないため、指定電気通信設備として
いない。
なお、費用配賦の適正性の担保に
ついては、指定の範囲ではなく、接
続会計・接続料金制度全体の中で対
応すべき。
|
・ 「電気通信設備の指定」において指定
される設備については、将来的に機能毎
にどの事業者が利用するのかが流動的で
あることから、当該指定電気通信設備に
おいて提供する全ての機能について指定
の対象とすべき。(中部テレコミュニケ
ーション)
|
指定の対象となるのは電気通信設
備であり、機能ではない。
|
・ 「レピーター」は、特定役務に限定さ
れることなく一定距離(概ね30km)以上
の伝送路には必須は設備であることから
、指定中継系伝送路設備の一部として指
定すべき(TWJ)
|
GC−ZC間のレピーターは、指
定中継系伝送路設備に含まれる。
|
指定電気通信設備の明確化に関するもの
|
意見・質問(抜粋)
|
考え方
|
・ 電話役務及び総合デジタル通信役務に
ついて、交換機能をもつUC及びUC−
GC間伝送路の帰属が不明確であり、規
定を明確化すべき(JT)
・ UC、UC−GC間伝送路についても
指定電気通信設備の範囲に含まれている
ものと理解(DDI)
・UC及びUC−GC間伝送路の帰属が不
明確なため、その扱いを明確にして頂き
たい(TWJ)
|
UCは、コスト削減等の理由によ
りGC交換機の機能の一部を提供す
るために設置される交換機であり、
GCと一体的なものとしてUC−G
C間伝送路設備と合わせて、全体と
して指定端末系交換等設備として扱
うことが適当と考えられる。
|
・ アンバンドル化された指定電気通信設
備の一部を利用する形態として、NTT
の局舎内のMDFやクロージャー等での
NTT網との接続(加入者回線のみの使
用)を以前から希望。
今回、公表された「電気通信事業法第
38条の2第1項に基づく電気通信設備
の指定案」(以下、「指定案」という。
)で指定された指定端末系伝送路設備に
は加入者回線区間についても含まれるこ
とから、「接続の基本的ルール」の原則
によれば、NTT以外の事業者がNTT
と同様の条件で加入者回線と接続可能で
ある必要。また、現在、実証実験が行わ
れているxDSLの実用化等加入者回線
の高度化によるニーズの増加が予想され
ることや、既存の電気通信設備の有効利
用の観点からも、他事業者による加入者
回線のみの使用が可能であるべき(アス
テル中部)
|
指定端末系伝送路設備のみに接続
する形態については、施行規則にお
いて、伝送速度の制御が可能な伝送
装置との接続及び端末回線伝送機能
の利用により、これを可能とするこ
とが定められている。
しかしながら、xDSL等につい
ては、郵政省の研究会の報告書等を
うけて現在実証実験が行われている
段階であり、その結果を待って判断
することとしている。
|
・ 6号及び8号の「信号用伝送路設備及
び信号用中継交換機」は、PHSに関す
る相互接続通信(接続型PHSと依存型
PHSとの通信及びローミング時の通信
)の際に、県を跨る通信について利用す
る場合があるため、「当該単位指定区域
内の通信を行うためのもの」を削除すべ
き(中部テレコミュニケーション)
|
施行規則に基づき、単位指定区域
内の通信を行うためのもの以外の設
備については指定の対象外となるが
、県を跨る通信について利用する場
合も単位区域内通信と同様に取り扱
うべき。
|
・ 電気通信事業法施行規則において網機
能開示される設備については、全て指定
されるものと理解
具体的には、電気通信事業法施行規則
において、網機能開示の対象外となって
いるユーザー向け付加機能サービス等以
外の網機能は全て指定電気通信設備の範
囲に含まれるものと理解(DDI)
|
届出及び公表の義務がある計画は
、指定電気通信設備に係る機能の追
加又は変更についての計画である。
|
・ Iアラーム専用端末等の監視装置につ
いても、接続に必須な電気通信設備であ
り、指定電気通信設備の範囲に含まれる
ものと理解(DDI)
・ 監視装置は接続に必須の設備であるこ
とから、指定電気通信設備に準ずる設備
として取り扱うこととし、接続約款にお
いても基本機能として規定するようNT
Tに対しご指導頂きたい(TWJ)
|
伝送路の監視装置の監視対象は、
指定端末系伝送路設備に限定されて
おらず、また、接続会計においても
支援設備として整理されていること
からも、指定電気通信設備に該当し
ない。
しかし、公正競争の確保の観点か
ら、Iアラーム専用端末の提供条件
等、具体的な監視装置の利用の条件
については、自己の電気通信設備を
接続することとした場合の条件に比
して不利でない条件で提供されるべ
き。
|






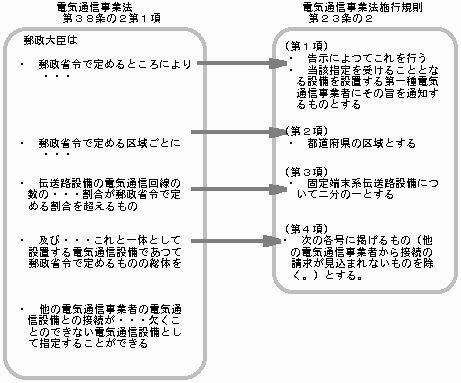 2 指定の手続
2 指定の手続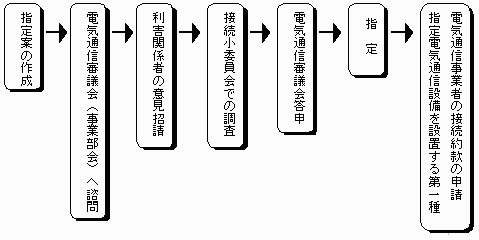 3 指定電気通信設備の指定 以下の設備のうち、日本電信電話株式会社が各都道府県に設置する設備を指 定電気通信設備として指定する。 (1)指定端末系伝送路設備 (2)指定端末系交換等設備(電話、ISDN役務の提供に用いられるもの等) (3)指定中継系交換等設備(電話、ISDN、専用役務の提供に用いられる もの) (4)指定市内伝送路設備(電話、ISDN、専用役務の提供に用いられるも の) (5)指定中継系伝送路設備(電話、ISDN、専用役務の提供に用いられる もの) (6)電話、ISDNの提供に用いられる信号用伝送路設備及び信号用中継交 換機 (7)電話番号案内に用いられる番号案内用データベース、サービス制御局等 (8)PHSとの接続に用いられるPHS接続装置、サービス制御局等 (9)公衆電話機等 (10)電話番号案内に用いられる交換機、案内台装置、伝送路設備 (11)二重帰属回線 (12)POIまでの伝送路設備 別紙2 (答 申) 平成9年11月28日付け諮問第54号をもって諮問された事案について、審 議の結果、下記のとおり答申する。 記 電気通信事業法第38条の2に基づく電気通信設備の指定については、以下の 事項に配慮した措置を講じた上で、諮問書のとおり指定することは適当と認めら れる。 なお、提出された意見並びにそれに対する当審議会の考え方は、別添のとおり である。 1 指定電気通信設備の範囲については、随時、関係事業者等からの要望を踏ま えつつ、必要に応じ見直しを行うこと。なお、その際「接続に関する議事手続 細則」に基づき、利害関係者等から聴取した意見を参考とすること。 2 指定の基準となる回線数については、毎年度末適正に回線数が把握できるよ う電気通信事業報告規則の見直しを行うこと。 別紙3 指定案に対する意見及び考え方
3 指定電気通信設備の指定 以下の設備のうち、日本電信電話株式会社が各都道府県に設置する設備を指 定電気通信設備として指定する。 (1)指定端末系伝送路設備 (2)指定端末系交換等設備(電話、ISDN役務の提供に用いられるもの等) (3)指定中継系交換等設備(電話、ISDN、専用役務の提供に用いられる もの) (4)指定市内伝送路設備(電話、ISDN、専用役務の提供に用いられるも の) (5)指定中継系伝送路設備(電話、ISDN、専用役務の提供に用いられる もの) (6)電話、ISDNの提供に用いられる信号用伝送路設備及び信号用中継交 換機 (7)電話番号案内に用いられる番号案内用データベース、サービス制御局等 (8)PHSとの接続に用いられるPHS接続装置、サービス制御局等 (9)公衆電話機等 (10)電話番号案内に用いられる交換機、案内台装置、伝送路設備 (11)二重帰属回線 (12)POIまでの伝送路設備 別紙2 (答 申) 平成9年11月28日付け諮問第54号をもって諮問された事案について、審 議の結果、下記のとおり答申する。 記 電気通信事業法第38条の2に基づく電気通信設備の指定については、以下の 事項に配慮した措置を講じた上で、諮問書のとおり指定することは適当と認めら れる。 なお、提出された意見並びにそれに対する当審議会の考え方は、別添のとおり である。 1 指定電気通信設備の範囲については、随時、関係事業者等からの要望を踏ま えつつ、必要に応じ見直しを行うこと。なお、その際「接続に関する議事手続 細則」に基づき、利害関係者等から聴取した意見を参考とすること。 2 指定の基準となる回線数については、毎年度末適正に回線数が把握できるよ う電気通信事業報告規則の見直しを行うこと。 別紙3 指定案に対する意見及び考え方