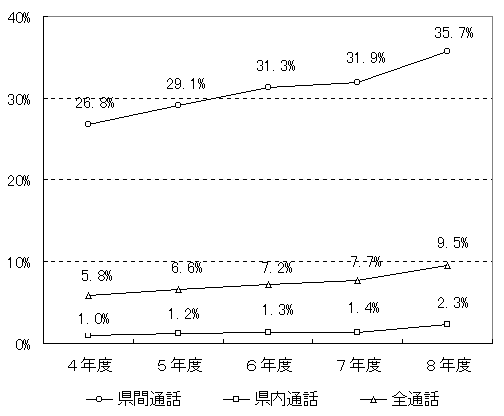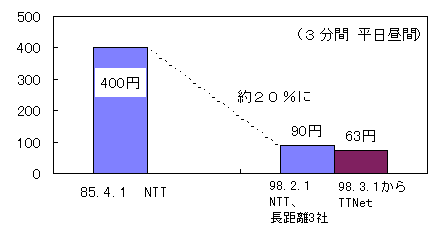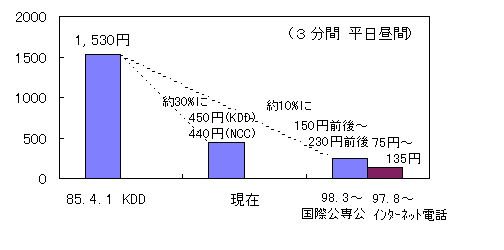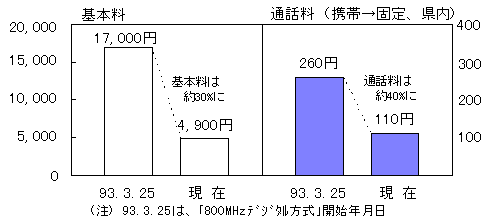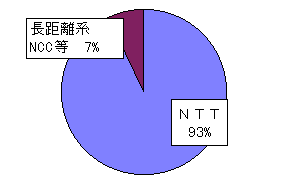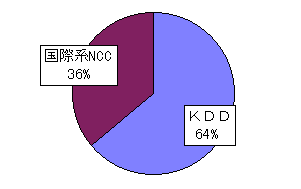優先接続は、電話サービスの提供に関し、地域網事業者が接続事業者に対して
提供する機能であり、利用者が接続事業者のサービスを利用する場合に、あらか
じめ事業者を選択し登録しておけば、当該事業者の事業者識別番号のダイヤリン
グを省略して通話を可能とする仕組みである。また、この優先接続は、電気通信
分野における公正競争条件整備の観点から、事業者識別番号のダイヤルが不要な
NTTと事業者識別番号のダイヤルが必要な他の新規参入事業者との間でダイヤ
ル方法の公平を図るとともに、利用者利便の確保の観点から、現行よりも余分な
ダイヤルを少なくするための手段である。
本研究会では、1999年夏に予定されているNTTの再編成に伴い、優先接
続の導入を検討する必要があることから、本年3月より、優先接続を巡る論点整
理を行い導入に向けた基本的方向を見いだすべく検討を行ってきた。
本中間報告書は、本研究会にオブザーバーとして参加して頂いた関係事業者か
らの意見も参考として、7回の会合を経て中間的にとりまとめたものである。優
先接続の問題は、電話サービスの利用方法及び契約方法に大きな変更を来す重要
な問題であり、利用者や関係事業者を含め広く利害関係者からの意見を踏まえた
十分な検討が必要と考えられることから、本中間報告書をもって、継続検討とし
ている項目だけでなく、一定の方向を示している項目を含めた全体について公開
意見招請を行うこととしたい。
なお、本研究会では、それによって得られた意見を踏まえて検討を継続し、本
年秋にも最終報告をとりまとめる予定である。
第一種電気通信事業については、1985年4月の制度改革以降、新規参入
が行われ、1998年4月1日現在の事業者数は153社となっている。この
内、新規事業者は142社あり、その内訳としては、長距離・国際系6社、地
域系47社、衛星系5社、移動系84社となっている。
|
第 一 種 事 業 者
|
第二種
事業者
|
合計
|
|
NTT
KDD
|
NTT
ドコモ
等
|
長距離・
国際系
|
地域系
|
衛星系
|
移動系・
その他
|
計
|
1998.
4.1
|
2
|
−
|
5
|
4
|
2
|
24
|
37
|
530
|
567
|
1998.
4.1
|
2
|
9
|
6
|
47
|
5
|
84
|
153
|
5,871
|
6,024
|
1) 国内通話のトラヒック
1996年度の総通話回数は1,092億回で、対前年度15.4%増と、
過去5年間で最高の伸び率を示し、初めて1,000億回を超えた。また、
総通話時間は44.4億時間で、対前年度6.7%増となっている。
発信種別
|
通話回数
|
通話時間
|
加入電話
|
946.9 ( 7.8%)
|
4,069( 2.3%)
|
携帯・自動車電話
|
109.8 ( 95.0%)
|
269( 102.1%)
|
PHS
|
18.9 (1050.0%)
|
50(1000.0%)
|
ISDN
|
16.1 ( 78.4%)
|
56( 93.1%)
|
合 計
|
1,091.7 ( 15.4%)
|
4,444( 6.7%)
|
(注)1 単位は、通話回数は億回、通話時間は百万時間
2 ( )内の数字は、対前年度伸び率
3 ISDNは通話モードに限る。
2) 国内電話トラヒックの距離別シェア
1996年度の加入電話相互間における長距離系NCCの通話回数のシェ
アは、NTTのウエイトの大きい県内通話においては2.3%であるが、県
間通話においては35.7%と3分の1を超え、県内、県間ともに最近5年
間で最高の伸びを示した。全通話回数のうち長距離系NCCの占めるシェア
は9.5%と拡大しつつある。
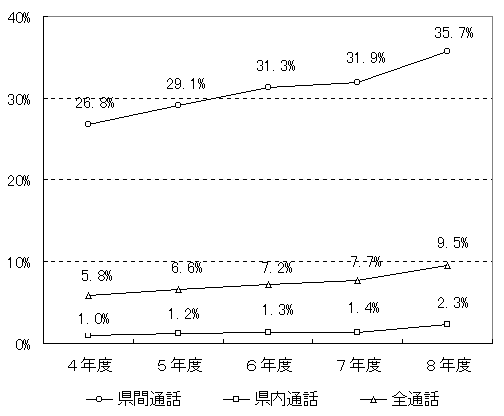
3) 国際通話のトラヒック、シェア
1996度の総通話回数は7.6億回で、対前年度11.4%増、総通話
時間は0.5億時間で、対前年度9.4%増となっている。また、国際系N
CCの発信分数のシェアは35.5%となり、対前年度比1.4%増と微増
している。
1) 国内通話
長距離系NCC3社が、1987年9月に最遠距離平日昼間3分間300
円(NTTは同400円)で国内電話サービスを開始して以来、NTTとの
値下げ競争を繰り返し、現在では、NTT及び長距離系NCCともに同90
円にまで低廉化している。
なお、現在ではTTNetが同63円でサービスを提供しており、またK
DDは本年7月1日から同69円で国内電話サービスを開始する予定である。
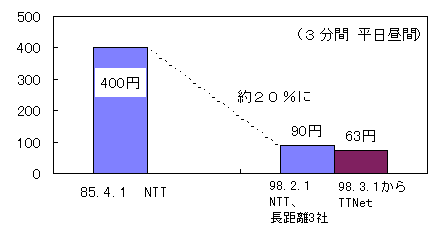
2) 国際通話
日本国際通信株式会社(現日本テレコム)及び国際デジタル通信株式会社
が1989年10月に、KDDより約23%安い料金でサービスを開始して
以来、KDDとの値下げ競争を繰り返し、現在では、日米間の国際自動ダイ
ヤル通話は平日昼間3分間でKDD450円、NCCが440円にまで低廉
化している。
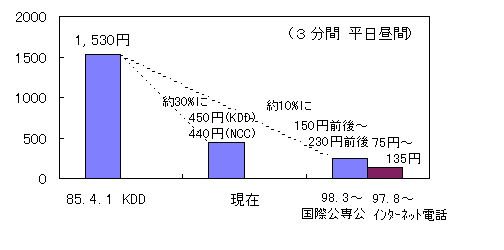
3) 携帯電話
携帯電話やPHSについても新規事業者が次々とサービスを開始し、料金
の低廉化が著しい。
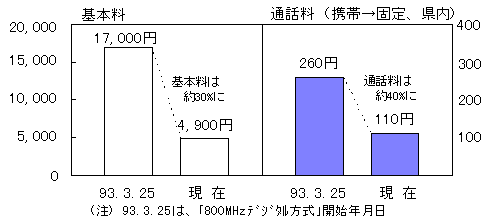
1997年度の第一種電気通信事業者の電話サービスの売上高は、 地域系・
移動体通信の大幅な増加のため、合計は9兆2,241億円(前年度比8.4
%増)となっている。
内訳は固定系の国内が5兆339億円(同8.0%減)、国際が3,961
億円(同1.1%減)、計5兆4,300億円(同7.5%減)、移動系が3
兆7,942億円(同43.7%増)となっている。
(単位:億円)
区 分
|
NTT
|
KDD
|
長距離系
NCC
|
国際系
NCC
|
地域系
NCC
|
移動体
通 信
|
合 計
|
電話役務
(増減率)
|
44,538
(-7.2%)
|
2,515
(-5.0%)
|
5,699
(-14.6%)
|
1,447
(6.4%)
|
101
(78.1%)
|
37,942
(43.7%)
|
92,242
(8.4%)
|
|
国 内
(増減率)
|
44,538
(-7.2%)
|
1
(注)
|
5,699
(-14.6%)
|
−−
|
101
(78.1%)
|
37,942
(43.7%)
|
88,281
(8.8%)
|
国 際
(増減率)
|
−−
|
2,514
(-5.0%)
|
−−
|
1,447
(6.4%)
|
−−
|
−−
|
3,961
(-1.1%)
|
(注) 1 KDDの国内電話サービスは、平成9年7月26日から開始。
2 減収要素
1)NTT:加入数の減少、平成9年2月及び平成10年2月の料金値
下げ及びアクセスチャージ改定等
2)長距離系NCC:平成10年3月の市外通話料金値下げ及び割引
サービスの普及等
3)国際事業者:割引サービスの普及等
<参考> 固定系事業者の電話サービス売上高シェア
国内電話
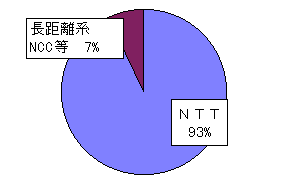
|
国際電話
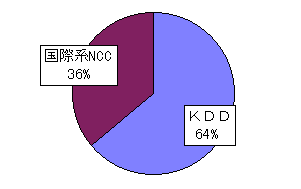
|
現在、情報通信は各国の戦略産業として位置付けられ、各国の情報通信政策
の在り方が国の将来の発展を左右するものと考えられるようになっている。我
が国でもこのような情報通信の戦略性を踏まえて、この数年新たな段階の改革
が推進されつつある。この数年の改革の基本的な柱は、「競争促進を通じたダ
イナミズムの創出」、「デジタル化を基礎とした放送革命」、「新しい情報通
信基盤の整備」という3点であり、1985年前後に経験したNTT民営化、
競争原理導入を柱とする第一次情報通信改革に対し、「第二次情報通信改革」
と位置づけられている。
電気通信分野の競争政策としては、以下の「規制緩和の推進」、「接続ルー
ルの整備」、「NTTの再編成」の3つの局面を中心に推進されている。
1) 規制緩和の推進
主な規制緩和の例としては、以下のものが挙げられる。
○ 移動体通信料金の自由化
○ 国内通信及び国際通信における公ー専ー公接続の自由化
○ 第一種電気通信事業の過剰設備防止条項の廃止
○ 第一種電気通信事業(NTTを除く)の外資規制の撤廃
○ 第一種電気通信事業の料金の原則届出化
○ KDD法の廃止
2) 接続ルールの整備
接続交渉を当事者間の自主交渉に委ねていた従来の制度を改正し、接続
をすべての第1種電気通信事業者に義務づけることとしたほか、NTTの
ように独占的な地域網を保有する事業者については、接続料及び接続の条
件について接続約款の作成を義務づけ、接続協定の締結は認可された接続
約款によることとされた。
3) NTTの再編成
NTTの再編成は、現在のNTTを持株会社の下に長距離会社1社、地
域会社2社に再編成するものである(詳細後述)。また、NTTは再編成
前にも子会社の形態で国際通信に参入することが可能となっている。
NTTの再編成は、我が国の電気通信市場における公正有効競争の促進を図
るとともに、NTTの国際通信業務への進出を可能とし、我が国の事業者が情
報通信のグローバル化に対応できる体制を構築しようとするものである。これ
によりNTT自身の活性化と我が国の情報通信産業全体のダイナミズムが創出
され、先に述べた規制緩和や接続ルールの整備と相まって、公正な競争市場が
生まれることが期待されるところである。
また、KDDについても、昨年7月から国内通信サービスを開始したほか、
今夏にもKDD法の廃止が予定されている。
また、1998年2月のWTO基本電気通信交渉合意の発効に伴い、今後、
世界的に電気通信分野の国際競争が急速に展開されると想定されている。既に
我が国においては、複数の外資系電気通信事業者が事業参入のための許可を取
得したり、参入の計画を有しており、NTT再編成や、既存長距離系事業者及
び国際系事業者の合併等とも併せ、通信のビックバンともいえる状況が生じつ
つある。