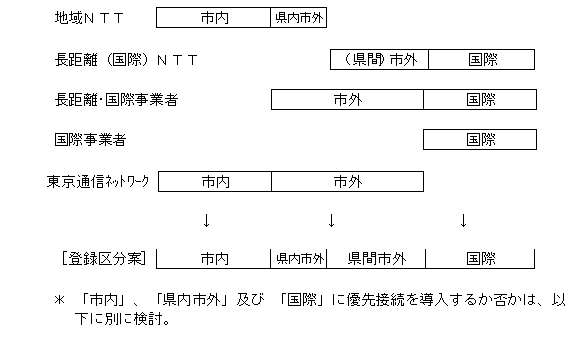4 優先接続の導入に関する具体的検討課題(論点整理)
|
1) 優先接続に関する経緯等
優先接続については、1985年の電気通信制度改革後、長距離系NCC
が参入した際や、それ以降にも長距離系NCCからNTTに対して、公正競
争及び利用者利便の観点から、我が国でも優先接続を導入して欲しい旨の要
望がなされ、事業者間協議が行われた経緯がある。(当時、米国では198
4年のAT&T分割にあわせて優先接続を導入していたため、米国と同様の
制度が必要ではないかという議論があった。)
しかしながら、1985年の時点では優先接続機能の提供が不可能な旧式
の市内交換機が存在していたことや、当時は接続ルールが必ずしも十分整備
されておらず、事業者間で協議が整わない事項を実施することが事実上困難
となっており、優先接続についても、費用負担等の問題でNTT、NCC間
の協議が整わなかったことことなどからその導入が見送られた。
その後、長距離系NCCは、利用者獲得手段として、利用者が事業者識別
番号をダイヤリングしなくともNCCネットワークに自動的に接続する装置
(アダプタ等)を開発・提供したため、優先接続の議論は、一時下火になっ
ていたところである。
しかしながら近時において、次のように、優先接続を巡る環境が変化して
きている。
○ 接続ルール(注)が整備され、いわゆる不可欠設備の接続条件の約款
化や事業者間の接続協議が整わない場合の手続きの迅速化などが実現し
たため、優先接続について再度議論する土俵が整備されたこと。
○ 規制緩和による競争の進展に伴い、例えば東京通信ネットワーク、K
DD等による中継電話サービスへの新規参入などが行われつつあり、こ
うした事業者から優先接続導入に対する要望が出されていること。
○ NTTの再編成に伴い、長距離NTTに関し、公正競争条件及び利用
者利便の確保の観点から、優先接続導入の必要性が高まっていること。
(次の2)に詳述)
(注)優先接続の接続ルール上の位置付け
電気通信事業法第38条〜第39条の2に規定される接続ルール
において、優先接続は次のように位置付けられている。
○ NTTの地域網は、他の事業者との接続が利用者の利便の向
上及び電気通信の総合的かつ合理的な発達に欠くことのできな
い「指定電気通信設備」と位置付けられている。
○ NTTは指定電気通信設備に関し、接続料及び接続の条件
(優先接続に関するものを含む)について接続約款を定め、郵
政大臣の認可を受けなければならない
(その変更も同じ)。
○ 当事者が取得し、若しくは負担すべき金額又は接続の条件そ
の他協定の細目(優先接続に関するものを含む)について当事
者間の協議が整わない場合は、接続事業者は郵政大臣に裁定を
申請することができる。
○ NTTは指定電気通信設備の機能(優先接続機能を含む)の
変更又は追加の計画を有するときは、事前に郵政大臣に届出た
上、公表しなければならない。郵政大臣は円滑な接続に支障が
生じるおそれがあると認めるときは、その計画の変更を勧告す
ることができる。
2) NTT再編成と優先接続の導入
NTTの再編成に際しては、利用者利便の観点から、既存NTT利用者が
長距離NTTの長距離通話サービスを利用する場合のダイヤル方式は現状の
ままとすることが適当と考えられる。
つまり、長距離NTTのネットワークは、東西の地域NTTとの関係では
他の長距離系NCC等のネットワークと同列に位置付けられ、競争条件の公
平性を確保する観点からは、地域NTTの利用者が長距離NTTのサービス
を利用する際には、他の長距離系NCC等と同じく4桁の事業者識別番号を
追加してダイヤルする方式とすることが望ましい。
しかし、多くの利用者に4桁の事業者識別番号を追加してダイヤルするよ
うに求めることは、明らかなサービス利用条件の低下であり、利用者利便の
観点からは好ましくない。
そこで4桁の追加ダイヤルを代替する方策として優先接続を導入すること
が考えられる。
そして、長距離NTTについて優先接続を導入する場合には、競争条件の
公平性を確保する観点から、他の長距離系NCC等についてもその仕組みの
適用を可能とすることが必要である。
|
NTT
|
長距離系NCC等
|
現行
|
06−234−5678
市外局番−市内局番−加入者番号
|
00XY+06−234−5678
事業者識別番号+同上
|
優先
接続
導入後
|
事前優先登録+
06−234−5678
|
事前優先登録+
06−234−5678
|
したがって、NTTの再編成に伴い利用者利便を確保しつつ公正競争条件
を確保する方策として、少なくとも長距離通話については優先接続を導入す
ることが適当と考えられる。
なお、市内通話、県内市外通話及び国際通話については、上記とは異なった
事情にあり以下に別に検討する。
通話ごと選択は、優先接続を導入する場合に、加入電話の契約回線ごとの事
前の固定的事業者選択に加えて、通話のつど事業者識別番号をダイヤルするこ
とにより他の事業者への接続をも可能とする仕組みである。換言すると、通話
ごと選択を併用すると、利用者は、普段は優先接続登録事業者に接続されてい
るが、個別的な必要性に応じて登録事業者以外の事業者識別番号をダイヤルす
れば、当該事業者に接続されるものである。
この通話ごと選択は、利用者の利便性の観点からは、故障や災害等に備えた
多ルート化のため、また接続事業者のサービス内容の違いに応じ通話のつど事
業者選択を可能とするためなど、優先接続を導入する場合でも併用を可能とす
ることが必須のものと考えられる。また、この通話ごと選択の併用を可能とす
ることはグローバルスタンダードでもある。
1) アダプタ等の現状等
長距離系NCCが利用者宅に設置しているアダプタ等(注)は、利用者が
長距離系NCCを利用するため電話番号をダイヤルするつど自動的に当該事
業者の事業者識別番号を発信する機能を有している。優先接続は基本的には
地域網事業者の市内交換機に機能付加することにより実現されると想定され
るが、このアダプタ等は実態的に利用者宅内の端末機において実現する優先
接続ということもできるものである。
このアダプタ等は長距離系NCCからの報告では、PBXへの機能付加を
含めて1997年度末時点の3社合計で1,650万回線程度である。なお、
長距離系NCC3社の重複を含む延べ契約回線数は約3,900万回線と
なっている。
(注)アダプタ等
長距離系NCC3社は、これまで、電話機に外付けするアダプタや
電話機やPBXに内蔵する部品(本報告書では「アダプタ等」と呼
ぶ。)により、LCR(Least Cost Routing:最も安い料金の事業者
を選択すること)と呼称する機能を提供してきている。
長距離系NCCは利用者に対して、LCRは最低料金事業者選択機能
(NTTと長距離系NCC3社(3社の料金はこれまで同一であっ
た。)との2つの料金表を基に、通話ごとの市外局番から距離段階別
の料金を算出して、料金が安い方の事業者を選択。NCC側が安い場
合はアダプタ等の提供事業者を選択。)と事業者識別番号自動発信機
能(料金を比較し自社の回線に接続する場合は自社の事業者識別番号を
市外局番の前に自動的に付加してダイヤル信号を発信。)を有するもの
と説明し、設置の勧奨を行っていた。
ところが、最近の多様な割引料金サービスの普及や新たな長距離電
話サービス提供者の出現に伴い、最も安い料金の事業者を選択すると
いう説明ができなくなったことから、本年3月までに、ACR
(Automatic Carrier Routing:自動電話会社接続機能)等と呼称を変
更している(ハード、ソフトの機能はこれまでと同様。)。
また、最近では東京通信ネットワーク(株)が事業者識別番号自動発
信機能を有するアダプタの提供を行っており、第二種電気通信事業者
においても別種の公専公アダプタの提供を行っている。
2) ネットワークによる優先接続とアダプタ等による優先接続との比較
一部の長距離系NCCには、これまで多くの時間とコストを投じてアダプ
タ等により実質的な優先接続を導入済みであり、優先接続の導入は時期を失
しており今日では不要との意見がある。以下ではこの点について検討する。
まず、ネットワークによる優先接続とアダプタ等による優先接続との経済
比較であるが、今回のNTTの試算によれば、約6200万の全回線につい
てネットワークの機能として優先接続を導入するための網改造費用、事前周
知費用、導入初期の大量登録費用等は約300億円(導入時の投資及び費
用)である。一方、アダプタ等を普及させている長距離系NCCの報告では、
約1,650万のアダプタ設置回線についてのアダプタ等の調達・工事費用
は3社合計で年間約400億円(毎年度の費用等)である。
したがってネットワークの機能として優先接続を導入する場合の方が、ア
ダプタ等を設置する場合より、一般的にはかなり経済的ということができる。
このことは、事業者が負担するコストは最終的には利用者の料金に転嫁され
るものであり、重要なポイントである(後に(13)において詳述)。ただし、
利用者が大規模な事業所でPBXに高度な機能を付加する場合など、個別的
ケースによっては経済性が逆転しうることはありうる。
また、経済性を別に置くとしても、現実にアダプタ等は多くの利用者宅に
設置されておらず、アダプタ等による優先接続機能の利用よりもネットワー
クによる優先接続の利用を望む利用者も想定される。
さらに、東京通信ネットワークやKDDの中継電話サービスへの本格参入
等に見られるように、今後とも料金、サービス競争が一層進展すると想定さ
れるが、これらの新規参入事業者からは、ネットワークによる優先接続に対
する強い要望が出されている。
また、これまでのアダプタ等は、長距離系NCC3社が、圧倒的な市場
シェアを有するNTTに対抗するという構造の下で、最も安い事業者を選択
する機能を有する機器として提供されてきたため、結果的に長距離系NCC
間の料金の多様化競争に対する阻害要因となってきた側面があり、今後多様
な料金競争の進展が想定される中で、アダプタのみによる優先接続では、利
用者ニーズに的確に対応することや健全な競争を促進していくことが必ずし
も十分ではなくなってきている。
3) 優先接続を導入する場合のアダプタ等の取扱い
このアダプタ等の取扱いについて、一部事業者から、以下のような意見が
出されている。
すなわち、ネットワークによる優先接続と現在のアダプタ等による事業者
選択機能は基本的に両立せず、矛盾するものである。優先接続の導入後もア
ダプタ等を併存をさせる場合は、アダプタ等が競争上優位となると考えられ、
アダプタ設置競争を招き事業者に二重投資を強い、利用者料金の将来的な低
廉化を阻害する要因になりかねない。また、優先接続の導入が事業者間競争
において既存のアダプタ等の設置者に優位となり、競争中立性が阻害される
恐れがある、というものである。
これに対しては、今後のアダプタ等ではネットワークによる優先接続機能
以上に小回りのきく高度な機能提供も可能であり、利用者にとりこの二つの
方法のうちから選択することが可能であり、また、利用者によっては、同時
に二つの方法を並行して利用することを希望することも想定され、両者が基
本的に矛盾するとはいえないと考えられる。なお、今後の競争に与える影響
等の問題については、次の4)及び(16)で検討する。
また、ネットワークによる優先接続を導入する場合には、国民経済的にも、
電気通信制度としても、アダプタ等は不要とすべきではないかということに
ついては、以下のように考えられる。
○ アダプタ等に併設される一定の制約内での料金比較機能や料金表示機
能等、利用者の電話利用の利便性を向上させる工夫は望ましいものであ
ること
○ すべての場合について一概にどちらが経済的かを断じることはできな
いこと、また、技術革新等により、今後、アダプタ等の機能向上やコス
トの低廉化も想定されること
○ アダプタ等の機能を内蔵する電話機の購入者(稼働数)も約900万
に上ると推定され、当該購入者の利益保護にも配慮する必要があること
○ これまで長距離系NCCは、事業者識別番号に係る競争条件の不利を
補う必要性もあり、多額の投資を行い自助努力でアダプタ等を普及させ、
実態上の優先接続を実現させてきたものであり、この市場実態は尊重す
る必要があること
○ 第二種電気通信事業者の中でも事業規模が小さい事業者は、加入者線
接続の形態をとるため、優先登録への参加もできず、20桁以上もの追
加ダイヤルを省略するためのアダプタ等の提供が必須であること
○ アダプタ等は電気通信制度上その設置・利用が自由とされている端末
機器に該当するものであり、技術的問題等特別な理由がない限り制度的
な制限は困難であること。
したがって、ネットワークによる優先接続を導入する場合でも、制度的に
アダプタ等の設置を制限することは適当ではない。
優先接続を導入済みの諸外国においては、我が国ほどアダプタ等が普及し
ている例は見られないが、これは、ほぼ競争導入と機を一にして優先接続が
導入されたため、アダプタ等を普及させるニーズが乏しかったためと考えら
れ、諸外国の優先接続の制度においてアダプタ等の設置が禁止されているわ
けではない。
利用者は、現行のアダプタ等や今後の新たなアダプタ等(端末機全般を含
む。)によるサポート機能とネットワークによる優先接続とを比較して選択
し、今後の在り方を決定することが可能であり、アダプタ等の今後の在り方
は、利用者の選択、市場の決定に委ねるべき問題と考えられる。
4) ネットワークによる優先接続とアダプタ等による優先接続との併存下にお
ける競争の在り方等
以上検討してきたとおり、優先接続の機能をネットワークでもアダプタ等
でも実現できるようにすることにより、事業者及び利用者の選択の幅が拡大
するとともに、ネットワーク系及び端末系の技術革新、サービス開発競争を
促進することが可能となると考えられる。
なお、現在のアダプタ等を巡る競争の在り方については、次のような問題
の指摘がある(後に(16)において詳述。)。
○ 事業者がアダプタ等を無料で設置する際、利用者に対してアダプタ等
の機能説明を十分には行っていないのではないか。
○ 利用者が設置後一定期間内にアダプタ等の利用契約を解除する場合、
違約金を請求されることがあるという仕組みは、競争制限的ではないか。
○ 競争中立性確保の観点から、固定優先接続方式(利用者の選択肢の一つ
として、アダプタ等から自動的に発信される事業者識別番号に係わらず、
ネットワークの機能として登録先事業者に固定的に接続する優先接続方
式)もあわせて導入するべきではないか。
他方、ネットワークによる優先接続を導入している米国では、後述のよう
に、競争事業者やその代理店等が利用者の同意を得ずに優先登録先事業者を
勝手に変更してしまうスラミングが大きな社会問題となっている。
これらの問題については、事業者が優先接続に関する提供条件、利用条件
をきちんと利用者に開示することや利用者の同意確認をきちんととることが
必要であり、行政としても競争の実態を注視するとともに、必要に応じて行
政指導等の措置を検討すべきである。
また、現在のアダプタ等については、事実上、特定の事業者に接続するよ
うにあらかじめ設定されてしまっており、利用者の利用要望に応じて弾力的
に事業者を使い分ける機能が組み込まれていない点が問題であるとの指摘が
ある。この点については、事業者から独立した中立的な事業者選択機能を有
するアダプタ等が開発され、各事業者の料金変更等に応じて利用者が、容易
に優先的に接続する事業者を変更したり、通話のつど複数の事業者の中から
自由に利用者が選択できるようになることが望まれる。
このように、アダプタ併存下における競争の在り方については、種々の論
点があり、優先接続の導入とアダプタ等の併存という本研究会での結論が事
業者間の競争にどのような影響を与えるか、問題が生じるとすれば、それを
解決するために、どのような措置が必要か等、今後公開意見招請において寄
せられた意見等も踏まえてさらに検討し、結論を得る必要がある。
1) 利用者が事業者を選択して優先登録を行う場合に、「市内」から「国際」
までの通話範囲をどう区分して取り扱うかについて検討する必要がある。
優先接続の通話区分については、現実の接続事業者の参入実態を踏まえ利
用者にとって選択しやすいものとするとともに、今後の新規参入事業者が多
様な形態で参入することや既存及び新規の事業者が料金を、より柔軟に設定
することが想定される中で、できるだけ競争中立的な区分とすることが望ま
しい。
具体的には、下図の競争領域の実態を踏まえ、当面、次の2)で検討するよ
うに市内、県内市外、県間市外、国際の4区分とすることが適当であるが、
この区分以外の通話区分を設けて欲しいという事業者の要望が今後出される
場合には、それに柔軟に対応できるよう優先登録の仕組みを実現する上で工
夫すべきである。
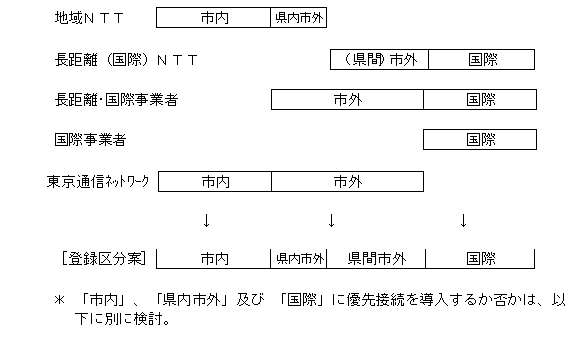
2) 優先登録区分の考え方
「国際」に優先接続を導入する場合は、現時点では国際又は国内を専業又
は主軸とする事業者が存在することから、少なくとも当面は、「国内」と
「国際」との別に区分を設けることが適当と考えられる。
また、「市内」に優先接続を導入する場合は、現時点では市外/長距離を
主軸とする事業者が存在することから、少なくとも当面は、「市外」と「市
内」との別に区分を設けることが適当と考えられる。
また、県の内外の区分を設けるかどうかについては、地域NTTの業務範
囲が法律により県内に限定されていることから(県内通話に限定された事業
者の存在)、「県内市外」と「県間市外」との別に区分を設けることが適当
と考えられる。したがって、上記登録区分案が適当と考えられる。
1) 市内及び県内市外通話への優先接続の導入
優先接続機能を提供する地域NTTにとり、市内及び県内市外通話は自社
が接続事業者と競合してサービスを提供する分野であり、自社との競合が生
じない県間市外及び国際通話分野とは、優先接続機能提供の意義に異なる面
がある。また、諸外国においても優先接続の対象は、市内を除く長距離及び
国際が対象となっている。したがって、我が国においても、優先接続の対象
は長距離及び国際に限定すべきとの考え方があり得る。
しかしながら、我が国においては、市内通話を含めた全分野で競争を促進
する競争政策をとっており、また、接続ルールにおいても市内中継を目的と
する場合を含め市内交換機接続や加入者回線接続のアンバンドル化を推進し
ていくこととしている。また、こうした政策の下、現に東京通信ネットワー
クのように市内通話を含めNTTより低廉な中継サービスを提供する事業者
が登場しており、それらの事業者とNTTとの公正な競争を確保する観点か
ら、市内及び県内市外通話についても優先接続を導入すべきと考えられる。
2) 地域NTTの位置付け
市内及び県内市外通話に優先接続を導入する場合でも、地域NTTの位置
付けについては、別に検討する必要がある。
まず、地域NTT自体は優先登録対象事業者からは除外すべきという意見
がある。これは、そもそも優先接続は、ある地域網事業者が他の接続事業者
に通話を接続する際に、あらかじめ利用者が登録している接続事業者に接続
するものであり、自網に事業者識別番号を付与し、自網の利用者に対してま
で登録を求めることは、優先接続の概念の混乱をもたらすこととなるだけで
なく、地域NTTと利用者との契約内容を抜本的に変更するものであるとい
う主張である。
また、仮に、地域NTTにまで事業者識別番号を付与する必要があるとす
れば、事業者間の公平性の観点から、直収加入者回線を有する事業者には全
て事業者識別番号を付与すべしという議論につながったり、それにより利用
者利便の低下を招くという指摘がある。
これに対しては、市内及び県内市外通話にまで優先接続を導入するとすれ
ば、例えば、東京通信ネットワークを登録した利用者が通話ごとに地域NT
Tを利用する場合、優先登録を解除するための番号をダイヤルする必要が生
じるが、優先登録を解除するための番号を設けることは、実質的に地域NT
Tに事業者識別番号を付与することと同じであるとも考えられる。そうであ
ればイコールアクセスの考え方を徹底させ、事業者間の公正競争条件を確保
するため、地域NTT自身も優先登録の対象とすべきとの意見もある。
さらには、市内及び県内市外通話についてまで地域NTTを優先登録の対
象とすることのメリット、デメリットについては、当該分野における競争の
進展状況を踏まえて慎重に検討する必要があり、現状においては、必ずしも
地域NTTを直ちに登録対象とする必要性に乏しいのではないかという意見
もある。
このように、この問題については、当研究会では、現時点まで必ずしも十
分な議論がなされていないことから、利用者から見ての分かりやすさに配慮
して今後の公開意見招請の結果を踏まえ、さらに検討を深めることとする。
国際通話については、現在でも、全事業者について通話ごとに事業者識別番
号をダイヤルする方式がとられており、国内長距離と異なり既存事業者(NT
T)と新規事業者(NCC)との間の4桁という大きなダイヤル格差(注)は
ない。
(注)国際事業者の事業者識別番号
国際事業者の事業者識別番号については、その格差は必ずしも大き
くはないものの、既存事業者(KDD)と新規事業者(NCC)はそ
れぞれ3桁と4桁になっている。これは、利用者に与える影響も考慮
し、1985年の自由化以前からのKDDの番号が継続して使用され
ているため生じたものである。
また、NTTが再編成後新たに国際通信分野に進出する場合も、国際通話用
の4桁の事業者識別番号を取得し、既存の他事業者と同様に通話ごとに事業者
識別番号をダイヤルする方式でサービスの提供が可能である。
したがって、国際通話については国内の長距離通話とは異なり、NTTの再
編成を機に見直しがぜひとも必要という事情にはない。そこで、国際通話に優
先接続を導入すべきか否かについては、国内通話とは別個の検討が必要となる。
まず、国際通話に優先接続を導入する場合に必要なダイヤル手順については、
国際的な番号計画との整合性を確保する観点から、新たに国際通話であること
を示す国際プレフィックスを設定して、現行のダイヤル手順を次のダイヤル手
順に変更することが必要となる。
【優先登録した事業者を利用する場合】
国際プレフィックス+相手国国番号+相手国国内番号
【優先登録を行わない場合及び優先登録した事業者以外の事業者を
利用する場合】
事業者識別番号+国際プレフィックス+相手国国番号+相手国国内番号
優先登録した事業者を利用する場合に利用者がダイヤルする桁数は、国際プ
レフィックスが3桁程度と想定されることから、現行のダイヤル桁数から大幅
に減少することにはならない。一方、いずれの事業者にも優先登録を行わない
場合(注)や、優先登録した事業者以外の事業者を利用する場合は、事業者識
別番号からダイヤルすることが必要であり、現行の手順よりも国際プレフィッ
クスの分だけダイヤル桁数が多くなる。
(注)国際通話については、常時利用する利用者は数百万程度と考えられ、
たまにしか利用しない人、ほとんど利用しない人などで事前に優先
登録する率は国内通話よりも低下すると考えられる。
この現行よりもダイヤル桁数が多くなることを回避するため国際プレフィッ
クスを設定しない現行のダイヤル手順を併存させるとすれば、将来的に国際的
な番号計画の変更に対応することが困難となるおそれがある。
なお、現在は生じていないが、中継線接続の形態で電話サービスを提供する
第二種電気通信事業者については、事業者識別番号が6桁であるため、優先接
続を国内、国際同時に導入するメリットが大きい。また第一種電気通信事業者
についても3桁と4桁の格差を解消するため、優先接続を導入すべきという意
見がある。
次にサービスの多様化の面については、近時、国内、国際の相互参入や、事
業者の再編により国内・国際一環サービス、共通割引サービスなどが登場しつ
つあり、優先登録も国内・国際の両分野に同時に導入することにより利用者利
便の向上が図られるという考え方がある。ただし、これに対しては、特に、既
存の国際系事業者の一部からは、国内通話を主軸とする事業者が国内通話と国
際通話の「抱き合わせ登録勧奨」を行えば、国際系事業者が一方的に不利にな
るという懸念が出されているところである。
このように、国際通話については、種々の論点があり、その取扱いについて
も、当面導入を見送り問題点を慎重に検討することとする案から、原則として
国内と同時に導入することとし、国際の特殊性に応じた措置を早急に検討する
こととする案まで様々なものが考えられる。
本研究会としては、こうした点について公開意見招請において寄せられた意
見等も踏まえて、さらに検討していくこととする。
優先接続は事業者間の電気通信設備の接続に係る網機能の問題と位置付ける
ことができる。接続ルールの原則は、第一種電気通信事業者(本件の場合は地
域網事業者:地域NTT)は他の電気通信事業者(本件の場合は接続事業者)
から接続を求められた場合は基本的に接続に応じる義務がある(一定の合理的
理由があれば拒否することも可能。)というものであり、接続を求めるか否か
は当該電気通信事業者の任意である。したがって、優先登録への参加の取扱い
についても、アダプタ等による代替手段もあり、必ずしも全ての接続事業者に
優先接続への登録を義務づける必要性は乏しく、各接続事業者が利用者に自社
を登録してもらうかどうかは、それぞれの経営判断に委ねることが適当と考え
られる。
なお、優先接続を含む網機能については、一定の機能についてはネットワー
クが本来備えるべき地域網の「基本機能」と位置付けられる場合があり、その
場合は当該網を保有する事業者を含む全接続事業者がその機能のためのコスト
を共同して負担するものとされている。したがって、優先接続を基本機能とす
る場合は網改造費用については優先登録に参加しない接続事業者に対しても負
担を求めることになるが、この点については後の費用負担の項で検討する。
優先接続の対象とすべき通話サービスは、原則として、通話サービスを利用
する際に「00XY」の事業者識別番号(資料編2参照:基本接続用のものに限
り、付加サービス用のものを除く。)をダイヤルする基本通話サービス(IS
DNを含む。)のみと考えられる。ただし、特殊番号に関連する多様な付加的
サービス等の一部については、対象とすべきと考えられるものもあり、対象範
囲を明確化することが必要である。
具体的には、「1XY」の番号の内の「184」、「177」、「136+
3」や「*XX」(短縮ダイヤル)の番号、「ボイスワープ」(転送電話)等
については、優先接続の対象とする方向で、今後関係事業者間で費用負担の問
題を含めて協議し、決定すべきものと考えられる。
なお、公衆電話については、利用者が不特定なため優先接続の対象とはなら
ないが、NTT再編に伴う地域NTTと長距離NTTの接続における事業者識
別番号の取扱い及び他の事業者の接続要望との関連で、別に検討が必要である。
1) 現在の電話サービスに係る契約関係
電話サービスの利用に係る利用者と通信事業者との契約は、利用者宅まで
の加入者回線を設置してサービスを提供する地域網事業者の場合は、利用者
との間で個別に利用(加入)契約を締結する個別契約の形態をとっている。
なお、電話サービスの場合は事業者が郵政大臣の認可を受けて定める契約
約款及び料金表に基づく付合契約であり、利用者が申込みを行い事業者が承
諾することで契約が成立する。
一方、接続事業者の場合は、利用者と地域網事業者との契約関係を前提に、
利用者との間で利用契約を締結する。また、電話の利用契約は、基本的な
サービス内容と基本的な料金を提供条件とする通常の利用契約に加え、利用
者の選択に従い多様な付加サービスや割引サービス等に係る付加的契約が締
結されることも多い。接続事業者の利用契約については、現在、長距離系N
CCは個別契約の形態をとっているが、国際系事業者の場合はいわゆる「み
なし契約」(注)と呼ばれる契約形態をとっている。
(注)みなし契約
みなし契約は、具体的には、NTTの加入電話サービスの契約約款
と国際系事業者の国際電話サービスの利用契約約款の双方の規定に基
づき、NTTと契約した契約者は、別の意思表示をする場合を除き、
同時に、国際系事業者の契約者となる、と構成する契約形態である。
これはNTTの契約者が、個別の契約手続きを要せずに国際電話を利
用できるようにするための仕組みであり、1985年の電気通信制度
改革以前は公衆電気通信法に基づいていた利用方法を継続させるため、
関係事業者の契約約款において取り入れられたものである。個別契約
の形態をとるかみなし契約の形態をとるかは、接続事業者の営業方針
等と関連するものであり、地域網事業者との協議を通じて実施するこ
とができる。
2) 優先登録の契約関係
優先接続を導入する場合、利用者の意思は事業者を選択する優先登録の申
込みにより示されるが、この意思表示を上述のようなサービス利用契約との
関係でどう位置付けるかという問題がある。
優先登録をサービス利用契約を締結するための個別の申込みと事業者識別
番号の自動発信機能の提供の申込みとが一体となったものと位置付ける方法
と、サービスの利用については別にこれまでと同様な利用契約を締結するも
のとし、優先登録はあくまで事業者識別番号の自動発信機能の提供の申込み
と位置付ける方法とが考えられる。
現在の長距離通話の利用者の中には、NTT及び複数の長距離系NCCと
重複して契約している利用者も少なくなく、通話のつど事業者を選択してい
る利用者もあり、それは国際電話についても同様である。優先登録に利用契
約締結の効力を持たせる方法では、優先接続導入時の初期登録が現在の利用
契約締結関係をご破算にするものとなるが、その公平かつ適正な実施方法を
見いだすことが非常に困難な課題となる。また、優先登録への参加を各事業
者の任意とした場合、ある利用者について優先登録非参加事業者との利用契
約と他事業者への優先登録とが競合した場合の契約の優先順位の問題等が生
じる。
競争導入から間をおかず優先接続を導入した外国の例と異なり、我が国で
は、長距離系NCCが電話サービスを開業した1987年以降10年に及ぶ
利用・契約の実態がある。したがって、上述のような問題を回避し、優先接
続制度を円滑に導入するためには、サービスの利用については別にこれまで
と同様な利用契約を締結するものとし、優先登録はあくまで事業者識別番号
の自動発信機能の提供の申込みと位置付ける方法をとることが適当と考えら
れる。
3) 通話ごと選択の契約関係(アダプタ等を利用する場合を含む。)
通話ごと選択による通話は、利用者と当該事業者との間の個別契約又はみ
なし契約に基づき利用可能とすることで、契約面での対応が可能と考えられ
る。個別契約とするかみなし契約とするか(あるいは両方の契約形態を設け
るか)は、各事業者の判断に委ねることが適当と考えられる。
優先登録の勧奨の方法としては、一斉投票方式と随時営業方式とが考えられ
る。一斉投票方式は、米国やオーストラリア、韓国の一部分でとられた方式で
あり、事前の制度周知の後、優先登録申込書を全利用者に郵送し、申込書に記
入の上利用者に優先登録の受付窓口あて返送を求める方式である。随時営業方
式は、カナダやドイツでとられ、EUにおける検討経過でも支持された方式で
あり、優先接続実施日以降、順次各事業者が営業活動を行う中で自社を指定す
る優先登録の勧奨を行う方式である。
我が国においては競争導入後10年に及ぶ競争と利用の実態があり、地域N
TTが実施主体となると想定される一斉投票方式よりも、各競争事業者がそれ
ぞれの顧客との契約関係や営業体制を通じて優先登録の勧奨を行う随時営業方
式の方が、公正競争上の問題が少ないと考えられる。また、一斉投票方式では、
マスコミを通じた広告等が有効であり、大規模な事業者が有利になると考えら
れる。また、一斉投票方式は、完全といえる事前周知は不可能であることもあ
り、無投票者の取扱いが大きな問題となる(参考1、2)。
したがって、随時営業方式とすることが適当と考えられる。
(参考1)最近の国政選挙の投票率
|
前 回
|
前々回
|
衆議院議員選挙
|
小選挙区 59.65 %
|
選挙区 67.26 %
|
比例区 59.62 %
|
−
|
(H8.10.20)
|
(H5.7.18)
|
参議院議員選挙
|
選挙区 44.52 %
|
選挙区 50.72 %
|
比例区 44.50 %
|
比例区 50.70 %
|
(H7.7.23)
|
(H4.7.26)
|
(参考2)一斉投票方式実施国における無投票者の取扱い
米国においては、第1回投票時の無投票者については、第1回の投
票による得票割合で関係事業者に利用者の優先登録を配分し、その事
業者名を通知した上で第2回目の投票の機会を設けている。オースト
ラリアにおいては、無投票者は従来の独占事業者を選択したものとし
て取り扱っている。韓国においては、新規参入した第二キャリアの利
用実績が多かった全利用者数の約1/8について一斉投票を実施して
おり、無投票者は第二キャリアを選択したものとし、その他の投票用
紙を送付しなかった利用者についてはコールセンターへの個別の申込
みがない限り第一キャリアを選択したものとして取り扱っている。
また、いずれの国も、その後は随時営業方式により変更登録を実施
している。
優先登録勧奨方法を随時営業方式とする場合には、事前周知の上で優先接続
実施時に、特定事業者を選択したものとして取り扱う初期登録が必要となる。
この初期登録は、事後的に意思表示があれば変更され、意思表示なき場合は
初期登録のまま継続されるものである。
幸い、我が国においてはNTTと接続事業者とが重複した契約を結んでおり、
現状、NTTのサービスを利用する場合は事業者識別番号が不要であり、他の
接続事業者のサービスを利用する場合は当該事業者の事業者識別番号をダイヤ
ルするか当該事業者のアダプタ等を設置することで通話サービスが利用可能な
状況にあり、この状態を継続する形で初期登録を行うことができる。つまり、
国内通話については原則として、市内及び県内市外については、地域NTTを
優先登録の対象とする場合は、地域NTTを選択したものとし、地域NTTを
対象としない場合は、地域NTT以外の事業者のいずれも選択しないものとし
て取り扱うとともに、県間市外については長距離NTTを選択したものとして
取り扱う。そうすること、すなわちデフォルト(注)としてNTTを初期登録
することで優先接続の円滑な導入が可能となると考えられる。しかしながら、
NTTをデフォルトとすることによって公正競争上問題が生じないかをチェッ
クする必要はある。
(注) デフォルト
デフォルトとは、本来の不履行や棄権の意味から、コンピュータの
用語に転じて、ソフトウェアの利用開始時点であらかじめ決められた
標準的な値や設定が自動的にセットされる初期設定のこと。ユーザー
が実際に利用する際に、別の設定に変更することが可能である。
一方、国際通話については、優先接続を導入する場合に新たに設定する必要
がある共通の国際プレフィックスの在り方によって、現在のダイヤル方法の変
更が生じうる。優先接続実施日以降、現行ダイヤル方法が使えなくなる場合は、
何らかの方法による初期登録を行う必要があるが、これについては国際プレ
フィックスの在り方の検討を待って、別途検討する必要がある。
なお、先に(10)で述べた随時営業方式を変形し、優先接続実施日の前に一定
期間の事前勧奨期間を設け、その間に意思表示があった利用者については、そ
の意向に従い初期登録を行う方式も考えられる。
また、一定の事前勧奨期間を設け十分な事前周知を行って利用者に意思表示
を求めた上で、意思表示のない利用者については、いずれかの事業者識別番号
をダイヤルしなければ通話できないものとする考え方もある。そうすることで
利用者の自己責任に基づく選択を促すことが利用者利益の向上につながり、か
つ真に競争が促進されるという考え方である。しかし、この方法については、
完全といえる事前周知は不可能であることもあり、優先接続実施時に大きな社
会的トラブルが生じると考えられる。この点については、公正な競争を促進す
ることによって得られる便益の比較の問題でもあると考えられ、多方面からの
ご意見を待ちたい。
また、現在長距離系NCC等のアダプタ等を利用する利用者については、初
期登録において当該事業者を選択したものとして取り扱うことも考えられる。
しかし、現在でも、利用者によるアダプタ等の利用の停止状況やアダプタ等の
利用契約の解除が関係事業者において十分正確に把握できているとはいえない。
また、アダプタ等を利用する利用者でも、通話のつど事業者を使い分ける利用
者も想定され、一概にアダプタ等を設置する事業者を選択したものとして取り
扱うことには問題が残る。また、優先登録により現行の電話利用の方法を変更
するからには、改めて表示される利用者の明確な意思に基づくことが望ましい
と考えられる。このため、この方法をとることは適当ではないと考えられる。
1) 優先接続機能の意義
優先接続の機能は、一度地域NTTの市内交換機に附属するデータベース
に加入者回線ごとに指定接続事業者を登録するだけで、その後通話のつど市
内交換機において自動的に当該事業者の識別番号が発信されることをいう。
その結果、利用者が当該事業者の識別番号をダイヤルしなくても当該事業者
の網に接続されるものである。この優先接続に係るシステムは地域NTTの
市内交換機及び附属する優先登録データベースであり、地域NTTが管理運
営するものである。
2) 優先接続機能の提供主体
この優先接続機能は地域NTTの地域網の機能であり、この機能の提供主
体は一義的には地域NTTであると考えられるが(資料編6参照)、地域N
TTの接続約款に基づき接続事業者が仕入れて利用者に提供する機能と考え
ることもできる。
地域NTTが提供する場合でも、接続事業者が利用者に対する営業活動を
行う際には、自社の電話利用契約を獲得するとともに自社を指定する優先登
録を獲得することが当然のことであり、利用者の直接申込みに加え、接続事
業者による申込代行を認め、接続事業者間の競争が働きやすい仕組みとする
ことが利用者の利便でもあると考えられる。
一方、優先接続機能を接続事業者による継続的なサービス提供と位置付け
ることについては、利用者が電話利用契約や優先登録の事業者を変更する場
合に契約解除通知を行うことを期待することはできず(月額の基本料金等が
ない場合は利用者としては放置しても支障がない。)、事実上接続事業者に
は優先登録契約の管理は不可能であるという無理がある(地域NTTが管理
することが合理的。)。また、接続事業者のみが提供することについては、
優先登録区分が2〜4区分となり、特に加入電話の新規加入時にワンストッ
プショッピングができず利用者に不便をかけるなどの問題がある。
したがって、地域NTTが提供するものとし、優先登録参加事業者の代行
を認めることが適当と考えられる。
1) コスト負担の考え方
優先接続の導入に当たっては、以下に述べるような金銭的なコスト負担が
生じる(注)。その費用については、事業者又は利用者が負担することにな
るが、事業者が負担するものについても、利用者料金に転嫁されることもあ
り得る。また、優先登録のための手数や一部のダイヤル方法の変更など、利
用者にとって直接の金銭の支払いに換算しがたいコスト負担も生じる。いず
れにしても、優先接続の導入により利用者がコストを負担することとなるが、
これらのコストの負担は、優先接続の導入や関連するNTT再編成が目的と
する長期的な公正競争の促進を通じた料金の低廉化、サービスの多様化等の
利益に対応するものとも考えられるので、優先接続の導入においてはこうし
た点について利用者の理解を十分得た上で行う必要がある。
また、以下の3)〜5)に述べる事業者側の費用負担の在り方は、どういう方
法をとれば関係事業者にとって公平といえるか、公正な競争を促進すること
になるか、という問題であり慎重な検討が必要である。
(注) NTTによるコスト試算
今回、NTTに依頼し報告を受けたコスト試算の結果は次のとお
りである。
今後、費用の額や負担方法について詳細な検討が必要なものであ
るが、一つの負担方法の例として述べれば、aの網改造費用は、年
経費化(投資額の約1/3)の上関係事業者が応分に負担すること
が考えられる。また、b及びcは一時期に必要な費用であり関係事
業者が応分に負担することが考えられる。
項目
|
コスト試算
|
内容・説明
|
a 網改造費用
(市内交換機に優先接続機
能を付加するための費用)
|
約 110億円
|
・ソフトウエア開発投資
・優先登録全4区分への導入を前
提 (区分が減少しても額に大き
な変動 はない)
|
b 周知費用
(利用者に対する事前周知
費用)
|
約 70億円
|
・全利用者に2回周知
・広報誌(請求書同封)への掲載
(3回)
・マスコミ広告
|
c 初期の登録申込みの集中
入力費用
|
約 100億円
|
・全国1ヵ所の投入データ一括処
理システムの開発・運用
・全国11ヵ所の投入センタの設
置・運用
|
d 変更登録費用
(事後の利用者の希望によ
る変更登録のための費用)
|
実 費/件
|
・登録先変更を市内交換機データ
ベースに入力(現行局内工事料
を準用)
|
・cは、本文(11)にいう「初期登録」ではなく、実施日以降集中的に
発生すると予想される接続事業者による変更登録代行申込を迅速に
処理するための費用である。
・b、cは平成10年2月の発信電話番号表示サービス導入のケース
を参考としている。
・dは優先接続の導入に伴う営業窓口等における制度周知等の顧客対
応の変更等の費用は含んでいない。
・現時点で一定の前提の下で試算されたものであり、優先接続導入
方法の具体化に応じ変更の可能性があるものである。
2) 網改造費の負担方法
事業者間の相互接続における網改造費用の負担方法には、その機能の性格
により、地域網事業者及び全接続事業者が共通に利用する機能(基本機能)
である場合には市内交換機等の接続料に含め費用回収する方法と、個別の事
業者の要望を受けて特別な機能を提供する場合には関係接続事業者が個別に
負担する方法と、大きく2つの考え方がある。具体的には個別の網改造ごと
に判断することとされているが、この2つの方法の中間に解を求める場合も
考え得るものである。
市内〜国際までの全通話区分に優先接続を導入する場合で、かつ地域NT
Tを優先接続の対象とする場合には、基本機能とすることが適当と考えられ
るが、市内交換機の接続料に含める場合には優先登録に参加しない事業者や
優先接続と無関係な携帯電話事業者にまで負担を求めることとなり、負担方
法の修正を検討する必要がある。
また、地域NTTや国際系事業者が優先登録の対象とならない場合は、優
先登録参加事業者による応分の負担をベースとして別の負担方法についても
検討する必要がある。
地域NTTの費用負担については、地域NTTが優先登録の対象とはなら
ない場合でも、地域NTTが取り扱う通話を疎通させるためにも優先登録
データベースを利用すること、他事業者を優先登録する利用者が通話ごと選
択の方法で地域NTTを利用するためには優先登録を解除するための番号を
ダイヤルすることが必要であるが、優先登録を解除するための番号を処理す
るために網改造が必要となることなどから、応分のコストを負担するべきで
あるとの意見もある。
なお、網改造費用は年経費化の上、関係事業者が関係の回線数や通話回数
等に応じ負担することが考えられるが、優先登録に伴う登録先事業者の費用
負担とアダプタ等によるサービス利用との不対応が生じないように、網の優
先接続機能の稼動を反映する稼動通話回数等をベースとすることについても、
そのためのコスト増も考慮しながら検討すべきと考えられる。
3) 初期登録費の負担方法
デフォルトとして初期登録を行う場合には、利用者の意思の確認がないこ
とから利用者に負担を求めることは適当ではなく、登録先事業者が負担する
ことが考えられる。事前登録勧奨期間を設けその結果初期登録を行う場合に
は、利用者負担又は登録先事業者負担とすることが考えられる。
また、NTTのみをデフォルトとして初期登録する場合は網改造と同時に
設定が可能であり、事前登録勧奨による接続事業者代行申込の場合には、磁
気媒体による大量入力が可能である。このようなことから登録方式に応じた
実費ベースの費用負担とすることが考えられる。
4) 変更登録費の負担方法
変更登録は利用者の希望に基づき行うものであるから一義的には利用者が
負担することが考えられる。
また、デフォルトとして初期登録を行う場合には、初期登録が利用者の意
思によるものでないため、その後の変更登録は初めての利用者の意思表示で
あるばかりでなく、場合によっては意に沿わない初期登録を正常に復させる
ものともなる。したがって、デフォルトとして初期登録を行う場合の一定期
間内の1回目の変更登録については、利用者負担をなしとするか低料金とす
ることが考えられ、その際はその実費を関係事業者のコスト負担の全体にお
いて回収する方法を検討すべきと考えられる。
また、負担額については代行申込みの場合には先の初期登録と同様、方式
と量に基づき実費ベースの料金設定を行うことが考えられる。
1) 優先接続の導入に伴う公正競争の確保
優先接続は、大きく見れば、競争事業者間でダイヤル桁数(覚えやすいと
いう質の面を含めて)を同等にするという公正競争条件の問題であるととも
に、できるだけダイヤル桁数を少なくするという利用者の利便の維持・向上
の問題である。優先接続の導入は、電話サービスの利用方法や、電話サービ
スの利用に関連する契約関係に影響を与えることから、通信事業者の営業戦
略や市場競争の構造にも大きな影響を与えるものである。
このため、優先接続の具体的実施方法については様々な局面で、公正競争
上の問題が生じるものであり、関係事業者間の協議を踏まえ、長期的な利用
者利益の向上を基本的視点として、意見調整を行う必要がある。
2) 地域NTTによる優先登録の実施
上述のように優先登録は地域NTTが実施することになるが、地域NTT
は自らも他の接続事業者と競争しつつ市内及び県内市外通話サービスを提供
する立場にある。また、長距離NTTの県間市外通話サービス等の販売業務
を受託することも予定されている。優先登録実施者である地域NTTと他事
業者との間の公正競争を確保するため、地域NTTの優先登録実施部門にお
いては優先登録関連情報を適正に管理し、必要な情報の授受については自社
の営業部門等を他の優先登録参加事業者と同等に取り扱うなどの措置を講じ
る必要がある。
3) 地域NTTによる新規加入者に対する優先登録勧奨
優先接続導入後は、優先登録を申し込むか事業者識別番号をダイヤルしな
ければ、優先接続を導入する通話区分(例えば県間市外通話)が不通になる
ことから、新規電話加入申込みの際に、そのことの情報提供を含め、最大4
区分となる優先登録の申込みの勧奨を行いワンストップショッピングを確保
することが望ましい。これは他の事業者には困難であり地域NTTのみが実
施しうる立場にある。
この場合、市内及び県内市外通話については他の優先登録事業者と自社と
が直接競合し、県間市外や国際通話はグループ会社である長距離NTTが競
合する。このため、地域NTT窓口での具体的説明、勧奨方法や地域NTT
の勧奨実績に対する評価を含めた費用負担の問題等、関係事業者間で十分な
協議が必要である。
1) 優先接続の導入と利用者への情報提供、情報開示
優先接続の導入の目的は、通話サービスを利用する際にダイヤル桁数の不
便を感じることなく、利用者にとって通信事業者の選択の自由度を増すこと
にあるということもできる。利用者利便の向上の観点からは、優先接続の具
体的実施方法とともに選択の対象となる通信事業者のサービスに関連する情
報が利用者の要求に応じ容易に提供されるようにすることが重要な課題であ
る。
2) 優先接続の導入に伴う具体的情報提供
以下のような情報提供、情報開示が必要と考えられる。
○ 各優先登録参加事業者による情報提供
・優先接続の導入に関する事前周知
・問合わせ窓口の設置及び周知
・自社の料金、サービス内容の説明、情報開示
・不当な情報提供の禁止
○ 登録実施者としての地域NTTによる情報提供
・ 優先接続の導入に関する事前、及び導入後一定期間内の制度周知、
情報開示
・ 新規加入契約者に対する周知
・ 優先登録参加事業者の問合わせ窓口の周知
○ 中立的機関による情報提供
登録実施者としての地域NTTの窓口か、中立的機関において、優
先登録全参加事業者の会社概要、サービス内容等の基本的情報の問合
わせに応え得る体制を整備することが望ましい。
・ 優先登録参加事業者に関する情報提供
・ 優先登録参加事業者の問合わせ窓口の周知
・ 各事業者の料金、サービス内容の情報提供
(インターネットHP等を利用し、データベースを整備して利用
者等からの情報検索を可能とすることが望ましい。)
1) 米国における不正優先登録問題(スラミング)
米国では1984年のAT&T分割を機に優先接続が導入されたが、その
後10年以上を経た現在でも、「スラミング」と呼ばれる、利用者の同意を
得ずに優先登録先事業者を変更する不正優先登録が大きな問題となっている。
このスラミングを防止するため、連邦通信委員会(FCC)が規則を制定
し制裁金制度が設けられているが、1997年度でもFCCに対し2万件以
上の苦情が寄せられている。
2) 不適正な営業活動の防止
米国の優先登録手続きにおいては利用者からの書面によらない申込みが許
容されており、優先登録事業者からの電話勧誘だけで処理される点がスラミ
ングの大きな原因と伝えられている。利用者から地域NTTに対する直接申
込みの場合は電話等による申込みも可能とすべきと考えられるが、優先登録
参加事業者やその代理店等を経由する代行申込みの場合は利用者からの書面
による申込みに限定することも検討すべきと考えられる。また、事後的な確
認を容易にするため申込書には取扱事業者名、取扱担当者名等を記入を要す
ることとすることや事後の確認・訂正手続き等についても、関係事業者間で
十分な検討が必要である。
3) 利用者からの苦情への対応等
不適正な営業活動の結果利用者の意思に基づかない登録が行われた場合、
利用者は地域NTTからの優先登録実施通知により、その事実を確認するこ
とができる。不適正な営業活動を行った登録先事業者に苦情が寄せられた場
合には当該事業者で適切な対応を行うべきことはもちろんであるが、地域N
TTへも苦情が寄せられることが想定される。その場合、利用者と新旧登録
先事業者と地域NTTとの4者間の連絡・協議が必要となり、その標準処理
方法、費用負担等について関係事業者による十分な協議が必要である。
4) 郵政省に対する意見申出制度の整備・活用
郵政省では、1997年7月に電気通信局に電気通信利用環境整備室を設
け、電気通信サービスに関連する利用者からの苦情・相談等の受付・対応を
行うとともに、利用者等に対する情報提供等を行ってきている。
また、1998年の通常国会において、第一種電気通信事業者の電気通信
料金の原則届出制の導入に併せて、意見申出制度(注)が法定されたところ
であり、今後この制度の活用が望まれる。
(注)意見申出制度(電気通信事業法関連条文)
第96条の2 電気通信事業者の電気通信役務に関する料金その他
の提供条件又は電気通信事業者の業務の方法に関し苦情その他の
意見のある者は、郵政大臣に対し、理由を記載した文書を提出し
て意見の申出をすることができる。
2 郵政大臣は、前項の申出があったときは、これを誠実に処理し、
処理の結果を申出者に通知しなければならない。
5) アダプタ等
上述のとおり、優先接続後もアダプタ等の併存を許容すべきと考えられる
が、現在のアダプタ等に関連し適正営業の面で以下のような課題がある。
これまで周知されてきた「LCR」の最低料金事業者選択機能に限界が生
じ、最近「ACR」と改称されたことは既述のとおりであるが、新旧アダプ
タ等を設置する利用者に対し、その取扱い方法や機能の限界等について十分
な情報提供、説明が必要である。また、災害時等の機能解除方法の在り方に
ついて、関係事業者間で協議し統一した分かりやすいものとすることが望ま
れる。
また、外付けアダプタについては、契約解除(アダプタ取り外し)時の違
約金の問題がある。通信事業者がアダプタの開発・調達・設置コストを回収
するために最低利用期間内(通常1年間)の契約解除時に違約金を請求しう
るとすることはそれ自体は是認されると考えられる。そして、通常は期間内
に解除する場合でも違約金の請求は行われていない。しかし、特定の事業者
との競争において違約金請求権が競争制限的に利用されることや、利用者に
とって差別的取扱いを被る恐れが否定できない。この点や取り外し工事料の
負担方法、取り外したアダプタの返送の問題等を含め、透明で公正な競争
ルールが確立されるよう望まれるところである。
6) 優先接続導入後の販売競争の展開
これまでの長距離通話サービスを巡る事業者間競争では、顧客宅内へのア
ダプタ等の設置が重要なポイントとなっていたが、優先接続導入後は、より
手軽な優先登録申込書獲得が重要なポイントとなると考えられる。また、事
業者変更が容易なことから、頻繁な変更登録の勧誘合戦が展開されることも
考えられる。また逆に、優先登録による電話利用を長期的に囲い込むための
割引サービス等も工夫されていくものと考えられる。
この点にも関連し、一部の事業者から次のような意見が出されている。す
なわち、上記の5)のアダプタ等の違約金等の問題が解決されない場合、アダ
プタ等の利用契約の解除が困難であり利用者は希望しても優先登録ができな
い事態が生じる。このため、利用者の選択肢の一つとして、固定優先接続方
式も併せて提供できるようにすべきである、というものである。また、この
固定優先接続方式については、アダプタ等を先行的に提供している事業者と
そうでない事業者とが対等に競争できるようにするために必要であり、優先
接続の導入と同時期に提供できるようにすべきであるという意見もある。
これについては、優先接続の導入によって利用者の利便や公正競争が確保
されるようにするという観点から、固定優先接続方式が利用者に具体的にど
のようなメリットをもたらすかや、長距離NTTをデフォルトとして初期登
録することとの関係をどう考えるか、長距離NTTを含む中継サービス事業
の競争環境にどのような影響を及ぼすことになるかなどを含め、公開意見招
請において寄せられる意見等を踏まえ、さらに検討していくこととする。
なお、いずれにしても、優先登録獲得のための景品営業等が加熱し、かえ
って営業コストが増大するようなことは本来望ましいものではなく、公正で
妥当な販売競争が展開されることが望まれる。
利用者利益の維持・向上、公正競争の確保の観点から十分な検討・準備を行
った上で、NTT再編後、できるだけ早期に導入すべきと考えられる。
なお、NTTでは、交換機の改造のためのシステム開発には具体的仕様の確
定後少なくとも18か月必要としている。
(18) NTT再編から優先接続導入までの間の経過措置
|
NTT再編時から優先接続導入までの間、長距離NTTの長距離通話サービ
ス利用については、形式的に公正競争条件の確保にはもとるが、サービス利用
の円滑な継続を重視し利用者の利便保護の観点から、現行ダイヤル方式を維持
することが適当と考えられる。