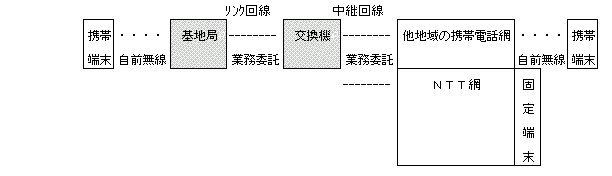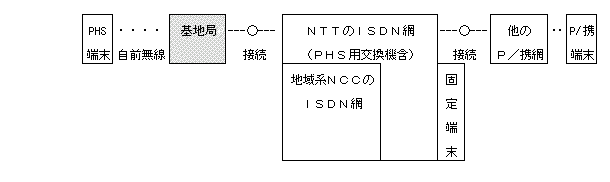1) 携帯電話網の取扱い
携帯電話サービスの総加入数は平成9年度末で31,527千加入に達し
ており、NTTの固定電話に次ぐ第二の地域網に発展してきている。そこで、
NTTの地域網に優先接続を導入することについて検討する場合には、携帯
電話網に導入することについても検討する必要がある。
携帯電話網の構成は、一般に、基地局と交換機とを自前で設置し、自社の
基地局と交換機との間の回線(リンク回線)も、交換機と隣接地域のグルー
プ系携帯電話網の交換機との間の回線(中継回線)も、ともに他の地域系又
は長距離系事業者に業務委託(中継回線につき、NTTドコモは自前設設置、
また一部事業者では関係のある長距離系NCC網と接続したり、設備共用し
ている例もある。)する形態をとっている。これは、携帯電話系NCCの新
規参入の段階で携帯電話事業者にとり中継回線を自前設置することが困難な
ため、他事業者に中継伝送業務の業務委託が認められたことや、携帯電話事
業者のグループ関係等が関係している。
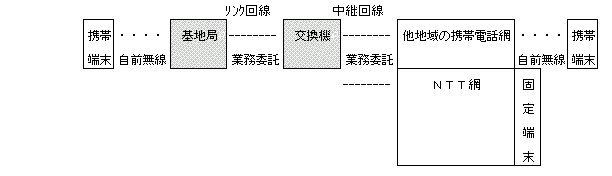
また、料金設定(利用者との契約)の面では、上述のいずれの場合も、携
帯←→携帯は発信側携帯電話事業者、携帯→固定と固定→携帯はともに携帯
電話事業者が行っている。つまり、中継回線部分を特定の長距離系NCCと
接続している場合を含め、発着いずれかの立場に立つ携帯電話事業者がエン
ド・エンドで料金設定をしており、携帯電話サービスの利用者が複数の接続
事業者(接続事業者の提示する料金)の中から1社を選択する仕組みになっ
ていない。これは、上述のような網構成の特殊性のほか以下のようなことか
ら、これまでそのような競争状態が生じていないものである。
○ 携帯電話サービスの事業展開の中心が端末加入数の拡大にあったこと
○ 長距離系NCCが既成の地域網であるNTT加入電話網との接続によ
る長距離電話サービスに力を注いできたこと(携帯電話加入数が百万を
超えたのは平成3年度、1千万を超えたのは平成7年度。)
○ 中継回線を設置して事業展開を行う地域系事業者や長距離系NCCは、
資本関係等から特定の携帯電話事業者に業務委託等の形態で中継回線を
提供することで一定の利益を上げていたこと など
したがって、現状では事業者選択の余地がなく、優先接続を導入する必要
はない。今後、NTT固定電話網と同様の形態で、携帯電話の地域網に他の
接続事業者が接続しサービスを提供することは考えられることではある。し
かし、それを制度的に強制することはできず、実際に複数の長距離系事業者
等が携帯電話事業者網に接続し、複数の長距離系事業者等が料金設定を行い
利用者に自社のサービス利用を勧奨する状況が生じた段階で、関係事業者の
要望を踏まえて優先接続の導入について検討することが適当と考えられる
(補足)。
(補足)諸外国においても携帯電話網に優先接続を導入している例はな
い。また、諸外国とも固定地域網分野における競争はあまり進展
しておらず、優先接続機能を提供する地域網事業者は既成の旧独
占事業体(固定網)に限られている。ただし、米国においては、
AT&T分割以前から独立系地域電話会社が存在しており、独立
系地域電話会社においても優先接続機能が提供されている。
2) PHS網の取扱い
PHSサービスの総加入数は平成9年度末で6,727千加入となってお
り携帯電話サービスと合わせると38,254千加入に達している。
PHS網の構成は、基地局以降は全て関連地域系NCCのISDN網又は
(及び)NTTのISDN網に接続しており、それらを介し他のPHS・携
帯電話網やNTT固定電話網と接続している。
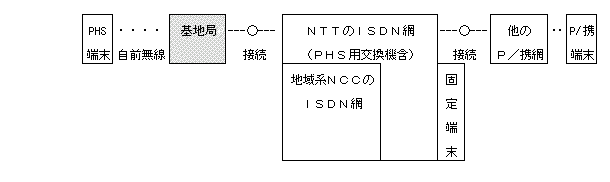
また、網の構成は異なるが、中継線部分の接続が複数化していないことや
料金設定については、携帯電話網と同様である。
したがって、優先接続の導入については、携帯電話網と同様に、複数の長
距離系事業者等がPHS事業者に接続を依頼し、複数の長距離系事業者等が
料金設定を行い利用者に自社のサービス利用を勧奨する状況が生じた段階で、
検討することが適当と考えられる。
3) 携帯電話及びPHS発信の国際通話の取扱い
携帯電話及びPHSに発着する国内通話については、上記1)及び2)のとお
りであるが、国際通話については事情が異なっている。現在国際電話サービ
スを提供している国際系事業者3社はいずれも、国際系事業者側から携帯電
話及びPHS事業者に対し国内網部分の伝送業務を業務委託する形態をとり、
国際系事業者側でエンド・エンドの料金設定を行っている(外国から我が国
へ着信する場合は外国事業者が料金設定。)。
通話種別
|
ダイヤル方法
|
携帯等←→携帯等
|
0A0−CD+12345
網識別番号−事業者識別番号−加入者番号
|
携帯等→NTT
|
06−234−5678
市外局番−市内局番−加入者番号
|
NTT→携帯等
|
0A0−CD+12345
網識別番号−事業者識別番号−加入者番号
|
携帯等→外国
|
00XY+44−234−5678
 ̄ ̄ ̄ ̄
事業者識別番号+相手国国番号−相手国国内番号
|
それでも、業務委託と接続との違いはあるが、携帯電話及びPHS利用者
が複数の国際系事業者のサービスを選択できる点で、優先接続を導入するこ
とを検討する余地がある。仮に、地域NTTの固定電話網に接続する国際通
話について優先接続を導入する場合には、できれば携帯電話及びPHSから
国際通話をかける場合にも固定電話発信と同様のダイヤル方法とすることが
望ましい。
しかし、上述のように携帯電話及びPHSに関し相対的に大きなウェイト
を占める国内通話には当面優先接続を導入する余地がなく、国際通話につい
てのみ優先接続を導入する場合は費用負担方法が大きな問題となると考えら
れる。したがって、この問題については、上記4の(5)の地域NTT網におけ
る国際通話に優先接続を導入するか否かの結論を待って、コスト試算を含め
関係事業者の意見を踏まえながら別に検討する必要がある。
4) NTT以外の地域固定電話網の取扱い
地域系NCCの直収電話網やISDN網、CATV電話網及び長距離系N
CCの直収回線網が、地域固定電話網に該当する。これらの網は現在、社毎
に見れば3万加入以下であり、優先接続機能を具備するためのコスト負担が
大きいものとなる。
いずれにしても、上述の携帯電話網の場合と同様に、複数の長距離系事業
者等がこれらの網に接続し料金設定を行い利用者に自社のサービス利用を勧
奨する状況が生じた段階で、関係事業者の要望を踏まえて検討することが適
当と考えられる。
1) NTTにおける実施計画の早期作成と関係事業者間協議
優先接続は、地域NTTと接続事業者との間の電気通信設備の接続に関す
る「当事者が取得し、若しくは負担すべき金額又は接続の条件その他の細
目」に該当する事項であり、関係事業者間の協議に基づき、NTTにおいて
その実施計画が具体化されることが期待される。したがって、NTTにおい
ては、本研究会の検討状況をも踏まえつつ早期に優先接続の実施計画案を作
成し、関係事業者等に開示した上関係事業者間で協議を進めることが望まれ
る。
2) 利用者からの意見の反映
電話サービスは国民生活に不可欠な情報通信手段であり、優先接続の在り
方は、利用者の日々の電話の利用方法や利用契約の在り方に大きな影響を及
ぼすものである。そのため、優先接続の具体的実施方法を検討するに当たっ
ては広汎な利用者からの意見や消費者団体等からの意見を十分に参考とすべ
きである。