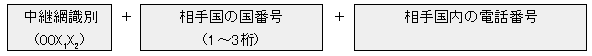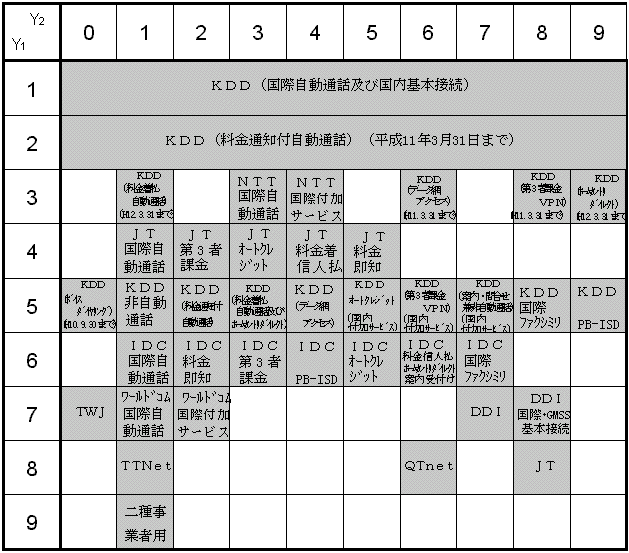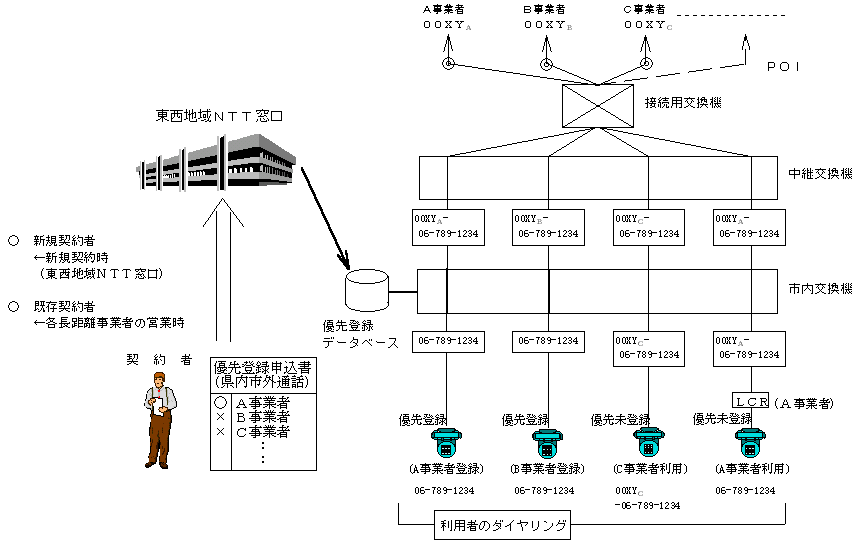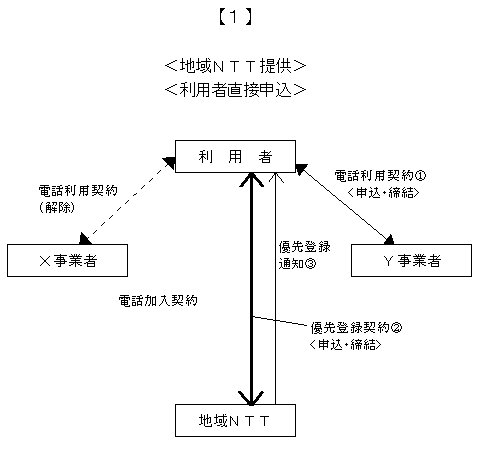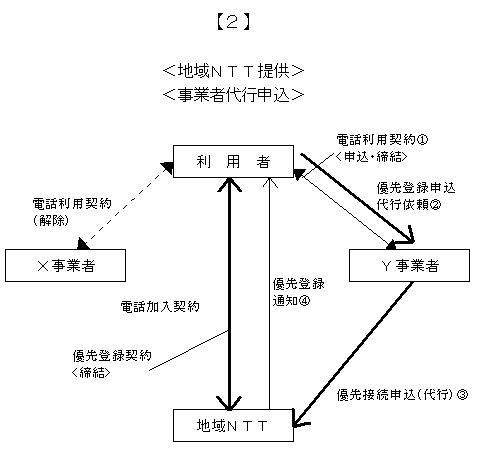優先接続に関する研究会中間報告書
資料編
1 接続のネットワーク構成
2 事業者識別番号の現状
3 優先接続のイメージ
4 海外における優先接続の導入状況
5 接続の推進(接続ルールの概要)
6 優先接続の事務フロー
7 「優先接続に関する研究会」委員名簿
戻る
1 接続のネットワークの構成
(1) 国内長距離電話の場合<現在>
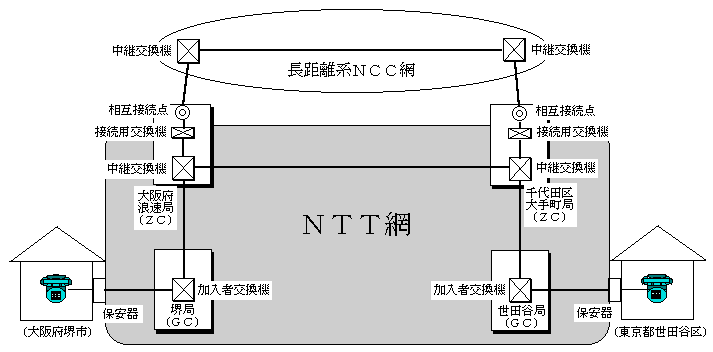 (2) 国際電話の場合
(2) 国際電話の場合
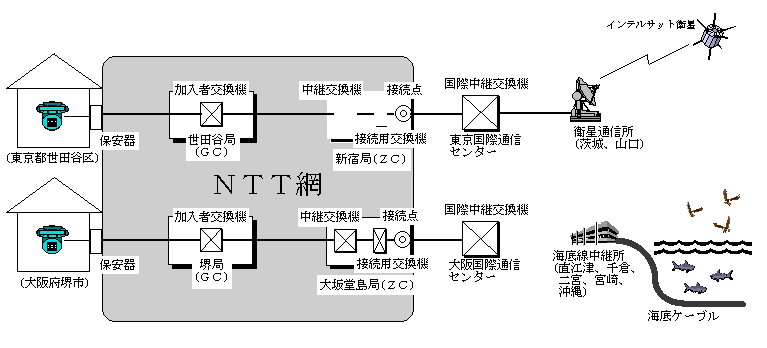 (3) NTT再編成後
(3) NTT再編成後
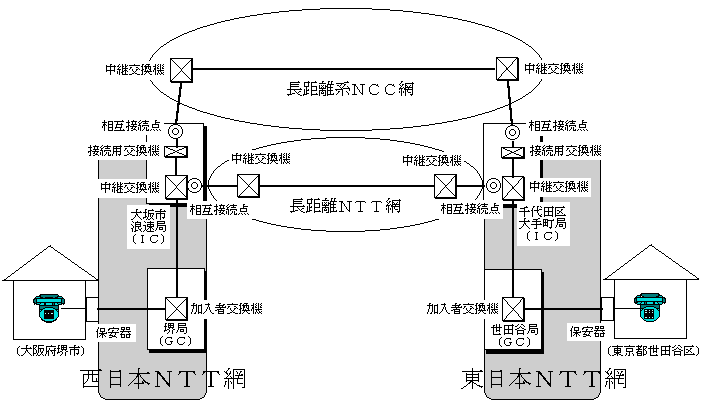
2 事業者識別番号の現状
利用者が特定の電気通信事業者を指定してその電気通信サービス(基本接続サー
ビス、不可サービス)を利用することができるよう、郵政省では電気通信事業者か
らの申請に基づき、事業者識別番号(00X1X2)の指定を行っている。00X
1X2の使用状況は別紙のとおりであり、ダイヤル方法については以下のとおりで
ある。
1 国内中継サービス(基本接続サービス)を選択する場合のダイヤル方法
電気通信事業者が指定を受けた事業者識別番号を市外プレフィックス(市外局番の
先頭に付く1桁の数字「0」のこと)の前に付加している。
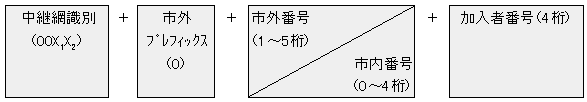 2 国際通信サービス(基本接続サービス)を選択する場合のダイヤル方法
電気通信事業者が指定を受けた事業者識別番号に続き、相手国の国番号及び相手
国内の電話番号をダイヤルする。
2 国際通信サービス(基本接続サービス)を選択する場合のダイヤル方法
電気通信事業者が指定を受けた事業者識別番号に続き、相手国の国番号及び相手
国内の電話番号をダイヤルする。
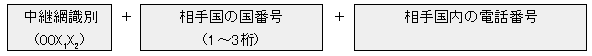
00Y1Y2番号の使用状況
(平成10年3月 現在)
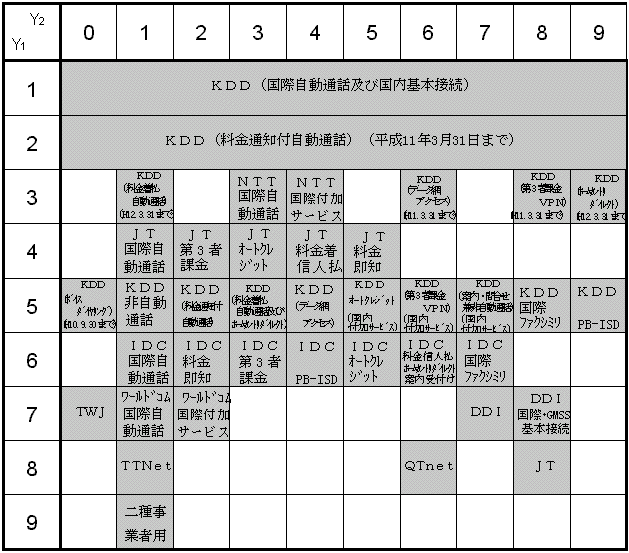
3 優先接続のイメージ
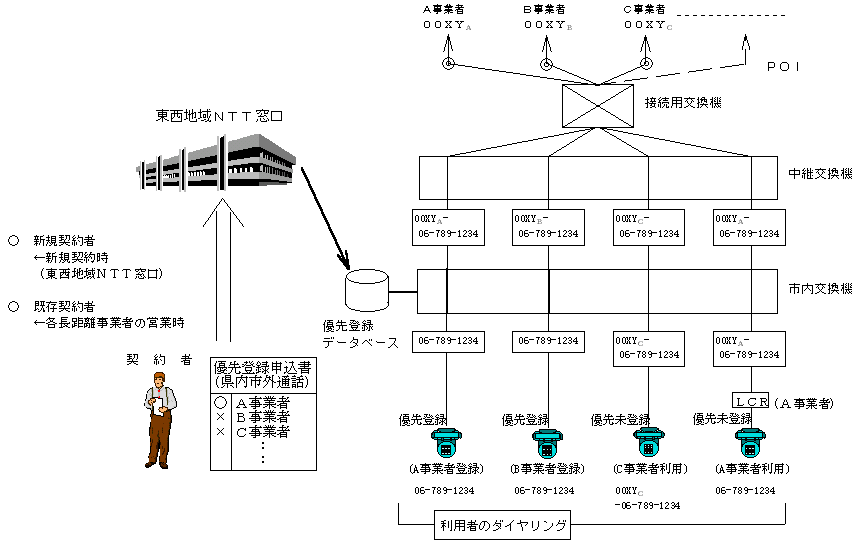
4 海外における優先接続導入状況
|
米国
|
オーストラリア
|
カナダ
|
ニュージーランド
|
韓国
|
ドイツ
|
導入時期
|
1984年
|
1993年
|
1994年
|
1994年
|
1997年
|
1998年
|
対象地域網事
業者
|
全ての地域系
事業者
|
テルストラ
(1社)
|
全ての地域系事
業者
|
ニュージーランドテレコム
(1社)
|
韓国通信
(1社)
|
ドイツテレコム
(1社)
|
対象接続事業
者
|
任意
|
オプタス
|
任意
|
任意
|
デーコム
|
ー
|
対象通話区分
|
長距離・国
際・地域(地域
は実際行われて
いない)
|
長距離、国際
|
長距離、国際
|
市外及び国際
|
市外
|
閉番号区域外、国際
|
通話毎選択の
有無
|
有
|
有
|
有
|
ー
|
有
|
有
|
登録勧奨方法
|
一斉投票
|
一斉投票
|
個別申込
|
個別申込
|
デーコムの顧客の
み郵便照会(1999
年サービス予定のオンセ通
信は個別申込みによ
る優先登録を行う予
定)
|
個別申込
|
無意思表示の
取扱
|
導入時は投票
得票割合で配
分(現在は行
われていな
い)
|
テルストラ
|
導入前契約事業
者
|
ー
|
デーコム
|
ー
|
LCRの取扱
|
有
(一般家庭には普
及せず)
|
ー
|
ー
|
なし
|
有
(優先接続の導入に伴
いダイヤリング方法が変
更になり、アダプタが使
用不可となる)
|
ー
|
費用負担
|
変更は利用者
(暫定的に事業者
を割当てられた利
用者は投票後6ヶ
月以内は事業者変
更料金無料)
|
変更は利用者
(投票後6ヶ月以内は、
1回に限り事業者変更料
金無料)
|
初期登録は長距
離事業者が負担
|
ー
|
初期登録費は事
業者負担、変更
料についても事
業者代行負担
|
初期登録は事業
者変更時は利用
者が負担
|
その他
|
不適正営業活
動多発
|
ー
|
ー
|
ー
|
ー
|
ー
|
|
EU
|
フランス
|
英国
|
デンマーク
|
香港
|
シンガポール
|
導入予定時期
|
2000年1月1日までに導入
を指令
|
2000年1月1日
|
2000年1月1日
|
1999年7月1日
|
導入予定なし
|
導入予定なし
|
競争状況
|
ー
|
1998年1月から全て
の分野で競争導入
|
全ての分野で競争
導入。
|
全ての分野で競争
導入。
|
長距離電話事業者
はなく、地域固定
電話や国際電話は
独占状態
|
長距離電話事業者
はなく、基本電気
通信サービスは独占状
態、2000年自由化
|
検討状況
|
・対象通話の範囲は、市
外及び国際
・対象通話の種類はすべ
ての電話サービス
(ISDN含む。)
・対象は、最低限重大な
市場支配力を持つ地域
アクセス事業者。
・優先登録の位置づけ、
実施方法、費用負担方
法等は、各国が決める
|
未検討
|
対象通話の範囲、
番号計画の影響、
コスト負担の考え
方等の検討を要す
る。
|
・国内、国際の両
方を対象とす
る。
・利用者が事業者
選択の意思を示
さなかった場合
は、現行事業者
を登録
|
ー
|
ー
|
検討体制等
|
欧州議会において審議中
|
未定
|
OFTELが基本的な考
え方をまとめ、諮
問委員会のNICCが
技術的仕様を決定
|
ー
|
ー
|
ー
|
検討の方向
|
ー
|
|
|
優先接続の導入は
事業者間の競争の
進展に極めて重要
|
競争状態に入ると
導入を検討する可
能性あり。
|
ー
|
5 接続の推進(接続ルール)
(1)経緯
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
平成8年12月・・・電気通信審議会答申(平成8年12月19日)
「接続の基本的ルールの在り方」について答申
平成9年 6月・・・電気通信事業法の改正
接続の基本的ルールについて法的枠組みを整備するた
め、先通常国会において電気通信事業法の一部を改正
(2)ルールの概要
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
1)特定事業者(独占的な地域網を有する事業者=NTT)
ア 接続約款(接続料及び接続の条件)の作成
イ 接続会計の整理・公表事務
ウ 網機能提供計画の公表事務
|
2)第一種電気通信事業者
ア 接続義務(接続条件は事業者間協議)
イ 事業者間の協議が整わないときには郵政大臣の命令・裁定
|
(3)スケジュール
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
(平成9年11月・・・改正電気通信事業法の施行)
→ NTTから接続に関する約款の申請
→ NTTにおいて接続会計を整理(平成10年4月
から)
平成12年 ・・・・必要に応じ見直し予定
(ex. 接続費用について実績費用に代わる理想的
費用の検討など)
6 優先登録の事務フロー
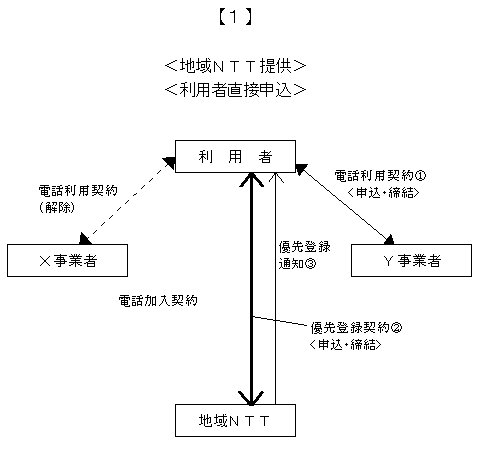
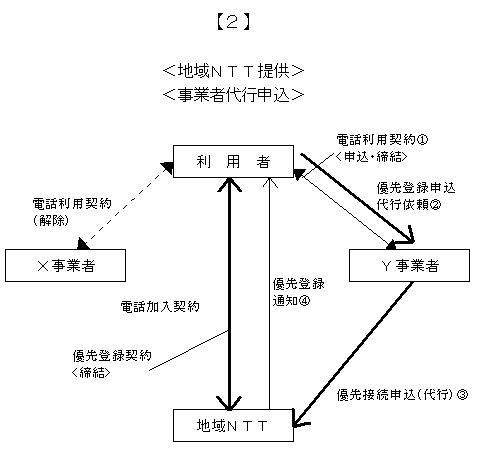
7 「優先接続に関する研究会」委員名簿
(敬称略・五十音順)
さいとう ただお
座 長 齊 藤 忠 夫(東京大学工学部教授)
いのうえ のぶお
座長代理 井 上 伸 雄(多摩大学経営情報学部教授)
あおやま みちこ
青 山 三千子(国民生活センター参与)
こすげ としお
小 菅 敏 夫(電気通信大学電気通信学部教授)
にいみ いくふみ
新 美 育 文(明治大学法学部教授)
やまうち ひろ たか
山 内 弘 隆(一橋大学商学部教授)

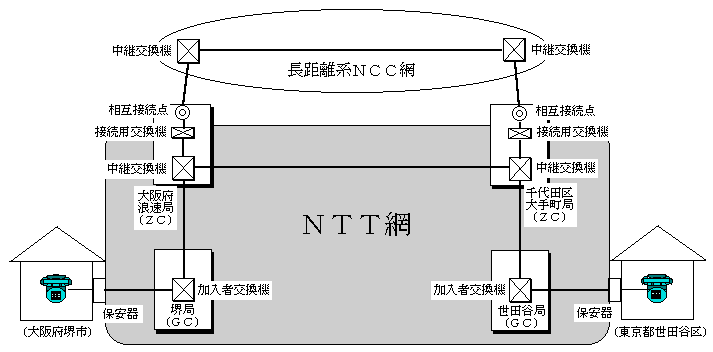 (2) 国際電話の場合
(2) 国際電話の場合
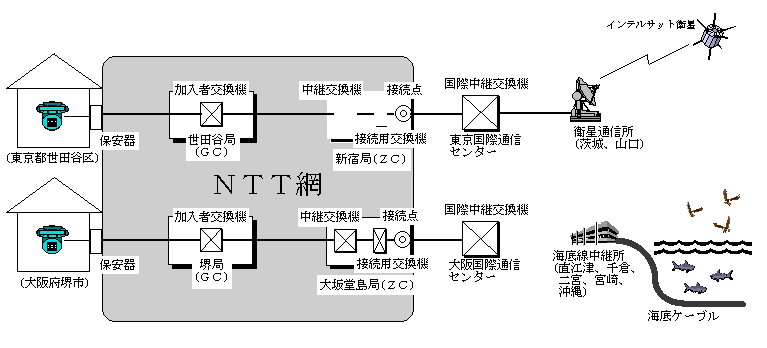 (3) NTT再編成後
(3) NTT再編成後
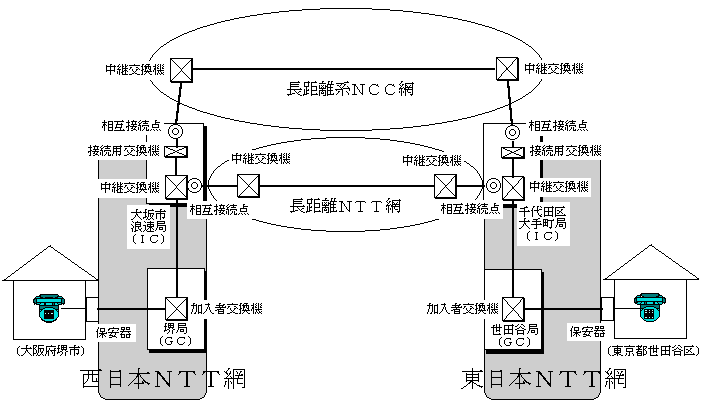
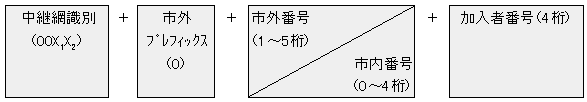 2 国際通信サービス(基本接続サービス)を選択する場合のダイヤル方法
電気通信事業者が指定を受けた事業者識別番号に続き、相手国の国番号及び相手
国内の電話番号をダイヤルする。
2 国際通信サービス(基本接続サービス)を選択する場合のダイヤル方法
電気通信事業者が指定を受けた事業者識別番号に続き、相手国の国番号及び相手
国内の電話番号をダイヤルする。