
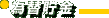



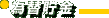
発表日 : 1998年 6月12日(金)
タイトル : 金融自由化と郵便貯金に関する調査研究会 第10回会合議事要旨
1 日 時: 平成10年4月27日(月)16:30〜18:30 2 場 所: 郵政省第2特別会議室 3 出席者: 岩田座長、井掘会員、鴨池会員、藤野会員、吉野会員、松浦会員 4 主な議題 我が国における個人金融資産選択の今後の展望 5 議事概要 議題に沿って以下のような意見が出された。 (1) 家計貯蓄率の動向について ○ 家計貯蓄率の現在の水準が今後とも維持されるかどうかについては、少 子高齢 化に伴う将来所得への不安による影響と、年金負担増の影響を併せて考慮 する必要がある。 ○ 個人の貯蓄動機としては、「老後の生活資金」といった項目の比重が、 中長期的には高まっており、少子高齢化の進展は、この動機に基づく貯蓄 を増加させると考えられる。 ○ 将来の年金受給の減少を予想する層が、貯蓄を増やして将来に備えるこ とから、家計貯蓄率は低下しない可能性もある。 ○ 年金負担の増加により生産年齢層の可処分所得が低下し、貯蓄額が低下 することが考えられ、公的年金制度が家計貯蓄率の動向に結果的にどう作 用するかは微妙。 (2) 個人のリスク許容度の変化について [個人のリスク許容度はそれほど変化しないとする立場からの論拠] ○ 個人の保有株式数が株価の上昇、下降期の如何にかかわらず、ほぼ安定 的に増加している。 ○ バブル期の実証分析において、個人のリスク選好度がほとんど変化しな かった。 [個人のリスク許容度が高まるとする立場からの論拠] ○ 土地、住宅等の実物資産の価格上昇があまり見込まれないことから、金 融資産の中である程度リスクをとってポートフォリオを組む方向に進む。 ○ 少子高齢化の下で、相続する資産が増加することにより、これまで住宅 ローンなどのいわゆる私的負担が大きく、自らリスクをとれなかった個人 の負担が軽減される。 ○ 供給者による活発な商品説明等を通じ、リスク金融商品の需要の創出が 行われる。 (3) 外為法改正の影響について ○ 日本で超低金利が継続し、海外の金融商品の相対的な有利性が存在する 限り、旧来から自由であった外貨預金のほか、今回自由化された海外預金 や対外証券投資が活発化する可能性が高い。 ○ その過程で発生する円安傾向が、円換算後の予想収益率を大きくするこ とから、海外の金融商品の購入が増大し、外為法改正などのアナウンスメ ント効果も相まって、短期的には金融資産が海外に流出するものと考えら れる。 ○ 海外金融商品の相対的な有利性も、いずれは国際金融市場において裁定 が働くことにより減殺されることが予想され、また、為替リスクも存在す ることなどから、金融資産の海外流出が長期にわたって継続することはな いものと考えられる。 連絡先:貯金局経営調査室 電話:3504−4471