
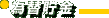



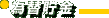
発表日 : 1999年12月 6日(月)
タイトル : 貯金局長定例記者会見資料
電信振替の振替先登録サービスの実施について 郵政省は、郵便振替の加入者の利便を図るため、ATMを利用した電信振替を行 った場合に、その送金先の口座番号を登録できるようにし、2回目以降の送金手続 の簡略化を図ります。 1 サービス概要 【1回目】【2回目以降】
2 対象となるATM台数 約2万台(平成12年3月末) 3 サービス開始時期 平成12年1月5日以降改造を実施したATMから順次サービスを開始 連絡先:貯金局経営企画課 送 金 企 画 係 (担当:鈴木係長、岸) 電 話:(03)3504−4496
別紙 平成11年度 「国際協力に関する作文」コンクール入賞者 <小学生部門>
一枚の写真から 石巻市立山下小学校 6年 安田 あゆみ 机の上に一枚の写真が飾ってある。私と妹とネパールのアンディコラの村の女の 子たちと手を組んで笑っている写真。私は、この写真が大好きだ。 私は、ちょうど一年前、三年間住んでいたネパールから帰ってきた。父がネパー ルの山の上の病院で働いていたので、私達も一緒にネパールで生活をした。電気は、 一応あったけれど、雷が遠くでなるとろうそくの灯より暗くなった。水道の蛇口は、 ついていたけれど、水は一滴もでなくて毎日水をくみに行った。日本では、スイッ チを入れれば電気がつき、蛇口をひねれば飲める水がでるのがあたり前だけれど、 日本に帰ってきたばかりの頃弟は、そんなことにも驚いて喜んでいた。 もののあふれる日本に帰ってきて、日本の時間は、ネパールでの時間より速く流 れていくように感じた。 でも、この一枚の写真を見るといつも思いだす。ネパールの女の子たちといっし ょに輪になって河原に座り、踊ったり歌ったりして肩を組み、手をつないだ日のこ とを。 国が違っても、言葉が違っても、皮ふや目の色が違っても、私たちは友だちにな れることを知った。 国際協力は、ただお金をあげることではない。ものをあげることでもない。友だ ちとして、人間として、私たちはどうしたらいいかを考え続けることだと思う。相 手の国の文化や習慣を知り、私たちの文化や習慣も伝えあい、どうしたらお互いの ことをわかりあえるかを考えあうことが国際協力だと思う。 私は時々、何時間もかけてネパールの村を歩いて診療する父についていったこと がある。一日に百五十人もの患者さんが来る時もあった。私も大きくなったら、い つか父のように、医者や薬の足りない国で働く医者になりたいと思う。そしていつ も心のどこかに今も戦争や貧困で苦しんでいる友達がいることを忘れずにいたいと 思う。
地球のニーズ 富山市立堀川小学校 4年 池田アリサ睦実 「一人の力では、ちょっぴりしかできません。でも、一人の人がもう一人の人を 助けたら、地球がちょっぴりずつやさしく、よくなるのでもっと人に手伝ってほし い。」 これは、アメリカのおじいちゃん、グランドパァの言葉です。おじいちゃんは耳鼻 いんこう科の医者で、インド北部の村で医療ボランティアを3回しました。その村 には、おじいちゃんの友達のお医者さんがしんりょう所を作るまで医者は一人もい なかったそうです。重い病気にかかった人だけ遠い病院まで行ったそうです。おじ いちゃんの話によると、村のしんりょう所まで車で来る人は一人もいなかったそう です。わたしは、遠い病院へ行くとちゅうで死んでしまう人もいたかもしれないと 思います。でも、おじいちゃんの友達のおかげで、村の人たちは病気が軽いうちに しんさつしてもらえるようになりました。 病院だけではありません。暖ぼう、電気、きれいな飲み水、トイレやおふろのた めのきれいな水も問題だそうです。 おばあちゃんのグランドマァも、いろいろ手伝っていました。耳のけんさをした り、ほちょう器をあげたりしました。また、インドの学校に行き、アメリカのこと を話したり、インドの子どもたちに英語を教えたりしました。 わたしにできることは何んだろう。わたしは初め、インドの学校の先生になりた いと思いました。子どもたちが勉強を覚えたり、友達に手紙が書けるようになった らうれしいです。でも、おじいちゃんは医者になった方がいいんじゃない、と言い ました。 私は最初、インドの人達はかわいそうでボランティアをしてる人達はえらいと思 いました。でももう一度よく考えてみました。もしほかの国の人が、 「インドの人たちはびんぼうでかわいそうだからこれをあげよう、これも、これも あげるよ。」 と言ったらインドの人たちの心をこんなふうに傷つけます。 「くれるのはありがたいけど、びんぼうとはよばれたくないな。わたしの国がばか にされてるみたいでいやだな。」 わたしがボランティアに行ったら、その国の人たちにわたしが知っていることを 教えてあげて、その国の人たちはわたしに、その国の言葉や知っていることを教え たりしてくれるとすごくいいなと思いました。
まず知ることから 各務原市立八木山小学校 5年 鈴木 祐衣 16円。65円・・。数字は私といっしょに大きくなっていきました。六才の私は、 ピンク色の通帳がほしくて、なにげなく国際ボランティア貯金に入りました。そこ に書かれた、寄附の意味も、ボランティアの意味もわかりませんでしたが、横にあ る「ありがとうございました」の言葉に、何だかうれしい感じをうけました。あれ から五年。私は大きな病気もせず、毎日学校で楽しく生活しています。 この夏、私はとても素敵な笑顔に出会いました。それは、小さな黒板をノートが わりにし、勉強しているラオスの子ども達の写真でした。ここでは今まで、地面に 字を書いていたそうです。私はすごいショックを受けました。私の回りには文房具 があふれています。何冊もの使いかけのノートや、途中であきてしまい、引き出し の奥にころがっている鉛筆。次から次へ新しい物を手にして勉強する私が、このラ オスの子のような笑顔でノートを開いたことがあったでしょうか。世界には、様々 な状況の中で生きている友達がいることに、この時私は気づいたのです。同時に、 NGOの存在も初めて知りました。私がジュースに使っている百円玉一枚で、鉛筆 が五本も買えたり、コッペパンが二十四個も買えるなんて・・。どれだけ多くの人 が、NGOの活動を待っていることでしょう。教育や環境、医療のあらゆる所で支 援を続けるこの活動に、私のボランティア貯金が、ほんの少しでも役立っていると 思うと、不思議な感じさえします。 国際協力とは、まず世界の現実の姿を知ることから始まると思います。薬があれ ば助かる命もあります。地球家族という言葉のとおり、お互いが助け合って生きて いけるようになりたいと思います。私の知ったことを友達に伝え、通帳に描かれた 手のように、もう一人の手を探して、ボランティアの心の輪を広げていけるように 努力していきたいです。
私の国さい協力 養老町立養老小学校 4年 早崎 有紗 私の家では、それぞれに国さい協力しています。でも、私は最初、国さい協力の 意味が分かりませんでした。だから、私が始めたぼ金がわが家では一番新しい協力 です。 おばあさんは、年末になるとユニセフのはがきを買ってあげてます。この代金は 少しが病気の子どもたちの命をすくうワクチン代になっていると言っていました。 私は、こんな小さなお金が命をすくうくらい大きなお金になるのがとても不思議に 思いました。 お母さんは、古着がたまるとアジアのめぐまれない国へ送っています。私が、 「こんなお古、だれが着てくれるのかな。」 というと、 「ほら、ちゃんととどいてるのよ。」 と言って写真を見せてくれました。たくさんの他の国の子が日本語の書いてあるT シャツを着て笑っている写真でした。古着を送る協会からもらったものだそうです。 お父さんは、会社で国さい協力をたん当したことがあると言っていました。いろ んな人たちの意見を聞いて、どんなことが会社としてできるか考えるのはとても大 変だったと言っていました。そしてネパールに小学校を建てたということです。ネ パールの子どもたちにも会いに行きました。みんなの笑顔がわすれられないと言っ ていました。 そして、今、私は家族ぼ金を集めています。空かんにふたをつけ家の食たくにぼ 金箱とて置きました。一年に一回、クリスマスの月に開けていくらかをたしかめま す。お母さんやおばあさんは、買い物のおつりを入れています。お父さんは思いつ くとたくさん入れています。私はおこづかいをもらったら入れています。たまった お金は、私とお父さんでボランティアのだん体に送ります。 「後で、どんなことに使われたか、ちゃんと教えてくれるだん体にしよう。」 とお父さんは言います。私は、学校に行けないまずしい国の子どもたちのえんぴつ やノートになればいいなと思います。 何から始めたらいいか分からなかったけど、思ったよりかんたんにできそうなこ とがあるのだなあと知りました。国さい協力に行って外国でがんばっている人のニ ュースも見ます。海外ボランティアという言葉もニュースでおぼえました。すごく、 大変なことだと思います。自分のことでなく、他の人のために何かしてあげるのは、 かんたんそうにみえてちっともできていないことだからです。それが、遠い外国な らば、もっとむずかしいです。 私は自分ができることを見つけて、ずっと続けていきたいと思います。国さい協 力という言葉はむずかしいけれど、やることはいっぱいあるはずです。世界中が協 力すれば、きっと一番大きな国さい協力になると思いました。
一枚のふくがあいのプレゼントに 萩市立明倫小学校 2年 田中 涼子 わたしのきられなくなった小さいふくは、毎年お母さんの手によって、日本きゅ えん衣料センターの方やボランティアの方がたにわたり、そしてアジアやアフリカ にわたっています。タイやカンボジアで地らいのぎせいになり、かた足をうしなっ た子どもが、今わたしのふくをきているかもしれません。 今、アジアのいなかの方では、学校へきて行くシャツにもこまり、きるものもな く、だき合ったままこごえ死んでいく兄弟もいるそうです。 お母さんには、アメリカ人とけっこんしてアメリカにすんでいるいとこがいます。 今年の夏休みに、わたしと同じくらいの3人の男の子をつれて、日本にかえってき ていたのです。わたしはおばあちゃまの家で、英語しか話せないその子たちと一し ょに遊びました。 ことばはおたがい分からないのに、心は通じ合っているようでした。 今のせかいは、けっしてそれぞれの国が切りはなされたものではなく、つながっ て生きていかなければいけないと思います。一人一人が立ち上がり、それぞれ同じ 地きゅうに生きている人間どうしが、ささやかでもできることをしていかなくては いけないと思います。 「お母さんみたいに、ウエストが入らなくなってふくがきられなくなったなんて、 タイやカンボジアの人たちにとって、そうぞうできないほどぜいたくなことだと思 うわ。それにね、こうして衣料があつまっても、海外ゆそうのしきんがとってもふ そくしているらしいの。」 と言っていました。 わたしたちのタンスの中にねむっている一枚のいふくや一枚の毛布が、その子た ちの手にわたれば、それはただものとしてわたるのではなく、心としてつたわるの です。 その心のぬくもりが、何よりもゆうきづけられるのではないかと思います。
国際貢献と日頃思っていること 仙台市立長町中学校 3年 櫻井 篤 日本は今、真剣に国際貢献について考えていかなければならないと思います。 日本は国際社会において、どのような役割を果たせば良いのでしょうか。また、ど んなことをすれば、貢献できるのでしょうか。 まず、過去の歴史をふり返ってみると分かるように、現在の日本の繁栄は、国民 自身の努力と同時に、戦後の復興期に世銀や外国から、大きな支援を受けたおかげ でもあります。そこで、考えていかなければならないのが、この「国際貢献」とい うことです。 日本の政府開発援助(ODA)の実績を見ると、その額は、先進国の中では一位 であるが、対国民総生産(GNP)比では十五位と低いです。また、国民一人あた りの負担額では、八位と高くないのが現状です。そして、ODAの質を表す贈与比 率でも十八位であり、これは、それだけ貸付けが多いことを示しています。 そこで、これから日本はどのように国際貢献をしていけば、良いのでしょうか。 我が国は、食糧や石油など多くの必需品を開発途上国からの輸入に頼っています。 また、軍事大国としての道は歩まないとした日本が、世界の平和と発展のためには、 どのような方法が望ましいのでしょうか。 まず、日本は人的貢献が少ない、と言われています。例えば、国連事務局の職員 数の場合ですと、実際の職員数が望ましいと思われる職員数の二分の一にも、満た ないということになっています。確かに、日本は、贈与の額は多いのですが、その 額はともかく、それよりも、内容が充実していなければならないと思います。そこ で、日本の援助などの貢献制度には、根本的な内容の面で、改善の余地があると思 います。ダムの発電タービンなどの機械を援助しても技術者の養成をしていなかっ たため、故障してしまうともう使いものにならなくなってしまうとか、港を造って も災害で使えなくなってしまったとか、いろいろな問題があります。 つまり、その国の自然環境や民族性、歴史、経済状態、制度などを考えて、援助 の方法を決めていかなければなりません。 また、私たちにはどのようなことができるのでしょうか。身近なことには、どん なものがあるのでしょうか。例えば、「手作り翻訳絵本」というのがあります。こ れは、教科書不足に悩むアジアの開発途上国の小学校で使われている、英訳された 日本の絵本です。とても役立っていて、不足するくらい大人気だとのことです。こ のことから、お金をかけた物よりも手作りの心のこもった贈り物が一番だというこ とが、分かりました。 そこで、国際貢献をするにあたって大切なことは、お金の援助よりも直面してい る問題が解決される物資を送ることです。そして、世界の平和と発展のための日本 の役割を、私たちは担っていかなければなりません。
海外生活で考えた国際協力 多賀城市立第二中学校 3年 高橋 岳大 僕は、今年三月まで三年間シンガポールに住んでいました。父の仕事のためです。 小学校六年から中学校二年までの期間に、外国、特にアジア諸国の文化に、生に触 れることができて貴重な体験をしたと思います。 シンガポールに引っ越してすぐ、アパートの外を散歩していた時、工事現場を見 ると、労働者の多くは外国人でした。彼らは、インドやパキスタンなどからの貧し い出稼ぎ労働者だったのです。 彼らはスラムのような所に住み、平日は毎日十時間以上働き、給料は日本円にし て百円程度という過酷な労働で、そこでためたお金を国の家族に送っています。海 外の美しい観光地として有名なシンガポールですが、その内側に入ってみると、こ の国の経済を支える貧しい労働者の姿がいたるところにありました。 また、日本人学校中学部の修学旅行でタイに行った時、寺院の外や道路わきで、 花やお土産を売っている少年、少女を何回も見かけました。中には高速道路の下で、 ダンボールをかぶって寝ている少年もいました。インドネシアでは、赤信号で車が 止まっている時をねらって、新聞を売ったり歌を歌ったりしてお金を稼ぐ、いわゆ る「ストリートチルドレン」を見かけました。一方、僕たち日本人、その他の外国 人と言えば、マンションや一軒家に住んで、これらの少年達とは比べものにならな いくらいぜいたくな生活をしています。 同じ位の年齢なのに家を支えるため労働をしなければならず、教育も十分に受け られない彼らと、自分の生活を比較して、何かがおかしい。民族とか宗教とかの違 いをこえて、この差はこのままであってはならないという思いが高まりました。 日本は、これらの国々に対し、様々な基金や海外青年協力隊の派遣などの援助を 行っています。この基金とは目的を持って集められ、使われていますが、僕が目に した貧しい子供達に何か変化を与えているのだろうか。社会の末端の貧しい労働者 の生活は、何一つ変わらず、今もストリートチルドレンは路上を走っています。彼 らにとっての本当の援助とは、生活の安定と共に人間としての守られる権利を保護 し、人としての誇りを持って生きる環境を整えることだと思います。そして、これ はお金ではどうしようもできないことなのです。 ある日本人はベトナムに行った時、両親を亡くした子供たちを見てとてもかわい そうに思い、教師を辞め、子供たちが生活できるように自己負担で、孤児院を建設 し、少年たちを保護しました。 本格的に援助するとはここまで、自分の生活を考えるなどできないものなのかも しれません。全ての人ができることではありませんが、少なくともお金イコール援 助ではなく、生き方にまでかかわってこそ、援助なのだと思うのです。何が現実的 で有効な援助の姿なのかはまだ分かりませんが、国の違いをこえて、人間として同 じ権利を持ち合えることを目標に国際協力について考えていきたいと思います。
本当の意味の国際協力を目指して 福島市立福島第四中学校 2年 相田 佳恵 みなさんは国際協力と聞いて何を思い浮かべますか。きっと、難民などの救済の ための食料や衣類の援助、医薬品の提供などを連想するのではないかと思います。 私も今までは、食料や服を現地の人に送り与えることが国際協力のイメージでした。 確かに、ワクチンなどの薬を送り、生後間もない子供たちや、 病気の人を救うことはとても大切なことです。でも、衛生状態を改善していかない かぎり、根本的な解決になっているとは言えません。飢餓をなくしていくことにお いても、ただ水や食べ物を送り与えるだけでは本当にその国のためにならないので はないでしょうか。 例えば、ミネラルウォーターや野菜を現地の人に送ったとします。きっと現地の 人々は喜ぶでしょう。その水と野菜で栄養失調の子供を救うことができます。たく さんの人々を飢えから守ることもできます。しかし、それは一時的なものであって、 永遠に続くものではありません。それでは本当の意味の国際協力にならないと思い ます。だから、私は水なら「井戸を掘る技術を伝え、実際に井戸を掘って水を得て、 できるなら、衛生的な水の給排水を行えるよう上・下水道の完備を行う。」野菜な ら「水を得た上で、土地を耕す道具、近代的な農業技術と人材の提供を行い、自分 たちの力で少しでも食料を自給していけるように助ける。」ということが、本当の 国際協力なのではないかと思います。 そもそも、国際協力とは何のためにするのでしょうか。それは、世界中の国々が みな平和に仲良く暮らすためであり、違う国家として経済的に自立し合った上で、 どちらかがどちらかに一方的に依存するばかりでなく、互いに補い合う力をつける ためにするのだと、私は思います。だからこそ、物資を送り与えるだけの協力では なく、設備や技術を提供し、人材を育ててその国が自立していけるほどの力をつけ るのを助けていくという「本当の意味での国際協力」を目指していかなければなら ないのだと思いました。 そこで、そのために私たちは何をしていかなければならないのかを考えてみまし た。 まず、新聞やニュースなどで国際情勢を知ることです。世界の情勢を知らなけれ ば、今どうすべきかは見えてこないでしょう。また、青年海外協力隊などのように、 実際 に現地に行ってきた人の話を聞いたり、ユニセフ親善大使の黒柳徹子さんや国連難 民高等弁務官の緒方貞子さんの著書を読んだりして、現地の人々の状況を知れば、 より確かにその国の状態を感じることができるのではないかと思います。そして、 いろいろな知識を得た上で、自分の判断により募金に協力するなり、難民の受け入 れを快く行うなりするべきだと思います。 このように考えてくると、国際協力とはもともと国と国とのつき合いのことです が、つきつめていくと人間同志のつき合いが根底にあるのだと思います。そのため、 国際協力を行う上では、一方的に与えるばかりで相手国の自立を妨げることのない よう、相手の本当に必要としているものを知って行動することが重要になるのです。 人間の場合でも、過保護になると、かえって本人の成長を結果として阻止してしま い、本当に相手のためにならなくなってしまいます。 これらのことを常に念頭に置き、国際協力に一人一人が臨んでいけば、本当に良 い国際協力をしていけると思います。私は、その国際協力を支える一員として、こ れから少しでも多くのことを実行していきたいと思います。
私が考える国際協力 栃木県立大田原女子高等学校 2年 田村 尚美 「ユネスコ部員は海外へ行けるからいいね」と、私は友達によく言われます。で も、私たちが開発途上国を訪れる目的は、観光や遊びではなく、どんな協力ができ るか、現地の人達と直接話し合うためなのです。普段知ることができない現地の裏 側の状況を、自分の目で見て、肌で感じ、行くことができなかった人にも、より詳 しい情報を伝え、これからすべきことは何か、一番適切な協力方法は何か等を確認 し、それを実行するために行っているのです。 私たちは、いろいろな勉強会を行い、正確な知識を身に付け、たくさん意見を言 って、自分たちには何ができるかを考え、それを行動に移しています。援助をする ためにも、様々な方法があるとことも、忘れてはなりません。高校に入学してユネ スコ部に入り活動して以来、私は今まで全く興味がなかったことにも関心が持てる ようになり、世界的にも視野が広がりました。そして多くの知識が身に付いてきま した。特に、初めて参加した勉強会では、今までの私の考えを大きく変えました。 例えば、募金箱があるから、ただお金を入れればよいのではない。そのお金は、ど んな人が、何のために集め、何に使われるのかなど、きちんと知った上で、はじめ て助けになっているということを知りました。学校でも行われている募金活動など も、募金したお金は、何の役に立っているのかも知らずに、ただ「募金したからい いことした。」と思っている人も中にはいると思います。しかし、そうではなく、 きちんと知った上で募金することで、初めて協力したことになると思うのです。 もう一つ学んだことは、「飢饉」と「飢餓」の違いです。戦争や災害などが起こ った地域で目にする飢饉というのは、一時的なもので、よくニュースで取り上げら れます。そのため食糧などの緊急援助が、世界中から集まります。しかし、途上国 の各地で日常的に続いている慢性的な飢餓というのは、あまり注目されることがあ りません。しかし、彼らは栄養不良、不衛生な環境の中で生活を送っているのです。 こういった地域には、ただお金や食糧、衣服を送ればいいのではありません。私も これまでは、「募金をして、食糧などを送ってあげればいいのではないか?」と思 っていました。しかし、彼らは、自分たちで自立し飢餓を終わらせようとする努力 が必要なのです。援助してくれている国に頼ってしまい、いつまでも自立すること ができないので、自立するための行動の援助をするのが、私たちの本当の協力だと いうことを知りました。 このように協力の方法もいろいろあります。その地域の正確な状況を知って、そ の地域に適した行動をとることが、本当の国際協力ではないでしょうか。そのため には、古切手や使用済みテレカを集め、お金に換えたり、小さなことの積み重ねや、 状況を知ったり、知識を増やすための勉強会が、今、私たちにできる国際協力だと 考えています。
「国際協力」とは・・・ 組合立甲陵高等学校 2年 穂坂 遼子 私は、去年の夏に山梨県青少年国際協力体験事業に参加しました。国際的に活躍 できる看護婦さんになりたいと思っていた私は、発展途上国での医療状況を見たい、 少しでも多くの人の役に立ちたいという思いがあり、参加を希望しました。そして 私は仲間とともにタイ王国に行くことになりました。 タイには、日本からのYMCAやJICAなどの国際協力機関があります。それ らの機関では、環境保全、医療など多くの社会問題に対するプロジェクトを展開し ています。資金援助・技術援助・物資援助。しかし、それだけではありません。私 は、今回の体験で、最も重要な援助を見つけたのです。 私達は、YMCAの皆さんと一緒に橋や高速道路の下にあるスラム街へと行きま した。スラム街とは、家を持てずに暮らしている人々の集団が住む場所です。そこ は決して清潔とは言えない場所でした。一日一日がやっとだそうです。YMCAの 皆さんは、そこで主に教育を行います。衛生、性教育、言葉の読み書き、食物の育 て方など幅広い面での教育です。すべて、人が生きるために知るべきことです。教 育を行う彼らを見ていると、それを教えているだけでなく、もっと大切なこともし ているように思えてきました。その大切なこととは、生きていく喜びを感じさせる ことです。相手に心でぶつかり、共に笑ったり悲しんだり、時には泣いたり。私が スラムで見たもの、それは現状の苦しい生活とはうらはらに、何だかあたたかいも のでした。 次に、私達は山岳民族を訪れました。そこでは、青年海外協力隊の人々が活躍し ていました。私は、一人の女性と話すことができました。彼女はぎこちない英語で、 勉強したいのだが、機関も資金もないと言っていました。彼女は、学問に深い興味 をもっていました。私が、今当り前のように通う学校、簡易に手に入る教材、めん どうだと思ってしまう勉強は、彼女にとって素晴らしいことなのです。私はその時 思いました。(必ず多くの知識と暖かい心を持って、人の役に立てる人間としてあ なたに会いに来ます。)と。 「国際協力」には、物質的援助がもちろん必要です。しかし、それ以上に精神的 援助が必要なのです。“開発”すなわち“Develop”とは、de;とき放つ、 velop;封筒。封筒の中に入っている可能性、能力、知恵などをとき放つこと。 そう、自分自身が生きていくことの喜びを感じさせることなのです。相手の立場に 立って、その場所、時、状況にあわせて考え、接することで、本当の意味での“開 発”をしていく必要があります。そのためには、多くの知識と技術を身につけ、多 くの人と出会い、暖かい心を持たなければなりません。“国際協力”とは、“心” でぶつかるものなのです。今、現場で多くの問題と戦っている皆さんへエールを送 りたいです。そして、いつの日か私もその一員として役に立てる人物になりたいで す。
身近なことから 岡谷市立岡谷東部中学校 2年 濱 雪乃 最近よく、新聞やニュースで「国際社会」だとか「国際化」といった言葉を見た り聞いたりします。また私自身も、様々な国の人と交流したり、街で外国人を見か けたりすることも多くなりました。ここ長野県でも昨年は冬季オリンピックが開催 され、ますます国際化が進んだように思われます。世界各国からたくさんの人が日 本を訪れたり、また日本人も世界各国に行ったり・・ということは互いの文化など を学び合えたりしてとても素晴らしいことだと思います。お互いの国を学び合うこ とは世界中の人々の協力へとつながると考えられるからです。どんな大きな問題で も一つの国で取り組むより、たくさんの国が協力して取り組めば、とても大きな力 となりいろいろな道が開けてくると思います。 二年程前に、私は新聞で、発展途上国の子供たちのために学校や文房具や本を送 ったという記事を読んだことがあります。私がその時まず驚いたことは、この地球 上に、勉強したくても貧しすぎて勉強する場所も本もない子供達がいるということ でした。私達日本の子供は毎日学校に行って授業を受けるという生活を当たり前の ことのように送り、時には学校に行くのがいやだ、なんて思ったりすることもあり ました。でも行きたくても行かれないという子供が世界中に約一億人もいるという ことを知り驚くとともに、改めて私達は幸福なんだなと実感したことを思い出しま す。 今、「国際協力」というテーマについて改めて考えてみて、その時の「かわいそ う」という気持ちは、「私も何かしたい」という願いに変わってきました。私でも、 何かできることはないだろうかと早速インターネットで詳しい情報を集めてみるこ とにしました。すると、募金をする、書き損じハガキを集めるなど、私達がいつも やってきたことがたくさん並んでいました。これらは今まで毎年学校で行われてい ることで、私も毎回協力してきています。でもこれまでその目的は漠然としていて、 よくわからないままお金だけ出すという感じでした。しかし、今回インターネット でその方法と目的がはっきりと結びついたことで、私の中に“その国の子供達の幸 福を心から願って募金やハガキ集めをしたい”という決意が生まれました。 インターネットで調べていたとき、ある文章が目に留まりました。それは、「日 本がユニセフの援助を受けていたことをご存じでしょうか」というものでした。 「えっ!?」とビックリして、詳しく調べてみると、戦後十五年間、日本も当時の金 額で六十五億円もの援助を受けていたということがわかりました。ミルクや洋服な どをユニセフから援助してもらったということでした。父の年齢を考えてみると、 約二年間その援助を受けていたことになります。 「そのお陰で今の私がいるんだな。」と思うと、世界中の人々のぬくもりが伝わっ てくる気がして、私はますます、 「発展途上国の子供達を助けたい。」という思いが強くなりました。 一人の力は小さなものです。でもまず一人一人が始めないと何も始まらないと思 うのです。一人からその身のまわりの人へ、それが世界中へと広がっていけば、と ても大きな支援の輪になるでしょう。この世界にかわいそうな子供が一人もいなく なるまで、私達一人一人が思いやりの気持ちをもって世界中の人々と手を取り合い 努力を続けていきたいと思います。そして世界中の人々とその協力と成功を喜び合 える日が一刻も早く来るよう祈りつつ、私自身の第一歩を踏み出したいと思います。
みんな地球家族 珠洲市立大谷中学校 1年 濱 志穂子 「やっぱり今年も出しに行こう」 連日報道されている北アナトリア断層を震源地としたトルコのギョルジュクの崩壊 した町の様子をテレビで見て、私は決心して空カン貯金箱に目を移した。 私の家では『いつか、誰かに役立つ心』とラベルの書かれた空カン貯金箱が、硬 貨の種類ごとに並べられている。自分のお財布の中に小銭がたまると、自分の意志 でその空カン貯金箱にお金を入れている。 この空カン貯金箱をはじめたのは、海辺の小さな大谷の町に大きな大きな被害を もたらしたナホトカ号の重油流出事故がきっかけだった。青く輝く自慢の海が、茶 黒色の重油の層に埋めつくされた。あの苦しい災害から救ってくれたのは、凍り付 く北の海に腰までつかり、油まみれになって取り除いてくれた、多くのボランティ アの人々の人力とあったかい心だった。 「私は年寄りで、そちらへ出向くことができません。せめて自分の手作りの梅干を、 おにぎりの中に入れて使って下さい。」 と、瓶に入った梅干が婦人会長をしていた祖母の元に送られてきたりもした。この ような心のこもった救援物資も、どんどん送られてきた。「大谷の地を訪れたこと もない、縁もゆかりもない人々が、こうして助けてくれている。感謝すべきだし、 今度は自分達もその心をもたなければ。」この、ナホトカ号の重油流出事故を教訓 に、家族はそう決心した。そして空カン貯金箱がはじまった。 ピンクの用紙に手が重ねられた図案の『国際ボランティア貯金協力証』、この手 の重ね合いの大切さを身をもって経験した私。そして家族。自分達のできる手の重 ね合いをしたいと考えた。 飲み水の確保のために学校へ行けない子ども達。内戦のために、自分の育った国 さえも奪われた難民の人達。毎年、ワクチンや予防接種ができないために死亡して いく千四百万人の乳幼児達。そして、今回の地震の被害のため、今もがれきの下で 命と向きあっている人達。同じ地球という国で苦しんでいる家族が今もいっぱいい るのだ。 能登半島の先端に生きている十二才の中学生の私にできる国際協力や国際ボラン ティア活動の幅は限られている。しかし、家族全員が協力証をもつことや、空カン 貯金箱に感謝の心を入れることなど、自分の小さな手でも今できることを精一杯や りたいと思っている。 私は、ミッキーマウスの空カンに、ぎっしりつまっている家族の心をもって、郵 便局のドアを開けた。「私もみんな、地球家族の一員だから、今年も、この空カン 貯金箱をどうぞ使って下さい。」
援助のあり方 豊田市立猿投台中学校 3年 小澤 愛可 私たちの学校では、修学旅行で、それぞれにお会いしたい人や団体に連絡をつけ て会って来る、というイベントがあります。 私は友達に誘われ、ユニセフを訪問することにしました。正直言うと、初めはそ う乗り気ではありませんでした。でも、実際に伺って、驚くような新しい発見の連 続で、いろいろなことを知ることができました。 例えば、アジア、アフリカ、中南米の子供たちの多くは、学校に行かず、親の手 伝いをして、水汲みや畑仕事をしているということ。このことはテレビなどを通じ て知っていましたが、これほど大変とは思いませんでした。 彼女たちが実際に水汲みに使う水瓶を持たせてもらうと、びっくりしました。も のすごく重くて、私たちが二人がかりでやっと持てるほどなのです。こんなに重い 瓶に水を入れ、私たちよりずっと小さい子が、毎日毎日何キロもある道を歩くのだ そうです。 それは、驚きと同時に、ショックでした。私が毎日テレビを見たり、ゴロゴロし ている時にも、彼らは生きるために一生懸命働いているのです。そう思うと、なん だか自分がすごく情けなく思えてきました。そして、少しでも彼らの生活が楽にな るように、私のまわりの物をたくさん送ってあげたくなりました。 しかし、ユニセフの方は、厳しい顔で言われました。 「彼らにただ物を送るだけでは駄目なんです。確かに物をあげれば、生活は楽にな ります。でもそれは、ほんの一時のこと。それでは、彼らは自分たちで生きられな くなってしまいます。彼らに一番必要なのは、一人で生きていけるように、技術を 身につけさせてあげるということです。」その言葉を聞き、安易に援助というもの をとらえていたことを深く反省させられました。 「彼らのために何かをしてあげたい」と思うことは、いいことだと思います。し かし、その際に、目先だけにとらわれず、長い目でみて、何が彼らにとって大切な のかを真剣に考えなければいけなかったのです。 食料にしても、送ってあげればとりあえずその場はしのげます。でも、結局は何 も変わりません。だから、彼らが自分の力で生活できるような形のサポートを考え て行っていく、これが正しい援助なのです。 考えてみれば、私は今まで学校で行われる募金活動に対しても、深い考えもなし に行っていました。ただお金を寄附すればいい、そんないいかげんな気持ちだった 気がします。 でも、これからはもっと心を込めて協力したいと思います。私たち学生には、ユ ニセフの方が言われる技術を教えることなど到底できません。でも、そういう技術 を持った人がその国へ行く資金の協力ならできます。 その国の人たちのために自分ができる最大のこととは、そういう問いかけをしな がら、これから先ずっと温かい援助活動に参加していきたいと思います。
ボランティア活動について私が学んだこと 津島市立藤浪中学校 2年 服部 有希 私たちが生きているこの同じ地球上で、明日の生活も不安な状況の中で、困難な 毎日を送っている人々がたくさんいます。食料不足や環境の違いの中で起きる人権、 貧困問題など、まだまだたくさんあります。 ある時、カンボジアの難民大量発生のことを、本で読みました。べトナム軍との 交戦で傷ついた人々が着の身着のまま何日も地雷原をさまよい、ようやくタイの国 境にたどりついた難民の人々のことが書いてありました。地雷を踏んでしまって命 をおとしてしまった人、両足を失った子ども、飢えと病気でバタバタと倒れて亡く なった人々のことなどと、私はとても大きな衝撃を受けました。きっとその中には、 私と同じ年代の子もいっぱいいたはずです。同じ人間として生まれ、育っていく上 でこんなにも違いがあり、しばらくボー然としてしまいました。そして、何の不自 由もなく学校に通い、勉強をさせてもらっていることに感謝の気持ちでいっぱいに なりました。 その難民キャンプの人々の救援活動が、国連機関や赤十字関係者との調整の下に 組織化されて行われていることも、知りました。欧米の人たちそして日本からもた くさんの人が、医療協力・食糧援助・仮設テントの建設・保健衛生面の活動までて きぱきと働いていると書いてありました。その中で難民の人々が自分というものを 見失わず、自立していけるようにするための教育活動があり、カンボジアの文化を 大切にしてもらおうと子供たちに絵本を届け、教育の機会を与えようとしている一 人のボランティア活動をされている方のことが書いてありました。 ボランティア活動とは、物資援助や緊急援助といったことのほかに、この先のこ とを考えた心の援助もあることを知りました。難民の人々の今の生活では、将来の ことなど希望を見出せるわけがありません。それだからこそ、人の温かい心が必要 だと思います。子供たちを集めて、絵本を渡し、その中で何か感じとってもらおう とすることで、少しでも自分に自信と誇りを持って、大きく育ってもらいたいとい う願いが伝わってきます。 ひとつ間違えば、危険がいっぱいの中でのこのボランティア活動。自分の命に代 えても、この難民の人たちのために何かできることをしたいとする人々に私は本当 に強く感動しました。私の将来は、夢も希望もたくさんあります。そのことに感謝 しながら、これからいろいろなボランティアについて勉強していき、私なりにでき ることを見つけて、困難な生活をしている私と同じ地球に住む人・同じ時代を生き る人のため、少しでも力になれるようにいろいろなボランティア活動、そして、そ のほかのことにでもいろいろ、自主的に参加していきたいと思います。
第一歩はその国を知る事から 生駒市立光明中学校 1年 宇田 圭吾 僕のお母さんの知り合いでNGO(非政府組織)からアフリカのギニアビサオと いう国に三年間派遣された人がいます。以前から海外へ行きたいと思っていたそう ですが、どうせ行くのなら自分のためだけでなく人のため国のためになることの方 がいいと思い参加したそうです。でも、実際に行ってみると国の習慣の違い、民族 の違いによるとまどいや、熱帯性の気候によるマラリヤ、コレラまたエイズなどの こわい病気もはやっており、その人もマラリヤに三回もかかるなど危険な目にあっ たりもしたそうです。あちらの人は衛生に関する知識が少ないので、不衛生な水を 飲んだり、まわし食べまわし飲みをしたりして感染します。 ギニアビサオでは、医者、農業を教える人、道路の舗装の指導者が必要だという ことですが、ただ、こちらから一方的に教えるだけではなくて、その国の人たちに とけこみ、彼らからもたくさんのことを学んだりして、お互いに成長していくこと が大切だと思います。 僕と同じぐらいの年のギニアビサオの子供達の暮らしは、ある一部の子供は優雅 な暮らしをしているけれど、ほとんどの子は一日一食しか食べられない子や、金持 ちの家のお手伝いをして働いている子など、すごく厳しい生活をおくっています。 そこで、僕達中学生にも何かできることがあるかと質問してみると、はじめは家 にある使っていないような文房具やサッカーボールを送ることなどと言われました。 僕は、それがまず海外協力の最初の一歩だと思います。僕はまだ海外に行ったりで きないけど、まずその国の様子や政治のことに関心を持ち、勉強していくことが大 事だと思います。でも最終的には物を送るだけでなく、彼らが自分達の力で貧しい 人達をなくすような政治を行ったり、病気の人の看護や治療のやり方を覚えたり、 病気や衛生に関する知識を持ったりして、自分たち自身で病気と戦っていけるよう にすることが、国際協力ボランティアの本当の役目だと思います。 世界中には、国の名前ぐらいしか知られていないような国がたくさんあります。 僕は、これから少しずつでいいから様々な国の状況、生活、文化などを勉強してい こうと思います。まず、その国を知ることが第一歩。僕も、将来ボランティアに参 加するために、みんなに、呼びかけて行きたいと思います。
理解しようとすること 府中町立府中緑ヶ丘中学校 3年 陶山 順一 コソボ紛争、トルコ大震災・・。ここ数ヶ月の間に戦争や様々な自然災害により、 世界各地で多くの命が失われていった。 戦争や自然災害による恐怖は、実際に被害にあった人々にしかわからない部分が 多いように感じる。日本でも、五十数年前まで戦争をしていた。戦争を本当に体験 した人にとってそれは忘れようとしても忘れられない思い出だろう。しかし、戦争 を経験した人達も段々と減り、それがどれだけ悲惨だったか、本当に理解できる人 はそのうちいなくなってしまうだろう。数年前の阪神大震災。多くの人が家族を、 友人を、生活を失った。僕はその様子をテレビで見ていた。同じ日本のことなのに、 どこか遠いところでのでき事、実際の事なのに、小説を読んでいるのと同じくらい の感覚しかなかった。口では「恐ろしい、悲しい、かわいそう」と言っても、実際 には本当にそれを体験した人の十分の一どころか百分の一もそう感じてはいないの だろう。 テレビで、コソボ紛争で難民になった子供達が他の国に迎えられるという内容の 番組をやっていた。家を追われ、親と別れた小さな子供達が、バスから降りてくる ときのさみしさと不安の入り混じった表情がとても印象に残った。きっと心に大き な傷をおったことだろう。しかし、僕達にいったいどのくらいその気持ちが理解し てやれるだろうか。あの子達は一生この事を忘れはしないだろう。だが、僕はずっ とコソボ紛争の事を覚えているだろうか。あの不安気な目をもう一度思い出し、あ の子達の気持ちを想像しようとすることが、はたして何年か先にあるのだろうか。 国際協力とは一体どういう事だろうか。苦しんでいる人々の存在を知り、募金を することだろうか。それともボランティアで海外等におもむくことだろうか。しか し、それでは、結果的に苦しんでいる人々の役に立つだけで、ただの自己満足に終 わってしまうのではないだろうか。僕達はめぐまれている。世界のどこかで戦争や 自然災害がおきていても、なかなかピンとこない。しかし、それではいけないのだ ろう。本当に苦しんでいる人の、困っている人の役に立とうと思うのならば、その 人達の現実をしっかりとはあくしなければいけない。その人達は、今どんな気持ち でいるのか、どんな事を考えているのか、完全に理解することはできないのだろう が、少しでも理解しようと努力することが大切なのだと思う。その上でどうしたら その人達の傷をいやしてやれるだろうか、どうしたらその人達のためになれるだろ うか。常にそう考える事が国際協力につながるのだと思う。テレビで見た子供達の 目。僕は、あの子達の目をいつまでも覚えていることができるだろうか。今はまだ、 結局のところどうすればいいのかはよくわからない。しかし、あの子達の目を忘れ ず、そして気持ちを理解しようと努めることを僕の国際協力の第一歩としたい。
やさしさの架け橋 松山市立三津浜中学校 3年 鈴村 知華 一九九八年十月末。ハリケーン“ミッチ”が中米にあるホンデュラス、ニカラグ アを直撃しました。その被害は、壊滅的なものでした。ホンデュラスだけでも死者 と行方不明者で二万人を超え、橋の流失・道路の破壊・通信網の損傷・異常な物価 高など、元々発展途上国だったこれらの国の発展を何年も後戻ししていました。 しかし、私がこのことを知ったのは、それから四ヶ月たった後のことでした。松 山在住の青年海外協力隊の家族の方々や、昔、ホンデュラスで隊員だった方々が、 救援活動を松山からも行おうと松山市生徒会連合会にも呼びかけをしたからでした。 生徒会役員だった私は、その話し合いに参加しました。そこではまず、現地にいる 隊員からの手紙を家族の方が読み、昔、隊員だった方が被災前の様子を話してくだ さり、写真も見せてくださいました。そしてその後、被害の様子をビデオで見まし た。それは、私が考えていたよりも悲惨なものでした。道路も、バナナ畑も水に埋 もれ、家もほとんどなくなっていました。私が一番ショックだったのは、貧しい人 々が住んでいた地域が最も被害が大きかったということでした。そして、救援活動 をどうするかということを話し合い、草の根レベルではあるけれども、各学校で取 り組んでいくことになりました。 三津浜中学校では、まず被害状況を知ってもらうために、生徒集会を開きました。 私たち生徒会役員は全校生徒に一生懸命説明をしました。その結果、家を失った人 たち、親をなくした子供たち・・。四ヶ月たっても復興の目処のたっていないその 被害の大きさを理解してもらうことができました。その上、救援活動においてもア ンケートで、義援金と学用品の送付の両方を行うことになり、緑の羽募金の還元金 も義援金に使っても良いと承認してもらいました。みんなから集まった義援金、学 用品はとても多く、青年海外協力隊の方たちのように、現地で活動することはでき ないけれど、この松山で精一杯、協力することができたと思います。 この救援活動は強制ではなく、ボランティアとして行いました。それにもかかわ らず、たくさんの人が協力してくれたことをとてもうれしく思いました。たとえそ れが日本のことでなくても困っている国を助けてあげるという、本来あるべき姿を 見せてくれました。最近、自分さえ良ければいいという人が増えているとよく耳に します。でも、私たち三津中生はそうではありません。それが、救援活動という形 で表れました。『ボランティア』三津中の良き伝統です。この良き伝統をこれから もずっと引き継いでいってもらいたいと思います。やさしさを持ち続けてもらいた いと思います。それは、時には国と国とをつなぐ架け橋にもなるのです。 そして、ホンデュラスとニカラグアの少しでも早い復興を祈って・・。
初めて考える国際ボランティア 大分県立臼杵高等学校 2年 吉良 仁見 「ボランティア」最近とてもよく聞き、よく使うこの言葉、しかしボランティア とは何なのか説明しろと言われても詳しく説明できる自信はないし、自分が何をす ればいいのかさえ分からない。ましてや国際ボランティアとなると、具体的にどん な活動をやっているのか全く見当もつかない。私は自分を情けないと思った。毎日 のようにテレビ・新聞や学校生活の中で登場するボランティア。それが今、とても 重要なことだということはよく分かっている。それについての話を聞くたびに、一 応は自分にできることは何かなど考えたりする。だけど私はそこから先、何もしよ うとはしなかった。海外の国々の現状、ボランティアの意味や内容など調べてみる ことさえしなかった。自分の周りの環境が豊かすぎて、頭ではボランティアを考え てはいたが、心では自分とは関係のない遠い国のことと思っていた。しかし私はこ の日本の豊かさをいろんな形で支えている国々の中に戦争や難民、貧困や飢餓など で苦しんでいる国が多くあることに気づいた。 私は国際ボランティアについて少し調べてみた。すると、そこには驚きと発見が たくさんあった。まずNGOだ。NGOという組織があるなんて今まで知らなかっ た。直訳すると「非政府組織」で、海外協力を行っている市民の組織をNGOと呼 んでいる。さらに驚いたことは、その団体の数が想像以上に多かったことだ。私の 知らないところでこんなに多くの人々がNGOに参加していると知って、私は何と もいえない気持ちになった。そして活動している多くの人に共通していることは、 相手を助けるつもりが、相手から多くのものを学び得て、気づけば自分の方が豊か になったと感じているということだ。海外協力は「援助」とは少し違う気がした。 援助だとこちらが与えるばかりで、相手よりも自分の方が、一段上に立っているよ うな感じがするからだ。ボランティアは対等な関係で理解と交流を進めながら、共 に学び生きていく共生だと思うのだ。 私はほんの少し国際協力について知っただけで、今までの何倍も興味をもった。 そこの人と人とのつながりの中に何かとても温かいものを感じたからだ。というよ り熱いに近い感覚なのかもしれない。 ボランティアの最も基本は「自発性」である。「したいからする」これが大切だ ということをとても感じている。 手助けを必要としている国はたくさんある。地球そのものだって悲鳴をあげてい る。ボランティア、その一つひとつは小さな力だけどそれが何重にも重なった時、 世界を変える大きな力になるだろう。 私は、もっと地球が見えるように視野を広げていきたいと思う。日本の豊かさの 裏には、どれだけ苦しい国があるか、その国の人々が本当に必要としているものは 何か考えられる力を身につけるべきだ。みんな地球に住んでいる。私は日本人だ。 でもその前に地球人なのだから。
KBC友愛の集い 鹿児島県鹿児島市 70歳 小田 美知生 クリオン島の朝は、かん高い鶏の鳴き声で始まる。フィリピン最大規模のハンセ ン病療養所のある小島クリオン。 以前、私がマニラの日比合弁の会社に勤めていた時、病に倒れたが現地の人たち の献身的な看護で回復。帰国後、恩返しにマニラへ援助物資を送った。その話を知 った島民から窮状を訴える手紙が届いたのがきっかけで、衣料品や文具、医薬品な どを送るようになって、やがて八年になる。 ハンセン病ゆえにこの島に送られてきた歴史を背負う人びと、その家族と子供た ち。大自然の花を見るような生き生きとした目、笑顔。一通の手紙からここまで友 情の輪が広がっているのを見て、年に一度、島を訪ねるたびに新たな感動を覚える。 しかし、まだまだこの島の人たちの生活は、豊かさなど質的な面では想像できな いほど惨めな状態が続いていて、学校へも通えずにいる子供たちが多くいることも また確かな事実である。いつの時代でも、子供たちの未来は輝いたものでなくては ならない。何とかこの空洞から生き残るためにと、昨年、手探りの状態ながら、島 民と話し合って始めた養鶏も順調に進み、島民一人ひとりが役割を分担し、耐乏生 活から自力で抜けだそうとする意識も浸透し、活気に溢れ、表情も明るくなった。 だが、療養所では、今なお手足に不自由の残る人たちがひっそりと暮らしている。 見舞いのお礼にと歌ってくれた年老いた患者。物悲しいギターの音色。涙が流れた。 その昔、島へ連れてこられた人たちの心を思った。国際協力、そこには常に自らを 律し、反省し、より深く理解することを自分に求める厳しさが問われているように 思う。 ところで、私が援助活動を続けられるのも、当初から深い関心と理解を示し、私 を支え続けてくれている友人たちのお陰である。これからもより質の高い協力の実 現に近づくために、ここ鹿児島で自主グループ結成の旗揚げを実現、「KBC友愛 の集い」という名のシナリオが出来上がった。またひとつ大きな目標が見えてきた。 ちなみに「KBC」とは、「鹿児島」、「ブーカル地区」、「クリオン島」の頭文 字である。 「KBC」の結成で、日本からの心の支えと激励が着実に続けられているという 安定した喜びと信頼感を持ち、島民は温かい夢と希望に育まれているとの便りも届 いた。これから先、島民に何が必要か、一緒に考える姿勢を我々も持たなければな らない。 援助する側もいわば一緒に走る伴走者のようなもの。お互いに知恵をだし合い、 島民の自立の確保により多くの人たちの理解と思いやりが連携して協力が出来るな ら、どんなにか素晴らしいことだろう。 国際協力、それは使い捨ての消耗品みたいなものではよくない。国境を越え、時 代を超えて生き抜く重み、骨格と質感こそ大切なことだと私は常に思う。