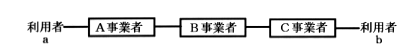発表日 : 10月1日(火)
タイトル : 海外調査概要(米国班)
7月14日〜7月21日
(1)ワシントン ・FCC
・司法省
・Comptel
・MCI
・Sprint
・MFS
(2)ニューヨーク ・ニューヨーク州公益事業委員会
(3)シカゴ ・イリノイ州公益事業委員会
・アメリテック
【AT&T分割以前 (pre MFJ) 】
1.州際サービスの相互接続
AT&Tが市外通話を独占していた時代においては、AT&Tは長距離
通信収入の一部を、BOCに対しては「分収(Division of Revenue)、
独立系電話会社に対しては「清算(Settlement of Commision)」という
形で相互接続料金を支払っていた。
1970年代になって、MCI等の競争通信事業者が長距離通信市場へ
参入し、BOCや独立系の地域電話会社の地域網に接続して長距離サービ
スを提供することになると、そのアクセスコストをENFIA(Exchange
Network Facilities for Interstate Access)料金として支払ってき
た。
2.州内サービスの相互接続
州内サービスには競争は導入されておらず、相互接続はLATA内の隣
接LEC(地域通信事業者)相互間に限られていたと思われるが、州の管
轄であり、競争導入の状況、相互接続の内容等は不明。
【AT&T分割以後 (post MFJ) 】
1.州際サービス
修正同意審決(MFJ)によるAT&Tの分割後、FCC裁定によりア
クセスチャージ制度が導入された。
これは、地域電話会社による州際アクセスサービスの提供を約款化する
ものであり、手続的にはFCCへの申請、FCCによる審査等を経て発効
する。
アクセスチャージの料金額の算定には、当初、報酬率規制が適用されて
いたが、1991年よりRHC、GTE等に、プライスキャップと報酬率
のハイブリッド規制が課されている。
また、拡大接続命令(1994年7月14日等)により、地域通信事業
者の交換アクセス網と競争アクセス事業者(CAPs)の州際サービス用
市内アクセス回線との接続を義務づけ、州際アクセスサービスへ競争を導
入した。
2.州内サービス
州内サービスについては州の管轄であり、競争の導入状況、相互接続の
状況等州によって異なる。特に、LATA内サービスについては、ほとん
どの州で競争が導入されていなかった。
【1996年通信法の制定】
1.1996年2月8日に成立した1996年通信法により、全ての電気通
信事業者に相互接続義務が課された。
2.法は、FCCに対して6ヶ月以内に相互接続に関する規則を制定するこ
とを要求しており、FCCは4月19日に規則案を公表しコメントを求め
ている。
予定では、8月8日に規則が制定、公表される予定である。
1.1996年2月8日に成立した1996年通信法により、全ての電気通信事
業者に相互接続義務が課されるとともに、義務の内容については、「全ての電
気通信事業者」「全ての地域通信事業者」「既存地域通信事業者」の3段階に
分けた。
また州際・州内によっても、アクセスサービスの義務が分けられている。
ア)州際サービス
州際アクセスサービスについては、当面原則的に現行制度が維持されると思
われるが、近い将来の変更が予測される。
(・251条(i)にFCCの州際アクセスの規制権限に変更のないことが規
定されているが、4月19日FCC規則案において、FCC規則69部(アク
セスチャージ)の近い将来の変更に言及している。)
イ)州内サービス
1996年通信法253条により州に対して競争導入が義務づけられ、25
1条により相互接続が義務づけられた。
2.地域通信サービスにおける相互接続の状況は、地域通信に競争を導入してい
ない場合がある等、各州によって大きく異なる。
今回の調査対象であるニューヨーク州及びイリノイ州は、カリフォルニア州
とともに地域通信への競争導入が進んでいる。
ア)ニューヨーク州
1996年通信法制定以前から、ニューヨーク州においては市内交換を含む
市内通信全般に競争を認めている。相互接続については、LECに対して、競
争事業者への接続及びタリフの届出を義務づけている。
イ)イリノイ州
ニューヨーク州と同様、1996年通信法制定以前から、市内交換を含む市
内通信に競争を認めている。相互接続については大規模LECに対して、他事
業者との接続及びタリフの届出を義務づけている。
※ 州の規制における「LEC」は、通信法の「既存LEC」とほぼ同義と思わ
れる。
1.地域通信に関する相互接続の条件は、原則として交渉によって決定され、接
続協定は州の公益事業委員会の認可を受けることとなっている(251条、2
52条)。
但し、BOCsについては、自社サービス地域内において長距離通信サービ
スへ参入する場合には、相互接続約款の策定等が条件となっている(271条
)。
2.料金水準に関し、1996年4月のFCC規則案によれば、州による相互接
続料金またはネットワーク要素の提供料金の決定に当たっては、
ア)歴史的費用とレートベースの精査を行う伝統的なサービス費用主義(レー
トベース方式)を採用することができないと仮決定した。
イ)法は、他のコストベースの料金設定(例:プライスキャップ)の使用、或
いは、将来費用に基づく料金設定(例:長期増分費用)の使用を考慮してい
る。
とされている。
8月に発表される規則による明確化を注視する必要がある。
3.相互接続料金算定に関する各州公益事業委員会の方針は以下のとおり。
ア)ニューヨーク州
PSCは増分費用方式の確立を提案している。また、フロンティア(旧ロチ
ェスター・テレホン)については、部門子会社化して算定している。
トータルサービス長期増分費用(TSLRIC)の測定もやっているが、コ
スト算定について、会計面の依存度を低めていく方向。FCCが示唆している
のは、コスト標準・レート標準の設定であり、価格は市場が決めるのが望まし
い。
イ)イリノイ州
ICCがイリノイベルに対し、長期増分費用に基づいて自ら算定した接続料
金(市内交換料 0.5セント/分等)を含むタリフの再提出を命令する等、
長期増分費用方式を採用している。
ストランデッドコストは顧客ではなく株主が負担すべきとの考えにたち、相
互接続によりユーザー料金へ波及することがないようにしている。
ウ)その他
一部に異論はあるものの、司法省、事業者とも、長期増分費用方式を一般的
に肯定している。
これは、長期増分費用方式が過去の地域通信事業者の投資(独占時代の多額
の投資)を引きづらないような配慮を行っているためである(司法省、イリノ
イ州公益事業委員会)。
しかし、長期増分費用方式の定義は多様であり、その採用の可否を含めて、
定義についても8月のFCCの規則を待つ必要がある。
1.州際アクセスチャージについては、FCCが監督し、「統一会計規則」「分
計必携」「コスト配分必携」等により、州際アクセスのコストと州内サービス
のコストを会計分離している。
2.州内アクセスについては、FCCの規則が明らかになっていないこと及び原
則として州公益事業委員会の管轄であることから、州際と同様の会計分離を義
務づけるのかは不明。
但し、州際アクセスチャージと同様の会計分離を望む事業者の回答もあった。
※1 州際アクセスチャージの料金規制として、BOCs等の大規模な地域通
信会社については、プライスキャップ規制と公正報酬率規制のハイブリッ
ド規制が適用され、会計結果と料金算定は必ずしも対応していない。
その他の地域通信事業者については、会計結果に基づき、公正報酬率規
制が課されている。
※2 州内サービスの料金規制は州の管轄にあり、州によって規制方式が異な
る。
1.米国ではすでに一部の事業者間により番号ポータビリティが実現されていた
が(例:NYNEXがMFSとケーブルビジョンライトパス等で提供されてい
る方式)、1996年米国通信法の改正により、FCCの番号に関する管轄権
が明確に記述された。
2.FCCにおいても通信法制定以前の1995年6月にルール化の意見招請を
行い、本年6月27日に規則が制定された。
【主な内容】
○ 長期的なポータビリティの方式としてはルールにおいて定める基準を満たし
たデータベース方式を採用することとしているが
・特定技術を強制しなくても全国的互換性を達成することが可能
・一方式を選ぶには情報が不十分であり州レベルで既に実施途上にある試みを
遅延させる恐れがある
・特定方式の強制は今後の技術革新を阻害する恐れがある、との理由から、特
定しないこととしている。
○ 番号ポータビリティの費用負担については、今後FCCのルールにより決定
される。但し、番号管理については、FCCが新たな番号管理機能を創設し、
その費用を全ての電気通信事業者が公平に負担することとなっている。
○ スケジュール
1998年12月31日までに上位100大都市でポータビリティを提供
1999年1月1日以降はすべての地域で要求されれば6ヶ月以内にポータビ
リティ実施。
1.1996年4月のFCC規則案では、アンバンドル化されたネットワーク要
素として「加入者回線」「市内交換能力」「市内伝送と特別アクセス」「デー
タベースと信号網」の4要素が仮決定されている。
2.FCCはアンバンドルの提供要素の明確化を図ってきており、これをどの程
度PUCの決定に委ねるかが重要である。新規事業者に対し地域事業者ネット
ワークを3つに分けて取り扱っている。
このアンバンドル化についての考え方は以下のようなものである。
(1)まず、別の地域事業者による加入者回線の提供が可能か、あるいは加入者
回線のアンバンドルを要するかを考えた。加入者回線のアンバンドルが可能
な場合、別の交換機を用意してMDFまで接続可能との理解。
(2)また交換機そのものもアンバンドル可能。この場合、AT&Tが交換機の
トランク側で接続して地域サービスを提供可能
(但し、交換機のアンバンドルは難しいとの回答もあった)。
(3)さらにコール・セットアップとコール・ルーティングに使用されているS
S7、データベースもアンバンドルの検討対象である。
3.最終的なFCCのアンバンドル化の考え方については、8月の規則制定を待
つ必要がある。
米国では、FCC命令により、BOCsは、1992年以降、ONA(オー
プン・ネットワーク・アーキテクチャー)等について、下記のような事項を記
載した年次報告を作成しなければならない。
・ONAサービスに関する3年間分の年次導入予測
・新規のONAサービス提供に関する要望及び処理状況
・以前に技術的に実現不可能とされたONAサービスの取扱い
・その他
96年通信法においても、FCCは網機能提供計画について監督権限を有す
ることが明確にされている(256条)。
ABC三者間による相互接続の場合、AB及びBC間に接続協定があれば、直
接接続しない事業者間(AC間)では必ずしも接続協定を結ぶ必要がない。例え
ば、AB合意の過程でAがCに運ぶトラフィックも表記するという内容にするこ
とも可能。
ただし、一般的には、3者間で接続する場合にはABC間それぞれで接続協定
を結ぶこととなるとの事業者の回答もあった。
○ 相互接続に要する期間
米国では、基本的に全てのキャリアが同一の技術による設備を選択し、ソフト
の開発も数週間から2ヶ月という回答があった。
(参考:NTTは、現在、約2年間かかるとしている。)







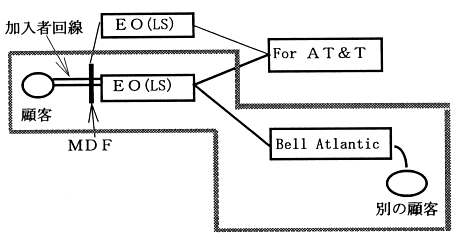 このアンバンドル化についての考え方は以下のようなものである。 (1)まず、別の地域事業者による加入者回線の提供が可能か、あるいは加入者 回線のアンバンドルを要するかを考えた。加入者回線のアンバンドルが可能 な場合、別の交換機を用意してMDFまで接続可能との理解。 (2)また交換機そのものもアンバンドル可能。この場合、AT&Tが交換機の トランク側で接続して地域サービスを提供可能 (但し、交換機のアンバンドルは難しいとの回答もあった)。 (3)さらにコール・セットアップとコール・ルーティングに使用されているS S7、データベースもアンバンドルの検討対象である。 3.最終的なFCCのアンバンドル化の考え方については、8月の規則制定を待 つ必要がある。
このアンバンドル化についての考え方は以下のようなものである。 (1)まず、別の地域事業者による加入者回線の提供が可能か、あるいは加入者 回線のアンバンドルを要するかを考えた。加入者回線のアンバンドルが可能 な場合、別の交換機を用意してMDFまで接続可能との理解。 (2)また交換機そのものもアンバンドル可能。この場合、AT&Tが交換機の トランク側で接続して地域サービスを提供可能 (但し、交換機のアンバンドルは難しいとの回答もあった)。 (3)さらにコール・セットアップとコール・ルーティングに使用されているS S7、データベースもアンバンドルの検討対象である。 3.最終的なFCCのアンバンドル化の考え方については、8月の規則制定を待 つ必要がある。