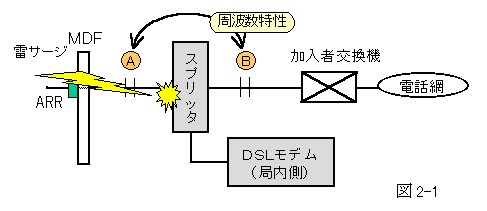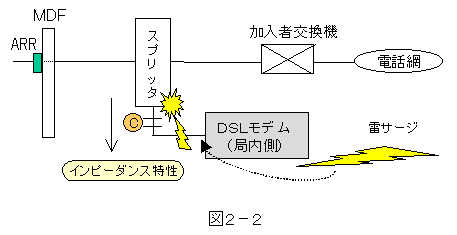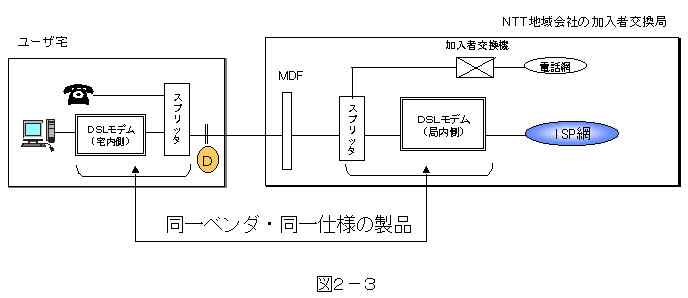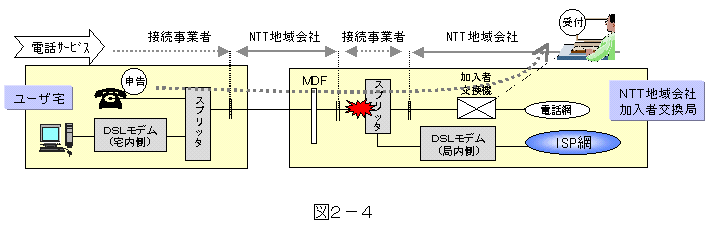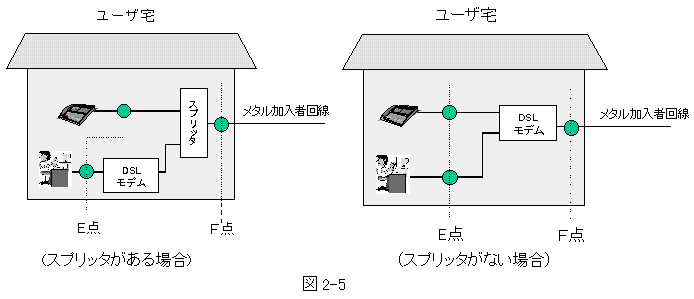(1) 試験的なDSLサービスの実施にあたっての基本的方針について
 |
接続箇所及び提供するDSLの方式等について NTT地域会社は原則として、接続事業者のMDF等での接続によるDSLサービスの試験的な実施にあたっては、既存サービスへの影響を考慮しながら、接続事業者から要望のある全ての接続箇所及びDSLの方式等について、特別な理由がある場合(注)を除き、これらを実施しなければならない。
|
||||
 |
試験的なDSLサービスの実施エリアについて 接続事業者のMDF等での試験的な接続によるDSLサービスの実施エリアについては、開始当初は、NTT地域会社が計画している実施エリアを基本とするが、DSLサービスの円滑な全国展開に向けて、可能な限りエリアを順次拡大されることが望ましい。 しかしながら、試験的なDSLサービスであることから、実施エリアを必要以上に拡大する必要はないものと考えられる。ただし、NTT地域会社は接続事業者から要望があったエリアについては、接続事業者がそのエリアでDSLサービスの提供ができるように努めなければならない。なお、実施エリアの拡大に際しては、その旨を郵政省へ報告することが望まれる。 |
||||
 |
試験的なDSLサービスの実施の位置付け MDF等での試験的な接続によるDSLサービスは、接続事業者がDSLサービスを本格的に実施可能かを検討するために行われるものである。したがって、この試験的なDSLサービスの間に特段の技術的問題等が生じなければ、接続事業者は本格的なDSLサービスに移行できる。 |
||||
 |
試験的なDSLサービスの実施にあたっての留意点 試験的なDSLサービスを通じて得られたデータによっては、接続事業者が本格的なDSLサービスを行うことが不可能になることがある。この場合、接続事業者に経済的損害や、事業計画の見直しといった問題が生じることが想定される。その際に接続事業者とNTT地域会社の間でトラブルが生じないように、接続事業者が試験的なDSLサービスの実施前に事業者間で十分な協議を行う必要がある。 |
(2) ADSL以外の方式によるMDF等での接続によるサービスの実施について
 |
接続事業者が試験的なDSLサービスの間にADSL以外の方式によるMDF等での接続によるサービスの実施を要望する場合は、NTT地域会社は接続事業者と速やかに協議を行い、特別な理由がある場合を除き、その要望に応じなければならない。
|
 |
NTT地域会社が平成11年12月より実施予定の試験的なDSLサービスの期間終了直前または終了後、接続事業者がMDF等での接続によるサービスの実施を要望する場合についても、NTT地域会社は速やかに協議を行い、特別な理由がある場合を除き、試験サービスを実施しそのサービスの提供可能性を検討しなければならない。 |
(3) DSLサービスの事業展開に必要な情報の開示について
 |
接続事業者は、DSLサービスの事業展開に向け、実施可能なエリアや実施可能な芯線数等の情報から、そのサービスの事業性を判断する必要がある。また、DSLサービスの事業展開は、ISDNの提供状況や加入者回線の光ファイバ化計画と密接な関係があると考えられることから、NTT地域会社は接続事業者の要求に応じて、その事業展開に必要となる情報(ISDN回線の敷設状況、光ファイバ化の現状及び今後の計画等)について、可能な限りその事業者に対して提供しなければならない。
|
 |
特にメタル加入者回線の存続はDSLサービス提供の必要条件であることから、NTT地域会社は、接続事業者がDSLサービスに用いているメタル加入者回線を含む、全てのメタル加入者回線の撤去に関する情報について、その回線の撤去を開始する一定期間前(5年前程度が望ましい)までに情報を開示しなければならない。ただし、一定期間の年数については、近年の情報通信の急激な進展等を考慮し、本研究会の最終報告書の取りまとめまでに再度検討する。
|
 |
接続事業者は、原則として、加入者回線が光ファイバ化された場合は、DSLサービスの継続が不可能となることを前提として事業展開を図ることになるが、DSLサービス開始前に光ファイバ化後の事業計画についても検討しておく必要がある。また、郵政省は光ファイバ化後におけるNTT地域会社の対応の在り方についても今後早急に検討する必要がある。 |
(4) 試験的なDSLサービスの提供にあたっての公平性の確保
| 接続事業者がMDF等での試験的な接続によりDSLサービスを実施する場合において、NTT地域会社が接続事業者に対して故意に芯線の収容環境を悪化させる等の公平性に欠く対応があってはならない。こうした観点から接続事業者が公平性の確保の状況を確認する方策について、研究会の最終報告書の取りまとめまでに検討を行う必要がある。 |
(5) 接続事業者のNTT地域会社の加入者交換局舎内への立入りについて
| 接続事業者が、コロケーションしているDSL装置の点検や、試験サービスの実施状況等を確認するために、NTT地域会社の加入者交換局舎内への立入りを要望する場合は、NTT地域会社は局舎内の他の装置等に対するセキュリティを確保しつつ速やかにこの要望に応じなければならない。 |