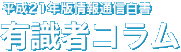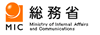佐々木俊尚フリージャーナリスト
今年の情報通信白書は、第2章第2節で情報通信の基盤、利活用、安心の3つの面について、日本やアメリカを含む7か国間の国際比較をしている。
日本のITはアメリカと比べて遅れているのか、それとも進んでいるのか。これはIT業界では以前からホットな議論となっていて、意見はさまざまに分かれている。進んでいる部分は、明確だ。まず第1に、ブロードバンドの普及率。国内のブロードバンド回線契約数は、平成19年末で2830万に達し、このうちFTTHの割合は40%を越えている。これは他のOECD諸国と比べても圧倒的で、インフラ面ではまさにブロードバンド大国の名にふさわしい。
携帯電話経由でのインターネット利用も同様だ。日本で販売されている携帯電話機の大半はインターネットのデータ通信が可能で、データ通信の定額料金制度も普及している。アメリカではiPhoneのようなスマートフォンが出てくるまでは携帯電話によるネット利用はあまり一般的ではなく、ビジネスパースンの間にBlackBerry端末が普及していた程度だった。多くの携帯電話機でのデータ通信といえばSMS(ショートメッセージ)が主流で、ウェブサイトを携帯電話で見るという文化自体がこれまではあまり普及していなかったのである。
一方、遅れている部分もはっきりしている。たとえば第3章第2節で分析されている医療分野。アメリカではEHR(Electronic Health Record)やPHR(Personal Health Record)など、カルテや投薬記録、日々の健康状態などの総括的な医療情報をITによって一元化し、医療機関と個人をネットワーク化していこうというサービスがすでに実用化され始めている。これに対して日本では、電子カルテでさえもまだ普及していない。
これは教育や食、福祉、電子自治体などの分野でも同じような状況で、要するに日本ではITのインフラは整ってはいるものの、それがわれわれの生きる社会のさまざまな分野にまで横展開できていないというのが現状なのである。
この現状を評して「日本はITのインフラは普及しているが、上位レイヤーであるサービス分野での利活用がまったく進んでいない」と批判する人もいるが、しかしその批判は実は当たっていない。
なぜなら日本ではたしかにITが生活の各方面に横展開できていないのは事実なのだが、ソーシャルメディアやデジタルコンテンツなどの先鋭的なウェブ分野に関しては、圧倒的な進化を遂げつつあるからだ。
たとえば動画共有サイト「ニコニコ動画」では、オリジナルの動画や楽曲をユーザー同士がお互いにコラボレーションさせて次々と新しいコンテンツが生み出されている。また携帯サイトの「魔法のiらんど」では、携帯電話によって書かれ、携帯電話によって読まれる「ケータイ小説」文化が勃興している。日本語ブログは書かれている数でいえば英語圏を凌駕するほどに多く、日本のいにしえからの日記文化がネット上で花ひらいている。これらは一般社会からはまだあまり認知されていないが、しかしインターネット上では世界的に注目を集め、クールジャパンの文化の一端として世界の人々を惹きつけている。
ITのカバーする側面はハードウェアから通信インフラ、サービスアプリケーション、コンテンツまで幅広い。日本のITは社会に全面展開して普及するという段階にまでは残念ながら進んでいないが、しかしこれまで述べてきたように非常に多層構造的な複雑な様相を見せており、今後の進化が非常に楽しみともいえる。何もかもが、まだこれからなのだ。
経歴
1961年生まれ。早稲田大学政経学部中退。毎日新聞記者、月刊アスキー編集部を経てフリージャーナリスト。主な著書に「グーグル」「ネット未来地図」(以上文春新書)「フラット革命」「インフォコモンズ」(以上講談社)などがある。内閣官房IT戦略の今後の在り方に関する専門調査会委員、経済産業省情報大航海プロジェクト制度検討WG委員。