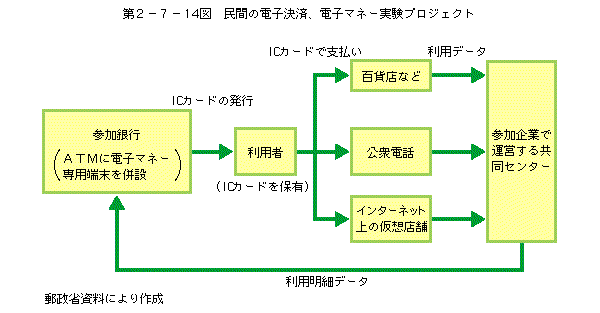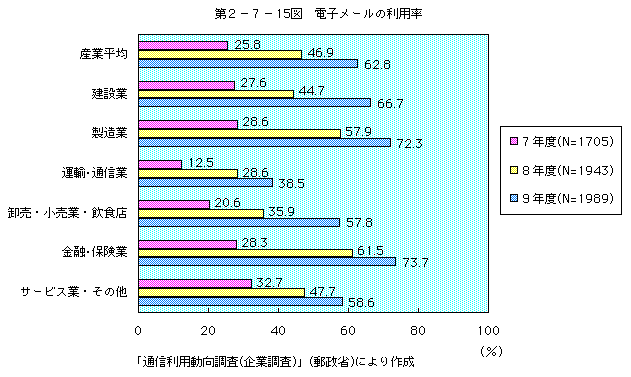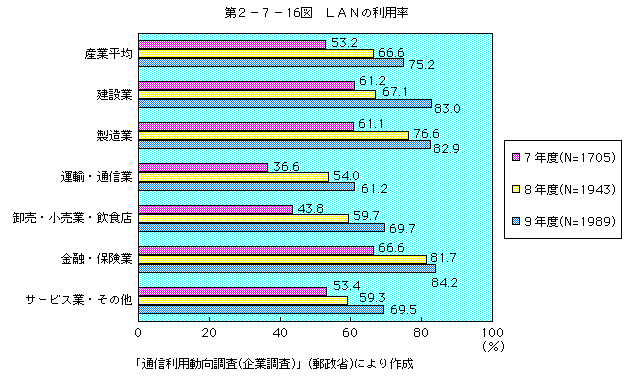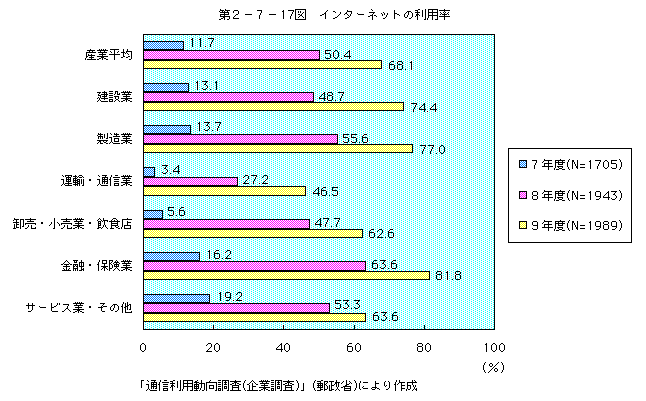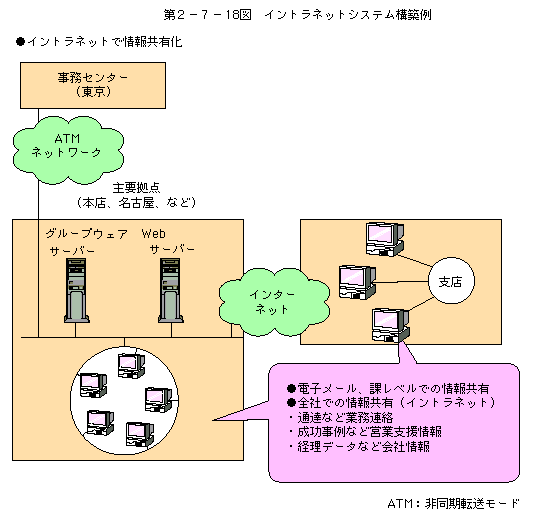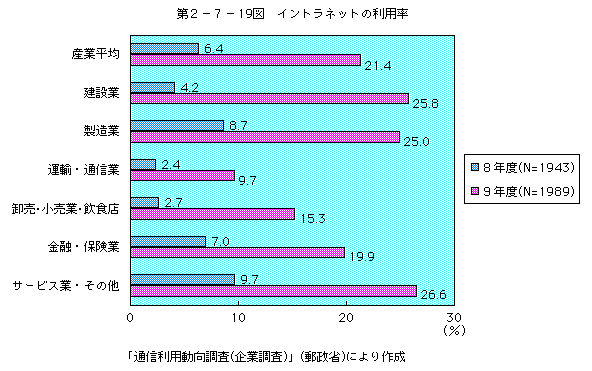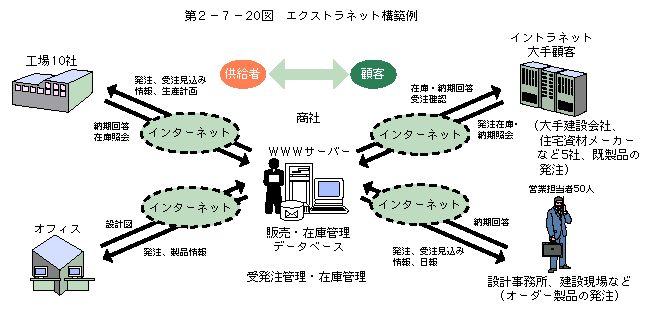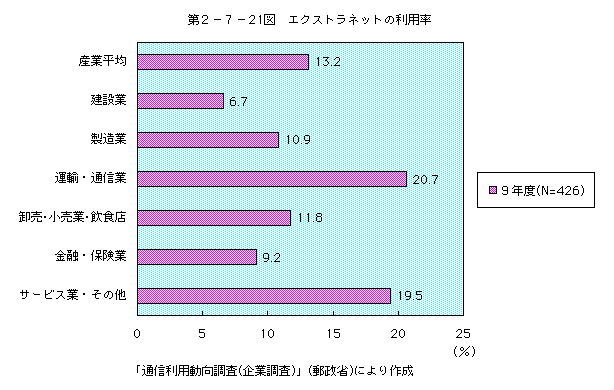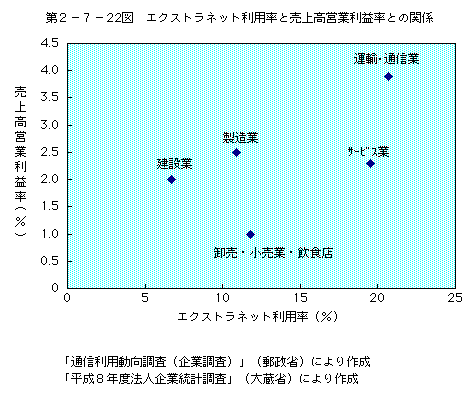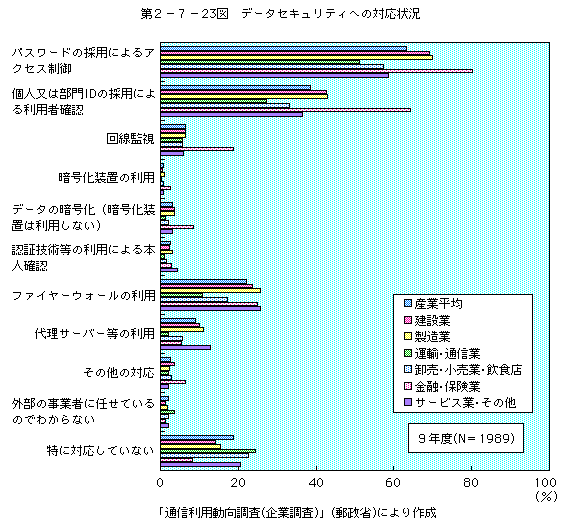第2章 平成9年情報通信の現況
第7節 情報通信と社会経済構造の変革
- 産業の情報化
(1) サイバービジネスの現状と課題
サイバースペースを利用した電子商取引に代表されるサイバービジネスは、インターネットの更なる普及により着実にその規模を拡大させている。
ここでは、サイバービジネスを「情報通信ネットワーク内のビジネス空間・社会的空間を提供し、その中で一般消費者、製造業者、サービス業者、各種団体等の取引(商品の受発注、決済等)・相互交流を実現するネットワークビジネス」(電気通信審議会答申、8年2月)と定義し、郵政省の調査(注17)を基に、サイバービジネスの現状と展望について分析する。
ア 市場規模及び店舗数の推移
我が国におけるサイバービジネスの9年度(注18)の市場規模は、約818億円である。
8年度の市場規模は285億円であり、1年間で約2.87倍の成長を遂げている(第2−7−1図参照)。なお、郵政省で行った「インターネットビジネスに関する研究会」(注19)報告によると、サイバービジネスの市場規模は、2005年には1.1兆円に達するものと予想される。
サイバー店舗数の推移を見ると、10年2月段階で6,560店舗(対8年度末比94.8%増)と、引き続き高い伸びを示している(第2−7−2図参照)。
また、米国におけるサイバービジネスの市場規模は、9年度には1兆2,525億円となり、引き続き大幅な拡大を続けている(第2−7−1図参照)。
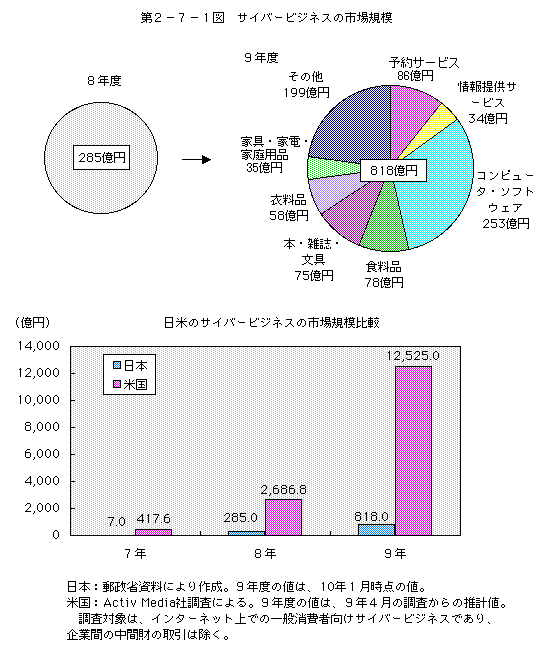
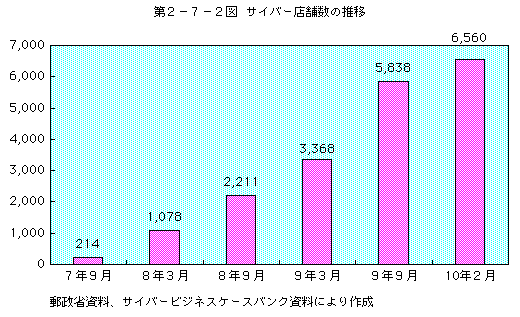
イ 経営動向
サイバービジネス事業者の売上高の推移を見ると、全体の半数近く(45.9%)の事業者で、前年と比較して売上が増加し、17.2%の事業者においては、前年の倍以上に売上が伸長した。一方、前年と比較して売上が減少した事業者の割合は8.6%にとどまり、サイバービジネス事業者の売上は着実に伸びていることが分かる。
また、開業後1年以上経過した事業者の収支状況について見ると、前年と比べ、累積損益ベース、単年度損益ベースともに、黒字を達成している事業者の比率が向上しており、サイバービジネスの経営環境は確実に好転していることが分かる(第2−7−3図参照)。
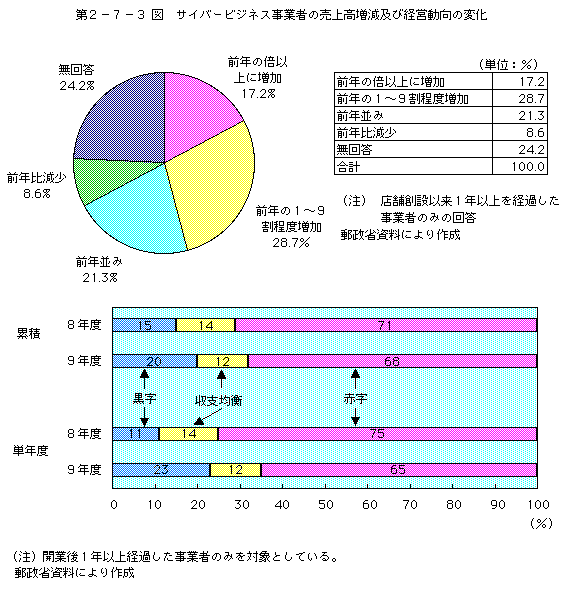
ウ 販売商品・サービスの動向
サイバー店舗での販売商品・サービスの動向について見ると、「コンピュータ・ソフトウェア」が253億円と最も大きく、次いで「予約サービス」(86億円)、「食料品」(78億円)等となっている(第2−7−1図参照)。
また、その取り扱っている商品品目の動向について見ると、前年と比較して、構成に大きな変化は見られないものの、「美術・音楽」が増加しているほか、「乗車券・ホテル・各種チケット」等の予約サービスが4%にのぼっている(第2−7−4図参照)。
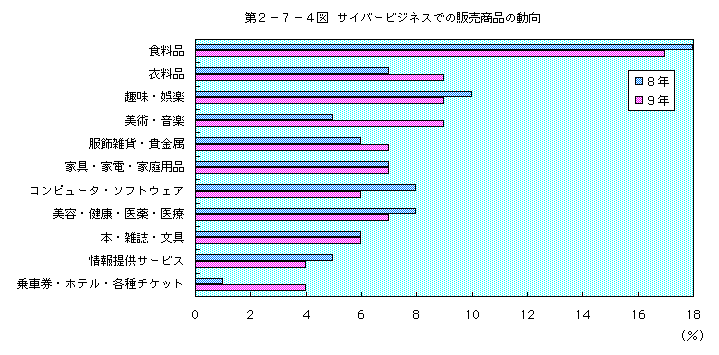
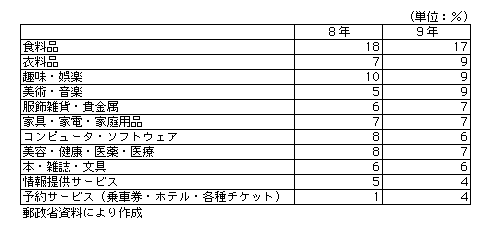
エ 顧客の変化
サイバービジネス事業者から見た、ここ一年間における顧客層の変化について、その内訳を見ると、「女性顧客が増加」(14.7%)を挙げる割合が高く、「年配の顧客層が増加」(4.1%)も挙げられている。
このことから、従来サイバービジネスにはあまりなじみのなかったと考えられる層にも顧客層が拡大し、インターネットを利用したショッピングがより一般的になりつつあることが分かる(第2−7−5図参照)。
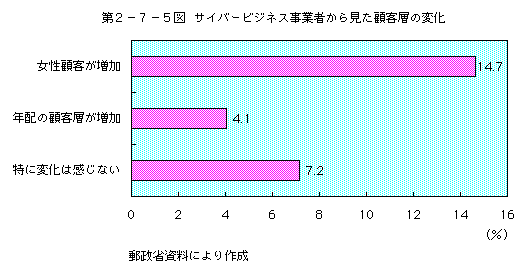
オ 決済方法
サイバービジネス事業者が採用している決済方法について見ると、「銀行振込」、「郵便振替」及び「代金引換」が主流で、「クレジットカード決済」は相対的に低くなっているが、利用者が実際に利用している決済手段としては「クレジットカード決済」が最も多く51.1%に達している(注20)。
このことから、クレジットカード決済については、利用者の利用意向が高いにもかかわらず、事業者側の導入が相対的に遅れていることが分かる(第2−7−6図参照)。
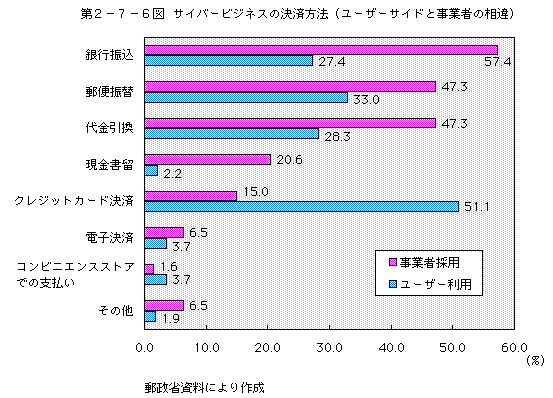
カ サイバービジネス事業者の経営努力とその効果
サイバービジネス事業者が事業を行うに当たって実施している努力について調査すると、「注文時に都度受注確認を行う」(60.0%)、「分かりやすい商品情報を提供する」(58.1%)等が上位に挙げられており、事業者は、注文時の顧客とのトラブルの防止や品ぞろえ、きめ細やかな商品情報の提供等を重視していることが分かる(第2−7−7図参照)。
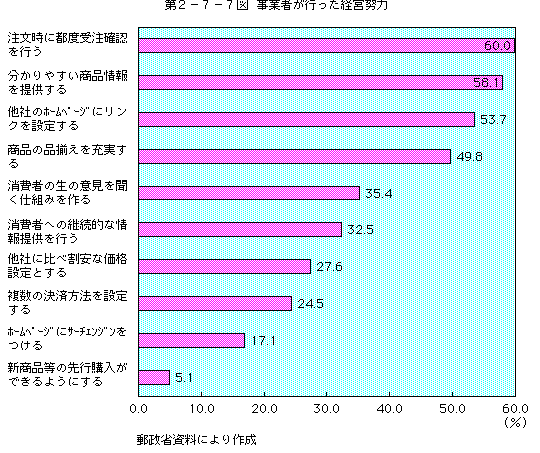
また、経営努力とその効果について、実施項目別に見ると、「新商品等の先行購入ができるようにする」、「他社に比べ割安な価格設定にする」、「複数の決済手段を設定する」、「消費者の生の意見を聞く仕組みを作る」といった項目を実施した事業者において、売上が前年の倍以上に増加していることが多く、顧客の利便性を重視した経営努力を行った事業者ほど、売上が伸長していることが分かる(第2−7−8図参照)。
特に、「消費者の生の意見を聞く仕組みを作る」という経営努力は、インターネットの特性を生かした方法といえる。
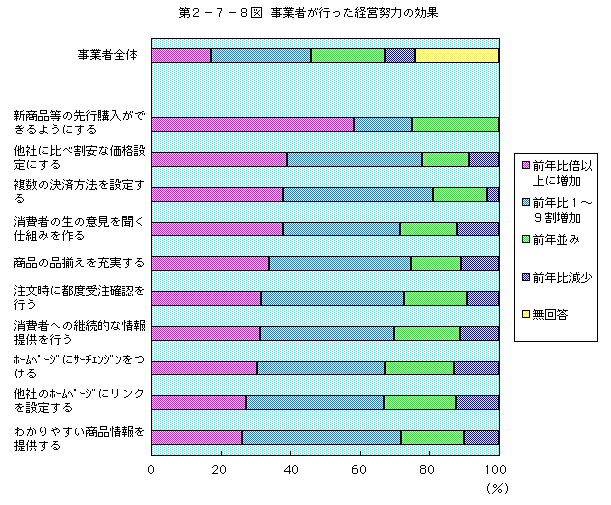
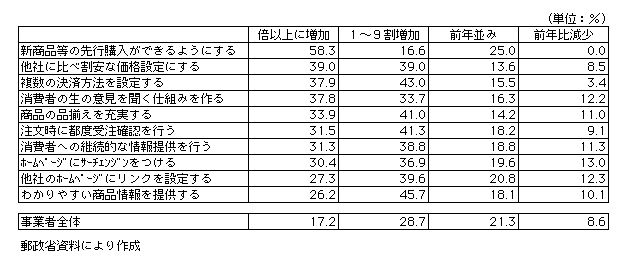
キ サイバービジネスの普及条件
サイバービジネス事業者は、今後、サイバービジネスを普及させるために必要と考えている条件について、「(消費者が)パソコンやインターネットを使いこなすことができるようになれば」(27.0%)、「通信料金が安くなれば」(20.1%)及び「信頼できる決済手段が利用できれば」(10.3%)を上位に挙げている。一方、消費者は、「信頼できる決済手段が利用できれば」、「プライバシーが漏れることがなければ」を上位に挙げており、両者の間での意識の差が顕著である(第2−7−9図参照)。
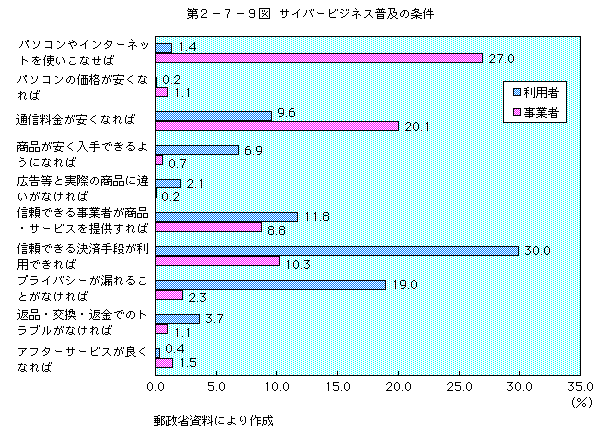
ク 行政への要望
サイバービジネス事業者が行政に望むことについて見ると、「ネットワーク利用料金の低廉化の推進」(57.6%)及び「電子現金等新たな決済手段の開発」(51.9%)を挙げる割合が高くなっている(第2−7−10図参照)。
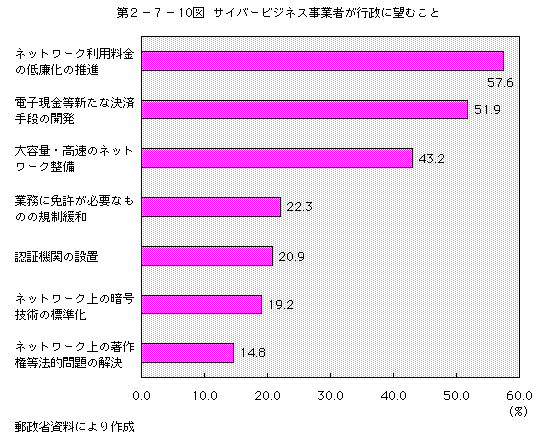
(2) インターネット関連市場の現状
ア インターネット関連市場の拡大
インターネットの発展は、それを利用したサイバービジネスだけでなく、端末、サーバー、プロバイダ接続サービス等の周辺分野の市場拡大ももたらしている。また、将来は、テレビ等の家庭用情報端末でもインターネットが利用できるようになり、インターネットを利用したサイバービジネスが大きく伸長することが期待される。
ここでは、インターネットに使用される関連機器や、通信サービス、決済・認証サービス等の関連サービスまで含んだ広い概念を「インターネット関連市場」と定義(注21)し、その市場規模の現状について述べる。
イ インターネット関連市場の市場規模
郵政省で行った「インターネットビジネスに関する研究会」によれば、インターネット関連市場の市場規模は、9年度には2.7兆円に達している。その内訳を見ると、関連機器の市場が5,440億円、関連サービスの市場が2兆1,257億円となっている。
(3) 電子決済、電子マネーの実態
ここ数年のインターネットの普及と技術の進展により、世界中で電子決済、電子マネーに関連した実験プロジェクトやビジネスが始まっている。
ア 電子決済、電子マネー関連プロジェクトの類型
現金の支払いを電子的に行う「電子決済」は、「小切手方式」、「クレジット方式」、「デビット方式」に分類され、暗号技術を活用して現金発行者の署名を付けた金額データである「電子マネー」は、「ICカード型」、「ネットワーク型」に分類される(第2−7−11表参照)。
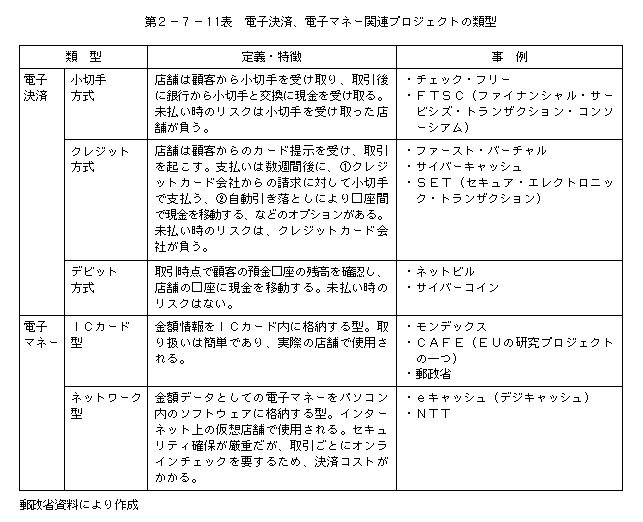
イ 我が国の電子決済、電子マネー関連プロジェクト
現在、いわゆる電子マネーと呼ばれる実験にはいくつかのプロジェクトが存在しているが、今後実施される実験の中には、ICカードに「匿名性」、「転々流通性」等現金の保有する機能を持たせたものも出てくるのではないかと考えられる。
(ア) 郵便貯金ICカードによる電子財布サービス実験

郵便貯金ICカードによる電子財布サービス実験
|
郵政省は、10年2月から10年度にかけて、大宮市(埼玉県)及びJR大宮駅周辺地域において、郵便貯金磁気カードのICカードへの移行に向け、その利用動向や技術条件等を把握するための実験を行っている。
この実験では、ICカード7万枚を発行する予定であり、現行の郵便貯金キャッシュサービス(預入、払戻し等)の他、スーパー、コンビニ、百貨店等において電子財布サービス(キャッシュレスショピング等)が提供される(写真参照)。
電子財布サービスの利用方法は、 ATM、移替端末機(約1,000台をモニターの家庭に配備)等により通常貯金の一部を保留データとしてICカードに記録、
ATM、移替端末機(約1,000台をモニターの家庭に配備)等により通常貯金の一部を保留データとしてICカードに記録、 ICカードの保留データの範囲内でのキャッシュレスショッピング等、
ICカードの保留データの範囲内でのキャッシュレスショッピング等、 代金は預金者の通常貯金口座の保留額から自動払込みにより後日引落し、となっている(第2−7−12図参照)。
代金は預金者の通常貯金口座の保留額から自動払込みにより後日引落し、となっている(第2−7−12図参照)。
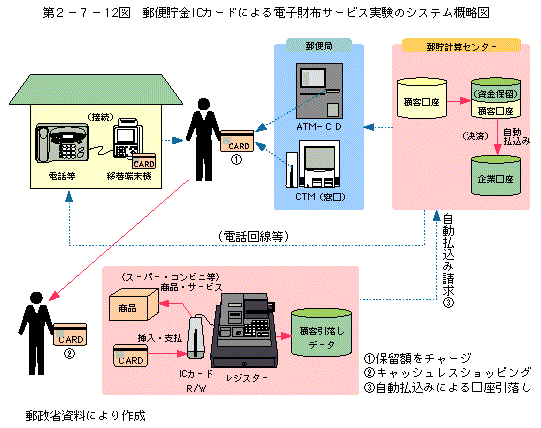
(イ) サイバービジネス協議会の「インターネットキャッシュ」の提供
郵政省が支援しているサイバービジネス協議会は、10年9月から、インターネット上で現金と同様の機能を実現した電子マネー「インターネットキャッシュ」の提供を開始する。
現金同様の「転々流通性」や「匿名性」を実現しつつ、インターネット上のバーチャルモールでの安全な電子決済が可能となる。
「インターネットキャッシュ」の特徴は、NTTが開発した電子マネーを基盤として、消費者モニター、モール及び金融機関をインターネットで接続し、次の機能を実現する。
 消費者モニター間の譲渡「転々流通性」
消費者モニター間の譲渡「転々流通性」
 現金同様の匿名性
現金同様の匿名性
 二重使用チェックを可能とする高度なセキュリティ
二重使用チェックを可能とする高度なセキュリティ
 複数金融機関が発行し、共通の利用が可能
複数金融機関が発行し、共通の利用が可能
 電子マネーを使用しない場合は、自分の金融機関口座への入金が可能
電子マネーを使用しない場合は、自分の金融機関口座への入金が可能
 24時間決済可能な環境
24時間決済可能な環境
また、「インターネットキャッシュ」は、一定地域内の店舗においてICカードを提示して取引の決済を行う地域限定型の電子マネー・プロジェクトと異なり、インターネットを通じて全国に展開することができ、インターネットの利用者であれば、消費者モニターや商店として参加可能である。
消費者モニターは、参加企業の社員中心に当初1,000人、11年度から一般公募で1万人を予定している(第2−7−13図参照)。
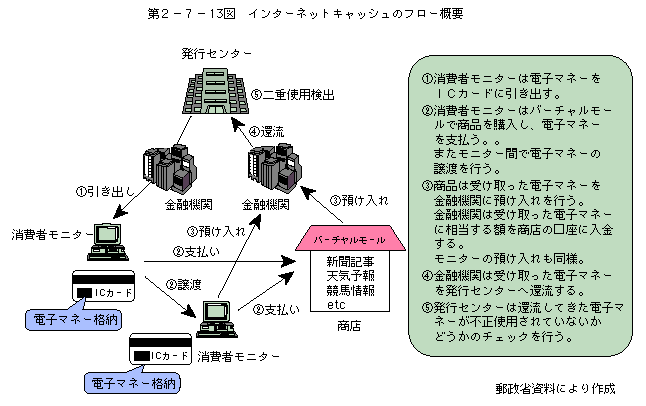
(ウ) 民間の電子決済、電子マネー実験プロジェクト
都銀等は、 インターネット上のバーチャルモールでの電子マネー及び決済実験(11年2月〜)、
インターネット上のバーチャルモールでの電子マネー及び決済実験(11年2月〜)、 新宿区(東京都)の百貨店やコンビニエンスストアでの電子財布実験(11年2月〜)を開始する。
新宿区(東京都)の百貨店やコンビニエンスストアでの電子財布実験(11年2月〜)を開始する。
バーチャルモール実験は、自宅のパソコンに接続した読取機にICカードを差し込むことにより、即座に決済を行うことができるものであるが、転々流通性は確保されていない。電子財布実験は、新宿区内の百貨店等でICカードに電子マネーを蓄積して使用するものであり、銀行で入金する。なお、ICカードは、バーチャルモール実験・電子財布実験で共用できることとなっている(第2−7−14図参照)。
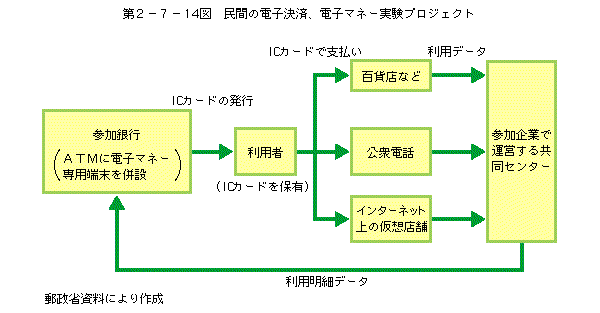
ウ 海外の電子決済、電子マネー関連プロジェクト
海外においても電子決済、電子マネーの実験プロジェクトが行われており、こうした中で、民間企業を中心に電子決済、電子マネー分野におけるデファクト・スタンダード(事実上の標準)の確立を目指そうという動きが現れている。
小切手方式は、既存の決済の仕組みにネットワークを追加した形式で、それほど仕組みや技術も複雑でないサービス(チェックフリー)については、実用段階に入っている。
クレジット方式では、クレジット業界で圧倒的なシェアを誇る大手クレジット会社が、複数の銀行や店舗が組織的に参加できる規格(SET)を発表し、クレジット方式の世界標準となりつつある。
デビット方式では、米国のネットビル及びサイバーコインが有力であり、インターネット上のコンテント販売等、少額決済への利用が期待されている。
また、電子マネーについては、自社方式を国際的に拡大しようとする動きが見られる。ICカード型方式では、英国企業が、自国内で行っているのと同様の実験を香港で行うほか、海外企業に対してフランチャイズ権の提供を行っている。米国のクレジットカード会社でも、日本を含めた海外での実証実験を開始している。一方、ネットワーク型方式では、米国の銀行が行っているほか、オランダ企業が日本を含む海外企業との提携を進めている。
(4) 企業の情報通信利用動向
近年、企業における情報化が急速に進んでおり、企業にとって情報通信の有効活用が不可欠なものとなっている。ここでは、企業の情報化の動向を、郵政省が行った「平成9年度通信利用動向調査(企業調査)」(9年10月)により分析する。
ア 電子メールの利用状況
電子メール利用状況を見ると、産業平均で約6割の企業が電子メールを利用しており、8年度と比較して15.9ポイントの大幅な上昇となった。今後利用予定のある企業まで含めると、約8割の企業での利用が見込まれている。業態別に見ると、金融・保険業が最も高く、製造業、建設業と続いている(第2−7−15図参照)。
また、電子メールの通信相手を社内と社外に分けて見ると、電子メールを社内外で利用している企業が、自社内に限った利用をしている企業の割合を上回り、約7割となった。このことは、電子メールが内部における情報伝達手段から発展し、外部に対する情報伝達手段としても企業に浸透してきたといえる。
なお、電子メール利用上の不満点として、約3割の企業が「相手先に届いたか不安」を挙げている。
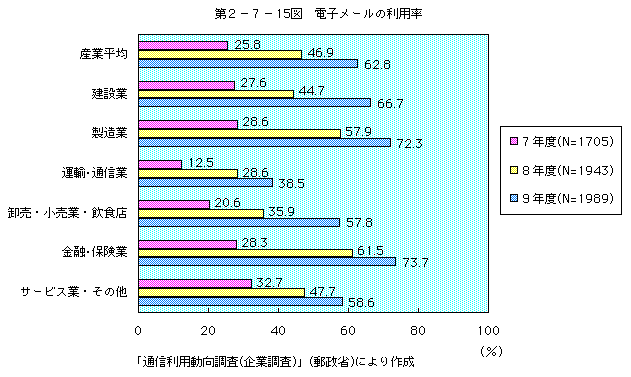
イ LANの利用状況
産業平均で約4分の3の企業がLANを既に利用しており、8年度と比較し8.6ポイントの上昇となった。今後利用予定のある企業まで含めると、約8割の企業での利用が見込まれている。業態別で見ると、金融・保険業が最も高く、製造業、建設業と続いている(第2−7−16図参照)。
なお、LAN構築等の問題点として、約6割の企業が「運用・管理者の人材が不足」を挙げている。
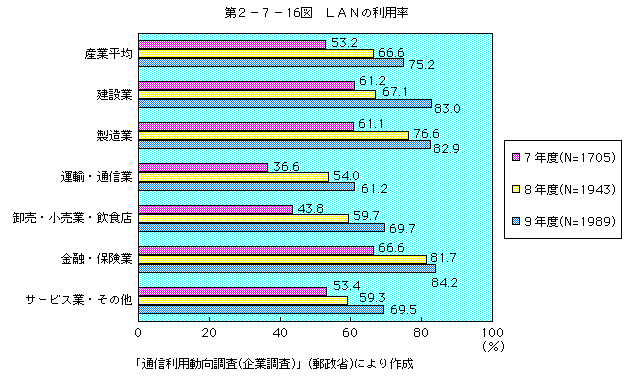
ウ インターネットの利用状況
産業平均で約7割の企業がインターネットを利用しており、8年度と比較して17.7ポイントの大幅な上昇となった(第2−7−17図参照)。今後利用予定のある企業まで含めると、約4分の3の企業で利用が見込まれている。業態別で見ると、金融・保険業が最も高く、製造業、建設業と続いている。
なお、インターネット利用上の不満点では、「コンピュータウィルスの感染が心配である」ことを挙げている企業が約5割と最も多かった。
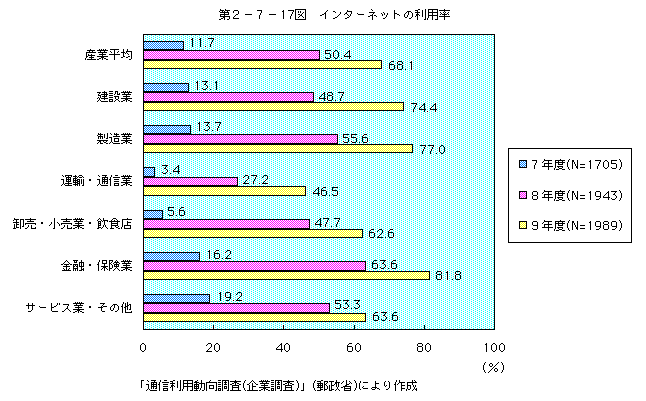
エ イントラネットの利用状況
(ア) システムの仕組みと特徴
インターネットを使った社内網であり、インターネットの新しい活用法である(第2−7−18図参照)。
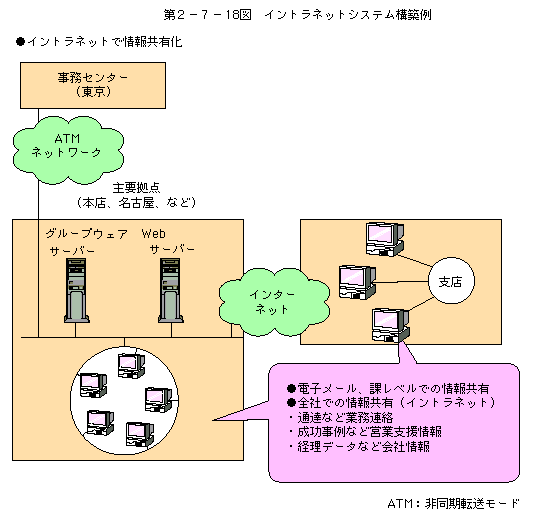
(イ) 産業別利用状況の分析
イントラネットの利用状況について見ると、産業平均で約2割の企業がイントラネットを利用しており、今後利用予定のある企業まで含めると、約4割の企業で利用が見込まれている。業態別で見ると、サービス業・その他が最も高く、建設業、製造業と続いている(第2−7−19図参照)。
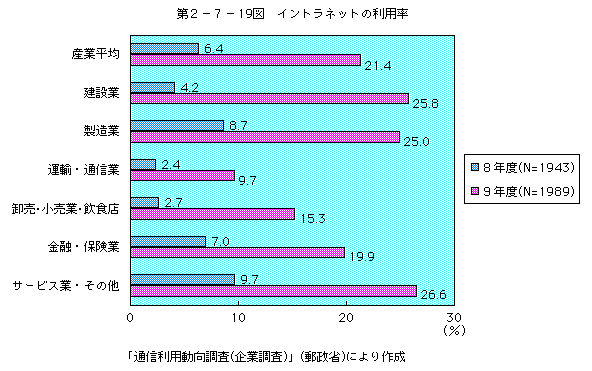
オ エクストラネットの利用状況
(ア) システムの仕組みと特徴
エクストラネットとは、異なる企業のイントラネットを、インターネットで結んだネットワークである。企業同士が、エクストラネットを利用して、顧客情報や販売情報を共有することで、コストの削減、納期の短縮、営業力の強化、顧客サービスの向上が図れ、また、比較的安価にシステムを構築でき、柔軟に連携相手を選択できるというメリットもある(第2−7−20図参照)。
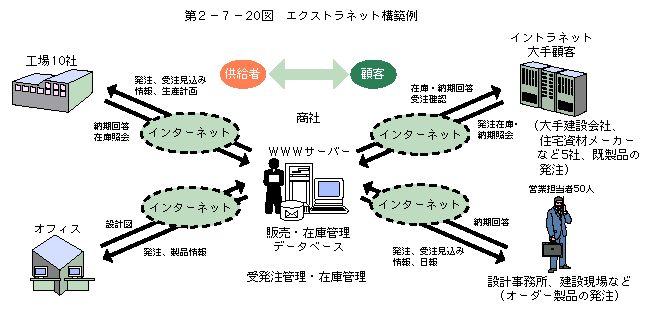
(イ)産業別利用状況の分析
エクストラネット利用状況について見ると、イントラネットを利用している企業のうちの、産業平均で約13%の企業がエクストラネットを利用しており、今後利用の予定がある企業と合わせると4割以上の企業で利用が見込まれている。業態別で見ると、イントラネット利用が最も低かった運輸・通信業が最も高くなっており、サービス業・その他、卸売・小売業・飲食店と続いている(第2−7−21図参照)。
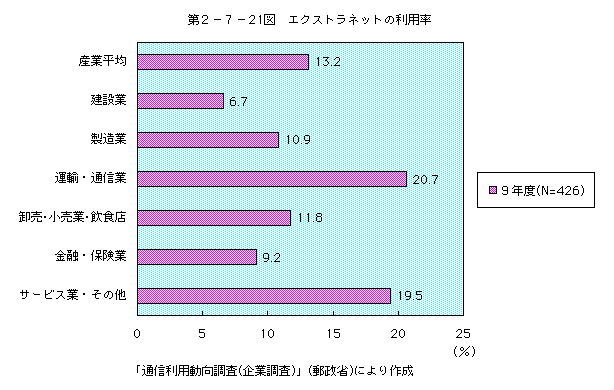
(ウ) 情報化と経営との関係
産業別のエクストラネット利用率と売上高営業利益率との関係を見ると、エクストラネット利用率が高い産業ほど、売上高営業利益率も高い傾向が見られる(第2−7−22図参照)。
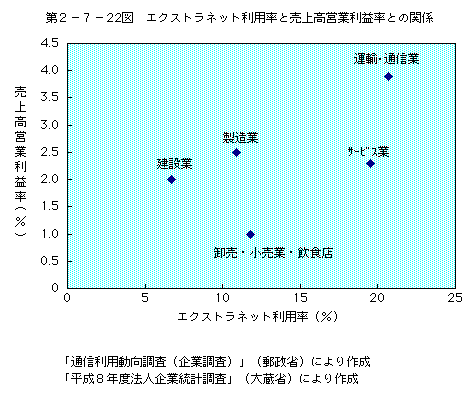
カ データセキュリティへの対応状況
ネットワーク上のデータセキュリティ対策の項目について見ると、全体として、「パスワードの採用によるアクセス制御」が63.5%と最も多く、次に「個人又は部門IDの採用による利用者確認」が38.9%で続いている。
産業別に見ると、金融・保険業が、最も「パスワードの採用によるアクセス制御」及び「個人又は部門IDの採用による利用者確認」に力を注いでいる。逆に運輸・通信業や卸売・小売業・飲食店では「特に対応していない」が多い(第2−7−23図参照)。
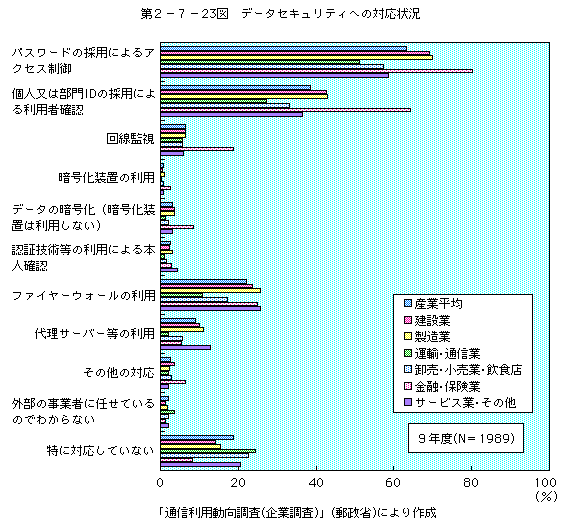


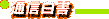



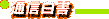
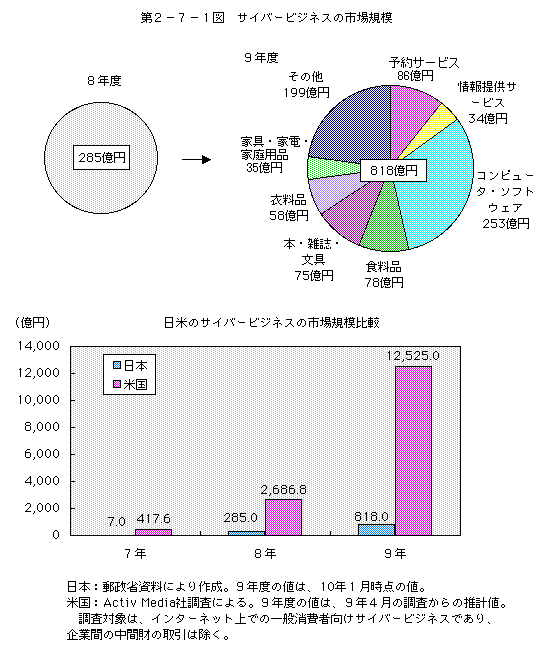
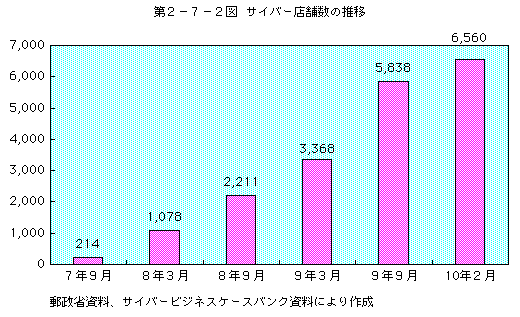
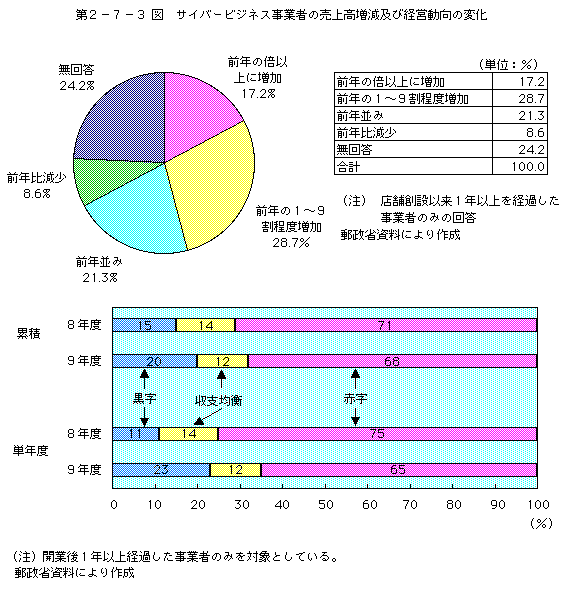
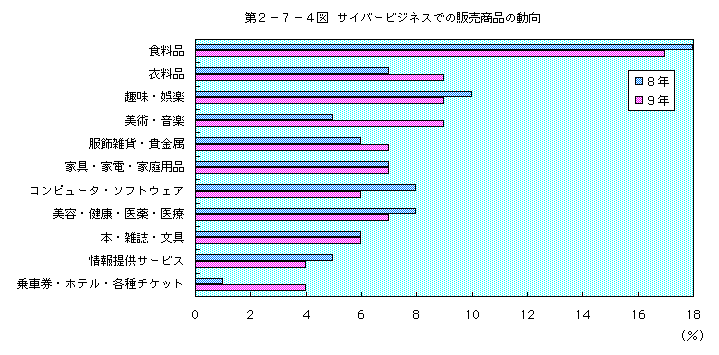
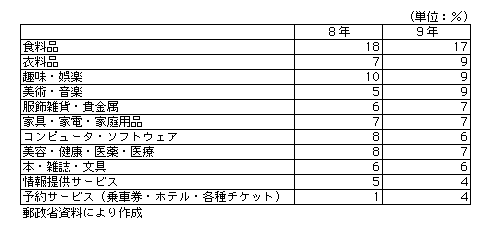
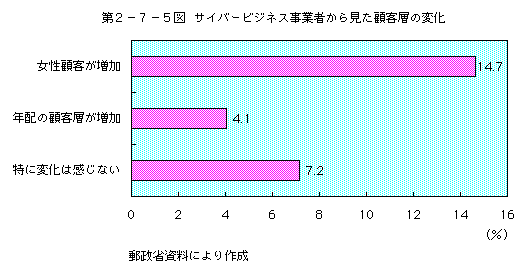
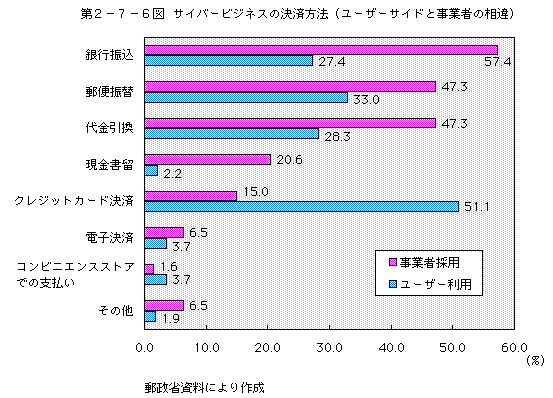
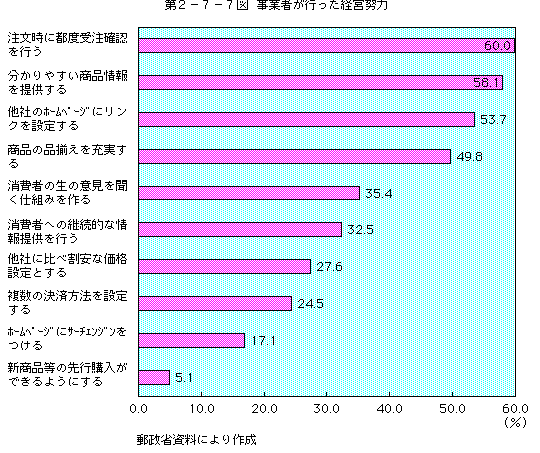
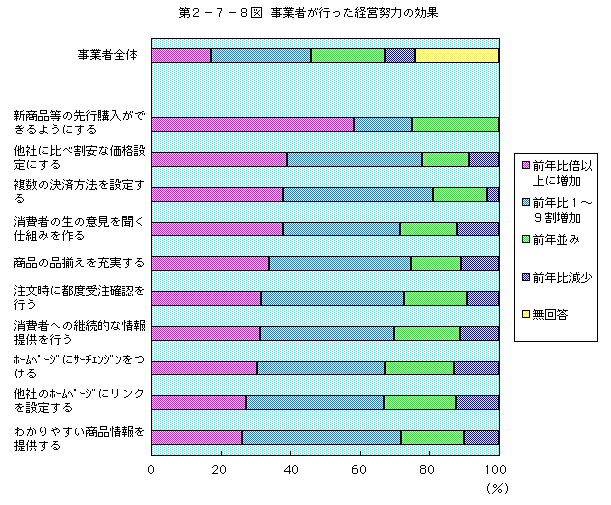
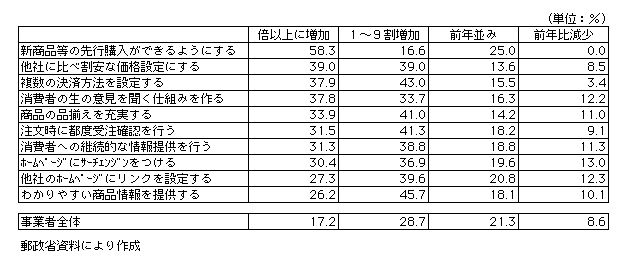
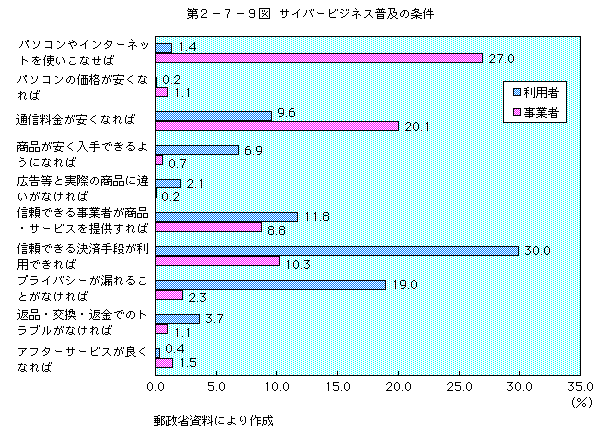
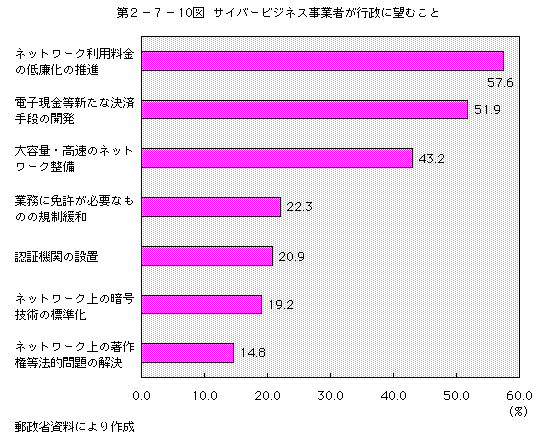
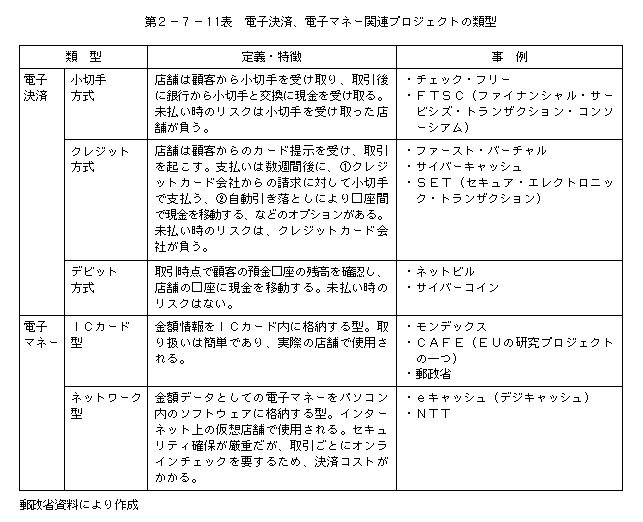

 ATM、移替端末機(約1,000台をモニターの家庭に配備)等により通常貯金の一部を保留データとしてICカードに記録、
ATM、移替端末機(約1,000台をモニターの家庭に配備)等により通常貯金の一部を保留データとしてICカードに記録、 ICカードの保留データの範囲内でのキャッシュレスショッピング等、
ICカードの保留データの範囲内でのキャッシュレスショッピング等、 代金は預金者の通常貯金口座の保留額から自動払込みにより後日引落し、となっている(第2−7−12図参照)。
代金は預金者の通常貯金口座の保留額から自動払込みにより後日引落し、となっている(第2−7−12図参照)。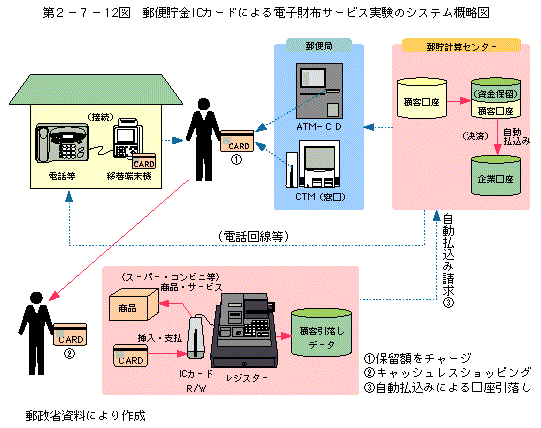
消費者モニター間の譲渡「転々流通性」
現金同様の匿名性
二重使用チェックを可能とする高度なセキュリティ
複数金融機関が発行し、共通の利用が可能
電子マネーを使用しない場合は、自分の金融機関口座への入金が可能
24時間決済可能な環境
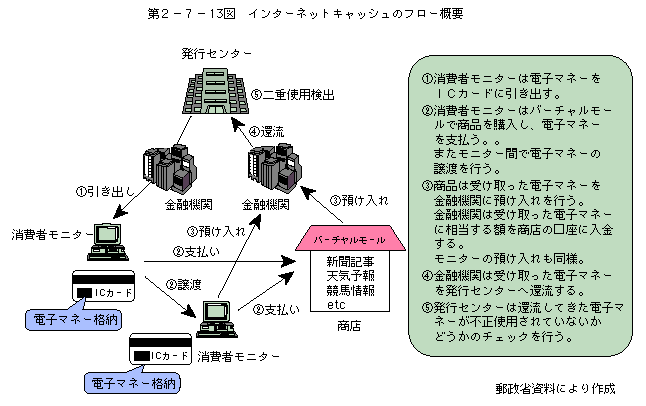
 インターネット上のバーチャルモールでの電子マネー及び決済実験(11年2月〜)、
インターネット上のバーチャルモールでの電子マネー及び決済実験(11年2月〜)、 新宿区(東京都)の百貨店やコンビニエンスストアでの電子財布実験(11年2月〜)を開始する。
新宿区(東京都)の百貨店やコンビニエンスストアでの電子財布実験(11年2月〜)を開始する。