





第3章 郵便局ビジョンI:情報の拠点
「情報」が鍵となる社会においては、行政の効率化、国民の利便性の向上を図 るため、内外のネットワークの融合を促進するとともに、情報の地域間・個人間 格差を是正することが課題である。郵便局は、そのネットワークの開放や、どこ でも誰でも簡易に利用できる基礎的通信サービスの提供を通じて、「情報の拠点」 としての役割を果たしていくことが期待される。 1 ネットワーク化の推進 ネットワークの融合は、既存のネットワークを活用して外部情報へのアクセ スが容易になるなど、ネットワークの規模を実質的に拡大する効果がある。こ うした効果は、ネットワークの融合が進むほど、経済産業や国民生活に対して 大きな効果をもたらす。インターネットの例で言えば、利用者は誰でも、地理 的な制約なしに、世界中からの情報、サービスへのアクセスが可能となってい る。 ネットワークを融合する場合、ネットワークへのアクセスポイントが国民に 身近であるほど、国民の利便性は向上する。郵便局は、国民にとって最も身近 な存在であるとともに、情報、カネ、モノのネットワークを統合している。 こうした点を考慮すれば、郵便局ネットワークを開放し、他のネットワーク との融合を可能とすることは、情報、サービス、商品へのアクセスを容易にし、 国民の利便性を向上させるものと考えられる。 特に、高齢者等、情報端末の操作に習熟していない「情報弱者」やネットワ ークの進展が遅くなる過疎地住民等にとって、身近な窓口であり、職員による 操作支援が可能な「郵便局」の役割は大きい。 (1)行政ネットワークへの開放 ア 行政改革の要請 行政改革の本旨は、「活力ある福祉社会の建設と国際社会に対する積極 的貢献」を目指し、「21世紀に向けて時代の課題を担いうる行政、すな わち変化への対応力に富み、総合性と整合性が確保され、簡素にして効率 的で、かつ国民の信頼が得られる行政」を実現することにある(第2次臨 調最終答申)。 諸外国においても、行政の効率化を進める行政改革が行われつつあるが、 その中心的課題は、行政コストの削減を図りつつ、政府と国民との関係を 改善することにある。こうした観点から、情報化のメリットを活用して国 民の利便性を向上し、併せて行政の効率化を推進するため、各国において 各種行政手続のネットワーク化に向けた取組みが行われている(図6)。 (ア)米国のWINGS構想 米国においては、インターネットを活用して行政サービスのネットワ ーク(「WINGS」〔The Web Interactive Network of Government Services〕)を構築し、転居や職業紹介等の日常生活に必要な手続を1 か所で処理できるようにする取組みが進行している。 このWINGSの構築は、クリントン政権による行政改革の一環とし て1995年に提唱された「全米キオスク・ネットワーク構想」の中で 進められている。同構想では、[1]単なる行政コストの削減のみなら ずサービスの向上が最大の目的であること、[2]ユニバーサルな、か つ利用しやすい情報スーパーハイウェー(*9)を速やかに構築するため には、双方向キオスクが必要であること等の原則の下に、「省庁間キオ スク委員会」が企画・立案し、米国郵便サービス(USPS)が取りま とめを行っている。 WINGSには、誰でもどこでもユニバーサルにアクセスできるよう、 家庭のパソコンのほか、全米4万局の郵便局ロビー等に公共キオスクを 設置することとしている。USPSでは、現在試行実験を実施している。 (イ)マレーシアのPSN マレーシアにおいては、現在、政府の各省庁と全国に設置された郵便 局(620局)をオンラインネットワーク(「PSN」(Public Services Network))で結び、様々な行政手続サービス(例:運転免許証の更新手 続、事業所登録証の更新手続、道路税の更新手続等)が郵便局窓口で提 供されている。 PSNのメリットは、[1]関連省庁にとって、多数の出先機関を新 たに設置することが不要であること、[2]住民にとって、行政手続の アクセス場所が増大すること、とされている。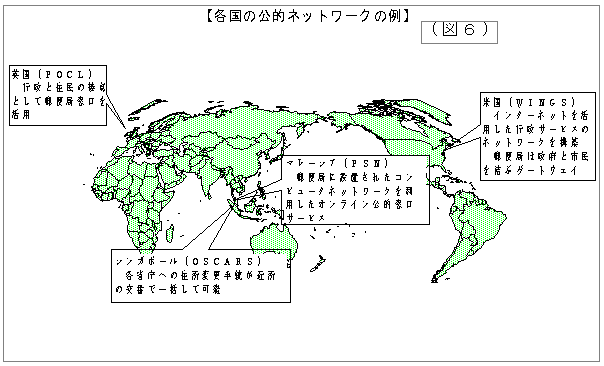 (出所)郵政省資料 イ 国民の利便性向上 行政手続は、国民生活においても必要なものであるが、現行の行政手続 は国民にとって煩雑な面がある。例えば、役所に申請をしようとする場合、 申請の窓口がどの役所の何という課か、一般には分かりにくい。また、転 居時のように、1つの行為について複数の役所へ複数の申請を行わなけれ ばならないこともある。 これに対して、一つの窓口で一括して申請手続等を行うことが可能にな れば、国民の負担は大幅に軽減される。これがワンストップ行政サービス である。郵政研究所が実施した住民意識調査の結果では、公的窓口が分散 している現状に対して、不便と感じる人の割合は8割近い。 最も身近な郵便局窓口においてワンストップ行政サービスが実施されれ ば、国民の利便性は著しく向上するものと考えられる。また、郵便局は従 来から、住民票、戸籍謄本等各種申請の取次ぎや国庫金の受払いをはじめ とした、公的窓口としての機能を果たしており、利用する国民の立場から も支持されるであろう。郵政研究所の調査では、様々な手続のための一括 窓口があれば便利な場所として、7割近い人が郵便局を挙げている(図7)。 【一括窓口があれば便利と思う場所】(図7)
(出所)郵政省資料 イ 国民の利便性向上 行政手続は、国民生活においても必要なものであるが、現行の行政手続 は国民にとって煩雑な面がある。例えば、役所に申請をしようとする場合、 申請の窓口がどの役所の何という課か、一般には分かりにくい。また、転 居時のように、1つの行為について複数の役所へ複数の申請を行わなけれ ばならないこともある。 これに対して、一つの窓口で一括して申請手続等を行うことが可能にな れば、国民の負担は大幅に軽減される。これがワンストップ行政サービス である。郵政研究所が実施した住民意識調査の結果では、公的窓口が分散 している現状に対して、不便と感じる人の割合は8割近い。 最も身近な郵便局窓口においてワンストップ行政サービスが実施されれ ば、国民の利便性は著しく向上するものと考えられる。また、郵便局は従 来から、住民票、戸籍謄本等各種申請の取次ぎや国庫金の受払いをはじめ とした、公的窓口としての機能を果たしており、利用する国民の立場から も支持されるであろう。郵政研究所の調査では、様々な手続のための一括 窓口があれば便利な場所として、7割近い人が郵便局を挙げている(図7)。 【一括窓口があれば便利と思う場所】(図7)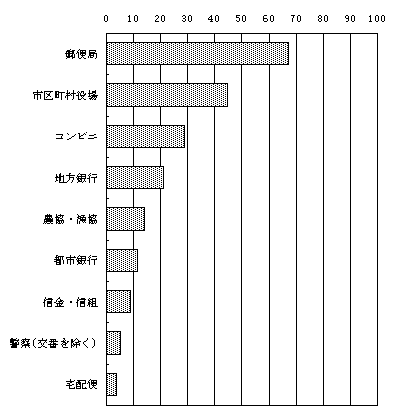 (出所)郵政研究所 ウ 国、自治体のニーズ (ア)現在、我が国は、高い水準の財政赤字の下で、行政の効率化により、 国や自治体の行政コストを削減するとともに、急速な高齢化等の進展に 伴い、新たな行政需要に柔軟に対応していくことが求められている。 また、行政の効率化を目的として、過疎地域における国等の出先機関 が統廃合されつつあり、こうした地域における行政サービス水準をいか に維持するかが課題となっている。 そうした取組の実践例として、平成8年4月から、国の出先機関であ る登記所の統廃合に際し、地域住民に対する行政サービスを確保するた め、郵便局が登記簿謄抄本の申請の窓口を代行するケースが全国的に生 じてきている。 (イ)こうした効率的な行政への要請と、国民の負担軽減・利便向上のため、 行政庁に対する申請等の負担軽減が極めて重要であるとの閣議決定が先 般なされた(「申請負担軽減対策」(平成9年2月10日閣議決定)参 照)。 その中で、申請、届出の電子化・ペーパーレス化のための重要な施策 として、ワンストップ行政サービスの早期実現が挙げられている。 行政全体から見た場合、新たな行政需要に対して、各々の行政機関が 窓口を設けるより、郵便局等、身近な一つの窓口で取り扱う方が、行政 全体のコスト削減、効率化に資することとなる。今後、国・自治体にお いて、ワンストップ行政サービスの実現に向けた積極的な取組みが期待 される。 エ ワンストップ行政サービスの効果 仮に、転居や結婚、出産等に伴う主な行政手続について、全国24,6 00の郵便局窓口でのワンストップ行政サービスが実現した場合、手続時 間の短縮によるその経済効果は、年間1,400億円〜2,400億円と 試算される。
(出所)郵政研究所 ウ 国、自治体のニーズ (ア)現在、我が国は、高い水準の財政赤字の下で、行政の効率化により、 国や自治体の行政コストを削減するとともに、急速な高齢化等の進展に 伴い、新たな行政需要に柔軟に対応していくことが求められている。 また、行政の効率化を目的として、過疎地域における国等の出先機関 が統廃合されつつあり、こうした地域における行政サービス水準をいか に維持するかが課題となっている。 そうした取組の実践例として、平成8年4月から、国の出先機関であ る登記所の統廃合に際し、地域住民に対する行政サービスを確保するた め、郵便局が登記簿謄抄本の申請の窓口を代行するケースが全国的に生 じてきている。 (イ)こうした効率的な行政への要請と、国民の負担軽減・利便向上のため、 行政庁に対する申請等の負担軽減が極めて重要であるとの閣議決定が先 般なされた(「申請負担軽減対策」(平成9年2月10日閣議決定)参 照)。 その中で、申請、届出の電子化・ペーパーレス化のための重要な施策 として、ワンストップ行政サービスの早期実現が挙げられている。 行政全体から見た場合、新たな行政需要に対して、各々の行政機関が 窓口を設けるより、郵便局等、身近な一つの窓口で取り扱う方が、行政 全体のコスト削減、効率化に資することとなる。今後、国・自治体にお いて、ワンストップ行政サービスの実現に向けた積極的な取組みが期待 される。 エ ワンストップ行政サービスの効果 仮に、転居や結婚、出産等に伴う主な行政手続について、全国24,6 00の郵便局窓口でのワンストップ行政サービスが実現した場合、手続時 間の短縮によるその経済効果は、年間1,400億円〜2,400億円と 試算される。【ワンストップ行政サービスの経済効果】(年間)
住民側の時間
現状
14,400万時間
ワンストップ後 2,100〜6,100万時間
削減効果
(金額換算)
▲ 58%〜▲ 85%
(1,200〜1,800億円)
行政窓口側の時間 現状
4,500万時間
ワンストップ後 500〜3,300万時間
削減効果
(金額換算)
▲ 27%〜▲ 89%
(200〜600億円)
合計
削減効果
1,400億円
〜2,400億円
(郵政研究所による試算結果) (注)表中の最大値は、行政手続のワンストップ化による時間削減効果に併せ て、窓口業務の電子化に伴う効率化効果を見込んだ場合の数値。 オ ワンストップ行政サービスの展開計画 郵便局を活用して、ワンストップ行政サービスを実現しようとする場合、 郵便局と自治体等との連携について、下記のような段階を経てシステムを 構築していくことが現実的である。
[1]第1段階
・郵便局→自治体等:郵送又はFAXにより各種の申請を取次ぎ。
・自治体等→申請者:各種証明書等を申請者に郵送。
[2]第2段階[郵便局−自治体等にネットワークを構築]
・郵便局→自治体等:オンラインで各種の申請を取次ぎ。
・自治体等→申請者:第1段階と同様。
[3]第3段階[ネットワークに本人確認機能や公的認証機能等を付加]
・自治体等→(郵便局窓口)←申請者
:オンラインで即時に各種行政手続が完了。
現在、第1段階として、郵送等による住民票等の交付請求の取扱いが全 国約1,600の市区町村、約14,800の郵便局で実施されている (平成9年3月末現在)。また、平成9年度からは、モデル市区町村にお いて、第2段階に相当する実証実験が予定されている。 今後、サービス実現の前提となる自治体等の事務や郵便局自体の情報化 を更に進めるとともに、21世紀初頭までに、ワンストップ行政サービス の全国実施を実現することが望ましい。 カ 諸外国との協力 郵便局におけるワンストップ行政サービスの実現はまた、世界共通の課 題でもある。 特に、モデル市町村における実証実験を予定している我が国と、WIN GS構想を推進している米国とは、ワンストップ行政サービスが21世紀 に期待される郵便局サービスの役割であるとの共通の認識に立って、その 国際的な推進に向け、情報交流、技術協力等について協力していくことで 合意が成立している。 今後、世界の主要国の間で同様の協力関係が構築されていくことにより、 郵便局におけるワンストップ行政サービスが、世界60万の郵便局共通の 目標として推進されていくことが期待される。 (2)民間ネットワークへの開放 ア 国民の利便性向上 (ア)モノの取引について、郵便局の情報・モノ・カネの統合ネットワーク を活用すれば、購入申込み、代金支払等のアクセス負担やコストを軽減 することができる。(例:「ふるさと小包」) 送金・決済ネットワークの結合という点からも、郵便局ネットワーク のオープン化の効果は大きい。我が国の金融機関の送金・決済ネットワ ークが一本化することにより、現金を送受する拠点が全国各地に拡大す るとともに、郵便局と民間金融機関の口座間の決済が可能になり、決済 機能や利便性が一層高まる。 (イ)今後、金融自由化の進展に伴い、ハイリスク・ハイリターン商品を含 めた多様な金融商品が提供されることが予想される。 こうした状況の下で、郵便局ネットワークを民間に開放し、民間金融 商品や情報を全国の郵便局窓口を通じて提供することは、国民の選択の 幅を拡大し、多様化する国民のライフスタイルに応じた生活設計に資す ることになる。 このことは、民間金融機関が身近に存在しない過疎地域等の住民にと って、都市部と同水準の多様な金融サービスや情報が享受できるという 点で、特に効果が大きい。 イ 民間企業のニーズ 民間企業としても、自らの選択により、全国に24,600の拠点を有 する郵便局のオンラインネットワーク等を利用する場合には、店舗の地理 的制約を越えて、全国津々浦々で自社のサービス・商品の提供が可能にな り、市場を拡大し得るといったメリットがある。特に、従来、民間金融の 業務分野の自由化に際して、業態間における店舗数の差が一つの制約とな ったが、こうした制約の解消にもつながるものと思われる。 なお、民間ネットワークとの接続に際しては、郵便局は、どの民間企業 に対しても公平・中立に対応することが必要とされる。 ウ 郵便局のオープンネットワーク化の展開計画 郵便局ネットワークのオープン化については、実用化に向けたセキュリ ティ(情報保護)対策や決済リスク等の問題点を把握し、改善方策を検討 する一環として、平成9年度から、郵貯ATM(現金自動入出金機)と信 販会社等のATMとの相互接続実験や、郵便局における電子取引に関する 実験が予定されている。 このような実証実験を通じ、技術的及び制度的問題の解決に取り組み、 早急にその実現を図ることが望ましい。 2 情報流通の促進 (1)高度情報通信社会における情報ニーズ ア 電気通信メディアと郵便 光ファイバやデジタル化等情報通信分野における技術革新を背景に、既 に述べたインターネットのほか、パソコン通信、移動体通信など新たな情 報通信メディアが急速に浸透してきている。 こうした新たな情報通信メディアの発展は、既存メディア・ネットワー クの需要に影響を及ぼすほか、異種のメディア・ネットワーク双方の特性 を活かすため、両者を統合した「ネットワークの融合」を進展させつつあ る。 情報通信メディアの多様化や融合が進展する中で、情報流通量は急増し ている。平成6年度までの10年間の推移を見ると、情報流通量(原発信 量)は約3.3倍にも達している。近年の新メディアの急激な増加傾向を 踏まえると、平成13年度(2001年度)の情報流通量は、現在のさら に約1.5倍以上に増加するものと推計されている。 国民が、必要な情報を最も適切な方法により選択する、すなわちその時 々のニーズに応じてメディアとネットワークを選択する時代になるものと 想定される。 イ メディアとしての郵便及び電気通信の特性 郵便の本質は、紙・現物としての情報を各家庭まで直接、ヒトが届ける ことにある。郵便は、特別の情報端末やそれを操作する能力が求められな い、簡便な通信手段であり、情報化に取り残されていく人、いわゆる「情 報弱者」にもやさしいメディアということができる。 郵便の印象についてのアンケート調査結果によれば、個人が郵便を受け 取る場合・送る場合いずれにおいても、「丁寧」、「気持ちがこもってい る」との回答が電気通信メディアと比較して多く、「心と心のふれあい」 を感じさせるメディアとしての特性を有している(表8)。また、企業か ら見た郵便の特性として、現物性・一覧性・手軽さ・情報密度の高さ・受 信者のコスト負担がないことなどが挙げられている(郵政省調査)。 他方、電気通信は、電子的に処理された情報を、端末から端末まで電気 通信回線や電波を通じて伝達するものである。電気通信、特にコンピュー タ間通信は、迅速性・加工性といった特性を有しており、大量の情報を瞬 時に伝達し、加工・編集処理するのに適している。 【個人利用者が郵便を受け取る場合の印象】(表8)(%)
丁寧な
感じ
形式的な
感じ
気持ちが
こもって
いる
先進的な
感じ
伝統的な
感じ
返事が必
要な感じ
郵便
48.4 22.8 41.1 0.6 14.9 22.5 電話
20.1 24.1 29.9 11.6 2.0 20.0 ポケットベル 0.5 13.3 1.6 33.5 0.4 26.0 FAX
3.4 17.1 3.1 46.2 0.3 9.0 電子メール
3.2 18.2 3.0 44.1 0.5 6.7 出所:「マルチメディア時代における郵便サービスに関する調査研究会」 におけるアンケート調査(複数回答)(平成7年12月)(郵政省) ウ 郵便に対するニーズ (ア)高度情報化に伴う情報格差の是正 高度情報化の進展に伴い、都市部と地方の情報格差や個人間の情報格 差が更に拡大するのではないかとの懸念がある。これに対して、郵便は、 基礎的な通信サービスとしてユニバーサルに提供され、かつ情報弱者に も簡便に利用できることから、情報の地域間・個人間格差の是正に資す ることが期待される。 (イ)郵便需要予測 これまで、電気通信メディアの発展につれて、郵便に対するニーズも 拡大してきた。これは国民が選択できる情報量の飛躍的増大の中で、現 物性、儀礼性といった特徴により、郵便がメディアの一つとして選択さ れてきた結果と考えられる。 昭和60年の電気通信の自由化以降、郵便物数の伸びが国内総生産の 伸びを上回っていることは、電気通信メディアの発展が必ずしも郵便需 要を奪うものではないことを示している。長期的に見ても、家計・企業 の支出に占める郵便費の割合は極めて安定的である。 a 企業通信の動向 企業間通信においては、今後、EDIやCALS等の伸展により業 務用通信の形態に大きな影響が及び、郵便需要の減少が予想される。 他方、企業から個人あての郵便需要については、電気通信メディア への代替も予想される一方で、広告・販売においては、個々の消費者 に直接アプローチするダイレクトマーケティングの重要性が高まって おり、その手段としてDM(ダイレクトメール)の需要が拡大してい るほか、インターネットなどを利用したオンラインショッピング(*10) 等の急激な拡大により、その決済に伴う請求書等の送付需要の増大が 予想される。 b 個人間通信の動向 近年、若年層を中心に、文章を書くことを面倒と考える傾向や、冠 婚葬祭などの行事を簡素化する傾向がある等の指摘がある。このよう なメンタリティ(気持ちの在り方)の変化は、コミュニケーションメ ディアについてもより手軽さを求める傾向となって現れ、個人間の郵 便による通信にマイナスの影響を与え得ると考えられる。 新たなコミュニケーション環境に対応する新しい文字文化・手紙文 化の創造は、国民文化の側面からも重要であり、個人間郵便需要の開 拓への努力が必要である。 c 諸外国との比較 我が国の郵便物数を諸外国と比較すると、総物数は米国に次いで第 2位であるにもかかわらず、1人当たりの差出物数は、199通(1 995年度)と、第16位となっている。これに対して、米国の1人 当たりの差出物数は我が国の3.4倍、フランスは2.1倍、英国は 1.6倍、ドイツは1.2倍となっている(図9)。 このような差が生じている理由としては、欧米においては、気軽に 郵便を差し出す習慣があるなど、郵便利用に対する国民性の違いや、 小切手取引やクレジットカード決済が国民生活へ浸透しており、その 処理に伴う郵便物数が多いなどの差があるからと言われている。 郵便サービスには規模の経済(*11)が働くことから、なるべく安 い郵便料金を達成するためには、個人間通信の振興を図るとともに、 一層のサービス改善を推進し、多様な国民ニーズに対応して、郵便需 要を開拓していく必要がある。 【各国の年間国民1人当たりの差出郵便物数】(図9)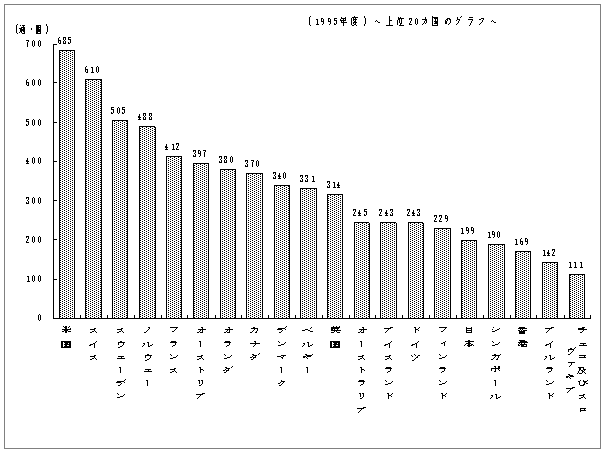 d 以上のような企業通信、個人通信の動向を総合すると、郵便サービ スが高度情報化や国民のニーズに柔軟に対応し、新規需要を開拓し、 拡大できれば、郵便物数は今後2010年頃まで安定的に拡大するこ とが可能である。以下で述べる郵便局サービスの改革を前提に、具体 的に21世紀初頭の郵便需要を予測すると、2010年の総物数はお おむね385億通(年平均3%程度の伸び)となり、これを基に推計 すると、収入伸び率は年平均2%程度となる(図10)。 【総郵便物数の予測結果】(図10)
d 以上のような企業通信、個人通信の動向を総合すると、郵便サービ スが高度情報化や国民のニーズに柔軟に対応し、新規需要を開拓し、 拡大できれば、郵便物数は今後2010年頃まで安定的に拡大するこ とが可能である。以下で述べる郵便局サービスの改革を前提に、具体 的に21世紀初頭の郵便需要を予測すると、2010年の総物数はお おむね385億通(年平均3%程度の伸び)となり、これを基に推計 すると、収入伸び率は年平均2%程度となる(図10)。 【総郵便物数の予測結果】(図10)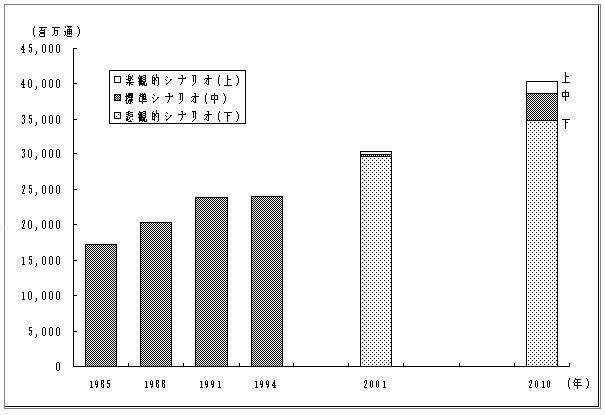 (2) 情報流通促進のための郵便局サービスの改革 郵便局は、高度情報通信社会における「情報の拠点」として、情報流通を 促進し、誰もが多様な情報に公平にアクセスできる社会の実現に貢献すべき である。このためには、基礎的な通信手段である郵便サービスの改革に積極 的に取り組むとともに、郵便局のマルチメディア化を推進することが必要で ある。 ア 低廉な郵便料金水準の実現とサービス水準の向上 電気通信メディアが高度化し、料金の低廉化が進む中にあって、郵便 サービスが基礎的通信手段としての役割を果たしていくためには、低廉 な料金水準とする必要がある。 今後、上記で述べた郵便業務収入の伸び率(年平均2%程度)を前提 に、低廉な料金水準を実現するため、多様な国民ニーズに対応し、郵便 需要を開拓し、収入増を図るべきである。このため、一部郵便料金引き 下げや料金割引制度の充実により郵便需要を喚起するとともに、マルチ メディア融合サービス等の付加価値的サービスを導入することにより収 入増を図る必要がある。これと同時に、平成10年2月以降の新郵便番 号制(*12)の導入に伴い、今後、10年間で8,000人、2,000 億円程度の削減を図るとともに、新郵便処理システム(*13)の確立や 郵政短時間職員(*14)の活用、効率的な区分・運送方法についての研 究を行うなど、郵便事業の更なる合理化・効率化を推進し、コスト削減 に取り組む必要がある。 また、国民が満足できるサービス水準を確保するため、各種のサービ ス水準の目標と実績を公表し、国民利用者との約束として、目標の達成 に努めるべきである。 以上の点を踏まえ、下記のような施策を実施する必要がある。
(2) 情報流通促進のための郵便局サービスの改革 郵便局は、高度情報通信社会における「情報の拠点」として、情報流通を 促進し、誰もが多様な情報に公平にアクセスできる社会の実現に貢献すべき である。このためには、基礎的な通信手段である郵便サービスの改革に積極 的に取り組むとともに、郵便局のマルチメディア化を推進することが必要で ある。 ア 低廉な郵便料金水準の実現とサービス水準の向上 電気通信メディアが高度化し、料金の低廉化が進む中にあって、郵便 サービスが基礎的通信手段としての役割を果たしていくためには、低廉 な料金水準とする必要がある。 今後、上記で述べた郵便業務収入の伸び率(年平均2%程度)を前提 に、低廉な料金水準を実現するため、多様な国民ニーズに対応し、郵便 需要を開拓し、収入増を図るべきである。このため、一部郵便料金引き 下げや料金割引制度の充実により郵便需要を喚起するとともに、マルチ メディア融合サービス等の付加価値的サービスを導入することにより収 入増を図る必要がある。これと同時に、平成10年2月以降の新郵便番 号制(*12)の導入に伴い、今後、10年間で8,000人、2,000 億円程度の削減を図るとともに、新郵便処理システム(*13)の確立や 郵政短時間職員(*14)の活用、効率的な区分・運送方法についての研 究を行うなど、郵便事業の更なる合理化・効率化を推進し、コスト削減 に取り組む必要がある。 また、国民が満足できるサービス水準を確保するため、各種のサービ ス水準の目標と実績を公表し、国民利用者との約束として、目標の達成 に努めるべきである。 以上の点を踏まえ、下記のような施策を実施する必要がある。(具体的な施策例)
・21世紀初頭、例えば、2005年までの手紙・はがきの料金据置き
現在の安定的な経済状況を前提に、手紙・はがきの料金を2005年
まで据え置き、更により低い水準とするよう努める。
費用に占める人件費の割合が高く、費用の伸びが収入の伸びを大幅
に上回る現在の郵便事業の費用構造の下では、料金の長期間据置きは
極めて困難である。長期間の料金据置きを実現するために、以下のよ
うな今後10年間にわたる大幅な合理化・効率化と、新規需要の開拓を
進める必要がある。
[1]大幅な合理化・効率化
・新郵便番号制の実施
・要員配置の見直し(郵政短時間職員、非常勤職員の活用等)
・経営効率化の目標と実績の公表
・外部評価システムの導入
[2]新規需要の開拓
・一部郵便料金の引下げ
・郵便料金割引制度の充実
イ 多様なニーズに応じた郵便サービス (ア)新スピードサービス 多様なニーズに対応して、郵便サービスに対しても、送達速度の多様 化が求められている。こうしたニーズに対応し、新たなスピードサービ ス等の提供を行うべきである。 例えば、国民が求める配達速度により、[1]緊急な用件に対応し、 2〜3時間程度で配達するサービス、[2]引き受けたその日に配達す るサービス、[3]引き受けた日の翌日午前10時までに配達するサー ビス等に整理し、提供することが考えられる。 (イ)マルチメディアとの融合サービス 高度情報通信社会における国民の通信ニーズとして、即時性、画像通 信、大量データ処理など、情報通信メディアの持つ高度な特性に対応し たものが想定される。 郵便サービスも、こうしたニーズに柔軟に対応し、電気通信技術の導 入により、既存のサービスの高度化や電気通信と融合した新サービスの 提供を行うべきである。 具体的には、以下のようなサービスの導入を検討すべきである。
[1]ハイブリッドメールサービス
インターネット等を通じてメッセージを24時間受け付け、郵
便物として配達するサービスである。紙として配達されるため、
将来予想される情報弱者に対する救済策としても有効なサービス
である。
[2]電子内容証明サービス
従来の「内容証明郵便の機能」に電気通信技術を導入すること
により、電子的な文書でも第三者的に証明することを可能とする
サービスである。高度情報化が進展する中で、電子的な文書の改
ざんや他人を偽装した文書発信(成り済まし)などに対するセキ
ュリティ向上のため、認証ニーズが社会的に高まっていることに
対応し得る。
ウ 郵便局へのアクセスの改善 今後、高齢者の増加、女性の社会進出、単身世帯の増加等により、サー ビス拠点へのアクセスが体力的に又は時間的に困難な利用者の増加が予想 される。 こうした中で、生活基礎サービスを提供する郵便局の役割を一層徹底す るため、郵便局に対するアクセスをより容易にする施策を実施すべきであ る。
[1]土日のアクセス改善
○地域特性に応じた郵便局の土日開庁の拡大
駅、デパート、観光地、住宅地等、多くの利用が見込める
郵便局について、積極的に土日の開庁を行っていく。
[2]アクセスポイントの増設
○郵便ポストの増設
○ゆうパック取次所、郵便切手類販売所等の増設
[3]24時間問い合わせ窓口の開設
○郵便サービス案内センターの設置
[4]ATMの24時間稼働
エ 郵便局のマルチメディア化 誰もが容易に多様な情報にアクセスできる環境を構築するため、郵便局 のマルチメディア化を推進し、地域の「情報キオスク」として活用すべき である。具体的には、全国の郵便局に自治体、インターネット等と接続し た情報端末を設置し、各地の地域・生活情報等を提供することなどが考え られる。 さらに、地域住民の情報リテラシー向上の観点から、郵便局において、 操作が容易な情報機器、特に高齢者や障害者に配慮した機器の設置や窓口 職員・外務職員による操作サポートの充実等の措置も検討される必要があ る。 なお、現在郵便局舎が狭あいであり、また、都市部を中心に窓口の業務 繁忙度が高いことから、こうした取組を困難視する声もあるが、ME (Micro Electronics:マイクロエレクトロニクス)技術の進展等により、 情報機器の一層の小型化と操作性の向上が期待できる。 3 ネットワークのグローバル化 (1)グローバル化に伴うニーズ ア 第1章で述べたように、情報通信や輸送手段の高度化に伴い、ヒト・モ ノ・カネ・情報が地球規模で移動するようになっている。今後、社会経済 や国民生活のグローバル化とともに、高度情報化が進展する中で、国内に いながら海外の公的機関や民間企業等の情報・サービスにアクセスし、あ るいは海外にいながら我が国の情報・サービスを利用するニーズが増大し ていくことが予想される。例えば、インターネットを通じた個人輸入や、 海外で自国のキャッシュカードを用いて現地のCD(現金自動支払機)・ ATMから直接現地通貨を引き出すといったサービスが挙げられる。 イ グローバル化の進展や世界経済に占める日本経済の比重の高まり等を背 景に、国際社会における我が国の責任と役割はますます増大している。今 後、我が国は、地球社会の一員として、その発展に積極的に取り組むこと が求められている。 こうした中にあって、郵便局もまた、国際的な連携を図り、国際社会の 一層の発展に貢献することが必要である。 (2)郵便局のグローバルネットワーク化 ア 我が国は、明治10年(1877年)、万国郵便連合(UPU)に加盟 している。UPUは、世界のどこにでも、国内と同様に、郵便を自由にか つ手軽に差し出し、また受け取ることができることを目的として、187 4年に創設された国際機関である。我が国にとっては、UPU加盟が初の 国際機関への加入であり、郵便を先駆けとして国際社会への参画を果たし た。 UPU加盟から始まった郵便局のグローバル化は、今や国際郵便ネット ワークや国際送金ネットワークを通じ、国内の地域拠点と海外とを結ぶグ ローバルな、モノ・カネ・情報のネットワークを構築している。国際郵便 については、全世界に向けて郵便を送ることが可能であり、また、国際送 金は、全国約20,000の郵便局から80の国・地域に送金することが 可能である。 こうした郵便局ネットワークがグローバル化や高度情報化を背景とした 国民のニーズに応えていくために、より広範に全世界60万に及ぶ郵便局 ネットワークとの連携を推進する必要がある。この場合、UPU、世界貯 蓄銀行協会(WSBI)等の国際機関を通じて、海外の郵政庁や貯蓄銀行 との連携を強化していくことが肝要である。 特に、日本版ビッグバンの皮切りとなる外為法の改正により、国内外の 資金移動が自由となるが、郵便局では、個人・小口の利用者のニーズにグ ローバルネットワークを活用して対応していくことが重要である。 また、郵便局のグローバルネットワークをより有効に活用するため、国 内と同様に、海外の行政・民間ネットワークに対してもオープン化を図り、 海外の公的機関のサービスの代行等も検討すべきである。 こうした郵便局ネットワークのグローバル化に際しては、国際間で提供 するサービスの仕様や技術について国際標準化を図ることが重要な鍵とな る。ICカード(*15)等今後導入が予定されるものの規格については、 グローバルな利用を想定して検討していく必要がある。 イ これまで郵便局では、開発途上国からの研修生の受入れや研修機材の供 与等により、郵便局サービス・業務のノウハウを提供し、また、現地への 職員の派遣により、郵便システム整備や機械化のマスタープラン(基本計 画)策定に貢献する等、相手国における郵便局ネットワークの整備に協力 している。さらに、ベトナム、タイにおける郵便貯金制度創設支援やタン ザニアにおける簡易保険制度創設支援など、開発途上国の貯金・保険制度 の整備への支援により、国内資本形成を通じた開発途上国の経済発展に貢 献している。 こうした協力は、開発途上国から期待されているものであり、また、郵 便局のグローバルネットワークの形成にも寄与するものであることから、 今後も途上国からの要望に応じて積極的に協力していくことは、国際貢献 の観点からも重要である。