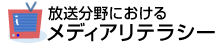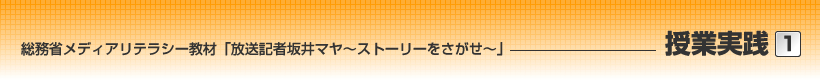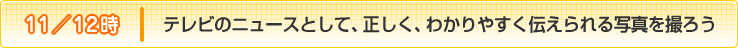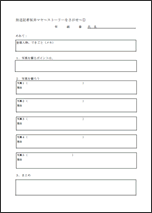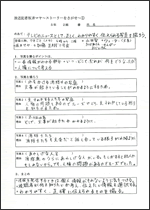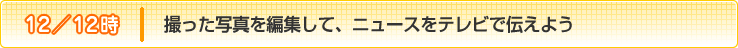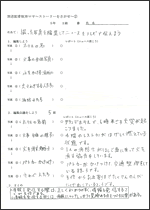5年生・社会科の「わたしたちの生活と情報」という単元で、「情報を発信しよう」という2時間の授業が行われました。
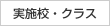
- 東京都中央区立京橋築地小学校 5年2組 30名

- 内山宝教諭 坂田真一教諭(T.T)
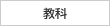
- 社会
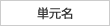
- 「わたしたちの生活と情報」(12時間)
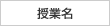
- 「情報を発信しよう」
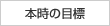
-
■11/12時
情報をわかりやすく伝えるためには何が必要かを考え、情報を選択することができる。
■12/12時
情報について学んできたことをもとに伝え方を考えて、正しく、わかりやすく情報を発信することができる。
また、メディアリテラシーの大切さを理解することができる。


これまでの授業を振り返る
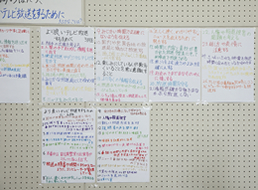
これまで学んできた、テレビや新聞のニュースづくりで大切なことについてまとめたものを掲示しています。
児童たちは、これまでの10時間の授業で、自分たちの生活と情報とのかかわり、テレビのニュース番組がどのように作られているか、くらしの中のコマーシャル、情報社会における個人情報の保護などについて学んできました。本時は、この単元の集大成として、児童たちが情報を発信する側に立ってニュースを作るという体験をします。
まず、これまで学習してきたことを先生と一緒に確認します。
ストーリー(前半)を確認し、登場人物と出来事をメモする
「放送記者坂井マヤ〜ストーリーをさがせ〜」(以下「Web教材」)を、教室正面のスクリーンで、先生が読み上げるストーリーを聞きながら、みんなでいっしょに確認します。登場人物とできごとをメモします。

めあてを確認する「テレビのニュースとして、正しく、わかりやすく伝えられる写真を撮ろう」
今日のめあて「ニュースを正しくわかりやすく伝えられる写真を撮ろう」を確認した後、内山先生から「みんなが坂井記者になったつもりで、取材をして、写真を撮ってもらいます」と一言。児童たちから「え〜!?」と驚きの声があがります。
まず、先生が操作の説明をします。
画面上には、消防隊員が消火活動をする様子、避難するホテルのお客たち、救急車で運ばれる人たちなど、火事の様子が映っています。マウスをドラッグすると、カメラフレームが自由に動き、クリックすることによって、撮りたい画面を切り取ることができます。キーボードの↓↑のキーで、画面をアップにしたりルーズにしたりすることもできます。
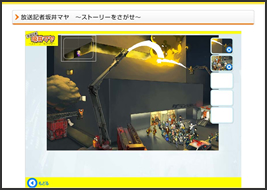
事件の様子をわかりやすく伝えるために、どの映像を撮ればいいか考え、5枚を選びます。

「面白そう!」と児童たちは早くもノリノリです。すぐにも作業にかかりたい ところですが、ここで、大事なポイントをまとめます。
先生
「せっかく今まで情報の勉強をしてきたんだから、写真を撮るポイントを確認してみましょう。」
児童たち
「いろいろな場面があるけど、正しくわかりやすくするために、いらない
ところは撮らない。」
「一番情報のわかる部分を撮る。」
「個人情報の保護のために、顔のアップは撮らない。」
先生
「そうだね。もう一つ、これはニュースだから、5W1H、いつ、どこで、だれが、何をして、どうなったか、ということを考えながら撮ってくだ
さい。」
ニュースを伝えるために必要と考える写真を撮る
児童たちは、各自、火災現場の画像の中から、5枚の写真を撮影します。そして、それぞれの写真に、「○○の写真」と名前をつけて、ワークシートに記入します。

炎が激しく燃えるところ、グランデホテルの看板、騒いでいる人たち、救出活動をする消防士たちなど、児童たちは、マウスをドラッグしながら何の写真を撮影するか考えます。画面の端のほうに、コートを着た怪しい人がいます。「あ、怪しい。」「犯人だ!」という声があちこちで上がります。木の上にはサルがいます。撮ろうかどうか迷っている子もいます。
撮った写真を発表する
児童Aさんが代表して、撮った写真の題名と理由を発表しました。

【1枚目】
- 題名
- 怪しい人
- 撮った理由
- なぜこの人だけ裏口にいるのかな?もしかしたら犯人かも?と思ったから。
先生:
「他にもこの写真を選んだ人はいる?」
児童たち:
「はい。サングラスをかけたり、帽子をかぶったり、服装が怪しいから。」
「一人だけ、みんなと違うところにいるから。」
「前のストーリーを見返すと、記者会見のときからいて怪しそう。」
先生:
「この人を撮っちゃいけない、と思った人は?」
児童たち:
「はい。まだ犯人と決まっていないから。」
「迷った。怪しいだけでは撮っちゃいけないけど、もし後で怪しい人がはっきりと犯人であるとわかったときは撮っ
ておいてよかったと思うだろうから、一応写しておいた。」

【2枚目】
- 題名
- 避難した人たち
- 撮った理由
- 現場の様子がわかるように、人がいっぱいいるところをルーズに調整して撮った。ルーズで撮ったわけは、人権の問題があるから。本当は、全体の様子がわかるためにはもっとルーズで撮りたかったけど、これ以上ルーズにできなかった。
先生:
「ほかにも、ここをルーズで撮った人いる?」
児童:
「人権のことがあるので、ルーズで撮った。それに、ルーズならまわりの様子がわかるから。」
先生:
「なるほど、まわりがわかるようにね。」

【3枚目】
- 題名
- 火が燃えているところ
- 撮った理由
- 火事の恐ろしさや、どんなふうに炎があがっているか知らせるため。

【4枚目】
- 題名
- パトカーが止まっているところ
- 撮った理由
- 通行止めになっていることを知らせるため。

【5枚目】
- 題名
- グランデホテルの看板
- 撮った理由
- どこで火事が起こっているかわかるように。
先生:
「Aちゃんのと違う映像を撮った人はいる? サルを撮った人はいない?」
児童:
「撮りました。理由は2つあって、サルは火事現場に普通はいないのにおかしいと思ったから。また、怪しい男とつながりがあるかも知れないと思ったからです。」
本時の授業のまとめをする
一人の児童が発表したところで、3時間目が終了。この時間のまとめをしました。
情報を発信するときは、
- ・個人情報がもれないように気をつける。
- ・視聴者が何を知りたいか考え、伝えたい情報を選択する。
- ・わかりやすく正確に伝えられるものを撮る。
先生:
「次の時間は、今撮った写真をもとに編集作業をします。最初に問題になった人権問題について、どの程度までなら写していいのか、『怪しいから撮る』ということはいいのかどうか、これまで学んだ新聞やテレビのニュースのことを思い出しながら考えて欲しいと思います。」

ストーリー(後半)を確認する

編集画面。5枚の写真を並び替えて編集し、ニュースを完成させる。
教室正面のスクリーンにWeb教材を映し、先生が残りのストーリーを読み上げます。主人公のマヤが、火災現場で撮った写真を編集してニュースを作ることになったようです。ここで、すでに選んだ5枚の写真に、先輩が撮った全景写真と、市民から提供のあった携帯写真の2枚が加わります。
めあてと本時の活動を確認する「撮った写真を編集して、ニュースをテレビで伝えよう」
まず、先生が本時のめあて「撮った写真を編集して、ニュースをテレビで伝えよう」を確認します。その後、この時間の活動を説明しました。
全部で7枚の写真から大事だと思う5枚を選び、伝える順番に写真を並べ替えます。次に、写真に合わせてニュース原稿(レポート)を考え、ワークシートに書きます。最後に、これをみんなの前で発表します。
作業手順
1. 一人ひとりでニュース原稿を考える- ・5枚の写真を選択し、並べ替える
- ・ニュース原稿をワークシートに書く
- (並び替えが早く終わり時間に余裕がある人)
- ・グループで話し合って、5枚の写真を選択し、並べ替える
- ・ニュース原稿を考える
一人ひとりでニュース原稿を考える
最初は自分ひとりで考えます。最初に選んだ5枚は本当にそれでよかったのか、ストーリーを振り返って再度選び直す子、画像を並べる順番を迷う子、それぞれに頭の中でニュースの流れを考えながら作業が進みます。
グループで編集会議をする

児童一人一人が編集作業をした後、今度はグループになって、みんなの意見を伝え合いながら、1本のニュースを完成させます。
「これじゃあ何が起きているのかわからなくない?」
「犯人がわからないのに入れるの?」
「サルは関係ないよ。」
「これはいらない。」
熱い議論が交わされます。
グループで作ったニュースを発表する
さて、いよいよ発表です。ニュースを読む人、パソコンを操作する人を決めます。
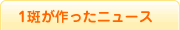
「グランデホテルで火災が発生しました。この火災でけが人も出たようです。ただ今隊員が消火活動を行っています。火災現場には山田愛さんもいたようです。山田愛さんも無事救出しました。」
●工夫した点は?
「話す順番を気を付けました。」
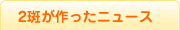
「今日午後6時ごろ、グランデホテルで火災が発生しました。火の手はすごく、ホテルの中は煙でいっぱいです。グランデホテルは大変混雑している様子です。グランデホテルで食事をとっていた人気歌手の山田愛さんは、ビルに取り残されて いましたが救出されました。グランデホテルでは、加藤正樹監督の記者会見が行われていました。ビルのかげには、帽子、マスク、サングラス、コートを着用している人がいました。」
●工夫した点は?
「写真に合ったレポートを書いたことです。」
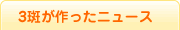
「今日グランデホテルで火災がありました。炎は激しく燃えあがり、消火は難航しました。逃げ惑っている人たちの中にはあの有名な加藤正樹さんもいました。さらに、火災現場にいた山田愛さんも4階のレストランに取り残されてしまいまし たが、無事、消防士たちにより救出されました。」
●工夫した点は?
「レポートの順番がきちんとつながるように考えました。」
「グランデホテルにいた人たちを、うまく映像に映し出そうと考えました。」
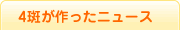
「夕方6時過ぎに火災が発生しました。有名歌手山田愛さんも火災に巻き込まれたようです。マスクとサングラスをかけている怪しげな人が逃げるように走っている模様です。また、ナゾのサルがこちらをうかがっています。どうやら、あの 怪しげな人と関係がありそうです。」
●工夫した点は?
「話がつながるように気を付けました。」
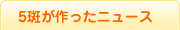
「今日グランデホテルで夕方6時ごろ火災が起こりました。4階のレストランが激しく燃えている状態です。消防車のホースのほかに、一人の消防士が梯子車に乗って火を消す協力をしています。この写真は、パトカーが駆けつけて交通整理をしている様子です。また、こちらの写真は、子どもから大人まで、たくさんの人が逃げ出している様子です。消防士の人も一生懸命でした。」
●工夫した点は?
「人の顔をできるだけ写さないようにしました。」
「つながりが変にならないように気を付けました。」
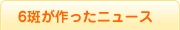
「午後6時頃、グランデホテルのレストランの厨房で火事がありました。まだ事件か事故かは、はっきりしていません。消防隊は、ほとんどの人を救出しましたが、まだ炎は強く燃えています。ホ テルには、人気歌手の山田愛さんも助けを待っていましたが、先ほど無事に救出されました。グランデホテルの裏側に、体を隠せるぐらいのコートを着用し、帽子を深くかぶりサングラスをかけ、マスクもしている怪しい人かげが見 えます。この人をもうちょっと調べていきたいと思います。」
●工夫した点は?
「5枚の写真と文をできるだけ合うように考えました。」
各グループの発表の後には、「その班のいいところ」を話し合いました。
「怪しい人」の扱いは、全くニュースに入れなかった班、入れても犯人とは断定しなかった班など、各班で分かれていました。
「山田愛は有名人だから顔が映ってもいい。」
「怪しげな人を映すのは人権問題にかかわる。」という意見が出ていました
。
以前、教科書で勉強した、松本サリン事件のことを思い出して、「怪しい人の映像を流して、この人がもし犯人でなかったら、サリン事件のときのように、その人が苦しい思いをする。」という発言も出ていました。
ここで、まとめとして、先生がわざと極端に作ったニュースの例を発表し、どこが問題かをみんなで考えました。
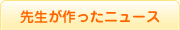
「今日午後6時半ごろ、○×区のグランデホテルで火災がありました。若い女性の話では、怪しげな男が、コートを着て歩いていたそうです。そして、監督の加藤氏は、あちらにその男が逃げたと言っています。その男はカメラに捕らえられ ました。あまりにもひどい火事だったので、シャワーを浴びていて、裸で出てきた人もいます。」
児童たち:
「裸で出てきた人をアップで撮るのはいけない。」
「あっちに逃げたと言っている人のアップもいけない。」
などの意見が出ました。
本時の授業のまとめをする
最後に先生が、本時の授業のまとめを黒板に書きました。
- ・情報を発信する際は、正しくわかりやすく情報を発信することが大切である。
- ・情報を受信する側は、情報についてしっかりと見極める力をつける必要がある。
先生:
「こういうことを『メディアリテラシー』と言います。
これからみんなは、発信する側にも受信する側にもなるわけですから、発信する時は、正しくわかりやすく情報を発信し、受信するときには、その情報が正しいかどうか、しっかり見極める力をつけてください。」

中央区立京橋築地小学校 内山宝教諭
Q 今回、「放送記者坂井マヤ〜ストーリーをさがせ〜」を授業で使ってみていいかがでしたか?
A 子どもたちの想像力が掻き立てられ、意欲的に取り組める教材だと思います。
内山先生:
一番はじめに感じたのは、子どもたちが、放送記者である坂井マヤの立場に身をおき、火災現場のニュース作りを主人公と一緒に疑似体験できるというのは、子どもたちの想像力が掻き立てられていいなということです。子どもたちは、次に何が待っているのだろうと想像しながら意欲的に取り組むことができるので、そういった意味では、大変よく考えられた内容になっていると思います。
子どもは、画像とか映像にすごく反応しますし、意見もたくさん出やすい。今回も、子どもたちが2時間、休み時間も休まないくらい集中して取り組んでいました。
Q 今までこのような教材はあったのでしょうか?
A あまりなかったと思います。「実際にやってみてわかる」という教材は貴重ですね。
内山先生:
従来の教材は読み物が多く、たとえば「こういうことはしてはいけないよ」とか「こういうことに気をつけなさい」といったことを読んでわからせる、というものはあるのですが、このWeb教材のように、実際にやってみてわかる、というのは少ないですね。
Q 操作感はいかがでしたか?
A クリックだけで作業ができるという点は非常によかったと思います。
内山先生:
ICTの機器などもそうですが、こういう新しいものを取り入れるときに大事なことは、先生も児童も無理なくできる、ということです。この教材は、基本的にクリックだけで作業ができますので、どんな子どもでも簡単にできる。その点も非常に良かったと思います。
Q 本教材を活用する際の課題” 、“より効果的に活用するためのポイント”などがあれば教えてください
A (1)活動をスムーズに進めるためにワークシートを活用する、( 2)火災と関係のない要素に注意する、だと思います。
内山先生:
1つは、活動をスムーズに進めるためにワークシートを活用することです。本Web教材は、ニュース原稿(レポート)をキーボードで入力できるようになっていますが、今回の2時間の授業時間でこの機能を使うことは難しいと思いました。
そこでワークシートを活用し、紙面上にニュース原稿を書かせるように工夫しました。また、写真を撮り、選ぶ際にも、ワークシートを活用して作業を簡略化しました。
いいものをつくろうとするといくらでも時間がかかってしまうので、子どもたちには常に時間を意識させ、指定された時間内に終わらせるようにしたのもポイントです。この教材を十分に活かすためには、できるならば3時間くらいの授業時間を取れるといいですね。
もう1つは、関係のない要素に子どもたちが反応してしまわないよう、注意することです。小学生の教材としては、サルのような明らかに火災と直接関係のないものは必要ないように思いました。子どもは、基本的にはとても純粋なので、目の前にあるものには素直に反応してしまいます。関係のないものがあることで、気が散ったり、話が違う方向に行ったりしてしまうリスクがあるかもしれません。
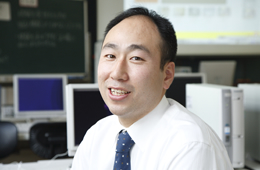
Q この教材がなかったら、代わりにどのような授業をされましたか。
A デジタルカメラを使って小学校や地域を取材し、発信するのもいいですね。
内山先生:
今は、デジカメで簡単に動画を撮り加工することができるので、例えば「京橋築地小学校や小学校周辺のおすすめの場所」などのテーマを設定し、色々な場所の画像を撮ってきて、それに合わせたナレーションを作り、発信する。その学習を通じて、メディアリテラシーを指導するといった授業もできると思います。
Q 学校の授業で、メディアリテラシーを取り上げることについてはどう思われますか?
A 今の情報社会の中で、意味があることだと思います。
内山先生:
今は情報社会なので、子どもたちも当たり前に携帯メールを使ったり、学校の授業でも調べ学習などで頻繁にインターネットを使います。
今の段階から情報モラルやメディアリテラシーを学ぶことは意味があるし、小学校5年生なら十分に理解できる内容だと思います。また、早くから取り組むことで、子どもたちの意識にも入っていきやすいと思います。
今回は、5年生の社会科の「わたしたちの生活と情報」という単元で使いましたが、5年生の国語科の「工夫して発信しよう」という単元の中で、自分の意見を映像とともに発信するという活動があるのですが、ここでも使えると思います。