情報通信産業の設備投資額は、移動通信産業を中心に拡大を続けており、バブル期以降の日本経済を支えてきた。さらに、情報通信産業は、1997(平成9)年12月に閣議決定された「経済構造の変革と創造のための行動計画」において、「新たなリーディング産業を形成していくものと予想される。」とされているように、成長の牽引役としての役割を担うものと位置づけられている(資料2)。
1996(平成8)年度の通信・放送産業の設備投資実績は4.9兆円であり、全産業に占めるシェアは11%とリース業を除き産業別で第一位となっており(資料3)、実際上も、産業全体の設備投資の牽引役としての役割を果たしているといえる。また、一方で、新聞、出版等の活字媒体や、直接対面によって行われてきた医療、教育等の分野においても、ネットワークを活用した新たなビジネスの萌芽が見られる。
情報通信産業の今後の展望としては、「情報通信21世紀ビジョン」(電気通信審議会答申、1997(平成9)年6月)」(以下「ビジョン21」と言う。)において、情報通信分野の市場規模は2010(平成22)年には約125兆円にまで拡大する(1995(平成7)年では約29兆円)と見込まれている(資料4)。
また、他の産業分野においても、情報通信の広範かつ効果的な利用により、生産性の顕著な向上とコストの削減が期待できることから、その活用方策が重大な検討課題となっている。
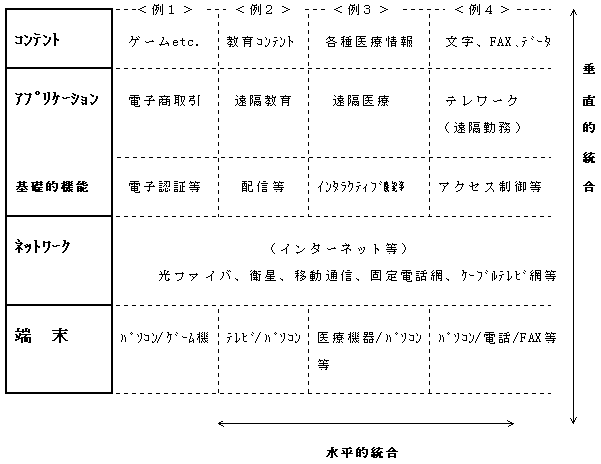
図1.1 情報通信産業の構造
こうした動きの中で、ネットワーク機能を中心とした情報通信産業の動勢、あるいは収支状況や設備投資額といった経済的要素について、統計的に正確に把握し、他の産業分野や国民経済に及ぼす影響等について、定量的に分析していくことが必要である。
また、これらの情報通信産業からサービス提供を受けて情報化を進めている他の産業分野や個人事業者の情報通信活動、ネットワーク機能を活用した電子商取引等についても、その形態や規模、情報通信ネットワークの利用度合い、ネットワークを流れるコンテント情報の生産、流通、販売などの実態について、統計で的確に把握・分析できるようにすることが、我が国産業経済全体を展望する上でも重要になってくる。
情報通信分野の中でも放送においては、以上のような産業的な側面のほか、視聴者とともに放送文化を発展させていくマスメディアとしての総合放送としての公共性と、デジタル化などの技術革新の成果を活用した新たなサービス展開をどう調和させていくかという課題がある。
情報通信の発展の成果を取り入れることにより、情報の流通を中心とする諸活動は飛躍的に変わりつつあり、今後とも一層の効率化が進むであろう。物理的な活動が中心となる場合においても、例えばCALS(生産・調達・運用支援統合シテム;(注))のように、情報通信は効率や生産性を高める効果があることに留意する必要がある。
| (注) |
CALS 文書データ、取引データ、図面データ及び製品データの標準化を行い、調達側と供給側で情報通信を利用してデータのやり取りを円滑化することにより、開発期間の短縮、品質向上、コスト削減等様々な効果を目的とするものである。その概念も徐々に拡大してきており、何の略記であるかについても数度の変遷を経て、最近ではCommerce At Light Speed(光速の商取引)の略とされている。 |
 先導的利用者としての政府・自治体
先導的利用者としての政府・自治体
 民間部門の情報化への支援
民間部門の情報化への支援
 制作資金調達制度の確立等
制作資金調達制度の確立等
 社会意識の変革、人材育成等
社会意識の変革、人材育成等
 サービス、
サービス、 事業体、
事業体、 ネットワーク、
ネットワーク、 端末の各面で生じている次のような現象、
端末の各面で生じている次のような現象、
