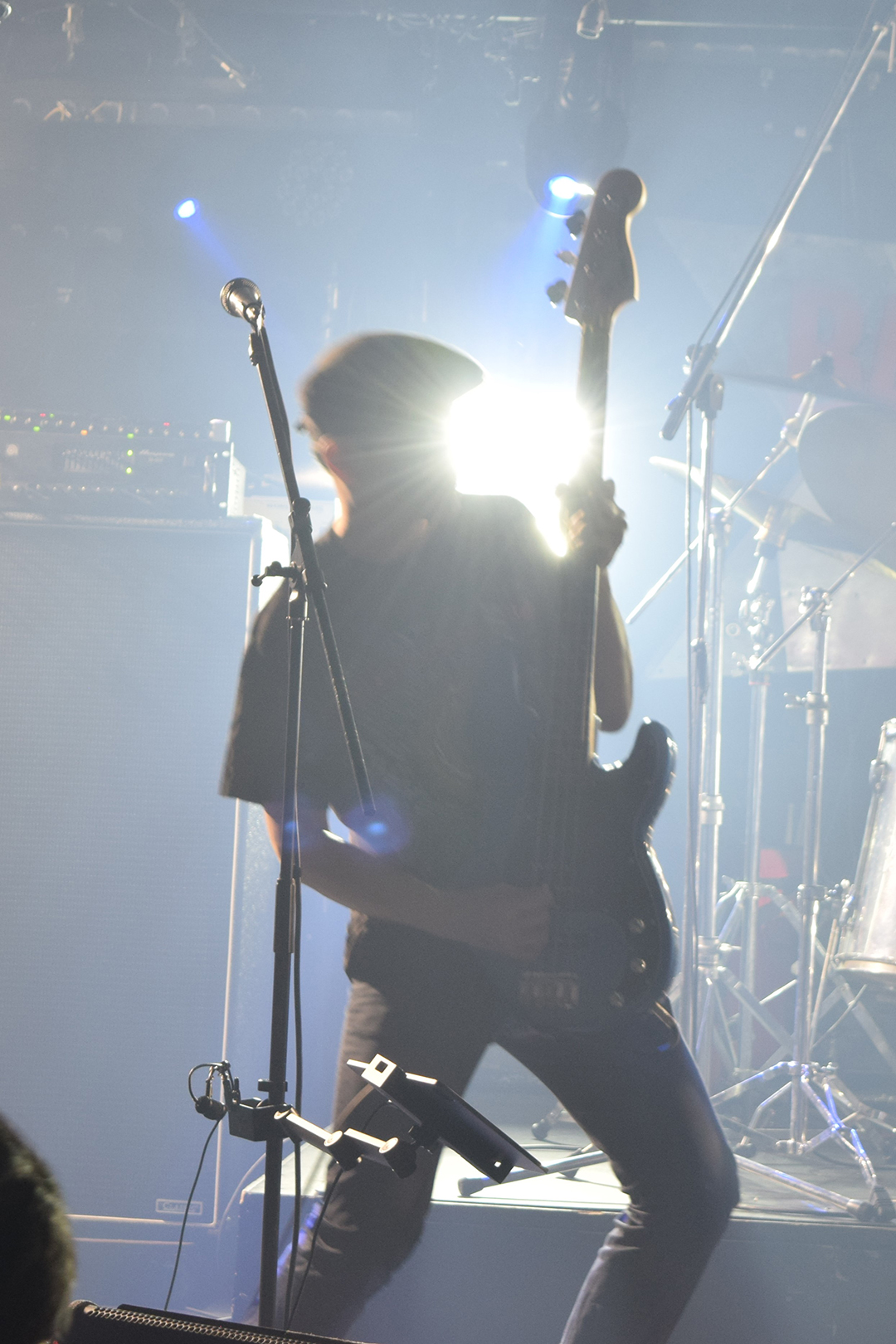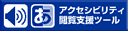西澤 能之
経歴など
- 平成8年4月
- 総理府採用 大臣官房総務課
- 平成15年4月
- 鳥取市企画推進部長
- 平成18年4月
- 総務省人事・恩給局参事官補佐(人事評価担当)
- 平成18年4月
- 同 行政管理局副管理官(内閣・内閣府・総務省担当)
- 平成22年8月
- 同 副管理官(特殊法人・独立行政法人総括)
- 平成23年7月
- 同 副管理官(定員総括)
- 平成25年6月
- 同 大臣官房秘書課課長補佐
- 平成26年9月
- 総務大臣秘書官
- 平成29年8月
- 内閣官房内閣人事局企画官(機構総括担当)
- 平成30年7月
- 同 内閣参事官(企画調整、労働・国際担当)
- 令和2年7月
- 総務省行政管理局管理官
(政府情報システム基盤・行政情報システム総括担当)
- 令和3年7月
- 同 行政評価局企画課長
- 令和4年6月
- 内閣官房内閣総務官室内閣参事官
- 令和6年7月
- 現職
20年先の「行政」を考える
国民の役に立つ
これまで、国の行政組織の機構・定員の審査、公務員制度などに長く携わってきました。常に心掛けてきたことは、この組織・この定員がどういう仕事をすれば国民の役に立つのか、国家公務員が最大のパフォーマンスを発揮し国民のために成果を上げるにはどういう仕組みにするべきか、ということです。
変化への対応
機構・定員審査では、消費者庁や復興庁など新たな組織の発足や、東日本大震災対応のための緊急増員など、公務員制度では、人事評価制度の導入・定年引き上げ・テレワークの推進などに携わりました。いずれも、直面する課題(=変化)に対応するため、行政組織の体制や公務員制度を整備したものです。
時代を先取り
行政を取り巻く環境(=世の中=国民の困りごと)の変化が激しい現在、変化に後追いで対応することではなく、将来起きるであろう変化に先回りして備えることが必要ではないかと思うようになりました。「未来は不確実だ」と言われますが、「2040年問題」(生産年齢人口が現在より1000万人減少)は確実な未来であり、また、20年後に20歳の日本人は70万人しかいないというのも確実なことです。
このような中、国民の安全を守り、経済活力を向上させ、必要な行政サービスを確実に提供し続けていくことが公務部門には求められます。生成AIなどの先端技術も活用し「人手によらない」業務実施を行い、限られたリソースを政策の企画立案に振り向けることを考えなければなりません。また、官民の人材流動性を高め、限られた人材が社会全体で有為に活躍していくことも、公務員制度としてアプローチしていく必要があります。
このほか、行政手続や情報公開などの共通制度、政策評価、統計データの利活用なども、将来を見据えて制度改革をしていく必要があると思います。
「20年先の行政」を見据え、やらなければならないことはたくさんあります。「日本を元気にする」「日本をより良くする」という志をもった皆さんと一緒に、これらの課題に取り組んでいきたいと思います。