授業実践パッケージ(小学校)
2年「生活/はっぱのいろがかわったよ」で行われた授業を紹介します。

- 実施校:仙台市立向陽台小学校 2年
- 実践者:稲垣奈美 教諭
- 監修:稲垣 忠 東北学院大学教養学部准教授
- 単元:はっぱのいろがかわったよ *
- 授業時間数:45分
- 学習の概要:校外活動「秋探し」のために、秋と夏をイメージした番組を児童に視聴させ、秋の色について学習するとともに、番組の「色」や「音」の効果について考える。
- 本時の目標:
- 番組で使われている映像や音から、表現されているイメージを読み取ることができる。
- 季節の変化は五感で感じられることを知り、秋探しのめあてをもつ。
*23年度以降:あきをさがそう

- 四季って言葉知っているかな。皆が知っている季節を教えてください。
- 「四つの季節」 「春」「夏」「秋」「冬」
- 今の季節は何かな。
- 「秋」「秋と冬の間」「冬」と児童の季節に対する回答が異なる
- 急に寒くなったから冬だと思うかもしれないけど、今は、冬が始まる立冬の前だから、秋です。
今日は、秋について、番組を見ながら勉強します。

- 番組を見る前に、学校の行き帰りや遊び場などで、みんなが見つけた秋について教えてください。
- 「紅葉している葉っぱ」「柿」「秋っぽい風」「夜に鳴く虫」「栗」「どんぐり」・・
- みんな、いろいろな秋を見つけてるね。

- これから2つ番組を見るので、どちらが秋か答えてください。
- ― まず秋の番組(A)を視聴し、次に夏の番組(B)を視聴。
- 秋の番組はどれでしょう?
- 一斉に手をあげて「Aでーす」
- 秋の番組には何が写っていましたか。
- 「ススキ」「紅葉」「コオロギ」「赤トンボ」「コスモス」「カマキリ」 ・・・
- Bは何の番組ですか。
- 「夏ー」
- 夏の番組には何が写っていましたか。
- 「カブトムシ」「海」「ヒマワリ」「空」「緑のイチョウ」「蝶」 ・・・
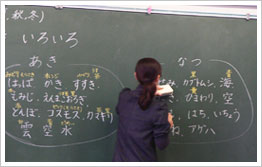
- 番組をもう一度見るので、今度は、色に注目して、気が付いたことを紙に書いてね。
- ― ワークシートを配付後、秋の番組(A)を視聴。
- 秋の番組にはどんな色がありましたか。
- 「柿がオレンジ色」「コオロギの羽がうす茶色」「カマキリが茶色」「紅葉が赤」「コスモスがピンク」 と、次々と秋に関する色を回答
- 次は、夏の番組にあった色を書いてください。
- ― 夏の番組(B)を視聴。
- 夏の番組にはどんな色がありましたか。
- 「海が青かった」「蝶が黄色と黒」「空が青」と、たくさんの児童が回答
- たくさんの色を見つけることができましたね。
色は何で見ることができましたか。 - 「眼」
- 他にはどんな方法で秋を見つけられるかな。
- 「耳」「眼で見る」「耳で聞く」「手でさわる」「心で見る」

- 今の番組のなかには、色以外にも、季節がわかるしかけがあったけど、何かわかりますか。
- 「音ー」と、数人の児童が回答
- 番組のなかでセミがワシワシって鳴いていたよね。
夏だなー暑いなと思うよね。
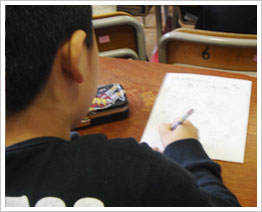
- みんなは今度、近くのお寺に行くけれど、どんな方法で秋を探してみたいですか。
鼻で匂いをかいでみることもできますね。
お寺に行ったときは、眼、耳、鼻、手で心も使って、秋を探しましょう。
では、今日の勉強で楽しかったことや初めて知ったことを書きましょう。
次回は、五感を使って、楽しく秋探しをしましょう。


 稲垣奈美 教諭(仙台市立向陽台小学校)
稲垣奈美 教諭(仙台市立向陽台小学校)
- Q.今日の授業の子どもたちの様子はどうでしたか。
- ◆授業に惹き込まれていた
- 秋と夏の番組に、子どもたちが好きな虫や花などが登場したこともあり、映像や音を聞いて、「ロマンチック」という子どももいて、みんな授業に惹き込まれていました。
低学年は、「わかること」がとてもうれしい年代ですが、今日の授業で使った番組は、夏と秋の違いが分かりやすい映像でしたので、子どもたちはそれぞれの季節の特色をたくさん発見できてうれしかったと思います。
- 秋と夏の番組に、子どもたちが好きな虫や花などが登場したこともあり、映像や音を聞いて、「ロマンチック」という子どももいて、みんな授業に惹き込まれていました。
- ◆夏と秋の番組は各1分半程度だったので、子どもたちが集中できた
- 今日の授業では、夏と秋の番組を2回づつ視聴する計画でしたが、子どもたちのほうから、番組を「もう1回見たい」との声が聞かれました。もし番組が今日のものより長かったら、子どもたちは途中で飽きてしまい「もう1回見たい」とは言わなかったかもしれません。夏も秋も、それぞれが1分半程度の番組でしたが、子どもたちが興味を持って見るのにちょうどよい長さだったと思います。
- ◆授業に惹き込まれていた
 Q.授業で工夫されたことは何ですか。
Q.授業で工夫されたことは何ですか。
- ◆ワークシートを活用
- 今日は、番組を視聴して、板書を中心に違いを見つけたり、イメージをまとめたりする授業だったので、子どもたちの集中力が途切れないように、書く作業を取り入れました。低学年にとって、番組を見ながらメモを取るのは、少し難しい作業に思えましたが、意外と子どもたちは、メモを早くたくさん書くことができました。
- ◆2回目は注目すべき点を提示して視聴する
- 1回視聴しただけで番組の特徴を掴むのは難しいので、繰り返して見せる必要があります。でも、2回とも同じように見せるのではなく、1回目は「ただ見る」、2回目は「色に注目してみよう」などと、課題を与えて視聴させるとよいでしょう。
- ◆ワークシートを活用
- Q.もっと時間をかけて授業ができる場合、実施するとよい活動はありますか。
- ◆音で、季節の特徴を考えるクイズをする
- 今日は、秋みつけクイズを映像と音で実施しましたが、時間があれば難易度を少し高くして、音だけで季節を考えるクイズをすると、それまで自覚していなかった季節の音の特色を意識するきっかけになると思います。音のクイズでは、映像でのクイズとは季節を変え、たとえば、冬は北風の音、春ならばウグイスの声を使ってクイズをするとよいでしょう。
- ◆音で、季節の特徴を考えるクイズをする
- Q.この授業を実施してよかったですか。 よかった点について教えて下さい。
- ◆クラス全員で秋のイメージを膨らませることができた
- よかったです。これまでは、秋探しの校外学習の事前授業として、子どもたちの感じた秋の話を聞くだけだったり、子どもが持ってきたドングリや葉っぱを個々に見ていました。でも、なかなかクラス全員で、秋のイメージを膨らませることができませんでした。今日は、映像を通じて、皆で秋の特徴について話すことができ、五感についても子どもたちに理解してもらえたと思います。
- ◆大きくなって、番組には色や音で季節を表現するしかけがあることを意識してもらえればよい
- 授業目標の「番組で使われている映像や音から、表現されているイメージを読み取ること」については、子どもたちはイメージを感じ取っていましたが、この目標を言葉で理解したわけではありません。これから大きくなってテレビ番組を見たときに、ふと今日の授業を思い出し、番組には、色や音で季節を表現するしかけがあることを、意識してもらえればよいのではないでしょうか。
- ◆クラス全員で秋のイメージを膨らませることができた

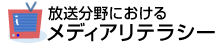

![[小学校2年・生活] 授業名:番組の色や音のイメージを知ろう](images/jissen_03_title_01.png)
![[小学校2年・生活] はっぱのいろがかわったよ 授業レポート](images/jissen_03_title_02.png)
![[小学校2年・生活] はっぱのいろがかわったよ 先生の一言 〜授業を終えて〜](images/jissen_03_title_03.png)