| 【地域情報化】 | |
| 第2編 総務省の情報通信施策 第1章 地域関連施策 第1節 地域関連施策の概要 |
5 その他の地域関連施策
| |
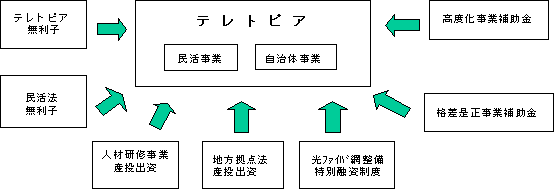 | |
テレトピア構想は、情報通信基盤整備促進の普及拠点となるモデル都市の構築、先進的アプリケーション・システムの導入効果、ケーブルテレビやインターネット等の新たメディアを活用して地域の実状に応じたシステムを構築することにより、各地域の抱える問題点を解決し、活力ある快適な地域社会の形成促進を支援することを目的としています。 昭和60年の第一次指定以来、全国では189地域(H12年度末)が指定を受けており、東北管内では、14地域18地方公共団体において55システムが計画されこのうち33システムが稼働しています。また東北管内の第三セクターは9地域において11社が設立されています。 |
テレコムタウン構想は、地方の拠点となる地域に、独自の情報を大量かつ高速に流通・受発信するために必要なハード、ソフト、人材の情報通信基盤を、道路や上下水道の都市基盤と同様、まちづくりと一体的に整備しようとするものです。 同構想の実現のために設立された「情報基盤協議会」では、産学官共同で地域情報化プロジェクトを実現するための調査研究会「地域分科会」を開催しています。 地域分科会開催の要件
運営方針
開催状況 (東北地域)
開催までのスケジュール(予定)
|
◆事業主体:公益法人 ◆対象地域:高速道路等のトンネル、地下街等の閉塞地域 ◆対象施設:移動通信用鉄塔施設(鉄塔、無線施設、光ケーブル等) ◆国の補助率:1/2 |
衛星放送受信設備設置助成制度は、地形等の影響により、NHKのテレビジョン放送が良好に受信できない地域において、NHKの衛星放送を受信するための受信設備を設置する方に対し、その経費の一部を国が助成し、難視聴解消を促進する制度です。 【主な要件】
【助成額】
【助成制度の流れ】 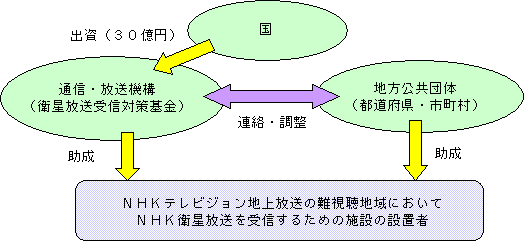 |