Process 募集から受け入れのプロセス
募集前
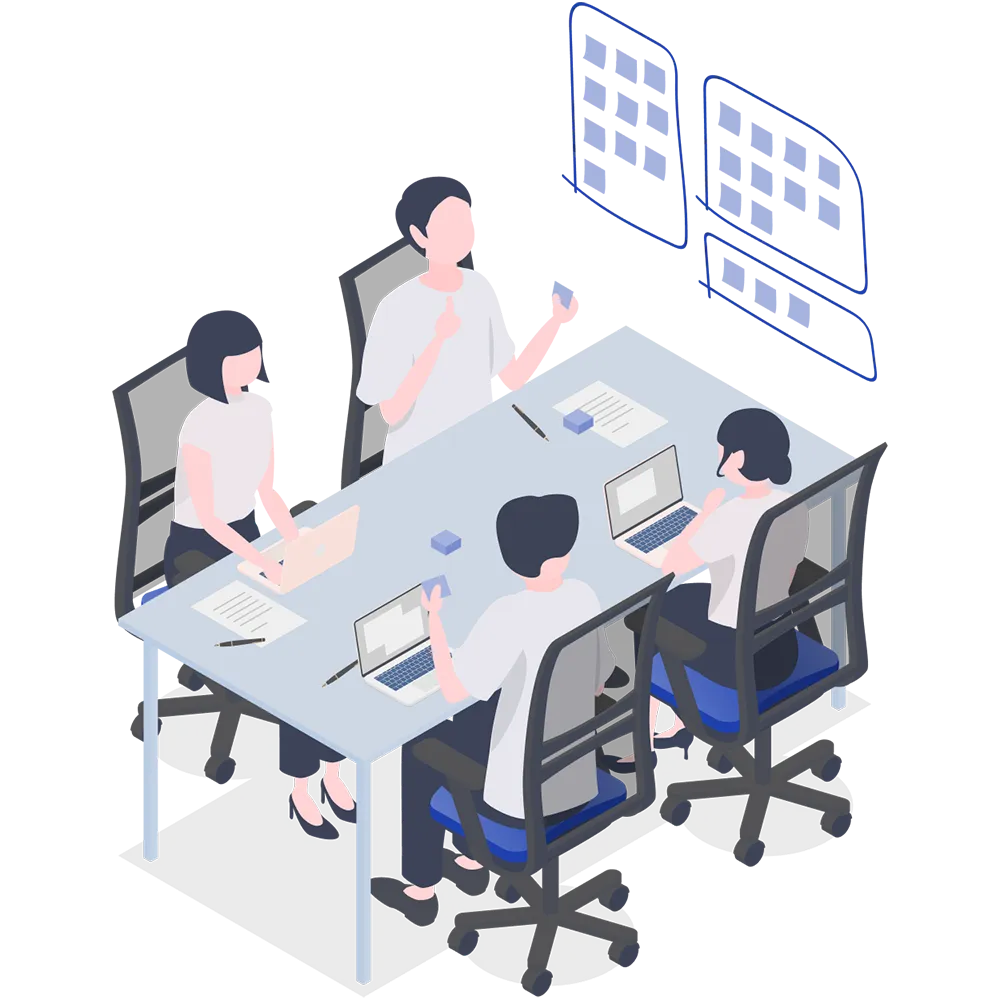
- 地域おこし協力隊員のサポート体制づくり
- 地域の課題・ニーズの把握
- 募集案件の組成
募集~採用
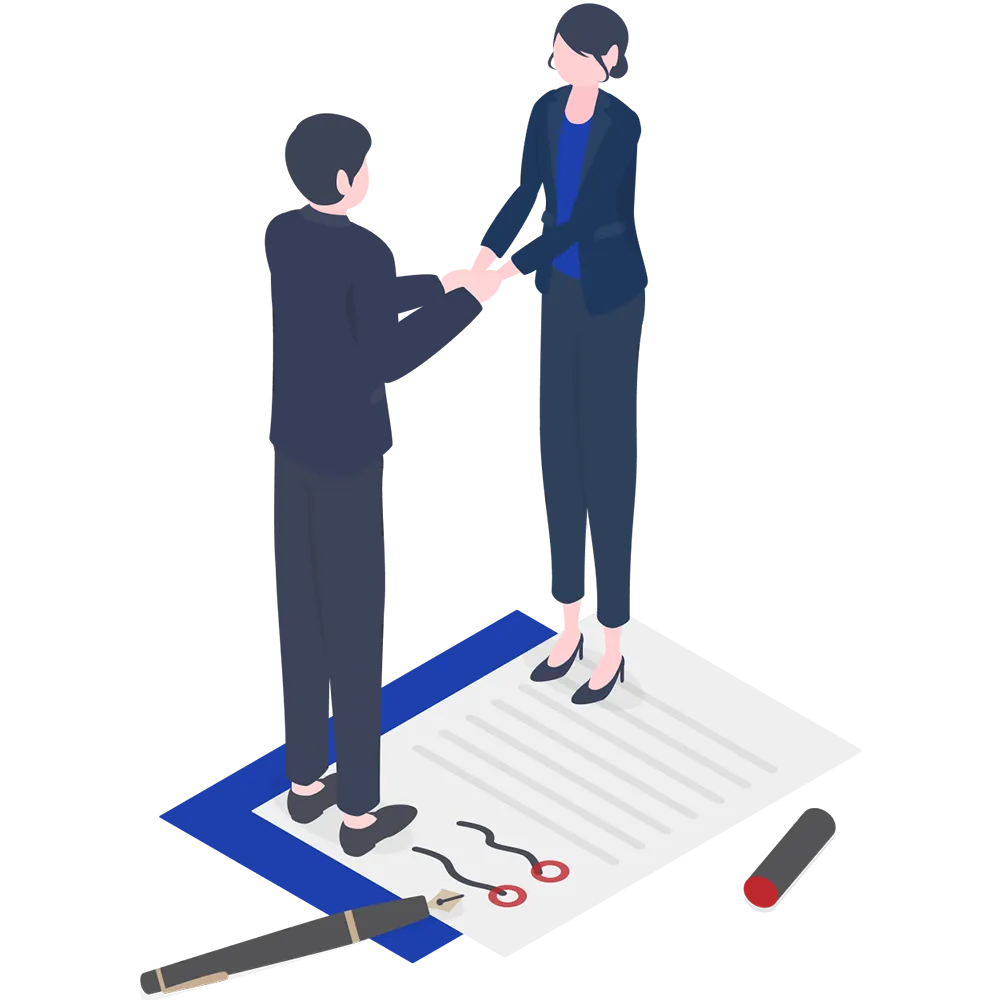
- 募集活動
- 任用決定
任期中
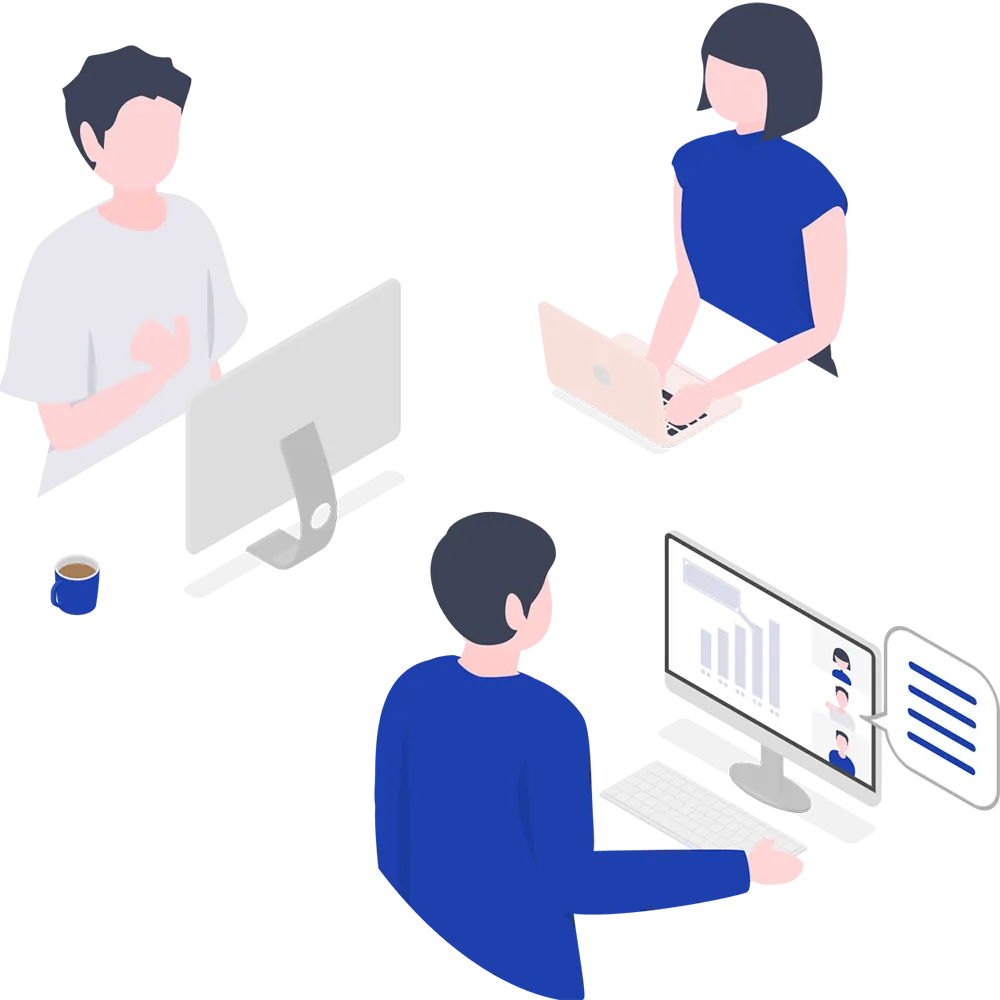
- 任期中~任期終了後に向けたサポート
募集前
地域おこし協力隊員のサポート体制づくり
地域おこし協力隊は地域活性化のための公的な役割を持つ一方で、その地域に移住し生活する一人の住民でもあります。
この二つの側面を持つ隊員が活動しやすくかつ地域に根付いていかれるよう、多角的なサポート体制と関係機関との緊密な連携体制が不可欠です。

ポイント
-
地域おこし協力隊が地域に根ざした活動を続けていくには求める人材を募集するだけではなく、着任後の継続的なサポートが欠かせません。このサポート体制が地域おこし協力隊が地域との想いを共有し活動を持続させるための基礎となります。
サポート体制の構築にあたり、関係者それぞれの役割や担当などを明確にすることが必要です。
例えば隊員の生活や仕事のサポート担当をそれぞれ置くほか、受入団体がある場合は隊員のサポート業務を当該組織のタスクとして盛り込むことが挙げられます。
また具体的なサポート内容や役割分担を定めるには、隊員の特性や希望を考慮することも重要です。このように構成員一人ひとりが自身の役割と任務を深く理解し、地域と隊員に寄り添った行動を実践できる体制こそが、地域おこし協力隊の成功に繋がります。
-
協力隊のサポート体制として、行政職員や地域のキーパーソン、活動先となる組織の担当者といった地域関係者だけではなく、中間支援組織と呼ばれる団体とも連携することが大切です。
外部の組織や専門家、中間支援組織などの外部主体は地域おこし協力隊制度を踏まえ専門的な視点からアドバイスやサポートを提供してくれるほか、地域の取組みの客観的な把握・検証のためにも、積極的に連携・活用することが望まれます。
外部パートナーの選定にあたっては、下記が見極めのポイントとなります。
- 協力隊制度への理解
- 協力隊員の受入支援業務の実績
- 事務処理能力
- 所在地などコミュニケーションのしやすさ
- 行政や地域への寄り添い方のスタンス
- 隊員経験者の有無
さらに中間支援組織のほか、外部の専門家や地域おこし協⼒隊経験者なども連携先の選択肢のひとつです。
どのような組織や人材が地域にマッチするか、各都道府県の担当課や都道府県単位の地域おこし協⼒隊経験者のネットワーク(以下、都道府県ネットワーク)、地域おこし協⼒隊サポートデスクなどに問い合わせて情報収集・相談することをおすすめします。実際に外部にパートナーに支援を依頼する際は、事前に十分な話し合いを行い、どのような考えのもと、どのような業務をどのように支援してくれるのかを明確にしておくことが大切です。
なお外部パートナーを活用し、隊員の活動や生活に関する⽇々の相談、地域住民とのつながりづくりなどを依頼する場合、その費用は特別交付税措置の対象となります。
-
サポート体制の構築後、地域おこし協力隊の募集や受入れに関する取組の前に、サポートチーム内で地域おこし協⼒隊の制度や、隊員を受入る目的をしっかりと理解・共有した上で、チームとしての意思統一や役割分担の明確化といったチームビルディングが求められます。
実践的なチームの強化方法として、サポートチームメンバーによる勉強会や、お互いの意見やアイデアを出し合うワークショップの開催が挙げられます。これらの開催に際し、都道府県ネットワーク等を積極的に活用し、講師の選定やカリキュラムの設計に助言を求めることも有効です。
また、担当職員の将来的な人事異動を考慮し、勉強会やワークショップなどで得られたノウハウや決定事項、実施手順などを網羅したマニュアルを作成することも有効です。
隊員の受⼊に向けた準備と⼼構え
総務省では地域おこし協力隊の募集・受入および活動支援に関する多様な相談に対応するため、「地域おこし協力隊サポートデスク」を設置しています。また、地域おこし協力隊の活用について課題を抱えている自治体に対し、より具体的かつ実践的な支援を行う「地域おこし協⼒隊アドバイザー」の派遣事業も⾏っています。
さらに隊員同士の交流促進や日常的な相談先として地域おこし協力隊経験者による各都道府県ネットワークがあります。
そのほか、現役隊員や協力隊経験者のみならず、自治体担当者などの協力隊に携わる全ての人々が、それぞれの立場でこれまで培ってきた知見や悩みなどを共有する全国ネットワークのオンラインプラットフォームもぜひご活用ください。
-
地域おこし協力隊サポートデスク
「移住・交流情報ガーデン」内に相談窓口を開設(平成28年9月27日開設)。
地域おこし協力隊に関して豊富な知見を有する相談員や協力隊経験者が電話やメールによる相談に対応します。
https://www.iju-join.jp/chiikiokoshi/7626.html
-
地域おこし協力隊アドバイザー
自治体からの求めに応じて、地域おこし協力隊に運用に知見やノウハウを有する有識者をアドバイザーとして派遣します。企画・募集から任期終了後に向けた支援まで、幅広い悩みに対応します。
000975732.pdf
-
地域おこし協力隊都道府県ネットワーク
都道府県単位の地域おこし協力隊経験者のネットワークで、それぞれの都道府県ごとに、隊員同士の交流促進や、隊員の日々のサポートなど、さまざまな活動を行っています。
network.pdf
-
地域おこし協力隊全国ネットワーク
地域おこし協力隊関係者のノウハウを全国レベルで蓄積するため、令和6年2月に設立された全国単位でのネットワークです、ネットワーク会員には、現役隊員だけでなく、隊員経験者、自治体の担当職員、都道府県ネットワーク関係者、集落支援員が含まれます。
オンラインプラットフォームの会員専用ページでは、
- 会員同士の交流用掲示板
- オンライン交流セミナー
- 地域おこし協力隊関連情報が掲載されているコラム
- 総務省が主催する研修のアーカイブ動画
といったサービスを利用することができます。
自治体の地域おこし協力隊の担当者は、自らの着任時や、新しい隊員の着任時には、ぜひ会員登録の手続きを行ってください。
https://www.soumu.go.jp/kyouryokutai-network/
地域の課題・ニーズの把握
地域の課題やニーズを的確に把握することは、地域おこし協力隊を採用する目的や隊員に期待される役割を明確にし、⾏政と地域住⺠との間で共通認識を形成する上で重要なプロセスです。
行政と地域住民の考え方には相違があることも踏まえ、地域住民や地域づくり団体と密なコミュニケーションを重ねながら、地域の課題・ニーズを丁寧に把握していくことが求められます。
ポイント
-
地域の課題やニーズの把握のために地域に入る際は、地域おこし協力隊の受入を前提とせず、地域が抱える本質的な課題を丁寧に汲み取ることが不可欠です。
隊員の受入を目的化してしまうと地域の課題やニーズの把握が形骸化し、根本的な解決に繋がらない可能性があります。
また隊員の活動内容と地域の課題・ニーズとのミスマッチや、隊員と地域住民との意識のギャップが生じるなど、隊員が着任した後のトラブルにつながりやすくなります。
また地域側が協力隊の受入を「行政からの押し付け」と捉えてしまう可能性も否めません。これらのリスクを回避するために、行政は住民との対話を通じ、隊員を受入ることが地域にとって必要かつ適切であることをしっかりと確認し、双方で合意形成を図ることが重要です。
-
行政と地域住民との間で、地域づくりの考えが一致しているとは限りません。
双方の認識の相違を解消するには、行政と地域住民が密な意見交換を重ね、地域の課題や目指す姿を明確にし共有することが重要です。その上で、すべての課題や目標を協力隊員に一任するのではなく、隊員と一緒にどのような課題解決や目標達成に取り組むのか、また隊員にどのような役割を期待するのかを具体化する必要があります。
地域の課題の多くは隊員の受入だけでは解決できないため、彼らの役割が適切かどうかを検討するとともに、地域の住民や地域づくり団体が担う部分、行政が担う部分、専門家に依頼する部分などを切り分けていくことが求められます。
このように行政と地域住民との間で課題や目標のほか、隊員の役割などをすり合わせていく過程により地域住民⾃身が当事者意識を持ち、地域住民の地域づくりへの理解や関心が高まることに繋がり、ひいては隊員の活動のサポートが得られやすくなります。
-
地域の課題やニーズによっては、外部人材の活用が必要であっても地域おこし協力隊が必ずしも最適な選択肢とは限らないケースがあります。
例えば活動に高度な専門性やスキルが求められる場合には、以下の制度の活用が有効です。- 外部専門家制度(地域⼒創造アドバイザー) (総務省)
- 地域活性化伝道師派遣制度(内閣府)
また集落の状況把握や集落点検の実施、住民間および住民・行政間の対話促進が主な目的の場合は、「集落支援員」の導入が適切といえます。
なお、単なる行政事務や組織の人員付属を補填する目的で隊員を受入ることは地域おこし協力隊制度の趣旨に合致せず、導入目的として適切ではありません。
地域おこし協力隊は、「地域協⼒活動」に従事する外部からの人材を、行政が期間を定めて任用する制度です。制度の趣旨を十分に理解し、導入の必要性や有効性を慎重に検討した上で、地域の中で合意形成を図ることが大切です。 -
地域おこし協⼒隊の導入実績がある場合、すでに活動中の隊員からの情報収集に加え、これまでの隊員の活動内容と成果の振り返りを行うことが、今後の隊員の募集・受入れ・サポートのヒントとして有効です。
振り返りを行う際にはれまでの隊員の活動年表を作成したり、外部のファシリテーターのもとで意見交換の場を設けるなど、客観的な視点と手法を取り入れることも有効です。
募集案件の組成
地域の課題・ニーズの把握は、隊員の受⼊れが必要かつ妥当であると合意された後、隊員の募集に向けて必要な要件(募集の⽬的、活動内容、活動場所、求める⼈物像等)を検討し、関係者と共有・合意したうえで、募集案件として組成して募集要項に落とし込んでいきます。募集案件の組成は、隊員の募集のための取組であると同時に、地域に対して隊員の募集・受⼊れを宣⾔することでもあります。そのため、応募者にどう伝えるかという視点のほかに、地域がどう受け取るかという視点にも⼗分留意することが重要です。協⼒隊の導⼊の必要性や隊員に期待する役割等を明らかにして、⾏政と地域住⺠との間で共有するための重要なプロセスです。⾏政の考えと住⺠の考えが同じではないことも念頭に置きながら、地域の住⺠や地域づくり団体との密なコミュニケーションによって、地域の課題・ニーズを丁寧に把握することが重要です。
ポイント
-
地域おこし協力隊の受入にあたっては、隊員を受入る目的や隊員に期待する役割が地域の課題やニーズ、地域づくりの目標と合致しており、地域の中で十分に合意されていることが重要です。
そのため、隊員の活動に関わる関係者どうしが意見交換できるワークショップの開催や、地域づくりの目標の実現に向けたロードマップを作成するなど、行政と関係者との間でしっかりとコミュニケーションを図り合意形成を進める必要があります。
また隊員を受入るに至った背景や経緯などを整理し共有することで、募集においても地域の想いや目標を効果的に伝えられるようになります。
こうしたプロセスを経て、地域が目指す将来の姿やその実現に向けて隊員に期待する役割について関係者全員が共通の認識を持つことは、隊員の着任後の活動環境の整備やサポート体制の充実にもつながります。
また、首長を含む自治体職員全体で地域おこし協⼒隊の制度趣旨や地域おこし協⼒隊の導入目的について意識を共有する機会や、地域のキーパーソンや受入団体、中間支援組織と同様の場を設けることも有効です。
なお、こうした意識合わせや合意形成のプロセスに係る費用についても、地域おこし協⼒隊の募集等に要する経費として特別交付税措置を活用を活用することができます。
-
活動内容を受入側が設定する場合、「どこで」「誰と」「何を」「どのように」取り組むのかについて、応募者が業務の具体的なイメージを持てるよう、できるだけ具体的に検討し表現することが重要です。
例えば観光分野での情報発信に取り組む場合、単に「情報発信」と明記するのではなく下記のように具体的に設定することが考えられます。
- 観光協会と連携し地元の商店のイベントや特産品に関する撮影・取材・発信を行う
- 観光協会が運用するインスタグラムアカウントを週3回以上の頻度で継続的に更新する
- 年2回東京で開催される特産品紹介イベントに出張参加し、PR活動を行う
複数名の隊員を募集する場合はそれぞれが担う役割や業務の分担などを具体的に検討することが大切です。
また、隊員が地域で無理なく生活と仕事を両立できるよう、生活環境や通勤手段、勤務時間なども考慮する必要があります。また活動内容は任期を通して一定である必要はなく、期間ごとに設定するのも一つの方法です。
例えば、着任直後は地域にその存在を認知してもらうための調査活動や広報活動を中心とした業務とし、その後、この期間で培われた人脈や信頼関係を活かし特定の分野や事業に取り組むといったように、時期によって活動内容に変化をつけることで隊員自身の成長と地域への貢献度が連動しやすくなります。
合わせて任期終了後の隊員の将来像(企業・地域企業への就職など)について、地域としての期待や方向性を地域の中で共有しておくことで着任後の効果的なサポートやミスマッチの回避にもつながります。
また活動内容や地域での役割に合ったわかりやすい肩書きを設けることも効果的です。しかしながら「○○プロデューサー」など、実際よりも裁量権が大きく見える名称はミスマッチの原因になります。地域の特色や魅力が伝わりやすい表現となるよう工夫することで地域のニーズに合致した人材とのマッチングにつながりやすくなります。
-
隊員の任用後における活動を円滑に進めるため、活動範囲(活動の主な対象となる空間やエリアの範囲)や活動拠点(隊員が日常的に勤務する場所)をあらかじめ設定します。
地域の方々は、隊員が実際に業務を行う姿を見て、隊員の活動状況や仕事ぶりを見ることとなります。隊員の活動を地域の方々に広く知ってもらい、サポートを得るためにも、活動の範囲や拠点を事前に設定することが重要です。
活動範囲については、以下のようにさまざまな設定が考えられますが、ミスマッチの防止や適切なサポート体制の構築のためにも、対象とする範囲を明確に設定することが求められます。
- 自治体全域
- 地区や集落
- 地域の団体や組織
- 特定施設
活動拠点の設定には、日々の活動管理やサポート体制との連携を前提に検討することが重要です。担当職員(管理者)と⽇々顔を合わせやすい場所に拠点をおき、活動場所に出向くような運用が望ましいと言えます。
なお最終的な活動範囲や活動拠点は、隊員の住居や希望なども踏まえ、着任後に見直すことも考慮に入れておきましょう。
-
業務内容が明確になった後は、その業務を円滑に遂行できる人物像を具体的に想定します。
その際、過度に理想化されたいわゆる「スーパーマン」ではなく、地域おこし協力隊としての処遇を踏まえ、現実的な人物像を検討することが大切です。
人物像の検討にあたっては、以下のような要素を丁寧に掘り下げて検討することをおすすめします。- 年齢・性別
- 職歴・スキル・資格
- 家族構成
- 趣味・特技
- 移住の動機
ひとつの人物像に絞る必要はありませんが、上記の情報をできるだけ具体的に書き出し、実在する人物を思い描けるレベルになるよう検討を重ねます。たとえば、「20代~40代の男性で会社員」だけではなく、なぜ地域活動に関心を持ったのか、どのような業種・業態の仕事に就いているのか、家族同伴での移住を検討しているのかなどまで落とし込むと良いでしょう。
設定した人物像は関係者間で共有しイメージをすり合わせることで、募集のターゲットが明確になります。この際敢えて対象としない人物像を考えてみるのも、その一助となります。
また事前にこうした人物像を地域の中で共有することで、サポート体制の準備が進めやすくなり、着任後の円滑な活動環境作りにもつながります。
-
募集案件を作成する段階で雇用形態や着任後の生活環境、特に住宅の確保について検討しておくことが望まれます。
まず雇用形態は業務内容などを考慮し、適切に設定することが大切です。また福利厚生の内容、各種手当の有無や額、各種支援内容や支給品などについてもしっかりと整理し明文化します。
生活環境、特に住宅の準備は必ず事前に行います。住宅の場所、間取り、家賃の負担などの条件について具体的に検討・確保しておきましょう。また必要に応じて写真や間取り図などを用意し、募集要項等に明記できるようにしておきます。
生活環境の検討が不十分な場合、着任の段階で「住宅が見つからない」「思っていた住宅と違った」というトラブルにつながり、ミスマッチの原因となりかねません。
-
募集要項は、採用の目的や活動の内容をはじめ期待する役割や目標、活動場所(範囲や拠点)、それに基づく人物像の想定、さらに雇用や生活に関する事項を関係者間で検討・共有した上で、文書に落とし込む必要があります。
応募者にとって募集要項は応募する地域を選ぶための重要な判断材料となるため、地域の想いや期待、募集の背景などを明確に伝えることが大切です。例えば、隊員と仕事や生活で関わることになる方々や職員の⾃己紹介、個別メッセージを掲載すると地域の想いや特徴が伝わりやすくなります。また他の地域と比較されることも考慮に入れ、見せ方や伝え方を工夫し他地域との差別化を図ることも大切です。
たとえば以下のような具体的な情報を盛り込むと効果的です。●差別化につながる募集要項記載内容の例
・一緒に働く仲間や職員のメッセージや顔が見える写真
・活動場所となる地域や拠点の写真
・先輩隊員の活動紹介やインタビュー
・住宅の間取り図や写真、周辺の生活環境の様子がわかる写真
・過去にメディアに取り上げられたときのリンク集
・1⽇のタイムスケジュール
・着任後最初の1ヶ月の大まかなスケジュール
* 1年目、2年目、3年目のそれぞれ活動の想定
* 任期終了後の想定
* 兼業・副業の可否募集要項で丁寧に情報を伝えることは応募者に任用後の具体的なイメージを持ってもらうために有効であるほか、地域側が協力隊の受入に積極的に取り組んでいることを示すメッセージにもなります。このため活動中の隊員や協力隊経験者に内容を確認してもらい、意見を求めることも大切です。
さらに募集要項での表現には注意が必要です。例えば、任用関係がない場合には、「勤務時間」「報酬」など任用があると誤解される表現は避け、「任用関係はない」ことを明記します。
募集〜採用
募集活動
活動内容や必要なスキルなどを明記した募集要項をもとに募集活動を進めます。募集活動では、協力隊としての活動内容や求める人物像に応じた情報発信の手段を選び、戦略的に情報を発信することが重要です。
詳しいデータはPCサイトでご確認ください。


ポイント
-
全国で多くの⾃治体が隊員の募集に取り組む中、募集活動は地域のPRの機会でもあり、広報活動と一体的かつ戦略的に情報発信を行うことが重要です。
募集の時期・期間、活用するメディア、チラシやホームページ等のデザイン、問い合わせや受付の窓口・体制、応募が集まらなかった時の対応策など、関係者間で方針や戦略を練り、具体的な活動計画に落とし込んでいく必要があります。下記のように計画すべき要素について関係者の間で方針や戦略を練り、具体的な活動計画に落とし込んでいきます。
- 募集の時期・期間
- 活用するメディア
- チラシやホームページなどのデザイン
- 問い合わせや受付の窓口・体制
- 応募が集まらなかった時の対応策など
特に問い合わせは応募者がはじめて地域と接触する機会です。迅速かつ丁寧な対応を心掛けるほか、問い合わせ内容を分析し、広報内容を随時改善する仕組みが大切です。
なお公益社団法人ふるさと回帰・移住交流推進機構(JOIN-FURUSATO)では、毎年アンケート調査を行い、地域おこし協力隊の現状、応募理由、情報入手手段などが公表されています。このデータをもとに、より効果的な募集条件や広報方法を設計することも有効です。
-
募集活動は、応募者と地域が接触する機会です。応募者にとっては、地域での生活や活動が⾃分にマッチしているかを見定める場でもあります。そのため、着任後に活動を共にする地域関係者の顔が見えるよう、担当者や活動拠点などの写真、動画などを活用し、地域の様子や活動のイメージを可視化することが重要と言えます。
また、現地での交流イベントや説明会、体験会など、応募者と地域とが直接交流できる機会を設けることも効果的です。総務省では応募前に実際の活動内容や生活が体験できる「おためし地域おこし協⼒隊」、「地域おこし協⼒隊インターン」制度を設けています。こうした制度を活用しミスマッチを防止することも有効です。 -
募集活動では、求める人物像に届きやすいメディアを選ぶことが重要です。メディアごとに特性が異なるため、地域への移住や求人に実績がある媒体を選定するのが効果的と言えます。
また予算とのバランスも考慮しつつ行政担当者が自らコンテンツを丁寧に作成・編集することも有効です。地域をよく知る目線で、活動の魅力や地域の思いが伝わる発信を心がけることがより良いマッチングにつながります。
任用決定
最初に思い描いていた人物像と比較しながら、今回の活動に最適な人材を選びます。
選考をスムーズに進めるにあたり、審査の基準や誰が審査をするのかを募集要項を作成する段階から検討しておくことが重要です。
ポイント
-
任用決定にあたっては、地域の課題やそれに基づく採用目的、求める人物像に沿った審査基準や方法を定める必要があります。
会計年度任用職員の審査基準を隊員の審査基準にそのまま用いるケースも見られますが、コミュニケーション能⼒、一般事務処理能⼒、文章作成能⼒、服装や時間厳守など社会常識といった基本的要件に加え、業務内容との適合性を見極める審査基準を設けることが重要です。独⾃の項目を設けたエントリーシートの作成をはじめ、書類選考や面接だけではなく、現地での業務体験を採り入れることでミスマッチの防止と適切な人材の選定につながります。
-
着任後のミスマッチを防ぐためには、実際の活動やサポートを見据えた多角的な審査が必要です。
例えば行政担当者やサポートメンバーが説明会や審査に加わり、応募者の人物像を事前に把握しておくことで着任後の関わり方を具体的に検討しやすくなります。また、複数の隊員を同時に募集する場合は、チームとしての相性や役割分担も考慮することが求められます。
-
任用決定後、正式な着任までの期間も、内定者とのコミュニケーションを継続し、地域づくりの「仲間」「チームの一員」としての関係づくりに努めることが大切です。
この間に転居や各種手続きのほか、関係者との顔合わせ、活動に必要な備品の準備などを円滑に行う必要があります。
特に服務上のルールや経費の取扱い、守秘義務事項(住民情報や行政情報の取り扱い、SNS等での書き込みなど)については、トラブル防止のために事前に丁寧な説明を行い、文書で共有し理解を得ることが求められます。特に活動費は、隊員が⾃ら申請する経費だけが活動費だと思っているケースがあり、トラブルのもとになりやすいため十分な説明が必要です。
募集活動の検証と見直し・横展開
地域おこし協力隊の募集活動を進めても、様々な要素や条件が重なり応募が思ったよりも集まらない場合もあります。
協力隊の募集から採用、そして着任後実際に地域で活動し、地域づくりの成果・効果が得られるまで、募集や受入に関わる一連のプロセスを常に見直し、改善をしていくことが非常に大切です。こうしたサイクルが隊員と地域のベストマッチに、ひいてはよりよい地域づくりにもつながっていきます。
また、各都道府県においてはこうした改善の積み重ねにより得られた経験や知識をノウハウとして蓄積し、独自の支援体制を構築することが求められます。そしてこのノウハウを各市町村へ積極的に展開することで地域おこし協力隊の活動全体の質的向上と、より効果的な地域づくりの推進が期待されます。
任期中
任期中から任期終了後に向けたサポート
地域おこし協力隊が地域でスムーズに活動し、その能力を最大限に発揮するには、着任後の自治体による適切なマネジメントと継続的なサポートが欠かせません。
日頃から隊員や関係者とのコミュニケーションの機会を設け、活動中に生じる隊員の悩みや状況の変化を的確に把握することが必要です。把握した状況に基づき活動内容やサポート体制、必要があれば任⽤形態も含めて、柔軟に⾒直しを⾏うことが求められます。
ポイント
-
任期中は、地域や自治体と隊員との関係性の変化をはじめ、活動内容の見直しが必要となることもあります。こうした状況に対応するため、継続的なフォローアップが重要です。
- 行政内部の人事異動などに備え、関係者の間で定期的に情報共有の場を設けること。
- 地域おこし協⼒隊員の活動状況や地域の受入れ状況を把握し、地域おこし協⼒隊員の活動が地域⼒の維持・強化につながっているか、地域おこし協⼒隊員が地域の中でどのような役割を果たしているか定期的に確認すること。
- 地域と隊員の間に問題が生じた場合は経緯を関係者間で共有し、問題解決調整に努めること。
- 実態に応じて活動内容やエリア、サポート体制の見直しを行うこと。
-
多くの隊員は、地域における活動基盤や人脈がない状態から活動を始めます。また、行政との仕事に不慣れなケースも少なくありません。そのため活動開始時に地域と関係づくりに当たっての心構え、行政の予算の使い方のルールなどを学ぶことが重要です。
また任期終了後の定着に向けては、一緒に地域で活動する仲間づくりや相談できる相手の存在が大きな支えとなります。
他の隊員も含め、地域内外の人々と交流し仲間をつくる機会を継続的に設けることが効果的です。総務省では地域おこし協⼒隊員や集落支援員を対象とした初任者向け研修や分野別研修、地域おこし協⼒隊の全国ネットワークによる交流の機会を提供しています。一方で隊員数が増加する中、より地域に根差した機会を提供する観点から都道府県や市町村単位での研修・交流の充実も求められています。広域での他自治体との合同開催の可能性も検討しましょう。
なお、受入⾃治体が地域おこし協⼒隊を対象とする研修などを実施する際は、⽇々のサポートに要する経費への特別交付税により外部機関を活用することが可能です。都道府県が実施する同様の研修等に要する経費については、普通交付税により財政措置されています。 -
隊員の定住・定着に向けては任期中の活動だけでなく任期後を見据えた計画的な支援が不可欠です。
例えば隊員が任期終了後に地域資源を活用した起業を目指している場合は、1年目は地域の資源発掘や信頼構築の期間とし、2年目以降にミッションの時間とは別に定住・起業準備のための時間を確保するなど、業務時間の配分や活動内容の見直しによる支援を検討します。こうした支援のために、隊員自身に出口戦略のロードマップを作成してもらい、一緒に定期的に進捗確認することで、必要な支援を段階的に検討していく方法も効果的と言えます。
また任期後の生業づくりの支援として起業や事業承継に関する研修や相談体制の整備も考えられます。
総務省では隊員向けにロードマップづくりを支援するステップアップ研修や、起業に必要なノウハウを学ぶ起業・事業化研修を実施しています。