|
平成21年10月20日
四国総合通信局
四国の地上デジタル放送の動向
≪アナログ放送終了まで642日、完全デジタル化移行に向けた課題と取組≫
四国総合通信局(局長:山本 一晴(やまもと いっせい))では、放送事業者、地方自治体及び関係団体と連携して地上テレビ放送のデジタル化に向けた取組を進めています。
完全デジタル化に向けた送信側の環境整備(中継局の整備)は計画どおり進んでいることから、今後は受信側の環境整備を着実に進める必要があり、なかでも、下記の共聴施設(辺地共聴施設、受信障害対策共聴施設、集合住宅共聴施設)のデジタル化と新たな難視地区対策に重点を置いた取組が必要となっています。
記
【主なポイント】
1 共聴施設のデジタル化対応について
(1) 辺地共聴施設
本年9月末で管内の施設のうち約21%が対応済みですが、改修計画ありを含めると約95%の施設で計画的にデジタル化が進められる予定です。今後はこれらの施設の改修工事が計画に沿って着実に実施されるよう国、NHK及び自治体の支援制度を活用しつつ推進するとともに、未定・未把握施設の解消が重要となっています。
辺地共聴施設のデジタル化対応状況
| 都道府県 |
平成21年9月30日現在(確認中) |
平成20年9月30日現在 |
| |
施設数 |
デジタル化
対応済
(施設数) |
デジタル化
対応率
[%] |
未定・未把握
施設数(注意) |
施設数 |
デジタル化
対応済
(施設数) |
デジタル化
対応率
[%] |
未定・未把握
施設数 |
| |
[%] |
| 徳島県 |
270 |
67 |
24.8% |
30 |
11.1% |
318 |
4 |
1.3% |
161 |
50.6% |
| 香川県 |
37 |
13 |
35.1% |
1 |
2.7% |
33 |
9 |
27.3% |
10 |
30.3% |
| 愛媛県 |
592 |
97 |
16.4% |
19 |
3.2% |
577 |
35 |
6.1% |
92 |
15.9% |
| 高知県 |
448 |
111 |
24.8% |
22 |
4.9% |
405 |
29 |
7.2% |
114 |
28.1% |
| 四国 |
1,347 |
288 |
21.4% |
72 |
5.3% |
1,333 |
77 |
5.8% |
377 |
28.3% |
|
(注意)デジタル化対応策が未決定・未把握のもの
(2) 都市受信障害対策共聴施設(いわゆる「ビル陰共聴施設」等)
「総務省テレビ受信者支援センター(以下、「デジサポ」という。)」の訪問調査等により、本年9月末で管内の施設のうち約18%が対応済みと判明していますが、改修計画ありを含めると約69%の施設で計画的にデジタル化が進められる予定です。
今後はこれらの施設の改修工事が計画に沿って着実に実施されるよう国の支援制度を活用してデジタル化を推進します。また、放送による周知活動等を通じて施設設置者や加入者の意識の向上を図るとともに、デジサポによる訪問活動を通じて未定・未把握施設等の解消を図り、デジタル化対応を進めます。
都市受信障害対策共聴施設のデジタル化対応状況(平成21年9月30日現在)
| 都道府県 |
施設数
(廃止を除く) |
デジタル化
対応済
(施設数) |
デジタル化
対応率
[%] |
計画有り |
計画無し |
未定・未把握
施設数 |
| |
[%] |
| 徳島県 |
274 |
84 |
30.7% |
97 |
30 |
63 |
23.0% |
| 香川県 |
576 |
108 |
18.8% |
165 |
2 |
301 |
52.3% |
| 愛媛県 |
1,808 |
291 |
16.1% |
1,124 |
60 |
333 |
18.4% |
| 高知県 |
320 |
58 |
18.1% |
125 |
52 |
85 |
26.6% |
| 四国 |
2,978 |
541 |
18.2% |
1,511 |
144 |
782 |
26.3% |
|
(3) 集合住宅共聴施設(いわゆる「アパート、マンション」等)
「デジサポ」の訪問調査等により、本年9月末で管内の施設のうち約30%が対応済みと判明していますが、現実には、施設改修が不要な築年数が浅い集合住宅もあり、実際には多くの集合住宅で地上デジタル放送が視聴可能と推定されます。本年5月29日の総務省報道発表(注意)によれば、四国管内のデジタル化対応不要の施設は約65%と見込まれています。
今後は、放送による周知活動等を通じてビルオーナーや加入者の意識の向上を図るとともに、デジサポによる訪問活動を通じて未定・未把握施設の解消を図るため国の支援制度の活用によるデジタル化対応を進めます。
(注意) 報道発表の数値は、デジタル化改修済み、CATV加入済み、シミュレーションにより受信可能と判断される場合等を合算しています。
四国管内:約65% (徳島:約45%、香川:約99%、愛媛:約54%、高知:約50%)
集合住宅共聴施設のデジタル化対応状況(平成21年9月30日現在)
| 都道府県 |
施設数 |
デジタル化
対応済
(施設数) |
デジタル化
対応率
[%] |
未定・未把握
施設数 |
| |
[%] |
| 徳島県 |
9,083 |
3,974 |
43.8% |
5,109 |
56.2% |
| 香川県 |
12,810 |
2,784 |
21.7% |
10,026 |
78.3% |
| 愛媛県 |
19,514 |
5,070 |
26.0% |
14,444 |
74.0% |
| 高知県 |
7,481 |
2,587 |
34.6% |
4,894 |
65.4% |
| 四国 |
48,888 |
14,415 |
29.5% |
34,473 |
70.5% |
|
2 地上デジタル放送の難視地区等について
本年8月31日、総務省及び全国地上デジタル放送推進協議会では、「地上デジタル放送難視地区対策計画(初版)(以下、「対策計画」という。)」を策定・公表しました。
総務省ホームページ https://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/dtv/zenkoku/index.html https://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/dtv/zenkoku/index.html
対策計画の構成は、以下のとおりであり、今後定期的に更新することとしています。
・「新たな難視地区に対する対策計画(都道府県別)」
・「デジタル化困難共聴施設に対する対策計画」
・「区域外波の受信困難地区の特定・対応手法」
本対策計画に基づき、対策の実施を図ることにより、平成23年(2011年)のアナログ停波までにデジタル難視地区の最小化を図り、また残された難視世帯については、衛星利用による暫定的な対策を行いつつ、最終的に地上系放送基盤による対策の実施を行うものです。
(1) 新たな難視地区
四国管内において、34市町村96地区(約1,500世帯)が新たな難視地区と判明しています。これらの地区については、市町村との協議や地元説明を行い、対策手法を確定させていきます。
なお、県別の状況は以下のとおりです。
| ・徳島県: |
7市町 |
25地区(約420世帯) |
| ・香川県: |
8市町 |
22地区(約190世帯) |
| ・愛媛県: |
10市町 |
30地区(約580世帯) |
| ・高知県: |
9市町村 |
19地区(約280世帯) |
新たな難視地区に対する対策計画の概要(注意1)
| |
調査地区数 |
新たな難視ではないと判明した地区数(注意2) |
新たな難視と特定された地区数 |
新たな難視と特定された世帯数 |
参考(平成12年国勢調査・一般世帯数) |
| (1) |
(2)
(注意3) |
(3) |
(4)
(注意4) |
(5) |
(6)
(注意5) |
(7) |
(8)
(注意6) |
(9) |
| 全国 |
6,075 |
- |
2,845 |
46.8% |
3,230 |
53.2% |
82,248 |
0.2% |
46,782,383 |
| 四国 |
363 |
6.0% |
253 |
69.7% |
96 |
26.4% |
1,454 |
0.1% |
1,536,109 |
| 徳島県 |
55 |
0.9% |
19 |
34.5% |
25 |
45.5% |
416 |
0.1% |
287,897 |
| 香川県 |
56 |
0.9% |
34 |
60.7% |
22 |
39.3% |
186 |
0.1% |
363,955 |
| 愛媛県 |
145 |
2.4% |
112 |
77.2% |
30 |
20.7% |
577 |
0.1% |
564,959 |
| 高知県 |
107 |
1.8% |
88 |
82.2% |
19 |
17.8% |
275 |
0.1% |
319,298 |
|
(注意1) 今回公表した難視地区の特定は、2007年までに開局したデジタル中継局を中心としたものであり、2008年以降に開局した中継局等の電波の実測調査を継続し、新たな難視地区の特定を進め定期的に更新することとしている。
(注意2) 「新たな難視地区ではないと判明した地区」は、デジタル放送の良視地区のほか、受信世帯が無い地区、ケーブルテレビ・共聴施設による受信地区を含む。
(注意3) (2)=全国に対する比率
(注意4) (4)=調査地区数に対する比率
(注意5) (6)=調査地区数に対する比率
(注意6) (8)=(7)÷(9)×100
新たな難視地区に対する対策計画の策定状況
| |
対策地区数 |
対策計画策定済みの地区数(注意1) |
検討中の地区数(注意2) |
| (1) |
(2)
(注意3) |
(3) |
(4)
(注意4) |
(5) |
(6)
(注意5) |
| 全国 |
3,230 |
- |
140 |
4.3% |
3,090 |
95.7% |
| 四国 |
96 |
3.0% |
0 |
0.0% |
96 |
100% |
| 徳島県 |
25 |
0.8% |
0 |
0.0% |
25 |
100% |
| 香川県 |
22 |
0.7% |
0 |
0.0% |
22 |
100% |
| 愛媛県 |
30 |
0.9% |
0 |
0.0% |
30 |
100% |
| 高知県 |
19 |
0.6% |
0 |
0.0% |
19 |
100% |
|
(注意1) 対策手法としては、中継局の設置、共聴施設新設、CATV加入、高性能アンテナ対策があり、対策手法について、地元自治体及び地元との調整が整ったもの。
(注意2) 対策手法について、地元自治体及び地元との調整未了のもの。
(注意3) 全国に対する比率
(注意4) 対策地区数に対する比率
(注意5) 対策地区数に対する比率
(2) デジタル化困難共聴施設
四国管内において、22市町村46施設(約1,250世帯)がデジタル化困難共聴施設となっています。これらの地区については、今後、市町村との協議や地元説明を行い、対策手法を確定させていきます。
なお、県別の状況は以下のとおりです。
| ・徳島県: |
2市町 |
2施設(約230世帯) |
| ・香川県: |
1市町 |
1施設(約30世帯) |
| ・愛媛県: |
10市町 |
22施設(約580世帯) |
| ・高知県: |
9市町村 |
21施設(約410世帯) |
デジタル化困難共聴施設に対する対策計画の策定状況
| |
対策施設数(注意1) |
対策計画策定(注意2) |
検討中(注意3) |
| 施設数 |
%
(注意4) |
世帯数 |
%
(注意5) |
施設数 |
%
(注意6) |
世帯数 |
%
(注意7) |
施設数 |
%
(注意8) |
世帯数 |
%
(注意9) |
| 全国 |
362 |
- |
16,187 |
- |
133 |
36.7% |
5,163 |
31.9% |
229 |
63.3% |
11,024 |
68.1% |
| 四国 |
46 |
12.7% |
1,251 |
7.7% |
10 |
21.7% |
342 |
27.3% |
36 |
78.3% |
909 |
72.7% |
| 徳島県 |
2 |
0.6% |
230 |
1.4% |
0 |
0.0% |
0 |
0.0% |
2 |
100% |
230 |
100% |
| 香川県 |
1 |
0.3% |
25 |
0.2% |
0 |
0.0% |
0 |
0.0% |
1 |
100% |
25 |
100% |
| 愛媛県 |
22 |
6.1% |
584 |
3.6% |
1 |
4.5% |
18 |
3.1% |
21 |
95.5% |
566 |
96.9% |
| 高知県 |
21 |
5.8% |
412 |
2.5% |
9 |
42.9% |
324 |
78.6% |
12 |
57.1% |
88 |
21.4% |
|
(注意1) 辺地共聴施設のデジタル化改修において、受信点の大幅な移設を要し、これにより受信点からヘッドエンドまでの伝送路整備の試算が1施設あたり800万円を超える自主共聴施設及び現地調査等において技術的に多大な困難があり現段階でデジタル化困難と判明した自主共聴施設。
(注意2) 対策手法について、地元自治体及び地元との調整が整ったもの。
(注意3) 対策手法について、地元自治体及び地元との調整未了のもの。
(注意4) 全国の対策施設数に対する比率
(注意5) 全国の対策施設の世帯数に対する比率
(注意6) 対策施設数に対する比率
(注意7) 対策世帯数に対する比率
(注意8) 対策施設数に対する比率
(注意9) 対策世帯数に対する比率
(3) 区域外波の受信困難地区(徳島県)
県外波に対する受信の依存度が高い地域を特別な地域として対策計画の対象に加え、今回、これに該当する地域として徳島県及び佐賀県における県外波の受信状況変化を実測調査(測定車による約1,000ポイント調査)し、個別アンテナで地上アナログ放送が受信可能な地域において地上デジタル放送へ移行することに伴い、県外波の受信に変化(受信困難)が生じると推定される地区を提示したものです。
その結果、徳島県内では18市町、213地区で受信環境の変化があると見込まれています。現在のところ、該当市町における受信対策手法については、まだ確定していませんが、情報通信基盤整備の現状や計画・検討状況を踏まえ、自治体と協議して確定していく予定です。
区域外波の受信困難地区の概要
| |
|
自治体名 |
受信局別 |
大阪局
(生駒山) |
和歌山局
(御坊) |
神戸局 |
岡山局
(金甲山) |
高松局
(前田山) |
| 徳島県 |
213地区 |
1 |
徳島市 |
23 |
13 |
4 |
3 |
0 |
| 1 |
鳴門市 |
10 |
8 |
1 |
4 |
0 |
| 1 |
小松島市 |
10 |
6 |
3 |
0 |
0 |
| 1 |
阿南市 |
20 |
21 |
7 |
0 |
0 |
| 1 |
吉野川市 |
9 |
0 |
3 |
1 |
0 |
| 1 |
阿波市 |
5 |
1 |
0 |
0 |
0 |
| 1 |
美馬市 |
5 |
0 |
1 |
2 |
0 |
| 1 |
三好市 |
2 |
0 |
0 |
4 |
0 |
| 1 |
勝浦郡勝浦町 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1 |
名西郡神山町 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1 |
海部郡牟岐町 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
| 1 |
海部郡美波町 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1 |
海部郡海陽町 |
1 |
2 |
0 |
0 |
0 |
| 1 |
板野郡松茂町 |
5 |
3 |
0 |
0 |
0 |
| 1 |
板野郡北島町 |
3 |
4 |
0 |
0 |
0 |
| 1 |
板野郡上板町 |
7 |
3 |
0 |
0 |
0 |
| 1 |
美馬郡つるぎ町 |
4 |
0 |
0 |
3 |
2 |
| 1 |
三好郡東みよし町 |
2 |
0 |
0 |
3 |
0 |
| 小計 |
|
18 |
|
110 |
62 |
19 |
20 |
2 |
| 合計 |
|
18 |
|
213 |
|
【別紙】 参考資料【PDF(Acrobat)形式(2009102003_1.pdf/376KB)】 参考資料【PDF(Acrobat)形式(2009102003_1.pdf/376KB)】
- ・資料1:「テレビ受信者支援センター」の活動概要
- ・資料2:平成21年度におけるデジサポの主な活動状況
- ・資料3:辺地共聴施設のデジタル化支援制度の活用状況
- ・資料4:辺地共聴施設整備支援事業の概要
- ・資料5:都市受信障害対策共聴施設デジタル化改修支援事業の概要
- ・資料6:集合住宅共聴施設デジタル化改修支援事業の概要
- ・資料7:「新たな難視地区」発生のメカニズム
- ・資料8:地上デジタル放送受信機の普及状況
- ・資料9:デジタル中継局等の整備状況と世帯カバー率
※PDF(Acrobat)形式ファイルの無料閲覧ソフトが必要な方はこちら ≫
(連絡先)
四国総合通信局 情報通信部 放送課
担当:吉岡課長、岡 課長補佐、小松上席電波検査官 課長補佐、小松上席電波検査官
電話:089−936−5037
ファックス:089−936−5014
|
|
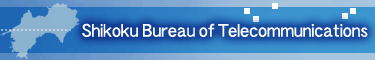
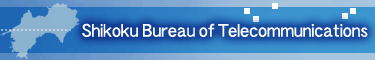
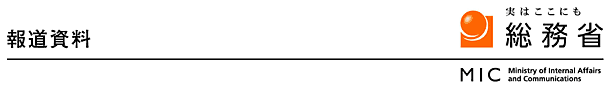
 https://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/dtv/zenkoku/index.html
https://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/dtv/zenkoku/index.html![]() 参考資料【PDF(Acrobat)形式(2009102003_1.pdf/376KB)】
参考資料【PDF(Acrobat)形式(2009102003_1.pdf/376KB)】