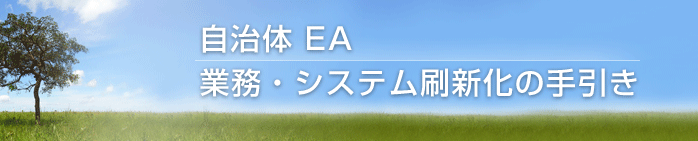【作業の目標】
給与と諸手当についての現状把握を行いました。給与業務と諸手当業務の目的は諸手当を含む給与支払いを正しく行うことです。
【当日の流れ】
同じ時間帯に職員が2名で5つの業務の分析を担当するため、5つの業務を2つに分割し、給与業務と諸手当業務をそのうちの1つとして作業を進めることにしました。
9:00〜 9:05 業務内容の意識合わせ(5分)
9:05〜 9:20 業務説明表の作成(15分)
9:20〜10:15 機能分析表(DMM:以下「DMM」という。)の作成(55分)
10:15〜11:15 機能情報関連図(DFD:以下「DFD」という。)の作成(60分)
【作業内容】
(1) 業務内容の意識合わせ
最初に、担当者間で業務内容についての意識合わせと作業内容を確認しました。
(2) 業務説明表作成
- 業務の目的・概要については、意識合わせで確認した内容を記述しました。
- 根拠法令については地方自治法、給与条例、各種手当規則が該当します。
- 業務規模については、担当者の人数、年度末の繁忙期、夏季の閑散期についての割合を概数で算出しました。
- 成果指標については、給与調整の回数・頻度を挙げました。(詳細は後述)
- 投入資源等については、臨時職員はいないこと、また情報システム費用、消耗品、パンチ費用(データ入力費用)の概数を記入しました。
(3) DMMの作成
- 給与と諸手当に大きく分けられ、思いつくままの業務を挙げ、大きく2分してのDMMへの配置を行いました。
- 年末調整は税法改正対応等も含めて、給与とは別の分類にしました。
- 賞与計算は給与でなく、手当てに分類することとしました。
- 年末調整については、税法改正への対応、各種控除類、その他支給等の計算も別にあることから機能を追加しました。
- 税法改正については、年末調整と月額給与計算に影響があるが、諸手当には影響はないことを確認しました。
- 差額修正については、作業量は大きいが機能としては重要度が小さいため、階層を下げることとしました。
(4) DFD作成
○給与支払
- まず、DMMで挙げられた機能を枠内に配置しました。
- 次に、関連する外部環境として、会計課、指定金融機関、職員、委託業者を挙げ、それを枠外に配置しました。
- それらの間で受け渡される帳票やファイルを挙げ、各機能、外部環境との関連を整理しました。
- 外部環境、ファイル、機能の間を受け渡される帳票等の情報を挙げ、順次記入していくと同時に、機能毎の関連についても整理しました。
- 職員への支給については現金もあることから、現金支給の機能をDMMにさかのぼって追記しました。
- 振込み不能は件数的に少なくないので、その機能について記載しました。
○給与計算
- 「給与支払」と同じ順序で、機能、外部環境、帳票、ファイルについて挙げ、その関連を整理していきました。
- 人事院勧告の時期の問題が話題となりましたが、DFDに記載はせず、意見として挙げることにしました。
- 給与の計算については、人手で行う仮計算は給与と諸手当の両方にあるため、DMMに戻って、一つの機能にまとめて記載しました。
(5) 情報実体一覧表の作成
- あらかじめ用意した通勤届け等の6種類の帳票について、一覧表を作成しました。
【出てきた意見】
DMM、DFDを作っていく過程で、以下のような課題、気づいた点がありました。
- 一部現金支給を含む現金支給については、8月時点で約5割あり、非常に手間がかかっている。キャンペーンを行って、振替に誘導しており、現時点では約3割に減っている。
- 銀行の統廃合の情報が正しく入ってこない場合(特に、地方銀行や信金の場合)があり、給与振込不能となる場合がある。・ 職員が結婚した後に、口座の名前が変わっているが、申告が遅れ、給与システムに反映されていない場合に給与振込不能となる場合がある。
- 給与計算については、システムを更改した直後で大きな問題はないが、職員の休暇等の申告が遅い場合には作業の手戻りが発生する場合がある。