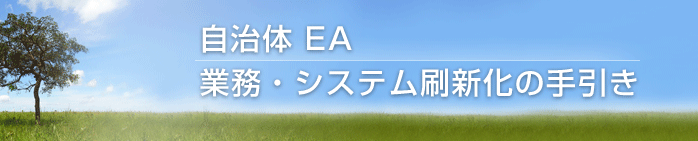| ■作業名 |
基幹業務 福祉関連業務 生活保護 現状分析(業務分析)作業(第1回) |
| ■日時 |
平成17年10月27日(木)
13:00〜15:00 |
 |
| ■場所 |
川口市役所5F大会議室 |
| ■参加者 |
職員:
福祉課 石井課長補佐、青羽主事、加藤主事、沢田主任 |
企業:【基幹】
日立製作所 榎本 |
| ■使った資料 |
|
| ■概要 |
【作業の目標】
- 生活保護に関する業務範囲・業務目標の設定と、現行業務がどのように行われているのか共通の記述様式を使って整理します。
【当日の流れ】
13:00〜13:10 業務分析の目的と本日の作業の確認(10分)
13:10〜13:20 業務説明表の記入(「業務の目的・概要」欄のみ)(10分)
13:20〜14:40 機能分析表(DMM:以下「DMM」という)の作成(80分)
14:40〜15:00 機能情報関連図(DFD:以下「DFD」という)の作成(20分)
【作業内容】
- 9/28の説明会に出席していない職員もいたため、事業の目的、実施内容等に時間を充て説明しました。
- 業務の目的・概要は、基本的に法令と同等ということで、これを基に議論を進め記入しました。
- DMM作成にあたっては初めての職員もいたため、「カレーを作る」といった身近な例題にて機能分割のコツ(順序があること、停滞箇所で切れること等)を5分程度説明した後で、生活保護の作業に取りかかりました。
- 生活保護は、保護決定までの業務と決定以降の業務に大きく分けられることから、それぞれの業務を順に記載することでDMMの階層1を固めました。
- 階層1が出来上がった時点で、一旦、機能に不足がないか確認したところ、国・県への補助金請求の機能が必要ということで、機能の抽象化(統合)を行い8機能に収まるよう、機能区分を工夫することとなりました。
- 同時に機能の抽象化に伴い、機能名称の付け方について言葉選びに苦労するところがありました。例えば、当初「実態把握」としていた機能について、その機能の指し示す内容が生活保護者への指導・指示を含むものであるといった議論から、もう少し広い意味の言葉を探すことになりました。結果としては、一般的な用語でないものの、生活保護に関わる職員にとっては「ケースワーク」といった言葉がしっくりくるとのことで、多少専門性を含んだ用語に落ち着きました。
- DMMの作成時にDMM上に情報の流れ(矢印)や外部の連携機関(外部要因)を記録していたこともあり、職員自らDFDの作成に取りかかることができました。
【出てきた意見】
- 9/28に実施した内容が残っていれば、それを取りかかりとして進めたかった、との意見が出されました。(今回完成したものとの比較も含め)
|
| ■成果物 |
- 業務説明表(1枚)・・・「業務の目的・概要」欄のみ記載しました。
- DMM(1枚)・・・階層1、2まで作成しました。
- DFD(1枚)・・・階層1「審査決定」のみ作成しました。その他の機能については、本作業時間帯で作成できませんでしたが、DMM作成時に業務の流れ・外部機関との連携部分を確認しています。
|
| ■ポイント |
- 身近な事柄を題材に機能分割の仕方を説明することで、自然と機能分割の揃え方、抽象化の考え方等を想定できるものと思われます。
- DMMでもある程度の業務の流れが確認できるため、多少DMMに時間を掛けてでも、共通理解を促すことが有効と思われます。
- 機能の名称の付け方については、なるべく専門用語を使わないような言葉選びが必要と思われます。
|